ピアニストのひとり言 第820回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”I
手元に、私が産まれた時のアルバムがあります。両親にとって初めての子供でしたのでいちいちが珍しかったのか、写真の横には几帳面に母のコメントが書き込まれています。当時24歳だった母の筆跡は今の私から見ても大人びていて、不思議なことにどうしても自分よりもずっと年下の女性が書いたものだという実感がわきません。
生後22日に撮影された写真の横には、こんなメモ書きがありました。“オルゴールを聞かせたところ、目を見開いてびっくり”“音に敏感で、小さな音にもすぐ反応を示す”。
音、音楽と濃密に向き合う人生は、すでに生後22日から始まっていたようです。その後、母が時折弾いてくれるピアノの音に強く興味を惹かれ、つたえ歩きできるようになると自らピアノに向かっていって鍵盤を押し、音を鳴らすことを覚え、さらに、椅子に座れるようになると“即興演奏”をするようになりました。その時の、イメージをもって音を出し、それを聴きつつ“メリハリ”を工夫して曲を構成していく素晴らしい感覚は、今でもはっきりと覚えています。“作品”を弾き終えると必ず母のところへ行って「どうだった?」と、感想を求めました。母は「上手よ」と必ず褒めてくれました。
時折、その“即興演奏”が、神がかったようにうまくいく時があるのです。新しい響き、思いがけない展開、想定を上回る表現…「これは!」という出来栄えになる時が。その演奏後、興奮を抑えつつ母に「どうだった?」と尋ねるも、母がいつものように「上手よ」と答えるのに軽い落胆を覚えたものでした。「どう考えても、ただの“上手”じゃない出来栄えだったのに。特に素晴らしかったはずなのに」…今思うと、どんな時にも「上手よ」と答えてもらえるだけでも恩の字なのに、なんて欲深い子供だったのでしょう。
生活の中の音楽体験は、ピアノだけではありませんでした。日曜日には必ず父がクラシックのレコードをかけてくれましたし(その時のビクター社の真空管のスピーカーの音は、今でも私の中の“いい音”の基準になっています)、母はいつも鼻歌を歌っていました(これは今も変わりません)。歌といえば、お風呂で顔を拭いてもらう時も、「おでこを拭いて、お鼻を拭いて…」という母自作の歌を歌ってもらいながらでしたし、母と一緒にダンスを踊って遊ぶ時も、いつも母の歌を聞いていました。
気に入った歌には反応を示し、母に「もう一回!」と、何度もアンコールをおねだりしたそうです。あまりにもそれが執拗なので歌い疲れてしまった母が「今度は美奈子ちゃんが歌って」というと、私はそのままを“空で”歌ってみせたとか。そんなこんなで、この子はよほど音楽が好きなのだと感じた母は、私を普通の幼稚園ではなく、ある音楽学校の幼稚科に入れてくれました。そこではピアノかヴァイオリンの個人レッスンが必須科目に入っていて、私は初めて正式にピアノを“習う”ことになりました。
個人レッスンはときめきと興奮に満ちたとても楽しい時間でした。先生の前で弾く曲すべてに、「うん、上手だ」「よし!」というお褒めの言葉と合格をもらえました。クラスで出欠を取る時も、ミュージカル仕立て。先生がピアノを弾きながら「美奈子ちゃん、美奈子ちゃん、どこですか〜?」と歌で呼びかけるので、手を高く挙げて星が輝くように、かつ、音楽のリズムに合わせて手首を回転させながら「ここです、ここです、ここにいます〜」と、やはり歌で答えるのです。
ソルフェージュの時間もありました。和音を聴き取って答えたり、リズム遊びをしたり、歌ったり。音楽に合わせて体を動かすリトミックのレッスンもありました。
こうして振り返ると、家でも幼稚科のクラスでも、私がいる場所にはいつも音楽があったような気がします。私にとって、歌うこともピアノを弾くことも、無条件に楽しい遊びであり大きな喜びでした。このように、音楽が当たり前のように身近にあった私がある小さなきっかけからピアニストを夢見るようになったのは、自然な流れだったように思います。
ピアニストのひとり言 第821回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”II
「わたし、この人みたいになりたい」ピアノを始めて間もないわたしが母にそう伝えたピアニストは、ルービンシュタインでもホロヴィッツでもなく、中村八大さんでした。
今のように、国内外の名演奏をオンデマンドで映像や音源で聴くことができなかった時代、レコードとラジオの役割はとても大きなものでした。ピアノの音に耳で触れることはあっても、幼稚園に通う私がプロの演奏家の生演奏を“観る”機会があるわけでもなく、いったいこういう演奏がどのように紡ぎ出されるのか、想像するしかありませんでした。
『夢であいましょう』という名番組が放映されていたのは、残念ながらわたしがものごころつく前まででしたし、だいいち番組が始まるのはとても3歳や4歳の子供が起きている時間ではありませんでした。でも、再放送なのか特別番組だったのか、ある時、同じメンバーが出演する番組を見る機会があったのです。私は、ピアノの前に座る素敵な紳士に目も耳も釘付けになりました。その方は、にこやかに柔らかく、こともなげに(当時の私にはそう見えました)ピアノを弾くのです。お仲間がそのピアノに寄り添って耳を傾けたり、一緒に歌ったり…。「ああ、なんて素敵な世界なんだろう」と魅入られてしまったのでした。
その一方で、その頃感覚的に“怖い”と感じた音も、ありました。波の音です。せっかく海に初めて連れていってもらったというのに、車のドアを開けた途端に耳に飛び込んでききた、得体の知れないリズムを繰り返す波の音に圧倒され、その近くに行くことがどうしてもできなかったのです。小さな妹は海の近くに行きたい、行きたいと好奇心満々。困った母は、私に車の中で“お留守番”しているように言い含め、妹を海岸に連れ出しました。皆が戻ってきたとき、私はひとりでのどかに「まつぼっくりがあったとさ〜」と、歌っていたそうです。
小学校に上がってからも、ピアノへの、そしてピアニストへの憧れは募るばかりでした。父の愛聴盤だったシューベルトのピアノ五重奏曲『鱒』のような室内楽、歌の伴奏、ソロ。いいなぁ、と思う全ての音楽に、ピアノの音がありました。ところが、上手になりたくて仕方ないわりに別段練習熱心だったわけでもなく、練習中に学校での出来事が思い出されては、ピアノを弾くのを中断して母にそれを伝えにいくような、おしゃべりが大好きな子供でもありました。
ピアノに向かっているときも、真面目に集中しているとは思えない様子だったはずです。なにしろ、「音の反対言葉ごっこ」と面白がって、今習っているソナチネをテンポを極端に変えて(アレグロの楽章をアダージョに、あるいはその逆)弾いてみたり、妹に長調を短調に変調して弾いて見せてはげらげら笑ったりしていたのですから。他にも、弱いところを強く弾いたり、その逆をやってみたり…。でも、思い返せばそんな遊びも私にとって、ちょっと意味のある“試み”でした。ふざけているようではありましたが、曲にはそれぞれ、ふさわしいテンポがあること、短調長調だけでなく、同じ長調同士でも調を変えるとがらりとキャラクターが変わってしまうことなどを、身を以て理解することができたのです。
父は休日になると、よく私たちをドライブに連れ出してくれました。車の中は、私たち姉妹にとって最高のステージになりました。妹と歌集を何冊か見繕って持ち込み、童謡や流行歌、『みんなのうた』…知っている歌を片っ端から延々と歌っていたのですが、考えてみたら両親からは一度も「もうやめなさい」と言われたことはありませんでした。
音楽の教科書は隅からすみまで目を通し、書いてあることは全て頭に入れました。楽器がカラーで紹介されているページは特にお気に入りで、たくさんの美しい楽器の写真をうっとりと眺めるのが好きでした。やがて、その全ての音を聞いたり弾いたりしてみたくなりました。管楽器ならリコーダーがありましたし、打楽器なら小さな木琴がありました。でも、弦楽器は?あの素敵な音色を奏でる弦楽器を、どうしても弾いてみたい…そうなると居ても立っても居られない性格です。
「ママ、ヴァイオリン習いたいの。習ってもいい?」おずおずと母に切り出すまでに、多くの時間はかかりませんでした。
ピアニストのひとり言 第822回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”III
ヴァイオリンは、祖母が弾いていた楽器でしたし、母方のいとこ二人ともが習っていたので、身近な楽器でした。お盆や正月休みに家族で帰省すると、私たち姉妹はピアノを、いとこたち兄弟はヴァイオリンを、一曲づつ祖母に聴いてもらいのが“なわらし”になっていました。私にとってそれは、発表会と同じくらい大切で楽しみなイベント。祖母は必ず「上手になったわね」と褒めてくれたので、そのコメントが聞きたくて聴いてもらうのが待ち遠しくて仕方ありませんでした。
小学校高学年の私にとって、ヴァイオリンの魅力は自分で音程を作ることができること、そして、ヴィヴラートをかけられる楽器だということ。いずれも、ピアノにはない特徴です。でも、実はもう一つ、心惹かれる大きなポイントがありました。それは、“持ち運べる”ということ。楽器のケースを持って颯爽と歩く…私にとってそれは、可愛いキャラクターのついた靴を履くことよりもずっと憧れてやまない、素敵な“いでたち”に思われました。
ピアノを習わせてもらうだけでも大変なことだったはずなのに、母はヴァイオリンを習わせてくれました。もちろん、安い方から数えた方がずっと早い値段の楽器と弓でしたし、一番安いケースでしたが、なんであれとにかく嬉しくて小躍りせんばかりでした。学校の“お楽しみ会”があるとヴァイオリンを持って行き、かろうじて弾けるようになったバッハのメヌエットなどを披露したりしました。ピアノの場合と同じく、この頃までは緊張するという自覚がまったくないほど、人に演奏を聴いてもらう喜びの方がはるかに大きく上回っていました。
結局、ピアノとの両立が難しいと悟り、ヴァイオリンを習っていたのは短い間だけになりましたが、なんとかヴィヴラートをかけて弾けるところまでは進みましたし、ボーイング(弓使い)を体験できたことや、音程に意識を向ける感覚を得られたことは、今にとても役立っているように思います。考えてみたら、弦楽器や管楽器の人たちは音大に入る時にも、入った後も必ず副科で
ピアノを学ぶのに、ピアニストが他の楽器を学ばないのはおかしなことです。種類の異なる楽器を弾く勉強をすることは、楽曲分析やアンサンブルをするにつけ、大事なことだと思っています。
というと、いかにも私の音楽人生は順風満帆のように聞こえるかもしれませんが、悩みや葛藤もありました。転勤族だったので転校が多く、そのたびピアノの先生も変わらなければならなかったのです。私は小さいうちから、先生によってとても大きな違いがあることを、身をもって感じることになりました。場合によってはせっかく終わりまで進んだ教則本なのに、「ちゃんとできていないから最初からやり直し」と言い渡されることもありました。同じレベルの演奏でも先生によって褒められたり、かなり厳しく直されたり、評価が異なることも知りました。
そんななか、祖母や友人に演奏を褒めてもらうのはとても嬉しいことでしたが、ピアノの先生からは、褒められるよりも足りないところをどんどん指摘して多くを教えて欲しい、と願うようになりました。それどころか、「音楽をきちんと学ぶには、レッスンだけでは足りない」と感じ始め、誕生日のプレゼントにはレコードをねだったり、お小遣いやお年玉を貯めては楽譜や専門書を買うようになりました。
知るほどに音楽への憧れは大きく膨らむばかりでした。その一方で、世の中には聴いたことがない作品がたくさんある。それぞれに様々な解釈もある。身につけなくてはいけないテクニックや知識も、山のようにある…。音楽を極めるためには、海のように大きく深い世界を隅々まで知り尽くし、体験しなければいけないことだらけに思われ、途方に暮れました。
自分がどこまで上達しうるのか、音楽の本質に近づきうるのか、何もわからない中でただ一つ明らかだったのは、音楽が好きでたまらない気持ちの揺るぎなさと、それがこれから先、決して衰えることはないだろうという確信でした。
そんなある日、ついに将来の目標を決定的にする出会いが訪れました。小学校6年の秋にワルシャワで行われた第9回ショパンコンクールの様子をテレビで観て、こともあろうにその時の優勝者に恋してしまったのです。(続く)
ピアニストのひとり言 第823回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅳ
クリスティアン・ツィメルマンという名のその優勝者は、ポーランド出身の18歳の青年でした。当時私は11歳になったばかり。自分とさほど変わらない年齢なのに、その堂々たる演奏はまるで別次元でした。貴公子のような風貌と、その演奏にふと感じられる青年らしい爽やかさに、憧れの気持ちは一気に沸点に達しました。
ショパンの音楽への憧れと、ツィメルマンへの憧れ。今思うと、どっちがどっちかわからないまま、両方ともに恋に落ちたような感じだったかもしれません。とにかく、それまでは漠然と抱いていた「ピアニストになれたらいいなぁ」という気持ちが、この時を境に「必ずピアニストになるぞ」という確固たる決意に至ったのは確かです。
ピアニストになるためには、兎にも角にもまず音楽大学を目指さなくては。でも、そのためには今までの“趣味のお習い事”の域を超え、“きちんとした”先生について基礎からしっかり身につけないといけません。二つ年下の妹もまたピアノを習っていましたし、九つ年下の弟はまだ幼稚園にも上がっていないという状況の中で、母にそれを願い出るのはかなりの勇気が要りました。でも、今思うと我ながらなんとワガママなことかと恥ずかしくなるのですが、その時は自分の願いをなんとしてでも通すことしか頭にありませんでした。
その頃、私たち家族は父の転勤の関係で名古屋に住んでいました。名古屋は今も昔も芸どころというか、お習い事がとても盛んで音楽教育も熱心な土地柄でした。音楽科が設けられている公立高校が二つありましたし、音楽大学は五つもあるほどです。親族に音楽家がいるわけでもなく、コネも特別な情報も持っていない私は、名古屋音楽学校というところに通わせてもらうことになりました。そこでお習いした先生はとても厳しく、テクニックを最初から全て“やり直し”することが課されました。今思うとその奏法には疑問に思う点がなくはないのですが、指を独立させて一つ一つの音を上部から打鍵するという奏法を叩き込まれました。スケール(音階)やハノンを、気が遠くなるほどゆっくりのテンポでお稽古する日々が続きました。
学校ではとてもいい友達に恵まれ、中学に上がっても、夏休み明けが待ち遠しくなるほど楽しい中学生活を送っていました。通っている学校の制服のセーラー服が大好きで、それを毎日着られるだけでも幸せでした。学校から帰ると、脱いだセーラー服を丁寧にハンガーに掛け、ブラッシングしてホコリを落とし、きちんと風呂敷をかけておきました。スカートは美しいプリーツを保つべく“寝押し”する…といったお手入れを、毎日欠かしませんでした。
ただ、バレーボールやドッジボールといった球技だけは突き指の心配があるため憂鬱で、いやいやボールを受けようとするからか、お約束のようにしょっちゅう突き指をしては保健室で手当てを受ける羽目になりました。放課後は器楽合奏部に入部して、小学校時代に少しだけ習ったヴァイオリンを弾いてもいました。名古屋音楽学校へレッスンに行くにはバスと地下鉄を乗り継がなければなりませんでしたが、母は小さな弟につきっきりでしたし一人で通っていました。
密かな楽しみは、レッスンの帰りに音楽学校の近くにあったヤマハ(当時は日本楽器)に立ち寄ること。特に楽譜売り場は夢のような場所でした。ずらりと並んだベートーヴェンやショパンの楽譜…。これらの曲を好きなだけお稽古できたらどんなに幸せだろう。他にも、値段が高くてお小遣いではなかなか買えなかった音楽雑誌を手にとってはドキドキしながらページをめくっていました。初めてお小遣いで買った音楽書は、ショパンの伝記。途中、感激して何度も泣きながら読み進めましたが、二度と祖国ポーランドに帰ることもないまま結核という不治の病に倒れ、39歳という若さでこの世をさってしまったドラマティックな最期には、ただただ号泣するばかりでした。音楽書を買うために、図書券狙いで音楽雑誌に投稿したりもしました。幸運なことに、投稿するたびに採用されました。
ピアノを弾くにつけ、書を読むにつけ、音楽への憧れは深まるばかり。名古屋市内の公立の音楽高校を受験して、音楽大学を目指す…目の前には素晴らしい道が広がっているような気持ちでした。ところが中学2年のある日、それまで光り輝いていた未来予想図に暗い雲が立ち込め、全ての希望が打ち砕かれるような知らせが飛び込んできたのです。
ピアニストのひとり言 第824回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅴ
「お父さん、転勤が決まったのよ」母のその言葉は、その地に引越しをすることを意味しました。私は胸の鼓動が早くなるのを感じながら、おずおずと尋ねました。「どこに行くの?」「仙台よ」
なんということ!幼い頃のたくさんの思い出がある仙台にまた戻ることになるとは…。でも、それは同時に、入学を夢みていた名古屋のK高校の音楽科を受験できなくなるということでもありました。「そんな…」言葉を失った後、出てきたのは涙でした。「じゃぁ、私K高校に行けないんだね。ピアノの勉強はどうしたらいいの?」
母は、自分のことばかり心配して、泣きながら転勤を嫌がる娘を前にどんなに困ったことでしょう。今振り返ると、我ながら恥ずかしい限りです。「仙台にもピアノの先生はいらっしゃるし、習えるわよ」「だって、だって、仙台には公立の音楽高校なんて、ないんだよ?」とても音楽が盛んだった名古屋に比べて、仙台にはのんびりしたイメージを抱いていました。音楽雑誌のコンサート情報を見ても名古屋の方がずっと外来のアーティストの公演が多いし、果たして“通用”するようになるための勉強ができるのか、いい先生が見つかるのか、不安がふくらむばかりでした。
名古屋音楽学校でのソルフェージュのレッスンでは、最後に担当の先生がこんな呼びかけをしました。「さぁ!誰かピアノを弾いてくれる人はいますか?」すると、発表会やコンクールが近い人が「はい」と手を挙げ、度胸試しのために演奏曲を披露してくれるのです。みんなうっとりするほど上手でした(その中には、のちに桐朋学園で再会を果たし、今も友情が続いている人たちもいます)。「ああ、私もいつか、あんなふうに弾けるようになるのかしら」自分が出遅れているのを感じつつも、憧れのため息をつきながら帰宅したものです。
ようやく正しいテクニックの基本を学び始めた私。彼女たちと同じ学校を受験するのだから、これからよほど頑張らないと、という焦りも感じていました。ですから余計に、このタイミングで仙台に転校するのは決定的に不利なことだ、という気持ちにとらわれてしまったのです。それからしばらくは、暗澹たる気持ちで過ごしました。大好きな学校の担任の先生や、クラスメイトたちとのお別れも、多感な年頃の私にとってはとても悲しく、一人だけ仲間外れにされてしまうような寂しさを感じました。
11月になり、引越しの日がやってきました。慌ただしく荷物を乗せたトラックを見送り、家族五人を乗せた車が住み慣れた家から発進した時、私はやはりめそめそと涙を浮かべていました。瞬間的に近くに住む、隣のクラスの同じ器楽部の男の子の部屋を見上げたら、窓辺に私たちを見送る彼の姿を見つけ、余計に切ない気持ちになりました。
仙台は、寒冷地だからか制服がセーラー服の中学はほとんどありません。転校先の学校の制服も、ご多分にもれずブレザーでした。セーラー服姿で、しかも顔には名古屋では当たり前の“ニキビ”という名の青春のシンボルがたくさんあった私は、東北のつるんと綺麗なもち肌の同級生たちの間ではかなり目立ちました。名前を覚えてもらうまでの間、私は「セーラー服でニキビの子」と呼ばれました。
ピアノの勉強への不安は無くならないまま、転校して半月ほどが過ぎたある日、お昼休みに音楽室から素晴らしいピアノの音が聞こえてきました。いてもたってもいられず音楽室を覗くと、スマートで優しそうなメガネの男性がピアノを弾いていました。音楽の教諭で吹奏楽部の顧問をしていらっしゃるY先生でした。「先生、それ…なんていう曲ですか?」「ワイマンの“銀波(ギンパ)”。“銀歯”じゃねぇぞ」Y先生の冴えない(失礼!)ダジャレとは裏腹に、そこには美しい音の雫がキラキラと踊っていました。いっぺんにY先生が好きになりました。
「先生。私、吹奏楽部に入ります」おやおや。熱血指導で有名なS先生の吹奏楽部に入ったりしたらピアノの練習どころではなくなってしまうかもしれないのに、気づいたら私はそう口走っていました。「楽器はなんでもいいです!」(続く)
ピアニストのひとり言 第825回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅵ
楽器はなんでもいいと頼み込んだものの、学期の途中からの入部です。吹奏楽ではコンクールでも名の知れた中学校でしたので、もうすぐ二学期も終わりという時期にほとんどの楽器には“空き”はなく、「これなら」と与えてもらえたのはバスクラリネットでした。
クラリネットは、オーケストラでいえばヴァイオリンのような“花形”ですが、バスクラリネットとなるとどんな音なのかも知りませんでしたし、楽器そのものも吹いたことはもちろん見たこともなく、少々心細いスタートになりました。いざ取り組んでみるとクラリネット以上に音を出すのが難しく、リードによっても、ふわーっと良い音が出たり、反対にうんともすんとも出なくなってしまったりするのです。なかなかコツを掴めない私に同じ学年のクラリネットの男の子が根気よく教えてくれて、懸命に彼のいうとおりにやってみようとするのですがなかなかうまくいかず、トランペット(小学校の頃、少しだけやったことがありました)とはまた違う、リードを使う管楽器の難しさを知りました。
S先生はよく面倒を見てくださって、お昼休みに音楽準備室に先生に会いに行くのがとても楽しみでした。行くと決まって「おお、入れ入れ。ほい、ミカン食べろ」と、ミカンをいくつもさし出してくださったり、お茶を淹れてくださいました。先生は私が将来の夢を話すと、「そうか、そうか」と、嬉しそうになさいました。何をアドバイスするわけではなく、とにかく笑顔で「うん、それはいいなぁ」と、楽しそうに聞いてくださるのです。私は先生に話を聞いてもらうだけで夢への一歩を進めるような…さらに、きっとその夢が叶うような心持ちになったのでした。今思うと、その時の私に、望みうる最高の導きをいただいていたのではないでしょうか。
ある日、思いきってピアノの先生のことをS先生に相談してみました。音大…できれば、できる限り“良い”ところに入りたい。その準備をしっかりできる先生をご紹介いただけませんか、と。S先生は、地元の音楽大学の教授で、作曲家のE先生をご紹介くださいました。E先生は、歌の伴奏などで演奏活動もして
いらっしゃるとのことでした。早速コンタクトを取り、ピアノの他にソルフェージュや聴音、楽典など、音大受験に必要なことを全てお願いすることになりました。
作曲家でいらっしゃるだけあって、E先生のレッスンはそれまでのピアノ科出身の先生方とは一線を画するものでした。実技だけでなくソルフェージュの時間がひときわユニークで、聴音や新曲視唱の教材は全て私のために先生が作曲してくださったオリジナルにしてオーダーメイドの課題でした。指揮科の学生がするようなスコアリーディングや、古楽専攻の人が学ぶバロック時代の“数字付き和声”の実習などもさせてくださいました。いずれも、音楽大学に入ってから学ぶようなレベルのものでしたので、入試対策を通り越して大学の予習までさせてもらった感じでした。
鍵盤楽器の古典調律についての話もしてくださいましたが、理論だけに終わることなく、ご自宅のピアノのうちの一台(先生のお宅には3台のグランドピアノがありました)を純正調に調律して実際に弾かせてくださったりしました。平均律調律に生じる“歪み”や、純正律の“純粋な”響きとの違いを耳で確かめることができたのは、知識を得るだけでなく和声感を身につけるのに大きく役に立ちました。
そんなふうに、ピアノのレッスンの他にもたっぷりと時間をかけてくださるE先生のレッスンはいつも二〜三時間に及びました。レッスンの二回に一回は、途中「はい、スタミナ補給!」とおっしゃって、コーヒーブレイクになりました。先生が豆を挽くところから淹れてくださるコーヒーがまた抜群に美味しく、ピアノという楽器の勉強だけでなく、スコアの読み方やバロックの様式、ひいてはヨーロッパの文化までを、幅広く学ばせてくださいました。
そんなある日のこと。いつものように音楽準備室に行くと、S先生がこんなことをおっしゃいました。「練習の時間を取られるから、もう吹奏楽部は続けなくて良いよ。それより、自分にとって大切なピアノの勉強を、思いっきりしろ」それは本当に私のためを思ってくださっての、真心からのアドバイスでした。先生のお気持ちがしみじみ嬉しく、「よし。こうなったら何が何でも夢を実現させて、先生に喜んでいただくぞ」と、改めて決意を固めたのでした。(続く)
ピアニストのひとり言 第826回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅶ
S先生のいらっしゃる中学校には、半年も在籍できませんでした。私たちの家族の家は、新しくできる分校の学区に入っていたからです。そのことを知ったのも、S先生からでした。「美奈子の家は、どこだ?」「大和町三丁目…大きな道路の東側です」「それなら、四月から新しい中学だ」母から仙台への転勤を告げられた時のようなショックでした。大好きなS先生と今までのようにお話しできなくなる…私はその場で泣きたい気持ちでした。
新しい中学校に通い始めると、間もなく仲良しの友だちもできました。その頃の友人たちとは今も連絡を取り合っていますし、リサイタルに来てくれたりもしています。でも、学校生活よりも気になっていたのはやはり音楽の勉強、そして進路のことでした。仙台に音楽科のある高校がないわけではなかったのですが、そこへ進むべきか普通の高校に進むべきか。来る日も来る日も、悩み込むばかりでした。
悩みはもう一つありました。楽器の問題です。それまで母が結婚する前から持っていたアップライトピアノで練習していたのですが、音楽の方に進むとなるとどうしてもそれでは事足りないと感じることが多くなっていったのです。微妙なタッチ、ダイナミクスや音色の変化を身につけるにあたって、グランドピアノで練習しているのとしていないのとでその差は歴然。「グランドピアノで練習したら必ず、もっと上手になるのに」と、悶々とする日々が続きました。
ある時、ついに決意しました。グランドピアノを買ってもらえないか直談判しよう、と。母に?父に?どう切り出そう…。社宅住まいでしたし、また転勤がないとも限らないのに、二つ返事で承諾してくれるわけはないということは、わかっていました。そこで、いきなり父に言うのはあまりにもハードルが高いので、母に話しました。予想どおりの返事でした。でも、私は折れませんでした。これは簡単に引きさがれる問題ではないのです。音楽大学に進めるのか、ピアニストとして生きていけるようになるのかの瀬戸際だという気がして、必死で交渉を続けました。そして、あまりにしつこい私に辟易としたのか、
ついに母が言ったのです。「わかったわかった。じゃあ、学年三番以内に入ったら買ってあげる」
その頃の私の成績はさほど悪くはなかったものの、せいぜい学年十数番といったところで、三番以内に入るほどではありませんでした。いつも数人の秀才たちがトップを争っていたので、その中に割り込むというのはほとんど不可能に思われましたし、母もまさかそれはないだろうと踏んだのでしょう。でも、私にしてみれば素晴らしく輝かしい光が目の前に広がった瞬間でした。
一日も早くグランドピアノを手に入れたい私は、果たして間もなく行われた模擬試験で学年三番に入りました。「ママ、買ってくれるよね?」母はやれやれと気持ちが重く沈み入ったことでしょう。私はというと、天にも登る気持ちでした。
選定したグランドピアノが搬入される前に、今まで使っていた母のアップライトピアノが搬出されました。私が生まれる前から今までずっと一緒に暮してきたのに、ひとり淋しく家を後にしてトラックの荷台に積み込まれるその姿を見た時、突然熱いものが込み上げて来ました。新しいピアノを得ることばかりを考えて、このピアノの気持ち(!)や運命を考えてあげなかった自分が、ひどく薄情な人でなしのように思われてきました。「ごめんなさい」「ありがとう」心の中で何度も繰り返し、視界が涙で滲んで仕方ないのをじれったく思いながら、目を凝らしてトラックを見送りました。
もちろん、新しくやってきたグランドピアノは毎日夢のような喜びをくれました。初めて私の部屋でその音色を聴いた妹は「すご〜い!ホールのピアノの音みたい!」と目を輝かせました。そんな中、私はずっと音楽高校に進むのか普通高校に進むのか、さらに普通高校ならどこを受験するか、決めかねていました。私立の音楽高校には、確実に特待生で入れると言われていました。でも、自分には上の人たちがたくさんいる学校の方が向いているという気もしていました。
そうこうしているうちに、運命を決めることになった三者面談の日がやってきました。(続く)
ピアニストのひとり言 第827回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅷ
「美奈子は二女だっちゃ〜」中学三年の進路を決める最後の三者面談で、担任のA先生が、私が目指すべき高校名をそうおっしゃったのには、母も私もお互いの顔を見合わせるほどびっくりしました。
二女…宮城県第二女子高等学校といえば、男子校の仙台第一高等学校と並ぶ、私たちが住んでいた仙台南学区切っての進学校。当時は男女別学でしたので、女子の私が望みうる最高レベルの高校だったのです。そこよりも二つほど偏差値の低い学校あたりが妥当なところかなぁ、と思っていたので、まさに青天のへきれきでした。どうやら、グランドピアノのために火事場の馬鹿力を発揮した私の頑張りを、A先生は本人の実力以上に評価してくださっていたようでした。
もちろん一度勢いで良い成績を取れたからといって受かるような高校ではなく、ピアノの勉強をしつつそんな厳しい受験勉強ができるものなのか、あまり自信はありませんでした。でも、 A先生がなんの疑いもないような表情でおっしゃった「美奈子は二女だっちゃ〜」という一言が忘れられず、それを思い出すにつけ、頑張れば本当に合格できそうな気持ちになっては悩みこんでいました。高校から音楽の専門の学校で学ぶ魅力も、捨てがたかったのです。
二女高に仮に入学できたとしても、授業についていくだけでも大変なのに、ピアノや音楽の勉強と両立できるのかしら、というのが最大の不安要素でしたが、母に「長い人生の中で高校の3年間は、大学への準備というだけではない、とても貴重な時間よ。良い学校に入って良いお友達ができたら、それは一生の財産になる。大学に入ったら音楽中心になるのだから、反対に今のうちに幅広い知識を身につけるのもいいことだと思うし、色々な分野に進むお友達から学ぶことも多いと思うのよ。大丈夫、きっとできる!」と言われると、確かにそうかもしれないという気がしてきました。
かくして私は二女高に合格。勉学のかたわらピアノも頑張って、高校2年の時には、ピアノを習っていたE先生の紹介で月に一度、東京にレッスンに通っていた弘中孝先生から「死ぬ気で頑張れば(大学は)桐朋に入れるよ。桐朋を目指すなら林先生につきなさい」と言っていただけました。…と、いうと聞こえがいいのですが、実は勉強そっちのけで、高校にいる間もわずかな空き時間を惜しんで音楽室を覗き、空いているとピアノを弾いているという有様で、成績は下がる一方でした。それでも担任の先生が「いいんだいいんだ。鈴木は音楽の方に進むと決めているんだから、成績は気にせずそっちを頑張れ」と、理解を示して応援してくださったのは、大きな励みになりました。
二女高時代の音楽担当のH先生には大学四年の時の教育実習でもお世話になり、のちに二女高の音楽科非常勤講師のお話をいただくことになりました。「演奏活動やピアノのレッスンの仕事で忙しいから、授業の準備や学校での時間を取られることには不安があるかもしれないね。でも、あなたなら両方立派にできるよ。それに何より、あなたに教えてもらえたら生徒は本当に幸せだと思う。大変だったら一年で辞めてもいいから、どうか引き受けてもらえませんか?」オファーをくださった時のH先生のありがたいお話は、忘れられません。
中学三年の担任A先生といい、音楽のH先生といい、弘中孝先生といい…思い返すと先生方にはなんと恵まれたことでしょう。どの先生も「大丈夫、きっとできる」と、いつも不出来な私を心から応援してくださいました。実際、それが全て本当に叶ったことを思うにつけ、教育とは相手を正しく導くことよりも、相手のちからを信じて励ますことに尽きるのではないかという気がしてくるのです。
そして、母が言ったとおり、高校時代の友人たちとは今も繋がっていて、お互いに近況を報告しては励ましあったり、相手の幸せを自分のことのように喜びあって友情を温め続けています。リサイタルの折には、恩師の先生方や彼女たち同窓生が集まってくれて、小さな同期会になることも珍しくありません。「ああ、早く終わらないかしら」一度、ある本番の前に緊張のあまりついそんなことを呟いたら、それを聞いた友人から「美奈ちゃんたら、そんなこと言わないの。私たちとっても楽しみになのよ。美奈ちゃんも楽しんで!」と諭されたことがありました。彼女の愛情がひしひしと感じられ、また、皆の思いがひとつになっているような気がして、涙が溢れそうになりました。 (続く)
ピアニストのひとり言 第828回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅸ
高校時代、ピアノコンクールというものを受けたことがありました。日本最大の規模のものではありませんでしたが、地元ではよく知られた比較的大きなコンクールでした。参加を決めたのは自分の実力がどれほどのものなのか知りたかったのもありましたが、本選に進めたら大きなホールでスタインウェイのフルコンサートピアノが弾けることも、魅力でした。
果たして本選には進めたものの、その時の出来事は今思うと、それからの音楽人生のあり方に影響を与えるものになりました。自分としては充分に力を尽くしたつもりでしたので、一位にはなれなくても後悔はありませんでした。胸につっかかったのは、その順位でした。いいと思った人よりも、全然といっていいほど良さを感じなかった人の方が上位になっていたのです。
結果に納得がいかないのは私の聴き方、捉え方がまだ未熟だからなのだろうと思い、そのあとも自分は出なくてもなるべくコンクールを聴きに行くようにしましたが、その“つっかかり”がなくなることはありませんでした。それどころか、「ああ、この人の演奏好きだな」と思う人が予選で敗退し、一位に輝いた人の演奏を必ずしも好きになれない…といった、腑に落ちない違和感が重なるばかりでした。
さて、私は高校2年の頃から月に一度、東京へ林秀光先生のレッスンを受けに通うようになっていました。仙台から上野に出るのには“はつかり”という特急に乗って四時間以上…と、たいそう時間がかかっていたのが、東北新幹線が大宮まで開通するようになって随分短縮された頃でした。
他に仙台でも別の先生についていましたので、ピアノやソルフェージュ、音楽理論のレッスン代と東京への交通費などで、家計にかなりの負担をかけてしまっていました。買いたい楽譜や行きたいコンサートがあってもなかなかそれを母に言い出せず、機嫌の良さそうなタイミングを狙って緊張しながら切り出したものです。
「地方にいていい勉強をしようとすると、どうしてもハンデが発生する。経済的な条件が影響してしまうのも、なんとかならないものか」漠然とそんなことを感じていました。家族にわがままを言って音楽の道を進ませてもらっているぶん、申し訳ない気持ちも膨らむのでした。私は、リクルートという当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった企業が募集していた、奨学金給付生の申し込みをすることを決めました。合格するとかなりの金額が返済不要で給付されるというものでした。
定員は全国で10名。選ばれても第一志望校に現役合格しなければ受給資格を喪失する、という条件でした。まず、書類選考。『私は大学で何を学ぶか』というタイトルで、原稿用紙十数枚の論文を提出することになっていました。そんな長い“作文”を書く経験を持っていなかった私は、高校の現代国語の先生に指南をお願いしました。「内容はとてもいい。真摯な気持ちが伝わってきます。ただ、少し直すともっと良くなります。例えば…」具体的な例をあげて教えていただき、なんども添削を重ねて仕上げました。文章で思いを伝える楽しさを、改めて感じました。
書類審査を通過できるのは全国で25名でした。私はその中に残ることができ、晴れてリクルート仙台支社での最終選考、面接に挑むことになりました。今までに芸術部門での合格例はないと聞いていましたので、よほどのことがない限りは難しいだろうと、半ば諦めながら臨みました。
この時の経験は、面接は得意じゃないとわかるきっかけになりました。聞かれたことに答えるだけでなく、伝えたいと思ったことをつい自分から話してしまうのです。「音楽大学を卒業してピアニストになる他に、夢があるんです」「ほほう、それはどんな?」「学校を作りたいと考えています。ヨーロッパのコンセルヴァトワールのような。奨学金制度を整えて、実力があれば経済的な条件が整わなくても良い勉強ができるようなシステムを樹立させて…」その時の面接官の複雑な表情から、自分の失敗をはっきり見てとることができました。もちろん、結果は不合格でした。 (続く)
ピアニストのひとり言 第829回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅹ
高校三年の夏に受講した桐朋学園の夏期講習では、ピアノの実技でトップ四人の“Aマイナス”という成績を取ることができました。合格ラインにすら乗っていないだろうと思っていたので、驚きました。桐朋学園が日本でいちばん難しいと言われている聴音やソルフェージュの成績も、トップクラスという結果でした。E先生のレッスンの賜物だと思いました。
それでも、いよいよ受験の準備となるととても大変でした。ピアノの実技だけで二回に分けて審査され、ショパンのエチュードを二曲、バッハの平均律、ベートーヴェンのピアノソナタ『告別』の全楽章を用意しなければならなかったのです。レッスンに伺うたび、林先生の怒号がお部屋に響きました。レッスンには目黒に住む祖母が付き添ってくれましたが、壮絶な(?)叱咤にさぞや心を痛めていたのではと思います。でも、当の本人は不思議なことに、どんなに怒られても落ち込むどころか、いつも希望に溢れていました。「よし、きちんとおっしゃったことをマスターすればまた一歩、桐朋学園に近ける」と思うと早くピアノが弾きたくてもどかしくなり、仙台に帰る車中で膝の上に楽譜を広げて、注意されたことを復習しました。
入学試験ではどう弾いたのかあまり覚えていませんが、試験会場のスタインウェイのフルコンサートピアノの響きが素晴らしく、「ああ、深くて華やかで、なんともいえない良い音だなぁ」と思いながら弾いたことは覚えています。音楽理論や初見試奏などの専門教科の他には、小論文とその内容についての面接がありました。面接には全く自信がありませんでしたが、なんとか合格することができました。その時の受験番号は今も覚えています。
桐朋学園の教育方針は当時からかなり進んでいて、室内楽や二重奏のレッスンを担当する教師は、学生が大学を通して学内の先生以外の演奏家、指揮者、作曲家も指名することができました。また、パリ音楽院、モスクワ音楽院、イギリス王立音楽院やウィーン音楽大学、アメリカやドイツの名だたる音楽大学の教授やピアニストを招いては、頻繁にマスタークラスを開いていました。国際
コンクールの審査員をしていらっしゃるような先生方の公開レッスンは聴講するだけでも刺激になりましたが、何人もの先生のマスタークラスを受講する機会に恵まれたのは、とても大きな財産になりました。
レッスンのスタイルやアドバイスの与え方は、それぞれの先生方で全く異なりました。楽譜の解釈について指示をするレッスンが多い先生、奏法についてヒントを与えるのが上手な先生…。でも、共通していたのは、欧米の先生はどう弾くかをただ示すのではなく、その学生に今必要なことを的確に見極め、それを気づかせてその場でワークし、解決を見出すような導きをなさる、ということでした。
寮に入って最小限の仕送りでやりくりしていましたので、行きたいコンサートに気兼ねなく行くにはほど遠く、お昼代を浮かせるためにサンドイッチを作って持って行ったり、自動販売機のお茶を買う代わりにティーバックを持参して学食でお湯をもらってお茶を淹れたりして、節約を楽しんでいました。寮生活2年目から、先輩の紹介で近所の小学生の兄妹のピアノをレッスンするアルバイトが入ったのはとても助かりました。初めて自分で得たお金を握りしめて渋谷の東急デパートへ出かけ、シャネルのカウンターで母の日のプレゼントの口紅を買った時の高揚感は、忘れられません。
学友にも恵まれ、寮生活はとても楽しくてなんの不満もありませんでした。大きな浴場でゆっくりお風呂に入った後、談話室で四種類の新聞に目を通すひと時が、何よりのリラックスタイムでした。気になっていたのはヨーロッパの時事問題。友人に「歩く国際面」とからかわれたこともありました。
実は、気になっていたのは時事問題だけではありませんでした。ヨーロッパそのものが気になって仕方なかったのです。そこにはどんな文化が息づいているのだろう。どんな音が溢れているのだろう。…ヨーロッパの先生方のマスタークラスを受けるにつけ、音楽の“本場”を知らずにいる自分は、決定的な何かが欠落しているのではないか、という不安と、本場への憧れが膨らみました。でも、仙台の実家には大学受験を控えた妹とまだ中学生の弟もいます。東京の私大に通わせてもらっているだけでも大変なことなのに、留学のことを母に相談する勇気は、さすがにありませんでした。(続く)
ピアニストのひとり言 第830回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅺ
“本場”への思いは憧れの域を超え、やがて「東洋人である自分が西洋の芸術を極めることにそもそも意味があるのだろうか」という疑問へと変容していきました。いくら頑張っても、生まれながらに伝統と遺伝子を持っている当地の人にはかなわないのではないか。日本人でありながら“本場”で認められている音楽家も多くいらっしゃるはずですが、そのことは私の中に膨らんだ悩みや疑問を解決するのに充分ではありませんでした。
「なら、留学を検討しなさい」大学4年の時、またも恩師からの鶴の一声を聞くことになりました。演奏法の講義でお世話になっていた、作曲家のO先生です。「でもその前に、どんな音楽家になりたいのかを明確になさい」「良い音楽家になりたいです」「それはわかります。でも、良い音楽家と上手な音楽家は同じではないし、良い音楽家が有名な音楽家であるとも限りませんからね」「え?」耳を疑いました。「良い音楽家が…良さが世間に認められて、結果として有名になるのではないのですか?」「何を寝ぼけたことを言っているんです。有名な曲の中に駄作はいくらでもあるし、有名ではないものに素晴らしい作品がたくさんあることは、あなたもわかっているでしょう?」「…あ…!」
O先生の言葉を聞きながら、それまでコンクールで抱いていた違和感の種子が、スーッと溶けていくのを感じました。そうか、“コンクールうけ”する演奏が良い演奏とは限らない。コンクールで優勝して“売れている”人が、良い音楽家とも限らない。そういうことだったんだ。その数秒後、O先生はさらに衝撃的なことをおっしゃいました。「いいですか。良い音楽家になるための勉強と、有名になるためのそれとは全く違うんです。あなたはどうなりたいんですか?留学を検討するにあたって、それをよく考えなさい」
どこに留学するかを決めるにあたって、国そのものよりも、何を学びどんなことを身に付けたいかや、誰に習いたいかを重視しろ、ともアドバイスくださいました。O先生はアメリカで学んでいらした方なので、留学に対する考え方も合理的でした。フランスに憧れてパリ音楽院へ、とか、本場ということになっていて“はく”もつくからウィーンへ、といって留学先を決める人たちがとても
多いけど、その多くは何を学んでくるやら懐疑的である、というのがO先生の所見でした。
さりとて、自分はどこへ行くべきか、どうなりたいのか…悩みは深まるばかりでした。それまでは、とにかく一目散に“もっと上手になりたい”“桐朋学園に入りたい”という目標を胸にピアノに向かってきたのですが、ぷっつりとその先への道が途絶えてしまったような感じでした。何も見えないくせに、このままでは不十分であることだけは明らかでした。
ハンガリーの作曲家バルトークの民族音楽に出会ったのは、そんな時でした。しばしばそれは、日本の民謡の音調にも似ているように聴こえました。「音楽に西洋も東洋もない。国境、民族、時空…そういうものを超越して、楽しさや悲しさ、懐かしさや美しさを共感しあうのが、音楽芸術の真髄ではないか」音楽を通して、バルトークがそう語りかけているようにも感じました。日本と同じペンタトニック(五音音階)をもち、日本と近い言語体系をもつマジャール(ハンガリー)という国に、強く心惹かれました。しかも、ハンガリーにはあのフランツ・リストが創設した名門リスト音楽院がある…。
「ハンガリーのリスト音楽院に留学したいと思います」O先生に打ち明けると、「ハンガリーは素晴らしいところですよ。第一次世界大戦まで、暫くオーストリー・ハンガリー帝国という二重国家だったのは知っていますね?複雑な歴史があって大変面白い、優秀な人たちがたくさんいるところです。社会主義国ですから、留学費用もそれほどかからないはずです」というお返事が。ますますハンガリーへの気持ちが高まりました。ウィーンと違って日本人が少ないのも魅力でした。
母に留学を申し出たところ、意外なことに「2年なら」という条件でお許しが出ました。妹が卒業まで6年かかる医学系の学部に入学していたので、私も2年の“追加”が認められたのです(心の中でどんなに妹に感謝したことか!)。早速入学のために必要な書類や手続きについて調べました。O先生に、教授の推薦状が必要なのでお願いできますか、と伺いました。「いいですよ。お世辞ではなく正直に書きますけど。留学がダメだったらお見合いしなさい。実はあなたに合わせたい人がいるんです。真面目で良い男ですよ」これには目が泳ぎました。合格を祈るしかありませんでした。(続く)
ピアニストのひとり言 第831回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”Ⅻ
「卒業後、仙台できちんとリサイタルをしなさい」専攻の林秀光先生からこんなお達しをいただいたのは、まさに青天の霹靂(へきれき)でした。「卒業試験で演奏する曲だけでは足りないからね。まずは全体のプログラムを考えてみなさい。時間的には、前半後半合わせて75分から80分程度だね」
リサイタル。それは一般的に、複数の出演者による“コンサート”に対して、一人の出演者が完結する演奏会をさす言葉です。卒業を機に、何人か集まって合同で行うコンサートはたくさんありますが、林先生がおっしゃったのはもちろんそれではなく、一人で一晩の演奏会をやってのける“リサイタル”のほうでした。
「私にできるでしょうか…」おずおずとそう言った時の私は、きっととても複雑な顔をしていたことでしょう。幼い頃からピアニストを目指してきた私にとって、自分のリサイタルをするのは確かに長年の夢ではありましたが、一方それは特別な才能と立派なコンクール歴に恵まれた若手か、プロだけがなし得るものだ、と理解していました。自分がそんな大それたことをやってのけられるものか自信がなかったうえ、「東洋人の自分が西洋音楽をする意味はどこにあるのだろうか」などという漠然とした悩みにはまり込んでしまったせいか、実技の成績も落ちてきていたのです。
「“できるかどうか”ではなく、“やる”んだよ。やると決めたら、やり切るしかない。ここまで勉強してきたのだから、ちゃんとリサイタルをしてデビューしなきゃ。仙台の先生にも話しておくから、相談して力になってもらいなさい。あなたならできるよ」レッスンからの帰り道だけでなく、寮に戻ってからも、いよいよピアニストとしてデビューするのだという夢のような気持ちと大変な重圧の両方を感じていました。同時に、プログラムをどうしたら良いか、時間を忘れて未明まで悩む日々が始まりました。
仙台に帰省した折には、受験前にお世話になったE先生のお宅を訪れ、アドバイスを頂きました。「弾きたい曲をただ並べるだけではいいものにならないよ。曲の性格、調性の兼ね合い、作曲年代、プログラムを通してのテーマ…それらを、聴く人のことも考えて、客観的に吟味して組み立てないと」そこで、様々な案を考えては改良を重ね、「よし、これがベストだ!」というものに絞り込むのですが、数日すると何かが違うような気がしてくるのでした。
たくさんの曲を知っているのが望ましいというだけではありません。全てを一人で演奏するのですから、自分の集中力、テクニックにとって無理がなく、似たようなものに偏りすぎず、かつデビューにふさわしく自身の個性をアピールできる、“ありきたりではないが奇をてらっている感じもなく、聴いているお客さまが飽きない”ものにしたい…。たくさん悩みましたが、その時に感じたのは「ああ、なんて楽しいのだろう」という喜びでした。膨大な楽譜に目を通し、実際に弾いてみたりしながらどれがいいか検討していると、こんなにも素敵な曲がたくさんあるピアノという楽器を、これからも弾いていける嬉しさがこみ上げてきました。
お客さまに喜んでもらいたいという気持ちは、いつしか不安を上回っていました。怖いもの知らずとはこのことです。その時の私は、まるでパーティーでお客さまにお出しする料理のメニューを組み立てるみたいに、ひたすらわくわくしていました。そして、ロングドレスを着てステージに立つ自分を想像しては、まだまだ暗譜もできていないというのにリサイタルが待ち遠しくなるのでした。ふと、思いました。「こんな感じ、前にもあったな」…それがなんだったのか思い出した時は、人知れず笑ってしまいました。小学校を卒業して中学の制服のセーラー服を買ってもらった時、あまりにも嬉しくて、春休みの間、毎日こっそり着ては姿見に映して心踊らせていた、あの時の気持ちとそっくりだったのです。
ようやく全てのプログラムが決まったのは、ホールを予約して数ヶ月が経ってから。会期は卒業して約一ヶ月後の4月16日。残された時間は限られていました。留学の申し込みは済ませていたものの、練習やらチラシ作成やら何やらにまみれて、リスト音楽院からの返事が来ないことも忘れがちでした。(続く)
ピアニストのひとり言 第832回
デビュー30周年記念連載 “楽しくなくては始まらない
楽しいだけでは終わらない”ⅩⅢ(最終回)
無事に桐朋学園を卒業して四年間を過ごした寮を出るとき、荷物はダンボール箱数個だった入寮時の数倍に膨れ上がっていました。楽譜、書籍、洋服、靴…グランドピアノとベッドが置かれた六畳足らずの部屋に、よくこれらが収まっていたなと思われるほどでした。増えていたのは、荷物だけではありません。心からの信頼を寄せられる楽友、貴重な経験や、一生大切にしたい思い出が、入学したときには想像もつかなかったほどたくさんできました。
父がレンタルしたワゴン車に荷物を詰め込み、最後の記念にと、寮の正門前で父に撮ってもらった写真があります。母の左腕を両腕でつかんで、甘えるように寄り添っている私。実家に戻る安心感よりも、もうここには戻ってくる必要のない立場になる寂しさや、これからの自分の行く末に対する不安のようなものがみて取れ、我ながら情けない表情です。
それもそのはず、リサイタルまであと一ヶ月を切っていましたし、リスト音楽院からもなんの返事もなく、この四月から何をしたら良いものかどっちつかずの状態だったのです。リスト音楽院は、特にピアノを学ぶ者にとっては世界的な名門中の名門、落ちたとしても何の不思議もありません。私はピアノ教室の広告を作り、新聞に挟み込んでもらいました。
そうこうしているうちに、あっという間にリサイタル当日になりました。前日までできる限り練習を重ねましたが、当日もピアノのそばにいないと落ち着きませんでした。ゲネプロ(通しリハーサル)を終え、いよいよ客入れの時間に。「ああ、今度このステージに上がる時には、もう本番なのだ」と思うと、不安と緊張に押しつぶされそうになりました。
開演。思ったよりもたくさんのお客様が拍手で迎えてくださいました。おじぎまではガチガチでしたが、いざピアノの前に座って弾き始めると、そこからは案外“いつも”の感じでした。楽屋や舞台袖で待っているのは確かに非日常のことでしたが、たとえそこがステージではあっても、聴こえてきたのは夢にまで
みるほどに弾き込んだ“いつも”の調べだったのです。音楽が体から自然に流れ出てくるようでした。前半はモーツァルトとショパン、後半はスクリャービンの初期から中期にかけての作品。本番はあっという間でした。
「迫力ある音楽を作りだしながらも激情に流されることはない。また、甘美に歌いながらも、さわやかな印象を失わない。この“知と情”のバランスによるさわやかさはこの人の持ち味のひとつだろう。楽しく聴かせるすべを心得ているようにも感じた。」「後半のスクリャービンは作曲家に対する強い共感を感じさせる確信に満ちた演奏で、透きとおった音色と明確な打鍵、いかにも自然な音楽の流れで聴衆をひき込んだ。曲がよくみえてくる。」新聞に掲載された演奏会批評です。
ちらほらと生徒さんが集まり始めた頃、一通のエアメールが届きました。ハンガリーからでした。「あなたの入学が認められました。つきましては、諸手続きに入っていただきたく…」夢のようでした。新学期は九月。当時は社会主義国でしたので、日本から送金できる銀行も限られていました。社会主義国はおろか、外国すら…いいえ、飛行機すら乗ったことがないというのに、何を用意したら良いものやら。第一、航空券の買い方も知りませんでした。ビザやパスポートの申請など、慌ただしく準備に取り掛かりました。
私に習い始めた数人の生徒さんは、高校時代の同級生に出張レッスンしてもらえることになりました。デビューリサイタルでも大変お世話になったE先生のお宅に留学の報告に伺うと、思いがけず、先生が主宰していらした仙台楽友協会の月刊会報誌に掲載される巻頭エッセイ『ハンガリー留学だより』の、連載執筆の依頼をいただきました。この会報誌は仙台で行われるコンサート情報や演奏会批評が掲載されている、地元ではよく知られた音楽誌でしたから、とても光栄なお話でした。以来、“書く”ことも私にとって大切なファクターの一つになり、この連載も18年ほど続いています。
喜びだけでなく、哀しみや心の痛みを表現した“音楽(音の楽しみ)”もあるように、楽しみとは、多層構造をもつ多面体なのではないでしょうか。あれから30年が過ぎ、さまざまな失敗も重ねてきましたが、弾くこと、学ぶこと、書くことからはいつも新鮮な刺激と楽しみをもらっています。失敗も、うまく“消化”されると楽しみに“昇華(昇格?)”するということも、少しだけわかってきました。
「音楽で幸せを届けられる人になりたい」という子供の頃からの夢は、今も変わりません。“楽しみ”を糧に、これからも生きていることに感謝しながら、音楽の道を歩み続けていきたいと思っています。 (完)
お知らせ
現在、「ピアニストのひとり言」のArchives化を進めています。近日中に公開の予定ですが、それまでの間、各年の連載は以下のリンクよりご覧いただけます。
また旧サイト時代の連載は、以下のリンクよりご覧いただけます。
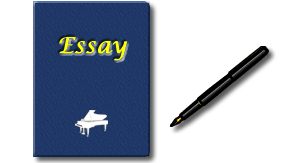
● 旧サイト