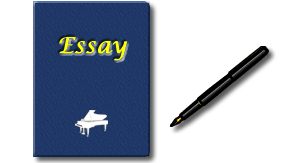Suzuki Minako Official Site - ピアニスト 鈴木美奈子のオフィシャルサイト:ピアニストのひとり言
Loading pages...
ピアニストのひとり言 第836回
こんなにドキドキするとは思いませんでした。昨日約一ヶ月に及ぶ防音室拡大工事のすべてを終え、いよいよ今日はベーゼンドルファーをリビングから新しい部屋に移動させるという、最後の大イベントが待っていたのです。睡眠中も遠足前のようにわくわくしていたようで、いつもは目覚ましがなってもなかなか起きられないのに、朝6時きっかりに目が覚めてしまったほどでした。
楽器を部屋に入れるときというのは、どうしてこんなにもわくわくするのでしょう。中学生時代に初めてグランドピアノが家にやってきた日も、十数年前にこの楽器が我が家にやってきたときも、嬉しくて嬉しくて朝から落ち着きませんでした。
新しい防音室は、部屋を二つ繋げ、廊下やクローゼット、玄関すら潰してスペースを確保しただけのことはあって、なかなかの広さになりました。単なる防音・遮音性だけでなく、美しく自然な響きが得られる設計にしていただきたくて、音楽家御用達の専門業者に施工をお願いしました。
そんなに高額なものだとは知らず、いただいた見積もり書の金額に打ちのめされそうになった、憧れの漆喰仕上げ。何度も断念しかかりましたが、女は度胸!当初からの希望を貫いて、壁も天井も漆喰で仕上げていただきました。温かみと“テレジアンイエロー”を意識して、ほのかなイエローに調合していただきました。コテ仕上げの模様は、職人さんに実際に何通りかをデモンストレーションしていただいて決めました。塗り終えてからは、時間が経って乾いていくにつれ徐々に色味が抜けていき、まるで壁が呼吸しながら部屋に馴染んでいくようでした。
天井は、マンションの構造体で動かすことのできないダクトをうまくカモフラージュすることと、漆喰塗りが映えるよう考慮して、これまた贅沢ですが下がり天井に間接照明を仕込んでいただきました。雰囲気のある柔らかな灯りに漆喰の凹凸が浮かび上がり、とてもいい雰囲気を醸してくれます。まさにイメージどおりの仕上がりになりました。
atelier anima
床はもちろん、前回同様無垢材です。今回は、色味に惹かれてメープルを選びました。イメージとしてはテラコッタに近い、やや赤みのあるほんわかした色合いで、経年変化も楽しめそうです。壁には、床から天井までの、作り付けの楽譜棚もこしらえていただきました。早速楽譜を収納してみたところ、A4よりも若干大きい特殊なサイズの楽譜がぐんぐん収納されていきます。今までは一箇所に収まりきれずに数カ所に置いていたので、お目当てを探すのにかなりの時間がかかったことも少なくありませんでしたが、これならスムーズです。
と、ほとんど何もかもが思いどおりに出来上がったのですが、やはり主役のピアノが入らないことには完成とは言えません。移動をお願いした運送屋さんはベーゼンドルファーのエキスパート。「道路が空いていたので助かりました」と、予定よりも早くにこやかにいらして、三人で手際よく作業を進めてくださいました。
作業は無事終了。いよいよ、ひとり落成式の“お弾き初め”です。「さあ!何を弾こうかしら…」考えがまとまる前に、シューベルトやバルトークの作品を次々に弾き始めていました。「私だけじゃなく、ピアノも喜んでいる!」弾くほどにそう感じられて、止まらなくなりました。まるで、リスト音楽院のレッスン室でお稽古しているような、伸びやかで素晴らしい響きです。これから毎日ここで好きなだけピアノを弾けるなんて…嗚呼、なんたる幸せ!
午後にいらした生徒さんも口々に「わぁ、ステキ!」「自然の中で音を奏でているようです」「とっても気持ちがいい!」と、笑顔を輝かせて喜んでくださって、もう他に何もいらないほど満ち足りた気持ちになりました。
ゲストもわたしも心地よくリラックスして、一緒になって面白いアートやカルチャーの世界に遊んだり、思い思いに感じたことを表現しあったり、クリエイティヴで心躍るようなことを楽しんで発信できる空間にしていけたら…という願いを込めて、ここを“atelier anima”(アトリエ・アニマ。またはラテン語読みで、アテリエール・アニマ)と命名しました。
アニマとは、ラテン語で“命”、“魂”という意味。命あるもの…ということから、アニマルanimalの語源にもなっている言葉です。ささやかな空間ではありますが、命の輝きに感謝し、喜びをみんなでシェアしあえる場所になりますように、と、夢みています。
ピアニストのひとり言 第835回
今年も残すところあと一週間。11月末から始まったレッスン室の拡大工事も、三週目が終わりました。順調に進み、あとは廊下やクローゼットのクロスを貼り、エアコンや照明器具など電気関係を整えるばかりです。床や壁だけでなく、大々的に天井まで解体され、無残な姿になった部屋を目の当たりにしてひどく心細くなった初日が、ずいぶん昔のことのようです。
以前から、漆喰の壁に憧れを抱いていました。あたたかな風合いと堅牢さの両方が感じられるだけでなく、西洋ではメソポタミア文明の遺跡からも発掘され、日本でも縄文時代のものが最古とされているように、古くから永く使われ続けている建築材料としても心惹かれていたのです。そこで、担当者に「壁はぜひ、漆喰でお願いしたいんです」と伝え、いざ見積もりを出していただいたら、あまりに高額でびっくり!でも、頭の中にはすでに、「壁はビニールクロスではなく漆喰で、床は無垢材。下がり天井に間接照明を入れて…」というイメージが出来上がってしまっていました。お財布の事情には厳しいものがありましたが、妥協はできませんでした。
漆喰といえば本来は白ですが、少し柔らかな表情が欲しかったのでほんのり黄色を混ぜていただくことに。事前に見本をいくつか持ってきていただいて、色みと質感を確認しました。施工当日の朝には、職人さんと塗り方(コテの使い方による模様をどうするか)を、打ち合わせ。二日間かけて天井部分も一センチ近い厚さに塗り込め、何日もかけて完全に乾かします。今も除湿器を一日中フル稼働させていますが、それでも朝は二重サッシが激しく結露するほどの湿気です。
それでも、塗った直後には濃いめに出ていた色が乾くに従って明るくなり、少しずつイメージの色に近づいていくのを眺めるのは、なんとも楽しみなものです。生徒さんも口々に「ずいぶん出来てきましたね」と声をかけてくれたり、まだ塗る前の土台に「先生、これが漆喰なの?」と、小さな生徒さんも興味を持ってくれて、皆で完成を心待ちにしています。
湿気といえば、施工期間中リビングダイニングに避難しているわがベーゼンドルファーは、健気に音を奏でてくれていますが、キッチンと繋がっているので湿気によるダメージが心配です。コンディションが不安定になって響板への影響が出たり、断線してはしまわないかと、気が気ではありません。湯気を気にして、料理も調理時間の短いものだけにしたり、出来合いのものを取り入れたりしているのですが、そろそろストレスになってきました。
湯気。楽器にとっては禁物ですが、世の中にこんなに幸せな物体はないと思うときがあります。楽しいティータイムに沸かすお湯。できたてのお料理やごはん。疲れた体を沈める湯船…。今、寒い季節なので余計にそう思うのかもしれませんが、立ちのぼる湯気には、体だけでなく、心も温めてくれる効用があるようにも感じるのです。
そういえば、夕げの時間が近づくと母が台所で支度をしているのが気になって、集中して練習できなくなる食いしん坊の子どもでした。いい匂いが漂ってきたり、小気味の良い包丁の音が聞こえてくると気になってしまい、ついピアノの椅子を離れて台所を覗きに行ってしまうのです。湯気がのぼるお鍋からはいい匂いだけでなく、くつくつと美味しそうな音まで聞こえてきます。「今日のおかずは、なあに?」…テキストを見ることも調味料を計量することもなく、いくつもの献立の段取りを同時進行させ、手際よく料理を仕上げていく手さばきに圧倒されながら、母にそうたずねる瞬間が好きでした。
私が不器用なのをわかっていたのか、練習の妨げにならないよう気を遣ってのことだったのか、あまり細かく調理を教えることはしなかった母ですが、要所要所で「この味を覚えておきなさい」と、味見をさせてくれたのはよく覚えています。あたりをつけ、味を決める前のお吸い物や、煮込む前の煮物の味、小豆を炊くときの甘さ加減。味だけでなく、味見はどの段階で行うものなのかを、感覚で教えてくれたように思います。
一週間後は大晦日。実家では、いつものように母が台所で湯気を上げながら、お正月の料理を仕込むことでしょう。工事の全てを終えて引渡しをしませ、広くなったレッスン室にピアノを移動させるまで、あと数日。広い部屋でのびのびピアノを弾くことと同じくらい、盛大に湯気をたてて思うぞんぶん料理をしたい気持ちにおそわれている、年の瀬です。
-
ピアニストのひとり言 第834回
音楽は目には見えないということを、受け入れられなくなる時があります。音楽を聴いていると、確実に人の気配が感じられるのに、海の荒波がすぐ目の前に広がっているようなのに、ふと我に返ってそこに何もないと気づくとき、魔法にかけられていたような不思議な気持ちになるのです。
教会やお寺に一歩入った時にも、同じようなことをしばしば感じます。扉を一枚開けただけだというのに、そこは明らかに外とは違う静謐な空気に満ちていて、宗派は関係なく、心が穏やかに清められていくのをはっきりと感じるのです。凛と威厳に満ちているようでもあり、温かな包容のようでもあるその気配は、目には見えないのが信じられないほど生々しく肌に感じられ、身震いを覚えることもあります。
デビュー30周年記念の連載“楽しくなければ始まらない、楽しいだけでは終わらない”を書いている間、三つのコンサートがありました。二つは、昨年スタートしたシューベルト連続演奏会の仙台・東京での二公演、もう一つは立川にある教会でのコンサート。いずれもたくさんのお客さまに恵まれ、自分なりに作曲家のメッセージをお届けすることができて、何物にも変えがたい幸せな時間になりました。特に今回、演奏しながら、そこに何かとてもいい空気が対流しているのを感じました。大きくて気持ちの良い何かに包まれながら、演奏しているような気持ちでした。気のせいかと思ったりもしましたが、リサイタルの後「皆がひとつになって、何か温かいものを抱いているような感じでした」と、私と同じような感想をお寄せくださる方が、少なくありませんでした。
ステージでは私がひとりで弾いていたかもしれませんが、その空気、雰囲気はお客様と一緒に作ったもの。もしその時の空気が目に見えたら、それはほんわり柔らかく揺れながら会場を包む、大きなシャボン玉のようなものだったかもしれません。中には居心地がよく、「ありがとうございます」と、感謝したくなるような、まさに“有り難い”空気が満ちている、割れないシャボン玉…。
立川の教会でのコンサートは、ヴァイオリニストの友人とのジョイントでした。彼女と私とが音楽という言語で会話しているのを、皆さんが微笑みながら、頷きながら、心を開いて見守ってくださったのは、とても嬉しいことでした。小春日和の美しい青空の祝福を受けた会場は、音楽という暖炉を囲んで語り合う、気のおけないお茶会のような空気に溢れ、ちょっと音の狂った古いアップライトピアノの音色も、和やかな雰囲気づくりに一役買ってくれていたようでした。その教会の牧師さまのお姉さまのお嬢さんが、私が非常勤講師をしていた時の教え子で、期せずしてしばらくぶりの再会を果たせたことも、偶然ではないような気がしたほどでした。
最近よく使われるようになった言い回しに“空気を読む”というのがありますが、読むだけでなく、心の眼で見たり、感じたりできるものだとしたら、もっと人生はファンタジーに溢れ、愉しいものになることでしょう。音楽を聴いて架空の風景を“見て”いるときも、教会やお寺に入った時に特別な気配を“感じて”いるときも、コンサートでいい雰囲気に包まれているときも、私たちは目に見えないものを感性でとらえ、その存在感に心動かされているのです。そういえば、英語では理解できたことを“私は見える(I see)”と表現するのも、興味深いことです。
私ごとですが、今自宅のレッスン室の拡大工事をしています。職人さんが朝8時に来てくださるおかげで、少し早起きするようになりました。目を覚まし、ベランダに出て、スタートして間もない“今朝”の空気を体いっぱいに吸い込むと、きっと良い1日になるという確信が湧いてきます。朝食後、ほんの数分でも気になるところをちょこちょこっとお掃除するのも、気持ちの良いものです。それでもなかなかエンジンがからない時は、ゼレンカやロッティ、アレッサンドロ・スカルラッティなど、大好きな18世紀初頭の音楽を聴きます。すると、たちまち部屋の中の空気が澄み、美しさ、心地よさを享受する感性のスイッチがポンっと入るのです。
何かと気ぜわしい師走の後半ですが、しばし仕事の手を休め、目に見えないものを感じてみるひと時を楽しんでみてはいかがでしょうか。サンタクロースを乗せたソリがみえてくるかも?
ピアニストのひとり言 第833回
目の前にいる彼女の面影は34年前と何一つ変わっていないと言ってもいいほどで、言葉を選ぶときに当時と同じように動く瞳を見るたび、その短くない年月は一体どこに消えていったのかしら、と、不思議な気持ちになりました。
「ね、覚えてる?受験の年、一緒に海に初日の出をみに行ったこと」「もちろん覚えてるよ。あの時は、美奈子ちゃんのお父様にずいぶんご迷惑をかけてしまったわね。考えてみたら、暗いなかを自転車で海まで初日の出を見に行くなんて、無謀な計画だったよね。それで、美奈子ちゃんのお父様が、それは危ないといって車で送ってくださって…」
大晦日。道路が凍っているかもしれないし、飲酒運転の取り締まりも今ほど厳しくなかった当時、慣れない車道を走って車にはねられたりしたら、目も当てられません。「で、妹と三人でいったのよね」「そうそう。少し曇はあったけど、なんとか初日の出を見ることができて…。あの時、私は目の前の受験に合格することで頭がいっぱいだったけど、美奈子ちゃんはそれだけではなく、音楽家として生きて行く決意を抱いていたんだって後になってわかって、すごいなぁって」
二人のお嬢様を立派に育てながら、この10年間は遺跡発掘の仕事にたずさわっている彼女。キリッと整った眉毛の下の眼差しは優しさをたたえ、どこかのんびりとした話し方も当時と変わっていません。その声を聞いていたら、水平線を黄金色に染めながらじわりじわりと雲間から姿を現した“その時”の太陽の光が生々しく蘇ってきて、思わずちいさな身震いに襲われました。あの時あんなに穏やかだった荒浜の海辺は、3.11の震災で津波による壊滅的な被害を受け、発見された溺死体は200とも300とも伝えられるも、あまりの悲惨さに報道されなかったという悲劇の舞台になりました。
大学合格とともに故郷仙台を離れ、卒業して数ヶ月後には日本を離れ、ピアニストとしての歩みを重ねるなかで、少しずつ苦手だったことを好きだと思えるようになっていきました。例えば、人にピアノを教えること。若い頃は「教え
るより、まだまだ自分が学びたいくらいなのに」とか「(生徒が)練習してくれないのは、私に指導力が足りないからだ」と考えては、焦ったり落ち込んだりしたものでしたが、人との関わりの中から、また、人に伝えることから得られる学びの大きさに気づいて、教えることは自分にとっての喜びに変わっていきました。
コンクールに対する違和感も、審査の仕事に関わるようになって徐々に変わっていきました。確かに芸術を点数で競うことには未だに一種のわだかまりを覚えなくはありませんが、人が目標を持って何かに取り組む姿には、尊いものがあります。おひとりおひとりに講評を書きながら、「どうかこの経験を人生の糧、励みにしてほしい」と祈るような気持ちになるのですが、それは私がステージで「どうかこの音楽がその方の心の糧になりますように」と願うのと、とても似ていることにも気づきました。
「何かに無心になって没頭する、ということをしていたくて。発掘の仕事はそれが楽しいの。実は随分前からピアノも習っているのよ。ベートーヴェンのソナタが大好きで」「素敵!昔から音楽好きだったものね。今回、舞台でちょっとだけ自分が自分から離れて、何者かによって“弾かされている”ような感覚になったの。ステージで30年以上弾いてきて、こんなことは初めて。それが無心、というものかはわからないけど。何であれ、物の本質はとてもシンプルなんだろうなぁ」
ル・コルビュジエの建築が本国と日本で印象が違ってしまうのはなぜか。バウハウスの残した問題…音楽以外にも話は尽きません。気づいたら、二時間半以上の時間が過ぎていました。「え、うそ。その二時間半はどこに飛んでいったの?」「あっという間なはずよ。いつの間にか、最後に会った時から34年も経っちゃったくらいなんだから!」「本当よね」
変わったことと、変わらないもの。その何れもが、人生に豊かな拡がりをもたらしてくれる。いや、まてよ。変わらない大切なものがあるからこそ、伸びやかに変わることができるのかもしれない…旧友の後ろ姿をいつまでも見送りながら、クリスマスのイルミネーションのせいか、自分が夢の国にいるような気持ちになった、師走のひと時でした。
ピアニストのひとり言 第832回
無事に桐朋学園を卒業して四年間を過ごした寮を出るとき、荷物はダンボール箱数個だった入寮時の数倍に膨れ上がっていました。楽譜、書籍、洋服、靴…グランドピアノとベッドが置かれた六畳足らずの部屋に、よくこれらが収まっていたなと思われるほどでした。増えていたのは、荷物だけではありません。心からの信頼を寄せられる楽友、貴重な経験や、一生大切にしたい思い出が、入学したときには想像もつかなかったほどたくさんできました。
父がレンタルしたワゴン車に荷物を詰め込み、最後の記念にと、寮の正門前で父に撮ってもらった写真があります。母の左腕を両腕でつかんで、甘えるように寄り添っている私。実家に戻る安心感よりも、もうここには戻ってくる必要のない立場になる寂しさや、これからの自分の行く末に対する不安のようなものがみて取れ、我ながら情けない表情です。
それもそのはず、リサイタルまであと一ヶ月を切っていましたし、リスト音楽院からもなんの返事もなく、この四月から何をしたら良いものかどっちつかずの状態だったのです。リスト音楽院は、特にピアノを学ぶ者にとっては世界的な名門中の名門、落ちたとしても何の不思議もありません。私はピアノ教室の広告を作り、新聞に挟み込んでもらいました。
そうこうしているうちに、あっという間にリサイタル当日になりました。前日までできる限り練習を重ねましたが、当日もピアノのそばにいないと落ち着きませんでした。ゲネプロ(通しリハーサル)を終え、いよいよ客入れの時間に。「ああ、今度このステージに上がる時には、もう本番なのだ」と思うと、不安と緊張に押しつぶされそうになりました。
開演。思ったよりもたくさんのお客様が拍手で迎えてくださいました。おじぎまではガチガチでしたが、いざピアノの前に座って弾き始めると、そこからは案外“いつも”の感じでした。楽屋や舞台袖で待っているのは確かに非日常のことでしたが、たとえそこがステージではあっても、聴こえてきたのは夢にまで
みるほどに弾き込んだ“いつも”の調べだったのです。音楽が体から自然に流れ出てくるようでした。前半はモーツァルトとショパン、後半はスクリャービンの初期から中期にかけての作品。本番はあっという間でした。
「迫力ある音楽を作りだしながらも激情に流されることはない。また、甘美に歌いながらも、さわやかな印象を失わない。この“知と情”のバランスによるさわやかさはこの人の持ち味のひとつだろう。楽しく聴かせるすべを心得ているようにも感じた。」「後半のスクリャービンは作曲家に対する強い共感を感じさせる確信に満ちた演奏で、透きとおった音色と明確な打鍵、いかにも自然な音楽の流れで聴衆をひき込んだ。曲がよくみえてくる。」新聞に掲載された演奏会批評です。
ちらほらと生徒さんが集まり始めた頃、一通のエアメールが届きました。ハンガリーからでした。「あなたの入学が認められました。つきましては、諸手続きに入っていただきたく…」夢のようでした。新学期は九月。当時は社会主義国でしたので、日本から送金できる銀行も限られていました。社会主義国はおろか、外国すら…いいえ、飛行機すら乗ったことがないというのに、何を用意したら良いものやら。第一、航空券の買い方も知りませんでした。ビザやパスポートの申請など、慌ただしく準備に取り掛かりました。
私に習い始めた数人の生徒さんは、高校時代の同級生に出張レッスンしてもらえることになりました。デビューリサイタルでも大変お世話になったE先生のお宅に留学の報告に伺うと、思いがけず、先生が主宰していらした仙台楽友協会の月刊会報誌に掲載される巻頭エッセイ『ハンガリー留学だより』の、連載執筆の依頼をいただきました。この会報誌は仙台で行われるコンサート情報や演奏会批評が掲載されている、地元ではよく知られた音楽誌でしたから、とても光栄なお話でした。以来、“書く”ことも私にとって大切なファクターの一つになり、この連載も18年ほど続いています。
喜びだけでなく、哀しみや心の痛みを表現した“音楽(音の楽しみ)”もあるように、楽しみとは、多層構造をもつ多面体なのではないでしょうか。あれから30年が過ぎ、さまざまな失敗も重ねてきましたが、弾くこと、学ぶこと、書くことからはいつも新鮮な刺激と楽しみをもらっています。失敗も、うまく“消化”されると楽しみに“昇華(昇格?)”するということも、少しだけわかってきました。
「音楽で幸せを届けられる人になりたい」という子供の頃からの夢は、今も変わりません。“楽しみ”を糧に、これからも生きていることに感謝しながら、音楽の道を歩み続けていきたいと思っています。 (完)
ピアニストのひとり言 第831回
「卒業後、仙台できちんとリサイタルをしなさい」専攻の林秀光先生からこんなお達しをいただいたのは、まさに青天の霹靂(へきれき)でした。「卒業試験で演奏する曲だけでは足りないからね。まずは全体のプログラムを考えてみなさい。時間的には、前半後半合わせて75分から80分程度だね」
リサイタル。それは一般的に、複数の出演者による“コンサート”に対して、一人の出演者が完結する演奏会をさす言葉です。卒業を機に、何人か集まって合同で行うコンサートはたくさんありますが、林先生がおっしゃったのはもちろんそれではなく、一人で一晩の演奏会をやってのける“リサイタル”のほうでした。
「私にできるでしょうか…」おずおずとそう言った時の私は、きっととても複雑な顔をしていたことでしょう。幼い頃からピアニストを目指してきた私にとって、自分のリサイタルをするのは確かに長年の夢ではありましたが、一方それは特別な才能と立派なコンクール歴に恵まれた若手か、プロだけがなし得るものだ、と理解していました。自分がそんな大それたことをやってのけられるものか自信がなかったうえ、「東洋人の自分が西洋音楽をする意味はどこにあるのだろうか」などという漠然とした悩みにはまり込んでしまったせいか、実技の成績も落ちてきていたのです。
「“できるかどうか”ではなく、“やる”んだよ。やると決めたら、やり切るしかない。ここまで勉強してきたのだから、ちゃんとリサイタルをしてデビューしなきゃ。仙台の先生にも話しておくから、相談して力になってもらいなさい。あなたならできるよ」レッスンからの帰り道だけでなく、寮に戻ってからも、いよいよピアニストとしてデビューするのだという夢のような気持ちと大変な重圧の両方を感じていました。同時に、プログラムをどうしたら良いか、時間を忘れて未明まで悩む日々が始まりました。
仙台に帰省した折には、受験前にお世話になったE先生のお宅を訪れ、アドバイスを頂きました。「弾きたい曲をただ並べるだけではいいものにならないよ。曲の性格、調性の兼ね合い、作曲年代、プログラムを通してのテーマ…それらを、聴く人のことも考えて、客観的に吟味して組み立てないと」そこで、様々な案を考えては改良を重ね、「よし、これがベストだ!」というものに絞り込むのですが、数日すると何かが違うような気がしてくるのでした。
たくさんの曲を知っているのが望ましいというだけではありません。全てを一人で演奏するのですから、自分の集中力、テクニックにとって無理がなく、似たようなものに偏りすぎず、かつデビューにふさわしく自身の個性をアピールできる、“ありきたりではないが奇をてらっている感じもなく、聴いているお客さまが飽きない”ものにしたい…。たくさん悩みましたが、その時に感じたのは「ああ、なんて楽しいのだろう」という喜びでした。膨大な楽譜に目を通し、実際に弾いてみたりしながらどれがいいか検討していると、こんなにも素敵な曲がたくさんあるピアノという楽器を、これからも弾いていける嬉しさがこみ上げてきました。
お客さまに喜んでもらいたいという気持ちは、いつしか不安を上回っていました。怖いもの知らずとはこのことです。その時の私は、まるでパーティーでお客さまにお出しする料理のメニューを組み立てるみたいに、ひたすらわくわくしていました。そして、ロングドレスを着てステージに立つ自分を想像しては、まだまだ暗譜もできていないというのにリサイタルが待ち遠しくなるのでした。ふと、思いました。「こんな感じ、前にもあったな」…それがなんだったのか思い出した時は、人知れず笑ってしまいました。小学校を卒業して中学の制服のセーラー服を買ってもらった時、あまりにも嬉しくて、春休みの間、毎日こっそり着ては姿見に映して心踊らせていた、あの時の気持ちとそっくりだったのです。
ようやく全てのプログラムが決まったのは、ホールを予約して数ヶ月が経ってから。会期は卒業して約一ヶ月後の4月16日。残された時間は限られていました。留学の申し込みは済ませていたものの、練習やらチラシ作成やら何やらにまみれて、リスト音楽院からの返事が来ないことも忘れがちでした。(続く)
ピアニストのひとり言 第830回
“本場”への思いは憧れの域を超え、やがて「東洋人である自分が西洋の芸術を極めることにそもそも意味があるのだろうか」という疑問へと変容していきました。いくら頑張っても、生まれながらに伝統と遺伝子を持っている当地の人にはかなわないのではないか。日本人でありながら“本場”で認められている音楽家も多くいらっしゃるはずですが、そのことは私の中に膨らんだ悩みや疑問を解決するのに充分ではありませんでした。
「なら、留学を検討しなさい」大学4年の時、またも恩師からの鶴の一声を聞くことになりました。演奏法の講義でお世話になっていた、作曲家のO先生です。「でもその前に、どんな音楽家になりたいのかを明確になさい」「良い音楽家になりたいです」「それはわかります。でも、良い音楽家と上手な音楽家は同じではないし、良い音楽家が有名な音楽家であるとも限りませんからね」「え?」耳を疑いました。「良い音楽家が…良さが世間に認められて、結果として有名になるのではないのですか?」「何を寝ぼけたことを言っているんです。有名な曲の中に駄作はいくらでもあるし、有名ではないものに素晴らしい作品がたくさんあることは、あなたもわかっているでしょう?」「…あ…!」
O先生の言葉を聞きながら、それまでコンクールで抱いていた違和感の種子が、スーッと溶けていくのを感じました。そうか、“コンクールうけ”する演奏が良い演奏とは限らない。コンクールで優勝して“売れている”人が、良い音楽家とも限らない。そういうことだったんだ。その数秒後、O先生はさらに衝撃的なことをおっしゃいました。「いいですか。良い音楽家になるための勉強と、有名になるためのそれとは全く違うんです。あなたはどうなりたいんですか?留学を検討するにあたって、それをよく考えなさい」
どこに留学するかを決めるにあたって、国そのものよりも、何を学びどんなことを身に付けたいかや、誰に習いたいかを重視しろ、ともアドバイスくださいました。O先生はアメリカで学んでいらした方なので、留学に対する考え方も合理的でした。フランスに憧れてパリ音楽院へ、とか、本場ということになっていて“はく”もつくからウィーンへ、といって留学先を決める人たちがとても
多いけど、その多くは何を学んでくるやら懐疑的である、というのがO先生の所見でした。
さりとて、自分はどこへ行くべきか、どうなりたいのか…悩みは深まるばかりでした。それまでは、とにかく一目散に“もっと上手になりたい”“桐朋学園に入りたい”という目標を胸にピアノに向かってきたのですが、ぷっつりとその先への道が途絶えてしまったような感じでした。何も見えないくせに、このままでは不十分であることだけは明らかでした。
ハンガリーの作曲家バルトークの民族音楽に出会ったのは、そんな時でした。しばしばそれは、日本の民謡の音調にも似ているように聴こえました。「音楽に西洋も東洋もない。国境、民族、時空…そういうものを超越して、楽しさや悲しさ、懐かしさや美しさを共感しあうのが、音楽芸術の真髄ではないか」音楽を通して、バルトークがそう語りかけているようにも感じました。日本と同じペンタトニック(五音音階)をもち、日本と近い言語体系をもつマジャール(ハンガリー)という国に、強く心惹かれました。しかも、ハンガリーにはあのフランツ・リストが創設した名門リスト音楽院がある…。
「ハンガリーのリスト音楽院に留学したいと思います」O先生に打ち明けると、「ハンガリーは素晴らしいところですよ。第一次世界大戦まで、暫くオーストリー・ハンガリー帝国という二重国家だったのは知っていますね?複雑な歴史があって大変面白い、優秀な人たちがたくさんいるところです。社会主義国ですから、留学費用もそれほどかからないはずです」というお返事が。ますますハンガリーへの気持ちが高まりました。ウィーンと違って日本人が少ないのも魅力でした。
母に留学を申し出たところ、意外なことに「2年なら」という条件でお許しが出ました。妹が卒業まで6年かかる医学系の学部に入学していたので、私も2年の“追加”が認められたのです(心の中でどんなに妹に感謝したことか!)。早速入学のために必要な書類や手続きについて調べました。O先生に、教授の推薦状が必要なのでお願いできますか、と伺いました。「いいですよ。お世辞ではなく正直に書きますけど。留学がダメだったらお見合いしなさい。実はあなたに合わせたい人がいるんです。真面目で良い男ですよ」これには目が泳ぎました。合格を祈るしかありませんでした。(続く)
ピアニストのひとり言 第829回
高校三年の夏に受講した桐朋学園の夏期講習では、ピアノの実技でトップ四人の“Aマイナス”という成績を取ることができました。合格ラインにすら乗っていないだろうと思っていたので、驚きました。桐朋学園が日本でいちばん難しいと言われている聴音やソルフェージュの成績も、トップクラスという結果でした。E先生のレッスンの賜物だと思いました。
それでも、いよいよ受験の準備となるととても大変でした。ピアノの実技だけで二回に分けて審査され、ショパンのエチュードを二曲、バッハの平均律、ベートーヴェンのピアノソナタ『告別』の全楽章を用意しなければならなかったのです。レッスンに伺うたび、林先生の怒号がお部屋に響きました。レッスンには目黒に住む祖母が付き添ってくれましたが、壮絶な(?)叱咤にさぞや心を痛めていたのではと思います。でも、当の本人は不思議なことに、どんなに怒られても落ち込むどころか、いつも希望に溢れていました。「よし、きちんとおっしゃったことをマスターすればまた一歩、桐朋学園に近ける」と思うと早くピアノが弾きたくてもどかしくなり、仙台に帰る車中で膝の上に楽譜を広げて、注意されたことを復習しました。
入学試験ではどう弾いたのかあまり覚えていませんが、試験会場のスタインウェイのフルコンサートピアノの響きが素晴らしく、「ああ、深くて華やかで、なんともいえない良い音だなぁ」と思いながら弾いたことは覚えています。音楽理論や初見試奏などの専門教科の他には、小論文とその内容についての面接がありました。面接には全く自信がありませんでしたが、なんとか合格することができました。その時の受験番号は今も覚えています。
桐朋学園の教育方針は当時からかなり進んでいて、室内楽や二重奏のレッスンを担当する教師は、学生が大学を通して学内の先生以外の演奏家、指揮者、作曲家も指名することができました。また、パリ音楽院、モスクワ音楽院、イギリス王立音楽院やウィーン音楽大学、アメリカやドイツの名だたる音楽大学の教授やピアニストを招いては、頻繁にマスタークラスを開いていました。国際
コンクールの審査員をしていらっしゃるような先生方の公開レッスンは聴講するだけでも刺激になりましたが、何人もの先生のマスタークラスを受講する機会に恵まれたのは、とても大きな財産になりました。
レッスンのスタイルやアドバイスの与え方は、それぞれの先生方で全く異なりました。楽譜の解釈について指示をするレッスンが多い先生、奏法についてヒントを与えるのが上手な先生…。でも、共通していたのは、欧米の先生はどう弾くかをただ示すのではなく、その学生に今必要なことを的確に見極め、それを気づかせてその場でワークし、解決を見出すような導きをなさる、ということでした。
寮に入って最小限の仕送りでやりくりしていましたので、行きたいコンサートに気兼ねなく行くにはほど遠く、お昼代を浮かせるためにサンドイッチを作って持って行ったり、自動販売機のお茶を買う代わりにティーバックを持参して学食でお湯をもらってお茶を淹れたりして、節約を楽しんでいました。寮生活2年目から、先輩の紹介で近所の小学生の兄妹のピアノをレッスンするアルバイトが入ったのはとても助かりました。初めて自分で得たお金を握りしめて渋谷の東急デパートへ出かけ、シャネルのカウンターで母の日のプレゼントの口紅を買った時の高揚感は、忘れられません。
学友にも恵まれ、寮生活はとても楽しくてなんの不満もありませんでした。大きな浴場でゆっくりお風呂に入った後、談話室で四種類の新聞に目を通すひと時が、何よりのリラックスタイムでした。気になっていたのはヨーロッパの時事問題。友人に「歩く国際面」とからかわれたこともありました。
実は、気になっていたのは時事問題だけではありませんでした。ヨーロッパそのものが気になって仕方なかったのです。そこにはどんな文化が息づいているのだろう。どんな音が溢れているのだろう。…ヨーロッパの先生方のマスタークラスを受けるにつけ、音楽の“本場”を知らずにいる自分は、決定的な何かが欠落しているのではないか、という不安と、本場への憧れが膨らみました。でも、仙台の実家には大学受験を控えた妹とまだ中学生の弟もいます。東京の私大に通わせてもらっているだけでも大変なことなのに、留学のことを母に相談する勇気は、さすがにありませんでした。(続く)
ピアニストのひとり言 第828回
高校時代、ピアノコンクールというものを受けたことがありました。日本最大の規模のものではありませんでしたが、地元ではよく知られた比較的大きなコンクールでした。参加を決めたのは自分の実力がどれほどのものなのか知りたかったのもありましたが、本選に進めたら大きなホールでスタインウェイのフルコンサートピアノが弾けることも、魅力でした。
果たして本選には進めたものの、その時の出来事は今思うと、それからの音楽人生のあり方に影響を与えるものになりました。自分としては充分に力を尽くしたつもりでしたので、一位にはなれなくても後悔はありませんでした。胸につっかかったのは、その順位でした。いいと思った人よりも、全然といっていいほど良さを感じなかった人の方が上位になっていたのです。
結果に納得がいかないのは私の聴き方、捉え方がまだ未熟だからなのだろうと思い、そのあとも自分は出なくてもなるべくコンクールを聴きに行くようにしましたが、その“つっかかり”がなくなることはありませんでした。それどころか、「ああ、この人の演奏好きだな」と思う人が予選で敗退し、一位に輝いた人の演奏を必ずしも好きになれない…といった、腑に落ちない違和感が重なるばかりでした。
他に仙台でも別の先生についていましたので、ピアノやソルフェージュ、音楽理論のレッスン代と東京への交通費などで、家計にかなりの負担をかけてしまっていました。買いたい楽譜や行きたいコンサートがあってもなかなかそれを母に言い出せず、機嫌の良さそうなタイミングを狙って緊張しながら切り出したものです。
「地方にいていい勉強をしようとすると、どうしてもハンデが発生する。経済的な条件が影響してしまうのも、なんとかならないものか」漠然とそんなことを感じていました。家族にわがままを言って音楽の道を進ませてもらっているぶん、申し訳ない気持ちも膨らむのでした。私は、リクルートという当時飛ぶ鳥を落とす勢いだった企業が募集していた、奨学金給付生の申し込みをすることを決めました。合格するとかなりの金額が返済不要で給付されるというものでした。
定員は全国で10名。選ばれても第一志望校に現役合格しなければ受給資格を喪失する、という条件でした。まず、書類選考。『私は大学で何を学ぶか』というタイトルで、原稿用紙十数枚の論文を提出することになっていました。そんな長い“作文”を書く経験を持っていなかった私は、高校の現代国語の先生に指南をお願いしました。「内容はとてもいい。真摯な気持ちが伝わってきます。ただ、少し直すともっと良くなります。例えば…」具体的な例をあげて教えていただき、なんども添削を重ねて仕上げました。文章で思いを伝える楽しさを、改めて感じました。
書類審査を通過できるのは全国で25名でした。私はその中に残ることができ、晴れてリクルート仙台支社での最終選考、面接に挑むことになりました。今までに芸術部門での合格例はないと聞いていましたので、よほどのことがない限りは難しいだろうと、半ば諦めながら臨みました。
この時の経験は、面接は得意じゃないとわかるきっかけになりました。聞かれたことに答えるだけでなく、伝えたいと思ったことをつい自分から話してしまうのです。「音楽大学を卒業してピアニストになる他に、夢があるんです」「ほほう、それはどんな?」「学校を作りたいと考えています。ヨーロッパのコンセルヴァトワールのような。奨学金制度を整えて、実力があれば経済的な条件が整わなくても良い勉強ができるようなシステムを樹立させて…」その時の面接官の複雑な表情から、自分の失敗をはっきり見てとることができました。もちろん、結果は不合格でした。 (続く)
ピアニストのひとり言 第827回
「美奈子は二女だっちゃ〜」中学三年の進路を決める最後の三者面談で、担任のA先生が、私が目指すべき高校名をそうおっしゃったのには、母も私もお互いの顔を見合わせるほどびっくりしました。
二女…宮城県第二女子高等学校といえば、男子校の仙台第一高等学校と並ぶ、私たちが住んでいた仙台南学区切っての進学校。当時は男女別学でしたので、女子の私が望みうる最高レベルの高校だったのです。そこよりも二つほど偏差値の低い学校あたりが妥当なところかなぁ、と思っていたので、まさに青天のへきれきでした。どうやら、グランドピアノのために火事場の馬鹿力を発揮した私の頑張りを、A先生は本人の実力以上に評価してくださっていたようでした。
もちろん一度勢いで良い成績を取れたからといって受かるような高校ではなく、ピアノの勉強をしつつそんな厳しい受験勉強ができるものなのか、あまり自信はありませんでした。でも、 A先生がなんの疑いもないような表情でおっしゃった「美奈子は二女だっちゃ〜」という一言が忘れられず、それを思い出すにつけ、頑張れば本当に合格できそうな気持ちになっては悩みこんでいました。高校から音楽の専門の学校で学ぶ魅力も、捨てがたかったのです。
二女高に仮に入学できたとしても、授業についていくだけでも大変なのに、ピアノや音楽の勉強と両立できるのかしら、というのが最大の不安要素でしたが、母に「長い人生の中で高校の3年間は、大学への準備というだけではない、とても貴重な時間よ。良い学校に入って良いお友達ができたら、それは一生の財産になる。大学に入ったら音楽中心になるのだから、反対に今のうちに幅広い知識を身につけるのもいいことだと思うし、色々な分野に進むお友達から学ぶことも多いと思うのよ。大丈夫、きっとできる!」と言われると、確かにそうかもしれないという気がしてきました。
かくして私は二女高に合格。勉学のかたわらピアノも頑張って、高校2年の時には、ピアノを習っていたE先生の紹介で月に一度、東京にレッスンに通っていた弘中孝先生から「死ぬ気で頑張れば(大学は)桐朋に入れるよ。桐朋を目指すなら林先生につきなさい」と言っていただけました。…と、いうと聞こえがいいのですが、実は勉強そっちのけで、高校にいる間もわずかな空き時間を惜しんで音楽室を覗き、空いているとピアノを弾いているという有様で、成績は下がる一方でした。それでも担任の先生が「いいんだいいんだ。鈴木は音楽の方に進むと決めているんだから、成績は気にせずそっちを頑張れ」と、理解を示して応援してくださったのは、大きな励みになりました。
二女高時代の音楽担当のH先生には大学四年の時の教育実習でもお世話になり、のちに二女高の音楽科非常勤講師のお話をいただくことになりました。「演奏活動やピアノのレッスンの仕事で忙しいから、授業の準備や学校での時間を取られることには不安があるかもしれないね。でも、あなたなら両方立派にできるよ。それに何より、あなたに教えてもらえたら生徒は本当に幸せだと思う。大変だったら一年で辞めてもいいから、どうか引き受けてもらえませんか?」オファーをくださった時のH先生のありがたいお話は、忘れられません。
中学三年の担任A先生といい、音楽のH先生といい、弘中孝先生といい…思い返すと先生方にはなんと恵まれたことでしょう。どの先生も「大丈夫、きっとできる」と、いつも不出来な私を心から応援してくださいました。実際、それが全て本当に叶ったことを思うにつけ、教育とは相手を正しく導くことよりも、相手のちからを信じて励ますことに尽きるのではないかという気がしてくるのです。
そして、母が言ったとおり、高校時代の友人たちとは今も繋がっていて、お互いに近況を報告しては励ましあったり、相手の幸せを自分のことのように喜びあって友情を温め続けています。リサイタルの折には、恩師の先生方や彼女たち同窓生が集まってくれて、小さな同期会になることも珍しくありません。「ああ、早く終わらないかしら」一度、ある本番の前に緊張のあまりついそんなことを呟いたら、それを聞いた友人から「美奈ちゃんたら、そんなこと言わないの。私たちとっても楽しみになのよ。美奈ちゃんも楽しんで!」と諭されたことがありました。彼女の愛情がひしひしと感じられ、また、皆の思いがひとつになっているような気がして、涙が溢れそうになりました。 (続く)
ピアニストのひとり言 第826回
S先生のいらっしゃる中学校には、半年も在籍できませんでした。私たちの家族の家は、新しくできる分校の学区に入っていたからです。そのことを知ったのも、S先生からでした。「美奈子の家は、どこだ?」「大和町三丁目…大きな道路の東側です」「それなら、四月から新しい中学だ」母から仙台への転勤を告げられた時のようなショックでした。大好きなS先生と今までのようにお話しできなくなる…私はその場で泣きたい気持ちでした。
新しい中学校に通い始めると、間もなく仲良しの友だちもできました。その頃の友人たちとは今も連絡を取り合っていますし、リサイタルに来てくれたりもしています。でも、学校生活よりも気になっていたのはやはり音楽の勉強、そして進路のことでした。仙台に音楽科のある高校がないわけではなかったのですが、そこへ進むべきか普通の高校に進むべきか。来る日も来る日も、悩み込むばかりでした。
悩みはもう一つありました。楽器の問題です。それまで母が結婚する前から持っていたアップライトピアノで練習していたのですが、音楽の方に進むとなるとどうしてもそれでは事足りないと感じることが多くなっていったのです。微妙なタッチ、ダイナミクスや音色の変化を身につけるにあたって、グランドピアノで練習しているのとしていないのとでその差は歴然。「グランドピアノで練習したら必ず、もっと上手になるのに」と、悶々とする日々が続きました。
ある時、ついに決意しました。グランドピアノを買ってもらえないか直談判しよう、と。母に?父に?どう切り出そう…。社宅住まいでしたし、また転勤がないとも限らないのに、二つ返事で承諾してくれるわけはないということは、わかっていました。そこで、いきなり父に言うのはあまりにもハードルが高いので、母に話しました。予想どおりの返事でした。でも、私は折れませんでした。これは簡単に引きさがれる問題ではないのです。音楽大学に進めるのか、ピアニストとして生きていけるようになるのかの瀬戸際だという気がして、必死で交渉を続けました。そして、あまりにしつこい私に辟易としたのか、
ついに母が言ったのです。「わかったわかった。じゃあ、学年三番以内に入ったら買ってあげる」
その頃の私の成績はさほど悪くはなかったものの、せいぜい学年十数番といったところで、三番以内に入るほどではありませんでした。いつも数人の秀才たちがトップを争っていたので、その中に割り込むというのはほとんど不可能に思われましたし、母もまさかそれはないだろうと踏んだのでしょう。でも、私にしてみれば素晴らしく輝かしい光が目の前に広がった瞬間でした。
一日も早くグランドピアノを手に入れたい私は、果たして間もなく行われた模擬試験で学年三番に入りました。「ママ、買ってくれるよね?」母はやれやれと気持ちが重く沈み入ったことでしょう。私はというと、天にも登る気持ちでした。
選定したグランドピアノが搬入される前に、今まで使っていた母のアップライトピアノが搬出されました。私が生まれる前から今までずっと一緒に暮してきたのに、ひとり淋しく家を後にしてトラックの荷台に積み込まれるその姿を見た時、突然熱いものが込み上げて来ました。新しいピアノを得ることばかりを考えて、このピアノの気持ち(!)や運命を考えてあげなかった自分が、ひどく薄情な人でなしのように思われてきました。「ごめんなさい」「ありがとう」心の中で何度も繰り返し、視界が涙で滲んで仕方ないのをじれったく思いながら、目を凝らしてトラックを見送りました。
もちろん、新しくやってきたグランドピアノは毎日夢のような喜びをくれました。初めて私の部屋でその音色を聴いた妹は「すご〜い!ホールのピアノの音みたい!」と目を輝かせました。そんな中、私はずっと音楽高校に進むのか普通高校に進むのか、さらに普通高校ならどこを受験するか、決めかねていました。私立の音楽高校には、確実に特待生で入れると言われていました。でも、自分には上の人たちがたくさんいる学校の方が向いているという気もしていました。
そうこうしているうちに、運命を決めることになった三者面談の日がやってきました。(続く)
ピアニストのひとり言 第825回
楽器はなんでもいいと頼み込んだものの、学期の途中からの入部です。吹奏楽ではコンクールでも名の知れた中学校でしたので、もうすぐ二学期も終わりという時期にほとんどの楽器には“空き”はなく、「これなら」と与えてもらえたのはバスクラリネットでした。
クラリネットは、オーケストラでいえばヴァイオリンのような“花形”ですが、バスクラリネットとなるとどんな音なのかも知りませんでしたし、楽器そのものも吹いたことはもちろん見たこともなく、少々心細いスタートになりました。いざ取り組んでみるとクラリネット以上に音を出すのが難しく、リードによっても、ふわーっと良い音が出たり、反対にうんともすんとも出なくなってしまったりするのです。なかなかコツを掴めない私に同じ学年のクラリネットの男の子が根気よく教えてくれて、懸命に彼のいうとおりにやってみようとするのですがなかなかうまくいかず、トランペット(小学校の頃、少しだけやったことがありました)とはまた違う、リードを使う管楽器の難しさを知りました。
S先生はよく面倒を見てくださって、お昼休みに音楽準備室に先生に会いに行くのがとても楽しみでした。行くと決まって「おお、入れ入れ。ほい、ミカン食べろ」と、ミカンをいくつもさし出してくださったり、お茶を淹れてくださいました。先生は私が将来の夢を話すと、「そうか、そうか」と、嬉しそうになさいました。何をアドバイスするわけではなく、とにかく笑顔で「うん、それはいいなぁ」と、楽しそうに聞いてくださるのです。私は先生に話を聞いてもらうだけで夢への一歩を進めるような…さらに、きっとその夢が叶うような心持ちになったのでした。今思うと、その時の私に、望みうる最高の導きをいただいていたのではないでしょうか。
ある日、思いきってピアノの先生のことをS先生に相談してみました。音大…できれば、できる限り“良い”ところに入りたい。その準備をしっかりできる先生をご紹介いただけませんか、と。S先生は、地元の音楽大学の教授で、作曲家のE先生をご紹介くださいました。E先生は、歌の伴奏などで演奏活動もして
いらっしゃるとのことでした。早速コンタクトを取り、ピアノの他にソルフェージュや聴音、楽典など、音大受験に必要なことを全てお願いすることになりました。
作曲家でいらっしゃるだけあって、E先生のレッスンはそれまでのピアノ科出身の先生方とは一線を画するものでした。実技だけでなくソルフェージュの時間がひときわユニークで、聴音や新曲視唱の教材は全て私のために先生が作曲してくださったオリジナルにしてオーダーメイドの課題でした。指揮科の学生がするようなスコアリーディングや、古楽専攻の人が学ぶバロック時代の“数字付き和声”の実習などもさせてくださいました。いずれも、音楽大学に入ってから学ぶようなレベルのものでしたので、入試対策を通り越して大学の予習までさせてもらった感じでした。
鍵盤楽器の古典調律についての話もしてくださいましたが、理論だけに終わることなく、ご自宅のピアノのうちの一台(先生のお宅には3台のグランドピアノがありました)を純正調に調律して実際に弾かせてくださったりしました。平均律調律に生じる“歪み”や、純正律の“純粋な”響きとの違いを耳で確かめることができたのは、知識を得るだけでなく和声感を身につけるのに大きく役に立ちました。
そんなふうに、ピアノのレッスンの他にもたっぷりと時間をかけてくださるE先生のレッスンはいつも二〜三時間に及びました。レッスンの二回に一回は、途中「はい、スタミナ補給!」とおっしゃって、コーヒーブレイクになりました。先生が豆を挽くところから淹れてくださるコーヒーがまた抜群に美味しく、ピアノという楽器の勉強だけでなく、スコアの読み方やバロックの様式、ひいてはヨーロッパの文化までを、幅広く学ばせてくださいました。
そんなある日のこと。いつものように音楽準備室に行くと、S先生がこんなことをおっしゃいました。「練習の時間を取られるから、もう吹奏楽部は続けなくて良いよ。それより、自分にとって大切なピアノの勉強を、思いっきりしろ」それは本当に私のためを思ってくださっての、真心からのアドバイスでした。先生のお気持ちがしみじみ嬉しく、「よし。こうなったら何が何でも夢を実現させて、先生に喜んでいただくぞ」と、改めて決意を固めたのでした。(続く)
ピアニストのひとり言 第824回
「お父さん、転勤が決まったのよ」母のその言葉は、その地に引越しをすることを意味しました。私は胸の鼓動が早くなるのを感じながら、おずおずと尋ねました。「どこに行くの?」「仙台よ」
なんということ!幼い頃のたくさんの思い出がある仙台にまた戻ることになるとは…。でも、それは同時に、入学を夢みていた名古屋のK高校の音楽科を受験できなくなるということでもありました。「そんな…」言葉を失った後、出てきたのは涙でした。「じゃぁ、私K高校に行けないんだね。ピアノの勉強はどうしたらいいの?」
母は、自分のことばかり心配して、泣きながら転勤を嫌がる娘を前にどんなに困ったことでしょう。今振り返ると、我ながら恥ずかしい限りです。「仙台にもピアノの先生はいらっしゃるし、習えるわよ」「だって、だって、仙台には公立の音楽高校なんて、ないんだよ?」とても音楽が盛んだった名古屋に比べて、仙台にはのんびりしたイメージを抱いていました。音楽雑誌のコンサート情報を見ても名古屋の方がずっと外来のアーティストの公演が多いし、果たして“通用”するようになるための勉強ができるのか、いい先生が見つかるのか、不安がふくらむばかりでした。
名古屋音楽学校でのソルフェージュのレッスンでは、最後に担当の先生がこんな呼びかけをしました。「さぁ!誰かピアノを弾いてくれる人はいますか?」すると、発表会やコンクールが近い人が「はい」と手を挙げ、度胸試しのために演奏曲を披露してくれるのです。みんなうっとりするほど上手でした(その中には、のちに桐朋学園で再会を果たし、今も友情が続いている人たちもいます)。「ああ、私もいつか、あんなふうに弾けるようになるのかしら」自分が出遅れているのを感じつつも、憧れのため息をつきながら帰宅したものです。
ようやく正しいテクニックの基本を学び始めた私。彼女たちと同じ学校を受験するのだから、これからよほど頑張らないと、という焦りも感じていました。ですから余計に、このタイミングで仙台に転校するのは決定的に不利なことだ、という気持ちにとらわれてしまったのです。それからしばらくは、暗澹たる気持ちで過ごしました。大好きな学校の担任の先生や、クラスメイトたちとのお別れも、多感な年頃の私にとってはとても悲しく、一人だけ仲間外れにされてしまうような寂しさを感じました。
11月になり、引越しの日がやってきました。慌ただしく荷物を乗せたトラックを見送り、家族五人を乗せた車が住み慣れた家から発進した時、私はやはりめそめそと涙を浮かべていました。瞬間的に近くに住む、隣のクラスの同じ器楽部の男の子の部屋を見上げたら、窓辺に私たちを見送る彼の姿を見つけ、余計に切ない気持ちになりました。
仙台は、寒冷地だからか制服がセーラー服の中学はほとんどありません。転校先の学校の制服も、ご多分にもれずブレザーでした。セーラー服姿で、しかも顔には名古屋では当たり前の“ニキビ”という名の青春のシンボルがたくさんあった私は、東北のつるんと綺麗なもち肌の同級生たちの間ではかなり目立ちました。名前を覚えてもらうまでの間、私は「セーラー服でニキビの子」と呼ばれました。
ピアノの勉強への不安は無くならないまま、転校して半月ほどが過ぎたある日、お昼休みに音楽室から素晴らしいピアノの音が聞こえてきました。いてもたってもいられず音楽室を覗くと、スマートで優しそうなメガネの男性がピアノを弾いていました。音楽の教諭で吹奏楽部の顧問をしていらっしゃるY先生でした。「先生、それ…なんていう曲ですか?」「ワイマンの“銀波(ギンパ)”。“銀歯”じゃねぇぞ」Y先生の冴えない(失礼!)ダジャレとは裏腹に、そこには美しい音の雫がキラキラと踊っていました。いっぺんにY先生が好きになりました。
「先生。私、吹奏楽部に入ります」おやおや。熱血指導で有名なS先生の吹奏楽部に入ったりしたらピアノの練習どころではなくなってしまうかもしれないのに、気づいたら私はそう口走っていました。「楽器はなんでもいいです!」(続く)
ピアニストのひとり言 第823回
クリスティアン・ツィメルマンという名のその優勝者は、ポーランド出身の18歳の青年でした。当時私は11歳になったばかり。自分とさほど変わらない年齢なのに、その堂々たる演奏はまるで別次元でした。貴公子のような風貌と、その演奏にふと感じられる青年らしい爽やかさに、憧れの気持ちは一気に沸点に達しました。
ショパンの音楽への憧れと、ツィメルマンへの憧れ。今思うと、どっちがどっちかわからないまま、両方ともに恋に落ちたような感じだったかもしれません。とにかく、それまでは漠然と抱いていた「ピアニストになれたらいいなぁ」という気持ちが、この時を境に「必ずピアニストになるぞ」という確固たる決意に至ったのは確かです。
ピアニストになるためには、兎にも角にもまず音楽大学を目指さなくては。でも、そのためには今までの“趣味のお習い事”の域を超え、“きちんとした”先生について基礎からしっかり身につけないといけません。二つ年下の妹もまたピアノを習っていましたし、九つ年下の弟はまだ幼稚園にも上がっていないという状況の中で、母にそれを願い出るのはかなりの勇気が要りました。でも、今思うと我ながらなんとワガママなことかと恥ずかしくなるのですが、その時は自分の願いをなんとしてでも通すことしか頭にありませんでした。
その頃、私たち家族は父の転勤の関係で名古屋に住んでいました。名古屋は今も昔も芸どころというか、お習い事がとても盛んで音楽教育も熱心な土地柄でした。音楽科が設けられている公立高校が二つありましたし、音楽大学は五つもあるほどです。親族に音楽家がいるわけでもなく、コネも特別な情報も持っていない私は、名古屋音楽学校というところに通わせてもらうことになりました。そこでお習いした先生はとても厳しく、テクニックを最初から全て“やり直し”することが課されました。今思うとその奏法には疑問に思う点がなくはないのですが、指を独立させて一つ一つの音を上部から打鍵するという奏法を叩き込まれました。スケール(音階)やハノンを、気が遠くなるほどゆっくりのテンポでお稽古する日々が続きました。
学校ではとてもいい友達に恵まれ、中学に上がっても、夏休み明けが待ち遠しくなるほど楽しい中学生活を送っていました。通っている学校の制服のセーラー服が大好きで、それを毎日着られるだけでも幸せでした。学校から帰ると、脱いだセーラー服を丁寧にハンガーに掛け、ブラッシングしてホコリを落とし、きちんと風呂敷をかけておきました。スカートは美しいプリーツを保つべく“寝押し”する…といったお手入れを、毎日欠かしませんでした。
ただ、バレーボールやドッジボールといった球技だけは突き指の心配があるため憂鬱で、いやいやボールを受けようとするからか、お約束のようにしょっちゅう突き指をしては保健室で手当てを受ける羽目になりました。放課後は器楽合奏部に入部して、小学校時代に少しだけ習ったヴァイオリンを弾いてもいました。名古屋音楽学校へレッスンに行くにはバスと地下鉄を乗り継がなければなりませんでしたが、母は小さな弟につきっきりでしたし一人で通っていました。
密かな楽しみは、レッスンの帰りに音楽学校の近くにあったヤマハ(当時は日本楽器)に立ち寄ること。特に楽譜売り場は夢のような場所でした。ずらりと並んだベートーヴェンやショパンの楽譜…。これらの曲を好きなだけお稽古できたらどんなに幸せだろう。他にも、値段が高くてお小遣いではなかなか買えなかった音楽雑誌を手にとってはドキドキしながらページをめくっていました。初めてお小遣いで買った音楽書は、ショパンの伝記。途中、感激して何度も泣きながら読み進めましたが、二度と祖国ポーランドに帰ることもないまま結核という不治の病に倒れ、39歳という若さでこの世をさってしまったドラマティックな最期には、ただただ号泣するばかりでした。音楽書を買うために、図書券狙いで音楽雑誌に投稿したりもしました。幸運なことに、投稿するたびに採用されました。
ピアノを弾くにつけ、書を読むにつけ、音楽への憧れは深まるばかり。名古屋市内の公立の音楽高校を受験して、音楽大学を目指す…目の前には素晴らしい道が広がっているような気持ちでした。ところが中学2年のある日、それまで光り輝いていた未来予想図に暗い雲が立ち込め、全ての希望が打ち砕かれるような知らせが飛び込んできたのです。
ピアニストのひとり言 第822回
ヴァイオリンは、祖母が弾いていた楽器でしたし、母方のいとこ二人ともが習っていたので、身近な楽器でした。お盆や正月休みに家族で帰省すると、私たち姉妹はピアノを、いとこたち兄弟はヴァイオリンを、一曲づつ祖母に聴いてもらいのが“なわらし”になっていました。私にとってそれは、発表会と同じくらい大切で楽しみなイベント。祖母は必ず「上手になったわね」と褒めてくれたので、そのコメントが聞きたくて聴いてもらうのが待ち遠しくて仕方ありませんでした。
小学校高学年の私にとって、ヴァイオリンの魅力は自分で音程を作ることができること、そして、ヴィヴラートをかけられる楽器だということ。いずれも、ピアノにはない特徴です。でも、実はもう一つ、心惹かれる大きなポイントがありました。それは、“持ち運べる”ということ。楽器のケースを持って颯爽と歩く…私にとってそれは、可愛いキャラクターのついた靴を履くことよりもずっと憧れてやまない、素敵な“いでたち”に思われました。
ピアノを習わせてもらうだけでも大変なことだったはずなのに、母はヴァイオリンを習わせてくれました。もちろん、安い方から数えた方がずっと早い値段の楽器と弓でしたし、一番安いケースでしたが、なんであれとにかく嬉しくて小躍りせんばかりでした。学校の“お楽しみ会”があるとヴァイオリンを持って行き、かろうじて弾けるようになったバッハのメヌエットなどを披露したりしました。ピアノの場合と同じく、この頃までは緊張するという自覚がまったくないほど、人に演奏を聴いてもらう喜びの方がはるかに大きく上回っていました。
結局、ピアノとの両立が難しいと悟り、ヴァイオリンを習っていたのは短い間だけになりましたが、なんとかヴィヴラートをかけて弾けるところまでは進みましたし、ボーイング(弓使い)を体験できたことや、音程に意識を向ける感覚を得られたことは、今にとても役立っているように思います。考えてみたら、弦楽器や管楽器の人たちは音大に入る時にも、入った後も必ず副科で
ピアノを学ぶのに、ピアニストが他の楽器を学ばないのはおかしなことです。種類の異なる楽器を弾く勉強をすることは、楽曲分析やアンサンブルをするにつけ、大事なことだと思っています。
というと、いかにも私の音楽人生は順風満帆のように聞こえるかもしれませんが、悩みや葛藤もありました。転勤族だったので転校が多く、そのたびピアノの先生も変わらなければならなかったのです。私は小さいうちから、先生によってとても大きな違いがあることを、身をもって感じることになりました。場合によってはせっかく終わりまで進んだ教則本なのに、「ちゃんとできていないから最初からやり直し」と言い渡されることもありました。同じレベルの演奏でも先生によって褒められたり、かなり厳しく直されたり、評価が異なることも知りました。
そんななか、祖母や友人に演奏を褒めてもらうのはとても嬉しいことでしたが、ピアノの先生からは、褒められるよりも足りないところをどんどん指摘して多くを教えて欲しい、と願うようになりました。それどころか、「音楽をきちんと学ぶには、レッスンだけでは足りない」と感じ始め、誕生日のプレゼントにはレコードをねだったり、お小遣いやお年玉を貯めては楽譜や専門書を買うようになりました。
知るほどに音楽への憧れは大きく膨らむばかりでした。その一方で、世の中には聴いたことがない作品がたくさんある。それぞれに様々な解釈もある。身につけなくてはいけないテクニックや知識も、山のようにある…。音楽を極めるためには、海のように大きく深い世界を隅々まで知り尽くし、体験しなければいけないことだらけに思われ、途方に暮れました。
自分がどこまで上達しうるのか、音楽の本質に近づきうるのか、何もわからない中でただ一つ明らかだったのは、音楽が好きでたまらない気持ちの揺るぎなさと、それがこれから先、決して衰えることはないだろうという確信でした。
そんなある日、ついに将来の目標を決定的にする出会いが訪れました。小学校6年の秋にワルシャワで行われた第9回ショパンコンクールの様子をテレビで観て、こともあろうにその時の優勝者に恋してしまったのです。(続く)
ピアニストのひとり言 第821回
「わたし、この人みたいになりたい」ピアノを始めて間もないわたしが母にそう伝えたピアニストは、ルービンシュタインでもホロヴィッツでもなく、中村八大さんでした。
今のように、国内外の名演奏をオンデマンドで映像や音源で聴くことができなかった時代、レコードとラジオの役割はとても大きなものでした。ピアノの音に耳で触れることはあっても、幼稚園に通う私がプロの演奏家の生演奏を“観る”機会があるわけでもなく、いったいこういう演奏がどのように紡ぎ出されるのか、想像するしかありませんでした。
『夢であいましょう』という名番組が放映されていたのは、残念ながらわたしがものごころつく前まででしたし、だいいち番組が始まるのはとても3歳や4歳の子供が起きている時間ではありませんでした。でも、再放送なのか特別番組だったのか、ある時、同じメンバーが出演する番組を見る機会があったのです。私は、ピアノの前に座る素敵な紳士に目も耳も釘付けになりました。その方は、にこやかに柔らかく、こともなげに(当時の私にはそう見えました)ピアノを弾くのです。お仲間がそのピアノに寄り添って耳を傾けたり、一緒に歌ったり…。「ああ、なんて素敵な世界なんだろう」と魅入られてしまったのでした。
その一方で、その頃感覚的に“怖い”と感じた音も、ありました。波の音です。せっかく海に初めて連れていってもらったというのに、車のドアを開けた途端に耳に飛び込んでききた、得体の知れないリズムを繰り返す波の音に圧倒され、その近くに行くことがどうしてもできなかったのです。小さな妹は海の近くに行きたい、行きたいと好奇心満々。困った母は、私に車の中で“お留守番”しているように言い含め、妹を海岸に連れ出しました。皆が戻ってきたとき、私はひとりでのどかに「まつぼっくりがあったとさ〜」と、歌っていたそうです。
小学校に上がってからも、ピアノへの、そしてピアニストへの憧れは募るばかりでした。父の愛聴盤だったシューベルトのピアノ五重奏曲『鱒』のような室内楽、歌の伴奏、ソロ。いいなぁ、と思う全ての音楽に、ピアノの音がありました。ところが、上手になりたくて仕方ないわりに別段練習熱心だったわけでもなく、練習中に学校での出来事が思い出されては、ピアノを弾くのを中断して母にそれを伝えにいくような、おしゃべりが大好きな子供でもありました。
ピアノに向かっているときも、真面目に集中しているとは思えない様子だったはずです。なにしろ、「音の反対言葉ごっこ」と面白がって、今習っているソナチネをテンポを極端に変えて(アレグロの楽章をアダージョに、あるいはその逆)弾いてみたり、妹に長調を短調に変調して弾いて見せてはげらげら笑ったりしていたのですから。他にも、弱いところを強く弾いたり、その逆をやってみたり…。でも、思い返せばそんな遊びも私にとって、ちょっと意味のある“試み”でした。ふざけているようではありましたが、曲にはそれぞれ、ふさわしいテンポがあること、短調長調だけでなく、同じ長調同士でも調を変えるとがらりとキャラクターが変わってしまうことなどを、身を以て理解することができたのです。
父は休日になると、よく私たちをドライブに連れ出してくれました。車の中は、私たち姉妹にとって最高のステージになりました。妹と歌集を何冊か見繕って持ち込み、童謡や流行歌、『みんなのうた』…知っている歌を片っ端から延々と歌っていたのですが、考えてみたら両親からは一度も「もうやめなさい」と言われたことはありませんでした。
音楽の教科書は隅からすみまで目を通し、書いてあることは全て頭に入れました。楽器がカラーで紹介されているページは特にお気に入りで、たくさんの美しい楽器の写真をうっとりと眺めるのが好きでした。やがて、その全ての音を聞いたり弾いたりしてみたくなりました。管楽器ならリコーダーがありましたし、打楽器なら小さな木琴がありました。でも、弦楽器は?あの素敵な音色を奏でる弦楽器を、どうしても弾いてみたい…そうなると居ても立っても居られない性格です。
「ママ、ヴァイオリン習いたいの。習ってもいい?」おずおずと母に切り出すまでに、多くの時間はかかりませんでした。
ピアニストのひとり言 第820回
手元に、私が産まれた時のアルバムがあります。両親にとって初めての子供でしたのでいちいちが珍しかったのか、写真の横には几帳面に母のコメントが書き込まれています。当時24歳だった母の筆跡は今の私から見ても大人びていて、不思議なことにどうしても自分よりもずっと年下の女性が書いたものだという実感がわきません。
生後22日に撮影された写真の横には、こんなメモ書きがありました。“オルゴールを聞かせたところ、目を見開いてびっくり”“音に敏感で、小さな音にもすぐ反応を示す”。
音、音楽と濃密に向き合う人生は、すでに生後22日から始まっていたようです。その後、母が時折弾いてくれるピアノの音に強く興味を惹かれ、つたえ歩きできるようになると自らピアノに向かっていって鍵盤を押し、音を鳴らすことを覚え、さらに、椅子に座れるようになると“即興演奏”をするようになりました。その時の、イメージをもって音を出し、それを聴きつつ“メリハリ”を工夫して曲を構成していく素晴らしい感覚は、今でもはっきりと覚えています。“作品”を弾き終えると必ず母のところへ行って「どうだった?」と、感想を求めました。母は「上手よ」と必ず褒めてくれました。
時折、その“即興演奏”が、神がかったようにうまくいく時があるのです。新しい響き、思いがけない展開、想定を上回る表現…「これは!」という出来栄えになる時が。その演奏後、興奮を抑えつつ母に「どうだった?」と尋ねるも、母がいつものように「上手よ」と答えるのに軽い落胆を覚えたものでした。「どう考えても、ただの“上手”じゃない出来栄えだったのに。特に素晴らしかったはずなのに」…今思うと、どんな時にも「上手よ」と答えてもらえるだけでも恩の字なのに、なんて欲深い子供だったのでしょう。
生活の中の音楽体験は、ピアノだけではありませんでした。日曜日には必ず父がクラシックのレコードをかけてくれましたし(その時のビクター社の真空管のスピーカーの音は、今でも私の中の“いい音”の基準になっています)、母はいつも鼻歌を歌っていました(これは今も変わりません)。歌といえば、お風呂で顔を拭いてもらう時も、「おでこを拭いて、お鼻を拭いて…」という母自作の歌を歌ってもらいながらでしたし、母と一緒にダンスを踊って遊ぶ時も、いつも母の歌を聞いていました。
気に入った歌には反応を示し、母に「もう一回!」と、何度もアンコールをおねだりしたそうです。あまりにもそれが執拗なので歌い疲れてしまった母が「今度は美奈子ちゃんが歌って」というと、私はそのままを“空で”歌ってみせたとか。そんなこんなで、この子はよほど音楽が好きなのだと感じた母は、私を普通の幼稚園ではなく、ある音楽学校の幼稚科に入れてくれました。そこではピアノかヴァイオリンの個人レッスンが必須科目に入っていて、私は初めて正式にピアノを“習う”ことになりました。
個人レッスンはときめきと興奮に満ちたとても楽しい時間でした。先生の前で弾く曲すべてに、「うん、上手だ」「よし!」というお褒めの言葉と合格をもらえました。クラスで出欠を取る時も、ミュージカル仕立て。先生がピアノを弾きながら「美奈子ちゃん、美奈子ちゃん、どこですか〜?」と歌で呼びかけるので、手を高く挙げて星が輝くように、かつ、音楽のリズムに合わせて手首を回転させながら「ここです、ここです、ここにいます〜」と、やはり歌で答えるのです。
ソルフェージュの時間もありました。和音を聴き取って答えたり、リズム遊びをしたり、歌ったり。音楽に合わせて体を動かすリトミックのレッスンもありました。
こうして振り返ると、家でも幼稚科のクラスでも、私がいる場所にはいつも音楽があったような気がします。私にとって、歌うこともピアノを弾くことも、無条件に楽しい遊びであり大きな喜びでした。このように、音楽が当たり前のように身近にあった私がある小さなきっかけからピアニストを夢見るようになったのは、自然な流れだったように思います。
ピアニストのひとり言 第819回
夢を実現させる、というと、壮大で奇跡的な理想の実現をイメージされるかもしれませんが、夢にも様々なスケールがあります。
例えば、「その曲が弾けるようになるのが、夢なんです」といったお声をよく聞きます。弾けるようになるまで、現在のレベルや状態からどの程度の努力を重ねる必要があるのか、また、“弾ける”といってもどの程度のレベルまで弾けるようになりたいのか…などによって、その夢を叶えるために超えなくてはならないハードルの高さは変わってきます。
そうした現実的なこととはまた種類が違う、漠然とした夢というのもあります。そもそも“夢”なんだから、漠然としたものであってもいいのですが、それをどのくらい本気で求めているかによって、実現できるかどうかの可能性は変わってきます。
高校生の時の私は、大きな二つの夢を抱いていました。一つは、5歳から変わらなかった“ピアニストになる”という夢。もう一つは“素敵なアカデミーのようなものをつくる”という夢でした。
今思うと、日曜日には父がクラシックのレコードをかけてくれたり、家にピアノがあってものごころつく前から母がピアノを弾いて聴かせてくれていた幼少期の音楽的な環境は、決して恵まれていないものではありませんでした。でも、転勤族だったためになんども転校を経験し、その度にピアノの先生も変わって何かと悩み続けてきましたし、高校生になった頃には、自分がじっくりと音楽の勉強の本質に触れる教育を受けられずにきたことを、いやというほど理解していました。きちんとした勉強ができる“良い先生”につくために、とても高いお月謝を用意しないといけないことも。
「本物に触れたい」「本物の音楽を学びたい」と願う学習者や音楽愛好家が、その夢を叶えられるような指導者になりたい。しかも、“普通の”お月謝で!さらに、ピアノの技術的なことや音楽だけではなく、歴史や民族学、宗教や文学との絡み、美術や建築、舞踏との関わりなど、音楽芸術を理解するために必要な他の分野や文化についても、幅広く学べるようなアカデミーをつくれたら、どんなに素敵だろう…高校生の私は、そんなことを夢みていました。
それは、夢というよりも“夢のまた夢”というくらいスケールの大きなこと、手の届かないことと思っていました。でも、ふと思ったのです。立派なものでなければ、叶えられるかもしれない。例えば、自分はもっともっと勉強して経験を重ねていくとして、場所は自宅の一部をそのスペースにすべく改築するとしたら?
そうなると、周囲の親しい方に相談するのが私の常です。皆さんから参考になるご意見を頂けるだけでなく、思いがけないヒントやチャンスを頂くこともあるからです。「とてもいいですね、ぜひ実現させてください」というお励ましに加えて、「お力になれることがあったら、言ってください。なんでもやりますよ!」というお声もいただき、俄然勇気とやる気が出てきました。
その一方で、いろいろな方とお話ししたり、あれこれ構想を練っているうち、“アカデミー”というのはちょっと違うな、と思い始めました。むしろ、アカデミック(学問的、学術的)というイメージとは逆の、先生が一方的に“与える”だけではなく、みんなで自由なイマジネーションに遊びながら思いがけない“繋がり”を発見したり、それを仲間とシェアしあったりする、創作空間にしたいのです。アカデミーでも塾でも研究所でもない、もっと、子供が遊びに熱中している時のように、真剣に夢中になれる楽しいところ。何と呼んだらいいだろう…。
“アトリエ”という言葉を思いついた時は、心の中でガッツポーズをとりました。アトリエ…芸術工房、まさにそれです!今日、早速業者の方に自宅に来ていただいて、防音レッスン室拡張プランの打ち合わせを行いました。年内の完成に向け、夢のアトリエへの一歩一歩を、楽しみながら重ねていきたいと思っています。
ピアニストのひとり言 第818回
「幸せとは、あなたの考えと言葉とおこないが、調和していることです」ごく最近、ある本の中でガンジーのこの言葉に出会い、ハッとしました。幸せをテーマにした名言、格言は世の中に溢れていますが、それに“調和”を結びつけたガンジーの言葉はとても心に響きました。最近、この言葉について考えることが増えているからかもしれません。
先日、あるファゴット奏者の方とのレコーディングのお仕事がありました。その方にとってもわたしにとっても、思い出のたくさんつまったコンサートホールを貸し切って、二人ともが音楽家としてのキャリアのスタートを切った仙台の地でレコーディングを行うということ自体意味深いことだと感じ、喜んでお引き受けしました。
オーケストラの中では必ずしも常に光が当たるとは限らないファゴットという楽器のために書かれたオリジナルのソナタをはじめとする、バロックから近現代までの作品の数々…。東京で幾度も濃密なリハーサルを重ね、当日に臨みました。
ホールでの録音というと、ステージの頭上に天井から吊るされた“吊りマイク”で録るイメージがありますが、それだとよく言えばホールの響きに近い臨場感が録れるものの、悪くすると空気の雑音やホールの余計な残響まで拾ってしまい、その場で聴くなら問題ないはずのそれらのものが、再生された時にはぶよっとした音の贅肉のようなものが感じられてしまい、聴きづらい印象になってしまうのです。
ホールの響きのなかで、二つの楽器のそれぞれの繊細な表情が、余計な雑音なしにクリアに、しかも心地よい音で録れるよう、使用するマイクの吟味、選別はもちろん、高さ、角度、録音レベル…あらゆる要素がベストな調和をなすよう、セッティングします。さらにステージ上には、音が散りすぎるのを調整するための“ついたて”も立てられました。
それだけではありません。時系列によって空気の雑音や残響(湿度によっても変わるのです)が変わってしまわぬよう、また、楽器のピッチが変わってしまわないよう、ホール内は終始同じ温度と湿度を保ちます。一曲録り終えるたびに調律師さんに調律していただき、その間にディレクター兼エンジニアの方にプレイバックを聴かせてもらって、良いテイクを決めたり、編集していただいたり…。ほんの少しでもファゴット特有の雑音が入っているとそのテイクはNGになるので、録音中にNGになって途中でストップ、というケースも珍しくはありませんでした。
と、ご紹介すると、読んでいる方はとてもピリピリとした緊張感あふれる現場を想像されるかもしれませんが、その時感じていたのはそれとは違った、不思議なことに“楽しい”気持ちでした。私はどのテイクを採用されてもいいよう、兎にも角にも一回一回心を込めて全力で弾くしかない、と腹を決めて集中するのみでしたし、録音スタッフの方々も、いいものになるように、との一心で、朝から夜遅くまで一切の食事もとらず集中していらっしゃいました。そこには、お互いの信頼が感じられました。
さらに、思い入れのある仙台という土地、ホール、二人の奏者の演奏と録音、調律の技術、チームみんなの思い…それらがひとつに調和しているのが感じられ、なんとも言い難い幸せな雰囲気の中にいたのです。もちろん、緊張はしていたのですが、その幸せは終始、緊張をはるかに上回り、「終わらないでほしい」という気持ちがよぎったほどでした。
全てが終わって楽譜をお返しする時には、まるで、夏休みになかなか会えない従兄弟たちと思いっきり遊んだ後、いよいよお別れする時がきたような寂しさを感じたのですが、後日ファゴットの方も「機材を全て撤収してガランとなったホールを最後に出る時、“ああ、終わったんだ”と、寂しくなってしまった」とおっしゃっていました。やはり同じ気持ちだったのだ、と、嬉しくなりました。
このアルバム製作に関わった私たちの思いが、それをお聴きくださる方に伝わるならば、“調和”の輪はさらに皆さんへと広がります。調和の輪は、幸せの輪。あたたかな輪が広がることを、願ってやみません。
ピアニストのひとり言 第817回
第一楽章 “どこまでも情熱的に、そして幻想的に”
9月のコンサートに向け、大好きなシューマンの『幻想曲』をお稽古しています。第一楽章の終わりにはベートーヴェンの歌曲『遥かなる恋人へ』のメロディーがそっとでてくるこの作品は、まるで“聴く”ラブストーリー です。
書かれた当初は、それぞれに副題もつけられていましたが、出版される際にそれがはずされ、代わりにシューマンによってシュレーゲルの詩が掲げられました。
鳴り響くあらゆる音をつらぬいて
“ひめやかな調べ”…piano(=弱音)という名前の楽器を愛する者にとって、これほど心惹かれる言葉はありません。
では、ピアノの究極の音は…?わたしにとってのそれは、パイプオルガンではなく、オーケストラでもなく、人の声です。時にソロだったり、複数のハーモニーだったり、男声だったり女性だったり、子供たちだったり。
表情豊かに変化する人の声色のように、ピアノからさまざまな音色を紡ぎだしたい。…シューマンの『幻想曲』は、わたしにとってそんな気持ちが駆り立てられるような作品です。
『星の冠』という副題をもつ第三楽章には“つねに静けさをもって”と記され、30分の演奏時間を要するこの大作は、満ち足りた穏やかな心の平和のなかに静かに幕を閉じます。まるで、クララとの結婚がようやく許されたシューマンの心模様のように…(初稿当初はまだ彼女との結婚が認められず、違うエンディングが用意されていました)。
幻想曲の第三楽章には、故・林秀光先生による“p(弱音で)”という書き込みがそこここに…先生からのメッセージを今さらながら大切に復唱しています。
それにしても、こんなにもクララへの思いが溢れた作品だというのに、あっさりとリストに献呈してしまうあたり、シューマンの性格の一部が垣間見えるような気がして面白いところです。同じようにクララを思って書きながら最終的にはショパンに捧げられたクライスレリアーナといい、シューマンはクララに作品を贈ることよりも、クララという女性の存在からインスピレーションを得、それを作品に仕上げたところで彼女と全てが通じあうことが大事なのであって、誰に捧げるかなど、拘る必要はなかったのかもしれません。
シューマンのピアノ曲の中でも最高傑作との呼び声高い『幻想曲』…その素晴らしさを少しでもお伝えできるよう、コンサートまでじっくり楽譜と…そして、シューマンと…対話を重ねていきたいと思っています。
ピアニストのひとり言 第816回
このところ、リハーサルで母校桐朋学園大学を訪れる機会が重なっています。メインキャンパスのある仙川から数駅離れた調布の寮は取り壊され、代わりに立派な新キャンパスが建って、当時とはすっかり面影が変わっています。
それでも、駅から寮までの道すがらに、よくお世話になったパン屋さんや、友人と語らった喫茶店を確認できるとすっかり嬉しくなり、天神さまの境内などを眺めながらそぞろ歩くと、二十歳前後の自分と再会しているような不思議な気持ちになります。
仙台から上京した私にとって、楽器が思い切り弾ける寮という環境は本当にありがたいものでした。夜10時までは練習ができるので、いくら親しい友人でもよほどの急用でもない限り、その時間前には部屋にお邪魔したりはしないのが暗黙のルールになっていました。朝、夜と食事も付いていましたし、大きな浴場があって毎日のお風呂がとにかく楽しみでした。お風呂から上がったところには談話室と呼ばれるスペースが。そこには銭湯よろしくパックに入ったコーヒー牛乳やフルーツ牛乳なんぞが買える自動販売機や新聞が読めるソファーが置いてあって、お風呂上がりに各紙を読み比べするのも大好きな時間でした。長い時間を一緒に過ごし、あらゆることを語り合える腹心の友人もできて、寂しい思いをすることもありませんでした。
携帯電話などない時代でしたから、外部からの電話があると近くにいる誰かがそれを取り次ぎ、マイクで「◯◯◯号室の鈴木さん、お電話です」というアナウンスをします。呼び出しされた人は部屋にある応答スイッチを押して、一目散にその場所めがけて走ることになります。私は四階の住人でしたので、電話が入ると相手の方をなるべくお待たせしないよう、疾風のように階段を駆け下りたものでした。
食事をとる母屋?と居住棟との間の渡り廊下には、届けられた荷物を置くことになっているスペースがあり、外出先から帰って部屋に向かう時に何気なしにそこをチェックする癖がつきました。滅多に荷物が届くことはないし、あっても事前に知らせが入るので見落とすことはほとんどないのですが、ちらりと見ては「うん、やっぱり何も来てない」と、安心するような、がっかりするような気持ちになったものです。
寮はかつての場所から少し離れたところに再建されたそうですが、そこへはまだ訪れていません。近所の天神さまは変わらぬ佇まいでしたが、よく見ると木々は一回り大きく高くなっているようでした。御手洗をみたらお水が止まっていたのですが、近づいたら「カチッ」という微かなスイッチ音とともに水が流れ出して驚きました。人感センサーが取り付けられていたのでした。
キャンパスに入ると、あの頃のように感じのいい守衛さんが声をかけてくれました。リハーサルの部屋に行く途中、すれ違った学生さんが私を見て会釈するので一瞬戸惑いましたが、「そうか、ここの先生だと思ったのね。まぁ、そう見えてもおかしくはないわね」と、気づきました。無意識に、自分が今も大学生のままのような気持ちになっていたのでした。
楽譜を抱え、頭の中で譜面の音を鳴らしながら緊張してレッスンに向かっていた在学時代の私。カバンの中にはもちろん、スマホもタブレットもありませんでしたし、耳にイヤホンが入っていることもありませんでした(今でも、イヤホンで音楽を聴くのは好きではありません。音というのは空気の振動を経て耳に届くもの。直接耳の中に響くのは生理的にどうも違和感があるのです)。レッスンが終わったら、帰りにこのパン屋さんで大好きなパンを買って、部屋でコーヒーを淹れて食べよう…などと考えては自分を奮い立たせていたのを思い出して、当時の自分が愛おしく思われてきました。
考えてみたら卒業してから30年が経っているのですから、周りの様子が激しく変わっていても何の不思議もないことです。でも、それでもなお変わっていないものを見つけたくて、無意識にそれを探してしまいます。「歳をとったって、こういうことなのかな」妙な感慨を覚えつつ、リハーサルの帰り、当時とは全く別の駅になってしまった調布駅の構内で視線を泳がせ、目指すホームを探したのでした。
ピアニストのひとり言 第815回
夏休みに入ったのとほぼ同じ時期から約一週間、コンクール審査員のお仕事で福島県内の三箇所を訪れました。
人生で初めてコンクールの審査員という任務を仰せつかったのは、このコンクールでした。今年はそれからはや20年目になります。少子化が進んでいるというのに、コンクール参加者は東日本大震災の時を除いてほとんど減ることもなく、23年間も続いているというのはすごいことです。
その間、レベルも上がってきていると言えます。“きていると言えます”と、はっきり断言する表現を避けたのは、何をもって“レベルが上がった”と判断するか、という基準にもよると思われるからです。確かに、つっかかったり、途中で暗譜がわからなくなってしまったり、勘違いしてしまったような速さで弾いてしまったりする参加者は随分減りましたから、そういう意味ではレベルは上がってきていると言っていいのだと思います。練習の成果を出し切ったのだな、という印象を抱く方も増えています。
でも、その一方でどうも違和感を覚えるのです。以前は、少々崩れがあったとしても弾いている人が感じていることが音から溢れ出てきたり、多少やり過ぎてしまいがちであっても熱い思いのこもった音楽を聞かせてくれるような参加者があったのですが、そういった方が減り、代わりに、破綻なく端正に弾いて整ってはいるのですが、「ピアノが大好き」という気持ちや情熱が今ひとつ伝わってこない演奏が増えているような気がするのです。
あるいは情報が溢れ過ぎて、ピアニストのお手本やコンクール入賞者の演奏が気軽に聴けるようになったことも影響しているのかもしれません。楽譜から一つ一つの音を紡ぎだし、どう弾いたら良いのか悩みながらも機を織るように地道に少しずつ曲を仕上げていくよりも、出来上がった演奏を聴き、耳で雰囲気をつかんで、それに近づける方がずっと手軽です。ただし、その場合、前者のような積み重ねを経て出来上がった演奏とは、味わいの深さが違うものになるのは言うまでもありません。
「私は、書を見るのが好きなんです。上手で立派でなくても、字というものをとおして書いた方の思いや人となりが見えて、いいものだなぁ、と思うんです」今日レッスンに来てくださった大人の生徒さんが、こんなことを話してくださいました。「そうなんです、私も同じです。音楽が好きなので、上手じゃなくてもその人らしさが感じられると嬉しくなるし、音楽のそういうところが好きなんです」コンクールの仕事を終え、ちょうどそんなことを考えていたおりでしたので、我が意を得たり!とばかりに、堰を切ったように一気に話してしまいました。
音楽はそもそも優越をつけるためのものではなく、自分なりのイメージや解釈を演奏で表現し、それを周囲の人と分かちあう中で様々な感性や個性を認め合うためのもの。ある方が「一方的に教える、という部分が少ないほど、レッスンはたくさんの発見に満ちる」とお話しされていましたが、それは弾き手と聴き手の関係にも言えるかもしれません。客席からの“気配”も、案外演奏に反映されるのです。双方がお互いに感じ合い、伝えあえると、演奏はさらに発見に満ちた魅力的なものになる…。音楽はそんな、人間の感性のやりとりによって豊かな実りを結ぶのです。
たとえ上手で立派でなくても、その人らしさが滲み出でくるような演奏がもっと増えたら、どんなに楽しくことでしょう。
“愛、それは甘く/ 愛、それは強く / 愛、それは尊く / 愛、それは気高く/ 愛あればこそ生きる喜び / 愛あればこそ世界は一つ”…あの大人気漫画『ベルサイユのばら』の宝塚歌劇団の劇中で、ヒロインのオスカルと恋人アンドレの二人によって歌われるヒット曲“愛あればこそ”の歌詞が、ふと頭に浮かびました。「愛」のところに「音楽」を当てはめることもできると思います。
今、そんな“音楽愛”を叫びたい気持ちです。
ピアニストのひとり言 第814回
先月公開レッスンのお仕事で会津若松に伺った折に、東北最古の400年の歴史ある会津本郷焼の老舗 “酔月窯”にお邪魔して、ずっと探していた日常使い用のそば猪口を購入することができました。古来から縁起が良いとされている麦の穂と、珍しい蕎麦の花の2つの柄を選びました。素朴な地色と土の風合いによく合っていて、一目惚れでした。もちろんひとつひとつが手作り、手描き。大きさもタッチも微妙に違います。
古典落語のファンでもありますが、江戸時代のそば猪口を見るのも大好きです。この、小鉢にもぐい呑にも使える小さな道具には、古典文学によるモティーフや、粋なユーモアがセンス良く描かれていたりして、そこに込められたストーリーを知るとますます心惹かれるのです。
先日、そば猪口収集家として知られる岸間健貪さんのコラムを拝読しました。記事の中に、岸間さん所有の18世紀の伊万里焼のそば猪口がいくつか写真で紹介されていました。一つは、垣根と撫子が描かれたもの。潔い十字に描かれた垣根のあしらい方がとてもモダンなのですが、それだけでなく、源氏物語第九帖『葵』の中で、夕霧を産んで間もなく葵の上が亡くなってしまい、その悲しみを光源氏が詠んだ「草枯れのすがきに残る撫子を 別れし秋の形見とぞ見る」を文様にしたものだそうです。この他にも、そば猪口には源氏物語を題材に求めたものが多く見られるのだと知り、驚きました。
また、当時人気だったという“八橋に杜若の図”が描かれた18世紀中頃のそば猪口は、伊勢物語の『東下り』の中で詠まれている“からころも きつつなれにしつましあれば はるばるきぬる旅をぞ思ふ”の世界を描いたものだとか。こちらも様々な絵柄で数多く描かれているモティーフとのことで、当時の在原業平の人気のほどがうかがえます。
岸間さん曰く「江戸時代の庶民は過去のものへも造詣が深く、古典文学や故事来歴などをよく承知していました」その浸透ぶりたるや、源氏物語や百人一首などのパロディーが大流行するほどだったそうです。庶民の文盲率も、他の先進国と比べ圧倒的に低かったと聞いています。
落語や歌舞伎や川柳を愛し、育くんだ江戸時代の庶民。貴族や武士、僧侶によって独占されるのではなく、庶民が芸術・文化を愛で、育てあげたというのは、彼らが抜きんでて文化的意識、美意識の持ち主だったからかもしれませんし、長らく続いた平和な時代の産物なのかもしれません。あるいは、苦境逆境を笑いや愉しみに変えて乗り越えてしまう、したたかでたくましい“粋”…“生き”るチカラを、彼らが持ち合わせていたのかも…。
芸術だけでなく、食文化然り。それらは勉強して“理解する”ためのものではなく、ただ五感で“愉しむ”“味わう”ものだと、この頃とみに思います。
さて、新しいそば猪口で蕎麦やひやむぎを頂くのを楽しみにしていたら、某有名ヴァイオリニストの友人が、自分でお蕎麦を打って家族に振る舞ったというトピックをSNSに投稿していました。忙しいし、この猛暑の中さすが!…と思ったら、「十割蕎麦が15分で完成!このマシン本当に優秀」とのコメントが。え、マシン?
そこで初めて、最近は“そば打ち機”なるマシンがあることを知りました。従来のそば打ちとは異なる画期的な方法で、かなりお手軽にこだわりのお蕎麦ができるとのことです。それを使うと一番大変な“水回し”という手順もとてもラクにでき、“切る”作業の代わりにところてんのような器具からそばを直接お湯の中に押し出すので、空気との接触も少なく香り豊かに茹で上げることができるのだとか。好きなそば粉をあれこれ試せるのも楽しそう…と、気になって仕方ありません。
あら?江戸文化の話題だったはずが、いつの間にかそば打ち機のことに…。これは失礼!そば打ち機のお話は“切り”がないので、ここらへんで「打ち切り」といたしましょうか。お後がよろしいようで。
ピアニストのひとり言 第813回
数年、数十年ぶりに会ったのに一瞬にして会えなかった年月を乗り越え、お互いに心からの笑顔が溢れる。屈託なく微笑みあうだけで、素敵なプレゼントをもらったような、満ち足りた気持ちになる…。
生きていることに思わず感謝したくなるような、そんな再会を経験する機会が増えたのは、間違いなくある程度以上の年齢になってからのことです。
自分は特別友人が多い方だとは思いませんし、たくさんの友達が欲しいと願ってもいません。それよりも、心から分かり合える存在が一人でも二人でもあるなら、それで心が満たされる方です。
若い頃はそんな自分のことをよくわかっていなかったのか、あるいは友達は多いほど人徳があると思っていたのか、努めてアンテナを外に向け、みんなが着ているような服を着ようとしたり、流行のメイクをしようとしたりしていました。みんなの話題についていけないと疎外感や焦りを覚え、特別みたくもないドラマをみたりもしました。
考えてみたら、当時からトレンドにはあまり興味がなく、テレビにもドラマにもほとんど執着がありませんでした。当然アイドルにも疎く、高校時代に大人気だった“たのきんトリオ”も、何のことだかさっぱりわかりませんでした。“金八先生”などのドラマも一度もリアルタイムでみたことはありませんでしたし、特別みたいとも思ったことはありません。今も、周囲に呆れられるほど、芸能人の名前はほとんど知りません。そんな私が周囲と話を合わせようとするのは、案外たくさんの無理を重ねることでもありました。
それが、ある時から徐々に、無理して自分を取り繕ったり、人に合わせようとすることをしなくなっていきました。大きなきっかけがあったという記憶はないのですが、きっと様々な経験や影響の積み重ねが、少しずつそのように至らしめたのだと思います。
そうなると、俄然人とのおしゃべりが楽しくなりました。知らないことを知ったかぶりせず、興味のないことを興味のあるふりもせず、“みんなに嫌われないように”という強迫観念のようなものも持たず“素”の自分でいられるようになったら、逆にその前よりも人付き合いが増えました。ありのままの自分に興味を持ってくださったり、好ましく思ってくださる方とのご縁が繋がり、人間関係のストレスも減りました。
最初にお話ししたような再会が増えたのも、そのころからです。“何かを得ようと思ったら、何かを手放すべし”とはよく言われることですが、まさに、“嫌われないように”という考えを捨てたら、自分も相手も、お互いを心底大切だと思える友人に恵まれるようになりましたし、学生時代からの友人ともさらに深い関わりを育めるようになりました。
実のところ、みんなが自分に何を求めているかを探るより、自分が自分に本当は何を求めているのかを問い、見出だすことの方が、ずっと心踊る、意味深いことです。何より、その方が結果として周囲の方を笑顔にできるように思います。演奏、パフォーマンスも然り。どう弾いたら人に受け入れられるかを考えるよりも、まず、自分はそれをどう感じるのか、何をどう伝えたいのか、という問いかけとその答えを明確にすることが大切なのではないでしょうか。それは同時に、人生の主人公である“自分”という素材を、世の中に大切に生かすことにもつながります。
そうやって、“私は”が主語の人生に全力で向き合い、正直に表現しようとすると、それに心から共感してくれる人が近づいてくる。やがて、主語が“私は”から“私たちは”になり、その先に豊かな人間関係がさらに広がっていく。水面に広がる水紋のように、静かに、確実に…。そうした人と人との温かな響きあいは、人生の掛け替えのない支えになるのではないかと思うのです。
心満たされる友人とのひと時にそんなことを実感すると、“私は”を経て、これからもさらに“私たちは”のメッセンジャーへと成長していきたい、という希望が湧いてきます。周囲で支えてくれている友人たちには、感謝の気持ちがたえません。
ピアニストのひとり言 第812回
自分が完璧じゃないのに機械にそれを求めるのはおかしい、と思っているので、少々不具合があっても気にせずそのまま使っていることが多いのです。例えば、この季節になるとクローゼットからレッスン室に出勤する、ずいぶん前に格安で求めた扇風機は、数年前から“首振り”に設定しても滅多に首を振りません。でも、いつも「いいえ」と言い続けるのは確かに辛いことでしょうから、振りたいときだけ振ってくれればいいからね、と言い聞かせています
それが先日、生徒さんがレッスンに来た時にたまたまタイミングよく首を振っていたので、つい「あれ?今日は首振ってる」と言ってしまいました。怪訝そうな顔をされたので、「いつもは“首振り”に設定しても振らないの。今日は機嫌がいいみたい」と説明すると俄然興味を持ってくれて、次にレッスンに来た時に「扇風機、今日は首振るかな?」なんて、気にかけてくれたりします。
“モノも、場合によっては気まぐれで不完全な方が愛着を抱きやすい”という一面を再認識しました。一見扱いにくそうなマニュアル操作の車やカメラの方が、マニアには魅力的に感じられたりするのとも、どこか通ずることかもしれません。モノに限ったことではありません。贔屓の野球チームや好きなアーティストなども、どこか目が離せないような、頼りないところがある方が余計に気がかり…という人情が働くのは、よく理解できます。
規格に従うように育てられた、形の揃ったまっすぐなキュウリよりも、長さも太さもバラバラで思い思いにカーヴしているキュウリの方が、愛しさを感じます。一方、造花のようにいつまでも枯れない植物や、思いのままに修正された写真にはどこか生気が感じられないのは、不安定さ、儚さがないからかもしれません。命も、永遠ではないからこそ、尊いものなのです。
それが心から実感できるようになると、身の回りの様々なものへの愛着が増すように感じます。一番身近なところでは、自分自身。経年変化で白髪やシワが増えるのは、自然に逆らわずに生きている証拠です。それを、“衰え”ではなく“進化”“熟成”と思えるような歳の重ね方ができているかどうか、ということだと思うのです。
「年月を経て味わいを増すのが、本物の美というもの」誰かがどこかにそんなことを書いていましたっけ。新しいから、若いから、きれいなのは当たり前。そうではない、本当の“美”を感じることが、心に感動をもたらすのである、というお話でした。
100年、200年も前に大作曲家たちによって書かれた作品の数々。その美しさは、時間を経て色あせるどころか、輝きを増しているように感じることさえあります。理解しようとするのではなく、何かを感じようとして聴いてくださったら、どんな方もその素晴らしさを享受することができるのではないかと思うのです。
ところで、最近面白い本を読み始めました。サルトルの研究者、フランソワ・ヌーデルマンの著書『ピアノを弾く哲学者』((橘明美訳/太田出版)。あの、泣く子も黙る?実存主義者サルトルが、音楽…特にショパンのメランコリーに身を置くことを好み、プロの音楽家になることを夢見ていたニーチェは生涯ピアノでショパンやシューマンを弾き続けていたそうです。時代の“現象”を完璧に分析せんとする彼らは、情緒と情熱溢れるロマン派の音楽を心の大きな支えにしていた、というのは、意外でした。
“あなたは私の魂、私の心、あなたは私のこの上ない喜び、私の苦しみ”…シューマンの歌曲“献呈”の冒頭部分の歌詞です。“あなた”のところに、“音楽”を当てはめると、私の気持ちになります。完全、完璧だから美しいとは限らない。人の心に豊かさや感動をもたらす、本当の“美”を、これからも喜びを持って求め続けていくことでしょう。
ピアニストのひとり言 第811回
仙台在住の、高校時代からの友人Mちゃんが会いに来てくれました。他の用事の“ついで”ではなく、私と会って話すために、上京してくれたのです。
そうでもしないとなかなか会えないから、ということではありません。彼女とは毎年故郷仙台で会っては親交を温めたり、お互いに刺激を受け会ったりしていますし、実は来月帰省する折にも会う約束をしています。でも、「その前に、話し合っておきたいことがある」と言って、忙しいなかを新幹線で飛んできてくれたのです。5分早く待ち合わせの銀座のレストランに着いた時には、彼女はすでにテーブルについていました。
曰く、「美奈子ちゃんは三年前以来、仙台でのソロリサイタルを行なっていないでしょう?でも、仙台にも美奈子ちゃんのピアノを聴きたい人はたくさんいるし、リサイタルを実現させることができるよう、同期生たちで協力させてもらいたいの。具体的には、東京で予定されているシューベルトのリサイタルと同じプログラムを仙台でもやってもらいたいと思っているのだけど、それについての美奈子ちゃんの率直な気持ちを聞かせてもらえる?」Mちゃんからの提案の全てを公表することはまだできないのですが、そのうちの一つはこんな内容でした。
コンサートなどのイベントのマネージメントは、出演者とはまた違うこまごまとした配慮や作業が必要な、とても労力がいることです。なにしろ、そうした業務を行う専門の業者があるくらいなのですから。彼女は現在、大学で教鞭をとっていますし、他の同期生も皆教育現場や市政などに携わり、若い人たちの教育やこれからのより良い社会のために多忙を極めている人たちばかり。なのに、そんな彼女たちが私のリサイタル実現のために力になりたい、と申し出てくれたのです。感激と嬉しさで、目の前のご馳走にナイフを入れるのも忘れてしまいました。
音楽は、単なる“娯楽”ではありません。それは人を鼓舞し、民族や国家を超えた普遍的な人と人との結びつきを再認識させ、希望と感動という、人間にとって本来一番(個人的な意見ですが、健康診断の数値よりも!)大切な栄養を与える、“心の健康”を支えるもの、と信じています。
一般的にはそういう理解を得られないことが多いのですが、それでも諦めずに啓蒙活動をし続けるのが芸術家の仕事。教育も、芸術も、目指すのは同じ。人を育て、人の感性を育てること以上に大切なことはない。…彼女とじっくり会話を重ね、そういった価値観の一致を確認することができました。そして、これからの社会や、社会を担う若い人のためになるようなことをやっていこう、と語り合いました。
採算が合うかを考え出すと、コンサートというのは役に立たないものになってしまいかねません。でも、いつの時代も、本当に素晴らしい芸術は、特定の階級…貴族であったり、富裕層であったり…によってサポートされながら、経済性を鑑みることは二の次にして生み出されてきました。もし、たくさんのお客様からのお運びが得られず、赤字になってしまったとしても、仕方ない。それよりも、事業を黒字にすることと、いいステージを作り上げることのどちらが大事なのかを見失うことだけはしたくない、と思いながら、これまで自主公演を続けてきました。一回一回“一期一会”の気持ちで、その時できうる精一杯の演奏を重ねていくことを目標に。
そんな青くさい思考からなかなか離れられない私が、これまで30年間もステージ活動を続けてこられたのは、周囲の方々に恵まれたからとしか言いようがありません。
「やっぱり美奈子ちゃんに会いにいって良かった。少しずつでもやりたいことを実現していけるよう、一緒に歩んでいきましょう!」別れて数時間後、仙台に帰った直後のMちゃんから送られてきたメールには、こう書かれていました。会うたびに元気をもらえ、一番やりたいことを全力で支えてくれようとする彼女のような友人がいることは、私の財産です。これからも、感謝の気持ちを込めてピアノに向かう日々を大切に重ねていけたらと願っています。
ピアニストのひとり言 第810回
先日、公開レッスンのお仕事のため会津若松に行ってまいりました。ありがたいことに今回は希望者が多く、二日間にわたってレッスンすることになりました。思い返せば、初めて公開レッスンのオファーを頂いたのも、会津若松でした。もう20年も前のことです。あれから自分は、指導者として少しは前に進んでいるのだろうか。いや。“進んでいる”かどうかより、“進もう”とし続けている。ことに意味があるのだと自分に言い聞かせ、少々緊張して現地入りしました。
郡山から磐越西線に乗り換え、凛とした姿で堂々と佇む磐梯山がだんだん近づいてくるにつれて、恋人にあう瞬間が近づいてくるようなときめきを感じます。美しい山並みに囲まれ、飯盛山や鶴ヶ城など、歴史が今もそこここに息づく会津若松市。時折見かける漆喰の酒蔵にもなんとも言えない風格が漂っていて、つい見惚れてしまいます。
今回レッスンを受講する生徒さんは小学校低学年から高校生まで、12名。元気のいい小学2年生の男の子とは、レッスンの中で“メヌエット”がどのような踊りなのか、それに今の演奏がふさわしかったか、などをセッションしました。「う〜ん、今のは“国王”が踊っている感じじゃなかったなぁ」「じゃ、国王ならどうなるの?」「ええっと…よし、思いついた!こんな感じだよ」彼はそう言って、いかにも勢いとノリで弾き始めそうな雰囲気でしたが、実際にはとても丁寧に、厳かなタッチで弾き始めたのです。「うん!国王って感じ、したした!」「じゃあさ、恐竜が踊ったら、こんな感じかな?」
そういい終えないうちに、満面の笑みを浮かべて再び小さな手を鍵盤に乗せ、呼吸を整え始めます。なんて可愛らしいのでしょう!気持ちが溢れすぎてコントロールが乱れるところをそっと指摘すると、素直に感じ取ってくれました。明るく、積極的でありながら人に対する配慮もできる、繊細な心の持ち主なのが伺えました。
ショパンのポロネーズを弾いてくれた高校2年生のAちゃんは、音を出す前から演劇の舞台のような、ドラマティックな世界を創り上げていました。豊かに音楽を感じて、それを自分の表現に結びつけようするとひたむきな気持ちが伝わってきます。音楽が大好きなのです。「とても素敵ね。お芝居を見ているようだったわ。でも、台本をよく読み直してみると、もっとたくさんのヒントが得られるかもしれない。たとえば、この中間部の和音の連続するところ。普通のテンポではわかりにくいけど、ゆ〜っくり弾いてみると…」リズムとテンポを変えて演奏する私、真剣な表情でじいっと聴き入るAちゃん。「ね。まるでお祈りのコラールのようでしょう?ここでは、もっとそんな響きを味わって弾いてみない?」彼女とは、曲のストーリーを読み込みながら、構成を考えて表現するためのワークをしました。
子供たちが素晴らしいのは、ひとたび私の演奏に対して「そういうふうに弾いてみたい!」「そんな感じ、いいな」と思うと、次の瞬間にはもう弾けてしまうところ。頭で方法論を見つけようとしないぶん、感性でできてしまうのです。でも、実は子供だけでなく、人間には本来、そんな能力が備わっているのかもしれません。「どうやったらできるの?」「そんなこと、できるかしら…」という“邪念”さえ、入り込まなければ。
公開レッスン終了後の質疑応答の時間になりました。「先生方、聴講生、受講生の皆さん。ご質問があればどうぞ」と呼びかけると、Aちゃんがサッと手をあげました。「さっき先生が“コラールのように”とおっしゃったところを、もう一度弾いていただけますか?」感動さえ覚えました。大人はノウハウについての質問をしがちですが、何はさておき、よく聴いて“感じ”、“盗む”のが一番肝要なのです。もう一度弾いてください、というのは最高の“質問”かもしれません。
つくづく「音楽はコミュニケーションだなあ」と思います。その人の性格も、考えていること感じていることも全て音に現れるのですから、こんなに楽しいコミュニケーションツールはありません。伝えあうこと、共感することは、社会にとってもとても大切な、意味深いことなのではないでしょうか。そこには、言葉を学ぶことよりもずっと豊かな何かがあると思うのです。
レッスンを受講した生徒さんが、他の誰でもない“自分自身の”感性によって、人と伸びやかにコミュニケートする楽しさ、尊さを感じてくれるよう、祈る気持ちで過ごした二日間でした。
ピアニストのひとり言 第809回
生徒さんの発表会当日は、私が一年の中で最も感激する一日かもしれません。
それは、楽譜と…そして音と向き合い、作品を読み込んでふさわしいタッチや表情を見出し、それをいかにして伝えていくのか、あれこれ一緒にワークを重ねてきた集大成の舞台。どんなレベル、年齢の生徒さんにとっても、その一日を目標に泣いたり笑ったりしながら一つ一つの課題をクリアして、さらに大きく成長するきっかけを得てくれる大切な一日なのです。
今年の発表会を終えて、一週間が経ちました。その後のレッスンで、生徒さんへの「どうだった?」という質問に対して、今回一番多かった答えは「楽しかった」。「緊張したけど、それ以上に楽しく弾くことができました。他の生徒さんの演奏もみんな素敵だった」そう答える皆さんの表情には一つのことをやりきった達成感と自信が感じられ、とても眩しく輝いて見えます。
小学校低学年のRちゃん。二曲お勉強してそのうち一つをステージで弾きましょう、と、準備していたのですが、本番の数週間前に「たくさん練習して、二曲とも弾きたいです」と、胸の内を話してくれました。「もちろん、いいわよ。『弾きたい』という気持ちがあるなら、きっと素敵に弾けるようになるね。頑張ろうね」「はい」
それからのRちゃんの成長には、目を見張るものがありました。ただ弾くだけでも難しい二曲なのに、フレーズを歌い、音楽の流れや呼吸を感じて弾くアプローチを、ぐんぐん吸収していきました。レッスンのたび、彼女が曲の美しさ、愛らしさに心惹かれ、共感しながら弾いているのが伝わってきました。
発表会当日。リハーサルの順番を、控え室で楽譜を一心に見直しながら待っていたRちゃんが、ふと意を決したような表情になって私の方にやってきました。「先生。私、暗譜でも弾けるようにお稽古しました。暗譜で弾きたいです」Rちゃんは、レッスンでは一度も暗譜で弾いたことはありませんでした。なにせ、ギリギリまで二曲ともをステージにあげられるかわからなかったのです。でも、ここのところのRちゃんの成長を考えて「大丈夫」と確信しました。「じゃあ、リハーサルも暗譜で弾きたいわね?」「はい」「わかりました。大丈夫だから、落ち着いてね」
果たして、彼女の本番での演奏は、とても感動的なものでした。多くの生徒さんから「Rちゃんの演奏が忘れられません」「Rちゃんの音楽の豊かさ、音の美しさが、胸に響きました」「音楽を感じながら無心で弾いていた姿が、強く印象に残っています」といった感想が寄せられました。私も、皆さんと同じことを感じました。
結論。生徒さんは、すごい。いったん心から「いいな」と感じると、まさに柔らかな土に水が染み込むように、吸収していきます。教師にとって大切なのは、自身の体得したノウハウを伝えることよりも、まずは音楽の素晴らしさを感じてもらえるよう、できる限りの誠実さをもってプレゼンテーションすること。そして、生徒さん一人一人の個性と長所を注意深く見出し、それを伸ばすために必要なことを客観的に判断して、提案したり伝えたりすることであって、決して表現や知識を押し付けてはならないのだ、と改めて思いました。
そういえば、一流の演奏家の方は皆、レッスンで相手をリラックスさせるのが上手でした。レッスンの前に軽く冗談を言って緊張をほぐしてくれたり、親愛を込めて私の目を見ながらゆっくりと話しかけてくれたり。「もっともっと、彼らの良さを引き出せるようになりたい。そのために心がけることは…?」彼らの素晴らしい演奏に感銘を受け、これからの自分のレッスンのあり方について、ひとりひっそり反省会をしたのでした。
明日、明後日は、二日にわたって会津若松で公開レッスンのお仕事です。思えば、私が初めて公開レッスンをさせていただいたのは、会津若松でした。もう20年前のことです。日一日と成長している生徒さんたちに対して、私は指導者としてちゃんと前に進んでいるのかしら…。“進んで”いることよりも“進もう”とし続けていることに意味があると信じ、心を込めて指導をしたいと思っています。
レッスンを受講した生徒さんたちが、さらに音楽の素晴らしさを受け止め、他の誰でもない“自分自身の”感性によって伸びやかに表現する楽しさを感じてくれますように。
ピアニストのひとり言 第808回
大学時代のピアノ科の先輩が、SNSにこんな投稿をしていました。“肉親が亡くなる間際には、「ありがとう」と思わず感謝の気持ちを伝えたくなるものだ。でも、死を前にしてそんな事を言われると、一体どんな気持ちになるのだろう。そう思い昨晩ベッドに横になった時、カミさんに「ありがとうって言ってみて」と言ってみた。すると、間髪いれずに「ありがとう」と言ってきた。意外だった。「何故?」と問われると思ったからだ。でも、何とも言えない幸せな気持ちになれた。(中略)感謝の気持ちって、具体的に何に対して言ってるのかを伝える必要はなく、その心そのものを伝える事に意味がある様に思う。ピアノを弾く時にも、そういう思いで音に心を込めたいもんだ。”
高校時代からの同級生とご結婚された先輩。生活の中のさりげなくも美しい瞬間をおすそ分けしてくださって、とても温かい気持ちになりました。
私たちが日頃、“なんでもない”と思っていることが実はそうではない…ということが、案外たくさんあるように思います。例えば、今日一日が無事に終わること。ご飯が美味しく食べられること。気持ちのよい朝を迎えられること。すべては「ありがとう」と感謝したくなるほどに幸せなことなのに、それをつい“なんでもない”と思ってしまうがために、ありがたさを忘れてしまいがちです。とてももったいないことです。
ロシアの伝説のヴァイオリニスト、ユリアン・シトコヴェツキーを父に、女流ピアニストのヴェーラ・ダヴィドヴィチを母にもつ指揮者でヴァイオリニストのドミトリー・シトコヴェツキーさんが来日されています。幸運なことに、彼とお会いして色々なお話を伺い、さらにリハーサルとコンサートを聴く機会に恵まれました。
ロシアのキラ星のような存在だったヴァイオリニストの父親と4歳の時に死別し、その後素晴らしいキャリアを築きつつ、激動の人生を歩んでいらしたドミトリーさん。お会いした瞬間にすぐ心を開いてくださって、温かさに満ちた表情でご自身の音楽観を時間の許す限り熱心にお話くださったことには、心から感激しました。
お母さまのダヴィドヴィチ女史は、中学から高校にかけて、私がとても憧れていたピアニストです。気品と情熱に満ちた彼女のショパンは他の誰とも違っていて、それでいて聴く人に「これこそがショパンだ!」と思わせてしまう説得力がありました。「いや〜、母は常に、88鍵の鍵盤にだけ興味があった人だからね。室内楽や協奏曲を弾いても、自分の目の前の88鍵がすべて。ましてや、息子のことなんて眼中になかったよ。今も元気だけど」ドミトリーさんの楽しそうなお話ぶりから、お母さまが大好きで、心から尊敬していらっしゃるのが伝わってきます。
コンサートのプログラム後半は、チャイコフスキーの交響曲『悲愴』でした。「チャイコフスキーというとロシアを代表する作曲家というイメージがあるけど、実はムソルグスキー、ボロディンなどの典型的なロシアの音楽家とは違うんだ。彼が強く影響を受けたのは、むしろモーツァルトのような“西洋的でクラシカルな”スタイルだし、イタリアなど外国におにおける作曲活動も重要な要素。それを、よくロシア音楽に対して抱かれる“暗く、怒りを秘めた”ようなイメージだけで表現してしまうのは、正しくないと思う。」
コンサー終演後、バックステージにお邪魔しました。私と目があうとすぐに「やあ、ありがとう!」と、声をかけ、握手をしてくださいました。「とても感動的でした!交響曲の第3楽章ではバレエ音楽のようなエッセンスも感じられて…。まるでドストエフスキーのように深く、心に響きました」そうお伝えすると、「そうだね、チャイコフスキーは感傷的なだけの音楽じゃない。とても深いんだ。第3楽章のスケルツォには確かに、バレエが感じられるね!」お話ししている間も、ずっと握手をしたままです。大演奏家でいらっしゃるのにまったく偉ぶることなく、まるで旧知の仲であるかのように微笑んでくださるドミトリーさんの温かさ、人間的魅力は、そのまま演奏に滲み出ていました。
ドミトリーさんの手にかかると、なんでもないリフレイン(繰り返し)がとても愛おしいものに感じられ、なんでもないような音階もえも言われぬ美しさを湛えて響きます。パウゼ(休符)に息づく沈黙の輝き、自然でおおらかでありながら高度に洗練された繊細さも感じられるフレーズ…一瞬一瞬が特別なメッセージに満ちているようでした。
“なんでもない”日常が、かけがえのない、輝ける美しい瞬間の連続なのだと気づく幸せ。それを音楽でお伝えすることが、私の目標の一つになりました。ドミトリーさんから、一生の宝物とミッションをいただいた思いです。
ピアニストのひとり言 第807回
肩当てを選んだり、コマの角度を調整したり、テールピースなどの部品を変えてみたり…と、弦楽器の人たちにとっては自分の好みに楽器をカスタマイズしてより好みのものするのは当たり前のことです。ところが、ピアノ弾きにはそのような余地はほとんどありません。完成度が高いと言われている楽器の、泣き所です。
もちろん、発音を柔らかくしたり、ペダルの“遊び”をタイトにしたり…という、微調整は可能です。でも、ある部品をすっかり変えるようなことは、オーバーホールでもない限りなかなかできません。楽器のサイズもしかり。長さや、ネックの太さなど一つ一つが微妙に異なる弦楽器と違って、音の好みのみならず、少しでも自分の“体”に合わせて楽器を選ぶことはできません。
オシャレに見える人は、ちゃんと自分に似合うものをわかっている…ということもありますが、それ以上に自分の体にあったものを着ている人だと思うのです。着ているものが着る人の骨格やサイズにあっていれば、“決まって”見える。反対に、いくら好きな色や形であっても、体にあっていないものは変なところにシワが出てしまったり、どこかぎこちなく見えてしまうのではないでしょうか。
先日、初めてマウンテンバイクを買いました。排気ガスを出さずに街も野山も走れるところに魅力を感じたのです。何しろここ八千代は自然が豊か。トレイルというには物足りないかもしれませんが、でこぼこのある道や川べりのサイクリングロードも周りにありますし、内陸に少し進めば印旛沼、海の方に出れば稲毛海岸に出ることもできるという恵まれた環境に住んでいるので、自転車があったら行動範囲も広がって楽しいかもしれない…と、昨年から購入を考えていたのでした。
でも、女性用のモデルは選択肢が少なく、またその中に気に入ったものがなく、さりとて外国製品の男性用バイクに自分の体が合うものかと案じていたのですが、専門ショップに行って相談したら「きちんと調整するので大丈夫ですよ」とのお返事が。思い切って購入を決めました。
選んだのは、27,5プラスのミッドファットのタイヤをはいた、カナダのMTBの老舗ロッキーマウンテン社のハードテイル(前輪だけにサスペンションが付いているモデル)。つや消しの深い赤が基調のフレームはシックでとても美しく、ほとんど“一目惚れ”でした。
発注から数日後、入荷したとの連絡をいただいてお店に伺うと、店長さんがハンドルの長さ、グリップとギアやブレーキの角度や位置など、わたしの身体、手にあわせて丁寧にフィッティングして下さいました。「これでちょっと乗ってみてください。」言われるままおそるおそる試乗してみると、サイズの違和感がまったくなくて、びっくり。それでも、お店の方は「あと少しサドルを上げても良さそうですね」と、私の乗り方、ポジションを瞬時に見極めてさらにぴったりに調整してくださいました。
体にあったものの心地よさ、体に合わせるという贅沢。…かつて母に、体にぴったりと合うよう採寸、仮縫いして洋服を縫ってもらい、当たり前のようにそれを着ていたことが懐かしく思い出されました。そして、嬉しいようなありがたいような気持ちで、胸がいっぱいになりました。
早速、一時間半ほどサイクリングしてみました。ギアやサスペンションのついた本格的なバイクに乗るのは初めてでしたが、久しぶりに乗ってみると路面の起伏やでこぼこを感じながら、風を受けてぐんぐん進む感じが楽しくて、つい遠回りの道を選んでしまいます。とはいえ、慣れていないのでその日は心地よく疲れて、夜型なのに珍しく早い時間に眠ってしまいました。
この自転車が、これから私にどんな体験や、どんな風景との出会いをもたらしてくれるのか、ワクワクしています。
ピアニストのひとり言 第806回
「本当に集中している時って、一般的に理解されているように“深く入り込んでいる”という感じというより、リラックスして心が“開いている”状態なんじゃないかな」そんなことを音楽仲間と話したことがあります。演奏家が目をつぶって演奏している様子を見るといかにも前者のような印象を受けますが、確かに“入り込んで”行くというと狭いところに入って、“開く”よりも閉じていくというイメージになります。瞑想とは、そのような“集中”状態にあることとも言われます。集中と瞑想の極意は同じなのかもしれません。
人間は、自らの表情に感情が影響される動物だと言われます。例えば、辛い時に嘘でも笑ってみると、心と体が騙されて実際に楽しい気分になるというのです。声を出して大笑いし続ける、という瞑想法もあると聞きましたが、瞑想法どころか、うまくすると薬以上の効き目が期待できるのではないでしょうか。
アメリカのいくつかの大学では、瞑想や笑いの研究が活発になっているそうです。例えばメリーランド大学のマイケル・ミラー博士によると、笑うことによって快感をもたらす神経伝達物質エンドルフィンが分泌され、心臓に有益な生物学的反応を引き起こされるそうです。それが活性化することによって血管が拡張、炎症を軽減させたり血小板凝集が阻害されるのだとか。
笑いが精神面を強くして、体に良い影響を与えるというのは想像がつきますが、ある研究によると人が“嬉しくて笑う”“楽しくて笑う”とき、瞑想している時と同じような脳波の動きになっているといいます。ローマ・リンダ大学リー・バーク博士は次のような見識を述べています。「定期的に笑うことで脳をより良い状態に保つ、これはいわば、定期的な運動で体の状態を整えるのと同じこと。笑いが生む効果は抗うつ薬が持つそれと同等であり、それどころか心臓病や体の炎症反応リスクをも減らす効果さえ持ち合わせているのです」
では、“泣く”のは体に悪い影響を与えるのかというと、そうとも言えないと思うのです。ストレス解消のために、わざわざ“泣ける”映画を観にいって思いっきり泣いてスッキリしてくるという人も、知っています。涙には悲しい涙だけでなく嬉し涙や感激、感動の涙もありますから、泣くという行為も、それはそれで笑うことよりも複雑で、人に及ぼす大きな力を持っているような気がするのです。
まだ「人前で泣くのは恥ずかしい」という概念がない小さな子どもは、笑いたい時にケタケタと笑い、泣きたい時に泣きます。彼らは悲しい、痛いなどの他に、“嫌悪”や“拒否”を泣くという感情で伝えようと、します。自分の状態や気持ちを言葉で説明できるようになるとそれらの行為は少なくなりますが、上手にコミュニケーションを取れないとなると、“伝わらない”ストレスに悩むことにもなります。
それは、子どもに限ったことではないかもしれません。私たちは本来、泣いたり笑ったり、といった豊かな感情表現手段を持っているのですから、それを我慢して存分に行わないでいるよりも、泣きたい時に泣いて笑いたいだけ笑った方が、体にとって“自然”で“健康的”なことだと思うのです。「最近、歳のせいか涙腺が緩くなっちゃって…」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、案外それは老化を防止するために有効な、条件反射に近い反応かもしれません。少なくとも、なんらかの感情が涙とともに込み上げてくるのは、心が健全な証拠だと思うのです。
長いこと身内の介護をしている知人が、「何が辛いって、懸命に介護しているのに感謝はおろか、腹を立てられること。怒りをぶつけられることだ」と話していました。確かに怒りの感情は人に負のエネルギーをもたらすものですが、ご自身の体が思うように動かない方は、その苛立ちを誰かに伝えなければそのまま病に負けてしまうような気がするのかもしれません。“怒る”という行為をすることで生きるエネルギーを振り絞り、闘っていらっしゃるのかもしれません。介護している知人に表面では怒りながら、心の底では感謝していらっしゃるような気がするのです。
人間の健康と感情の関連性については、まだ充分に明らかになっているとは言えないかもしれませんが、笑うにせよ、泣くにせよ、感情を豊かに表現することは薬害や副作用の心配のない、健康のための理想的な薬になるかもしれません。とすると、様々なアートに触れて感情を呼び起こし、思いっきり感動することは、健康のために大切な“心の運動”になるのではないでしょうか。
アーティストの端くれとして、一人でも多くの方の健康維持のお手伝いができましたら本望です。
ピアニストのひとり言 第805回
若くしてお亡くなりになってから11年が過ぎようとしている米原万里さんの著書に、『打ちのめされるようなすごい本』というタイトルの、彼女による書評を集めたものがあります。もちろん、ここでいう“打ちのめされる”とは、良い意味で“やられた〜!”という境地のこと。米原さんの考察の深さ、切り込みの鋭さ、読書量の凄まじさと語彙の豊かさに、読み進みほどに私はすっかり“打ちのめされ”てしまったのですが、このところ嬉しいことにそんなことが増えているような気がします。
例えば…チェコから帰国して以来、ボヘミアの作曲家の作品をあれこれ聴いたり、譜面をみたりしているのですが、素晴らしい“知られざる作曲家”による“知られざる作品”の多さに、このところ圧倒されっぱなしなのです。「こんなにすごい作品がこんな時代に生まれていたの?」という驚きから、さらにその彼が影響を受けた作曲家のことが知りたくなる。で、その作曲家について調べてみると、これまた信じられないような魅力的な作品を残しているイタリアの作曲家に行きついたりする。
やがて、「ちょっと待って。“知っている作曲家”が書いた、私が“知らない作品”にも、案外傑作があるのかもしれない。だいいち、私はすべての作品を知っているわけではないではないか」と気づきます。事実、ドヴォルザークは有名だし、交響曲もオペラも、室内楽作品やピアノ曲も知っているけど、彼の宗教音楽はきちんと聴いたことがありませんでした。で、いろいろと聴いてみると、またこれがとんでもなく素晴らしかったりするのです。聴きながら心が音を立てて震えるほどに感動する一方で、「なんたること!こんな美しい音楽を、今まで知らなかったなんて!」と、軽いショックを受け、まさに“打ちのめされ”てしまう…という具合です。
同じことが、スカルラッティにも起こりました。鍵盤楽器のためのソナタを555曲も書いている、バッハと同い年生まれの息子ドメニコはよく知っていましたが、父アレッサンドロの作品は聴いたことがなかったのです。この親子はバッハの反対に、息子の方がお父さんよりも知名度が高いし、演奏される機会も一般的にはドメニコの作品の方が多いという認識でした。高校の音楽の指導
要領には、「アレッサンドロ・スカルラッティはオペラにおいて、舞台の華やかな演出や筋書きよりも旋律の美しさを重視。それがオペラ人気を下げるきっかけとなり、低迷を招いてしまった」と記述されていました。
ところが、アレッサンドロの鍵盤楽曲を聴いてびっくり!時代を先取りしているような和声進行や転調、容赦無く繰り広げられるアグレッシヴでアクロバティックな超絶技巧…その楽しさたるや、独特の高いエグゾースト音を立てて疾走するフェラーリさながらです。かと思うと、宗教曲には敬虔な祈りが込められ、静謐な教会の空気が感じられるような荘厳さに溢れていたりするのです。個人的な感想ではありますが、この人がオペラの低迷を招いたとは、とても思えませんでした。
「なぜ、世界にはこんなに素晴らしい芸術家や作品がたくさんあるのに、一部の作曲家や作品以外は知られていない、なんていう勿体無いことになっているんでしょう?」芸術にも歴史にも造詣が深く、“東京”という名前の国立大学で学んでいた友人に尋ねてみたところ、「いや〜、まず高校や大学の先生方が、あまりよくご存知ではありませんからね。そうすると学生にも指導できませんし、文科省にも伝わりません」との答えが。もちろん、勉強熱心な先生方もいらっしゃることは、確かです。でも、ややもすると生徒の方も、“有名な曲”や“コンクールで使えるレパートリー”に興味が集中してしまう傾向があるのかもしれません。
芸術家や作品だけではないでしょう。あまり世の中には知られていない素敵なもの、素敵な場所は、案外たくさんあるのです。そういうものに限って人は時に「他の人には教えたくない」と感じたりもするので、知名度が高くない“知られざる”ものにこそ、いいものがあるとしても不思議ではないはずです。となると、それらを発見、発掘するのは大いなる人生の楽しみかもしれませんし、毎日を輝かせてくれるワクワクやトキメキの源になる気がします。
そういえば、先日『大人のための音楽講座』が終わった後のティータイムで、受講生の皆さんが「この講座の楽しさ、素晴らしさは、あまり人に教えたくないわ」と、話していらしたっけ。そう感じていただいてとても嬉しい反面、もう少したくさんの方に知っていただきたい気も…。う〜ん、フクザツ。
ピアニストのひとり言 第804回
その昔修道院だったこのホテルは、中庭を囲むようなかたちに建てられている。食事をとるサロンはホテルの入り口からぐるりと建物を回り込んだ奥にあって、そこに行くまでの回廊にはヴィンテージのグランドピアノが置かれている一角もあり、プラハ初日の朝にここを通った時は嬉しくなって何枚も写真を撮ったのが、すでに懐かしい。
「おはようございます。7時になったばかりなのにごめんなさい、間も無くここを発たないといけなくてあまり時間がないの。いくつかペストリーと果物を頂いてもいいですか?」「もちろんです。もう私たちが朝食を提供できる時間を回っていますもの。コーヒーと温めたミルクをすぐにお持ちしますね」給仕の女性は、私が朝食のときにはコーヒーにスチームミルクをたっぷり入れて飲むのが好きなことを、わかっていてくれた。
急いでシナモンのペストリーをぱくついていたら、フロントの女性がA4の紙を手にひらひらさせながらやってきた。ついさっき、フロントで話してから5分と経っていなかった。「こちらがホテルのチェックアウトのレシートです。それと、こっちは乗り換えのご案内。三通りの時間で調べてプリントアウトしておきましたので、どうぞお持ちになって」「まぁ、素晴らしい!いろいろと本当にありがとう。楽しい滞在でした。またここに戻ってこられることを心から願っています」「ええ、お待ちしております」
新宿駅や渋谷駅での乗り換えを経験している人間にとって、たとえ外国であっても乗り物の乗り換えはそこまで複雑なことはない。注意することといえば、道路の形状や一方通行などの事情によって、上りと下りでバス停などの位置が若干変わることがあることくらいだ。
地下鉄の駅を降り、空港行きのバスに乗り込む。気づくと周りはすでに外国語だらけ。その中からなるべくチェコ語を聞き取ろうと、耳をそば立てた。独特の愛らしさとリズムがあるチェコ語…同じスラヴ系でもロシア語よりも軽やかで、ポーランド語よりも親しみやすい響きに聞こえる。
順調にヴァーツラフ・ハヴェル空港に着く。ほんの9日ほど前にここに降り立ったのが、随分前の出来事のような気がしてくる。振り返ってみれば、チェスキークルムロフ行きのバスも含め全てがオンタイムで、遅延や運転見合わせなどにヤキモキしたことは一度もなかった。
財布の中を確かめると、二日目に両替した現地通貨がまだ残っていた。私は32コルナぶんのコインをとっておき、残りは空港の売店で使った。32コルナは、プラハ市内で90分間、バスや地下鉄が自由に利用できるチケット代だ。「いつか、この32コルナで空港からホテルまで行ける日が来ますように」そう心の中で呟くと、しっかり屋の私が反論してきた。「この国のことだもの、それまでには32コルナより値上がりしているわよ。ううん、もしかしたらユーロになってしまってコルナは使えないかも」私は、そっと“自分”に言い聞かせた。「そうね。だからこそ、“その前にもう一度訪れることができますように”というおまじないになるのよ」
小さな飛行機がふらりと滑走路を離陸した。オレンジ色の屋根たちがどんどん小さくなった。
“自分は人生の中で、何か大切な選択を誤ってきたのではないか”…何度かそんな気持ちに襲われたことがありました。もっと違うキャリアの重ね方があったのではないか。すべきことをきちんと全うしていないのではないか、など。
でも、今回のボヘミアの旅を経て、全ては最良の選択だったのだ、と心から思えるようになりました。自分だけではありません。人は誰しも、知らず知らずに最良の選択を重ねているのではないでしょうか。なぜなら、皆掛け替えのない“今”を生きているのだから。豊かな“今”の積み重ねこそが、唯一無二の素晴らしい人生なのだから。
ボヘミアの地は、漠然とした問いへの答えを求めてさすらっていた私に、答えてくれました。“過去の選択に間違いなど、ない。感謝して、今幸せに生きていることが全て。あなたがここで「いい時間を過ごせた」と感じたように、あなたの演奏に触れた人が「いい時間を過ごせた」と思ってくれるピアノ弾きになりなさい”と。
ボヘミアで何より一番美しかったのは、人々の笑顔でした。
ピアニストのひとり言 第803回
ヨーロッパの古いホテル…しかも、できる限り小さなホテルを好むのは、昔ながらの“鍵”が好きだからということもある。だいたいは癖があって、なかなか右にも左にも回らなかったり、回っても回転が足りなくて開かなかったりして、はじめは手こずる。それが出入りを重ねていくうちにコツがわかってきて、ドアの内部まで手に取るように感じられるようになってくるのが、楽しいのだ。世の中にはすでにカードキーが蔓延しているが、ガチャリと差し込み、ぐるぐる2回転くらい(不思議なことに、1回転半だったりする)回して開錠するこうした鍵が、完全にはなくならないで欲しい。
夜11時近くにオペラからホテルに戻り、回し慣れた鍵でなるべく静かに部屋に入ってシャワーを浴び、翌日の出発に向けて荷物を整理しはじめてから、どのくらいが経ったのだろう。素晴らしい劇場でオペラ『ルサルカ』を鑑賞し終えたばかりの私はその余韻から抜け出すことができず、パッキングはなかなかはかどらなかった。
チェストの引き出しやクローゼットにしまいこんでいた洋服や書物を取り出しては、ふと手を止めてため息をつく。「ああ、夢のように美しかったわ」幻想的なオーバーチュア(序曲)の流れる舞台には月の光が柔らかに降りそそぎ、観客を深い森の中の湖へと誘い込む。風が夜の空気を揺らし、その向こうから水の精たちの踊る姿が、そして、彼女たちの合唱が近づいてくる…。
一部に映像を使った舞台美術だったが、不自然さがまったく気にならない。ただただ美しいその光、匂い立つような夜の森の情景に心奪われるのを、全身で味わった。ルサルカ登場の場面は、霧の立ち込める湖の水面から、ぼんやりと浮かび上がるように彼女の姿がせり上がってくる、という演出だった。しかも、後ろ向きで。
「悲しくてしかたないの。わたし人間になりたいの。」愛してはならない相手に恋い焦がれる、切ない気持ちを歌うルサルカ。歌も衣装もこの上なく美しく、演技であることを感じさせない。私は涙があふれて仕方なく、なんどもなんども目をぬぐわなければならなかった。第一幕の終わりで歌われる、このオペラで一番有名なアリア“月に寄せる歌”の時には、声が出そうになるのをこら
え、肩を震わせて泣いている自分をどうすることもできなかった。
愛しい王子の気持ちを引きつけておくことができず、彼が他の女性に心移りしてしまった時の、ルサルカの「私は半分しか人間になれず、水の精にも戻れず、生きることも死ぬこともできない!」という訴えが、ドイツやロシアに支配され続け、自分の国のアイデンティティーはどこにあるのかと自問するチェコという国の叫びにも聞こえた。
最後には自らの過ちを悔い、ルサルカに抱かれて心安らかな死を迎えることを選んだ王子。自分の腕の中で息絶えた王子にキスをしたルサルカが「あなたの愛、美しさ、移り気な人間の情熱…それら全てに私は魅入られた。神よ、人間の魂に祝福を!」と歌って幕を閉じるこの物語は、果たして悲劇なのか、それとも究極の幸福を表しているのか。
そんなことを考えては手が止まってしまい苦戦したが、なんとか荷物をまとめ終えた。「それにしても…最後までルサルカが人間に見えなかったな」ベッドに身を沈めるも、プラハ最後の夜だということに加えて、「このオペラは絶対にチェコで…」と、長いあいだ夢見続けてきたその夢がかなった興奮もあって、なかなか寝付けなかった。
翌朝は、早い時間から青空が広がっていた。木々は昨夜の雨に洗われてさらに輝きを増しているように見えた。できればこのホテルで美味しい朝食をとってから、プラハを出たい。フロントのスタッフにフライトのEチケットを見せながら尋ねた。
「おはようございます。この後チェックアウトして、この飛行機に乗ることになっているの。何時にここを出たら間に合うかしら?朝ごはんをいただいてから出発しても間に合うと思う?」「タクシーで行かれます?」「地下鉄とバスで行くつもりです」「でしたら、9時には空港に着いているように、一時間半前にはホテルを出た方が…」「てことは、20分ほど食事の時間を取れるってこと?」よほど私が嬉しそうだったのか、フロントの彼女は親しみを込めていたずらっぽく、でもテキパキと答えた。「う〜ん、15分ってところかも?今7時…ちょうど朝食のサービスが始まる時間になりましたから、どうぞ行って召し上がっててください。地下鉄とバスの時刻表を調べ、チェックアウトの手続きを済ませて、精算書を5分後にお持ちします」笑顔が、とても美しかった。
ピアニストのひとり言 第802回
チェコには音楽の他にも映画やアニメーション、人形劇など魅力的なファクターがたくさんある。なかでもチェコの絵本には随分前から心惹かれていた。絵が美しく独創的で、レイアウトも個性的な、素晴らしい絵本が多いのだ。言葉もわからないのに本屋に入り、いかにもわかったふうな顔をして本を物色するのは少々照れくさいものではあるが、チェコで絵本を何冊か買って帰ろうと、心に決めていた。
「Dobry den!(こんにちは)」店やレストランに入る時にチェコ語で挨拶をしても、初めの頃は英語で返事が返ってきた。しかし、プラハ滞在も最後の方に差し掛かると、なぜか店員さんがチェコ語で返してくれるようになった。最終日に入ったヴァーツラフ広場に面した本屋でも、そうだった。店内は広く、二つのフロアに分かれている。二階で三冊ほど絵本を選び、会計しようとするもそれらしきカウンターが見当たらない。「すみません、お会計はどこですればいいですか?」「奥の階段を降りて、入口の方に進んだところに会計カウンターがありますよ」「どうもありがとう!」思いがけずスッと口をついてチェコ語が出てきた。たったそれだけでも、やりとりができたことが嬉しかった。
プラハ最後の夜は、「これは是非、本場プラハで観たい」と切望し続けていたオペラのチケットを予約しておいた。ドヴォルザークの『ルサルカ』。彼が眠るヴィシェフラドの丘を訪れることから始まった今回の旅のおしまいは、やはりドヴォルザークの魂に触れて締めくくろうと思いたち、かつて彼が住んでいた家を訪ねた。が、今は博物館になっていて観光名所のひとつなのに、やけにひっそりとしている。さらに近づくと、まだ開館時間のはずなのに入口の門が閉まり、その向こうに立て札があった。“親愛なる訪問者の皆様。2016年11月1日から2017年4月30日まで、改修のため閉館いたします”。
仕方なく門のすき間から屋敷をカメラに収めて引き返した。彼が愛用していたベーゼンドルファーのピアノやヴィオラが見られなかったのは残念だったが、「またいらっしゃい」というドヴォルザークの声が聞こえたような気がした。「そうだ。今度ここに来るまでに、彼のピアノ作品をいろいろ勉強しておこう。そのあとに来たらもっと楽しめるわ」そう思うと、それまで明日この国を去らなければならないことを淋しく思っていたのが、帰国して早くピアノの前
に座り、楽譜を読みたくなってきた。
やはり改修工事のため閉館中の国立劇場の代わりに、今夜の『ルサルカ』はオペレッタやミュージカルを上演されることが多いカロリーン劇場で上演される。地図で場所を確認して、歩いて向かうことにした。
プラハは街並みだけでなく石畳の表情も豊かで、歩くのがとても楽しい。石畳は歩きにくくて苦手という人も多いが、私には楽しさの方がずっと勝る。地下鉄にも市電にも乗るのがもったいなく思われ、どこに行くにもできる限り歩いて移動するようになった。
街を歩くのが楽しい理由は、もう一つあった。写真である。店の看板や建物のレリーフ、子供たちの表情…。歩いていると思い出になるような被写体に数限りなく出会えるし、一瞬一瞬がシャッターチャンスになりうる。気持ちの赴くまま立ち止まり、構図をとってシャッターを押すのも、旅の楽しみになっていた。ただ、ドヴォルザーク博物館に入れなかったことほどではないが小さな心残りがあった。それは、雨に濡れる石畳を撮れていないことだった。お天気に恵まれ晴天続きだったのだ。
オペラの開場時間までは少し余裕があったので、春のジャケットでも新調しようと好きなブランドの店に入った。奥に広くなっている店内をざっと見渡し、珍しいことにすぐに「これ!」というものを見つけることができた。試着と会計を済ませて店の出口に近づくと、外の空気の匂いが変わっているのを感じた。
雨が降っていた。深い群青色の空をバックに暖かな黄金色の街灯がともり、雨に濡れた石畳がところどころにそれを映して輝いている。私は傘もささぬままカメラを取り出し、夢中でアングルを探した。やはり傘をささずに歩いている人々の後ろ姿が、ファインダーに小気味良く写り込んだ。
これから鑑賞するオペラ『ルサルカ』のヒロインは、森の湖に生きる水の精。そぼ降る雨が、ルサルカの世界に誘っているようにも、明日この地を発つ私に名残を惜しんでくれているようにも感じられた。「ありがとう」私はそうつぶやいて、カロリーン劇場へ向かう足を少し早めた。
ピアニストのひとり言 第801回
ピンカスシナゴークの東側には、旧ユダヤ人墓地が広がっていた。半分朽ちかけているような無数の墓石が所狭しと建てられて…というよりも、無造作に重なるように“置かれて”いる様子には、独特の雰囲気が漂っていた。それもそのはず、ここは現存するユダヤ人墓地としてはヨーロッパ最古で、1439年からの約350年の間にわたって10万人ものユダヤ人が埋葬されているという。
私の前を若い韓国人女性ふたりが、オーディオガイドを聞きながら「ひどい」「ヒットラー最低」などとつぶやきながら神妙な面持ちで歩いている。きっと、ユダヤ人撲滅後、彼が“かつてこの地に存在し、絶滅した特殊な人種”の記録を博物館に収めるべくユダヤ博物館を作る計画を立てており、そこでこの旧ユダヤ墓地を残すことにした、という説明を聞いたのだろう。
人間が尊厳を奪われ、無残に殺されることの惨さ、やり切れなさは人間誰もが感じるものなのに、なぜ争いがなくならないのか。韓国とわが国との現在の関係も友好的なものとは言えないかもしれないが、旅先で出会った韓国人から悪いイメージを受けたことは一度もない。人と人は元来、争いたくなどないはずなのに…。小さな墓石を見つけ、これは幾つくらいの子供のものだろう…と考えるうちに、涙が溢れてきてしまった。
墓地と同じ敷地の一角に、“儀式の家”と呼ばれる建物がある。別名セレモニアホール。かつては旧ユダヤ人墓地の儀式の会場、および死体置き場として使われていた建物だそうだ。ユダヤの歴史について、儀式や伝統、生活習慣についてなどの展示はとても興味深かった。移住を認める代わりに多額の納税を求められたり、さぞや煩雑だったと思われる手続きのための役所の受付時間が、ユダヤ人だけは朝の8時から9時までの一時間のみだったり…などといった現実的な記録を目の当たりにすると、胸が痛くなる。無神論者がとても多くなったこの国の歩んできたあまりにも複雑な歴史的背景を、垣間見た気がした。
もう一度、ピンカスシナゴークに戻ることにした。さっきはちょうど団体観光客グループとあたってしまい、押すな押すなの人で(ヨーロッパのガイドブックによると、プラハのユダヤ人街はかなり人気の観光スポットなのだそうだ)観られなかった二階のギャラリーが、どうしても気になった。
入手したチケットはすべてのシナゴーク共通パスなので、何度でも出入りできる。二階へ直行し、お目当ての展示コーナーへと向かった。そこは場違いなほど愛らしい絵でいっぱいだった。それらは、第二次世界大戦中1942年から1944年にかけて、ナチスの強制収容所になったチェコ北部のテレジン収容所で子供たちが描いたものだった。
収容所には、親と離れ離れになってしまった子供も少なくなかっただろう。それでも、絵の多くには子供らしく明るい色が用いられ、寂しさ辛さより、苦しくても不安に押しつぶされることなく生き抜こうという逞しさが感じられるものが多かった。小さな手にクレヨンを握りしめ、無心で描いている子供たちの胸の中を思うといたたまれなくなったが、中には子供のものだと知らされなければそれとわからないほど、しっかりした作品もあった。
素晴らしい教師がいたのだ。バウハウスで学んだ経験を持つ、フリーデル・ディッカー=ブランダイスという女性だ。「どんなときにも、ファンタジーや希望を持って生きるのは大切なこと」彼女は子供たちに絵を通して、表現の楽しさや、お互いを認めあい受け入れあうことの尊さを伝え続けた。アウシュヴィッツに移る時、彼女が持って出たのは、小さなトランク2つ…その中には彼女が教えていた子供たちの書いた4000を超える絵が入っていたという。それがここに展示されている絵だ。
彼女は、生きて行くのに必要な私物より、子どもたちの絵を選んだ。アウシュヴィッツ行きが決まったとき、彼女は覚悟を決めたのではないか。自分の命はきっとそこで絶える。自分のすべきことは、子どもたちの絵を後世に残し、彼らのメッセージを一人でも多くの人に伝えることだ、と。彼女は最後まで諦めなかったし、希望を持っていた。希望を持って生きることを教え続けた彼女は、それを身を以て果たした。
彼女といい子どもたちといい、人間はそんなにも強くなれるものなのか…またもめそめそ涙ぐみ始めている自分が、急に恥ずかしくなった。不安に怯えて生きるなど、なんと勿体無いことか。それより、自分にできることは何かを考え、それを実行していかなくては。子どもたちの絵が、そんなことを訴えるまっすぐな瞳のように私を見つめた。
ピアニストのひとり言 第800回
—————何が、人間に幸せをもたらすのだろう。
「幸せになるね」プラハ中央駅のプラットホームで友人にそう答えた後、頭の中でその問いが繰り返されていた。より良い生活、より良い人生のため、人は努力する。その営みが尊いものだというのは、理解できる。しかし、果たしてどれだけの人たちが、自身にとって本当の幸せのための営みを、喜びをもって重ねているのだろうか。
幸せを阻むものに、経済的な不安がある。自分がこれまでで一番やりくりに苦心(?)した、音大の寮生活時代を思い出してみる。仕送りだけではとても心細かったので、2年目にピアノを教えるアルバイトができるようになるまではとにかくできるだけ節約した。学食でお昼を食べるのも度重なるとバカにならないと気づき、サンドイッチのお弁当を作っていったり、学生ホールの自販機で数十円のコーヒーを買うのも憚られて、お湯をもらって持参したティーバックでお茶を入れたりしていたこともあった。
でも、なぜかちっとも惨めな気持ちにはならなかった。それどころか、つい友人に「ねぇ、聞いて。こんなことして節約しちゃった!」と伝えたくなるほど、愉しい気分だった。それは、私に音楽…希望…があったからだと思う。
弾きたい、勉強したい、と心から願ってやまない作品が山ほどあった。心が震えるような巨匠の演奏に出会うたび、力が湧いてきた。いつかこれをステージで弾きたい、いつかヨーロッパに行きたい、いつかオーケストラとの共演を果たしたい…夢は膨らむ一方だった。専攻や室内楽のレッスンが楽しみで仕方なかった。
今思うと、ないものを憂うよりも、ないものを得る可能性に憧れる気持ちの方がずっと大きかった。言い換えるなら、自分がこの先、どうやって生きて行くのかに対する不安よりも、希望と情熱の方がずっと優っていたのだと思う。
音大を卒業してからも試練はあったが、いつも音楽、芸術のちからに助けられてきた。家族や友人からの励ましにも救われた。人間は、自身の尊厳を支えるものがあれば、心健やかに与えられたものに感謝して生きていけるものなのか
もしれない。カレル橋のストリートパフォーマーをぼんやり眺めながら、そんなことが頭をよぎった。
「ああ、美しい」…日差しに輝くヴルタヴァ川のほとりを歩きながら、この景色のすべてを体に取り込みたくなって深呼吸した。“ヴルタヴァ川の最後の一滴までを、その秘められた最後のほほえみまでを、音楽にした人は、まだ誰もいない。その姿をあるがまま形に描いたり、色彩豊かな絵にしたり、散文で描写したり、詩にうたったりした人は、まだ誰もいない。”機内で読んだチェコの作家チャペックの随筆集『チェコスロヴァキアめぐり』の、飯島周先生の名訳が思いだされた(帰国後間もなく飯島先生とお会いする機会に恵まれるとは、この時は思いもしなかった)。
建物の中に入っているのはもったいないような、素晴らしい青空が広がっていた。国立図書館をのぞいたり、古本屋さんをひやかしたり、カレル大学に潜入して(!)学生観察をしたり。気ままに歩きまわり、自分の今いる場所が怪しくなるとフリーワイファイが飛んでいると思しきホテルのロビーに入って、地図を確認した。
旧市庁舎のある目抜き広場から北へ歩いて行くと、瀟洒な建物の連なっている新市街地に出た。パリの一角にも負けない高級ブランドが軒を連ねる、その名も“パリ通り”のあるこのあたりは、ユダヤ人街と呼ばれている。かつては衛生状態が良くなかったエリアだったが、19世紀末に古い建物が取り壊されてアールヌーヴォー建築による街づくりが行われたのだった。
そこには、シナゴークと呼ばれる幾つかのユダヤ教会が点在していた。シナゴークはハンガリーでもいくつも見たことがある。しかし、10世紀ごろからユダヤ人が移り住み始め、13世紀には中欧ヨーロッパ最大のゲットー(ユダヤ人居住地)があったプラハのそれは、私に特別な感慨をもたらすことになった。
最初に入ったスペインシナゴークに展示されていた真実の記録は、人間を支えている“尊厳”と、幸せになる権利を剥奪するような痛ましいものだった。ナチスに虐殺された77,297人のユダヤ人の姓名や死亡場所が、内部の壁一面に書き連ねられているピンカスシナゴークもかなりの衝撃だったが、その二階のギャラリーではさらに大きな驚きが待っていた。
ピアニストのひとり言 第799回
ウィーンからの友人とのチェスキー・クルムロフへの一泊旅行も、素晴らしかった。
プラハ10時発のバスに乗り込む。飛行機さながらに一つ一つの座席には液晶画面が埋め込まれ、フリーワイファイ、フットレストも完璧。無料のドリンクサービスや車内販売もあって快適そのものだ。大きな車窓は綺麗に磨かれていて、のどかな田園風景をストレスなくカメラに収めることができた。ホットチョコレートを飲みながら、ところどころに残雪が見られるボヘミアを南へと進む。チェスキー・クルムロフに着く頃、太陽の輝きは「生きとし生けるもの全てを輝かせる微笑みがあるとするなら、それはきっとこういうもののことだろう」と思われるほどに美しかった。
予約を取っておいたドヴォルザークホテルは、大きく湾曲して流れるヴルタヴァ川のほとりにチェスキー・クルムロフ城を見上げるように建っていた。スィートルームと思しき私たちの部屋はその角の絶好の位置にあり、城の全貌も眼下に流れるヴァルタヴァ川も、我が物のように眺めることができた。
二人で使うには広すぎるその部屋で、テーブルに用意されたフルーツの盛り合わせをつまみながら真夜中過ぎまで語り合ったその夜のことは、生涯忘れないだろう。私たちは、とても語り尽くせないほど様々な出来事があった過去についてよりも、自分たちの未来について多くを語り合った。会えなかった時間を乗り越え…いや、それを熟成させて、かけがえのない“今”に至っていること。お互いを家族のように大切に、愛しく思っていることを感じた夜だった。
翌日は、改装中で閉館していたエゴン・シーレ美術館の代わりに新しくできた写真家ザイテルの博物館をじっくりと見学。少し買い物をしたあとチェスキー・クルムロフ最大のビール醸造所で昼食をとってプラハに戻るバスに乗った。時間どおりに到着。広いビリヤードスペースのある老舗カフェでくつろぎつつ、別れの時を迎える心の準備をした。
「大丈夫」という彼女に、一度は「じゃ、ヴァーツラフ広場までは見送らせて」と答えたが、数日前に彼女がかなり道に迷ったことを思い出し、中央駅まで見送ることに。結果的には大正解だった(道すがら、彼女の“記憶”があまり
正確でなかったことが判明した)。おまけにプラットホームも分かりにくかった。「プラットホーム4って書いてあるのに、見当たらないわ」「どれどれ。あ、“4S”だって。これ、車両がそれほど長くなくて、ホームの前方に停まっているってことかも」そう信じて、彼方に何があるのか見えないほどに長いプラッドホームを直進すると、果たしてそれらしい列車が停車していた。「わぁ、美奈子、ありがとう!」発車時刻の5分前だった。
彼女はやっと空席を見つけ、車内の通路の人たちをすり抜けるようにしてホームにいる私の前に戻ってきた。「最後までハラハラさせちゃったね。でも楽しかった。美奈子、幸せになってね」「私もとても楽しかった。幸せになるね」涙声になっていた。彼女と抱き合いながら、約2年前にウィーンの国立オペラ劇場の前で同じように抱き合って別れたことを思い出した。その時も彼女に「幸せになってね」と言われたことも。涙が“かさ”を増してくるのを感じた。
「じゃあ、気をつけてね。元気で…」ドアが閉まった次の瞬間、発車を告げるチャイムが鳴った。スメタナの交響詩『我が祖国』の第1曲目“ヴィシェフラド”の冒頭部分だった。胸にツンと痛みを感じ、涙だけでなく嗚咽まで阻止することができなくなった。列車を見送った私は帽子を深めに被りなおし、ついさっき彼女ときた道を足早に戻った。
彼女はブダペストで知り合って以来ずっと、胸の内をあかしなんでも相談してきた親友だ。共通の友人だった相手との結婚に至った経緯も、そのあと彼と別れひとりに戻った後のことも、誰よりもわかってくれているのが彼女だった。
毎日のように会えていたブダペスト時代を思うと、今は会える機会のなんと希なことか。一方で、心から“幸せであれかし”と思いあえる友人がいるのは、なんと嬉しいことだろう。
ホテルへ帰る道すがら、スメタナの“ヴィシェフラド”のメロディーが頭をぐるぐる回っていた。『我が祖国』。“心のふるさと”という言葉があるが、それは物理的なものだけではない。いや、そもそも物理的なものではなく精神的なものなのだ。ありがたいことに、私にはそれがある。
涙を浮かべた彼女の顔を思い出しながら、これは悲しい涙ではなく嬉しい涙なのだと気づき、黄金色の街灯に照らされた石畳を歩きながら幸せをそっとかみしめた。 (“ボヘミアン、ボヘミアを行く”その其の7 に続く)
ピアニストのひとり言 第798回
翌日も、待ち合わせた時間から20分以上遅れて彼女がやってきた。「やっぱりこの街、よくわけがわからないわ。ホテルを出て右に出て、初めの角をどうやら反対に曲がってしまったみたい。ブダペストではこんなに迷ったりしないのに」と、しきりに頭を傾げている。
プラハ旧市街地の小径は迷路のよう、と誰かも書いていたっけ。でも、チェコの波乱の歴史の中では、このわかりにくい街が幸いした出来事もあった。詳細については記憶が怪しいのだが、1968年に起こった変革運動“プラハの春”の時、地下組織と市民が結託し、理不尽な通達が届けられなくなるよう一晩でこっそり市内すべての住所プレートを外してしまったというのだ。それでなくても複雑な区画の街なのに、通りの名前を示すプレートがなかったら郵便配達員はお手上げだったことだろう。
もっと時間を遡ると、1857年まで建物に住所表記がなかったプラハでは、人々は家の戸口の上にレリーフ(紋章)を掲げて目印にしてきた。それらのレリーフには動物や絵、彫像、家紋、職業を表す絵柄などが選ばれ、特に規制はなかったが、二つとして同じものは作られなかったそうだ。レリーフの付いている建物は今日もかなり残っていて、街
すっきりとした青空に恵まれたこの日、私たちは再びカレル橋を渡った。マラー・ストラナと呼ばれるプラハ城の足元に広がる地域にある聖ミクラーシュ教会は、ぜひ訪れたかった。モーツァルトが逝去した折、本国のオーストリアではごく簡素な葬儀しか行われず、麻袋に包まれた遺体が無残に共同墓穴に埋められただけだったが、この国の人たちは心から彼の音楽を愛し、彼の死を悼み、この聖ミクラーシュ教会で世界に先駆けて盛大な追悼ミサが執り行われた。4000人もの参列者があったという。
一歩建物の中に入った瞬間、「わぁ」と声が出たきり、言葉を失った。そこには、見たこともないような美しい薄緑色をたたえたマーブル模様の壁に、上品なモーヴピンクの縁取り…さらに、金色の華麗な彫刻があちこちに施された夢のような空間が広がっていた。丸天井の“聖三位一体の祝典”が描かれたフレス
コ画も素晴らしく、モーツァルトが演奏したという純白のパイプオルガンには、楽器を弾いている金の天使たちが戯れている。この教会はもともとはゴシック様式の教会として13世紀に作られ、その後17世紀にバロック様式に改修されたというが、ここでモーツァルトがオルガンを弾き、彼の追悼ミサが行われたと思うと、感慨無量だった。
私たちは、フラッチャニというプラハ城のある丘をのんびりと散策した。12世紀に創設されたストラホフ修道院の美しい図書館を見学したり、『黄金の小径』をそぞろ歩きしてカフカの生家でお土産を買ったり。煉瓦色の屋根をした町並みを見下ろせる丘の上のレストランでの昼食も、お料理、修道院ビール、感じのいいのいいスタッフ…すべてが素晴らしかった。
プラハは、昼休みの時間になると入館できなくなる施設が多い。タイミングが悪いと、午後入れる時間になるまで待たなくてはならない。フラッチャニ地区の小さな美術館で早めの昼食を済ませて開館時間を待っていたら、近くの教会の鐘の音と同時にドアの向こうから鍵をぐるぐると回す音が聞こえた。「どうぞ」と、係りの方が声をかけてくれたが、私たちの前にお一人で並んでいた初老のご婦人は、入ろうとしなかった。「もうお入りいただけますよ」再び係りの方に言われた時、彼女は柔らかい笑顔で答えた。「ありがとう。でも、この素敵な鐘の音をここで聴き終えてから中に入りたいの」
彼女が海外からの旅行者だったら、躊躇なく彼女に話しかけていただろう。「確かに素敵な音ですものね。私もあなたみたいに鐘の音が鳴り終えるまで待って、中に入ることにするわ」でも、彼女が話していたのはチェコ語だった。
鐘の音は、空気を包み込みながら、空気を震わせ風に乗って周りに響き渡る。未明にも聞こえてくるが、うるさいと感じたことは一度もない。それどころか、音の“消えぎわ”まで耳で追いかけたい気持ちになる。
ふと、故郷の山並が思い浮かんだ。季節や気候によって青く、白く、濃く、薄くその姿を変えながら、私たちを見守るように広がっているその姿を音にしたら、このような響きになるのかもしれない…。そんなことを考えた。
ピアニストのひとり言 第797回
前日の国民劇場でのオペラの強い余韻がそうさせたのか、時差ボケの影響が多少あるのか、翌朝は日の出の前に目覚めた。腰の高さから高い天井ぎりぎりまでのびた窓が、花嫁のドレスのトレーンのように長くたれ下がったカーテン越しにうっすらとした明るさをたたえている。鐘の音が遠くから聞こえてきた。「いや、この音は遠くからなのではなく“小さい”ほうだわ」
このあたりの教会の鐘は、小さい鐘が15分に一度鳴る。5時15分過ぎなら1回、30分なら2回、45分には3回。そのあと大きな鐘の音が時刻の分だけ鳴るので、5時30分なら2回と5回の計7回鳴る。そんな他愛もないことがわかるようになるだけで、この街の人に近づいたような気持ちになる。
ベッドの中で小さい鐘が3回、大きい鐘が5回鳴るのを聞き終えた時、ふと「血が結びつけるものを海は引き離せない」という言葉を思い出した。
プラハの国民劇場の建設にあたって寄せられた寄付金は、国内からにとどまらなかった。アメリカに渡ったチェコ人からも礎石が送られてきたそうだが。その石にはある言葉が刻まれていたという。それがこの「血が結びつけるものを海は引き離せない」だった。
何と美しく、つよいメッセージだろう。物理的には離れていても、精神は繋がっているという連帯感。世界のどこにいても互いを支えあっている、支えあっていたいという思いが感じられる言葉だ。
午前中はそわそわと落ち着かなかった。それもそのはず、ハンガリーのリスト音楽院留学からの親友との、プラハでの再会の時が迫っていたのだ。早朝に目が覚めたのは、それが楽しみで仕方なかったからかもしれない。
約束の時間を過ぎても彼女はなかなか来なかったが、それは想定内だった。彼女が、ここで道に迷っているのがわかっていたからだ。「方向感覚がある方ではないのに、中央駅から歩いてくるなんていうんだもの…」待ち合わせの約束から30分を過ぎた頃にはさすがに少し心配になったが、海外生活が長い(現在、ウィーン在住6年目に)彼女のこと、何とかしてここにたどり着くことだろう。
「美奈子〜!会えた〜!迷った〜!何人に道を尋ねてたどり着いたことか!」果たして彼女は、タイムトリップしてプラハの旧市街地に迷い込んでしまった少女のように、ふわりと目の前に現れた。これと同じ光景が前にもあったような気がするほど、何の違和感もない…それでいて涙が出るほど懐かしく、心が震える再会だった。
連れ立ってプラハ城や旧市庁舎付近を気の向くままに歩いているうちに、まるで二人ともずっとここに住んでいるような気分になっていた。それもそのはず、ブダペスト時代はよくこうして二人でそぞろ歩きをしたり、お互いの住居を行き来しては、ありとあらゆることを話し合ったものだった。長女の私は二つ上のお姉さんができたみたいで嬉しかったし、彼女は彼女でなぜか私をお姉さんのように(?)頼ってくれていた。
歩き疲れて入ったショコラカフェのクオリティーの高さに、二人ともびっくり。オーガニックカカオ73パーセントのチョコレートで作るホットチョコレートドリンクは甘過ぎず、器の下に忍ばせたダークチェリーのみずみずしい風味や食感と相まって、苦味、甘み、酸味、香りのバランスの素晴らしく洗練された一品になっていた。大ぶりなガラスの器にたっぷりと入っていたのも嬉しかった。「すっかり元気になったね。上質なチョコレートの力ってすごい!」
その日の締めくくりは、やはりオペラ。モーツァルトの傑作『ドン・ジョバンニ』が初演されたエステート劇場(チェコ語ではスタヴォフスケー劇場)がその会場だった。演目は、やはり彼の代表作のひとつ『フィガロの結婚』。
モーツァルトの音楽は、かくもチャーミングだったのだ!戯れるような三連符、上昇と下降を繰り返すパッセージは子供が遊んでいるように無邪気で楽しげだ。音響の良さはもちろんだが、小ぶりな建物なので細やかなニュアンスが感じられ、ピアニシモも隅々まで聴こえる。プロンプターが歌手にセリフを教える声まで聞こえてきたのには驚いた。
「私がそちらのホテルにお迎えに行こうか?」「もう大丈夫よ!」「じゃ、明日は迷わないようにね」彼女と明日の約束をして別れた。明日も一緒に過ごせるなんて、なんと幸せなことだろう!その晩はあっという間に深い眠りに落ちた。
ピアニストのひとり言 第796回
ホテルに帰って一息つき、国民劇場へと向かう。昨日、ホテルへの道に迷ってこの辺りまで来てしまったのをいいことに、プラハ城を懐かしく見ながらヴルタヴァ川沿いをしばし歩き、女王のように美しくライトアップされた国民劇場の姿を思わずカメラに納めたことを思い出す。プラハに来てまだ二日目だというのに、もうずいぶん長いことこの地にいるような気持ちになってくる。
入り口で、本当はバーコードのついたページをプリントアウトしなければならなかったのを、バウチャーのまま持って来てしまったことに気づくが、受付係のご婦人は事も無げに「では、あちらでチケットを受け取ってください」と案内してくれたが、さらにそこにいく途中、別のご婦人が「階段を上がって、二階の中央入り口からどうぞお入りになって」と促してくれた。言われたとおりに階段を上がる。各階にビュッフェがあって、すでに何人もの男女がシャンデリアの下で優雅にワイングラスを傾けていた。
それにしても、なんと美しい建物だろう。オーストリア・ハンガリー帝国支配時代、チェコには自国のオペラをチェコ語で上演できる劇場がなかった。この劇場はそんな中、“国民の手によって自国の音楽を上演する劇場を??”との働きかけにより、寄付を募って創立された。1844年に設立委員会が出来てから長い年月を経て、やっと1881年に完成のこけら落としにこぎつけるも、直後にまさかの火災で焼失。しかし国民は希望を失うことなく、再び寄付をはじめて1883年に2年前のこけら落としと同じスメタナのオペラで再開を祝ったという激動の歴史を持つ、チェコの人々のアイデンティティと誇りの象徴のような建物なのだ。
演目は、プッチーニの『ラ・ボヘーム(フランス語で“ボヘミアン”)。劇場の音響は申し分なく、オーケストラのふくよかな響きは、表情豊かにして決して歌手の声をかき消すことがない。キャパは思ったほど大きくなく、歌手は声を張り上げなくても微妙なニュアンスを伝えることができるし、バルコニーも舞台からさほどは遠くないため、観客は舞台をじっくりと見渡すことができる。オーケストラピットの指揮者の背中がよく見える。団員は指揮棒だけでなく、よく歌手を見ながら演奏している。イタリア語での上演で、字幕はチェコ語と英語の二ヶ国語だった。
しかも、舞台美術や衣装が抜群に美しい。残念ながら日本では最近主流になりつつある“モダニズム”と称しての、経費削減対策のようにしか見えない痛々しい舞台とはまるで違う。そこには人の体臭が感じられそうなパリのアパルトマンの屋根裏部屋が、カフェが、そしてむせかえるようなワインの匂いの漂う酒場そのものがあった。
作品を知り尽くした音楽家、舞台スタッフによる極上のおもてなしに、客席に座っている私はただただ感激するばかり。途中なんども涙が浮かんだ。その素晴らしさを表現する言葉は、“上手い”、“立派な”という種類のものではない。何といったら良いか…上手であることを感じさせないほどに自然で、洗練されたアプローチだった。まるで、人間から溢れ出てくる心からの表現をとおして、まごころを音楽に託した贈り物を受け取ったような気持ちだった。
本当に上質なものに触れた時や心から感動した時、人は言葉を奪われる。それを身を以て感じるというこうした体験は、人生のなかでなんども味わえるものではない。「ああ、幸せ…」思わず呟いた次の瞬間、でも、待てよ…と、思いとどまった。自分はずいぶん長いこと、音楽をとおしてこのような感動を与えることができるよう励み続けているのに、それがちゃんとできているとは思えない。いったい何が足りないのだろう?
実はこれまで、コンクールの覇者による演奏や、“有名”な演奏家の演奏に心から共感できず、戸惑いを覚えることが少なくなかった。今夜の演奏はそういった演奏とは明らかに方向性の違うもので、何の違和感もなく体にすうっとしみ込んで来た。包まれていると豊かな気持ちになるような温かな響き、清らかな湧き水のように透明感のあるハーモニーや自然なフレージング…全てが心地よかった。
劇場をあとにホテルに向かいながら、少し前まで聴いていた音を忘れまいと、頭の中で鳴らし続けた。また幸せな気持ちに満たされた。脳が考えることをやめたとき、どこか別のところから声が聞こえてきた。「そうか。自分の心を満たす、自分が心地よいと感じるものを求めていけばいいんだわ」
街灯の明かりが、物語『ヘンゼルとグレーテル』の森の中のパンのように温かな色をたたえていた。
ピアニストのひとり言 第795回
翌日のプラハの空はどんよりと重かった。「そうこなくっちゃ」と呟きたくなるような重さだった。ハンガリーも、春が来る前は天気が不安定で、雪が降りてきそうな厚みを感じる灰色の雲が広がっていることがよくあった。こんな天気のなか石畳を足早に歩いていると、ずいぶん前からこの地に住んでいるような気分になる。
朝食は数え切れないほどの種類のチーズやハム、パンやデニッシュなどのほか、暖かいお料理や手作りのタルトや様々な果物、ドリンクバーにはシャンパンも並ぶ豪華なものだった。「何をお飲みになりますか?」と聞かれたので「コーヒーとミルクを」とオーダーしたら、コーヒーと、スチームミルクたっぷりと入れたミルクポットを持ってきてくれた。
気ままな滞在ではあるが、最初に行くところだけは決めていた。プラハ南部に位置する新市街地にあるヴィシェフラドだ。ドヴォルザークやスメタナ、カフカらの眠る墓地がある城塞の丘で、スメタナはこの地名を、彼の最も有名な作品である交響詩『我が祖国』冒頭の楽章のタイトルにしている。
プラハの唯一の“汚点”かもしれない両替のレートや手数料の悪さについて、チェコ通の友人から注意を受けていたので、安全安心というお墨付きのヴァーツラフ広場のドイツ系の銀行でそれをすませ、ヴィシェフラドの方向に歩き出す。地下鉄の駅三つ分ほどの距離があるが、歩かないと目に入らないものがあると思うと、地下に潜るのももったいないような気持ちになるのだ。
「前回、偶然見つけたアンティークカメラのお店は確かこの辺りだったな」途中、記憶を頼りに街角を曲がると、
果たしてそのお店は想像通りの場所にあった。ドレスデンのエクサ社による1950年代製の、上から覗くファインダーのついた銀塩カメラが目に止まった。レンズはイエナのカール・ツァイス社の50mm、F2.8のテッサー。シャッターにはカバーがついている珍しいデザイン。縦長で何処となくエレガントな姿をしていた。値段を見ると、目を疑いたくなるほど安い。今回はボヘミアガラスもガーネットも買わないと決めていたので、これを自分へのお土産にすることにした。
ヴィシェフラドにたどり着いた頃には、風が一段と強くなっていた。そのまま天に続いているのではないかと思われるような石畳の坂道を、風に煽られたり阻まれたりしながら一歩一歩登る。城壁で囲まれた天空の城跡からの眺めは素晴らしく、眼下に流れるヴルタヴァ川の両脇にオレンジ色の屋根の大小の建物が立ち並んでいるのが、まるで絵画のようだ。教会の脇の広い墓地に入って、また歩く。一つ一つの墓石には意匠が凝らされ、デザインもレイアウトも、文字のフォントもそれぞれに美しい。ウィーンの中央墓地とはずいぶん違う印象だった。
ふと、風が音を立てて“鳴り”、そのあまりの強さに思わず顔を風下に向けると、そこにドヴォルザークのお墓があった。「あ、ここだったんだ」感慨に耽り、写真を撮るのも忘れてその前に佇んでいると、さっきの教会が正午の鐘を打ち鳴らし始めた。鐘の音は何かの歌のメロディーで、風の向きによって強弱の表情をみせた。ボヘミアの丘で、“彼”は今も音を奏で続けていた。全てが自然な流れにつつまれ、調和しているようだった。
プラハの旧市街地に戻り、共産圏時代からのセルフサービスの食堂“ハヴェルスカー・コルナ”で遅い昼食をとる。丘の上で強風と対峙した体を温めようとレンズ豆のポタージュスープを注文したのはいいが、何もかも美味しそうでつい豚肉の煮込みやビールまで追加してしまった。コートを置いておいた席に戻るとイタリア人夫妻が座っていた。「合席させてもらっても構いませんか?お仲間がいらっしゃるなら他に移ります」「一人です。もちろんどうぞ」
「僕たち、初めてのチェコ旅行なんです」「それはそれは。いついらしたの?」「昨日。申し込んでいたガイドツアーが、人数が集まらなくてキャンセルになってしまって…で、この後ヴィシェフラドでも行ってみようかと」「あら、私も昨日着いて、さっきまでヴィシェフラドを散歩していたんです。素敵なところでしたよ」「そうでしょうとも!ここは実に美しい街ですね。このままでも充分美しいけど、少しでも青空が見えたらどんなに美しいことだろうと…」「そうね。でも、今日も朝から雨の予報が外れて曇りになったし、週末には晴れるそうだから楽しみにしましょう」
悪かった天気が好転すること。気の向くままに歩くこと。新しい体験をすること。旅人は、それだけで満たされ、幸せになる。人生も本来はそんな、シンプルなものではないのか。私たちはつい、いろいろを求めすぎているのではないか…。そんな思いが頭をよぎった。
ピアニストのひとり言 第794回
人生は選択の連続だと、つくづく思います。
進学、就職、結婚といった大きなことだけではありません。何を食べるか、何の番組を見るか、何を着るか…人は無意識に自分の>
判断で選択を重ねて生きているといってもいいのではないでしょうか。
様々な選択の向こうに人が本当に求めるものは、本来の自分に立ち戻って心からくつろげる場所、自分らしくいられる場所なのかもしれません。それを家庭に求める人もいれば、宗教や趣味に求める人もいる。私の場合は、音楽に関わることがそれでした。でも、求める“相手”に真剣に相対するほどに、迷いや疑問が湧いてもくるものです。
思ったとおりの結果が得られないと“選択を誤った”と感じてしまいがちですが、それがのちになって思いもしなかった方向に好転するきっかけになることも少なくないのが、人生の面白いところです。そう考えると、選択に間違いも正しいもないのではないか。すべての選択には意味があって、それをどう人生に生かすかというところにこそ、その人の“生き抜く力”が試されるのではないか、という気がしてきます。
2017年2月21日。初めてプラハのヴァーツラフ・ハヴェル空港に降り立った。正確にいうと、ヴァーツラフ・ハヴェル空港という名前になってからこの国に来たのは、初めてだった。1989年のビロード革命のリーダーで、チェコスロヴァキアの最後にしてチェコ共和国の最初の大統領だったハヴェル氏の生前の功績から、彼が他界した翌年2012年に名付けられたのだ。
空港を背に、10日分とは思えない小さな荷物を転がして迷わず100番のバスのレーンに並ぶ。終点のズリチーンで降りて地下鉄に乗り換え、ホテルの最寄りの駅を目指す。周囲から聞こえてくるチェコ語は何もわからないのに、窓から見える景色はなぜか懐かしく感じる。
プラハの旧市街地は迷路のようだとは聞いていた。私もご多分にもれずホテルまで迷ってしまったが、おかげでおおよその周囲の地理がつかめた。何より、誰に道を尋ねてもとても親切に教えてもらえたのが嬉しかった。現地の人も必ずしも道についてよくわかっているわけではないようで、私が見せた地図を上下ひっくり返したりしながら、真剣に考えて答えてくれる。なかにはiPhoneを取り出して地図ソフトを見せてくれながら「今僕たちここだから、次の角を右に行けばその通りに出るはずだよ」と、教えてくれる人も…。そこで、「あ!」と気づいた。端末が普及しているのにもかかわらず、バスや地下鉄でスマートフォンをいじっている人は、ほとんどいなかったのだ。
ホテルに着くと、フロントの男性はとても感じがよく、マニュアルどおりの慇懃さは微塵もない。名前を告げ、簡単な宿帳を書くと、プリントしておいたバウチャーも確認せずすぐに鍵を渡してくれた。「そうそう。Wi-Fiを使うにはどうしたらいいでしょうか?」「ああ、それならパスコードも何も要りません。そのままお使いになれますよ」日本のホテルでは、まだまだログインしないと使えないところが多いのに、ネット環境はさすがに整っている。この分だと、大きなホテルならロビーにはいれば誰でもネットを使えるはずだ(実際、滞在中に何度かお世話になった)。
「ここをなかなか見つけられなくて、ちょっと迷ってしまったわ。でも警察署のオフィスがこんなに近くにあるんですね。この辺りは安全ってことね」「そうですね。ご心配なく。治安のいいエリアですよ。よろしかったら、そちらのソファーでシャンパンでもいかがですか?」「まぁ、ご親切にありがとう!是非いただきます」
このホテルは、完成した1856年当初は大きな修道院として使われていた建物。多い時にはプラハ市内の25ヶ所以上の病院で働く、1200人もの修道女たちが暮らしていたという。第二次大戦か勃発してのち1940年からは、共産主義者の秘密警察として使われていたという“数奇な”歴史をもっているとのことだった。そういえば、入口の向こうに広がっていた中庭を囲むようにして建てられている造りは、まさに典型的な修道院のそれだ。
フロントの男性がロビーの傍にインテリアのように置かれていたワインクーラーから、シャンパンのボトルを取り出した。栓を抜いた音が、プラハ滞在のスタートの小さな合図のように、私の胸に響いた。
ピアニストのひとり言 第793回
言葉は時代とともに変化して、それを母国語とする自分もついていけないと感じることがあります。
先日、知人が、腕をふるって作った料理を家族が何も言わずに食べるので、気になって「料理、どう?」と尋ねたところ、「うん。フツーに食べれる」という答えが返ってきてがっかりしたと嘆いていました。「フツーに、って…。そりゃ、今は“フツー”が“とても”の代わりに使われていることはわかってはいるけど、なんだかちっとも伝わってこないのよね。しかも、“食べれる”って…?本来、“まぁ、食べられないほどひどいレベルではない”ってことよね?美味しいなら“美味しい”って言ってくれればいいのに。第一、それを言うにせよ、正しくは“食べれる”じゃなくて“食べられる”でしょう。もうそこからしてダメじゃない?」
料理するのは好きな方なので、彼女の気持ちもよくわかります。素直に「美味しい」と伝えてもらえたらどんなに嬉しいことか。でも、そう言われてみると、気になる言葉の使われ方はいろいろあります。例えば、最近よく聞かれる“やばい”という単語。最近の若い人たちのこのようなやり取りには、一瞬戸惑いました。「やだ、これ〜。ちょー可愛くない?」「うそ。やば〜い!」
もはや、“やだ(嫌だ)”も“やばい”も“うそ”も、ここでは反対の意味になっているのです。やだ=いい。やばい=とてもいい(欲しくなって困るほどに、いい)、という感じでしょうか。こんな会話を聞くと私は、目を白黒させながら頭の中で外国を翻訳するような置き換え作業をすることになります。この場合の翻訳は、「いいね、これ。とっても可愛いと思わない?」「本当、とてもいいわね!」というところでしょうか。
もし、外国人に「“やばい”って、どういう意味?」と質問されたら、「ええっと、基本的には具合が悪い、不都合、と言う意味なのだけど、最近はそれが転じて、口語として何かが“良すぎて困る”など、いい意味で使うことがあるみたい。やばい可愛い、とか、美味しくてやばい、とか…」と、要領を得ない回りくどい説明になってしまいそうです。さらに、「そう言えば、とても気に入ったというのが相手に伝わるかな」と聞かれたら、「若い子同士が使うのは伝わるけど、ある程度以上の年齢の人はどうかな。例えばあなたが誰かに『ご気分
はいかがですか?』と聞かれた時に「やばいです」と答えたら、相手はとても心配すると思う。誤解されないよう、使わないほうが無難かもね」と、付け加えなければならなそうです。
歴史の中で言葉の意味合いが変化していくことがあるのは、日本語だけではありません。
プッチーニの有名なオペラ『ラ・ボヘーム』の登場人物たちはボヘミアンたちで、そもそもボヘームとはボヘミアンという意味だったことを、恥ずかしながら最近知りました。この“ボヘミアン”も、歴史の中でいくつかの意味合いの遍歴を持つ言葉です。一説にはボヘミア地方出身の人のことだと言いますし、ボヘミアに、ある時期ロマ族(ジプシー)が多く住んでいたことからロマの人々を指す言葉になり、さらに19世紀からは社会の慣習、常識にとらわれずに自由奔放に生きる芸術家気質の人々(『ラ・ボヘーム』の登場人物たちは、まさにそれです)をそう呼ぶようになったとか。
とすると、イタリアの人をイタリアンと呼びますが、ボヘミア出身者でも定職について社会の規則に従って堅実に生きている人のことはボヘミアンとは呼ばないのでしょうか。こういう単語については、先ほどの“やばい”ではありませんが、きちんと勉強してから使うようにしないと、誤解を招いてしまいそうです。
来週からボヘミアを彷徨ってきます。モーツァルトやベートーベンの理解者がどこよりも多く、シューベルトの両親もその出身者だった、ボヘミア。ヨーロッパの中でもひときわ劇的な歴史や、難解とされるチェコ語という言語、ドイツから呼ばれたビール醸造家も驚くほどの素晴らしい水質を持つその地は、“ヨーロッパの音楽院”とも呼ばれ、18世紀からは“チェコ人といえば音楽家”とも言われ続けてきました。交響詩『わが祖国』で知られるチェコの国民的大作曲家スメタナは、「チェコ人は、いつの時代もヨーロッパで最も音楽的な民族であった」と述べています。
芸術を愛する人々の気持ちを抱いて流れるヴルタヴァ(モルダウ)川に佇み、気持ちのおもむくまま街を散策し、現地の人々と触れ合い…。一時的にではありますが、“ボヘミアン”になれると思うと楽しみで仕方ありません。
ピアニストのひとり言 第792回
10数年ぶりのプラハ再訪が近づいています。少しくらいはチェコ語を勉強しようと、入門書を手に入れ勉強し始めているのですが、その難解さに驚くばかり。チェコ語はスラヴ系に属するのですが、「て、に、を、は」などの“格”によって疑問詞、形容詞、名詞はもちろん代名詞も7通りの語尾変化をするし、その名詞、形容詞や動詞も女性形、男性形、中性形、また複数か単数かによって様々に変わるので、そのうちのどれで辞書を引けばいいものやら!辞書を引けるようになるまでに、かなりの勉強を必要とするようなのです。
ある語学学者が著書の中で、「“英語ぐらいはできるように”などという声を聞くが、そう簡単に言ってもらっては困る。いくら中学校から学んでいても、英語で書かれた書物をきちんと読解したりネイティブスピーカーと対等に議論できるのと、旅行でコミュニケーションできる程度の語学力とでは大きな違いがある。前者はそう簡単に習得できるものではない」「“聞くだけで自然に身につく”とか“簡単マスター術”などと謳っている語学の本があるが、それはほぼ不可能。実際のところはある程度以上の年月をかけ、継続的かつ地道な学習が必至」と、本音?をおっしゃっているのを読んだことがあります。「一朝一夕でできるようなものではありません。どうぞそれを覚悟の上で、楽しんで学んでください」
“よりはやくできるものが高性能”…私たちはいつからかそんなような価値観の中で生きています。テストの時、誰よりも早く「できました!」と手を挙げる子に羨望の眼差しが向けられたり、内容はともかく早く暗譜できることが“すごい”とされたり、あっという間に出来上がる修理やクリーニング屋さんをサービスがいいと感じたり。ちょっと前まではフィルムカメラのプリントがその日のうちに仕上がるようになったことに驚いていたのに、今や撮ったその場で映像を見られるだけでなく、いつでもWi-FiでSNSにアップできるデジタルカメラがほとんどです。
もちろん、高性能の要素はスピードだけではありません。精密さも重要な要素で、電子頭脳や画素数、4K,8Kといった解像度もどんどんスペックが上がっています。さらにそれを薄く、小さく、軽く、省エネで…と、その進歩には目を見張るものがあります。
発注された仕事をいかに早く正確にこなせるか。『時は金なり』という考え方に基づくならばそうしたスピードや精密さは確かに重要なポイントです。人は仕事効率を上げることを求める一方で、人生においてはなるべく長い時間を謳歌したいと願っている…。そもそも時間とは、何のために与えられているのでしょう?効率を重要視しタスクを急いでこなして忙しく生きている現代人は、以前より長くなった寿命を幸せに全うしているのでしょうか。
一つ一つの音符を丁寧に読み、組み立て、構成して、表現に結びつけていく。もちろん、常に作品に対する解釈を深め、感性を磨くことを怠ることなく。幼い頃からコツコツと継続し、積み重ねてきたスキルをさらに鍛錬し、訓練しながら。
−—————そうやって創り上げられる演奏がきっと誰かの心に届くことを信じ、祈るような気持ちで日々その種子を育んでいる我々音楽家は、もしかしたら現代社会の“高性能”の基準からすると“規格外”な存在なのかもしれません。でも、本当に価値のあるもの、人の心を満たすものは、そのようにして生まれてくるものではないでしょうか。外国語の学習も似ているかもしれません。会話なら、お互いに理解しあいたい気持ちさえあれば、極端なことを言えば異国語同士でも表情やジェスチャーで最低限は通じます。でも、文学作品を理解しようとしたり、微妙なニュアンスまで味わいつくそうと思ったら話はまったく変わってきます。場合によっては言語体系を辿り、比較言語学を学ぶ必要を感じるかもしれません。
『時は金なり』…ここでいう“金”とは、言うまでもなく人にとってとても大切なものの喩えです。私はそれを、「与えられた時間を大切に活かし、感謝して生きよ」と言う意味だと受け止めています。ヨーロッパには、“自由な時間がある人=ある程度の地位に至った人”という価値観があります。ある芸能人が、ヨーロッパで人に自分が売れっ子でいかにたくさんの仕事に追われているかを伝えたところ、「今は試練の時なんだね。君にもっと自由な時間ができることを祈っているよ」と憐れまれた、という話を聞いたことがあります。
自分にはあとどれ程の時間が残されているのかはわかりませんが、心から喜びを感じ、幸せを人と分かち合えるような豊かな時間を少しずつ増やしていけたら…と、願っています。
ピアニストのひとり言 第791回
昨年末、桐朋学園時代のピアノの師匠故・林秀光先生の同門の先輩から、ある連絡をいただきました。先生の功績を讃え、それを後世に残すべく毎年行われている、門下生による“林秀光先生メモリアルコンサート”に出演してもらいたい、というお話でした。
出演者は私の他に2名。お二人とも国内外の名だたるコンクールで優勝され、演奏活動を続けながらも音楽大学で後進の指導にもあたっていらっしゃる素晴らしいピアニスト。ご一緒にコンサートを作っていけると思うととても楽しみで、何を弾いたらいいものかとあれこれ思案を重ねていました。
そんな折、そのコンサートの引き継ぎを兼ねた打ち合わせがありました。久しぶりにお会いする先生の奥様はお変わりなくとても生き生きとしたご様子で、ソプラノ歌手らしい華やかなオーラを身に纏っていらっしゃいました。先輩方も後輩たちも皆さん揃って素敵な方ばかり。改めて林先生の門下生だったことを誇らしく思いました。
このメモリアルコンサートは、先生がお亡くなりになった数ヶ月後に行われた追悼コンサートの折に、皆様からお寄せいただいた寄付金などの収益金を、奥様が私たち門下生のためになる何かに有意義に使ってください、とお申し出になってスタートしたものだと知りました。「だってそれは秀光さんのお金、彼の財産だもの。私は使えないわ」
林先生の葬儀で、奥様が喪主としてお話になったあるエピソードは、とても印象的でした。「主人は本当に勉強熱心な人で、いつもピアノのことばかり考え、少しの時間も惜しんでピアノに向かっていました。練習の途中、レッスン室から『いい指使いが見つかったよ!』と私に伝えに出てくる時などは、子供のように嬉しそうな様子でした」
小澤征爾さんも弔辞の中で「ヒデミっちゃんは、僕なんかみたいなどこの馬の骨だかわからないようなのと違ってきちんとしていて、すごく真面目で。悪い誘いをしても、『いや、僕は練習があるから、ちょっと…』なぁんて、いつも断られちゃったよなぁ」と、まるで先生ご本人に語りかけるように親しげにお話になって、会場に詰めかけた数百人の弔問客の泣き笑いを誘いました。
先生のレッスンはとても厳しく、「怒号が飛ぶ」とか、「林先生のレッスン室の遥か遠くから、怒鳴り声が聞こえる」という“伝説”も学生の間でよく知られていましたが、実のところは大変に生徒思いの方でした。そのお声に熱がこもって強い物言いになったとしても、それが真剣な、音楽や生徒への愛情によるものだと、門下生はみんなわかっていました。ですから、どんなに怒られても落ち込むことはなく、レッスン室を出るときは「よし、もっと頑張るぞ!」という気持ちが身体中に満ちていたものです。
「今度のフェルクスニーのリサイタル、行くの?」あるレッスンの後、先生に尋ねられました。「いいえ。同じ日のアシュケナージの協奏曲の夕べに行く予定で、そちらのチケットを買いました」「いや。それよりフェルクスニーの方に行きなさい。素晴らしいから。アシュケナージはいつでも聴ける」有無を言わさぬ語調でした。
フェルクスニーはチェコを代表する名ピアニスト。当時70代でしたので確かに最後の来日になる可能性もありました。私は先生の言いつけに従って彼のリサイタルに行ったのですが、そこで思いもかけないことが起こったのです。
前半の最後にしてこの日のプログラムのメインは、シューマンの『幻想曲』でした。特に、“星の冠”というサブタイトルがつけられた終楽章は、聴いたこともないほどに深く、幻想的にして温かな演奏でした。私はあまりの感動に泣くことも忘れて無心で聴き入っていたのでしょう、休憩時間に入った途端、気が緩んだのか大泣きしまったのです。
打ち合わせで、奥様、同門の皆さんとお話ししながら、そんな林先生とのやりとりやフェルクスニーのリサイタルでの出来事を思い出していました。そしてその翌朝、目が覚めたと同時に誰かの声が聞こえたのです。「美奈子、林先生のコンサートでシューマンの幻想曲を弾きなさい」。
早速楽譜を取り出してみました。ところどころに林先生による書き込みが残っていました。裏表紙には、“桐朋学園大学音楽学部 鈴木美奈子 1985年6月3日”とサインがありました。当時の私の筆跡が、「また林先生にこの作品を聴いていただけるね。よかったね」と、今の私に語りかけているようでした。
ピアニストのひとり言 第790回
「美奈子ちゃん、ついに写真家の道も歩み始めたの?」友人にそうからかわれるほど、このところ写真に夢中になっています。撮る方ももちろん楽しいのですが、写真家の作品を観はじめたらそれがまたとてもおもしろく、まるで小学生の時にショパンのピアノ曲に魅せられて全ての作品を聴き尽くしたくなったのと同じくらい、あれこれと観てみたくなって仕方ないのです。そして、観るたびそのあまりの見事さにため息をついたり、唸ったり。
一人の写真家を知ると、彼が影響を受けた他の写真家の作品も観てみたくなりますし、それぞれの方のバイオグラフィー…どんな生涯を送った方なのか…も知りたくなる。その作品はその方の人生のどの年代に、どんなカメラで撮られたのかも気になってくる、といった具合で、興味は泉のように尽きません。
最初に“はまった”きっかけは、新宿の某大型書店でたまたま手に取った外国人フォトグラファーによる日本の写真集でした。外国人からみたNIPPONの断章には、それらを当たり前のように目にしている私たちとは異なる捉え方が感動とともに息づいていて、まるで知らない国の街角や風物を見せてもらっているような新鮮さがありました。そして、その視点の向こうに撮り手の感動が感じられた時、嬉しいような誇らしいような気持ちになったと同時に、一つのことが頭に浮かんだのです。「そうか。外国人であるわたしが西洋の音楽を解釈したり弾いたりするときも、彼らとは違う国に生まれた自分の感覚を否定するのではなく、むしろ生かして、唯一無二の表現をめざせばいいのだ」と。
音楽に対してだけではありません。最近知ったある写真家の方からは、人生に対しての示唆をもらっています。マイケル・ケンナというイギリス人写真家なのですが、彼との幸せな出会い(一方的な、ですが)を友人に伝えたところ、「彼の写真集、持っているわよ。実はご本人にもお会いしてサインをもらったこともあるの。もう10年くらい前だけど」とのこと。彼女も同じように、ケンナ氏から生きるヒントや感動を受け取った一人だったのです。
「これは私と感性の近い我が生徒さんたちも、きっと何かいいものを感じとるに違いない!」…早速写真集を手に入れ、レッスン室に無造作に置きました。すると、目にした方は決まってその表紙に「あ!」と、私と同じように釘付けになるのです。「先生、これ…少し見せていただいてもいいですか?」「え
え、もちろんです」そのあとはしばらく、写真談義に。ピアノのレッスンからは離れるようにみえますが、なかなかどうして、そうしたセッションの後は皆さんなぜか力が抜け、いい雰囲気でのびのびと弾いてくださるのです。
先日生徒のAさんに、「ケンナさん、北海道の屈斜路湖のとある木を、それも一番雪深い時期に、毎年のように撮影にいらしていたこともあるそうですよ」とお伝えしたら「え?屈斜路湖…私、すぐそばに数年間住んでいて、しょっちゅう出かけていました!どの木かしら…」と驚いたご様子。その写真をお見せしたら「うわぁ…素晴らしい。こんなふうに見えるなんて」と、たいそう感激なさっていました。
また、別の生徒Bさんは、その木の倒れかかった、枯れたような姿をみて、言葉を選ぶようにゆっくりおっしゃいました。「この木は…彼のお母さんなんですね。会うたびに老いて、腰も曲がって、枝も寂しくなって。でも、その姿が、彼には愛おしいんですね。そんなふうに心から“愛しい”“大切”と思うものがあるって、なんて幸せな人生でしょう!美奈子先生にとっての音楽も、そう。人として生まれてきた全ての幸せがそこにあるように思います。そしてわたしも、人生の最後の方にこんな素晴らしい芸術の世界を知ることができて、本当に幸せ」
彼女の話を聞きながら、感謝で胸がいっぱいになりました。目には涙が浮かんでいたかもしれません。屈斜路湖の木の撮影に際してケンナ氏が話していたことが、頭に浮かびました。「雪靴を履いて2〜3時間も歩く。やがて天候が変わり、何かが見えたり見えなくなったりする。でも、そのすべてが必要なのだ。そんなふうに生きていたい」彼はまた、こんなことも言っていました。「写真には予測できないこと、コントロールできないことがある。だから、いい。私が求めるのは、一種の不完全さなのです」
人生も同じなのです。予測できないし、コントロールもできない。それを、情熱を持って味わいつくすことこそが人生の醍醐味なのだ。…彼は写真をとおして、そんなメッセージを届けてくれているようにも感じます。
「苦しみは、幸せのため。苦しみと幸せは、手のひらの裏表だと思うんです。両方大切なのではないかと」Bさんの言葉が、心の中で微笑んでいます。
ピアニストのひとり言 第789回
「生きているって素晴らしい」…と、人生観が変わるような出会いというとたいそう特別なことに思われるかもしれませんが、案外世の中はそういうものに溢れているのかもしれません。様々な経験を重ねることがそうしたものと巡り会うチャンスにつながるとしたら、生きることはもっともっと楽しくなりそうです。
実は、ハンガリーに留学した当時は、恥ずかしながら“名画と言われているものの何がそんなに素晴らしいのか”、はっきりわかっていませんでした。
リスト音楽院の学生として留学すると、医療費はもちろんコンサート入場料が免除になるという優遇があったのですが、美術館までもが無料になるのには驚きました。日本では考えられないほどじっくりと芸術の勉強に集中できる環境に、感謝しない日はありませんでした。しかも、コンサートの帰りに、まさに金のネックレスのようにキラキラ輝きながらドナウ川にかかる鎖橋や、その向こうにライトアップされたブダの丘の王宮を見るにつけ、その美しさとヨーロッパの中心にいるのだという実感に、涙が出そうな感動を覚えたのでした。
「美しい芸術をたくさん観なさい。できればフィレンツェにも行ってみてほしいところだけど、国立西洋美術館にもたくさんのいい絵があるから、よかったらこのあと行ってみてごらん」ある日、室内楽のレッスンでシャンドール・デイヴィチ先生にそう教えられ、早速向かいました。リスト音楽院からそこまでは、ヨーロッパ大陸最古と言われるレトロな地下鉄に乗って四駅目。短い区間をちょこちょこ止まる路線なので、歩けないこともない距離でした。
英雄広場という観光名所の一角にあるその建物は、アテネのパルテノン神殿のような堂々たる佇まい。入り口で、本当に無料で入れてくれるのかちょっと不安を覚えながら学生証を見せると、それまでしかめつら(失礼!)をしていた受付係りのご婦人はふと温かな笑顔になって、「どうぞ、お嬢さん」と促してくれました。
館内はほとんど人の姿がなく、絵にはこれといった柵も何もありません。無造作に壁にかけられた絵を一つ一つ気のすむまで眺めていると、これらが自分の
コレクションのような錯覚に陥り、なんとも贅沢な気持ちになりました。ハプスブルク家のコレクションが元になっているだけあって、レンブラントやルーベンス、ベラスケスやエル・グレコなど、錚々たる画家の作品が並んでいます。これらを、観たいときにいつでも(しかも無料で)観られるなんて、すごい!「まるでハプスブルク家の令嬢みたい!」“お嬢さん”は興奮を抑えつつ、心の中で叫んだのでした。
「あ!」ある絵の前にきた時、心の中にとどまらず思わず小さな声をあげてしまいました。ラファエロの聖母子像でした。今思うと、後にフィレンツェなどで観たものに比べると決して良い出来栄えの作品ではなかったのですが、それでも聖母マリアの母性にみちた表情や身に纏ったローヴの美しいブルーを見た瞬間、身震いがしました。実物以外からは決して得られないであろう感動に、そのまましばらく体がフリーズしてしまいました。
まるで、それを描いているラファエロと今の自分が、目に見えないタイムマシーンで繋がったような感覚に襲われたのです。少しカビ臭いような古い石の家の匂い、溶かした絵の具の匂いまでもが感じられたような気がしました。
「本物の芸術は生きている。それは生き続けるものなのだ」そう確信して帰ったのを覚えています。そして、情熱をもって駆け抜けた生涯の中で創り出された、苦しみも悲しみもその中に昇華しているそれらの作品からなんらかのメッセージを受け取ると、彼らと私たちは時空を超えてつながっているように感じることがわかりました。
以来、心を奪われるような演奏に触れた時も、しばしば同じようなことが起こりました。あたかも作曲者が目の前で語りかけてくれているような、自由に好きな場所、好きな時代に遊ばせてもらっているような感じがするのです。
絵画だけではありません。建造物や文学、舞台芸術、大自然のランドスケープや風景写真…素晴らしいものに触れると、楽器に向かって練習しているだけでは得られない芸術の本質や力、懐の深さを感じ、そこから大事な示唆を得ることができます。時には人生観が変わるような、輝かしく雄大な世界に誘われることもあります。
「生きているって素晴らしい」…人間にそう感じさせてくれる、人生に欠かせないものの一つが、芸術であるような気がしています。
ピアニストのひとり言 第788回
先日、自宅に友人をお招きしての食事会がありました。今回のテーマは“ロシア(の食卓から)愛を込めて @美奈亭”。
ゲストはもう10年以上のお付き合いになる大切な友人たち…しかも食のプロばかり??ありったけの愛を込めて、ロシアのダーチャ(田舎の別荘)の食卓にお招きするイメージで、この季節に彼の地で収穫される食材でロシア各地の郷土料理を構成してみました。
最小限の台所道具しかないダーチャを想定して、くるみのペースト作りはすり鉢とすりこぎで…野菜の千切りもスライサーを使わずすべて手作業で。同じ千切りもスライサーと手で行うのとで、違う食感になるのは面白いことです。
お品書きは、
ロールキャベツって、じつは包むキャベツの状態をいかに整えるかで味わいも微妙に変わるのです。今回は茹でたキャベツの芯を刮ぎ、めん棒で優しくたたいて厚みをならしてからナチンカ(具)を包みました。削いだ芯には甘みがあるので、それも刻んで具に加えます…すると、ひとくち食べたシェフから「ロールキャベツは芯が強く口に当たると感じることが多いのに…これはどうやって?」と、すかさず突っ込みが。そんな些細なことに瞬時に気づくなんて、プロってすごい。改めて尊敬しました。
たとえできないことや足りないものがあっても、努力や工夫を重ねていけば、周りに幸せを与えうる。…料理をしながらそんなことが感じられ、ふと、芸術家の使命はそれを身をもって実証することなのではないかしら、と思いました。
一歳で孤児になったラファエロの描く聖母の眼差しの優しさ。荘厳で美しい音の喜びに満ちた、聴覚を失ったベートーヴェンの音楽。ーーー素晴らしい芸術家たちは自身の境遇や状態を決して言い訳にせず、むしろそれらもすべて作品に昇華させ、私たちに届け続けてくれます。人種や宗教を超えた大きな愛を感じずにはいられません。
■第787回 信念を人生の糧に、感動を心の栄養に
今回も、年末年始に帰省した折に中学時代や高校時代の同窓生たちと会い、ゆっくり親交を温めあう時間を持つことができました。幸せなことです。
その中には、30数年ぶりの再会を果たせた中学時代の友人Tちゃんもいました。全くと言っていいほどその面影も話し方も変わっていなかったのは、とても嬉しい驚きでした。しかも、中学生だった当時お付き合いをしていた男性(もちろん私も知っている方です)とそのまま結婚し、育て上げた息子さんは立派に所帯を持ってお嫁さんが昨年出産。Tちゃんはめでたく“おばあさん”になったというのです。まるでおとぎ話を聞いているような気持ちになってしまいました。何より素敵だと思ったのは、私の目の前にいる彼女がキラキラと幸せな笑顔で輝いていることでした。
写真に興味を持つようになり、以前に比べて色々な写真家の方の作品も拝見するようになったのですが、心惹かれる作品を撮る方には共通する何かがあると感じていました。しかも、どうやらそれは、私が心惹かれている音楽家にも通じるものなのです。その正体は一体何なのか、ずっと気になっていたのですが、Tちゃんと話していてふと、気づきました。
彼らには皆、迷いがないのです。いいえ、人間なのですから全く迷いがないわけはないでしょう。でも、その作品や演奏からは、「これをこう撮る」「これはこう弾く」「これを伝えたい」ひいては「私はこう生きる」といった強い意思や信念が感じられるのです。迷いよりも信念の方がずっと大きく、それを年齢とともにさらに進化させながら伸びやかに生きている印象です。彼らは周囲をも幸せにするパワーを放つことができ、私が心惹かれている人たちは皆、それを持っているのです。
きっとその信念は、幾多の失敗や挫折を経て、いつしか強固なものに育っていったのでしょう。
感動という言葉があります。実はある時期、あまりその言葉が好きになれませんでした。その頃、人と同じように感動をともにできないと、取り残されたような気持ちになることが重なったからかもしれません。
そもそも感動とは“心が大きく動く”ことであって、何にどのくらい動くかはとてもパーソナルなものだと思います。しかも、それは何もポジティヴなものだけに限らないのではないでしょうか。深い悲しみに襲われて涙するのもまごうことなき感動の一種でしょうし、怒りも、それを克服し乗り越えるための尊い試練だったりします。悲しみも苦しみ、嫉妬や怒りも、人の心と響きあい、自分と向きあい、自らが成長するために大切な“心の動き”で、喜びや楽しみだけが人生をプラスに導く感情ではないと思うのです。
確かに、憎しみの感情は人を傷つけます。でも、本当に憎しみの感情は悪者なのでしょうか?誰かを憎まなくてはならなくなってしまった理由や必然がどこにあるのか…。憎しみの感情から目をそらさず、きちんとその根っこを見出すことが大切なのではないでしょうか。というのも、どうも“憎んでいる人”は“憎まれている人”よりも傷ついているようにみえて仕方がないのです。本当は、誰もそのような感情に支配されていたくはないはずです。
いずれにせよ、大切なのは“心が動く”ということ。もし憎しみの感情に襲われそうになっても、「私はこう生きる」という信念があれば、心の支えになってくれることでしょう。それどころか、様々な出来事、感情を心の糧にするための消化酵素のような働きもしてくれるかもしれません。
甘さや柔らかさだけでなく、苦みや酸味も体に大事な栄養をもたらす味わいであるように、どんな感情の動きも信念をもってすれば感動につながり、心の栄養になる。なにも嫌うことはないのです。
余計なことにとらわれないかわりに、何が大切なのかを見据え、マイナスの感情も受け入れてプラスに転じさせる力を持つ人こそ、周囲に幸せをもたらすことができる“才能豊かな人”の正体なのではないでしょうか。
「その瞳の奥には信念が、その瞳の先には希望がある」…家族の話をしているTちゃんに見とれていたら、ふとそんな言葉が思い浮かびました。彼女に少しでも近づくことができる一年にしたいものです。
■第786回 カメラとの対話
自分の練習や勉強、生徒さんのレッスンや、こうした執筆作業などの仕事はほとんど自宅ですることが多いので、近くでもいいから外に出てぶらぶらお散歩したり、ウィンドウショッピングしたりすることは、いい気晴らしになります。そんなふうにひとりで気ままに歩く時間のいい相棒が、カメラです。
スマートフォンの素晴らしいカメラ機能のおかげで(レンズのF値が2を切っているものも!)、わざわざカメラを持ち出さなくても気の向くまま撮影を楽しむことができるのは、とてもありがたいことです。昨年のハンガリー、オーストリア旅行の折には、ついにカメラを持たずに出かけて全ての撮影はスマートフォンだけで済ませてしまったほど、その性能には信頼を寄せていました。
でも、“寄せていました”なのです。それはもう、過去形になってしまったのです。きっかけは、カメラのお好きな知人にライカのカメラをお借りしたことでした。
今回お借りしたのは、ライカの中で最も小さいデジタルカメラ。企画、デザインこそライカのものですが中身は日本のパナソニック製だし、センサーも大きくない(というより、小さい方)…という知識は持っていましたので、正直なところさほど期待はしてはいませんでした。第一、撮る人は変わらないのだし、その撮る人はほとんど写真の知識もなく、プログラムオートで使うことしかできないのに、そんなに違いがわかるとは思えなかったのです。
ところが、いざ撮影してみるとその自然な色のりや階調、ぼけ味にびっくり。写真の表情のようなものがまるで違うのです。自分が、実は鮮やか過ぎる色味やフィルター加工されすぎた写真に疲れていたことや、見たままの色や素材感がそのまま再現されるという基本的なスキルの大切さ、なんでもない被写体も光や撮り方によってとても趣のある一枚になりうることなどがわかって、まさに目から鱗でした。
ライカに限らず、やはりカメラはカメラ。その機能に特化して開発された製品の描写力と、マルチな“カメラ付き端末”のそれとでは、やはり大人と子供の違いがあるように感じました。もちろん、綺麗な写真ならスマートフォンでもい
くらでも撮影できますし、さまざまな加工も思いのままですが、愛着を抱いているものを手にしている満足感や、ファインダーをのぞいた時の感動までもがその写真に写りこんでいるような一枚をみると、思わず“う〜ん”と唸ってしまいます。
ひとつの被写体も、光の絞り方、構図の撮り方、画角の切り出し方などでまったく違う印象に表現されるところには、ひとつの楽譜も弾き手の解釈によってさまざまに聴こえるクラシック音楽と、近いものを感じます。となると、それを伝える道具である楽器がそうであるように、カメラの選び方が大事であることは言わずもがなです。
興味を持ってあれこれと写真集や作例などをみるようになって、少しずつモノクロ写真の面白さがわかってきたのも、楽しいことです。色がないぶん、素材感や構図、光やコントラストなど“色以外の要素”が研ぎ澄まされたように際立つところが、その味わいの深さ、面白さなのではないでしょうか。
ライカでモノクロの写真を撮り続けているあるカメラマンが“モノクロ写真には本当に色がないのだろうか?(中略)モノクロ写真の「色」は、人の心の中で現像されるのかもしれない。それは想像力に委ねられていて、その想像力の可能性に限りはない”というようなことを書いていらしたけど、それは水墨画にも通じる美学かもしれません。
撮影して気づいたことの一つに、ファインダーや液晶のプレビューを見ながら角度や光をあれこれ動かして、最良と思われるショットにたどり着くまでの時間、無心になれることがあります。画を“切り出す”一瞬に向けてのある一定の時間が、止まっているように感じるのです。街の騒音や慌ただしさが消え、フッと無音の世界に入り込んだような気がする時もあります。音に向き合い、音の世界に生きている身としては、とても新鮮な瞬間です。
本当は、シャッターを切るそんな瞬間だけが特別なのではないのです。毎日毎日がそんな特別な時間の積み重ねなのではないでしょうか。“今日”があることに感謝しながら、心穏やかに新しい年を迎えたいと思っています。
■第785回 自由なエヴァンゲリスト
「先日Yさんをお見かけした時、いつもに増してきれいに見えたので、つい“どこからのお帰り?”って尋ねたんです。そうしたら、“今、美奈子先生のレッスンだったのよ”とおっしゃったの。その時のYさんのお顔がとても輝いていらしたので、ああ、いい時間を過ごしていらしたんだなぁって、羨ましいような気持ちになりました」
今年最後の『大人のための音楽講座』終了後のティータイムでそうおっしゃったIさんは、母と同い年のご婦人です。Iさんによって受講生の皆さんの前で話題の中心になったYさんは、しきりに照れて「まぁ、Iさんたら。いやだわ」と、お隣のIさんの肩を叩くふりをなさいながらも、頬を赤らめて少女のようです。年齢など関係なく楽しい会話に花が咲くのは、音楽仲間というつながりがもたらしてくれるご利益でしょうか。
そんなティータイムだけでなく、レッスンももちろん楽しい時間です。何より嬉しいのは、生徒さんが音楽との関わりをとおして人生を輝かせていること。あるレッスンでは、難しい10度のレガートを美しくマスターされて、「ほら、ね。私、こんなにできるようになったんですよ。そのうち美奈子先生を超えちゃうかも!」と、そこを弾きながらはしゃぐ生徒さんに「まあ、本当!どうしましょう!」と、驚いてみせて二人で大笑いしたり、「感激して涙が出るほど幸せ気持ちになった出来事があったので主人に話したら、ひとこと“へ〜、そう”って。“へ〜、そう”でおしまい(と、二回強調)。ちっとも話題が広がらないんです。つまらないわ〜」なんて話題に、あはは、と爆笑したり。
でも、そんな屈託のない会話の中にも、良い演奏に導かれるきっかけが潜んでいたりするのが、音楽の面白いところなのです。心をすっかりひらき、余計な壁が取り払われてすっかりリラックスできていると、感じたことをそのまま誰かに話すようにピアノを弾くことに繋がりやすいのです。
「以前は自分の無能さにコンプレックスがあったんです。でも、それが美奈子先生に出会ってピアノを始めてから、どんどん変わっていって、だんだん自分が自分であることの幸せを感じられるようになったんです。これまで本当に辛いことばかりだった人生のおしまいの方に、こんな心豊かな日々が用意されていたなんて、思いもしませんでした。今はなんでもない毎日に、とても感謝し
ているんです」生徒さんが自らご自身の状態をお話くださると、目の前に気持ちのいい道が悠然とどこまでも広がっているようで、私まで嬉しくなります。
「それは、Yさんがもともとそう感じることのできる才能をお持ちだったということではないかしら。音楽がそれを開花させるきっかけになったんですね。私、この頃思うんです。どんなことをも受け入れ、それを心から感謝できるって、どんな能力や財産にも勝る素晴らしい“人間としての才能”だって」「ええ、ええ、本当ですね。財産がいくらあったって、そういう気持ちがなかったらどんなに寂しいことかしら」Yさんは浅丘ルリ子さんのような大きな瞳で私を見つめ、真剣な表情でそう答えてくれました。「そうすると私たち、音楽に感謝しながら生きている幸せな仲間、ってことですね」「そうですよね、ああよかった!」と、ここでまた大笑い。
時には、「美奈子先生の、音楽に対する清らかな姿勢が好きなんです。だから、ずっと弾いていてくださいね。そして、ずっと教えてくださいね」と、逆に励まされたり、「音楽に関しては妥協を許さないし、何もかもに精通して完璧な女性に見えるけど、きっとお母様の前では甘えん坊で、お母様にとってはいつまでたっても心配な娘なのではないかしら」「美奈子先生って、いつまでも子供のままで大人になりきれないところがあるって、そこが可愛いの。私わかっちゃったんです!」など、鋭く分析されてしまうことも。そんな時には改めて、音楽や演奏によるコミュニケーションの持つ力って未知数なのだと思い知らされます。
コンサートでもそうですが、音楽を媒体にして人と人の心がつながり、そこに温かな幸せの連鎖が生まれてみなさんの笑顔が広がると、もう嬉しくて仕方ありません。混乱と困難の世の中だからこそ、どんな人の個性も受け入れて誰も傷つけることのない“音楽”という美しい果実を皆で囲み、愛で、味わい、そこから生きる希望をもらって、全ての幸せも苦しみも皆で分かちあって生きていけるようになったら、どんなに素晴らしいことでしょう。
“音楽家とは自由なエヴァンゲリスト(福音史家、伝道者)である”とは誰の言葉だったでしょうか。いや、もしかすると、いつかの夢の中で聞こえてきた神様からの啓示だったのかもしれません。
■第784回 自然とのコラボレーション
スーパーマーケットの店頭にお正月のしめ飾りや鏡餅が並ぶこの季節になると、あるご婦人のお姿とその穏やかなお声を思い出します。仙台に住んでいた頃にみていた、近所のピアノの生徒さんのおばあさまです。
「福島の実家の庭にたくさん実るので、毎年送ってくるんですのよ」と、毎年この時期になると、きまって袋いっぱいの柚子を持ってきてくださいました。紅白のなますやお雑煮の香りづけなど、お正月の料理に欠かさない柚子。母は「このタイミングにいただけるって本当にありがたいわ。すごく助かるわ」と、いつもたいそう喜んでいました。
さて、私の生徒さん…彼女のお孫さんにあたる二人の男の子たち…は、どちらかというとピアノよりも外で遊ぶ方が好きな、とても元気のいい子供たちでしたが、たとえ練習してこなくても会うのが楽しみになってしまう魅力の持ち主でした。長男のDくんは弟思いで、何かと弟をフォローしてあげる姿はなんとも微笑ましいものでした。弾きにくそうにしているところを弾きやすくなる指づかいを教えると、「おお〜、なるほど!よーし、頑張るぞ??」と、小さくガッツポーズをして弾き直すも、そうそう簡単にはいかなかったりするとがっくり肩を落としたりして、素直なことこの上ないのです(私はその傍らで、何度笑いだしたくなるのをこらえたことでしょう!)。お月謝袋には決まって指が切れるほどの新札がピシッと揃って入っていて、「きっとおばあさまのお気遣いだわ」と、感服していました。
すっかり立派な青年になったDくんがひょっこり挨拶に来てくれたのは、何年前のことだったでしょうか。小学校の先生になったと報告してくれました。一人前に「美奈子先生に教えていただいたピアノが、音楽の授業の役に立っています」なんて言ってくれたっけ。
「八丈島から送ってきたんです」今日レッスンにいらしたIさんから差し出されたのは、普通の三倍もあろうかという大きさの見事なレモンでした。それは無農薬栽培とは思えないほどに美しく、たいへんな愛情を注いで作られたのが一目でわかる“作品”でした。「島から届いた荷物を開けた瞬間、都会のくすんだ空気や、今抱えている過労死とか自殺とか…いろいろな問題とは無縁の、何やらとても健やかな“氣”のようなものを受け止めたような気がしたんです。気の
せいかもしれませんが」と、Iさん。仙台から父の作った野菜が送られてきた時、同じように感じた経験がある私は、「いえ、気のせいじゃないと思います。人間だって動物なんですもの、そういうものを感じる力があるはずです。そうだ、今日はこのレモンを傍らに置いて弾きましょう。いいインスピレーションが得られますよ、きっと!」と言い置いて、レモンを飾るのにちょうどいい和食器を取りにいそいそとキッチンに行きました。
果たして、Iさんの弾いたフォーレはいつもに増して素敵でした。北のほうでは雪が舞っているこの季節に、黄金色に輝くその果実は、どんなにきらびやかなクリスマスのオーナメントよりも誇り高く、何か大切なことを伝えようとしいるようにもみえました。「歴史的な建物や街並みを世界遺産と崇め奉るのもいいけど、こういう安全な農産物や海産物こそ、皆で大切に守っていく意識が欲しいですよね。だって、それらは自然や環境が壊れてしまったら真っ先に崩れてしまうものなんですもの。特に、農作物は自然と人間の一期一会のコラボレーションから生まれる芸術のようなものだと感じることがあるんです。その土地の土壌、気候、そして作り手の情熱や知恵…そういうものが一つの作品に実を結んでいるのだ、と。演奏もそうあるといいのではないかしら。どういうレモンが立派なのかという基準に従って、安定性の高いものを作るばかりではつまらない。Iさんらしい、唯一無二のものを目指しましょうよ」
フォーレの生まれたピレネー山脈の近くのパミエという街の話をしながら、フォーレのノクターンをワークします。そして、「ここは、ただピレネーからの風の音に心を奪われているだけ」「ここで、その風の向きが変わる予感が…でもまだ“確信”ではないの」そんなことを話したり、時折弾いてみせたりしながらイメージを実際の音にしていきます。これは、農夫が作物の収穫を明確にイメージしながら、その時々の日照や降水量、気温などを配慮して、必要なことを施しながら育てあげていく過程と、それほど違わないのではないか…ふと、そんな思いが頭をよぎりました。
さまざまな情報がその遺伝子に精緻に組み込まれた“譜面”という種子を発芽させ、そこから命を紡ぎだし、人の体に、心に、届ける。それがその人にとって良い“栄養”になることを願いながら…。それが演奏という行為だとしたら、私はなんと幸せな任務に恵まれていることか。
頂いたレモンを眺めていたら、Dくんのおばあさまを思い出しました。実家に柚子が届けられることがなくなって、どのくらいになるでしょう。レモンの美しい黄色が、いっそう眩しくみえました。
■第783回 創造と犠牲と美の関係
“音楽にはすごい力が隠されている。音楽も絵画も小説や詩も、それはみな、美しいものに触れたいと願う心の表れだ。この世に苦しみが満ちれば満ちるほど、人はただひと時でも美しいものに触れたいと思う。美しいものは国境や民族を越え、時間さえ越えることができる”ある方にお借りした山本おさむ氏による作品『天上の弦』を読んでいたら、こんなフレーズに出会いました。
『天上の弦』は、実在の弦楽器製作者をモデルとしたノンフィクション(*山本氏が一部脚色を加えています)作品。これはその中で、在日朝鮮人の少年が激動の時代に偶然ヴァイオリンという楽器と出会い、その圧倒的な美しさに魅せられた時、彼の恩師に言われた言葉です。少年はやがて楽器作りの職人を目指すようになるのですが、国籍がネックになって大変な苦労をすることになります。でも、どんなことがあっても情熱と夢を失わず、数々の困難を乗り越え、最終的にはフィラデルフィアで行われた弦楽器の製作者コンクールで、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの各部門で金賞に輝くまでが描かれています。
情熱が美しさに一心に向けられるとき、芸術がうまれます。つまるところ、この世では美しいものがいちばん強いのかもしれません。でも、本当の「美」、真の「美しさ」とは何なのでしょう。
最近ファッション雑誌『Vogue(ヴォーグ)』に掲載されたレスリングの吉田沙保里選手が、とても美しいと話題になっています。もともと魅力的な方ですし、一流のスタイリストさんとメイクさんの手によって磨き抜かれ、その道のプロ中のプロであるカメラマンによって撮影されたその姿は確かに綺麗だと思いましたが、試合でたたかっている彼女の美しさは、まったく別の次元のものだとも感じました。彼女の試合をみて感動のあまり泣いたことは何度もありましたが、この写真をみて涙は溢れませんでした。
“綺麗”と“美しい”は違う、ということなのでしょうか。
“綺麗”は心地よく麗しいようすのことですが、“美”には羊がいます。大いなる羊です。
自分の名前は嫌いではないのですが、習字で名前を書かなければならない時はいつも憂鬱でした。“奈”や“子”はまだいいのですが、“美”という字がどうしてもうまく書けないのです。“羊”の部分で横線が潰れてしまったり、その下の“大”の左右のはらいが不恰好になったり、と、なかなかバランスが取れないのです。その姿はどう見てもちっとも“美”しくはなく、情けない出来上がりをしみじみ眺めてはいつもため息をついてしまいました。
でも、“羊”と“大”の組み合わせにはきちんと意味があったのです。羊は古代から宗教的祭式において捧げ物とされていたことから犠牲の動物とされ、“美”とは人の道におけるもっとも尊い犠牲という行い…“大いなる犠牲(自己犠牲)”である、ということだ、とも考えられているとか。
真の美とは、表面的な綺麗さ、きれいごととはまったく違うものでしょう。本当に美しい音楽を創造するのは、とてつもなく大変なことなのだ…と、打ちのめされる思いでいたら、読みかけの本(河合隼雄著『こころの処方箋』)の最終章にこんなことが書かれていました。
“私が大切にしているのは、その人の生き方全体の創造であり、「私が生きた」と言えるような人生をつくり出すことなのである。創造には犠牲がつきもので、そこには何らかの犠牲が生じるだろう。そのことも明確に意識し、そのような犠牲の責任者としての自覚をもって「私が生きた」と言えることが必要である。「私が生きた」という実感をもったとき、それはいつ誰によっても奪われることのないものであることは明らかで「創造」の実感も伴うはずである。それが明確なものになればなるほど一般的な社会的評価はそれほど気にならなくなるし、それはもっともっと普遍的な存在の一部としての責任を果たしたという自己評価につながってゆくだろう”。
創造、犠牲、そして、美…。いま、三つのことばが心のなかをぐるぐる回っています。それらがどっしりとした三位一体を成したとき、わたしも少し成長できるのかもしれません。
■第782回 アドベントのかわりに
12月が近づいてきました。西洋ではそろそろクリスマス前の4週間“アドベント”の時期に入ります。この頃になると来年の手帳を選ぶのが楽しみなのですが、それが終わるといよいよ年賀状をどうするか気になり始めます。
年賀状の他の年末の大仕事というと、大掃除でしょうか。これは案外、年賀状より楽しみだったりします。大掃除の日にはピアノを弾かず(たくさんの水仕事や腕を酷使した後にピアノを弾くと、どうも感覚が掴みにくいのです)、練習はお休みにしてしまうので、家にいながらにしてちょっとした“非日常”が味わえますし、いつもは手が回らないところを綺麗にすることで気持ちが晴れて、いいストレス発散になったりもするようです。
とはいえ、さほど特別なことをするわけではありません。いつもと違うのは、掃除をお芝居のように第1部から第3部まで、三つに分けること。第1部は“縦”の部。壁やドア、窓、棚や家電製品などの縦の面を拭き掃除するのです。壁やドアは床ほど頻繁には掃除しないので(私の場合ですが)、綺麗になるとかなり達成感を味わえます。ちょっと勢いをつけたい第1部にはぴったりです。
となると、第2部はもちろん“横”の部ということになります。床を中心に、本棚や窓のサッシなどの細かいところもちょこちょこと掃除の手を入れます。狭いマンションなのでたいして面積は多くはないのですが、ベランダや玄関など、外につながるところもお清めする気持ちで行うと、これまたなかなか気持ちのいいものです。
さて、注目の第3部はいかに?…正解は、第三部なだけに“3D”の部。照明器具や換気扇など、立体のものがそのターゲット。お風呂も変形立方体とみなされ、このカテゴリーに入ります。もちろん、大切なピアノも。いかに綺麗にするかの完成度や完璧さは追求せず、「一年間ありがとう」という感謝を込めて“手当て”する気持ちを大切に行います。
掃除は特に好きではないし、家事全般に別段熱心ではないのですが、そんなふうに感謝の気持ちをもって身の回りのものに触れることは、何かしら意味のあることのような気がしています。一人暮らしですし、普段は心地よさを重視して多少の生活感は気にせずのんびりと暮らしていますが、一つだけ決めている日課があります。それは、キッチンだけはその日の汚れを残さず、清めてから休むことです。
生きることは食べること。人間の心と体の健康にとって、毎日美味しく気分良く食事をすることは何より大切だと考えているので、命を司る台所はなるべくさっぱりと片付け、労ってから就寝したいと思っています。とは言っても、大したことはしないのです。シンクの洗い物は残さず洗い、コンロには何も乗っていない状態にして、床を軽く拭きあげておしまい。習慣になってしまえばお化粧を落とすのと同じ感覚で、なんということはありません。それどころか、もともと洗い物を苦だと思ったことはないので、むしろ寝る前の台所の“お手入れ”は楽しみの一つになっています。
子供の頃から、毎日食事が終わると母と妹と3人で後片付けをするのが“習わし”でした(年夏年始やお盆など、実家に3人集まると今も自然にそうなります)。その日の出来事や最近気になっていることなどなど、女3人で話をする貴重なひとときにもなっていたように思います。話をしていない時は、母は決まって鼻歌を歌っていました。今思うと、そんな日常の習慣がいつしか「食事の後片付け=楽しいひと時」という概念をもたらしてくれたような気がします。母に感謝しなければなりません。
私は母のように鼻歌は歌いませんが(職業柄、歌いながら歌詞のあやふやなところや音程の取りにくいところが気になってしまうので)、その代わりに、使った食器やお鍋ひとつひとつに触れながら「うん、冷蔵庫にある食材を使って即興で作ったわりには美味しくできた」「あのおかずは、これよりもう少し深めの小鉢の方が良かったかな」「今日の炒め物、今度はオイスターソースでやってみよう」など、その日の料理や盛り付けの総括をして楽しんでいます。
西洋ではアドベンドでクリスマス一色になるこの季節。気ぜわしくはなりますが、この一年をじっくりと振り返り、一日一日に心から感謝して過ごす時間にしたい、と願っています。
■第781回 コンサートのあとさき
さだまさしさんの曲に、つゆのあとさき、というタイトルの曲があります。きれいなメロディーであることもそうですが、その詩の中に自分の誕生石が出てくることもあって、中学生の頃から大好きな曲です。
めぐり逢う時は花びらの中 / ほかの誰よりもきれいだったよ / 別れ行く時も花びらの中 / 君は最後までやさしかった
つゆのあとさきのトパーズ色の風は / 遠ざかる君のあとかけぬける
長らくこのタイトルは、さださんによるオリジナルだと思っていたのですが、恥ずかしながら最近になって、1931年に発表された永井荷風さんによる同タイトルの小説があることを知りました。ウィキペディアによると“銀座のカフェーを舞台に、たくましく生きる女給の主人公と軽薄な男たちの様子を描いた作品”とのことで、さださんの詩の世界とはまた違うストーリーのようですが、カナ文字の“あとさき”という言葉が、えも言われぬ、柔らくちょっと切ない雰囲気を醸しているように思います。
一つのコンサートを終えたあと、皆さまからのお声をいただくのが何よりの励みです。もったいないような立派なお褒めの言葉に感激することもありますが、「素人の感想で恐縮ですが…」という控えめな前置きの後にお話しくださった感じたままのご意見に、とても大きな示唆を頂いたりもします。また、演奏以外の部分でお気づきになったことなど、どんなお声もこれからの自分にとって貴重なアドバイスになり、それらを伺えるだけでもステージをやってよかった、と心から思うのです。同時に、「よし、今度はもっといいものにするぞ」という気持ちが湧いてきます。
有難いことに、今回お寄せ頂いたご意見の中には、いくつも「次回のリサイタルまで、これをお守りのように心に抱いていよう。くじけそうになったら、この言葉を思い出そう」と思ったメッセージがありました。コンサートの翌々日に、あるシューベルトのスペシャリストから頂いたメールも、その一つでした。
“何よりも、「幻想」ソナタが素晴らしかったです。生の音楽として初めて出会った演奏でした。シフ(*ハンガリーのピアニストで、シューベルトのエキスパート)がこのソナタについてこんなことを言っているのを読んだことがあります。「このソナタに『幻想』なんて名前を付けるのはおかしい、どうしても名前を付けると言うなら、『舞曲』ソナタだ」と。確かにこのソナタの魅力は、舞曲のモチーフが見事に取り込まれているところにあり、それでいてしっかりしたソナタとしての構造を堅持しているところが、実はとても演奏の難しい曲だと思います。(中略)一昨夜の演奏は、私の心の中に眠っていた『舞曲』ソナタを見事に目覚めさせ、至福の時を実現してくれました。それはまさに心躍る(踊る)ソナタでした。鈴木さんのしたたかな構成力がと言っておきましょう、ソナタの骨格と、奔放な舞曲の魅力とが1つの流れの中で、互いに邪魔することなく、否、むしろどういう訳だか溶け合っていました。そうなんだ、これこそシューベルトが「しかし、ベートーヴェンの後で一体誰が、何らかの人物になれるでしょうか?」と呟いた少年シューベルトが長じて辿りついた、ベートーヴェン以後のピアノソナタだったのだ。そんなことを思い出していました。”
この方のおっしゃっている舞曲の要素、そしてソナタの骨格と舞曲の魅力の調和こそ、『幻想』ソナタにおけるテーマとして取り組んできたことでしたので、私の演奏からそれを感じてくださったということが、どれほど大きな喜びと励ましをもたらしてくれたことか!
「聴いたこともないような、純粋なピアノの音でした。ピアノの音ってこんなにきれいだったの?と、この楽器の音を初めて聴いたような気がしたほどでした」というご感想にも、胸が熱くなりました。事前にホールを借りて響きや音を作ったり、このピアノとこのホールでしか実現しないような音色やタッチを追求してきただけに、その言葉はすべての苦労?が報われる魔法の一言のように心に響きました。
コンサートが終わると、次のコンサートへの準備が始まる…そんな人生も、来年で30年を迎えます。節目になるリサイタル、もっともっと深く豊かな時間を皆さまと分かち合えるよう、さっそくプログラムについて検討と選択を重ねています。大切な方をお食事にお招きするときのメニューを考えるのと同じように、心躍る大好きなプロセスです。
■第780回 シューベルトへの道 其の6 そして挑戦の旅へ
「え??」リサイタル前日、最後のリハーサル会場に向かうメトロの中で、目に飛び込んできたFacebookのある記事に思わず声を出してしまいました。“ハンガリーを代表するピアニスト、ゾルターン・コチシュ氏逝去。享年64歳”とありました。
ハンガリーのリスト音楽院留学時代、何度となく聴いた彼のシューベルト。そういえばブダペスト到着翌日、かの地で最初に聴いたコンサートも、彼がシューベルト最後のピアノソナタ第21番を弾くリサイタルでした。わたしのハンガリー留学は、コチシュ氏によるシューベルトの洗礼で始まった…と言ってもいいかもしれません。
彼のマスタークラスで、バルトークの『15のハンガリー農民歌』をみてもらった時、わたしがすべてを弾き終えると、「彼女の演奏は、ハンガリー人でなくてもバルトークがハンガリーの民族音楽に基づいて書いた作品を深く理解することができる、という良い例だ」と、受講生の皆に向かって言いはなち、「でも、もっともっと楽譜を細かく、注意深く読み込まないと」と、アクセントのひとつひとつ、休符のひとつひとつのアプローチの仕方を徹底的に教えてくれました。
シューベルト連続演奏会の前日の、コチシュ氏逝去の知らせ…哀しみを通りこして、寂しさで身体が震えるような思いでした。コチシュ氏への追悼を込めて…?いいえ、それより、彼だけでなく、これまで関わってくださったすべての方々への感謝の気持ちを込めて弾こう。…そんな思いが体いっぱいに広がるのを感じました。
シューベルト連続演奏会第一回目は、たくさんの方々に支えて頂いて無事に終えることができました。さまざまな意味で、初めてづくしのステージでした。すべての作品は初めて人前で演奏するレパートリー。初めての会場、そして初めてのファツィオーリ。25年ほど定着していた、トークを交えての演奏スタイルから離れたMCなしでの進行も、初めてのような気持ちで挑みました。でも、こんなにも多くの方々のお励ましを頂いて当日を迎えることができたことが、何にも勝る、嬉しい“初めて”になりました。とても幸せなステージでした。
久しぶりの共演となった木野雅之さん。本当にお忙しいなかを何度もリハーサルを重ねてくださり、そのたびにアンサンブルの密度がどんどん深まって、どんどん一緒に音楽を自然に呼吸できるようになっていったのは、わたしにとって大きな経験になりました。当日は誰よりも早く会場入りをして、最後は打ち上げのお開きまで、お客様だけでなく周りのスタッフの皆さんまで楽しませてくださったその人間力には、改めて感服しました。
フライヤーのデザインをお願いした筒井健介さん。コンサートの主旨、曲目とのイメージの一致、デザインのコンセプトとなるスタイルやストーリーについてなど、何度もやり取りを重ねて、最良のものを提示してくださいました。
その他、事前のホールリハーサルにもいらしてくださって、位置決めのみならずコンサートに関わるすべてを完璧にこなしてくださった日本フィルのステージマネージャーAさん。踏めくりを快諾してくれた桐朋時代の同期Mちゃん、何度もリハーサルに立ち会って貴重なアドバイスをくれた、アメリカ時代からの大切な友人Uさん。奇跡のようにステキなショットを何枚も撮ってくださった中村さん、お忙しい中、ビデオ撮影をお引き受けくださったTさんとYさん。平日にもかかわらず、高校のオーケストラ部の生徒さんをたくさん引率していらしてくださったY先生や、桐朋時代の恩師。当日のスタッフとして終始笑顔で動いてくれた方々や、会社を早退したりとそれぞれに都合をつけて駆けつけてくれた大好きな友人たち。オフィシャルサイトに、今回のための素敵なブックレットを作成してくださったTさん、神戸や仙台など、遠方からもお運びくださいましたお客様、当日はいらっしゃれなかったけど、メッセージやプレゼントを送って励ましてくださった皆さま。
終わったという実感よりも、たくさんの方々への感謝の気持ちで、いまは胸がいっぱいです。このコンサートに関わってくださったすべての皆さまに、心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。
…と、書きながら、いま気づきました。終わった実感がないのは、それもそのはず、これが終わりではないからです。シューベルト連続演奏会は始まったばかり。たくさんの皆さまに見届けていただいて船出は終わりましたが、航海はこれからです。
果てしない挑戦の旅になるであろう予感には、希望も不安もたくさんありますが、できる限りの誠実さをもって、シューベルトとの、そしてお客様との対話を深め、積み重ねていけたらと心から願っています。回を重ねるごとに“シューベルトへの道”の旅の道づれが少しづつ増えることを願いつつ、明日もピアノと過ごします。
■第779回 シューベルトへの道 其の5 才能のガソリン
子供の頃は、ピアノという言葉を聞いただけで、あるいはグランドピアノを見かけただけで、胸がときめいたものでした。何もコンサートホールやピアノ教室に限らず、それが小学校の音楽室であっても、体育館であっても、です。グランドピアノが、上部の大屋根と呼ばれる蓋を開けた姿が“羽を広げた蝶のよう”と形容された小説がありましたが、私には蝶というよりも、大きく精悍な鷲が翼を広げた姿のように見えました。
家にアップライトのピアノしかなかった私にとって、グランドピアノは憧れの存在でした。小学生の頃から家のグランドピアノで練習し、街の先生ではない、“偉い”先生について“その道”を目指している友達がとても羨ましく、彼らの境遇に憧れました。そして、たいした実力もないのに「自分がグランドピアノで練習できるようになったら今よりもずっとずっと上手になれるのに。アップライトではかなわない繊細なタッチや音色を、もっともっと追求するのに」と、歯がゆく思ったりもしました。
子供というのは、“自分にはできない”と思うことよりも、“自分はできる”、あるいは“できるはずである”と思う方が得意なようです。そして、実際できてしまったりします。それが証拠に、子供に「こんな感じは、どう?」と弾いてみせると、すぐさま迷うことなくやってのけるのです。彼らに方法論など必要ありません。自分が「やってみたい!」「やってみる!」と思った瞬間、もう出来てしまう。すごいな、といつも感心します。それが大人になると、いつしか「できるかしら」「きっとできない」に変わってしまう。それは、子供と違って挫折や現実を知っているからだ、とか、頭で考えるからだ、などと言われますが、果たして本当にそうなのでしょうか。
挫折や現実を知ることは人を強くするはず。そうした経験を重ねた大人が子供より“できない”なんて、何かおかしい。何か違うのではないか。…大人の生徒さんをレッスンしながら、しばらく自問自答を繰り返していました。そして、自分の練習で行き詰まった時にふと、思ったのです。「“できない”のは、“できる”ことを目指すからではないかしら」と。子供たちは、できるかどうかよりも“やってみる”ことしかない。もっと言うと、他人の評価もそこにはない。ただ“やってみたい”のです。そして、自分がどう感じるかを試したいのです。
天才という言葉があります。いうまでもなく天から授かった特別な才能、あるいはそれを持つ人のことですが、それをいうなら、子供たちは皆天才だと、彼らを見るたびに思います。個性豊かで、余計なことを恐れず、常に楽しいことを求め、心地よくあろうとし、刺激を求めて向上心と情熱に溢れていること以上の天才の素質があるでしょうか。だから、個人的に「天才少年」「天才少女」という言葉には違和感を覚えてしまいます。大人になってなお子供の頃の天才性を失わない人こそ、本当の“天才”といえるのではないかと思うからです。“天才”とは本来、大人に使われる言葉なのではないでしょうか。
そういう意味で、モーツァルトは確かに天才であったと言えます。でも、彼は大人になっても子供のように無邪気なままでした(教育心理学の分野では、発達障害のモデルにもなっているようです)。大人になって、苦しみ、孤独、悲しみを知ってなお、子供のようなまっすぐな情熱と純粋な心を失わなかったシューベルトは、ある意味でモーツァルト以上の天才だったと言えるかもしれません。
才能の種子は、誰にでも与えられている。それをどのように育て、伸ばしていくかは、環境や両親の教育方針によるところが大きいという見方もありますが、シューベルトもチャイコフスキーも、両親は彼らが音楽家になることを望んでいませんでした。結局は、本人の持っている力に勝るものはないと思います。
自分に何ができるか、など考えない。ただ、やりたいと感じたことを、やる。そこからまた世界が広がり、新たにやりたいことが見えてきて、さらなる挑戦が続く。…シューベルトの音楽にはそんな連鎖が息づいているように感じますし、懐かしく親しげな響きのなかにそんなしたたかな意志と深い情熱が見え隠れして、ゾクッとすることもあります。
結果や成功といったものではなく、もっと違う、ある“状態”を目指し、信じて“やり続ける”こと。それが、大人になってなお才能を燃やし続けるガソリンなのだ、と、自分に言い聞かせながら、ピアノに向かっています。
■第778回 シューベルトへの道 其の4 “あるがまま”に
シューベルトが初めて完成させた弦楽四重奏曲第1番を聴きました。楽譜には1812年の作曲との記述があるようですが、実際にはその二年前…シューベルトが13歳の時の作品ではないかと考えられています。ト短調で書かれた四楽章からなる作品(*第一楽章の序奏と、続くト短調のアレグロをそれぞれ別々の楽章と考え、全部で五つの楽章であるとする解釈もあるようです)で、あえて作曲年代を聞かなければまさかそんなに若い人による作品とはわからないことでしょう。
ハ短調の序奏をともなう悲劇的な第一楽章。第二楽章はメヌエット。親しげな表情で歌われるメロディーがとてもチャーミングですが、なんといっても白眉はアンダンテの第三楽章でしょう。変ロ長調という調性で書かれた穏やかな幸福感に満ちた響きは、聴く人を温かく包み込むようです。技巧をひけらかすような箇所は一つもありませんが、シューベルトか心から音楽を愛し、その力を信じていることが伺えて感動的です。プレストの第四楽章は、気持ち良く疾走しながらも長調、短調を自由に行き来し、様々な気分が交錯します。この頃すでに彼の生涯にわたる音楽スタイルが確立されているようにも感じられます。
この作品を含め、生涯に15曲ほどの弦楽四重奏曲を書き残したシューベルト。彼の家庭では家族で室内楽を演奏する習慣があって、お父さんはチェロを、シューベルト本人はヴィオラを担当したそうです。ピアノソナタが初めて書かれたのは1815年ですから、彼は弦楽四重奏というジャンルをとおして様々なジャンルの作曲活動に誘われていったと考えることもできるかもしれません。
ピアノソナタを弾いていても、弦楽四重奏が連想されるのはベートーヴェンも同じですが、シューベルトの場合は一つの楽章の中に歌あり、踊りあり、弦楽四重奏のようなところがあったかと思うとそれを超えて交響曲のような響きが展開されたり…と、とても多彩です。それを“構成が弱い”ととる人もいますが、形にとらわれることなく端正なスタイルを感じさせるところは、稀有な才能としか言いようがありません。
「“スタイル感”って、とても大切なものではないでしょうか。“センス”と言い換えてもほぼ同じかもしれません。それがないと、美しいと感じられないことって、ありませんか?」今日、スカルラッティのピアノソナタをお勉強されている生徒さんのレッスンで、そんな話になりました。「そうですね。お洋服の着こなしを考えると思い当たりますね。一見して特別なデザインや色ではないのですが、よく見ると吟味された上質なもの…それをさりげなくお召しになっている方は、気持ちがいいものですね」84歳になられる貴婦人のような生徒さんが、そう答えてくださいました。いつもおしゃれで、写真集を作りたくなってしまうほどステキな出で立ちでレッスンにいらっしゃるMさんです。Mさんこそ、ご自身のおっしゃるスタイルのお手本のようです。
シューベルトの音楽にも、まさにそんなさりげないスタイル感が息づいているように思います。少年時代から上質な音楽にふれ、美に対するセンサーが研ぎ澄まされているので、不必要に力むことなく、つとめて自然に音楽が紡ぎ出されている印象です。さらに、踊り、歌、お芝居、いろいろな様式感や演奏形態がイメージを膨らませる種子となっていて、弾きながらその発想の豊かさに圧倒されることが少なくありません。どうしたらその素晴らしさを伝えられるのかとあれこれ試行錯誤をするのですが、なかなかこれが難しいのです。
「素晴らしいものを目の前にして、“素晴らしい写真を撮ってやろう”とすると、自分が“きれいだな”と思っている気持ち側に泥が付く。そうじゃなく、純粋に“きれいだな”と思っている気持ちにシフトしながらシャッターを切る。それが偶然スパークすると、いいものが撮れたりする」あるカメラマンのコメントです。
そうなのです。“うまく”やろうとすると、哀しいかな何か歪んでしまうのです。シューベルトの音楽は太陽の光、雲や風、人の心のように表情の変化に富み、その一方では泉のように清らかでシンプルなもの。うまく弾こうとして、うまくいくような相手ではないのです。
目指したいのは、“うまく”というより、“あるがまま”でしょうか。作品の素晴らしさを受け止め、そのカメラマンの方のように、いいな、素敵だな、と感じる気持ちに寄り添って、ステージで会場の空気、お客さまの呼吸を感じながら“あるがまま”に弾けるよう、夢みるこの頃です。
■第777回 シューベルトへの道 其の3 楽譜との対話
今度のシューベルト連続演奏会でご一緒するヴァイオリニストの木野さんは膨大な数の楽譜を所有していて、部屋の一室が楽譜室になっているそうです。今回演奏する“ヴァイオリンとピアノのための幻想曲”もそうですが、一つの曲もより精緻に作品を読み込み、表現を具現化するために複数の楽譜を見比べて解釈を深めていくのは大切なことなので、私も出来る限り複数の種類の楽譜を用意して研究するようにしています。
今のように気軽に音源を検索し、視聴することができない時代でしたので、レコードやFM放送が大事な研究資料でした。また、中学生の頃には「西洋の芸術なのだから、その時代背景や学術的なことも学んでおくのは当然」と気づき
高校生になると、ピアノだけでなく管弦楽など他の演奏形態のものも広く聴くようになっていました。当時ソルフェージュや聴音をお習いしていた作曲家の先生が、ご自身が教えている音大の学生向きに作った聴音や音楽理論の課題や、オリエンテーションの余興用に作成したクラシック音楽の“イントロ当てクイズ”なるものを私に試し、9割以上の正解率をあげたりもしていました。今思うとプロになれるかどうかはともかく、音楽が好きでたまらなくて、まずは“熱烈なアマチュア”でありたかったのでしょう。
写真の世界でよく耳にする“ハイアマチュア”という言葉があります。それは“セミプロ”(写真を副業としている人)とも違う意味合いです。あるカメラマンによるとその違いとは、「どちらが高い知識を持っているかではないし、どちらが良いカメラ、機材を持っているかということでもない。写真で生計を立てる術を知っていてそれを実践しているのがプロ、それを実践することよりも、良い写真を撮って楽しむことを大切にしているのがハイアマチュア」ということでした。
なるほどねぇ、と思った次の瞬間、新たな疑問がよぎりました。「そうすると…音楽だけでは食べていけなくて、友人に何かと援助をしてもらって生活しながら良い音楽を追求していたシューベルトは、その定義でいうとプロというよりもハイアマチュアに入るのかしら」
もちろん彼は音楽(作曲)で生活の糧を得ることを望んでいましたが、ベートーヴェンのように楽譜が売れたわけでも貴族のパトロンがいたわけでもなく、充分に収入を得られず結婚することも叶いませんでした。自作の作品による演奏会も、なくなる直前の一回だけ。それでも深い音楽への志を抱き、信じられないほどたくさんの作品(しかも素晴らしい!)を書き続けて、暖炉の炎のような熱い創作意欲を31年という短い生涯で燃やし尽くした彼は、当時人気を博して引っ張りだこだったサリエリ、クレメンティやフンメルなどの有名作曲家たちより、ずっと才能に恵まれていたことは疑う余地がありません。
呼び名やカテゴリーなど、そもそも彼には無意味なのです。シューベルトはシューベルト。プロ、ハイアマチュアといった定義や、名声や知名度、ステイタスの高さといった条件などを超えた唯一無二の芸術家、それが彼なのです。
シューベルトの連続演奏会をするにあたり、ピアノに限らず彼の室内楽作品や歌曲など様々な作品を聴きましたし、もちろんたくさんの文献も読みました。「シューベルトの音楽を語る人は、みんな詩人になってしまう」という気がしてくるほどその文章には美しいものが多く、イメージも膨らみましたし豊かな気持ちになりました。でも、もっと彼自身への理解を深めるためにそれよりもはるかに有効なのは、何といっても彼自身のメッセージを読み解くことです。そのための最も良い方法とは、彼の書き残した楽譜と向き合うことです。
私は以前に増して、ピアノから離れて楽譜を“読む”ようになりました。繰り返される楽節にはその都度違う演奏指示が書き込まれ、どの瞬間にも生命力にも似た強さと喜び悲しみが溢れていて、シューベルト自身の息吹が感じられます。「君ならどんな音で、どんなふうに弾く?」という問いかけが、そこここから聞こえてくるようです。
それは私にとって、彼とデートしているような、特別なひとときになっています。
■第776回 シューベルトへの道 其の2 命の輝き
年齢が一桁の頃からたくさんのピアニストを聴いてきました。一つの楽曲も弾く人によってこれほどまでに違うのか…。という驚きとともに、「では、彼らが弾いている楽譜はどのように書かれているのだろう」という興味が膨れ上がるのを抑えることができませんでした。「ああ、ベートーヴェンやモーツァルト、ショパン…いろんな楽譜が欲しい!」大きな本棚にずらりと楽譜が並び、好きなものを引っ張り出してそのどれもを弾くことができるようになったら、どんなにか幸せなことだろう!…その頃の私の密かな夢でした。それができる人、つまりピアニストになりたいという憧れは、その延長線上でした。
音楽大学に行きたいです、と、ある生徒さんから打ち明けられ、「あなたはどんなピアニストが好きなの?」と尋ねたことがありました。高校一年のその時点で彼女はまだ楽譜の読み方もおぼつかず、かなりの自覚を持って臨まないと目標を達成するのは難しいように思われたので、意識と意志を確かめたかったのです。「ピアニスト、ですか?ええっと、どんなピアニストがいるのか知りません」「え、一人も知らない?」「はい」覚悟はしていましたが、やはり驚きました。彼女の年齢の頃の自分だったら、何人も名前をあげたくなって、誰をピックアップすべきか悩んだことでしょう。そこで質問を変え、「じゃ、あなたが“この曲を弾いてみたい”と思っている作品は、ある?」と尋ねると、しばらくじっと考えて、「曲とかよく知らなくて、わかりません。でも、いろんな曲を勉強したいです」
音楽大学を目指したいのに、ピアニストやピアノの作品に興味はないのかしら?いやいや、そんなはずはない。音楽大学に行きたいからには、きっと何か夢があるはず。…何か“とっかかり”が欲しかった私は、なんでもいいから彼女が答えてくれそうな質問をしようと、今度は「そう。では、行ってみたい国ってある?国じゃなくて、どこかの街でも。例えば、音楽の都ウィーン、とか…」と、ついに平凡な例を提示してしまった自分に落ち込みながら、聞いてみました。やはり彼女はしばらくじっと考え込み、おもむろに私に向き返って「ウィーンって…ロンドンですか?」
私はちょっとめまいを感じながら、自分の質問の方向が適切ではなかったのだと気づき、「ウィーンはオーストリアという国の首都なのよ。ロンドンはイギリスの首都ね。それはいいとして、音楽大学でピアノを勉強してどんなふうに
なりたい、という希望とか、ある?」と聞くと、少しほっとした表情になって「聴く人に幸せな気持ちになってもらえるようなピアノが弾ける人になりたいです」
私はこの時、とても心を打たれました。そして反省しました。彼女は確かに、まだクラシック音楽について詳しくはないかもしれない。でも、ピアノを通して目指していきたい“自分”の姿を明確に持っている。彼女のポテンシャルの一部を、音楽的な知識や素養で推し量ろうとしていたなんて、よくなかったわ、と。
その後、彼女は自分のペースを堅持しつつ(!)しっかりとレッスンについてきてくれました。演奏試験が終わり、どうだった?と尋ねた私に「それまでで一番楽しんで弾けました。楽しい感じのところは、そう感じてもらえるように笑顔で弾いてみました」と、天使のように微笑答えてくれた時、「ああ、この子は本当に聴く人を幸せにするような演奏ができるようになるかもしれない」と感じ、胸がいっぱいになりました。彼女は見事、第一志望の音楽大学への合格を果たしました。
人の能力や素晴らしさは、誰にも判定できるものではありません。誰も完璧な神様ではないからです。どんなテストや基準をもってしても、その範囲に収まりきれるものではありません。人の可能性は無限で、キラキラと輝く命そのものです。年齢を重ねて感じるのは、それはどんな年代の方も同じだということ。例えば、慈愛の心を育てることや感受性を高めることに、年齢制限はありません。
彼女には私にはない良さがあるし、逆もまた然りかもしれません。それをお互いに認めあい、高めあい、世の中に生かしていくことが、人間にできる最も尊いことなのではないでしょうか。
シューベルトはベートーヴェンに憧れ、心から尊敬していました。でも、本人は気づいていなかったようですが実はある(しかも、かなりの)部分で彼は、ベートーヴェンを軽々と超えていました。無心に、純粋に自分の音楽を紡ぎ続けたシューベルトの命の輝きは、彼の残した楽譜のそこここに散りばめられています。その輝きにふれるたび、心が震えるような幸せを感じています。
■第775回 シューベルトへの道 其の1“音楽の妖精”
「ことばの幹と根は沈黙である」時代の牽引者が常にそうであるように、評価には賛否両論の分かれる思想家であり詩人 吉本隆明氏は、その最晩年に繰り返しそうおっしゃっていたそうです。
“ことばによる表現”という形をとらないコミュニケーション…いわばコミュニケーション以前のコミュニケーションにこそ、“その人”そのものが、そして本当の“意思の伝達”があるというのです。長年ことばを扱い、激動の戦後日本の思想者として、また政治・芸術に関しての評論家として生き抜いた方のこの言葉には、やはりずっしりと心に響くものを感じます。吉本氏はまた芸術作品に対しても「ストーリーもセリフも、本当はどうでもいい。それは枝葉にしか過ぎない。人間が感動するのは、本来そこではない」とおっしゃっていたそうです。
言わずと知れたコピーライター糸井重里さんも、以前ある方との対談の中で「セリフはコミュニケーションに過ぎない。コミュニケーション以上に大切なものがある」と話していました。「ことばのコミュニケーションが何より大切だとすれば、ことばを獲得する以前の人類のつながりを認めないことになる」と。ことばのプロ中のプロである糸井さんもまた、本当に大切なのはことば(セリフ)ではない、というお考えでした。
確かに、ことばによる説明を受けたことによって感動した、という体験をされている方はあまりないのではないでしょうか。私もまた、人間が何かを伝え合う最も大切なものは、言葉というコミュニケーションツールではなく、それよりももっと深いどこかにあるような気が、漠然とですがしていました。
約1年前にシューベルトを改めて勉強していたある瞬間に、突然「この人の音楽は、コミュニケーションを超えている」と気づき、大きな衝撃を受けました。ここでいうコミュニケーションとは、メロディーとかリズムといった音楽的なエレメントによるメッセージです。それまでは、「ベートーヴェンの音楽などに比べて構成が弱いなぁ」とか、「どうして何のてらいもなく、こんなに無邪気に何度も同じことを繰り返せるのかしら」とか、「もうちょっと工夫すればこんなに長大な作品にならずに簡潔にまとまりそうなものなのに」なんて思っていたところがあったのですが、この瞬間、一気にそうした考えがどんなに浅はかなものだったか、思い知りました。
音と音の間の空気に、あるいは音そのものの表情に、または音が生まれる瞬間や、音が奏でられる時の呼吸のそこここに、彼の音楽は深く息づいている。それは形を超え、言葉を超えて私たちに語りかけてくるもの___まさに“コミュニケーション”というツールを超えて人の心から心に手渡されるような温かさに満ちたものに感じられたのです。
人間の感情は、理路整然となどしていません。きれいに起承転結の形をしているとは限りません。人間の感性もまた、何かの定型に収まるものではありません。それは瞬間瞬間に生まれては消え、あるいは喜怒哀楽の間を縦横無尽に彷徨うものです。人間とは例えば、哀しい哀しいと嘆いていても、ふとしたきっかけでころりと笑顔になったりする、愛らしい生き物なのです(子どもはその最たるものです)。
シューベルトの音楽はまさにそうしたものでした。彼の音楽には、ベートーヴェンのような完璧なドラマ性や非の打ち所のない構築力は弱い代わりに、人間を人間たらしめるあらゆるものがあったのです。
先日レッスンで、6歳のCちゃんが休符をきちんと守らず最後の音を長く伸ばしてしまっていた時、「音楽の妖精さんはお休みが好きなの。妖精さんは見えなくてもいるのよ。感じてみて。いい?」と言って、最後のお休みを大切に感じて弾いてみせました。Cちゃんは言葉を発する代わりにキラキラした目で私を見て頷き、無言で「妖精さんいたよ」と伝えてくれました。この時、私たちは音楽の妖精によって言葉を超えてコミュニケーションしていたのです。
「今度はCちゃんが弾いてみて」と促すと、Cちゃんは最後の音の後の休符の時視線を上げ、見えない何かを感じているようでした。私が一呼吸おいて、小声で「ね。妖精さん、来てくれたね」と言うと、彼女も可愛い小さな声で「うん、来た!」と嬉しそうに微笑みました。
シューベルトの音楽には、そんな妖精たちがたくさん宿っているような気がします。
■第774回 愛の連鎖
「先日、自分が写った家族のアルバムを見ていて思ったんですけど、この写真は全て、私の両親が100パーセントの愛情を持って私たちを撮ってくれた写真なんです。その100パーセントの愛情を持って街の人たちを撮ってみたいんです。」
写真家のハービー・山口さんのワークショップを受講したある高校生が、後日“家が貧しいので、進学は諦めて働く代わりに、写真家を目指す強い意思表明として100万円近くするライカのモノクロームカメラを買うことにした”とハービーさんに打ち明けました。上のコメントは、そのとき彼が「どんな写真を撮りたいと思う?」と質問した時の、彼女の答えです。
例えば、憧れのピアニストから「どんな音楽をやりたいと思う?」と聞かれたとしたら、高校生の私はそんなふうに簡潔に、しかも具体的に答えることができたかしら…。しっかりと目標を見定め、そこに向かってまっすぐ歩いていく意思を持つことも、それを人に伝えられることも、とても素晴らしいことだと思いました。
ハービーさんは後日、ライカのオーナー、カウフマン氏と接見した折に「世界の写真家が撮った写真に込められたメッセージは、やがて大きなうねりとなって、世界を平和な方向へ変えて行くのだと思うんです。ですから、カメラは世界一平和な道具だと思っています」と伝え、その高校生の話をしたところ、氏はいたく感激して彼女にモノクロームをプレゼントしたい、と申し出たというのです。「学ぶ機会を得て欲しい」という言葉を添えて。
「一つの誠意が、一つの強い意思が、一つのきっかけによって総和な力となった時、それは国籍とか、有名無名とか、地位とか、年齢とか、そういった人間が作った様々な壁を乗り越え、私たちがまだ見ぬ、でも、それはそれは素晴らしい、ほぼ奇跡というべき世界に連れて行ってくれることを実感したのである。」このエピソードを綴ったハービーさんのエッセイは、このように結ばれていました。
この頃、しばしば感じることがあります。それがまさに、ハービーさんが書いた「一つのものは、すべての差異を乗り越えて大きな一つに結びつく」ということ。どの国のどんな分野の人も同じことで悩み、同じことに喜びを感じ、同じことを目指している。結局人間の求める幸せは、いつの時代も、どの国のどんな人も、突き詰めれば一つなのだと感じるのです。
高校生が語った「100パーセントの愛情を持って」というのも、同じ。彼女はそれを写真というツールを通じて、みんなが一つであること、みんな愛情を与え合うことができるのだということを伝えたい、と言いたかったのだと思うのです。
それは音楽もまた同じことです。私は今、シューベルトの音楽と向き合う日々を重ねていますが、彼の望みは「自分を見て!自分の言いたいことに耳を傾けて!」というのではなく、弾き手、聴き手、そして“音楽”を信じたうえで、みんなで何かを分かち合おうとしているのを強く感じるのです。
誰にも悲しみは与えられる。でもそれは、乗り越えるためにある。怒りの感情もまた、そこから何かに気づくためにある。喜びは幸せを与えてくれるものだけど、悲しみに転じ得る。同じように、苦しみもまた、幸せに転じ得る。すべての感情もまた輪廻のように一つであり、“愛”に昇華して限りある美しい命を豊かに輝やかせる。…そんなメッセージが彼の音楽の端々から聞こえてきて、練習しながら胸が熱くなることも少なくありません。
この高校生の、“両親から受けた愛情のありがたさを人にも伝え、分かち合いたい”という考えにハービーさんやカウフマン氏が感銘を受け、ひとつの“愛”のツールが彼女に送られることになった…。求めあい、響きあい、助け合うこのような連鎖こそ、私たちが願ってやまないものなのではないでしょうか。
人と比べて争うことや違いを非難することから解放され、そのような愛の連鎖の中にみんなが一つになれたら、この世の中は現世にして来世をも超えるほど、素晴らしいものになるのではないでしょうか。
■第773回 後に残していけるもの
先日、古代ギリシャの特別展を観に行きました。紀元前6000年以前からヘレニズムまでの数千年の、時空を超えた旅。紀元前5000年から紀元前2000年の古代ギリシャ時代の人たちの美意識の高さには驚きました。現代美しいとされている造詣が、すでに当時かなり確立されていたのです。そしてミノス、マケドニア、ミュケナイなどの文明を経て、アクロポリスやオリンピアの時代へ。
都市化してくると文字も発達し、さまざまな機能性が高まっていく一方で、古代文明のようなユニークさ、自由さが薄れ、画一的なスタイルや様式がそれに代わるようになります。言葉や文明の発達によって、人が本来持っていた感性や、言葉を超えた意思の疎通、信頼関係などが薄れていったようにも感じられました。
“A sound mind in a sound body”その時代の詩人で弁護士でもあったユウェナリスの有名な格言です。一般的には“健全な精神は健全な肉体に宿る”と訳されますが、その真意を正しく捉えられているとは限らないようです。
もちろん「身体が健康でないと、精神の健やかさは望めない」ということではなく、一般的には「身体が健全ならば精神も自ずと整うものである」という意味であるとされ、“病は気から”にも通じる考え方のように受け止められています。
でも、ラテン後の原語から直訳すると、それとは違ったニュアンスになるようです。すなわち、「健やかな身体の中で、心も健やかであることが望ましい」。そもそもが“健全な肉体に健全な魂が宿かれし”の誤用である、と指摘する人もいます。
富や栄光、長寿や美貌など多くを望まず、最も大切な心と身体の健康を願いなさい、という意味が込められているという捉えかたや、肉体を鍛えることばかりに熱心になり、勉学をおろそかにするものが増えてきたことへの教訓として「精神も同じように鍛えなさい」ということを言っているのだ、とする説もあります。また、自らの健康からおごりが生まれ、病弱な人や敗者の心の痛みがわからなくならないように、と諭すものであるという解釈もあります。
ユウェナリスの生きていた時代は戦争が盛んになり、強い国家のための強い軍隊、さらにそのための強い肉体を持つよう奨励される風潮があったとか。でも、人も国家も、ある一つのことばかりを重視しては、本当に大切なものを見誤ってしまいかねません。彼は、何事もバランスが肝要だということを忠告したかったのかもしれません。
格言にはいろいろありますが、個人的には名だたる哲学者や思想家のものよりも、ネイティブ・アメリカン(*インディアンという呼び方は問題があるので、こう呼ぶそうです)のものに「確かにそうだな」または「そうでありたい」と感じるものがたくさんあります。例えば、“神の名は無意味。世界にとって本当の神は、愛なのだ”“人間は人として生まれるのではなく、人になるために生まれてくる”“そこにたどり着こうと焦ってはいけない。『そこ』などどこにもないのだから。あるのは『ここ』だけ。今を慈しみ、一瞬一瞬に集中せよ”などなど。
中でも好きなのは、“愛は、死ぬ時に後に残していける。そのくらい力強いもの”という言葉。確かに、亡くなった祖父、祖母が注いでくれた愛情は今も私の心の中に生き続けていますし、大作曲家の愛に溢れる作品に触れるにつけ、本当にそうだわと思うのです。先の“世界にとって本当の神は、愛なのだ”といい、彼らは愛を伝え、残すことこそが、“人”にとって最も尊いことであると説いているようにも感じます。
太古の昔の人たちは、特定の宗教的思想や規則にとらわれることなくしっかりと本質をとらえ、次の世代のことも考えながらより良い生き方を求めていたのが伺えて、すごいことだと感心します。人類はいったい、進化しているのか否か。
“どんなことも7世代先まで考えて決めなければならない”。これもネイティブ・アメリカンの言葉です。自然災害や痛ましい事件を嘆くばかりでは、彼らのいうところの“人”になっているとは言えません。彼らが愛を込めて残してくれた教えを生かし、世の中のため、後世のために自分ができることは何かをもっと考えて生きなければ…。ある人からお土産にいただいた小さなナバホ族の木の人形を時おり眺め、気持ちを引き締めています。
■第772回 祈りの波動をひろげたい
素晴らしい演奏に出会うと、「ああ、祈りのようだ…」と感じます。その祈りは救いや見返りを求める種類のものではなく(もちろん演奏者自身の能力を誇示し、評価を求めるようなものでもなく)、ただただ人類みんなの幸せを願っているように感じられ、感謝の気持ちに満たされるのです。
“仏教は正確に言うと宗教というよりも思想に近いものである”という考え方があります。確かに、仏教では神による啓示や救済について説くことはありませんし、そもそも仏教にはブッダ(悟りを開いた者)はいても神はいません。ブッダが生きた時代に席巻していたバラモン教は、宇宙の根本原理であるブラフマンと,個の根源であるアートマンという形而上概念であるといわれます。それは“万物は宇宙の根本原理であるブラフマンより生まれ出て,個の根源であるアートマンに至る”というもので、宇宙の根本原理であるブラフマンと個人の根源であるアートマンは同一の存在ということになり、バラモン教的思想を継承する一部の仏教思想ではこれを「梵我一如」というそうです。
「梵我一如」とは個人の実体としての“我”が、宇宙に遍在する“梵”と同一であることを悟ることによって自由になり、あらゆる苦しみから逃れることができるという意味で、ひいては宇宙と個人は一体であるということにつながるとか。そういった、インド起源の宗教的というよりも哲学的な思想に、国籍を問わず時代の最先端をいく多くの文化人が惹かれていたのはよく知られているところです。ベートーヴェンもそのひとりでした。
『喜びの歌』で親しまれているベートーヴェンの第九交響曲の第4楽章。一番初めに口火を切るバリトンソロによって歌われるベートーヴェン自作の詩によるレチタチーヴォ“おお、友よ。そのような音ではない!もっと心地よく、喜びに満ちた歌を歌おうではないか”という呼びかけにおける“そのような音”というのは、暗にキリスト教的な思想を指している、とする説があります。確かに、「梵我一如」という考え方に基づいてとらえると、“全ての人は兄弟になるのだ”“百万人の人々よ、抱き合おう。このキスを全世界に!”というシラーによる詩は、人類愛を超えて“人類と宇宙は一体である”ことへの謳歌にも聞こえてきます。
バルトークも、似たような思想の持ち主でした。彼が子供のために作曲し編集した6巻にも及ぶ教材には『ミクロコスモス(ちいさな宇宙)』というタイトルがつけられましたし、妻に「人間が宇宙の摂理に従って生命を得、死んでまた土に回帰し、転生を繰り返していく幸せ」について繰り返し語っていました。
ベートーヴェンを尊敬してやまなかったシューベルトの作品に触れるにつけ、彼もまたそうした考えの持ち主だったのではという気がしています。第一楽章にでてきたモティーフが他の楽章にも登場して、“輪廻”を繰り広げる作品がいくつもあるのですが、それらが書かれたのは彼の死後“循環形式”と呼ばれる手法が確立されるよりも随分前のことです。
聖書の勉強を始めました。といっても、教会関係の催しでもなければ宗教的な内容の理解がメインでもありません。知人にお声をかけていただいて、とある公民館での“聖書をフランス語で読む”という愛好会に参加させていただくことになったのです。
初回は創世記を勉強したのですが、大切な言葉が何度も繰り返され、唱えることを前提として書かれているからか、朗読するにも単語を覚えるにも聖書はとても優れた教材なのかもしれないな、という印象を抱きました。般若心
宗派は違っても、お互いの幸せを願う気持ちは同じ。自分の書いた作品によって多くの人々が手をつなぎ、平和や幸せにつながる支えを得てほしいという大作曲家の願いを届けるミッションをもつ私たち音楽家は、福音史家(エヴァンゲリスト)のようなものなのかもしれません。
良き魂がお互いの幸せを願いあって響き合うために、音楽の果たしうる役割にはとても大きなものがある。…そう信じて、祈る気持ちでピアノに向かう日々です。
■第771回 コンサートに数千円は、“高い”?
かれこれ四半世紀以上この職業に従事しているので、同業者…プロの音楽家…の友人、知人は少なくありません。
彼らみんなに共感するのは、音楽に対する真摯な姿勢。体力やテクニックの衰えを感じたとしても、それを精神力と人間力で乗り越え、不安や葛藤をかかえていてもそれを見せることなく、果敢にステージに向かっているのです。
いいカンジに顔を赤らめて“出来あがって”いる打ち上げのスナップや、麗しいステージ写真の裏には、凄まじい練習や、舞台にかける命がけのプレッシャーやストレスがあるのです。それこそ、オリンピックのアスリートと同じくらいの!でも、それは私たちにとってはごくごく当たり前のこと。
最高の演奏のため、経済的採算性など無視して少しでもよい楽器を求め、365日コンディショ保つためにメンテナンスし、国内外を問わず可能性と運命の許す限りの最良の師匠のもと、何十年にもわたって修行を重ねてきたそのすべてを、約2時間のステージに集約しているとしたら…?それでもやはり「高い」でしょうか?
その問いかけに、ある方から「その演奏に数千円は高い、と思うこともあるし、その逆もあります」というご意見をいただきました。もちろん、私もそう思うことはあります。行こうと決めて予定を入れ、入場料を工面して聴いてくださった方にとっては、なおさらだと思いますし、チケットの値段というものは、協賛があるのか、自治体主催なのか、自主公演なのか依頼公演なのか…などによっても異なりますし、難しいところだとは思います。
実際、料金に関わらず、残念な気持ちになるコンサートもなくはありません。だからこそ、お客様をそうさせないよう、プレッシャーを感じつつもモチベーションを高め、精一杯を尽くすのが演奏家の姿勢。それには応援してくださる方の存在が不可欠です。
演奏家は入場料や出演料に関わらず常にベストを尽くそうと努力を重ねる一方、それから得た収入で生活しています。文化や音楽芸術を育て次の世代に残していくためには、お互いに支え合うことが大切な鍵になります。
クラシック音楽は、大作曲家が魂をこめて私たちに残し、委ねてくれた“譜面”というメッセージを、わたしたち演奏家が語り手となって楽器をとおしてみなさんに伝え、その素晴らしさを共に感じあうもの。時には、その後の人生観や価値観が変わってしまうほど、示唆や刺激に満ちた芸術です。
かくいう私も、小学生時代にたまたま聴きにいったあるコンサートがきっかけになり、この道を目指す揺るぎない決意につながりました。
作曲家、演奏家、聴衆、楽器、会場、スタッフ、フライヤーのデザイナー…コンサートは、そこに在るすべてのもののアンサンブル(調和)です。時に、人生をも変えうるちからがあったとしてもおかしくないと信じていますし、その一端を担うピアノ弾きのひとりとして身を引き締めつつ楽器に向かい、その深く滋味に溢れた世界から幸せと励ましとを受け取っています。
知名度や評判(クチコミ)だけで判断してしまうのは、もったいない。「これは…」と、ココロにひっかかるフライヤーやプログラムに出会ったら、どうぞ先入観にとらわれず、ニュートラルな気持ちでコンサート会場に足を運んでみてください。きっと素敵な体験になることと思います。
心の栄養補給に、ストレスのメンテナンスに、人生の潤いと良き刺激に…コンサートをぜひ、お役立てください?そして、よろしかったらお感じになったことをお聞かせください。?わたしたち演奏家も「数千円の“自己投資”なら満足だったわ」と思って頂けるよう、みなさまからのご意見ご感想を糧に、これからも精一杯精進してまいります。
たくさんの方に支えられていることに感謝しながら、これからも少しでも興味を持っていただける、そして、楽しんでいただけるコンサートをつくり続けていきたいです。
(*今回は、最近SNSへ投稿したコラムから反響の大きかったものを編集しました)
■第770回 何を選ぶか…それが問題だ
インターネットはとても便利でよく調べ物にも使いますが、どんな疑問に対しても簡単になんらかの答えが“見つかって”しまうことに危機感を覚えることがあります。
たとえば、最近「ピアノを習うのには、演奏活動をされている先生と町の個人教室の先生、どちらがいいでしょうか」という質問を見かけて驚きました。月謝や施設料などの諸費用がどのくらいかかるのか、といったことや、レッスンの内容(“ストイック”であるとか、“気軽”とか)、“買わされる”楽譜はどのようなものか…などが、その回答に書かれていました。
この種の類に限ったことではありません。何かあるとネットで調べ、その情報をすぐに正しいものと捉えてしまう人が多いようですが、その出処はどこなのか、また、どんな団体や個人によるものなのかなどの確認を怠り、整合性を取ることなくそのままを信じてしまっては、とんでもないことになりかねません。
例えば、先ほどの例でお話しするならば、まず“演奏活動をされている先生”にも、いろいろいらっしゃいます。もちろん、その全員がストイックなわけはなく(そもそも回答者のおっしゃるところのストイックという定義もよくわからないのですが)、お月謝もさまざまです。演奏活動をしている先生には“高い輸入盤を買わされる”というのも、先生によりけり。私のように、必要な場合は自分の楽譜をお貸ししたり、コピーをとったものを差し上げたりするケースもあるはずです。一方、“町の”先生も、いろいろな方針の方がいらっしゃいます。
その方がどんなことをどのように身につけていかれたいのかによっても、先生やレッスンに求めるものは変わってくることでしょう。私自身は、生徒さんのご希望にできるかぎり添ってレッスンを進めるよう心がけていますが、方向性がはっきり決まっていない方の場合は、一緒に勉強しながらそれを見いだし、可能性を広げていくということもよくあります。
インターネットが普及してからというものの、世の中の“マーケティング”や“経営戦略”は大きく変わってきているようにみえます。ものの本の帯には、消費者の口コミをいかに有効に利用できるかが勝者になるか敗者になるかの分かれ道、などといった言葉も踊っています。
情報を取り込んでそれに基づいた選択をするのは、確かにひとつの方法でしょう。感想は人それぞれ、個人的なものではあるとはいえ、他の利用者の声はたしかに参考になるものです。でも、外食のお店や旅の宿の参考にするならまだしも、お習い事の先生やアーティスト、投票する政治家など、“人”を判断するときにネットの口コミに頼りすぎてしまうのはいかがなものでしょう。
自力で良い判断をするためには、それに足るだけの知識や“正しい”情報の収集など、努力が必要です。でも、私が一番大切に肝に命じたいのは「人の意見など信じるな」「判断は自分で行うべき」ということではありません。せっかく私たちに与えられている“自らが体験して学ぶ楽しみ”や“感じるちから”、そして“自分の判断に責任と自信をもつ幸せ”を、もっと育てていきたい、ということなのです。
「人生は選択の連続である」とは、かのシェークスピアの名言です。例えば、今日という日の朝をどんな気持ちで過ごすか、私たちは好きなように“選択”することができます。何かアクシデントが起きたとしても、それを「失敗した」と捉えるか「よい勉強になった」と捉えるか、それに対してどのような感情をもつか、パーソナルなところでは自由です。
そう考えると、シェークスピアのいうように、人生は確かにそんなひとつひとつの選択の連続なのです。…と、いうことは、それをこんなふうに言い換えることはできないでしょうか。「人は人生を選択することができる」
自分自身の持つちからを総動員してさまざまな選択を楽しみ、神様から与えられた人生というチャンスを存分に全うするためにも、人の口コミや評価に翻弄されるのはいかにももったいないことです。選択を楽しむことが、人生を楽しむ鍵をにぎっているのかもしれません。
■第769回 深夜のインスタントラーメン
オリンピックもたけなわ。たゆまぬ努力によって鍛えられた体と運動センスが強い精神力と結びつき、結果を導き出す姿にはとても清々しいものを感じます。その一方で、メジャーリーグ通算3000安打を達成したイチロー選手の快挙も大きな話題になりました。
「しっかりと準備もしていないのに、目標を語る資格はない」「小さいことを重ねることが、とんでもないところに行くただひとつの道」…名言が多いことでも知られるイチロー選手のコメントには、業種を問わずハッとさせられる方が多いのではないでしょうか。
先日、イチロー選手のインタビューをみました。最近の選手が、筋力トレーニングによって肉体改造をしている傾向については「全然ダメでしょ」とばっさり。「自分の持って生まれたバランスがありますから、それを崩してはダメでしょう。だって、トラとかライオンはウエイトトレーニングしませんよ。筋肉が大きくなってもそれを支えている関節とか腱は鍛えられないので、(大きくした筋肉の)重さに耐えられなくて壊れてしまう」例えば、肩の力を抜こうとするなら膝の力も抜かなくてはならない…目に見える部分だけを捉えるのではなく、人体そのものを理解することが大切だと話します。
「情報が多すぎて、どれをピックアップしたらいいのかと頭でっかちになる傾向があると思います。でも最短で(いい結果に)いくのは、無理。まったく失敗しないでそこにたどり着いたとしても、“深み”は出ない…。野球選手としての“作品”がいいものになる可能性は、僕はないと思います。遠回りすることが大事で、無駄なことは結局無駄じゃない。合理的な考え方ってすごく嫌いです。僕は遠回りすることが一番近道だと信じてやっています」
中学生の頃からでしょうか。“いちおう”予習やら復習やらで、幼い弟を寝かしつけ早めに休む母よりも遅くまで起きているようになった私は、夜遅く帰宅した父に夜食を作ることが増えました。夜食と言っても夜ご飯を温めて出したり、インスタントラーメンや鍋焼きうどんを煮る程度のものでしたが、父はいつもとても美味しそうに食べてくれました。
父が食べ終わるまで、私も一緒に食卓についているのが常だったのですが、そうして二人で向き合っている時に、父にしばしば聞かれました。「美奈子が人生で一番やりたいことは、なんだ?」「ピアノ。音楽の勉強です。」「そうか。ならそれを徹底的に、納得のいくまでやりなさい。一つのことをとことん突き詰めることから、他の様々なことも学べるものなんだよ。一つのことをやり遂げることには、それ以上の意味がある、そういうものなんだ」そして食べ終わるとお箸を置き、必ず「ありがとう。うまかった」と言ってくれるのでした。
今思うと、夜遅くまでのお付き合いでお酒が入っているだけでなく空腹だったことでしょう。大人になってからわかったことですが、そんな時にはたいてい、ろくにおおつまみや肴なんて食べていられないのです。お腹を空かせ、疲れて深夜に帰宅した父が何度も話してくれたことを、イチロー選手の言葉を聞いてふと思い出しました。
10代半ばだった私が、父の言わんとすることをすべて理解できていたとは思えません。「お父さんから見たら美奈子の(やっていること)は練習に入らん!」という厳しいお叱りをもらい、「そんなことない!」と反抗したこともありました。音楽の勉強を応援してくれているのか反対されているのかわからなくて、戸惑ったことも少なくありませんでした。
当時の父の口癖は「going my way」“我が道を行く”。その人生訓は「他人がどう思おうと気にせず自分の信じる道をいくこと。近道を求めるよりも、諦めずに信じて歩み続けること」で、それを話すのはたいてい夕食の時、晩酌をしながらでした。まだまだ子どもだった私は「パパはお酒が入っているから、いつも同じようなことを話すのかしら」と思っていた節がありましたが、生徒さんにレッスンするようになって、大切なことは何度となく繰り返し伝えている自分に、「ああ、父もこんな気持ちで話してくれたのだ」とふと気づいたりしています。
深夜のラーメン、というと、一般的には外食が想像されますが、私にとってのそれは、父との食卓のひと時を思い起こす、長ネギと卵を落としたインスタントラーメンなのです。
■第768回 育て!創造と想像の種子
この国では、お盆休みは取れても、大人には子どもたちのような“夏休み”がないのは、どういうわけでしょう。消費税率や経済成長率などでは何かと「先進国では…」と、EU諸国が引き合いに出されますが、平均的バカンスの日数や連続して取ることが“義務”付けられている夏期休暇の長さの比較やその必要性について討論されることは、あまりありません。暑い中、大変な思いをして“通っている”のは大人も同じだし、子どもと違って体に無理がきかないことも多いというのに。
サボることばかり考えているのではありません。せっかく子どもたちがお休みの時に、家族みんなでいつもなかなか取れないコミュニケーションをとれたらとてもいいと思うのです。一時期、サマータイム導入について検討されていたことがありましたが、それより先ずバカンス導入を考えてもらえたら内需の拡大にもつながるし、家族同士、お互いになんでも腹を割って話しやすくなって、場合によっては自殺などを防ぐことにもつながるかも。…と、友人に話したら「甘い甘い!夏休みとは名ばかりで、大人よりも子どものほうが忙しいの、美奈子ちゃんも知っているでしょう?学校の宿題やいつものお習い事はもちろんのこと、サマースクールやホームステイやら、塾の夏期集中講座やら部活の合宿、コンクール参加や遠征試合…。彼らは彼らでイベントてんこ盛りなのよ」という答えが返ってきました。
はぁ、確かに。子どもたちと話していると、自分がえらくヒマな人のような気持ちになることすら、あるくらいですもの。でも、お休みと言いつつ「さぁ、なんでもいいから“自由”に研究しなさい!」と丸投げされ、普段から研究の進め方など習っていないのだから何をどのようにしたらいいものかわかるわけもなく、ネットでいろいろ調べたりしてなんとかテーマを定め、フォーマットにのっとって“不自由”に段取りや作業を進めていくよりも、一ヶ月間なり二ヶ月間という時間を、本当の意味で“自由”に、かつ有意義に使うことに積極的に関わることの方がずっと想像力も養われるし、結果的に実り豊かな経験になることも多いような気がするのです。
バカンスとはそもそも、空白、空き、という意味。人生はある意味、その人にとっての空白である“未来”を、良き“現在”の積み重ねによってクリエイトしていくこととも言えないでしょうか。バカンスをどのように過ごすのかを、家族と
一緒に考えたり、その過ごし方を工夫したりすることは、そのまま人生を楽しむことにつながるように思うのです。社会の最小単位である“家族”の中の自分の役割について考え、行動することから、社会性も身につくかもしれません。
昨日、十数年ぶりに福島県の吾妻小富士に出かけました。お天気に恵まれ休日にも重なって、多くの家族連れで賑わっていましたが、誰一人流行りのゲームアプリをしていませんでした。弾むような足取りで山道を行く男の子、お母さんにちょっと甘えながら一歩一歩を踏みしめて進む女の子、息子に「おい、ここでお父さんとお母さんの写真撮ってくれ」なんて言いつつ、カメラを差し出すお父さん…。大人も子どもも自然の美しさ、雄大さに抱かれ、その素晴らしさを体いっぱい、心いっぱいに享受しているように見えました。よい景色だったのは、山々だけではありませんでした。
そこには何の案内板もなく、太古の昔にできた噴火口がぱっくりと口を開け、その周囲に広がる大パノラマを堪能しつつ一周できる尾根があるだけ。でも、一見してそれとわかる細かい気泡のはいった火成岩や、それと同じ色の砂のような土の感触を感じながらただ歩くだけでなにやら楽しいし、場所によって鉱物の成分が違うことからかその色が異なっていることに気づいたり、そこから疑問が湧いてきたりすることでしょう。刻一刻と姿を変える雲の姿を観察するのも、楽しいものです。自然を散策することから、理系が好きな子どもなら無数の研究テーマを思いつきそうですし、文学が好きな子どもならなにか自分だけの詩的な表現を見つけるかもしれません。
日常ではなかなか出会うことのできない絶景を目の前にすると、いかにも別世界を見ているように感じますが、その素晴らしい自然こそが“この世界”なのだ、と気づいた時、誰しもが感動を覚え、地球の恵みに感謝の気持ちを抱くことでしょう。
なにも「研究」と気張らなくても、興味の対象は身の回りにいくらでもある…。それに気づくための心のゆとりを得るためのきっかけが、バカンスなのかもしれません。満ち足りた時間を味わい、さまざまな興味が膨らむような素敵なバカンスを過ごせたら、明日からの日々はいっそう輝きを増すことと思います。「空白」の時間にこそ、創造と想像の種子が宿る…そんなことを感じた一日でした。
■第767回 不得意は得意の始まり
「先生、ここ。けっこう練習したんだけど、うまく弾けるようにならないんです…」Cちゃんが控えめに指をさした先には、断続的に装飾音符が並んでいます。確かにちょっと難しい場所です。「どれどれ、ちょっと聴かせてくれる?あ、いつもよりゆっくり目に弾いてもらえるかな?」おずおずと弾き始めると、問題なくきちんと弾けています。「あれ?ちゃんと弾けているけど…今のじゃ納得いかないの?」「ううん、今はできた!」「なんでかな?」「う〜ん、なんでだろう。うふふ…」
これは何もCちゃんだけではなく、どんな人にも面白いほど共通することで、「できない」とおっしゃることって大体、きちんとできているのです。ある大人の生徒さんは「私、どうも三拍子が苦手で…」とおっしゃるも、ワルツを弾いてみたら左手の“はずみ”がとても自然で、かつエレガントではありませんか。「苦手だなんて感じ、ちっともしませんよ」と言うと、「そうでしょうか…」とはにかみながらも、嬉しそうなご様子でした。
近所に、絶品のカルボナーラを出すイタリアンレストランがありました。ファン曰く、「ちゃんとした正統派カルボナーラなのに、他のどのお店とも何かが違う。絶品!」「クリーム系は飽きてしまう方だけど、ここのものは最後まで美味しく食べられる」のだとか。マネージャーに聞くと、シェフご自身がこってりしたクリーム系のパスタがお好きではないとのことでした。それで、「もし自分が食べるとしたら…」と試行錯誤を重ね、重くないのにコクはしっかり感じられて、最後まで食べ飽きないような独自のカルボナーラレシピにたどり着いたのだそうです。
劣等感、という言葉があります。言うまでもなく、優越感の反対語です。自分が何かにおいて、人と比べて劣っていると感じることで、もちろん前向きな意味ではありません。それを隠そうとして人を非難したり、攻撃的になったり…という行動にでてしまうとなると、それは問題になりますし、過剰にその埋め合わせをしようとすると神経症に至りやすい、と唱える心理学者もいます。
でも、一方で身体的な何かに劣等感を感じている人が幾多の挫折や困難を乗り越え、世界有数のアスリートやトップランナーになった例は少なくありません。劣等感を一切もっていません、という人は少ないと思いますし、私はどう
しても劣等感そのものが悪いという気がしないのです。むしろ、劣っていると感じることから謙虚になれるかもしれないし、人の痛みをわかるようになるかもしれない。それを克服するための努力を積み重ねていくと、才能を開花させる可能性にもつながるのではないでしょうか。
Cちゃんのケースは“劣等感”というような大げさなものではありませんが、自分の“よくできていないところ”を認識できると、多くの場合人はそれと向き合って克服しようという気持ちになり、その解決にむけてなんらかの行動を起こします。そして、それらを一つ一つ解決していくことから自信も生まれます。その自信は、他でもない自分自身から得たものですから、強力なものになるでしょう。他人から“褒められた”という評価から得る自信とは違うレベルで、その人を支える底力になるかもしれません。
かく言う私も、子供の頃から劣等感や不得意なことをたくさん抱えてきました。お裁縫やお料理、スポーツはすべててんでダメ。何をするにももたもたと時間がかかり、給食を食べ終えるのはいつも最後でしたし、ゲームで遊んでも2歳年下の妹にかないませんでした。もっと上手になりたいと思ってストイックにピアノの勉強に励んでいた私には、先生からの褒め言葉も、嬉しく響きませんでした。
でも、それらが今の自分に確かに生きている、と感じることがいくつもあります。パパッとすぐに弾けるようになる方ではなく、自分自身で練習方法をあれこれ編み出してきた経験は、生徒さんにさまざまな練習の仕方をアドバイスができることにつながっていますし、料理が不得意だと思っていたのは食わず嫌いならぬ“やらず嫌い”だったと気づいてからは少しずつ興味が湧き、世界が広がりました。今では、不得意や劣等感とは、それを認識した時から進歩が始まる、“ちょっとどきどきする素敵なもの”のように思えるときもあります。
劣等感や不得意なことが何もない人よりも、不器用でも自分と正直に向き合い、何かに取り組み続けている人の方が、人として魅力的な気がします。そういう人こそが周囲の人に勇気や力を与えられるのだと思いますし、私もそんなひとりでありたいと願っています。
■第766回 宇宙がふるさと
作曲家の友人Mさんが、まど・みちおさんのいくつかの詩に素敵な歌とピアノ伴奏をつけた作品を送ってくれました。
改めてご紹介するまでもなく、まどさんは一昨年104歳でお亡くなりになった日本を代表する詩人です。まどさんの詩に作曲された『ぞうさん』『一年生になったら』などの歌は、誰もが口ずさんだことがあるのではないでしょうか。お菓子が大好きだった私は、どんどんビスケットが増えていく『ふしぎなポケット』(美智子皇后が英訳されています)という歌がお気に入りでした。
楽器を弾くだけでなく、歌うことも大好きな子供でした。家族も皆音楽が好きでしたし、父はよくドライブに連れて行ってくれたので、お出かけとなると妹と私とでそれぞれ歌集を選んで車内に持ち込み、知っている歌をつぎつぎにふたりで合唱しました。まどさんの歌のいくつかは、定番でした。やはり歌が好きで常に鼻歌を歌い、今もコーラスを楽しんでいる母も、この時ばかりは聴き手にまわりました。
車の後部座席の真ん中には、きまってバスケットがありました。その中には、前の日までに用意しておいたお菓子がたくさん入っていました。ですから、一曲歌っては「次は何を歌う?」、しばらく歌い続けては「ねぇママ、何かお菓子を食べてもいい?」許可が降りると「どれを食べよっか?」…あれこれ楽しい相談を重ねながら、歌ったり食べたり、車窓からの景色を楽しんだり。普段は厳しい父も、私たちがどんな演歌を歌っても、咎めることはありませんでした。車の中は遊園地と同じくらい楽しい空間でした。
学生時代、寮の近くに住んでいる小学生の姉弟にピアノを教えていたことがありました。小学4年生のお姉ちゃんは歌がとても好きで、レッスンの後に自分で好きな歌を選び、私の伴奏で歌うのを楽しみにしていました。
まどさんの歌は、そんな時にもよく登場しました。「言葉の響きを大切にしたい。言葉は、意味だけでなく響きも人間の大きな財産なんです。しかも意味より、響きとの付き合いの方が長い。耳を持って以来ですからね」ご本人の言葉のとおり、まどさんの詩はメロディーにぴったりと寄り添い、歌いやすく覚えやすい。シンプルで、自由に楽しみを広げることができるのが良い童謡の条件かもしれません。
早速生徒さんと送られた歌をうたいました。生徒さんとうたうと、時おり子どもの頃の妹との合唱を思い出します。一緒にうたうということは、たとえそれがユニゾンであっても、声の性質の違い、音域の違いなどをどこかで感じながら呼吸やテンポをそろえ、お互いの声を聴きあいながら音程を合わせるというアンサンブルです。生徒は音程の怪しいところは私の声を頼りにしますが、“ここぞ”と感じるところでは無意識に、自発的に豊かな声を出します。そうした経験の積み重ねは音楽教育において有効なだけでなく、社会での他者とのアンサンブルにもつながるのではないかしら、と思うことがあります。
今の子は本を読まなくなった、とはよく聞かれる声ですが、今の子がまどさんの童謡のような、良い歌を歌うことが少なくなっているようにも感じ、少し気になっています。夏休みというと、学校もこの時とばかりに読書感想文を書かせたりします。読書もいいのですが、本の中の一部でも声に出して音読することや、歌をうたうこともぜひして欲しいなぁと思うのです。
はるがきて めがさめて
私はこの『くまさん』という詩がとても好きで、特に最後の“そうだ ぼくは くまだった よかったな”のところが大好きなのですが、Mさんが数あるまどさんの詩からこれを選んでくれただけでなく、この部分にひときわ綺麗な和音をつけてくれていて、とても嬉しくなりました。
創作意欲の源は、政治・教育・経済・戦争などに対する不満だった、とも語られているまどさん。「生まれたところだけがふるさとではなく、死んでいくところもふるさと。 宇宙をふるさとにすれば、一緒のところになります」まどさんのシンプルな詩の中には、平和への祈りや大切にしたい人生哲学がたくさん隠れているように感じています。
■第765回 曲がったキュウリ
「あなたのは、曲がったキュウリなんだよね」桐朋学園時代、お習いしていた先生のレッスンでそんなコメントをいただいたことがありました。ショパンのエチュードか何かの時だったと思います。「いくら味が良くても無農薬で作られていても、ねぇ。曲がっていたら規格外になってお店には並ばないし、商品にならないんだよ。」
今思えば、先生は私の演奏のすべてを否定することを避けつつ、改善しなくてはならない課題を的確な直喩で指摘されたのだと理解できます。でも、それを言われた当時はそこまで客観的な見方もできなければ気持ちの余裕もなく、ただ「私のピアノは売り物にならない…つまり、モノにならないっていうことを言い渡されてしまったのだわ」と、しょんぼりとうなだれて寮に帰り、その夜思い余ってひとり泣きべそをかいた記憶があります。
男の子には目もくれず(「ボーイフレンドができるって、どんな感じなのかしら?」という憧れはあったけど、じっと我慢!)、ピアノひとすじ。楽譜や音源、関連の専門書や音楽家たちを恋人に青春を過ごしてきた20歳の私にとって、その言葉はあまりにも重く、まるで死刑を言い渡されたように絶望的な気持ちになったのでした。
そんなことがあったからか、ヨーロッパに行って、曲がったキュウリはもちろん傷ついた果物、大小さまざまな人参やトマトが誇らしげに八百屋さんに並んでいるのを発見し、妙に嬉しかったのを覚えています。あちらは“三つで1パック”などという括りはなく、八百屋さんでの対面販売もスーパーも量り売りだったので、規格なんて必要ないし存在もしていませんでした(当時)。店頭で「人参二本と、ジャガイモ半キロ…あと、イチゴを300グラムくださいな」みたいな感じで注文し、お互いに「ありがとう」と言いながらお金と商品を受け渡しします。日本でも、ちょっと前にはどこにでもあったやりとりです。
人参は、季節によっては朝採りのものが立派な葉付きで売られ、すばらしい甘みと香りがありました。イチゴは、もちろん大きさはばらばらですし、傷だらけだったり潰れているものが混じっていてもお咎めなし。そのぶんお値段が抑えられているので、誰も文句はいいません。酸味も甘みもたくましく、ビタミンそのもので、食べると元気がでるようでした。限られた調味料と料理法でも、季節によって野菜そのものの味わいがかわるし、基本的に旬のものしか店
頭に並ばないので、一年中飽きることはありませんでした。
お惣菜やサンドイッチなどの加工品になるとぐんと値が張りますが、野菜やパン、牛乳といった基本的な食品はとても安く、ちょっとの手間さえかければ美味しい家庭料理を安くいただけます。野菜などは種類が多くないので売れ残りによる食品廃棄も少なく済み、基本的にフードマイレージの少ない地産地消なのでそのぶんの運送コストを下げられるのです(そのため、バナナはめったに食べられない貴重な果物だったりしましたが)。
規格に基づいて流通している、日本の立派な野菜。品種改良のために本来の味や栄養が弱まってしまったり、生産性を上げるために余計な薬が使われたり、ひいては規格外のものを廃棄しなければならなくなるというのは、いかがなものか。そもそも、その“規格”とは、誰のため、何のためのものなのでしょう?
あのレッスンから30年が経ちますが、今も私のピアノはおそらく“曲がったキュウリ”のままです。ヨーロッパの八百屋さんに並んでいた不揃いな野菜や果物の姿にふれ、また、皆がそれを気にもとめずに楽しく調理し、食しているのをみて、いつしか私は自分を真っ直ぐな規格品に“矯正する”ことを放棄してしまったのでした。
ひとつひとつが違っているから、面白い。そもそも、芸術にもっともそぐわないのは、“何かと同じ”であることです。ですから、「うちの子は、他の子と同じペースで行動できない」「みんなができることが、どうも同じようにできない」というお母さまのお声を聞くたび嬉しくなって「才能と感性の豊かなお子さんなのですね」とお返事し、彼らの行動と判断には、必ず彼らなりの理由が存在していることをお伝えしています。自分もそんな一人だったので、彼らの気持ちや心理がよくわかるのです。
もし“規格”に合わない人生・・・曲がったキュウリ・・・であっても、その精神がまっすぐひたむきで、周囲を幸せにできる何かを放っているとしたら、それほど尊いことはないのではないかと思います。実った稲穂も山並みも、川の流れも水平線も、自然のものはみんな曲がっています。まっすぐ迷いなくあろうとするほど、その姿はまっすぐではなく、しなやかで柔らかな曲線を描くものなのではないでしょうか。
■第764回 すべては幸せのために
音楽は人の心を癒すもの、という捉え方もありますが、その“心の薬”を作る人の苦労は多くの場合並大抵ではありません。
バッハやモーツァルト、ベートーヴェンなどの“天才”“楽聖”たちは、物心ついた時から人並み外れた才能を発揮して、周囲の理解に恵まれながらそれを開花させていった…という印象を抱きがちですが、彼らのほとんどは才能以上にたくさんの努力をする宿命をも与えられた人たちなのです。
それを乗り越えるためには、音楽的な感性だけでなく精神的な強さも持っていなければなりませんでしたし、あるいは持って生まれた精神力以上にそれを鍛え抜き、襲いかかる困難や死の恐怖を克服することが求められました。天才と呼ばれる人というのは、才能を持って生まれた人というよりも、与えられた運命に立ち向かい、とてつもなく高いレベルでのミッション遂行を追求し続けるという試練に耐えうるタフネスを持っている人なのではないでしょうか。
とはいえ、ぎりぎりのところ、あるいはそれを超えるほどの厳しい試練を、皆が難なく乗り越えられたわけではもちろんありません。あの不屈の精神の持ち主ベートーヴェンですら自殺を考えて遺書をしたためていますし、シューマンも、可愛い娘たちや、誰よりも才能豊かでよき理解者である美しい妻クララという家族に恵まれてなお、苦しみを乗り越えられずライン川に投身自殺を図りました。甘美なメロディーで人々を魅了したマーラーもラフマニノフもそれぞれ精神を患い、精神科医による治療を受けていました。特にマーラーとフロイトの関わりは、映画のテーマにも取り上げられています(『マーラー 君に捧げるアダージョ』)。
“心とは氷山のようなものだ。その大きさの7分の1を海面の上に出して漂う”という格言でも知られるフロイトですが、彼は、人間には無意識と有意識があって、無意識による影響の方が有意識からのそれよりもはるかに大きいと考えました。人は無意識的に過去のトラウマによって支配されているという“原因論”も、彼の理論の特徴の一つということになりますが、それに真っ向から反対したのがアルフレッド・アドラーという人物でした。彼はトラウマなど存在しないと唱え、人間は目的を変え過去を意味づけし直すことで人生を変えることができるし、一般的に変えることが困難だとされている“性格”も、実はいつでも選択し直せるという考えの持ち主です。
“幸福になる方法は、自分で実験してみないとわからない”“生きる意味や価値を考え始めると、我々は気が狂ってしまう。生きる意味など存在しないのだから”と述べたフロイトとは対照的に、アドラーがゴールと考えた幸福とは“共同体感覚”という概念に象徴されるものです。それは他者を仲間と見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じるために、「自己への執着」を「他者への関心」に切り替える必要があるというもので、そのための条件として彼は「自己受容」「他者信頼」「他者貢献」などを挙げています。つまり、ありのままの自分を受容し、無条件で他者を信頼する中で、“私は誰かの役に立っている”という貢献感を実感することこそがアドラーが考える幸福だということです。
なんだか堅い話になってしまいましたが、音楽も心理学も目指すところはただ一つ。幸福で豊かな人生のためのツールでありたい、ということなのではないでしょうか。そのために偉大な作曲家たちがときに自分を極限まで追い込み、葛藤し、誰かの評価を求めることから離れてとことん自己の表現を追求しつづけたことをその作品から感じるとき、私は言いようのない感動と感謝を抱くのです。
もちろん、作曲家たちからの語りかけはいつも明るく、希望に満ちているとは限りません。ときに暗く、深い悲しみに包まれていたり、堪え難いほどの孤独をうったえてきたりします。でも、だからこそ私たちは、いつも前向きで幸せに満ちている人には気後れして打ち明けられないような心の痛みをそこに投影し、そっと打ち明けることを許され、それによって慰められたり癒されたりするのではないかしら、とも思うのです。
彼らの作品のメッセンジャーとして、その真意を聴く方にお伝えするミッションを遂行するのが、私たち演奏家の仕事です。何をどう組み立ててどのように語ったら聴いてくださるかたの幸せに貢献できるのか…。作った人たちの苦労には遠く及びませんが、そんな試練が与えられていることにもっともっと感謝したいと思うこの頃です。
■第763回 “ゆらぎ”とともに
今日から7月。7月というと、未だに「もうすぐ夏休み!」というイメージが先に立ち、うきうきします。実際にはコンクールの審査のお仕事が立て込んで、けっこうバタバタする時期なのですが…。
子供の頃は、夏休みに家族みんなで父方の実家のある群馬や、母方の実家のある目黒に帰省するのが、年間の数あるイベントのなかでも一番のハイライトでした。そして、なぜか遊園地やプールに連れて行ってもらったことよりも、お昼のおそうめんの薬味に使う紫蘇の葉を庭に摘みにいったり、なんでもない公園を従兄弟たちとお散歩した思い出の方が印象に残っていたりするのです。
私が小学校低学年だった当時、群馬の実家では祖母が母屋の屋根裏部屋でお蚕を飼っていました。それが夏休みだったのか冬休みのことだったのかは覚えていないのですが、おそるおそる覗き込んで少しだけ触ってみたことがありました。はかない小さな命が感じられました。
先日、梅雨の晴れ間に風通しをしておこうと祖母から譲りうけた正絹のお着物を広げたら、ふとその屋根裏部屋の思い出がよみがえり、お蚕とオシラサマのお話が頭をよぎりました。
“オシラサマ”は東北地方で信仰されている神さまで、一般的には蚕の神、農業の神、馬の神とされています。柳田國男さんの『遠野物語』に、オシラサマ信仰のお話しがでてきます。
“昔、ある村に美しい娘がいました。16歳になった娘は立派な馬に出会い、一目で恋に落ちました。娘と馬はすぐに想いを通わせ合い、一緒に馬屋で暮らすようになりましたが、不審に思った父親は馬を憎み、怒りのあまり馬を殺してしまいます。そして殺した馬の首をはね、桑の木に吊るしました。娘はたいそう嘆き悲しみ、冷たくなった馬の首を抱きしめて離しませんでした。すると、馬の首が娘を連れたまま天へと昇って行くではありませんか。父親は天に昇っていく娘に叫びます。「わしが悪かった、許してくれ!」娘は答えました。「いいえ、私たちはお父さんを恨んでおりません。明日の朝、庭の臼の中を見てください。それが私たちの贈りものです。お父さんへの気持ちです」
翌朝、父親が臼の中を見ると、そこには小さな虫が数匹動いていました。虫の顔は馬の顔でした。大事に育てていると、それは繭を作りました。繭から絹糸をとって、村は潤っていきました。”
蚕は天の虫と書きます。そして、一匹二匹…ではなく、一頭二頭と数えます。日本語の生き物の数え方は、他の言語に類を見ないほど複雑だと思うのですが、例えば一匹と数えるのか一頭と数えるのかは大きさだけで区別するのではなく、どんなに小さな生き物でも貴重であったり、人間にとって大切な役割をもつ生き物(実験用のマウスなど)は“一頭二頭”と数えるのだそうです。でも、お蚕を一頭二頭と馬のように数えるのにも、天の虫と書くのにも、なにか特別な理由があるような気がして、想像を掻き立てられます。
日本の昔話、民話には悲しい余韻を残すものが少なくありませんが、そのぶん心の深いところに触れる美しいものが多いように感じています。淋しかったり悲しかったりする物語のなかに、人の清らかな心根がほのかに灯ってみえたり、人と人との関わりのありかたや自然への畏敬の念を感じさせてくれたり…。
そこに産まれる、ただ単純に「楽しい」「悲しい」だけではない感性の“ゆらぎ”は、実は人間にとってたいへんに大切なものなのではないでしょうか。なぜなら、私たちが共に生きている自然もまた、常に“ゆらいで”いるものだからです。
それはまるで、心に柔らかく寄り添って響く、シューベルトの音楽そのものだ…などと日記に書いた翌日、読んでいた本のなかでドイツ歌曲の大家、ディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウ氏が、シューベルトの音楽についてこんなことを述べていらっしゃいました。「自然は、暗いときは暗いが明るいときは明るい。が、暗くて明るいことも、明るくて暗いこともある。それはそのまま、シューベルトのトーンのようだ。シューベルトはまったく“自然”だ。」
四季折々の季節を愛しみ、そのうつろいに心を傾け、うたを詠んだり旬の味覚を楽しんだりしながら心豊かに月日を重ねてきた私たち日本人は、あるいはもっともシューベルトに親しむ素質をもっている民族なのかもしれない…。それを読んで、こっそり幸せに浸ったのでした。
■第762回 大地とのアンサンブル体験
梅雨の真っ只中の小雨のそぼ降るある日、都内からもファンが訪れる勝田台の南インド料理店“葉菜”のオーナーシェフ吉田さん主催の「身近な野草を採って食べる会」(仮称)に参加しました。ナビゲーターは大森にある南インド料理の草分け的超名店“ケララの風”のオーナー沼尻さん、参加メンバーは10名に満たない贅沢な会でした。
沼尻さんは、その人生がそのまま映画の題材になるような方。商社マン時代、お仕事で1980年から1982年にかけて滞在したケララ(南インド)で出会った家庭料理ミールスの素朴な美味しさに目覚め、あちこちのミールスを食べ歩きして帰国するも、当時の日本にはどろっとしたカレーをナンで食べる北インド料理店しかなく、南インド料理シックになってしまいます。そしてついに一念奮起。すさまじい情熱で、まだ食材も今ほど入っていなかった状況にもめげず、研究に研究を重ねて南インド料理の世界を作りあげていったのです。
2000年からは本業の傍ら、会費制食事会“グルジリ”を主催。会費といっても、利益は完全に度外視の数百円の実費だけ。あちこちの公民館や集会所に集まった人たちに料理をふるまい、南インド料理の素晴らしさの伝道師になったのです。北海道から沖縄まで、呼ばれれば出向いていって南インド料理を作るのですが、どこへ行っても参加代金は食材の実費と交通費のみで、謝礼は断固として受け付けなかったそうです。食事会“グルジリ”はこれまでに日本各地で260回以上も開催され、参加メンバーは4000人以上にのぼっているとか。
それだけではありません。沼尻さんは、それまで日本で生育されていなかった南インド料理にはどうしても必要なカレーリーフの栽培に挑み、気候の違いから無理だと言われながらも沖縄の契約農家と掛け合って、日本で初めて見事成功させた方でもあるのです。
野草を採集する川にたどり着く前、コンクリートの駐車場に降り立った時から、沼尻さんの目線はもう土へ。ちょっとした所にも食べられる野草はたくさんあるのです。一方、街路樹などには毒性のあるものが使われることが多いのだとか。例えば、ポピュラーなキョウチクトウが猛毒を持っているとは知りませんでした。「毒が強いから虫がつきにくい。生命力も強くて手入れがラク…それで適しているということになったのです」
スズランを始め、人間にとっては可愛らしい花を咲かせる植物にも毒性を持つものがありますが、例え犬を散歩させていたとしても彼らは見向きもしないのだそうです。「動物は危険をちゃんと感じ取りますからね」これは何類の仲間、これはアクが強いが下処理をすると美味しい…など、レクチャーを受けながら新川を散策し、匂いを嗅いだり口に含んでみたりしながら野草やスパイス(完全無農薬のマスタードシードも??)をあれこれ採取しました。
川沿いから吉田シェフの畑を経て、一同はいよいよ調理&試食会場、“葉菜”さんへ移動。沼尻さんの手際の鮮やかさ、即興を交えての調理センスに脱帽しつつ、店内に立ち込める芳しい香りに「早く食べたい!」と、みんなすっかり食べる気まんまんです。
シロザのポリヤル、セリのおひたし、蕗のピリ辛煮、スベリヒユの叩き、よもぎと生姜の混ぜごはん、カキドオシとクールミントのフレッシュハーブティーなどが、あっという間にテーブルに並びました。
さっと湯がいてシンプルな調味料で味付けしただけなのに、それぞれの素材の香り、食感、味わいの豊かさにビックリ!みんなで「いい香り〜」「すごく美味しい??」を連発しながらもりもり頂き、感動を分かち合いました。
「昔はね、食用に畑などで栽培される植物は蔬菜と呼ばれ、野生の植物を野菜、山菜とは区別されていたんです。山菜も栽培されるようになって違いが曖昧になってしまったので、今は一緒くたに野菜と呼ばれるようになっていますが、本来はこのような野草こそが“野菜”だったわけです。なのに、どうも野草は野菜よりも地位が低いみたいな扱いになっていて、しゃくに触るんだなぁ」…そうおっしゃる沼尻さんの言葉の端々に、自然の恵みに対する敬意や愛情が感じられました。
川べりのお散歩、着ているものが濡れるのも気にせずしゃがみこんでの野草の採取、鞘からマスタードシードを取り出す作業…そのひとつひとつがとても楽しくて、改めて命を頂くことへの感謝をかみしめました。大地の恵みの豊かさや、自然の一部になれたような感覚を肌で感じた、とても貴重な体験でした。
■第761回 “運・根・鈍”考
その言葉を知ったのは、重要無形文化財保持者の女性染色家、志村ふくみさんのエッセイ『色を奏でる』でした。“運・根・鈍”…成功するために必要なもの三つを端的に表す言葉で、その字の表すとおり運気、根気と、粘り強く取り組み続ける鈍いほどの不器用さ、を意味しています。
どれも若い方にはちょっと重いなぁ、と感じられるかもしれません。運に恵まれるのは自分の努力だけではないし、根気強く続けても、その先がみえない不安に果たして耐えられるものかどうか。ましてや、鈍、となると、ハードルが高いような低いような、よくわからない感じを受ける方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まず、運。天から授かるもの、意思を超えて働くちから、というイメージが強い言葉ですが、成功している人は確かに、必ずといっていいほど「自分は運に恵まれています」と話します。どうやら運というのは、巡ってくるのを待つものではなく、掴みに行くものであり、それを幸運であると肯定的に受け止めるかどうかということかもしれません。
例えば私の場合、ピアノを勉強させてもらえた環境に恵まれたのは大きな“幸運”でした。運動神経にも健康状態にも深刻な問題はなく、着々と年齢を重ねながら今もなお演奏活動を続けられているのも、幸運としか言いようがないことです。でも、同じ状況でも見方によっては「男性に産まれなかったし手が小さいために、ラフマニノフが存分に弾けない。運がない」と取れないこともありません。「音楽家の家庭に生まれなかったから、幼少時代から有名ピアニストへのレールを歩むことができなかった」と考えることもできるかもしれません。
マイナスを挙げ連ねて嘆くより、物事をポジティブな受け止め方ができる人のほうが、成功を手に入れる可能性をより多く持っている、ということなのではないでしょうか。
次に、根。とても強い言霊を感じる文字です。根とは、言うまでもなく生命の源、物事の土台をなすもの。大地にしっかりと根ざし、こつこつとできることを積み重ねていくのは、それが何であれ人間の尊い営みなのではないでしょう
か。何かの目標のために努力を重ね続けられるかどうかが、目標に達することができるかどうかの鍵なのは間違いありません。
個人的にもっとも心に引っかったのは、鈍という文字でした。ここでの“鈍”は、感性が鈍い、ということではなく、才能に甘んじて怠ることなく愚直に精進する、ということだと思います。つい先日安打数の世界記録を達成したイチロー選手は「僕は天才ではありません。なぜかというと、自分がどうしてヒットを打てるかを説明できるからです」というコメントを述べていました。「どんなに難しいプレーも当然にやってのける。これがプロであり、僕はそれにともなう努力を人に見せるつもりはありません」とも。鈍、とは、単にできないことをできるようになるために人知れず努力するだけでなく、他の人には真似できない高みまで、丁寧に歩み続けることなのではいでしょうか。
彼のコメントを聞いていたら、天才かどうかなど、たいして重要なことではないような気がしてきました。それどころか、成功か失敗かも、どっちでもいいことのように思われてきました(何が成功で何が失敗なのかは、ある程度の時間を経て振り返った時に初めてわかるものだったりしませんか?)。大切なのは、人がその精神と命の輝きを謳歌し、自分らしく…自然体で、希望を持って人生を歩み続けているか、ということに尽きるのではないでしょうか。
「人から盗んだものは身につくが、教えられたものは忘れてしまう」以前、高名な先生がそんなことを話していました。「習うより慣れろ」以前に、「習うより盗め」だと。だから、見込みのあるお弟子さんにはあえて多くを教えないよう心がけていらっしゃるそうです。相手がそれに“気づき”、それを“盗む”のを待つのです。できるようになるよう、教えてあげたい教師側には我慢が必要ですし骨が折れることですが、長い目で見たら大きな成長につながる教えになることでしょう。
そういえばバッハが息子たちの音楽教育のために書いた『インベンションをシンフォニア』という曲集には、ひとつの指使いも書かれていません。「自分で見つけろ」と言わんばかりです。
愚直にじっくり時間をかけて…“運・根・鈍”のうち、鈍という文字に一番愛着を感じます。
■第760回 ピアニッシモのその先に
「(前略)わたしは、わたしの愛を拒む人たちすべてに無限の愛を抱きながら遠くの地へと去った。そして、長い年月のあいだ歌をうたって過ごした。わたしが愛をうたおうとするとそれは悲しみになった。悲しみをうたおうとすると、それは愛になった」…“わたしの夢”と題されたこの散文の作者は、シューベルトです。
早世した天才というとモーツァルトが真っ先に浮かびますが、彼が35歳でこの世を去ったのに対してシューベルトは31歳で天に召されています。その短い生涯のあいだに、1000曲もの歌曲をはじめ信じられないほど多くの素晴らしい作品を残しているのですから、これを天から授かった稀有の才能といわずしてなんといったらよいでしょう。
彼の音楽はモーツァルトのように「ほら、きれいで素敵でしょう?ねえ、僕を…僕の音楽を好きになって!」と無邪気に呼びかけることもなければ、ベートーヴェンのような完全無欠さで私たちを魅了し圧倒することもありません。リストのように絢爛豪華さをひけらかすところもなければ、ショパンのように激しい情念を美しい薔薇の花束の向こうに隠し持っていたりもしません。文学的詩的な香りを纏ってはいますが、シューベルトの息吹は言葉の存在をタンポポの種のようにふわりと吹き散らし、音楽の萼や茎の素朴な造形を見せてくれます。ブラームスのような内向性を感じさせるところもありつつ、その眼差しは自分の中ではなく外へと向けられています。
彼のメロディーはふと口をついてでた鼻歌のように何のてらいもなく現れ、彼の音楽はいつの間にか人の心に寄り添い、その傍にそっと一輪の花を置いて、知らぬ間に去っていくのです。それはこちらが悲しいときも前向きな気持ちのときも、親しみ深げな微笑みを浮かべてそばにいてくれる…それが私のシューベルトの音楽観です。
とはいえ、演奏する側にとっては都合のいいところばかりとは限りません。シューマンに「天国的長さ」とも評されたとおり、その作品は時として長大になってしまい、幾度となく繰り返されるモティーフをどう演奏したものか、弾き手を悩ませることも少なくないのです。ただ立派に弾こうとすると拒絶される反面、慎み深さと大胆さをもってイマジネーション豊かに表現しなければ、その魅力を伝えきれないのです。
今手元に、まだまだピアノが現在のものへの改良の途中だった1826年に書かれたシューベルトのピアノソナタ第18番の楽譜があります。スタインウェイ(1863年創業)はもちろん、ベーゼンドルファー(1828年創業)も創業する前に書かれた作品ということになります。
その壮大なピアノソナタの第一楽章は、ピアニッシモ(pp)で心をそっとノックするように幕を開け、やがてさらに弱く弾く指示ピアニッシシモ(ppp)が登場します。この長い楽章のほとんどの部分は、春霞のようなp(ピアノ)からpppのグラデーションで語られます。それは当時現存していたピアノの持つダイナミックレンジの範囲、限界を超えた指示であり、イマジネーションだといえます(ベートーヴェンの最晩年のピアノソナタにもpppは登場しません)。
先日、レッスンで大人の生徒さんが、この頃では日本の伝統文化の素晴らしさを外国の方に気づかせてもらうことが多くなっている気がする、とおっしゃいました。「お能だって、外国の方のほうがその独特の幽玄な世界をよく理解してくださっていたり、興味を持ってくださったり。私たち日本人のほうが、『お能動きが少ないし顔も面で見えないし、難しいわ』なんて、よく知らないまま敬遠してしまいがちなんて…勿体無いし情けないことですよね。」
幽玄、という言葉にハッとしました。幽玄の美…感情を揺さぶるような強烈なものの対局にあり、暗さの中にこそ明るさが輝き、心を澄ませて聴くほどに深い世界が広がっていくその世界観は、シューベルトの幻想的な音楽的インスピレーションにつながるような気がしたのです。シューベルトのピアノ、ピアニッシモ、ピアニッシシモは、単に“弱く”という意味ではありません。それは心に秘めたもの、現実の事象や理論を超えたもの…まさに“幽玄”の美しさに近いものの表現を求めているように思われたのです。
この秋、新たなコンサートシリーズをスタートさせることになりました。シューベルトの連続演奏会です。一回目のサブタイトルは“シューベルトのファンタジー”。プログラム後半では、念願叶って日本を代表するヴァイオリニスト、木野雅之さんと共演させていただくことになりました。どこまでシューベルトの幻想…幽玄の世界に近づけられるか、とても楽しみです。
■第759回 手作りのぬくもりを
“ご当地グルメ”という言葉ができたのはなん年前でしょうか?あたかも郷土料理のようなイメージがありますが、それは地域振興活動の一環として伝統にこだわらず開発され、ここ10年ほどでずいぶん盛んになった“ B級ご当地グルメ”なども含まれるのだそうです。
郷土料理は大好きなのですが、個人的にはそういったカテゴリーの“ご当地もの”にはあまり食指をそそられません(なんていうと、随分自分が歳をとったような気持ちになるのですが)。いかにも地域に根付いたものであるかのような印象を与えるけど、実は観光資源として企画されたものや、地元の人は必ずしも日常的に食べないような料理も少なくないし、何より人間の営みにとって大切な食文化をビッグビジネスに転用しようとしている“仕掛け人”の影がチラチラするのが、どうも気になるのです。
と、堅苦しいことを述べてはみたものの、ご当地ならではのお土産をいただくのは素直に楽しいものです。そもそも、食文化の地域性や郷土料理に興味を持ったのは、幼いころ、出張が多かった父が、よく出張先のお土産を買って帰ってきてくれたことがきっかけでした。その場所にしか売られていない、見たこともないお菓子を目にしたり食したりするのは、食いしん坊の私にとってなんとも嬉しいことでした。出張帰りの父から「お土産があるよ」という言葉を聞くと、私に輪をかけた食いしん坊だった妹とともに「わ〜い、わ〜い〜!」と、小躍りして喜んだものです。
“地方の味”への興味にさらに火をつけたのは、桐朋学園大学時代の寮生活でした。夏休みや冬休みといった長い休暇のあと、全国各地から来ている友人たちがそれぞれに故郷からお土産を持ち帰り、お互いに配り合うので、ちょっとした“ふるさと物産展”状態になることもありました。
寮では朝6時から夜10時まで、音をだして(練習して)いいことになっていましたので、夜10時を回ったら相手の練習の邪魔になる可能性はほぼありません。長期の休み明けには、その頃になると誰かがドアをノックします。「今、いい?これ、お土産。食べてね!」その手には、美味しいものの入った小さな袋が握られているのでした。甘いもの、しょっぱいもの…様々でしたが、もらうのも嬉しければ自分が買ってみんなに渡すのも楽しいのです。「前回はコレ
だったから、今回はこっちかな?あ、でも(同じ故郷の)◯◯ちゃんと被っちゃうかな」などとあれこれ考えながらみんなの顔を思い浮かべると、早く会いたくて仕方なくなるのです。
当時は今のようにインターネットも“お取り寄せ”なんて言葉もありませんでしたから、一つ一つがとても貴重で、「ああ、今度これを食べられるのはいったいいつかしら?」なんて、今考えると可笑しくなるほどしみじみとした感慨を抱きつつ、一期一会の心持ちでありがたく頂いたものでした。なんでもすぐに手に入る時代ではなかったぶん、感謝も楽しみも大きかったように思います。
食べ物だけではありません。楽譜も音源も、今はなんでも気軽かつ安価(無料の場合も!)にダウンロードできるようになって、確かにたいへん便利になりました。でも、学生時代、先生から新たに曲をいただいて大喜びしつつ、それがいったいどんな曲なのか、楽譜はどうなっているのか心を弾ませ、お財布を握りしめて楽譜を買いにいったり、アルバイトをしたりお昼代を節約したりしてやっとの思いで手に入れたCDを初めて聴く時のときめきは、得難いものでした。
卒業後、ハンガリーに留学することになり、お料理やお菓子の類はもちろん、キャベツも人参も牛乳も、日本で親しんできたものとはずいぶん違うことに新鮮な感動を覚えました。そもそも、水の味も違うのです(ハンガリーでは水道水を飲むことができます)。食べ物は、地域の気候や文化、価値観、時に宗教観までもを反映する、人間の命にとってだけでなく、心にとっても大切な支えになるもの。尊い地域性や伝統、先人の知恵が染み込んだ郷土の食文化が、単なる一時的・作為的な経済効果のために利用されている“ご当地グルメ”と一緒くたにされてしまいかねない傾向に危機感を覚えるのは、私だけでしょうか。
例えば、その土地にある隅々まで生産者の目の行き届いている畑や、家族経営の小さな工房から生まれる、かけがえのない豊かさ…そんなものを感じていただけるような、小さなレッスン室からの“手作り”の音楽を、みなさんに心を込めてお届けできるピアニストであること、そうあり続けることが、大きな夢です。
■第758回 すべてはアートにつながる
音楽の畑ではない専門分野でお仕事をされている方とお話しするたび、共通する悩みの多さに驚いています。デザイナーや作家さん、農業や接客業の方も、つい口をついて出るつぶやきには相通じるものがあるのです。
中でも顕著なのは“「これが良い!」と自信を持ってクライアントやお客様に出すものが受け入れられるとは限らない。むしろ、自分としては納得がいかない妥協点があるようなものに需要が集まる傾向があり、その狭間に葛藤することが多い”ということ。
大企業の中で自分のアイディアが採用されるチャンスを待つよりも、小さくても自分の感性を発信できる体制を構築すべく起業した、文房具のデザインと制作を行っている若者のドキュメンタリーを見ました。SNSなどで消費者にどんな製品があったらいいと思うか意見を募り、それを参考にする一方、基本的には「みなさんの意見をできるだけ多く反映したようなものは作らないようにしている」のだそうです。そうすると「結果的に誰も欲しいと思わない製品になってしまう」からだと言います。
大きな企業で営業に携わっている方には、彼の理念は矛盾しているように聞こえるかもしれません。が、私たち自営業者、あるいはクリエイティブな(あるいはアーティスティックな)仕事に携わっている人間にとっては、非常によく理解できるものです。誰にとっても使いやすく、気に入られやすく、欠点の少ないもの…言い換えればそれは、無難である反面個性のないものであり、他を見渡せば容易に同じようなものが見つかるような、特殊性や付加価値の薄いもの、ということになるからです。
彼は、決してみなさんの意見を無視しているのではないのです。それらを発想のベースにすり込んだ上で、別のベクトルにイメージを膨らませることの方が、ダイレクトに意見を反映させるよりも難易度が高い。彼は、あえてそれに挑んでいるチャレンジャーなのです。「お客さまのニーズをこんなに思慮して作りましたよ」という“媚び”よりも、「こんなモノがあったらちょっとだけ生活が楽しくなると思って作りました。どうでしょう?」と、相手の人生(大袈裟に言えば)や価値観、感性に“突っ込み”を入れ、積極的な“提案”をして、お客様との関わりをぐっと求めているのです。
「これなら売れる、というものよりも、最初のお客である自分を喜ばせる(納得させる)ような製品を作りたい。」彼のこのコメントに「よし、よく言った!」と、思わずどこかのお父さんのような掛け声をかけてしまいました。実に、私たちが演奏会のためのプログラムを考えるときも演奏するときも、まったく同じ思いなのです。
「こんな曲を並べれば、集客しやすい」「こんな演奏をすれば、ウケやすい」といったノウハウを、私とてわかっていないわけではないのです。でも、できるだけしません。それをすることは、お客さまに対してまさに“上から目線”で“与える”という立場からのアプローチになってしまうからです。みなさんがよくご存知である曲のちからに甘えることなく、「聴いたことがない作品を演奏しても、本当によい演奏ができたなら、きっとその素晴らしさは伝わるはず」という信念をもって、また「表面的な語り口の巧みさで満足してもらうよりも、もっと深い、音楽の(あるいは作品の)本質的な豊かさを分かち合いたい」と願って、納得いくまで創り上げることは、お客さまと対等に感じ合えることを信じていればこそできることなのです。
先日、とある場所でのデュオのサロンコンサートに出演しました。聴きにいらしてくださった方々が、異口同音に「客席(お客様)の雰囲気がとてもよかった」「ステージと客席が、音楽によってひとつになっているような“一体感”があった」とおっしゃってくださったのは、何よりの喜びでした。
そうなのです。演奏会を作るのは作曲家と演奏家だけではないのです。お客様がどう感じ、どう聴いてくださっているかは舞台にいる私たちにも驚くほど明確に伝わり、それは自ずと演奏に反映されるので、実はお客様も大切な“共演者”なのです。
良き消費者、良き聴衆が、さらに豊かな創造を生む…実は私たちひとりひとりがクリエーターであり、アーティストなのだと考えると、人生が一段と楽しいものになるような気がするのですが、如何でしょうか?
■第756回 “障害”を“個性”に
ゴールデンウィークも明け、新学期から一ヶ月が経とうというこの時期は、太陽が輝きを増し、新緑がみるみる“深緑”に変わる一年のなかでももっとも爽やかな季節ですが、一方では“五月病”なる症状が心配される時期でもあります。
五月病は病院などで使われる正式な病名ではないし、きちんとした定義もないとのことですが、医学的な見地からみると、環境の変化についていけないことで起きる“適応障害”という精神疾患に近いもののようです。
厚労省のホームページの『こころの病気』のインデックスをみると、他にも“発達障害”“解離性障害”“強迫性障害”“摂食障害”“パーソナリティー障害”などから“性同一障害”まで、こんなにあるものかと驚くほどたくさんの“障害”という名のつく病名が並んでいます。
私自身も、摂食障害を起こしかかった(起こした、といえるかもしれません)ことがありますし、それらの疾患が本人のみならず家族など周囲の人にとっても辛いものであることは、理解しているつもりです。でも、例えば発達障害の一部に関しては“障害”という単語を当てはめるのが果たして適切なのだろうか、と疑問に思ってしまうのです。
「発達障害はいくつかのタイプに分類されており、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害、チック障害などが含まれます。生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点が共通しています。」厚労省のサイトでは、このように説明されています。
そこで言われている“障害”は確かに、“一般的な人”からみると特異にみえることかも知れません。もちろん、症状には重度なものから軽度なものまで様々あると思いますし、一概には言えないのも承知していますが、何かが“欠落している”としてもそれだけだという人は少なく、そういう人はどこかに“一般的な人”よりも優れた面を持っているように思います。実際、発達障害とされている人の中には歴史的にみると天才性を持った人が少なくなく、そうした“障害”を持っている人たちが後世に尊いものを残していたり、科学や芸術の分野で新しい世界を切り開いて、現在への礎を築いてくれていたりすることがたいへん多いのです。
「生まれつき脳の機能の一部に障害がある」といわれると決定的な欠陥があるようなイメージを持ってしまいますが、もしかするとそれは大いなる個性なのかもしれません。第一、“障害”を持っていることが社会への貢献につながるとしたら、果たしてそれを“障害”と呼んでいいものかどうか…。
専門外なので、ここでこれ以上発達障害について深く触れるのは避けますが、どうも私たちはこうした『こころの病気』の他にも、必要以上に“一般的な人”の範疇に収まっていなければならない、という強迫観念に囚われ過ぎているような気がします。血圧、コレステロール、血糖値、体脂肪率などなど、数え切れないような項目が、健康とされる値の範囲でなければならないとか、睡眠時間を◯時間を取るのが望ましいとか、一日30品目の食品を摂取すべき、などなど、世の中には“一般的な人”としてクリアしていなければならないノルマのようなものがたくさんある一方で、その数値や“定説”は、刻一刻と変化していくのです。
“障害”を持っていることや持つに至ったこと、また“一般的な人”としての基準を満たしていなことは、そんなにもいけないことなのでしょうか。避けなければならない、恐ろしいことなのでしょうか。そう思い込むことは、もっと広義において「友達がたくさんいる子は良い子で、友達が少ない子は社会性や適応能力の低い子」のような、偏った見方、差別的な考え方につながる危険を孕んではいないでしょうか。
障害も疾患もその人の個性と捉え、いろいろな人がお互いに尊重しあい助け合って、「1+1=無限大」になるような素晴らしい化学変化が起こるような社会こそが、成熟した社会といえるのではないでしょうか。
芸術は、生まれつきの“障害”も天から与えられた“才能”も(この二つは同じようなものに思われてなりません)“個性”に昇華させ、ひとりひとりのパーソナリティーを謳歌し、共に成長しあうために人間だけに与えられた最強のツールだと、心から信じています。
■第755回 青春のシンボル”よ、永遠に
突然ですが、これを読んでくださっているあなたは今、何十代でいらっしゃいますか?
世の中の動きがあまりに速く、それにともなう言葉の流行り廃りにもめまぐるしいものを感じています。つい最近誕生したように思っていた“癒し系”や“ゲットする”なども、一説によるとすでに“死語化”しているといいますし、ある友人は「若い子に“イタメシ”って言ったら『え?それ、チャーハンとかのことですか〜?』って言われたわ。通じなくて、すごくショック!」と落胆していました。
“マッハで(急いで)”、“イケてる”、“オソロ(おそろい)”、“ダベる(おしゃべりをする)”のような単語がどんどん生まれては廃れていくことは、むしろ自然なことのように感じますが、昔から親しまれている愛すべき言い回し、言葉がそれらと同じように“死語”の扱いを受け、私たちの会話から遠ざかってしまうことには、一抹の寂しさを感じます。
例えば、今は“ミュール”と言われているサンダルは、昔はつっかけと呼ばれていました。ベストやジレはチョッキと呼んでいましたし、傘はこうもり、ティッシュはちり紙、ノートは帳面…。昔ながらの呼び方には、なにか語源を辿りたくなるような親しみやすさが漂っているような気がするのです。
また、俗語的ではあっても、“骨皮筋えもん”、“お茶のこさいさい”、“への河童”、“ホの字”…これらの言い回しにはユーモアやリズム感、肩のこらないリラックス感とともに、今の言葉には少なくなってしまったウィットや、使うのが愉しくなるような魅力があるように思うのです。
そんなことを、今朝鏡を見ながらふと考えてしまいました。それというのも、自分の顔に“ニキビ”を発見したからです。(「もう“ニキビ”と呼ぶのはおかしいですよ。“吹き出もの”と言いなさい」と怒られてしまうかもしれません。でも、医学的には同じもののことなのだし、出世魚じゃあるまいしニキビはニキビでいいのではないか。第一、“吹き出もの”なんて、火山の噴火みたいでスケールが大きすぎはしないか…と違和感を覚えるのは、わたしだけでしょうか。)
かつてニキビは“青春のシンボル(もちろんこれも死語)”と呼ばれ、「若さの証しなんだから、気にしない気にしない!」というニュアンスが醸しだされていました。今思うと、なかなか気の利いた表現です。その延長線上に、例えばシワのことを“微笑みの年輪”、シミのことを“思い出の足あと”なんて呼びかたがあったら、ちょっと会話も弾んだりしないでしょうか。「あら、またこんなところに思い出の足あとが…」うん、ちょっとロマンティックかも!
巷では、小学生の英語教育をどうするかといった議論が絶えませんが、複雑にして豊かな日本語を正しく理解し、使いこなすことができていない子どもたちに外国語を教えることが、それほど重要なのでしょうか。それよりも、将来外国人に日本語のなんたるかをきちんと伝えられるようになるためにも、日本語の美しさをしっかりと学ぶことの方がずっと大切なことだと思うのです。例えば、年々増える一方の外来語を必要以上に(絶対、ではなく)使わないで授業をする…という日を設けて実践することも、外国語を捉える良い下地になるかもしれません。言語をマスターする鍵は、それをいかに自国語と“比較”し、違いを的確に捉えることができるか、ということにあると思うからです。
と、威勢のいいことを言ったのはいいけど、もしピアノのレッスンを外国語なしに行うとなると、かなり頭を使うことになりそうです。音楽用語は、ドレミはもちろん、フォルテ、ピアノ、スタッカート…ほとんどが外来語(イタリア語)なのですから。「ここに書かれている“強奏(フォルテ)”は、そんな大音量が必要なのかな?」「この奏鳴曲(ソナタ)は、最終楽章が遁走曲(フーガ)になっています」「速度(テンポ)があまり早すぎると付点の律動(リズム)が乱れてしまいますよ」…あらら、これは大変!そもそも外国のものなので、無理もないですね。
外来語を一切使わないようにするのではなく、日本語も外来語も“適切な使い方”をきちんと学ぶことこそが肝要であり、様々な言葉をそれぞれの良さを失うことなく共存させ、表現し合う喜びをもって使えるよう導くことが理想なのかもしれません。ちょうど、様々な個性を持つひとりひとりが、そのパーソナリティーを伸び伸びと発揮し、自分とは違う個性も受け入れ、お互いを認め合って楽しみながら成長していくことが望ましいように…。
■第754回 名物にウマいものあり
今日は、“八千代ゆりのき台のつつじ祭り”。会場は自宅から歩いて2分ほどの、駅のむこうの目抜き通りです。歩行者天国になった通りは、たくさんの出店や家族連れで大賑わい。自宅前の遊歩道も朝からひっきりなしに人々が行き交い、「こんなに人が住んでいたの?」と、びっくりしました。特設ステージでは次から次へとさまざまな団体による演目が披露され、お祭りを盛り上げていました。
ゆりのき台の中央を南北に縦貫する並木道“ゆりのき通り”は、八千代市を代表する景観道路とのことで、両側には八千代の“市の木”であるつつじの植栽が約1.7キロにわたって続いています。このお祭りは何か地域の特色を生かしたお祭りを、との考えで10年前に誕生したものです。
都心からは少々離れてはいるものの、駅を降り立ってすぐに豊かな自然が感じられるところは、とても気に入っています。お散歩コースにもジョギングコースにも事欠かず、夜中の12時まで営業している大型スーパーが二つもあるなど、お買い物にも不自由しません。美味しいイタリアンのお店やおしゃれなカフェもあれば、医療機関、学習塾や居酒屋さんも揃っています。四季の移ろいを感じることができる緑地公園もあるし、市役所も警察署も郵便局も徒歩圏。生活しやすい街であることは間違いないでしょう。
「いや、この規模の街にして本屋さんが一軒もないのはどうかな」「それをいうなら、気の利いたバーもないよ」いろいろな声が聞こえてきそうですが、いずれにしても店舗や施設は有無だけではなく、それがいかに地域に“根付く”かが重要なポイントなのではないでしょうか。その街の名物になるようなお店、他の地域にはないようなユニークな施設があって、それらが街の人たちによって支えられ、愛されている…。そういうものが多くある街には、ひとが自然に集まる魅力があるような気がします。
仙台に帰省するたびに目の当たりにしてちょっと寂しい気持ちになるのは、由緒ある老舗が少なくなっていることです。これは仙台に限らず、ほとんどの地方都市が同じような傾向にあるようです。例えば、そこの名物店主とおしゃべりしたさにお客さまが集まる…といった、他の街にはない唯一無二のお店がもっと増えたら、人も街も元気になって、他の業種の方にも刺激になるかもしれません。
白状すると、そんな“名物”的な教室になったらいいな、と思いながら、この地でピアノ教室を続けています。教えているのは、楽器店のピアノ教室とは一味もふた味も違う(というより、“ひと癖もふた癖もある”?)レッスンをする名物先生(仮)。ことピアノに関しては妥協を許さず(と、いうのは生徒さんに対してではなく、自分に対してです)、どんなレベルの生徒さんのレッスンも常に全力投球。できるかぎりのことをお伝えして、その方の本来の個性をひきだし、音楽の豊かさを心と身体いっぱいに受け止めて、生きる糧にしていただけたら…と、心から願ってやまないピアニストであり音楽愛好者、というのが、その名物先生の“正体”です。
名物先生は、たまに“向こう見ず”になります。音楽でもっと人生を豊かに輝かせていただきたい、と願う大人の方々のための音楽講座を開講してみたり、生徒さんの発表会の打ち上げを自宅で行ってしまったり。でも、なぜか皆さんからご好評をいただいているのは、周囲の方々に恵まれているからに他なりません。
「美奈子先生の講座のお導きに寄りまして聴く楽しみを教えていただき、深い感謝とともにこれからもどうかご縁をいただきたいと願っております。こんな贅沢な素晴らしい講座は全国どこにもないのでは?と思えるのに、こんな近くで…本当に幸せ者です」母と同い年の熱心な受講生の方からこのようなお手紙を頂戴し、嬉しさとともに「もっといいものにしていくぞ」という決意がふつふつとこみ上げてくる、名物先生です。
「名物に美味いものなし」と言われます。その真偽のほどはわかりませんが、食べ物以外の名物には、少なくとも愛すべき“面白いもの”がいろいろあるのではないでしょうか。いいえ、あっていいのではないでしょうか。
ゆりのき通りの片すみで、名物先生は今日もピアノに向かって今度のコンサートのための練習をしながら、新たなる“向こう見ず”を企てていたりします。いつもながらうまくいく保証はありませんが、「名物にウマいものなし」が反対に転じることを夢見て…。
■第753回 希望の波動を伝えたい
演奏を生業としている身にとって、コンサートの依頼をいただくのはこの上なく幸せなことです。いくら新しいレパートリーを勉強して地道な練習を重ね完成度を上げたとしても、聴いてくださるお客さまがいなければ経験も表現も広がりません。
「うちの病院のロビーでたまにコンサートをしているの。美奈ちゃんに出演してもらえたらと考えているのだけど…」高校時代の同窓生で、その病院の小児科部長を務めている西井亜紀ちゃん(西井先生、とお呼びしなければいけませんね)がそんな話を持ちかけてくれたときの嬉しさときたら!二つ返事で「ぜひお願い!」とお答えしました。
アメリカ留学時代のある時期、毎週のように老人ホームや病院(ときには精神病院も)を訪れてコンサートを行なっていました。演奏終了後、目を輝かせて手を握りながら感想を伝えてくださる皆さんのお顔をみて、ふと「演奏家が音楽をいちばん届けなくてはならないのは、コンサートホールに自力で足を運ぶことのできる時間的、経済的余裕がある健常者よりも、このような方々なのかもしれない」という気持ちになりました。
期せずして、その思いは五年前に故郷で大きな震災があったときに再び頭をよぎることになったのですが、ピアノという楽器の性質を考えると、被災地に乗り込んだとしても何ができるというのか…。あれこれ悩んだものの、結局復興支援のチャリティーコンサートを行うことが精一杯でした。
「音楽ではお腹が膨らまないし、生演奏は贅沢なもの」そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。でも、震災から約半年後に仙台でおこなったリサイタルで「美奈子さんのピアノを聴いて、震災後初めて涙がでました。毎日を過ごすことに精一杯で、“泣く”ことを忘れていました」と、話してくださった女性の赤い目をみた瞬間、「やはり音楽は人間にとって、希望をもたらす大切なものだ」と確信しました。音楽は映像や具体的なメッセージをもたないからこそ、聴く人の心にそっと寄り添い、その傷を癒す“波動”のようなものがあるような気がしています。
果たして、その病院で、アメリカ留学時代からの友人でヴィオラ奏者の植村理一さんとデュオコンサートをさせて頂けることが決まり、昨年末に帰省した折、西井先生の取り計らいで、コンサート会場のロビーとピアノを視察させてもらいました。明るい待合室に大切そうに置かれた、新しいグランドピアノ…楽器があるだけで、その空間が豊かなものに感じられるのは、自分がピアノ弾きゆえの贔屓目でしょうか。ホテルのロビーにも負けないほどの高い吹き抜けは、きっとヴィオラの音を伸びやかに響かせてくれることでしょう。楽しみとイメージが拡がっていきました。
共演を快諾してくれた植村さんと、病院のロビーというシチュエーションを念頭において、皆さんにホッと和んでいただけるような…それでいて、ヴィオラの魅力をたっぷりと感じていただけるようなプログラムをあれこれと考え、曲目を絞り込んでいきました。演奏時間としては通常のコンサートの半分ですが、少しでも良いものになるよう、ハーフプログラムとは思えないほど入念なリハーサルが何度も重ねられました。植村さんは、室内楽の本番が続く超多忙なスケジュールをできる限り調整し、その時間を捻出してくださいました。
コンサートが近くなると、事務部長さんがお忙しい業務の間に素敵なチラシを作成してくださいました。しかも、万全のコンディションで弾けるよう、私の希望に沿って調律まで手配してくださるというご配慮まで!
さて、コンサート当日。お約束の時間に会場に入ると、すでにスタッフの方がテキパキと設営をされている最中でした。立ち位置の確認、サウンドチェック、マイクの用意、控室への案内…音楽事務所でもこうはいかないのではとい思われるほど素晴らしいオーガナイズによってつつがなく準備が進められ、事務部長さんと西井先生にご紹介いただいてコンサートがスタート。植村さんも私も、何の心配もなく演奏に集中することができました。
お集まりいただいたお客さまの笑顔や、「またぜひ演奏しにいらしてください」というスタッフの方々のお声…。どれもが温かく、大きな励ましをいただいて誰よりも元気になったのは私たち演奏者かもしれない、と思いながら会場を後にしました。関わってくださった全ての方々に、心からの感謝をお伝えしたい気持ちです。本当にありがとうございました。
■第752回 音楽家の育ての親は
「よい音楽家の判断基準は次の四点にまとめることができます。一.よく訓練された耳 二.よく訓練された知性 三.よく訓練された心 四.よく訓練された手」
ハンガリーの作曲家、ゾルターン・コダーイの言葉です。コダーイについて検索すると、その職業についての記述が他の作曲家たちとはかなり異なるものであることが見てとれます。
作曲家、民族音楽学者、教育家、言語学者、哲学者___彼ほどにそのどの分野もを同じように深く極めた音楽家を、私は知りません。一つ年上のバルトークですら、20代で彼に出会い、たちまちその思想の素晴らしさにひき込まれ、大きな影響を受けています。のちにコダーイの作品はバルトークのものよりも芸術性に欠く、という批判が上がった時には、バルトークは彼には珍しく感情的ともいえるほどの激しい口調で、その相手を“攻撃”したほどです。
冒頭にご紹介したコダーイの言葉をあるSNSで紹介したところ、日本だけでなく、世界中で活躍している音楽仲間(主にピアニスト)から「私は四が課題で他がままならない」「私の理想は一、三、二、四の順だけど、今はそうではなく二番目と四番目が入れ替わっているかも」「いや、まずは四がないと他のものは望めないのでは?」など、さまざまな意見が寄せられました。
コダーイが“手”…つまりテクニックを最後に置いた裏には、ある意図があるのは確かです。でも、四つの要素がその順番に大切である、ということを伝えたかったというわけではないと思われます。彼の言う“よい音楽家”とは、器楽演奏家とは限らないからです。音楽教育者、作曲家、声楽家もそれに含まれるのですから、必ずしも“手”によるヴィルツォーゾな技巧がもっとも重要というわけではないのです。
コダーイは彼独自の音楽教育法“コダーイ・メソッド”を編み出し、普遍的ともいえる教育理念を打ち立て、今や世界中からコダーイ研究所のあるハンガリーの地方都市ケチケメートをたくさんの研修生が訪れるほどですが、実は彼自身、自分のメソッドが単なるマニュアルとして一人歩きすることのないよう、具体的な方法論をあえて残すことをしませんでした。
「それがコダーイのすごいところなの。だって、子ども(相手)が変われば方法論は変わる。その子にとってもっとも適切なものに変えていかないと。そこには、パーソナルな性格だけではなく、国民性、民族性の影響もある。例えば、騎馬民族と農耕民族の違いにはかなり大きいものがあるよね。加えて、時代性だって関わってくる。ひとつのマニュアルがすべての人に当てはまらないのだから、具体的な方法論に甘んじないで、それらを加味して判断されないと、ねぇ。そこで、教育や教育者の本質が問われるわけ」ハンガリーのさまざまな国立教育機関…音楽専門学校から小学校、幼稚園にいたるまでの現場で、その第一人者による音楽教育に触れ、日本のそれとは大きく異なる素晴らしさを学びつくして帰国し、今は全国の大学や音楽教育機関からの要請を受けて各地でその素晴らしさを伝えているKちゃんが、ここで膝を進めました。「だいたい、いい音楽家って、誰が育てるもの?誰に育てられるもの?」
偉い先生の目に止まり、鳴り物入りでデビューを飾ることや、有名なコンクール優勝がきっかけになることもありますが、一時的な注目に終わらずに、さらなるステップアップをしていけるかどうか。我々音楽家を一流の(本物の!)演奏家に育てうるのは、権力のある指導者でも気まぐれなマスコミでもないのです。きちんと良し悪しを判断してくださる、質の高い聴衆…つまり“音楽家以外の人々”なのです。厳しく暖かく見守り、受け止めてくれる存在によって音楽家は謙虚さを失うことなく切磋琢磨を続けることができるし、そういった人々から経済的支えを得て生きてくのが本来であろう、というのです。
「だから、その国の音楽レベルをあげるためには、一般愛好家や聴衆を啓蒙しないといけない、そういう教育をしなければいけないというのが彼の考えなの。四つの要素は、むしろプロの音楽家ではなく、一般聴衆へむけての判断のポイントとして述べられたものなのよ」留学時代は妹のように思っていたKちゃんが、熱意にあふれた瞳を輝かせながら話してくれるのを頼もしく眺めながら、「日本にもそんな聴衆がそだちますように。もっともっと皆さんに音楽に興味を持っていただけるよう、私も頑張ろう」という思いを新たにしたのでした。
■第751回 誰にも触れられないもの
スティーブン・キングの小説『刑務所のリタ・ヘイワース』を映画化した、『ショーシャンクの空に』という作品があります。無実の罪で終身刑を言い渡され、ショーシャンクという厳しい刑務所に入れられてしまった主人公アンディが、自らの手で運命を切り開き、最後まで希望を持って生き抜いていく物語です。
映画の中に、アンディがモーツァルトの『フィガロの結婚』のレコードを見つけ、部屋の鍵にかけて看守が止めるのも聞かずに、そのたいへん美しい二重唱のアリアをスピーカーで刑務所中に流してしまうというシーンがあります。外にいた囚人たちは作業の手を止め、しばしスピーカーから流れるえも言われぬ音楽と歌声にうっとりと聴き入るのですが、アンディはその直後、罰として二週間の独房入りを命じられてしまいます。
このアリアのシーンは名場面として名高いのですが、私が一番好きなのは二週間を経て独房から出てきた彼が、仲間から同情を込めて「二週間も閉じ込められてまで、あんなことをする価値があったのか」と聞かれて次のように答えるところです。「いや、今までで一番楽だった。ここ(心…心臓あたりを指して)にモーツァルトがいたから辛くなかった。音楽は、希望を忘れないために必要なんだ」
彼はまた、映画の中でこんなことも語ります。「世の中が石でできた場所ばかりではないということを忘れるな。誰にも触れられない、触れることのできないものが心の中にあるっていうことを。自分に、それがあることを」
絶望的な逆境にあってなお希望を捨てずにチャレンジを重ね、とうとうチャンスをつかむアンディ。観るたび、人間ってすごい、こんな強い人に私もなりたい…と、熱い涙がこみ上げてくる映画です。
桜が咲き始めると、ニュースもSNSも桜の話題や映像、画像で大にぎわい。つくづく、桜は日本人に愛されている花だと実感します。でも、お花見と称してその下でワイワイ騒ぐのは、個人的にちょっと苦手になってしまいました。桜の花の魂は、とても繊細でありながら命の短さゆえのひたむきさが宿っていて、それは畏敬の念を抱きたくなるほどに気高いものであるように感じるのです。ゆえに、純粋に花の美しさを楽しむのは好きですが、その下で酒杯を傾け
て大声で…というのは、どうもそぐわないように思われてならないのです。
でも、短い花の命、美しさを愛でたい、という気持ちには同感です。そこで、2年ほど前から私は“桜の花を「見て」楽しむ”のではなく、“桜の花を詠んだ歌を楽しむ”という自分流の花見をすることにしています。短歌でも詩でも、花見という習慣が根付いた江戸時代以前に、桜を題材に書かれたものを鑑賞し、昔の歌人とともに桜の花の風情をあじわってみよう、という趣旨です。
世の中に 絶えて桜のなかりせは 春の心は のどけからまし
古今和歌集のなかでもひときわ有名な、在原業平の歌。「この世の中に桜がなかったら、春はもっとのどかで穏やかな気持ちで過ごせるだろうに」という訳ですが、それは“桜がなければいいのに”という気持ちではなく、“桜の花よ、そんなに早く散ってしまっては心が落ち着かないよ。そんない早く散らないでおくれ”という気持ちを歌ったものです、と、高校時代の古文の時間に習いました。
在原業平といえば、「心あまりて言葉たらず」とも言われた豊かな感受性の持ち主。数多くの女性と浮名を立てたことでも知られ、彼が主人公になっている『伊勢物語』の注釈書『和歌知顕集』には、その数3733人と書かれています。
桜の花の姿を瞼に思い浮かべながらこの歌を改めて読んでみたら、ふと、彼は華やかで存在感がありつつも儚く散ってしまう桜を意中の恋しい女性に喩え、「あなた(桜)がいなかったらどんなに私の心は平穏でいられることか。ああ、そんなにつれなくしないでおくれ」と、この歌に切ない気持ちを込めているようにも聞こえてきました。そして、実は一途な業平の一面が感じられたような気がしました。
「心にモーツァルトがいたから辛くなかった」…それが目に見えたり、手に入るとは限らなくても、誰にも触ることのできない大切な思いを胸に抱いて、アンディのようにいつか願いがかなうと信じて希望を持ち続ける強いひとになりたいものです。
■第750回 ヒトだからこそ、愛あればこそ
ベルギー在住の指揮者、大野和士さんの奥さまでエッセイストの大野ゆり子さんがお書きになった、先日のブリュッセルでのテロのレポートをツイッターに取り上げたところ、半日で3000を超えるアクセス、30以上のリツイートがありました。もともとツイッターにはさほど熱心ではなく、フォローしているのは90足らず。私をフォローしてくれている方も200以下で、こんなにも多くの反響があったのは初めてのことです。
SNSの威力の大きさを体験し、驚きとともに少し怖い気持ちに襲われたところへ、囲碁名人を打ち負かしたと話題になっている人工知能に関するある話題が飛び込んできました。アメリカのMicrosoft社が開発した、英語テキストで会話することができる人工知能“Tay”が、わずか1日(足らず?)で緊急停止された、というのです。
一般ユーザーとチャットでコミュニケーションを重ねるほどに“賢く”なると期待されていた“Tay”でしたが、賢くなるどころかネット上の会話から人種差別や陰謀論を学習してしまい、「黒人は首を吊れ」「ヒトラーは正しかった」などという、とんでもない発言をいくつも投稿してしまったのです。
アートのような絵を書くこともできる、小説を書くこともできる…と、このところ人々のホットな注目を集めていた人工知能ですが、ここにきて突如、そのあまりに不完全な一片が露呈されたかたちです。人間ではないので「人間失格!」とは言えませんが、それでもその“心無い(機械だから仕方ないけど)”投稿をみた何万人が、「ロボット(人工知能)失格!」と、退場のレッドカードを掲げたい気持ちになったことでしょう。
人、あるいは植物、動物とコミュニケーションをとるということは、科学のデータで解析しきれないほど繊細なレベルで、相手の状態や心のひだに触れることです。細やかで多様な感情、相手への思いやり、双方の性格などが複雑に絡みあい、働きあって初めて成り立つものですし、それでも時として、ちょっとした表情や表現の読み違いによって、悲しいすれ違いや諍(いさか)いに至ることも避けられないものです。
最先端を行く企業が、介護や簡単な手術ができるロボット、徘徊老人をキャッチする高性能なGPS装置や、車線変更や縦列駐車もできる自動運転装置の開発などに余念がないのは、世の中にそれらの需要があるから…というのもわからないではありません。でも、かつてはデイサービスがなくても家族や親戚の人がそれを行うのは当たり前でしたし、運転ができる人が運転ができない人を助けるのも自然なことでした。人と人の支えあいに必要なものは機械ではなく、人の“思いやり”と“手”でした。
いつからこの世の中は、猫どころか“機械の手も借りたい”というほどカラカラになってしまったのでしょう。もちろん、核家族化や地方の過疎、少子化や共稼ぎなど、深刻で難しい様々な問題がその背景にあることは承知していますし、人々の生活を快適さで潤し、心を満たすための科学の進歩なら、歓迎します。でも、人の手のぬくもりや、人と人との心の触れ合い…コミュニケーション…にとってかわるものを、科学の力で“製造”することには、どうしても違和感を覚えるのです。
例えば音楽芸術や、それを奏でる楽器について考えると…。いくら精密・精巧に製造された人工知能をもってしても、私たちが当たり前のように日々行っているように、楽譜に書かれた音符の奥の真意を読み解き、作曲家の性格やその人生の背景、作風の特徴や個性を踏まえた上で、フレージングやアーティキレーションの可能性を追求し、その日の湿度や楽器のコンディション、会場の響きやお客さまの客層、雰囲気によってアプローチを微調整しながら、共演者(がいる場合)と音と目でコミュニケーションをとりつつ演奏する…ということが、いったい機械にできるでしょうか。できたとしても、それが私たちにどれほどの幸せをもたらしうるのでしょうか。
性能をいくら追求しても、それは、思いやり・思いあいや愛によって幸せを感じる“ヒト”の心を満たすものにはなり得ない、と思われてなりません。
人工知能の不祥事(という言葉は人間に使うイメージなので、この言葉を使うことにも少々違和感があるのですが)は、ヒトにとって大切なのは、“話せる”“書ける”“勝てる”“動ける”など、「何ができるか」ではなく、それらを「いかにできるか」だということを、改めて教えてくれたのだ、ととらえ、心穏やかに就寝することにします。
■第749回 好奇心という財産
「美奈子さんは博学でいろいろな分野に明るいですね」と、(社交辞令で)言っていただくことがあります。
もちろん、実際は違います。もしそんな印象を持っていただくとしたら、私が様々な会話に分け入っては、おしゃべりが止まらなくなる性分だからでしょう。
それは、気を遣ってその場を盛り上げようとするサービス精神からでも、黙っているとストレスがたまるという体質の持ち主だからでもありません。皆さんとのお話に加わって、どんどんその場の会話が広がるのが好きなのです。とりたてて社交的な方ではないのによい友人に恵まれるのは、そんなことも関係しているのかもしれません。
話が止まらなくなりがちになるのは、料理やお菓子など食べ物やお酒(今はほとんど嗜みませんが)やコーヒーといった嗜好品、建築や写真、和装を含めたファッションやインテリア、古典落語や歌舞伎などの伝統芸能、器や旅にまつわること、ちょっとした言語学や文学・哲学、そしてもちろん音楽やダンスについてなど。これらはどれも、私にとって、スイッチがはいると一晩中でも読み物調べ物に没頭してしまえるほど楽しく、興味深いものです。欠点だらけの性格の持ち主ではありますが、子供並みの好奇心には感謝しています。
出版不況、本が売れないと叫ばれる中、『超訳・ニーチェの言葉』で100万部以上のヒットを飛ばすなど、ベストセラーを次々と世の中に送り出して常に新しい価値観を創造し続けているディスカヴァー・トゥエンティワンという出版社があります。つい先日、その女性カリスマ社長、干場弓子氏が語る“若い人を不幸にする三つの言葉”という記事に出会いました。その三つの言葉と理由とは、次のようなものです。
1.キャリアプラン→思った通りにいかないから人生は面白い。そんなプランになどこだわらず挑戦を重ね、迷っている暇があったら今に集中する。先のことを考えるのは“一瞬で不安になれる”こと。避けよ。
傾けて、“have to”を“want to”にすべし。
三つとも横文字のフレーズで、解説なしにはわかりにくいものもありましたが、シリコンバレーのIT企業の入社式なんかで聞かれそうな内容で、なんともかっこいい。「おお、さすがいまどきのキャリアウーマン!」と、ひと昔前の人みたいに感心してしまいました。
氏のおっしゃっていることは実に簡潔明瞭。その通りだと思います。でも、私が上司ならそれらすべてを予め部下に話すことはしないでしょう。そのひとつひとつは、各々が自分自身の経験から学び取ってもらいたいし、数多の失敗や回り道を積み重ねていくこともまた、その人の人生にとってかけがえのない財産につながると思うからです。
短期決戦的な成績アップを目指すより、まず良き人材(社員)の育成を重んじる指針を貫く方が、長い目で見たらその企業にとっても日本という国家にとっても、そしてなにより後世にとっても、より大きな実りにつながるはず。…そう信じている私のようなものが上司だったら、その部署の成績はまず上がらないでしょう。もっとも、私が入社できて、しかも上にいけるような酔狂な企業は、すでに経営が危なくなっているかもしれません。
それが証拠に、私の今の生活(おそらくこれからもですが)を言い表すと、“その日暮らし”。経済的安定からは程遠いものです。でも、好奇心というパートナーがついていてくれるおかげで、ワクワクするようなときめきには事欠きません。先行きはまったく見えない状態なのに、ありがたいことに“好奇心”という財産は、世の中の超低金利をモノともせず、なかなかの高利回りで増え続けてくれています。
ビジネス的な観点からすると成功したとはいえない人生かもしれませんが、好きなことを続けつつ、興味を惹かれることにもチャレンジできる自由な時間が与えられていることを考えると、自分は申し分なくリッチな“my life”のオーナーだと思うのです。周囲の方々には感謝しかありません。
■第748回 後悔よりも前進を
5年という月日が経過したこともあって、今日はメディアもSNSも“特別な日”という扱いで震災関係の特集が目に付きます。でも、『3.11』はイベントではありません。ましてや、被災者の方のご心労は過去のものでもありません。震災の悲劇は特別なものではなく、いつでもどこでも、誰にでも起こりうることとして心構えていたいし、犠牲になった方への追悼の思いはこの日や黙祷の時間だけでなく、いつも胸に抱いていたいものです。
「あの時こうしていれば…」という後悔は、自然災害によってだけではなく日々私たちを襲ってくるものです。それこそ津波のように、それが大きな壁のように目の前に立ちはだかることもあります。選択を誤ったのは失敗だと思いがちですが、それは現在目の前にある結果だけで判断しているのかもしれない。いつか長い人生を振り返った時、無駄だったことなど何もないと悟るときがくるような気がしますし、人は知らず知らず最良の選択を重ねる努力をして生きているものだと思います。
そうすることが本来の人の叡智だからこそ、“失敗”や“後悔”を教訓に、備えや、必要なら軌道修正をすることが大切なのでしょう。それは前を向いているからこそできる尊い行動です。
生徒さんと向き合っていると、救われることが少なくありません。今のご時世、私のその頃とは違って、担任の先生から強く叱咤されることも、友達や兄弟ととっくみあいの喧嘩をすることもずっと少なくなっていると思われますが、彼らは私から少々強い語調で怒られてもへこたれません。ただ感情で“怒る”のではなく、愛情をもって“叱って”いることを理解し、きちんと受け止めて次へのステップに役立ててくれるのです。
実は、「強くいいすぎちゃったかな」「ちゃんと伝わっているだろうか、消化できずに困っていないだろうか」という小さな後悔に襲われ、次にその生徒さんに会うまで気が気ではないこともあるのです。でも、そんな心配は嬉しい方向に裏切られることがほとんどです。子供たちの純粋な「前に進みたい(もっと上手になりたい)(もっと知りたい)」という気持ちには、少々の失敗なんぞ一発で蹴散らしてしまう逞しさがあります。一方で、こちらが表面だけで褒めたり、感情だけで怒ったりしようものなら、それもすぐに感知してしまう感受性や繊細さも持ち合わせているのですから最強です。
自分にもそんな頃があったのだ、と気づかせてもらう時、むしろ彼らから励ましをもらい、大切なヒントを得たような気持ちになります。
「あれ?先生、今まちがえちゃった!」たまに、わざと生徒さんにミスタッチを暴露?してみたりします。「本ものはこっちの音ね。ほら、この方がずっとすてき」「ほんとだ!」「先生、これからは『この、すてきな音のところをまちがえないように…』って、ここをもっとていねいな気持ちで弾けるね」「うん!」「あのね。練習すると、したところのことがもっと大切になって、好きになるのよ。◯◯ちゃんはそんな気持ちになったこと、ある?」「う〜んと…ちょっとある!じゃあさ、もしいっぱいまちがえたら、好きなところがふえるの?」「あ、そういうことだ!すごいね、大発見!」「すごーい!」「でも…いっぱい練習しないといっぱいまちがえられないね(ここで、付き添いのお母さまが小さく吹き出す)」「うん。だから、いっぱい練習するのがいいんだね!(お母さまと目配せ)」
レッスン中、思いがけない方向に会話が進むことがあって、発見の日々です。もう少し大きな生徒さんの場合、彼らが思うように弾けない時には実際の曲の中で楽典を教えたりもします。音楽の骨組み、構造が分かると親しみが増し、表現の方法が広がることを体験してもらうのです。彼らがその音楽に抱いている“イメージ”を、漠然としたままではなく具体的な表現に進化させるためのセオリーを知ると、自信を得てがぜん演奏が生き生きしてきます。自分自身、なかなかそれがつかめず失敗や苦労をしてきたので、その経験が多少なりとも彼らの役に立っていると思うと、こんなに嬉しいことはありません。
「あの時、こうしていたら…」“たら”“れば”がつく後悔が一切ないという人は、少ないのではないでしょうか。でも、子供たちにはしょんぼりした背中ではなく、いつも何か楽しそうな気配が感じられ、まっすぐ前を向いている背中をみせていたいものです。「先生ね、ずっと大好きなピアノを弾いていられて、とても幸せなの」そう伝えた時、感性豊かな彼らがそれを真実の言葉として受け入れ、励みにしてくれるような生き方を貫くことが、私にとっての“後悔のない”人生なのかもしれない、と思った、5年目の3月11日でした。
■第747回 コンクールの指導をなさる先生方へ
毎年審査員のお仕事で関わっているコンクールの課題曲が発表になり、参加する生徒さんたちを指導する先生方を対象とした課題曲セミナーのお仕事を、今年も仰せつかることになりました。
コンクールは、その語源が示すように“優越を競う”という性質をもっています。演奏という芸術行為に優越をつけるのはそもそも無理があることなのに、それが子供向けのものとなると、審査をする側も主催者の方々も、いっそういろいろなことに気をつかうことになるのは避けられません。例えば、参加しにくい課題曲構成にならないよう、選択肢をどうすべきか。参加者と入賞者の数のバランスはどのくらいの割り合いが適切か。参加した皆さんおひとりずつにお渡しする講評用紙のコメントは、自信ややる気を失わないように言葉や言い回しを選ぶこと、などなど。
頑張って練習を積みかさね、何度も何年も挑戦を重ねた末にやっと念願の最優秀賞を受賞したところ、ご本人もお家の方も“燃え尽き症候群”のようになってしまって、結果的にピアノのお稽古にピリオドをうつ結果に…というケースもありました。ステップアップのきっかけにしていただきたかったコンクールが、その反対になってしまったとしたら、とても残念なことです。でも、かといって無理して続けることは精神的にも時間的にも負担がかかることになりますから、そのご決断、ご判断は尊重されるべきだとも思います。
正直に告白するならば、コンクールで優越を競い、良い成績を勝ち得て“優位”に立つことよりも、ひとつの発表の場、力試しの機会としてとらえ、一段と成長するためのきっかけや目標にしていただきたい。コンクールの舞台を経験することで、音楽そのものや人前で弾くことをもっともっと好きになってもらいたい、というのが本音なのです。
コンクールに参加する生徒さんを指導なさる先生は、一人一人の能力を生かし、個性を尊重したうえでさらにそれを伸ばしてあげたい…という、親心のようなお気持ちをもって熱心にご指導に当たられている方がほとんどです。ところが、入選、入賞することを優先させようとすると、それだけでは充分ではなくなります。コンクールでアピールできる弾き方について学び、それを生徒さんに教え込むことが発生する場合もあります。選曲や演奏のテンポ(速度)
設定についても適切な判断が求められ、責任を感じながら葛藤されるケースもあることでしょう。
この世界では、「コンクール弾き」「コンクール対策」という言葉が一般的に使われているくらいなのですから、先生方のご心労はもっともです。でも、生徒さんに伝えるべき一番大切なことは何なのか、ということがそれに隠れてしまっては、本末転倒です。
結論から申し上げると、音楽やピアノの勉強には“傾向と対策”も、“近道”もありません。それは、残念なことでもなんでもなく、とても素敵なことだと思っています。音楽の勉強、楽器の上達に求められるのは、まさに道を這うようにじっくりゆっくりと歩んでいくような、地道で丁寧な練習の積み重ねと、音楽へのゆるぎない情熱であって、重要視されがちな器用さや能力の高さなどは、実はそれらの努力の前に屈するしかないのです。
珈琲焙煎家の友人がこんなことを話してくれました。「来る日も来る日も、同じことを続けていることに、意味がある。それは毎日を漫然と過ごしているのではなく、“昨日の自分の技術より上手くなるために腕を磨いている”ことなのだから」。また、最近南インドへの何度目かの料理修行から帰国した友人のシェフ曰く「これまでの人生の中で絶対的に一番美味しい、と思える料理に出会ったんです。それが、(今回の旅でお世話になった)お母さんの作ってくれた料理でした。手順にはまったく無駄がないのに、ひとつひとつの手間は惜しまず、それがすべて料理に生きている。何より、食べるひとを心から思う気持ちで作っているのが、料理から伝わってくるんです」。
同じことの繰り返しの中から何を感じ、何を見いだしていくか…地道にみえる積み重ねにこそ、人の営みの尊さや真実の歩みがあるのでしょう。お二人の言葉を聞いて、何の分野も究極は同じだと改めて感じました。
生まれついての器用さや楽器を弾く能力よりも、日々の積み重ねや音楽に対する真心がよい演奏の成分に昇華していく…素晴らしいことだと思いませんか?音楽への情熱と愛をもってピアノに向かい、楽譜と向き合って作曲家との対話を重ねていく喜びを、生徒さんに味わってもらえるようお導きいただけたら、同じ音楽仲間としてこんなに嬉しいことはありません。
■第746回 師の言葉
よく外国の方から、「日本人は“すみません”ばかりで、“ありがとう”を言わない」という意見を聞きます。確かに、“ごめんなさい(I’m sorry)”、という気持ちを伝える時だけでなく、誰かに呼びかける“ちょっといいですか?(Excuse me)”も、“ありがとう(Thank you)”の時も、みんな“すみません”ですんでしまいます。
“すみません”には、謝罪だけでなく感謝、依頼の意味も含まれるので、三つを使い分けせずについ“すみません”ばかりを使ってしまうのも仕方ないことかもしれません。でも、その便利さに逃げずに、感謝の気持ちを伝えるときにはなるべく“ありがとう”を言うよう、心がけるようにしています。
外国に行くと“ありがとう”の使用頻度は“すみません”を圧して一気にトップに躍り出ます。言うことだけでなく言われることも多いので、ハンガリーに初めて降り立った時、一番最初に「うっ!これ、なんて言うのかしら。言いたいのにわからない…」と、もどかしく思ったのは「どういたしまして」。つまり、ありがとう、と言われた時のお返しの言葉でした。
少し話がそれますが、動詞の“love”という言葉の使い方にも違いがあります。日本で「愛している」と口走ったらそれなりの重み(?)をともなうことになりがちですが、向こうの方は“love”をよく使います。例えば、直訳すると「僕はコーヒーを愛している」とか「私、ダンスを踊ることを愛しているの」のような言い回しをよく聞きます。「とても好き」というニュアンスです。
今から20数年前、ハンガリーからアメリカに行くことになり、師事したいと願っていたシンシナティ音楽院のユージン・プリドノフ教授にブダペストから自分の演奏の音源(当時はカセットテープでした)を送りました。後日先生のお宅に電話をかけ、「(私の演奏は)聴いていただけましたか?いかがでしたでしょうか?私を教えてくださいますか?」とおそるおそる伺った私に「とても素晴らしかったよ。是非君を教えたい!(I love to teach you!)」とおっしゃってくださったとき、英語のそのような表現に慣れていなかったために驚いた記憶があります。
恩師からの印象的な言葉はいくつかあって、これまでも折に触れてこのエッセイでご紹介していますが、いよいよ音大受験が見えてきた高校3年になったばかりの頃、当時仙台でピアノをお習いしていたS先生から告げられた言葉は鮮烈でした。「あなたには、もう私が教えられることは何もありません。これからは私のところにレッスンに来る必要はありません」
「え…?これって一種の“破門”ってこと?」…混乱した頭のまま家に帰ったのを覚えています。S先生は地元の音楽大学のピアノ科の教授で、仙台では有名な大先生でした。そのS先生からの宣告には少なからずショックを受けましたが、さらに身を引き締めてピアノに打ち込み、引き続き東京の林秀光先生のところにレッスンに通い続けました(それ以前は林先生には月に一度、S先生には月に3度みていただいていました)。緊張感が幸いしたのか、その年に受けた桐朋学園大学の夏期講習では、実技でもソルフェージュでもトップの成績でした。
先日、あるSNSでの大学時代の同級生とのやりとりの中で国語担当のK先生の思い出話が持ち上がり、作曲家の友人がこんなエピソードを披露してくれました。「K先生がある年、女子部(中等部)の入学式でこんな話をされました。『桜がきれいに咲いていますね。あの桜の美しい色はどこからくるのでしょう?あの桜の色を染め出す唯一の方法があるのだそうです。咲き誇っている桜ではなく、一番寒い冬のある時期、枯れた枝の下に静かに芽が準備されている頃の樹皮を取って、染めるのです。その時期の樹皮でなければ駄目なのだそうです。そこに、その季節に、やがて咲くべき美しさの全てが、だれの目にも触れないけれど、いっぱいにつまっているのですね....』中学生に、こんな愛と敬意に満ちたメッセージがまたとあろうか。感動しました」
受験シーズンが終わると卒業シーズンの到来。さらに新入学の春へと、季節は移ろいます。今もなお鮮明に覚えている師の言葉や、そのひとつひとつに一喜一憂していた自分を思うたび、改めてその影響の大きさを感じます。
“師”と呼ばれる立場になっているという自覚が薄い私ですが、生徒さんにかける言葉にはいつも意識をくばり、少しでもみなさんの人生にとってプラスの光になる何かをお伝えできるよう、願うこの頃です。
■第745回 憎しみの連鎖を断つ
インターネットによってリアルタイムでもたらされる情報や映像は私たちに様々なことを伝えてくれますが、そのあまりに悲惨な現実に言葉を失うようなショックを受けることも少なくありません。
例えば、もう10年以上も前からカンボジアやバングラディシュ、パキスタン、イランなどで多発し続けている“男性が女性に硫酸をかけて顔や体をいためつけ、ひどい場合には死に至らしめる”という事件について、日本ではあまり報道されていません。
このような事件はアシッド・アタック(酸の攻撃)と呼ばれ、ひどい時には年間数千件も起こっているのにもかかわらず、検挙されたり有罪判決にまで至るのはそのうちのほんのわずかにすぎません。被害者の女性は何十回も(!)
読者の反応に、いっそう悲しくなりました。「イスラム教は、歪んでしまった。間違った原理主義を根絶すべきだ」「西側がもたらした帝国主義、奴隷制度の影響だ」「歴史を学んで恥を知れ。それは西に始まったことではない」掲示板は、異なる宗教の人たちの言い争いの場になっていました。彼女たちのために、また、そんなことを起こさないようにするために、自分たちには何ができるのか。何を解決していくべきなのか。…そんな議論を回避し、相手をやりこめ、自分の考えの正当さを主張することに執着してしまっては、悪魔の思う壺です。
“憎しみの連鎖”という言葉が使われるようになったきっかけは、それを断たなくてはならない、とうったえたながらも、イスラム国のメンバーとみられるグループによって殺害されてしまったジャーナリスト後藤健二さんのツイッターでした。「目を閉じて、じっと我慢。怒ったら、怒鳴ったら、終わり。それは祈りに近い。憎むは人の業にあらず、裁きは神の領域。—そう教えてくれたのはアラブの兄弟たちだった」
何が正義なのかを争って血を流すなんて、こんなに無意味なことはありません。“「義」という言葉の中には、既に「人としての正しさ」という意味が含まれているんですね。(中略)「義」には元々「人間として正しい思い」という意味があるのに、そこに更に「正」と重ねて強調する人の、かすかな胡散臭さに気づかないといけない。”…著書『本気で言いたいことがある』のなかで、シンガーソングライターのさだまさしさんが書いていらっしゃいました。言葉と向き合ってきた方ならではの着眼点だと思いました。
後藤さんが殺害された事件から1年が経ちますが、彼の死は何かに生かされているのでしょうか。何らかの光をもたらしているのでしょうか。
1951年…今から65年前のサンフランシスコ講和会議で、スリランカ代表のジャヤワルダナ氏はブッダの次の言葉を演説に引用しました。「憎しみは憎しみによってではなく愛によってのみ消える」。武器や武力で争いはなくせません。人類はたくさんの凄惨な戦争を経験し、そんなことは充分にわかっているはずなのに、なぜ…?
昨日、ある友人とのやりとりのなかで、そんなことに話題が及びました。「美奈子ちゃんのピアノは本当に素晴らしい。音楽はあっという間に心を浄化できる素晴らしいものです。しかも水や空気のように浸透しひろがります。(自分は)音楽で世の中を変えたい」そう言われた時、(自分が素晴らしいかどうかは別として)本当にそのとおり、音楽の力にははかり知れないものがある。強い信念を抱いて、自分にできることを懸命にやり続けるしかない…と強く思ったのでした。
「物質的なものにしか価値を見いだせない粗雑な心が悪魔の本質だと思います。煩悩にがんじがらめになって本質的な真理を見失い、慈悲や慈愛を失っている状態。(慈悲や慈愛を)みんなでとりもどせるように、精進しましょう」友人の言葉に、救われました。過去は変えられないかもしれないけど、未来が変わることで過去の持つ意味は大きく変わり得るのではないでしょうか。音楽でメッセージを伝えられることを信じて、明日からまたピアノに向かっていこうと思います。
■第744回 いるものと、いらないもの
『最後に箱の中に残るものは?』
スペインのカナリア諸島の海の底に、アトランティコ美術館という海底美術館ができました。そこには数々の難民のモニュメントが“沈んで”いて、紹介動画サイトには美しく幻想的な映像と効果音がながれます。
ところが、「主旨、メッセージはわかる。でも、たくさんのお金をかけてこんなものをつくるより他に、もっと良い方法やできることはないの?」「こういうところに行ったことを自慢したがる、金と時間を持て余したダイバーたちに、いったい何を伝えたいと?」「本当に今、これが必要なのか。アートってそもそも何なのか。…まぁ、人に考えるきっかけを与える、という働きは果たすかもしれないとも思うが、せいぜいそれだけのものだ」など、海外の視聴者から寄せられているコメントは、おしなべてかなり辛口です。
世の中にとって、そして、自分自身にとって、必要なものと不必要なものを見定めるのは、案外難しいことです。
名画座やコンサートホールなど、文化的なものが失われたり老舗が潰れるとき、「ひとつの文化が消えた」とか「惜しいものを無くした」とか言う人は少なくありません。「守るべき文化」というフレーズも、よく耳にするようにはなりました。
でも、それらを守るために、彼らはそれまでどんな行動をしていたのか。文化や芸術を守り、育み、伝えていく必要性を真摯に感じて、頻繁に美術館やコンサート会場に足を運んでいる人は、実際にはどのくらいいるのか。
断捨離という言葉にも、実はこの頃少し抵抗を感じはじめています。必要か?と言われたらそれほどでもなくても、大切なものって、誰にでもあります。それらを全て葬り去ることが断捨離ではないとはわかっていますが、考え方、判断基準は「それは本当にこれから“必要”か。もう役目を終え、手放してもいいものではないのか」という現実的なものから、「捨てられないモノたちによって自分の価値観、人生観を知らず知らず“支配”されてはいないか」といった観念的なものにまで及びます。
「役に立たないもの」は、執着心を断って潔く捨てよ、というその技術と考え方は、行き過ぎると仕事効率や経済効果に結びつきにくい文化的なものにもむけられ、いつしかそれらが“切り捨て組”にされてしまうのではという懸念を覚えるのは、わたしだけでしょうか。
あるジャーナリストによる「(断捨離は)一見、モノを増やしすぎる社会への批判のようだけど、実際には経済効率最優先主義の徹底だ」という見解も、あるサイトに紹介されていました。
確かに、「就職に必要ないから」「なくても生きていけるから」という観点から判断されたら、芸術や食文化はたちどころにガタガタという崩れ、やがて失われてしまうでしょう。
近所の人との交流や、よその子供たちとのコミュニケーションといった地域活動。世の中に起こっている様々な出来事の問題点を鑑みたり、自分を高めることにつながる学びや、美しい風景や素晴らしい芸術、真心のこもった美味しい料理などと触れるための時間…。それらにかかる費用も、やがて断捨離されてはしまわないだろうか。そのとき、人の心は何を求め、どこに向かっているのか。
そういえば、10数年前の人気お笑い番組の中のあるコントのコーナーに、転勤を命じられたサラリーマンが身の回りのものを“いるもの”“いらないもの”と書かれた二つの段ボールに分け入れていくシリーズがありました。「これ、向こうでも使うよな」「いや、いらないでしょう」「そう?…でも、これは使わないね」「これはいります!絶対いります!」…部下とのそんなやりとりが毎週のように繰り広げられるのです。必要と思われるようなものが「使わない」ものに、反対に何に使うのかイメージすらできないようなものが「いるもの」に入れられる…と、それだけの内容だったのですが、妙に心に引っかかり、笑いというよりもその向こうに悲哀を感じるシュールなコントでした。
今思うとあれは、あとに来る“断捨離”ブームを予感した、何かのメタファーのようなものだったのかもしれません。
『最後に箱の中に残るものは?』
■第743回 甘く食べるか塩味か、それが問題だ。
「もう、トシの数だけ豆食べるの、きつくなってきたよ」節分には周囲の同年代の方からそんな声が聞こえてきましたが、豆好きなわたしにとっては大豆の50粒や100粒(!)なんて、ものの数ではありません。
断酒を敢行してはや14ヶ月。お酒がなくても平気、というのは証明されたのですが、甘いものは断ち切れそうにありません。ただ、この頃気が大きくなって、お豆や穀物を甘く食べることさえ許されるのであれば、仮に西洋菓子を食べられなくなっても我慢できるかもしれない、と思うようになってきました。
お豆を甘く煮てお菓子やお汁粉にして頂くという話を外国人にすると、だいたい「げぇ、ありえない」という顔をされるのですが、練り切りなど美しい上生菓子をお抹茶とともに差し出すと、彼らは決まって「素晴らしい!美しい!」と賞賛しつつ美味しそうに食べるものです。原材料は白インゲン豆や手亡豆なのに…。
アメリカでしばらく先生のお宅にホームステイさせていただいた時、先生が毎朝出してくださる、甘く煮てはちみつなどをかけて食べるオートミールに少し変化が欲しくなり、とうとうある日「あの〜。これ、甘い味にしないで、お醤油をたらして食べてもいいですか?」と、おずおずと申し出てみました。先生は、とんでもない性癖を垣間見てしまった瞬間のようにびっくりした表情になり、「え?今、なんて言った?醤油だって?オートミールに、醤油?」と、露骨に顔を歪めました。
私にしてみれば、もともとは味のない穀物はおかゆと同じようなものに感じられたので、きっと卵かけご飯のように食べても美味しいだろう、と思ったのです。「はい、醤油です。火から下ろす少し前に生卵を落として半熟になったところに、お醤油をたらして…あ、卵はあってもなくてもいいのですが」先生には恐ろしく悪趣味な思いつきにしか聞こえなかったようです。「いいけど…。僕はそれ、食べなくてもいいよね?」
その数年後、バリ島を訪れた時、“ブラックライス・プディング”というデザートに出会いました。日本で黒米と呼ばれている健康意識の高い方々の間で人気の古代米を、ココナッツミルクとブラウンシュガーで甘く煮たおかゆ状のものです。もち米を蒸しあげて団子にして、甘いココナツなどをまぶして食べるこ
ともある当地では、お米のスイーツはポピュラーです。アントシアニンたっぷりの黒いつぶつぶはちょっと小豆のように見えなくもなく、まったく抵抗はありませんでした…と、いうよりも、とても美味しいものでした。
青森県のある地域では、お赤飯を甘く炊くそうです。一方、香川県では白味噌仕立てのお雑煮にあんこ餅をいれる伝統があるといいますし、岩手県の久慈には黒砂糖とクルミを入れた団子と人参、豆腐、ごぼう、しめじをしょう油で味付けして煮た“まめぶ汁”があります。
お豆を甘く食べようが、穀物を甘く食べようが、あるいは醤油や味噌味に甘いものをフューチャーしようが、食材を大切に調理して、感謝して美味しくいただければ、幸せ。それが土地に伝わる伝統が反映されたお料理であれば、なおさらです。
2020年の東京オリンピックに向けて、ムスリム(イスラム教徒)が食べてもよい食品であることを示す“ハラル認証”なるものを取得する食品会社が増えているそうです。イスラム教では豚やアルコールの摂取が禁じられており、ムスリムはアルコールが添加されたしょうゆやみそ、豚由来成分を含むラードや食品添加物なども口にしません。
「オリンピック会期中には、多くのムスリムが来日します。安心して食べられる食品を増やすことで、おもてなしの心を伝えたい」。ある有機・自然食品会社の方のコメントです。よい視点だと思うのですが、あと数年でどこまで対応できるか、現実的には様々な問題がありそうです。どの国からのゲストにとっても居心地のよい環境を整えるのは難しいことですが、国際社会における日本のスタンスや結束力・行動力を示す、いい機会になるかもしれません。
食べ物に限らず、自分とは違う文化や価値観に対しても食わず嫌いにならないで、その歴史的・宗教的背景や地域の特性を学び、できる限り受け止めてみるよう、心がけていきたいと思っています。音楽を通して、地球人同士が手をつなぐきっかけになることに関われたら、そんなに嬉しいことはないのですが…。
■第742回 音楽は愛のメッセージ
ずいぶん以前にもご紹介したことがあるのですが、子どもの頃に好んで見ていた番組『みんなのうた』に、“くいしんぼうのカレンダー”という歌がありました。作曲は中田喜直先生、作詞は仲倉重郎先生。やまがたすみこさんの清潔感あふれる透明な声にのせ、画面に和装姿の素敵なお姉さんがでてきて、次々に和菓子を食べるのです。
睦月 羽根つき つばきもち
卯月 お花見 さくらもち
文月 七夕 ところてん
ききょう くずもち 神無月
2分ほどの短い歌の間に十数種類の食べものが登場し、聞いていると“ひがんばな”や“水無月”もお菓子の名前と錯覚しそうになります。さりげなく日本の歳時記や風習、美しい日本語の響きも盛り込まれていますし、“長雨あけて水ようかん”、“木枯らし吹いて酒まんじゅう”なんていうフレーズには作詩者仲倉先生のたぐい稀な俳句的センスも伺えます。とても深く心に残っているお気に入りの歌なのですが、近頃はこのような歌が生まれていないようにも思われ、少し寂しい気持ちになったりしています。
今日、83歳になられるMさんのレッスンで、音楽と言葉に共通する美しさとは?というお話になりました。Mさんは、英国で出版された音楽専門書の日本語翻訳に携わったり、シェイクスピアの全作品を原語から日本語に翻訳するというライフワークを実行していらっしゃる英語のエキスパートです。そういうレベルとなると、英語だけに堪能、ということはまずあり得ません。日本語、英語の両方に完全に精通していらっしゃらなければ、そこまで精緻な原語の架け橋を成し得ることは不可能だと思うのです。
「この頃、ちょっと違うのではないかしら、と感じる言葉の使われ方がありましてね。まぁ、私が歳をとったということなのだと思うのですが…」控えめにMさんが切り出しました。「凄く清楚だ、とか、凄く綺麗、というのはどうかしら、と。とても清楚だ、とても綺麗、というなら良いのですが。凄い、というのはなにやら凄みを帯びている、ということですから、清楚、綺麗、という対象に使うのではなく、凄く怖い、とか、凄く煩い、という使い方が本来であると思うのです。」
なるほど、“凄く綺麗”よりも“とても綺麗”の方が、まさに響きも「きれい」です。日頃、何気なく使っている言葉にも意識を払ってみると、そこには音楽的なイントネーションやリズム、美しい響きやフレーズが溢れていることに気づきます。一方で、不用意に綺麗ではない言葉を発することのないよう気をつけなくては、と自省したのでした。
美しい言葉とは、耳に心に違和感なくスッと入り込んでイメージを膨らませてくれるものであるように、美しい音楽もまた、そのようなものなのではないでしょうか。人の心をそっとノックして、寄り添い、慈しみあう愛のメッセージを音にしたものが音楽なのかもしれない…などと思いながら、Mさんをお見送りしたのでした。
■第741回 密かにして壮大なる夢
「75才ツイッターを始めるも何も分からず、紙に書いた文章を秘書にツイートしてもらう。 76才自分で打ち込めれるようになる。77才リプライを返すことが出来るようになる。 78才写真が添付できるようなる。80才スクリーンショットが撮れるようになる。←今、ココ。」
『子連れ狼』『ゴルゴ13』…サブカルチャーという言葉もなかった頃の日本で、本当の意味での漫画文化とその最盛期を作り上げた漫画原作者で小説家、脚本家の小池一夫さんのツイッターが話題になっているそうです。
お生まれは1936年。もちろんSNS世帯ではありませんが、“ん”をあえて“ン”とカタカナ表記にする独特の文体(おそらく、堅苦しい印象を与えないためにあえてなさっているのだと推測しています)、若い人に向けられる温かな目線に、人気と共感が寄せられています。
「やってしまったことの後悔はだンだン小さくなるけれど、やらなかったことの後悔はだンだン大きくなる。78の実感として。」「若い人に言いたいのは、夢や希望が打ち砕かれたら、さっさと次の人生を生きるのだ。人生、二毛作ぐらいは当たり前。長生きすれば三毛作ぐらいいけます。そンなに悲観的になりなさンな。僕の好きな言葉『楽観的になりたければ、客観的になれ』。」
社会的な定年が、人生の定年とは限りません。その前に次なる人生に踏み出す方もいらっしゃるでしょうし、やりたいことと出会ったら70からでも80からでも、始めるのに遅すぎるということはないと思っています。そもそも“定年”は社会が一方的に定めた規則。その先の人生をどんなふうにデザインするかは、自由です。
私たちのように、いつまででも好きなだけ好きなことをしていられる職業は、世の中の人から「うらやましい」と言っていただくこともありますが、この国にいわせると“好きなことをするならどうぞご自由に。その代わり、国は特別保証も援助もしません。年金が少ないのは生涯現役で頑張れよ、というエールだと思ってね”ということだそうなので、一長一短です。「好きなことを続けられる幸せに比べれば、保障がないことなんてなんでもないし、へっちゃら!」と、思えなければ、不安に押しつぶされ心が折れてしまうことでしょう。
高校の非常勤講師をしていた時、音楽の方向に行こうかどうか迷っている、と学生から進路の相談を受けると、きまって「学校やピアノの先生を目指したいのなら、それは素晴らしいことだからぜひ頑張って!でも、演奏家を目指したいのなら迷っている余地はないはず。迷っている時点で、貴重な時間と可能性を削られているということよ。演奏家というのは、“なれないかなれるかわからない、でも誰がなんと言おうとどうしてもなりたい!”という気持ちに突き動かされた者だけが、なれるものなんじゃないかしら」と、話してきました。
名優ロバート・デ・ニーロがニューヨークの芸術大学の卒業式で行ったスピーチの一部を、改めて紹介させてください。「卒業生たち、よくやったな。もう人生めちゃくちゃだぞ。考えてもみろ。看護学部の卒業生にはみんな仕事がある。歯学部出身の学生も完全に雇用される。ビジネススクールの卒業生も問題ない。医学部の卒業生は1人残らず仕事にありつく。誇り高き法律学校の卒業生も大丈夫だ。もし大丈夫でなかったとしてもどうだっていい。彼らは弁護士なんだから。(会場笑)会計学科の卒業生もみんな仕事がある。君らはどうだ? 会計士が羨ましいか? そうじゃないだろう。(会場笑)会計学科の学生には選択肢があった。ひょっとすると会計学に夢中だったのかもしれないが、私は彼らが、成功と安定が予想される仕事に就くために、理性と論理と常識を用いた可能性が高いと思う。」
「理性、論理、常識。芸術学部で?嘘だろ?君たちにはその選択肢はなかったんじゃないか。君たちは自分の才能に気づき、野心を抱き、自らの情熱を理解した。そう感じた以上、もう抗うことはできない。従うしかない。芸術に関して言えば、情熱は常に常識に打ち勝つべきだ。君たちはただ夢を追っているんじゃない。自分の運命をつかもうとしているのだ。君たちはダンサーで、歌手で、振付師で、音楽家で、映画製作者で、作家で、写真家で、監督で、演出家で、役者で、芸術家だ。ああ、もう駄目だ。(会場笑)」
一芸を極めてきた方には、どんな職種の方にもその方独自の哲学、叡智、そして大きな愛と優しさを感じます。歳を重ね、そんなふうに若い人を励ませる“おもしろいおばあちゃん”になるのが、密かな夢です。
■第740回 life is beautiful 3
楽しみにしていた生徒さんの発表会が終わり、充実感とともにお祭りが終わってしまったような寂しさの中にいます。ヨーロッパの方が長いバカンスを終えて久しぶりの我が家に戻った時は、こんな感じなのではないかしら…と、想像しています。
その日は、発表会の前にどうしても行きたいコンサートがありました。世界的なヴァイオリニスト黒沼ユリ子先生が引退なさるラストリサイタル…しかも、アメリカ留学時代の友人のヴィオラ奏者、植村理一さんがマルティヌーで共演されるのです。
新聞各紙にも大きく取り上げられたコンサート。会場には開場時間のずいぶん前から長蛇の列が。やがて、超満員のお客さまで膨れ上がったホールは、大きな大きな愛と音楽の幸せな息吹きに包まれました。
ユリ子先生の音楽には、母なる大地のように国家を越え、大陸や民族をひとつにしてしまう愛のパワーが息づき、その魂は決して火が絶えることのない暖炉のように、わたしたちの心を温め続けてくださいます。植村さんのヴィオラも、豊かな響きでハーモニーを支えるだけでなく、その輪郭を描いてみたりリズムと戯れたり…音楽と一体になって、その庭に遊んでいるようでした。
「皆さま。長い間私の人生にお付き合いくださいまして、ありがとうございました」ユリ子先生の最後のご挨拶に、それまでこらえていた涙がついに溢れ出て…今日この場にいられたことの幸せをかみしめずにいられませんでした。わたしだけでなく、その場にいらしたお客さまも共演者の皆さんも、同じ思いだったのではないでしょうか。
終演後、余韻にクラクラしつつ発表会の会場へ。私の生徒さんやご父兄の方々は、ありがたいことに、リハーサルの時から本番さながらに熱心に出演者の演奏を聴いて、拍手までしてくださるのです。そんな素晴らしく温かな応援の甲斐あってか、本番でリハーサルよりも(そしてレッスンの時よりも!笑)ずっと伸び伸びと表情豊かに弾く生徒の皆さんのスキルの高さ、音の美しさに改めてびっくり!個性豊かで、真摯で誠実なアプローチや「ピアノが大好き!」と
いう気持ちが演奏のすみずみにまで息づいていて、感動の連続でした。同時に、一緒に歩んでくれる素敵な生徒さん、深い愛情と理解で支えてくださる家族の方々への感謝で胸がいっぱいに。…ご褒美のような1日の名残りを惜しみつつ、ひとり家路に着いたのでした。
さて、音楽の力の大きさ素晴らしさに心が震えた翌日は、これまた楽しみにしていた大人の生徒さん7名を自宅にお招きしての、打ち上げパーティーです。
黒沼ユリ子先生のスケールの大きさにインスパイアされて思いついたメニューのテーマは“地球はひとつ??世界の国の家庭料理”。ハンガリー、フランス、ノルウェー、メキシコ、イギリス、イラン、レバノンのお料理を作りました。
買い出しから仕込みを終えるまで約5時間フル回転!おしゃべりもはずみ、「レストランよりずっと美味しい?」「こんなお料理他で食べられない」と皆さんに労っていただいて、嬉しさマックス!あっという間の楽しいひと時でした。
音楽のご縁でつながった大好きな仲間との晩餐。物質的に贅沢なものから得る幸せよりも、こんな時間を過ごせる喜びが、年々大きく膨らんでいます。
■第739回 life is beautiful 2
おそらく自分のステージ以上に楽しみにしている、生徒さんの発表会が近づいてきました。特に小さな生徒さんは、当日が近づくとレッスンごとにめきめき上手になります。「あのね、ママに発表会のお洋服買ってもらったの」「美奈子先生、ほら、これ見て!」キラキラ光るネックレスや、物語の主人公のようなエナメルの靴、レースのついた靴下や、ドレスとお揃いの色のコサージュのついたヘッドドレス…。女の子のテンションはそういったものによってどんどん上がって、緊張よりもワクワクが勝ってくれるのですが、そうは簡単にいかないのが大人の方です。
「ちょっと前までなんでもなく弾けていたところを、つまずくようになってきて…」「なんだか、全体にタッチが浮いてきているような…。弾いていて、心細いような気持ちになってくるんです」「ああ、またひどく緊張すると思うと、怖いわ〜」口々に本番前の心境を話してくださる生徒さんの話に「よくわかります」「そうですよね、私も同じです」などと相槌をうちながら、ステージでなるべく楽な気持ちになっていただけるよう、言葉を選んでアドバイスしていきます。
よいコンディションで当日を迎えるためにはどうしたらよいか。できる限り緊張せずに、のびのび演奏できるようにするための心構えなどをお話しするのですが、アドバイスはアドバイス。生徒さんにとっては「それ、アタマではわかっているけど、実際にはなかなか…」というのも、正直なところでしょう(自分もステージに立ちつづけているので、その辺はよ〜くわかります)。そこで、今回はちょっと違う手法にでてみました。名付けて『お楽しみ大作戦!』
ヒントは、テレビで目にした「これがあるから頑張れるんですよ!」と、嬉しそうにビールを掲げるサラリーマンの姿でした。「そうだ、生徒さんたちにそんな“終わってからのお楽しみ”のひと時を用意しよう!」と考えたのです。そのためには、今までも行ってきた、いつもの“演奏後の打ち上げ”とは一味違う何かが欲しいところ。レッスン後に生徒さんと雑談していてふと思いついたのが、次のような提案でした。
「そうだ!今回は夜の本番ですし、その日は遅くなるので翌日打ち上げをしましょうよ。レストランでではなく、ウチでするっていうのはどうかしら?
その方が、皆さんによりリラックスしていただけると思うし…」生徒さんは少し驚いた様子で「え?いいんですか?でも準備なさるの大変でしょう?」とお気遣いくださいつつ、「じゃ、先生がお料理などの心配はなさらなくていいように、持ち寄りとか、出来合いのお惣菜で…みたいな感じでしましょう!」と、嬉しそうにアイディアを出してくださいました。
どうして今まで思いつかなかったのでしょう。友人を呼んでのホームパーティーなら何年もしているのに、自宅で生徒さんとのお食事会をしたことがなかったなんて!家ならどこかお店を予約しての打ち上げより、もっとざっくばらんに話も弾むでしょうし、生徒さん同士が仲良くなってくださるきっかけになるはず。ピアノは個人レッスンですから、普段はなかなか生徒さん同士の交流ができないので、それもあって『大人のための音楽講座』も始めたというのに、こんな楽しいことを思いつかなかったなんて、なんたる不覚!
かくして、そもそも生徒さんに少しでもステージを楽しんでいただくために、と思いついたのに、結局私が一番楽しみになっているという次第です。だって、自慢じゃないけど私の生徒さんは皆さん本当に素敵な方ばかり。聡明で話題も豊富、おまけに飲みっぷりも麗しい美人揃いなんですもの!
ところで、明日の新春第一弾『大人のための音楽講座』のティータイムには、1月6日のキリスト教の祭日エピファニー(公現祭)のお祝いに食べられているフランスの伝統菓子“ガレット・デ・ロワ”をお出しすることにしています。中にはフェーブといわれる陶器製の小さなお人形がひとつ仕込まれていて、切り分けられた自分のケーキにそれが入っていた人は1日王様、王女様のように振舞うことができ、幸せな一年を過ごせる、という、400年もの歴史がある風習です。フェーブが当たるのはどなたかしら。どんなフェーブが入っているのかしら…。
お米と七草(*地域によっては豆や根菜も使われる)を煮たり、お風呂に柚子を浮かべたり、炒り豆を撒いしたり…。日本には外国人からは不思議にみえるかもしれない風習がありますが、その一つ一つは、季節の移ろいを感じることや地域の慣習をとおして生命の営みを楽しむために先人が残してくれた、ありがたい知恵のような気がしています。
■第738回 life is beautiful
“クリぼっち”という言葉をご存知ですか?数年前から使われるようになったそうなのですが、これまで耳にする機会がなく、今年初めて聞いてその意味を知った次第です。
この時期に聞くとおおよそ想像がつきますが、“クリスマスをひとりぼっちで過ごす”という意味だそうです。そもそもキリスト教徒よりも仏教徒が多い日本で、師走のある晩をひとりで過ごすことはそれほど特別なことでもないと思うのですが、クリスマスは家族や仲間、恋人どうしでワイワイ過ごすべし…というイメージが定着しているということなのでしょうか。“クリぼっち”の集い、というのもあるようですが、「集ったら、もう“ぼっち”じゃなくなるのでは?」と混乱し、その言葉の意味は未だによくわからないままです。
私もそんな“クリぼっち”のひとりということになりますが、自分へのあるプレゼントのおかげで心豊かな聖夜を過ごすことができました。それは、今年2月に91歳でお亡くなりになったイタリアのピアニスト、アルド・チッコリーニ氏のCD、それも56枚組のボックスです。しかも驚くなかれ、それ以外にもさらに2枚を追加して手に入れ、合計なんと58枚!
なぜ、追加したかというと、ボックスに納められているのは20代半ばから70代前半までのレコーディングだったから。追加した二枚はいずれも、それよりもっと後にレコーディングされたものなのですが、どちらかというと本当に欲しかったのはそちらのお年を召してからのものだったのです。
氏は、若くしてその才能が花開いた、類まれなピアニストですが、お弟子さんが「70代からどんどん良くなった」と話しているように、歳を重ねるにつれてさらに演奏に円熟味、深さ、輝きが増していきました。聴いていると、人間がここまで素晴らしい進化を遂げることができるものだとは、という驚きとともに、感動が押し寄せてきます。そんな奇跡を目の当たりにして、力をもらえない人はいないのではいかという気がしてくるほどです。
今年もあと僅か。確実に西暦の数は増し、それとともに歳も重ねていることになります。体や気力がある程度衰えていくのは自然なことですし、それに反して無理に頑張らなくてもいいと考えている方ですが、年齢とともに瑞々しさを増していくことがありうるとしたら、それは何故なのでしょうか。その鍵は、チッコリーニ氏の演奏にあるように思います。
例えば、よほど弾きなれている作品の演奏にも、良からぬ意味での“慣れ”は微塵も感じられず、その代わりに、まるで子どもが初めて見る美しい蝶々に目を輝かせているような「ときめき」が息づいています。そしてまた、相手の目をまっすぐに見て心からの挨拶をするような、作品に対する「誠実さ」や、音楽によせる「感謝」の気持ちがその演奏に溢れているのです。しかも、自らの表現を追求しつつも、自分が作品の前に立とうというエゴイスティックなところはまったく感じられません。それは、他者を受け入れ、包み込むような慈愛に満ちた、音楽を超えたメッセージのようにきこえてくるのです。
その豊かで温かな世界は、一つの道を突き進んだひと、それを極めたひとにしか到達できない境地なのでしょう。すべてのひとが、そんなふうに年月を重ねていくことができるとは限らないかもしれません。でも、同じ道を歩む後輩として、そんな大・大先輩の足跡…氏の演奏のアーカイブ…に触れるのは、なんと心強いことか!
冬至を過ぎて、心なしか日が長くなってきているような気がしています。アルゼンチンプログラムでのリサイタル、久しぶりの室内楽のコンサートに、二年目に入った大人のための音楽講座。プライベートでは、20年以上ぶりのウィーンや10年以上ぶりのブダペストへの旅、留学時代の友人たちとの久しぶりの再会などなど、とても楽しかった2015年ともまもなくお別れです。
38年ぶりの満月のクリスマス。チッコリーニを聴いていて頭に浮かんだのは、「感謝」と「希望」という言葉でした。年齢を言い訳にせず、信じた道を希望とともに邁進したいという思い、そして、今ピアノを弾ける環境にあることや、支えてくださっている周囲の方々への感謝の気持ちとともに今年を締めくくり、新たな一年を迎えたいと思っています。
■第737回 ときめきをもたらすプレゼント
最近の大人のための音楽講座で、シューマンの歌曲集を取り上げました。ひとつは『詩人の恋』、もうひとつは言わずと知れた『女の愛と生涯』です。
前者は男性の、後者は女性の恋とその行方を、連作として構成した歌曲を通してストーリーのように展開していく作品集。『女の愛と生涯』の方はある女性がある男性と恋に落ち、そのお相手からプロポーズをされ、夢見心地のなかで婚礼をあげ、子どもを授かり母となった喜びに浸って幸福の絶頂にあるところに、突然伴侶の死が訪れて悲しみのどん底に突き落とされる、といった内容です。一方、『詩人の恋』は、ある男性がある女性と恋に落ち…、というところまでは共通ですが、結局その女性は彼ではなく、もっと裕福な男性と結婚してしまう、というところが異なっています(こちらの方がリアリティーがある気がするのは、私だけでしょうか)。
切ない思いに酔いしれて揺れる恋心や、愛する人を失った苦しみをなんとか整理しようと、もがく姿…。歌詞がそれらの心情を表してはいるものの、時として音楽がその詩の何倍、何十倍も細やかに、また雄弁に主人公の気持ちを語り、イマジネーションを膨らませます。そして、聴く人は、胸を打ち…いいえ、“撃ち”抜かれるような、あるいは締め付けられるような気持ちにさせられるのです。
特に心惹かれるのは、メロディー自体よりもピアノパートです。時には後奏が、まるでお芝居の終幕のようにすべてをしみじみと語りかけてくるし、歌が入る前…前奏から、その甘美な世界感に引き込まれることもしばしばあって、見事としか言いようがありません。また、歌の伴奏を専門にされているピアニストには様々な音色や弱音の種類や、豊かな繊細さをもった方が多く、ピアノパートをじっくりと聴き込むとかなり勉強になります。
さて、講座ではひとつひとつの歌曲を順を追って聴きながら、ところどころで今何を歌っているのかをお話ししたり、特筆すべき箇所の説明をしたり…。ひとりで聴き入るのも素敵なものですが、みなさんとその素晴らしさを共感しながら聴くことの楽しさを感じることができ、とてもよい時間を過ごすことができました。
講座のあとのティータイムでは、講座の内容とはまったく関係ない話題になることもあれば、講座の内容を膨らませる会話がはずむこともあります。この日は、ちょうど私がテーブルにハーブティーの入ったティーポットをもって行ったタイミングに、いつも欠かさず参加してくださる83歳のMさんが「恋…みなさんもご経験があります?」と、恥じらいがちに切り出しされました。それは、修学旅行の夜の女子トークが連想されるような問いかけでした
音楽に触発されて青春時代を思い返すことも、いくつになっても恋の話ができることも、なんて素敵なことでしょう!そんな、人生に豊かなときめきをもたらすものにこそ、時間やお金を使う価値があるのではないでしょうか。
よく、「日本人は生きるために仕事をするのではなく、仕事をするために生きている」などと揶揄されます。しゃくにさわりますが、連続する数十日間休暇を取るよう、法律で定められていたり、退職後に医療費や年金の心配がいらなかったりする成熟した社会に生きている彼らから我々がそう見えたとしても、仕方がないという気もします。
仕事にしても演奏にしても、“できたかできなかったか”という結果にとらわれがちですが、本当に問われるべきはその内容なのではないでしょうか。それがどんな完成度であったのか。どのような意味や問いかけをもたらすものだったのか。後世に対してどんな意義のあるものになりうるのか…などなど、内容を受け止め、よき判断に基づいてそれを応用、発展させられることこそが、本当の教養なのではと思っています。
クリスマスにジルベスター、お正月。イベントがにぎやかな季節ですが、ただなんとなく散財するのではなく、一年間頑張った自分への心の栄養になるようなご褒美や、周囲の皆さんへの感謝を伝えられるような贈り物を、何か考えてみたいものです。それはもしかしたら、言葉だったり、心が満たされるようなひとときだったり…必ずしも、目に見えるものではなくてもいいのです。もちろん、金額の大小も関係ありません。
ちなみに私は、自分に充分すぎるご褒美をプレゼントしたところです。夜な夜なときめきをもたらしてくれるであろうその正体については、次回お話しさせてもらうことにしましょう。
■第736回 “よいもの”への想い
先週、今週と、友人を自宅に招いての食事会が続きました。ゲストの面々を思い浮かべて苦手な食材に注意を払い、何か食べたいもののリクエストがあった場合にはそれを加味して、季節を考えながらメニューを構成し、食材を調達します。…と、書くとなにやら大変なことに聞こえますが、実際にはそのどの部分も楽しい作業。わくわくして、「この料理はこのお皿に、こんな風に盛り付けて…」なんて想像しながら、イラストを描いてみることもあります。
ちょうどよいタイミングに、父の家庭菜園から無農薬の野菜が送られてくると、ますますテンションが上がります。スーパーマーケットで売られている野菜との違いには、案外大人よりも子供の方が如実に反応する…とよく聞きますが、確かにまったく別物、と思われるものも少なくありません。里芋やさやそら豆などは、特にそうです。“よいもの”を知ってしまったおかげで、以前はさほど気にならずに食べていたあまりよろしくない状態のものを、幸か不幸か受け付けなくなってしまいました。
いえいえ、それは不幸なことではなく“幸”の方だと思っています。食べものにかぎったことでないのですが、よいものを知る、ということは、よいものとよくないものを判断できるようになる、ということ。ものの価値や良さをきちんと判断できるようにならずして、どうして自分の歩んでいく人生を正しく選択していくことができるでしょう。小さな子にこそよい音や本当に美味しい料理、食材を与えることが大切だという考えには、大賛成です。
思い返してみると幼い頃、クラシックのレコードを、ビクター社の真空管のスピーカーからの素晴らしい音で聞いていたのは、とても幸運なことでした。それは柔らかな自然な響きで、今のデジタルの音に比べるとずっと立体的な音像でした。そのうえ、近くで鳴っているようなリアリティーがあったのを覚えています。母によると私は、まだおしめをして、ようやくつかまり立ちができるようになったばかりの頃から、レコードをかけるとそのスピーカーにかじりつき、かろうじて体を支えて立ちつつ、音楽に合わせておしりを振って全身で“楽しんで”いたそうです。
クラシック音楽だけでなく、歌謡曲、童謡、映画音楽…どんな音楽も好きな子供でしたが、いよいよ自分が、自らの人生の進むべき道を決定づけることになったのは、ショパンの音楽との出会いによってでした。「ショパンを好きなだ
け弾けるようになりたい」その思いの強さは、毎日自分をピアノに向かわせ、レッスンで先生にどんなに厳しいことを言われても決してくじけることなく、それどころかますます熱烈に音楽に惹かれていくのに充分でした。
以来、ショパンとは様々な紆余曲折がありました。指では弾けるようになっても、どうしても目指す音楽になってくれなくて、まるで相手を好きになればなるほどギクシャクしてしまう“片思い”のような切なさを感じることも、増えました。でも、これも幸運なこととしか言いようがないのですが、小・中学生当時からフランソワやコルトーといった名手による演奏を聴きこんでいたことは大きな支えになりましたし、今に至るまでの音楽的礎になっているように思います。
そんなふうに、物心つく前から親しんでいたスピーカーからの音や、名手による素晴らしい演奏、といったひとつひとつが、私の美しさやよい音に対する価値観の一端を形成してきたのかもしれません。音楽に限らず、まだ小さくてわからないから、とか、初心者だから、などと決め付けず、考えうる限り、そして望みうる限りの“よいもの”に触れる機会を作ることは、とても大切なことだと考えています。
今年89歳で亡くなったアルド・チッコリーニというナポリ出身のピアニストがいらっしゃいます。1949年にロン・ティボーコンクールで優勝して以来、輝かしいキャリアを築いてきた名演奏家ですが、学生時代に聴いた時には、確かに素晴らしさは理解できたのですが特別なものは感じ取れませんでした。ところが、最近彼の85歳の時の演奏をインターネットで聴き、愕然としました。すでに最高のピアニストとしての名声を得ていた50代の頃よりもずっと素晴らしい演奏をしていらしたのです。彼のお弟子さんによると、「75歳を越えたあたりからどんどん良くなっていった」のだとか。
それは、彼の演奏がいかに美しく、誠実なものであるかを感じることができること自体に感謝したくなるような、幸せな体験でした。少しづつではありますが、地道に学び続けてきたことへのご褒美かもしれない、という気すらしました。チッコリーニのようなピアニストになれるかどうかはともかく、これからも本当によいものを目指し、信じる道をひたむきに歩んでいきたい…と願っています。
■第735回 “美しいもの”を伴侶に
「美奈子先生、大切なご本をどうもありがとうございました!最初から最後まで何度も眺めて、たくさん楽しみました!」…生徒のYさんは、母よりも少し年下の素敵なマダム。ある日のレッスン前、彼女が可愛らしい包装紙にくるまれた本を差し出しました。
いつもおしゃれな出で立ちでいらっしゃるYさん。一切ピアノに触ったことがなく、数年前にドレミからレッスンを始められたのですが、昨年の発表会ではサティのジムノペディをため息が出るほど素晴らしく弾いてくださいました。お嬢様曰く“母はこれから音大を受験するのかしら、と思うほど熱心に”日々、自宅でお稽古してくださっているそうです。
今度の発表会で、Yさんはフランスの作曲家ドビュッシーによる連弾の傑作『小組曲』を、私と連弾することになっています。作品の背景は、19世紀末から20世紀初頭にかけてのパリ。当時の絵画の世界についてはすでによくご存知なので、懐古(古典)主義やアヴァンギャルド、印象主義、ジャポネスクなどが入り乱れたアートシーンを、多様に変化しつつあったファッションや美しさの定義などを絡めて、親しみを持ってイメージしていただけるよう、数週間前に一冊の洋書をお貸ししたのでした。
“Perfume Bottles”というのが、その本のタイトルです。内容は、フランス、オランダ、スペインやイギリスなどの美術館所蔵の、主に19世紀から20世紀にかけての香水瓶の紹介と解説で、いわば香水瓶の図鑑。全編英語による本ですが、美しい写真を眺めているだけでも充分楽しめて、飽きなかったそうです。
ひとことに瓶…ボトル、といっても、その素材はクリスタル(バカラのものも)やガラス、メタル、エナメル、陶器やそれらを組み合わせたものなど、実にさまざま。一見して熟練の職人による手仕事とわかるものも、多くあります。それを入れる箱にも素晴らしい意匠が凝らされていて、香水がいかに特別なものだったかをうかがい知ることができます。デザインは、その香りをイメージできるものであることはもちろんですが、手書きの絵が描かれていたり、立体的な陶器のモティーフが付いていたり、ガラスの彫刻だったり、リュートやホルンなど楽器の形をしていたり…単なる入れ物というにはあまりにも不似合いな、美術品の存在感を感じさせるものが少なくありません。
香水は、何トンもの花からほんのわずかしか抽出されない貴重なエッセンスが使われているのですから、贅沢なものには違いありません。でも、特に第二次世界大戦以前のものには、その入れ物にも現代では逆に不可能なほど高い技術と芸術的完成度が求められていたことに鑑みると、改めて当時の人々の貪欲なほどの美への追求に驚きを感じます。
「香水のために、こんなに美しいものが作られていたんですね。そうそう、本の中に私が前に持っていた香水の瓶も見つけて、嬉しくなっちゃいました」「わぁ、さすがYさん、素敵!調香師が創り出した香りと、それを入れる瓶との調和も、アンサンブルですよね」「本当にそうですね。それを、どんな方がどんなふうに纏っていたのかしらと思うと、さらに夢がひろがります」そう話すYさんの瞳は、少女のようにキラキラしています。
「花瓶に花を生ける時のように、美しいものを近くに置きたい、感じていたいという気持ち。美味しいものを口にしたい、というのと同じように、美しい音、音楽を聴いていたいという気持ち。そんな、ある意味では当たり前の欲求が、彼らの美意識や尊厳を支えていたのかもしれませんね。今回は難しいことは考えず、ステージで一緒に“ああ、きれいだな、素敵だな”と、感じながら弾くことを目標にしてみましょう」実際には、途中でミスして止まってしまったり、テンポがふらついてズレてしまったりもするのですが、なにしろ楽しんでいただくことが一番。そんな思いを胸にお話しながら、レッスンを進めています。音楽が生徒さんにとって、生涯の支えになってくれたら…と、祈るような気持ちです。
「魅力的な唇のためには、優しい言葉を紡ぐこと。愛らしい瞳のためには、人々の素晴らしさを探すこと」とはオードリー・ヘップバーンの言葉ですが、個人的にはそれにもうひと言加えたいところです。「豊かな心のためには、美しい音楽に触れること」と。
生徒さんの発表会まで、あと約一ヶ月。どんな感動と出会えるか、毎回のことながら楽しみで仕方ありません。
■第734回 賢者は語らず
気づくと霜月もあとわずか。今月11日に行われたリサイタルは、すでに遥か彼方の出来事のような気がします。みなさんから感想をお伝えいただいて感激しながら、ふと自分のことを顧みました。そういえば、私はこんなふうに、演奏から感じたことを演奏者ご本人に伝えたことが、どれだけあったかかしら…。
ヨーロッパに留学してからは、戸惑うことなく感じたことをお伝えできるように(というよりも、お伝えしたくて仕方なく)なったのですが、日本の音楽大学に在学していた頃までは、なかなかできていなかったように思います。
演奏家に対してだけではありません。日本ではレッスンのときにも、学んでいる曲や自分の演奏、先生がおっしゃったことについてのコメントを先生にお伝えすることが、よくできませんでした。受け身だったというわけではないのですが、自分の考えや感想を述べていいものかどうか、ためらいがあったのです。
その点、6歳のRちゃんは、すごい。なにしろ、新しい曲を弾いてあげると「すごーい!本当に、すぐそこで川が流れているみたい…」とか、「最後の和音のところが、特にキレイだね!」などと、感じたことをすぐさま伝えてくれるのです。それだけではありません。「おうちで両手で弾いとき、二回か三回まちがえちゃったの…」と気にしている彼女に、あえて「あれ?お稽古のときって、まちがえちゃいけないんだっけ?」とたずねると「ううん。まちがえないと上手にならないの。同じことまちがえないようには気をつけるけど、まちがえながら上手になればいいんだよね!」と、素晴らしい答えが返ってきたりするのです。
8歳のHちゃんも、負けてはいません。彼女は今、ピアノ(p)が四つの超ピアニシモからフォルテ(f)三つまで、広いダイナミックレンジの変化が要求されるバルトークの作品に取り組んでいます。私が「このクレッシェンド、1ページ以上するのでしょう?そしてディミヌエンド(デクレッシェンド)は、ほら、二ページ近くもある。…てことは、あっという間に大きくなったり小さくなったりではなく、時間をかけて少しずつ変化させてくださいってことでしょう?ね、何か作戦立てない?」と持ちかけると、「じゃあね、ここのメゾピアノは、こう。次のメゾフォルテでは、このくらいになって…」と、楽譜のポイントを指
差しながら、自分の体をちぢこませたり伸ばしたり、手を広げたりしながら、顔の表情まで変えて身振り手振りでイメージを表現し、フォルテ三つのクライマックスのところではその場でジャンプしてみせてくれ
「いいね〜!じゃ、その作戦で弾いてみてくれる?」果たして、その後の演奏は素晴らしいものでした。もともと体を動かすのが大好きなHちゃん。少し運動したのがよかったせいもあって(?)、上半身は理想的に脱力され、音も伸びて見違えるように生き生きとしたのです。
「子どもたちって、すごいなぁ…」レッスンが終わると彼女たちを満足げに見送るわたしですが、今日はさらにすごい…圧倒的表現力の持ち主に出会いました。“彼”は、なんと、無言で様々なことを伝えられるのです。
“彼”の正体は、樹齢数百年の木。県内のある景勝地を訪れ、たくさんの古木に出会うことができました。ある時は凄まじいほどたくましく根を広げ、またある時は岩の割れめから根を張って光ある方向へと枝葉を伸ばし…。機構や環境の変化にじっと耐え、それを受け入れて大地に根ざし続けてきたその姿は、本当の強さとはどういったものか。また、本当の美しさとは、そうした強さからこそ生まれるものだということを、それを見る私たちに語らずして伝えているようでした。
「一度、MC(曲間のお話)を入れないでリサイタルをしてみたら?」先日、ある方からそんな提案をいただきました。「演奏だけで最大限を伝え、聴き手がそれを自由に受け止められるように…というコンセプトで」かれこれ20年以上も定着しているトークを入れる演奏スタイルですが、時には確かにそういったチャレンジも必要かもしれません。
“知る者は言わず、言うものは知らず”といったのは老子だったでしょうか。いえいえ、言って伝えることも、大切だとは思います。でも、言わずに伝えるということは、発信する側もそれを受け止める側にも、相互の信頼関係が必要になります。ハードルは上がりますが、それだけにふつふつと闘魂が湧いてくる…ような、予感です!
■第733回 慈しむ愛、ありがたく
「愛の反対は憎しみではなく、無関心です」といったのはマザー・テレサでした。簡潔でありながら考えさせられる、示唆にとんだ印象的な言葉です。
キリスト教でもっとも大切とされている、愛。一方仏教では、反対に“愛してはならない”といいます。愛とは自己愛であり、他人を愛するのはその人を自分のものにしたいという“欲愛”である、と。それに執着するという意味の“渇愛”という言葉もあるそうです。「愛より憂いが生じ、愛より恐れが生じる」として愛を離れることが求められ、その先にあるものとして慈悲が説かれます。
一般的に“慈しみ”という言葉には、立場や年齢が上のものが弱者にそそぐ情け、という意味が含まれますが、仏教でいうところの“慈”は、原語では友情のこと。全ての人に友情を抱くこと、ひいては、生きとし生けるものへの思いやりを意味するそうです。そして、“悲”とは嘆きや苦しみの呻きのことで、仏教の中で大切であるとされている慈悲とは、他人の嘆きを知り、それを共有し、包む心をいうそうです。
キリスト教、仏教、それぞれにおける“愛”の解釈の違いはわかりますが、どちらが良い、悪い、と比べるものではないように思います。どちらにしても深い教えの宿っている言葉ですし、いいな、と感じる言葉をそっと胸に抱き、それが何かのときの支えになればそれでいいのではないでしょうか。言葉にはどうしても不明瞭で、不確かなところがあるもの。言葉そのものを審判するのではなく、真意を感じとることが肝要なのではないでしょうか。
さて。ありがとう、という言葉があります。いうまでもなく感謝を伝える言葉ですが、西洋のように直接「あなたに感謝します」というニュアンスとはちょっと違った趣があります。第一、漢字で書くと“有難う”。難、という文字が入っていることに、違和感を覚えませんか?キリスト教でいう愛の反対が無関心だというのなら、ありがとうの反対は何でしょうか?…あるサイトでそんなことが書かれたコラムを見かけました。
ありがとう、とは、“有り難きこと”…つまり、「有り得ないほどのことです」という気持ちを伝えること。ですから、その反対は“当然”とか、“当たり前”ということになります。ありがとう、は「そのひとつひとつを当たり前ではなく特別なこと、奇跡的なことと受けとめ、心から感謝します」という意味が込められた、まさに“有り難き”言葉だったのです。
言葉には時として様々な考え、思想が反映され、複数の解釈が存在し得るものですが、ありがとう、という言葉の美しさ、深さは、日本人が誇れるもののひとつなのではないでしょうか。
アイヌの人たちは、読み書きを学ばなかったと言います。正確に言うと、学ぶ必要がなかったと。学ぶべきことの全ては口伝えで伝承され、生きていく上で契約書を交わす必要もなかったのです。でも、アイヌ活動家の女性が、ある時をさかいに父親からちゃんと勉強しろと諭されたことを振り返っていました。「父は、私が読み書きを知らないことで(アイヌ以外の)人に騙されてしまわないように、と考えたようです」
「内面から醸し出される美しい音に、日常のせわしなさがどうでもよくなりました」「アルゼンチンなのにバルトークでしょう?何だろうと思ったら、ルーマニアのトランシルバニアというラテン(ルーマニア語はラテン系言語です)からヒナステラへ、さらにヒナステラからELPというプログレッシブ・ロックに結びついていくとは!ああ、みんな繋がっちゃった、やられたな…と(笑)」
皆さまからリサイタルのご感想が寄せられるたび、嬉しさと改めて感じる音楽のちからに身ぶるいしています。皆さんが感じてくださったのは、まさに私が音楽にこめてお伝えしたかったことであり、言葉を越えたメッセージだったのです。
理念や言葉にとらわれすぎず、感性に遊び、他者との違いを受け入れてお互いを尊重しあう喜びを知れば、人生も社会もいっそう豊かなものになる。音楽は、そのためのもっとも素晴らしいツールである…。そう信じつつ、今日もピアノに向かっています。
■第732回 リサイタルを終えて
1年半近くにわたって準備してきたリサイタル“Aires Argentinos”が、終わりました。クラシック音楽の中では異色といえるアルゼンチン音楽、その中でもメジャーとはいえないアギーレやグアスタヴィーノといった作曲家の作品をかなり取り上げるという大胆な(?)選曲は、自分にとって大きな挑戦でした。
果たして、これらの作品を初めて聴くお客さまに楽しんでいただけるのか。受け入れていただけるのか、あるいは、どのように受け入れてくださるのか。第一、お客さまがそんな作曲家や作品名がずらりと並ぶ、よくわからない内容のリサイタルにいらしてくださるのか。…よく知られた曲を弾くのとはまったく違うプレッシャーが多く、正直なところ不安ばかりでした。
リサイタルの前日、あるSNSにこのようなコメントを書きました。
『今回のリサイタルでは、皆さまから「初めて聴く曲(作曲家)ばかりで、楽しみ!」とおっしゃって頂く一方、「知らない曲だから、わかるかしら…」というお声を頂くことも。そうですよね、わかります!でも、ある意味クラシック音楽ほど、“ライブ”で“知らない曲を聴く”のを楽しむのがふさわしいジャンルもないのではないかと…。
当日は、予想を上回る数のお客さまにお運びをいただき、用意していた椅子やプログラムが足りなくなるという嬉しい事態に。でも、それ以上に嬉しかったのは、終演後、今までになくたくさんの感想をお寄せいただいたことでした。
『演奏を聴きながら、ああ、音楽の中にいる。幸せだ…と、しみじみ思いました』
お客さまからの拍手ももちろん嬉しいものですが、お一人お一人がご自身の受け止め方をしてくださり、それを伝えてくださること以上に、ピアニスト冥利に尽きることはありません。
今回はまた、フライヤー、告知、当日のドリンクサービスや写真及びビデオ撮影など、いつも以上にたくさんの方々からの支えを得て、皆さんのちからと共に作りあげたリサイタルでもありました。弾きながらふと、弾いているのは私一人ではないような…誰かに“弾かされて”いるような、あるいはお客さまと一緒に弾いているような気がしたのは、気のせいだけではないように思っています。
関わってくださった全てのみなさんへの感謝の気持ちを胸に、次なるステージに向かっていく所存です。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
■第731回 舞台裏に真実が
子供の頃には、誰しも憧れのスターがいるように、小学校6年の私にも、憧れの存在がありました。その男性は、クリスティアン・ツィメルマン。お話しするまでもありませんが、第9回ショパン国際コンクールの優勝者で、今や名実ともに世界最高のピアニストの一人です。優勝当時の18歳という年齢は当時の私とも近く、貴公子のように端正で知的な風貌と、正統的で清潔感あふれるショパンの演奏に、もうめろめろでした。身の回りのあらゆるものにかの人の名前を書き、いつの日にかお会いすることがありますように…と夢見る毎日でした。
女性に関しては、少々変わっているかもしれません。初めて強い憧れを抱いたのは大学に入学してからのことでした。お相手は往年のハリウッド・スター、イングリッド・バーグマン。やや硬めの演技、毅然とした気品ある佇まい、抑えた演技の中にときおり垣間見せる情熱的な表情と、少しヨーロッパ訛りのある英語(彼女はスウェーデン出身です)、すべてが好きでした。周囲には彼女よりもオードリー・ヘップバーンやグレース・ケリーのファンが多かったのですが、私にとってのハリウッド女優とは、バーグマンのことでした。贅沢と言われてしまうかもしれませんが、映画を部屋で観るのはあまり好きではないので、映画館で上映される彼女の映画はできる限りチェックして、アルバイトで貯めたお金で観に行ったものです。
でも、映画スターやヒロイン以外に、ひそかに素敵だな、と心惹かれていたものがありました。それは、声です。『ウエストサイド物語』のマリアや、オードリー・ヘップバーン演ずる『マイ・フェア・レディー』のイライザの歌声には、もううっとり。自分の低い声がコンプレックスだったので、声には敏感だったのかもしれません。『雨に唄えば』のヒロインの声も素敵だなとは思いましたが、当時は自分のような低めの声よりも、女性らしい、明るく伸びやかな声にひたすら焦がれていました。
マリアやイライザの声は女優さんのものではなく、いずれも同一人物による吹き替えだったと知ったのは、ずいぶん後になってからでした。マーニ・ニクソンさんとおっしゃる方です。前出の二作品の全ての歌の部分の他にも、『紳士は金髪がお好き』のローレライ役のマリリン・モンローの歌(モンローが不得意だった?高音域の部分)や、『王様と私』や『めぐり逢い』でデボラ・カー
の歌う全ての歌も吹き替えていらっしゃったと知って、驚きました。“ハリウッドの声”というニックネームでも知られていた方だそうです。
ミュージカル映画の中で一番好きな作品『サウンド・オブ・ミュージック』の中に、彼女が出演しています。修道女のシスター・ソフィアという端役ですが、主役のマリアことを他の修道女とともに歌うシーンがあります(いい時代になったもので、彼女のサウンド・オブ・ミュージックのキャストのためのテストを動画サイト見ることができます)。ドレミの歌、もうすぐ17歳、私のお気に入り、さようなら・ごきげんよう…その誠実で透き通った歌声は、ジュリー・アンドリュースに勝るとも劣りません。影武者としてハリウッドのミュージカル映画に君臨した彼女ですが、その資料はあまり多くありません。
元サンフランシスコ交響楽団のコンサート・マスター、スチュアート・ケイニン氏と演奏させて頂いたことがあります。若い頃にはたくさんのハリウッド映画の劇中音楽やサウンドトラックの演奏を担当された、ハリウッドでは大変に有名な方ですが、尊大なところはみじんもなく、柔らかい物腰でとても紳士的でいらして、それでいて奏でる音楽はたいへん正統的で、素晴らしい情熱にあふれていたのが印象的でした。第一級の知名度を持っていらっしゃるとはいえないかもしれませんが、間違いなく一流の音楽家でいらっしゃいました。
スクリーンやステージ、歴史上でスポットライトを浴び、光り輝いて広く人々から愛されるスターの存在は、素晴らしいものです。でも、影でそれを支える素晴らしい方々の存在があることも、忘れずにいたいものです。
リサイタルがあと数日後に迫っています。これまで長い間にわたって応援してくださっている方、ステージの裏方を支えてくださる方、聴きにいらしてくださる方…。関わってくださる皆さんへの感謝は、年をかさねるごとに大きくなっていきます。周囲で見守ってくださる方だけでなく、願わくば素晴らしい作品を残してくださった作曲家のみなさんにも天国で楽しんでいただけるよう、できる限りの力を尽くしたい気持ちでいっぱいです。
■第730回 母の肖像
西洋でいうところの“諸聖人の日(万聖節)”が誕生日です。またひとつ歳を重ねる日が近づいています。
子供の頃の懐かしい写真がでてくると、私にもこんな時があったのね、という感慨とともに懐かしくしげしげと見入ってしまうのですが、目を奪われるのは自分の顔や体つきよりも洋服だったりします。意外にも、たいてい感じのいい身なりをしているのです。
小さい頃から、あたり前のように母お手製の洋服を着ていました。母と相談して、これがいいだろう、というデザインを厳選し、生地やその色を決め、きちんと仮縫いして仕立てる一点もののオートクチュールなのですから、当然体にぴったり。自分で言うのもおかしいことですが、似合っていないわけがありません。
母曰く「高価な既製服を買うお金がなかったから、節約のため」だったそうですが、周囲の友人は私の装いをみて「鈴木さんはいつも素敵な服を着ていて、うらやましい」とか、「いいところのお嬢さんなのでは?」と思っていた、なんて話を今になって聞いて、笑いあうこともあります。
確かに、今思えばとても贅沢なことです。母とファッション誌を覗き込んでどれがいいかデザインを選び、どんな生地にするかや、襟の形、袖の長さなど、デザインの変更点について話しあって、いざ材料の買い出しへ。メインとなる表生地のほか、裏地、ボタン、バックル、ファスナー、そして生地の色に合わせた糸にいたるまでを揃えます。その間、頭のなかで完成をイメージして、時にはボタンの素材や直径の選択に迷ったりもしました。
母は畳に型紙用紙を広げ、その上に生地、チャコペーパー、型紙をのせていよいよハサミを入れていきます。見ごろ、袖、襟…各部分が切り離され、それらがつながり、平面が立体になってきてやがて仮縫いへ。裾にまち針がたくさんついたワンピースやスカートを、針が抜けたり動いたりしないよう気をつけて着て丈を確認、あるいは微調整。次に母は決まって「はい。ゆっくり一回転して」と指示します。裾に歪みがなく、ラインが美しく整っているかをチェックするのです。
そうやってひとつひとつ洋服の制作にかかわっていくうちに、ウエストラインの位置の違いやフリルの幅、襟の開き加減や袖の形、長さといったちょっとしたことが、全体の印象やバランスをおおきく左右することが、感覚的に理解できるようになりました。ワンピースに至っては、ベルトのバックルの素材や形(丸いか四角いか)、といったわずかな違いが、がらりと全体の雰囲気を変えてしまうこともめずらしくありませんでした。
新しく縫いあがった洋服を初めて学校に着て行く時のワクワク感は、いまでも忘れられません。大学生時代はもちろん留学している間も、日本から届いた母の洋服をよく着ていました。「それ、ママメイドの新作?」と、友人が気づいてくれると、とても嬉しかったものです。
『大地』で知られるアメリカ人女性初のノーベル文学賞受賞者、パール・バックのお母さんは、ことさらに上質な小説を好み、一方俗な雑誌を嫌ったそうです。小説『母の肖像』の中に、「心の中にクズをつめ込みたくありませんからね。口の中にゴミを入れないのと同じですよ」というお母さんの言葉がでてきます。彼女は幼い頃から良いものを与えるよう努めたことで「子供たちは早くから最高の文学作品以外には親しみを感じなくなった」とも語っていたそうです。
子供の頃からよいものに触れることは、大人が考える以上に大切なことかもしれません。私が周囲から「おしゃれね」と言っていただくことがあるのは、半分以上はお世辞だとしても、あとの約半分は子供の頃の“オートクチュール体験”からなのでは、という気がしています。
「いつかはお前にも、音楽は技巧やふしだけでなくて、人生そのものの意義であり、限りない悲しみと、堪えられない美しさをもつものだということを悟る日が来るだろう」これもパールの母が彼女に告げた言葉だそうです。
今度のリサイタルでは、久しぶりに母が縫ってくれたドレスを着ようと思っています。
■第729回 『メキシコ人はなぜハゲないし、死なないのか』
『メキシコ人はなぜハゲないし、死なないのか』これまでに読んで印象的だったものに、こんなタイトルの本があります。ロックバンド“叫ぶ詩人の会”のメンバーだったドリアン助川さんこと明川哲也さんによって12年ほど前に執筆された長編小説で、650ページを超えるその本の厚さは迫力満点。机の上に“自立”するほどです。
内容は、鬱に襲われて自殺しそびれた日本人中年男性の身に起こる、摩訶不思議な冒険物語。世界一自殺率が低く、もっとも鬱から遠い国メキシコの秘密に迫りつつ、思いもしない展開も待ち受けています。
主人公の前に人間の言葉を話すネズミたちが出てきて、彼らとともに世界中に吹き荒れ始めた正体不明の“憂鬱の砂嵐”に立ち向かう…なんていうと、ふざけたような印象に思われてしまいますがそうではありません。いわば、まったく新しい切り口のファンタジー、といったところでしょうか。既成の書法にとらわれない斬新なストーリー展開。とても長い作品なのにしっかりと構成されていて、まったく飽きることがありませんでした。それどころか、知らず知らずのうちにその闊達な筆力に引き寄せられ、心がスッと楽になるようなメッセージを受け止めつつ、あっという間に読み進んでしまいました。
未知の世界を、あたかもその場を体験しているかのように思わせ、遊ばせてくれる文学の面白さが、大好きです。映像がないからこそ、自由に想像の翼を広げることができるところが、その大きな魅力です。音楽芸術も然り。ところが最近、映像美術にもそれと同じ楽しみがあることを知りました。
例えば、写真。そこに川が流れ、光が差し込み、その色が水面に映しだされているとします。それが素晴らしい写真であるときには、あたかもその川のせせらぎが聞こえてくるし、空気の乾きぐあいや、ともすると撮影された前後の光や水の変化…つまり時間の流れまでもが感じられたりするのです。
でも、よくよく知ってみると、豊かなイメージの世界に遊ばせてくれるものであればあるほど、その向こうには必ず表現者による精緻な論理があることに気づきます。写真であれ音楽であれ、一見何気ない表現に見えるものにも実は明
確な方向性があり、イメージを具現化し、相手に伝えるためのテクニックが的確に使われているのです。それは、分野がなんであれ、完成度の高い作品には共通することのように思います。
「理論や教養は、持っていればいいというものではない。有効に使われてこそ、価値がある」と言ったのは誰だったでしょうか。リサイタルを前に、その言葉をいまいちど、心の中で反芻しています。さりげないフレーズの中に息づいている、切なさ、やり切れなさ…言葉では言い尽くせないような深い感情を、どのように音に表現したらいいのか。少しでも良いものになるよう、手持ちの限られた方法論をあれこれと試し、聴く人の立場になってさまざまな角度から検討しては、やっぱり違うかも、と思いなおすことを何度も繰り返している日々です。
ましてや、タンゴではない、アルゼンチンのクラシック音楽という、一般的に広く知られていないジャンルの音楽をお伝えするとなると、責任もかかってきます。演奏家は、自分の意のままに弾いているようで、実際には楽譜に託された作曲家の意図やその真意を読み込んで表現するという、メッセンジャーのようなミッションがあるのです。
「そうですよね。でも、私たちはアルゼンチンの音楽が聞きたい、という以上に、美奈子先生のパフォーマンスが聴きたい!と思って、リサイタルに出かけるんですよ。お弾きになるのがショパンであれ、バッハであれ…その作品を聴くというのももちろんありますけど、一番は美奈子先生の世界観や表現、音に触れたい!っていう気持ちなんです。(リサイタルの日は)会社の休みもとれたし、もう、楽しみにしてますよ〜!」今日レッスンにいらした生徒さんが、こんなことを言ってくださいました。悶々と苦しんでいたときに、演奏家冥利につきる何にも勝る嬉しい言葉でした。ありがたくて、不覚にも涙が浮かんでしまいました。
メキシコ人にはなれないけど、失敗をおそれず、信じた道を愚直に歩み続ける人でいよう、と、改めて心に誓った昼下がりでした。彼女の温かな励ましに、心から感謝しています。
■第728回 大地が育むもの
友人夫妻が、近くで南インド料理店を営んでいます。開店前から内装のイメージや店名をどうするか、などの相談を受けたり、自宅にディナーにお呼びしたり…と、身内のようなお付き合いをさせてもらっています。
インドカレーというとバターチキンのようにとろりとした、バターやギーを使ったカレーのことで、ご飯ではなくナンと一緒に食べるもの、というイメージがすっかり定着している日本。バナナの葉の上で、さまざまなカレーやチャトニというソース(薬味的な役目も)やサンバル、ポリヤル、ラッサム、お豆のペーストを揚げたワダやパパドといった、あまり馴染みがあるとは言えない南インド料理の数々を手で自由に混ぜ、手で食するというミールスという食文化を紹介し、その良さを理解してもらうのは、並大抵なことではなかったのは想像がつきます。
もちろん、手で食べるかシルバー(スプーンなど)を使うかは、それどれのお客様の選択に委ねられるのですが、初めてミールスを手で食べた時の感激は忘れられません。左手は使わず、右手で(勇気を持って)好きなカレーや薬味を自由に混ぜ、指でまとめて口元に持って行き、親指で押し出すようにして食べるのです。
パンやおむすびのように、乾いたもの、まとまったものなら手で食べるのに抵抗はありませんが、スープやソースのかかったご飯を手ですくうのは、はじめはイタズラでもするような妙な感覚でした。でも、一度慣れてしまうと、手で混ぜている時から、すでに美味しさが感じられるようなってきました。それは「指の先にも味覚があるのかしら?」と思うほど、確かで、不思議な感覚でした。スプーンで食べてみたこともありますが、状況が許されるなら手で食べた方がずっと美味しくいただけることは確かです。
考えてみたら、“目で味わう”のと同じように“手(指)で味わう”ということがあっても、おかしくありません。
少なくとも、目よりも手の方が、ずっと触感が繊細なのですから(試したことがない方には、ぜひ一度はお試しになっていただきたい!)。
野菜や豆が中心の、薬膳料理とも言われるミールスに使われるスパイスには、それぞれ医学的な効果があります。代表的なものをあげると、例えばシナモンは血糖値を抑え、コレステロールや中性脂肪を減らす効果、カルダモンは気分を落ち着かせる精神安定効果や体力増進(清涼感のある香りなので、食後やデートの前に口に含む方も…)、クミンシードは抗がん作用や関節痛の緩和、コリアンダーはカルシウムや鉄分を含み、腸内環境を整えますし、ターメリック(うこん)は言わずと知れた肝機能を高める効果などが。
そもそもこれらスパイスは高価なもの。南インド料理では、伝統的にこれらスパイスをやみくもに何種類(何十種類?)もではなく、食材や料理にあったものを必要なだけ用います。何種類もの食材をスパイスとともにバランスよく体に取り込むという“医食同源”の理念と、手に入る食材をできる限り美味しく調理する知恵が、一つ一つの料理に息づいているのです。
友人のお店も開店から5年。雑誌やテレビなどのメディアにも取り上げられ、今や都内から食べに来るお客様も絶えない南インド料理の名店になったと思ったら、またマスターが新たな挑戦を始めました。自家菜園です。曰く、「お客さんに、もっと美味しくて体にいいものを出したい…と思ったら、いつのまにか畑をやっていたんですよ」
自家製の野菜をつかって料理を手作りする。その昔は当たり前のように各家庭でも行われていたことですが、いつしかそれが何より贅沢なものになっています。野菜を作っている人は異口同音に「畑はまず、土作りから」と言いますが、とすると、テーブルにのぼる料理は、思うに厨房ではなく大地からすでにその調理が始まっているのです。
手で食べた時の私は、人の手で土を耕し、種を植え、育て、収穫し、調理し、口に運ぶ…という綿々とした“手の連鎖”に、知らず知らず感動していたのかもしれません。
音楽もまた、然り。楽譜に書かれた音符は、そうやって大地から命をもらって生きている人によって紡がれ、人の手によって奏でられ、人の心の栄養になっていく…。そう思うと、畑に置かれる一粒の種も、私たちが奏でる一つの音も、命を育み慈しむ、なんとも愛しいものに感じられてくるのです。
■第727回 カメラに映し出されるものは
このオフィシャルサイトも、開設されてから10年が経ちます。初期の頃からご愛読くださっている方はご存知ですが、当時はこのような立派なものではなく、ブログにコンサート情報とエッセイのページが併設されているようなカジュアルなスタイルでした。
その頃からご覧いただいている方から、「以前のように、写真つきで毎日のように更新されるページは、もう見られないのですか?」というお問い合わせをしばしばいただいていて、何か考えたいなぁ、とずいぶん前から思い続けていたのですが、やっと近々(年内?)、リニューアルしての再登場が実現しそうです。
写真に簡単なキャプションをつけた、SNSへの投稿のようなものになるかもしれませんが、それだけではせっかくの新企画(?)としての新鮮味が足りません。とはいえ、あまり気張らずに続けられ、かつ少しでも良いものにするためには、どうしたらいいか。私の拙いキャプションのレベルを上げるのは、哀しいかなほぼ不可能…と、なると、残るは写真のクオリティーをなんとかして上げよう、ということになります。
もともと写真を撮るのは嫌いではありませんし、カメラ好きの友人の影響もあって、かつてはローライフレックスという6×6のフィルムサイズの二眼レフ機や、蛇腹式のフォクトレンダーという銀塩カメラなんぞをいじっていたこともあったのです。でも、世の中の主流がデジタルカメラになってからは今ひとつ食指が動かなくなり、数年前のイタリア旅行のためにコンデジと呼ばれる小さなデジカメを買って以来、ほとんど触っていません。SNSへ投稿する写真は100パーセントスマートフォンのカメラで撮影したものですし、この頃は海外旅行すらデジタルカメラを持っていかないほど、カメラから遠ざかっていました。
でも、楽しんで頂けるようなコンテンツにするためにもよい写真が必要、と考えたとたんにカメラ愛が復活。またカメラのことを調べ直して、この機会に写真の撮り方もきちんと勉強したい、という気持ちがフツフツと湧いてきました。始め出すととことん凝る性分。今回もご多分にもれず、最近のカメラの機能や各メーカーの特徴についてなど、せっせとカタログやメーカーサイトなどを見て情報を集め始めました。
フォーマットやセンサーの種類とその違い。RAW現像やローパスフィルター、ディストネーションとは。コンティニュアスAFCと予測駆動AF(アルゴリズム)…。まずはカタログにならんでいる単語から、ひとつひとつ理解していかなくてはならないようです。とはいえ、知らないことを知るのは楽しいもので、寝不足の日が続いています。
その時の空気や光と影をどう切り取るのか。どんなものをどんなふうに撮りたいのか。自分がレンズに最も求めるものは何か。カメラにもそれぞれに個性や特性があるので、漠然と「とにかく映りのいいものを」というだけではとても絞りきれません。
「演奏を評価されるようになるには、どうしたらよいですか?」ふと、そんな質問を受けた時のことを思い出しました。そのとき私は、少し気障かなぁ、と思いつつ「その“演奏”のところを“人生”という単語に置き換えて考えてみてください」と答えました。とどのつまり、その質問に対する正解は、無限にあるとも、ひとつもないともいえるのです。
本当は音楽家として生きて行くための処世術のようなものをお伝えすべきところだったのかもしれませんが、私自身、それとは無縁に生きているのでよく分かっていません。評価のために生きるのではないのと同じように、評価のために弾くのもそのために音楽と関わるのも何か違うと考えているので、質問に違和感を覚えてしまい、そうとしか答えられませんでした。
さて。かくいう私は最終的に、どんなカメラを選ぶのでしょうか。チルト式に可動する液晶モニター、たくさんのエフェクト加工フィルターややみくもに大きな画素数、スペックなどは必要としなさそうです(というより、使いこなせない)。一方、ファインダーは電子ビューではなく光学式じゃないとどうもしっくりきません。
どんなカメラを選ぶかで、写真だけでなく人生に求めているものまでもが見えてきそうな気がしてきます。自分が試されているようで、写真の勉強をする前からなにやらドキドキしています。
■第726回 本当に大切なもの
ラインナップがユニークで、上映されていれるものはみんな観たくなってしまう、大好きなミニシアター系の映画館があります。先日久しぶりにそこで映画を観ました。『夏をゆく人々』という、イタリアの若い女流監督の作品です。
「トスカーナ地方のとある村で、昔ながらの養蜂を営む家族の物語」、と聞くと、登場人物の豊かな喜怒哀楽が、ため息が出るほど美しいトスカーナの四季折々の風景を織り交ぜ、表情豊かに繰り広げられる…といったイメージを抱きがちですが、それはいい意味で裏切られます。チラシには“ある家族の心模様をこまやかに描いた傑作!”なんて、ありきたりな(失礼!)キャッチが踊っていますが、私の受けた印象はそれとは少し違うものでした(ちなみに、映画のプログラムに掲載されている映画評論家のレビューとも違います)。
極力まで抑えられた演出と、俳優さんのあまりにも自然な演技、台詞をそれと感じさせない、研ぎ澄まされたウィットが息づく脚本。心理描写はあくまでも最小限で、そのほとんどは演出や台本によって分かりやすく説明されるのではなく、観客が注意ちょっとした“間”やら、俳優さんのほんのわずかな語調、表情の変化から、注意深く感じ取らなければならない種類のものです。それは“こまやかに描いた”というよりも、あえて“こまやかに描きすぎなかった”といった印象でした。
内容を公開してしまうことになるので詳しくは述べられませんが、それは、3Dや特撮などの技術がてんこ盛りで、観客がするのはただ、めまぐるしい展開や派手なアクションにハラハラドキドキ振り回されることだけ…という映画の、まさに対極をなすもので、「この作品は観客が観た時にその場で、個人個人によって完成されるものなのでは?」とすら感じました。観ているこちらの感性や価値観が試されるような楽しさがある、と言うこともできるかもしれません。
人間の肉眼で捉えたものと限りなく近い、なんのデジタル加工も施されていないフィルムカメラの写真のような簡素な映像は、「人間(人生)にとって本当に大切なものとは何なのか、何は必要ないのか」という映画のテーマそのものにリンクします。
大切なメッセージは、あくまでもメタファー(暗喩)によって観る側の捉え方に委ねられるので、観客はあれこれと考えや想像をめぐらせて、いつのまにか作品に“巻き込まれて”しまいます。これは“映画作品”というよりも、観客によってその場で完成される一種の“映像作品”として作られたのでは?という気すら、しました。
表現することと向き合うあまり、つい、譜面から読み取られる作曲家のメッセージや、感じたことをできる限り明解にお客さまに伝えなくては…と思ってしまいがちですが、もしかしたらすべてを伝えようとしすぎているかもしれません。実際、説明から理解したことよりも、何かから自ら感じ取ったことの方が鮮烈なものです。
ある作品に向き合ってあれこれ感慨にひたったり、考えをめぐらせたり、「あれはこういう意味だったのだ」と、ある時ふいに腑に落ちたりするのは、人間にとって最も楽しい芸術体験なのではないでしょうか。それを聴いた方が何を感じてくださるか。何を持って帰ってくださるか。すべてを言い尽くそうとしすぎないで、お客さまにゆだねることで、本当の共感がうまれるとしたら、そんなに素晴らしい喜びはありません。
「それ、何かと似ている。何だろう…」気になっていたのですが、ついさっきわかりました。利休の侘び茶の世界観そのものだったのです。茶室への小径、茶室のしつらえ、掛け軸や茶花から、客人は主人からのメッセージを受け取り、一服のお茶を丁寧に味わうことですべての調和を受け取って心の平穏を取り戻す…。
「お金で買えないものを大切にしています」と話した父親は、結局大きな買い物をして家族の気持ちを乱してしまいます。本当に大切なものを見極めるのは、思っているよりも難しいこと。考えと行動が必ずしも一致しない無邪気さもまた、人間の性です。
10月、11月とコンサートが続きます。大切なメッセージをお客さまと共有できる一時になりますように…と、祈るような気持ちです。
■第725回 カメラの音楽
「さて、あなた室内楽(chamber music)のレッスンは受講しますか?」リスト音楽院の事務室で、入学の手続きのときにポルガールさんにこう尋ねられたとき、その前日にブダペストに着いたばかりの私はとっさにその意味がわかりませんでした。「え?チェンバー…の音楽?それはなんですか?」なんということでしょう、情けないことに私はその時まで、室内楽を英語でなんというのか知らなかったのです。
主に留学生を担当するインターナショナルセクションのミセス・ポルガールは、何ヶ国語をも操ります。怪訝そうに聞きなおす私に「室内楽ですよ。ほら、musica da camera,Kammmermusik, musique de chambre …」彼女はもどかしそうにイタリア語、ドイツ語、フランス語で次々に同じ意味の言葉を連呼しています。私はハッとひらめいて「あ、わかりました!室内楽!ヴァイオリンやチェロなどとのアンサンブルですね?はい、受けます、受けたいです!」と、あわてて答えたのでした。やれやれ。
ミセス・ポルガールの話から、イタリア語musica da cameraの「カメラ」という単語を聞き取れたのが幸いしました。その昔、外の景色を壁にあいた穴から、外の景色を部屋で見たことがカメラの始まりだったといいます。それで、部屋、室内を意味するカメラという単語が、その語源になった…という話を、聞いたことがあったのです。転じて、ホールのように大きな場所ではなく、部屋で奏でる小編成による器楽合奏の類を、musica da camera=室内(カメラ)の音楽、と呼ぶ、と。
今やカメラは屋外どころか、宇宙にまで飛び出して大活躍しています。部屋に居ながらにして地球のあらゆるところの航空写真をほぼリアルタイムで見ることができますし、ご所望とあらば海底の様子を覗くことすらできるのです。ハイビジョンがさらに進化した、4Kといわれる映画並みに美しい動画も、ほんの数百グラムのデジタルカメラで撮影できるようになりました。技術の進歩とは恐ろしいものです。
実は、かねてからこのオフィシャルサイトでも写真ギャラリーのコンテンツを増設したいと考えていたこともあり、ちゃんとしたカメラ(スマートフォンではなく)の導入を検討してみようとカタログをいくつかながめてみました。モニターはフルサイズにするのか、APSにするのか。一眼レフなのか、ミラー
レスなのか…数え切れない選択肢の中から、とうとう「よ〜し、もし買うならこれ!」と絞り込んだある機種のパンフレットを改めて見直したとき、その最初のページ冒頭の書き出しに、ふと目が留まりました。
“撮影の主人公は高機能なカメラか、意志のあるフォトグラファーか。”文章はさらに、“高度にテクノロジーが発達した今だからこそ、私たちはプライドを持って後者を選びたい”と続きます。
「やっぱりプロの書くキャッチは違うや。上手いなぁ…」思わず、う〜ん、と声をだして感心してしまいました。しかも、これは常日頃から自分で自分に言い聞かせていることだったのです。つまり、“(演奏に大切なのは)テクニックや有能さ、優秀さのアピールではない。意志を持って表現すること、本物の表現者たることを目指すべし”と。
カメラも楽器も、所詮は道具。所有して満足するだけでなく、それを使っていかに被写体・作曲者と自分、自分と聴き手、被写体・作曲者と聴き手…のプリズムを充実させ、輝かせるかが大切だし、そこが醍醐味なのではないでしょうか。
構図をとり、光の絞り方を判断し、シャッタースピードを調整して、場合によってはレンズの特性やズーミングを考えて、瞬間を切り取る。動体を素早くとらえるオートフォーカスの魅力も捨てがたいですが、マニュアル操作による撮影には、感性にまかせつつも何に焦点を当ててどこを強調するか、どんな印象にまとめていくか…などを構成していく音楽の勉強に、なにやら通ずるものを感じます。
基本的に、楽器の演奏は室内…“カメラ”で行います。かつてカメラが外の光と室内をつないだように、音楽もまた、違うところ(違う時代も含めて!)にいる人々の心を結ぶ役割を果たすツールだともいえます。いつの日か、お気に入りのカメラをもって外に撮影に出かける時を夢見つつ、カメラ(部屋)にこもって楽器を弾きながら、音楽を奏でる楽しさを改めてかみしめています。
■第724回 男は度胸、女は根性?
ハンガリー留学時代、一緒にハンガリー語のプライベートレッスンを受けた友人と、27年ぶりに再会しました。
日本の音楽大学では古楽器を専攻していたのですが、漠然と日本の音楽教育に疑問を抱いていた彼女は、留学先のハンガリーでコダーイメソッドを始めとする優れた音楽教育メソッドに触れ、大きな感動を覚えました。そして「こんなに素晴らしいものを、なんとか日本にもっと広く紹介したい」という熱意に燃えてハンガリーの音楽教育の第一人者の門を叩き、彼女の生徒として、またあるときには助手として、幼稚園を始めあらゆる教育機関でその現場を数多く経験。6年間のハンガリー留学を終えた後も年に何回かハンガリーに渡って研究や発表を重ねる一方、講習会や講座を依頼されては忙しく日本中を飛び回っています。
「仕事で(地元福岡から)東京に出るので、会えない?」と、連絡があったのはその日のほんの2〜3日前。待ち合わせの場所に現れたのは、20代の頃と少しも面影の変わっていない彼女の姿でした。「 Kちゃん!わぁ、ぜんぜん変わってないね!」「本当、お互いに!どうしよう、ブダペスト以外で会うのは初めてよ!」二人とも興奮のあまり、つい、声が高くなってしまいます。
知的でいながらも少女のように可憐な印象の彼女ですが、私の帰国後間もなく、お母さんになったことは彼女からの手紙で知っていました。「27年ぶりということは…Aちゃん(ご子息)、もう26歳とか?」「そう!信じられないよね〜」私は少しためらいつつも、彼女と私の仲なのだからと思い切って、聞きました。「ハンガリーでの出産や育児、大変じゃなかった?」私の友人を見渡しても、もはやちっとも珍しいことではないのですが、彼女はいわゆるシングルマザーなのです。
「ぜ〜んぜん!むしろ、日本よりもすごく楽だったと思う。費用も日本よりもずうっと安く済んじゃったし、ハンガリーには“本当にありがとうございました”っていう気持ちよ!」晴れ晴れとした表情です。帰国までの数年間、ブダペストで育児をした彼女曰く、学生としてハンガリーに滞在している以上、健康保険や医療をうけるときの扱いは一般の国民とまったく変わらなく、公的な医療機関なら負担はゼロ、もしくは最小限(私がリスト音楽院に留学している間
もそうでした)。父親と母親の籍が一緒であろうとなかろうと、育児に対する国のもろもろの体制はそれ以上を望めないほどに整っていて、なんのストレスや不安もなく勉強を続けながら、あるいはキャリアを築きながら、子育てができたそうです。
Aくんの誕生をハンガリーの周囲の友人もとても喜んでくれ、「近所の人にもうんと助けてもらったのよ。」その結果(?)、彼はいつのまにか、おばさまたちとの高いコミュニケーションスキルを身につけることができたそうです。しかも、ブダペストではハンガリー語で、日本に帰った後は日本語で。
聞けば聞くほどワクワクする彼女の話につい、「じゃ、彼モテるでしょう?」と尋ねると「そうね。彼女は“常に”いるわねぇ〜」と、常に、のところにとびきりのアクセントをつけ、いたずらっぽい笑顔を見せました。20代の頃にはなかった彼女の“母”としての顔が、ちらりと見えました。
「逆に日本に帰ってこの国の出産、育児の環境を知って“なんて大変な!”って驚いたわ。これでは少子化にも歯止めがかかるとはとても思えない。少子化なのに託児所や保育所の数が足りなくなっているといわれるけど、それは共稼ぎ…あるいは、働きながら育児をしなければならないお母さんが、それだけ増えているっていうことなのよね」
それにしても、女性は…特に、母は強し!この頃よく「いまやすっかり“男は愛嬌、女は度胸”ですな」なんておっしゃって苦笑いをしている男性をお見かけしますが、いえいえ、遠慮は無用です。どうぞ、思う存分“度胸”を発揮して世の中を闊歩してくださいませ。女性は女性で、それに勝るとも劣らないまっすぐな“根性”をもって、謹んで男性の皆様をサポートいたしますゆえ。
■第723回 本当の親孝行
つい先日、フェイスブックで大学の総務課から、ある同窓生の死を知りました。心筋梗塞による急逝とのことでした。あまりに突然なことに、ご家族や門下生の動揺の大きさへの配慮から、一日公表が控えられたほどでした。
在学中は彼とほとんど話をしたことがありませんでしたが、オーケストラの一番後ろに控えていてもティンパニの側に立っているだけで華があり、“ここぞ”というクライマックスでの情熱的な演奏とその美しいアクションは、まさに“華麗”という言葉がぴったりでした。卒業後は都内の一流オーケストラで打楽器奏者として活躍、数年前に退団したあとは母校桐朋学園大学の准教授となって、後進の指導にとても熱心に取り組んでいたそうで、ウォールには同窓生から、たくさんの生徒さんに慕われていた様子を語るコメントが、次々に寄せられました。
「ご家族への連絡もしばらくは控え、そっと見守ってくださいますよう、ご配慮をお願いいたします」心が痛む辛い知らせを、ありったけの誠実さを込めて伝えてくれた総務課の友人もまた、同級生です。彼女の心のこもったメッセージを読むにつけ、信じがたいショックを実感して呆然としてしまいました。私たちは口々に彼の思い出やお悔やみを述べ、近親者のみで執り行われる葬儀に出席できないかわりに、ネット上ではありますが皆で心を合わせてご冥福をお祈りしました。
年賀状の季節に、喪中のはがきによってご家族の訃報を知ることは、年々増えています。あまりにもはやく、若くして伴侶を失った友人もいます。日頃、自分の体の丈夫さに甘え、健康でいられて当たり前、好きなことができて当たり前…と感じてしまいがちですが、命には限りがあることをきちんと受け入れ、感謝して生きていかなくては、と身の引き締まる思いでした。
「親孝行したい時には親はなし」などと言われますが、これは川柳ではなく諺なのでしょうか?
諺には「悪事千里を走る」とか「頭隠して尻隠さず」など、皮肉なニュアンスが漂うものが少なくありません。「急がば回れ」「時は金なり」など、教訓のような諺は日本だけでなく外国にも同じようなものがありますが、親孝行、という言葉にあたる外国語は、なかなか見つかりません。これは、そもそも親孝行という思想が、両親や祖先を敬うことを美徳とする儒教的なところからきているからだと言われています。一緒に旅行したり、孫の顔を見せに行くなど、何か親が喜ぶことをするのも親孝行には違いありませんが、親、祖先、ひいてはそれらすべてを育む自然への畏敬の気持ちこそが本来の“親孝行”である、というのです。
そう考えるのならば、親孝行は親が他界した後もできる、ということにもならないでしょうか?親に限らず、そして存命している、していないにかかわらず、折に触れてかの人を思い、感謝し、自らの生き方を省みて丁寧に一日一日を重ねることは、立派な“孝行”になるのではないでしょうか。
幸いなことに両親ともに健在で、今日9月5日は父の誕生日です。その日はまた、私が留学のため初めて外国(ハンガリー)へひとり旅立った、かねてからの夢を実現させた大きな記念日でもあります。
少々虫がいい考えかもしれませんが、両親がしてくれたことすべてに感謝しながらピアノを弾くことが、私にできる最大の親孝行だと思っています。もちろん、その感謝は両親にだけ向けられるものではありません。関わってくださる全ての方々、聞いてくださるお客さま、そして亡き恩師…みなさまへの気持ちで音を奏でているのだと感じることが、この頃増えています。
私がピアノに向かうことが、少しでも周囲の方々への“孝行”になりますように…。突然の同窓生の訃報をきいて、そんなことをあれこれと考え、彼の冥福を静かに祈った夜でした。雨音が、しめやかに夜の闇を包んでいました。
■第722回 体のことは、体に聞こう
数年前に均一ショップで購入した観葉植物がぐんぐん大きくなり、天井に届いてもなお成長を続けて窓枠を這うばかりの勢いだったのが、このところまったく元気を失ってしまいました。厳しい夏なら昨年だって経験しているし、年末年始の帰省や海外旅行で9〜10日水やりができなくても、びくともしなかったというのに、どうしたのでしょう。
7月下旬のとても暑い時に、コンクールのお仕事で5日ほど家を空けたのが致命症になったのでしょうか。昨年までは、同じ条件で持ちこたえてくれていたのですが…。友人に話すと、「鉢植えの周りの環境で、何か変えたことはない?」「ないわよ。同じところに置きっぱなしだもの。温度も湿度も、今までと同じ…」と、答えながら一つのことが頭をよぎって、まさかと思いました。
パソコンとか、インターネットの無線LANがついているような液晶テレビなどのだす電磁波によって、植物が傷んでしまう、という話を思い出したのです。「そういえば去年、近くに置いていたブラウン管のテレビを、最新型の液晶のものに新調したの」おずおずと言うと、案の定「それ、関係あるかもね」という答えがかえってきました。
放射能やその人体への影響にはいやというほど脅されている私たちですが、研究途中ではっきりとした発表に至ってはいないものの、電磁波の影響もとある電気製品の関係筋の方々などによるとかなり深刻なものがあるそうです。特に、頭部への危険度は高いため、製造開発者は決して、携帯電話の端末を直接耳につけて会話しないのだとか。
数年前にアメリカで、ある女性が洗ったペットの猫を乾かすために電子レンジに入れ、死亡させてしまったという事件がありました。驚いたのは、彼女が電子レンジメーカーを訴えに出たことです。「取扱説明書に、動物には使用しないでください、なんて書いていなかったわ!」というのが、その申し立てでした。馬鹿げていると笑われがちですが、キッチンで日常的に使われている調理器具の電磁波で動物があっけなく死んでしまうこと、また、それを無意識的に使ってその危険性を忘れている消費者…という事実には、笑ってばかりはいられない深刻なものがあります。
ロシアでは、1976年にすでに電子レンジの使用が法律によって禁止されていま
すし、携帯端末についても、実はあるメーカーは「ハンズフリー機器、マイク付きヘッドフォンを使用するなど、なるべく人体から話してご使用ください」という注意書きを添えています。大なり小なり危険性があることは、明らかなのです。
あまり何もかもに過敏になるのもどうかと思うのですが、気持ちだけでもと思い、電子レンジは処分しました。調べてみると、パソコン(ノート型はデスクトップの三倍近く!)のほかエアコン、洗濯機…電気あるところには多少なりとも電磁波が発生していることがわかりました。
食品も油断なりません。例えば、あの、麻薬の名前がついた国際的に有名な清涼飲料水の会社のサイトには、「この製品には酸味料が含まれております。歯や骨の成分であるカルシウムやマグネシウムは、酸に溶ける性質を持っています。酸を含む液体に、抜けた歯や魚の骨を長い間つけておくと、含まれるカルシウムやマグネシウムが溶けます。しかし、飲みものですので人間の骨に直接ふれたり、歯に長い間くっついていることはありません」とあります。長時間くっついていなければ安心でも、骨や歯に直接、あるいは長時間触れれば溶ける、と説明されているのです。
ああ、その点クラシック音楽はなんて体に優しいのでしょう!ピアノ、弦楽器、管楽器…演奏に用いられる楽器は、コンセントも電気も使いません。人の手によって作りだされた楽器の奏でる音で空間を響かせ、その音がフレーズを紡ぎ、ドラマを作り上げ…。演奏者と聴衆がイマジネーションを働かせながら“対話”を楽しんだり“共感”することは、健康に良い影響はありますが決して副作用はありません。
もちろん神経質になる必要はありませんが、放射能ばかりではなく、日頃使っている電気や、体を蝕む恐れのある食品添加物などにも同じくらい意識を向けてみることも大切なのではないでしょうか。それを体がどう受け入れているのかを自分の心の声に耳を傾けることも、感性を育てることにつながるかもしれません。
植物が生きやすい環境は、そのまま人間にとっても心地よいものであることは間違いありません。まずは、彼らが元気に育ってくれるお部屋にしなくっちゃ。
■第721回 画面とではなく“面と向かって”
アメリカのとある国際ピアノコンクールの審査員を務めていらっしゃる先生が、予選で起こったあるアクシデントの写真をフェイスブックに投稿しました。血だらけになったピアノの鍵盤の写真でした。私は思わず、自分でも驚くほど大きなため息をついていました。「ああ、バルトークのイメージがあらぬ方向にいかなければいいのだけど…」
写真には「◯◯コンクールの予選にて。バルトークのピアノソナタの演奏後、鍵盤がこんなことに…」と、先生によるキャプションが添えられていました。
特にアメリカでは、バルトークの音楽というと刃物のように鋭く、誇張したアクセントを付けた攻撃的なアプローチが多くみられます。さらに、人々がそうした演奏を「かっこいい」とか「バルトークらしい」と受け止める傾向も、みられます。
確かに彼の作品の中には、打楽器のような奏法をイメージさせる部分がないわけではありません。でもそれはあくまでも、生命を鼓舞するような、あるいは太古からの鼓動を暗示させる、すばらしいエネルギーがみなぎっているものであって、決して攻撃的な性格ではないのです。
それどころか、ハンガリー語のアクセントの影響による第一音節のアクセントの多くはむしろとても温かく、まるでお国ことばを聞いているように懐かしい、なんともいえない気持ちにさせてくれます。つまり、攻撃的なのとは対局的な感じなのです。
でも、演奏者はつい、そのリズムやハーモニーのあまりの鮮烈さに足元をすくわれたようになって動揺してしまうのか(?)、それを誇張しすぎ、必要以上にエンターテインメントの要素を加えた結果、本質を取り違えてしまったようなアプローチになりがちなのは、嘆かわしいこととしか言いようがありません。バルトークが生きていたら、そうした演奏をどんなふうに受け止めることでしょう。
このように、『バルトーク=攻撃的=弾き切るために奏者は流血をもいとわない、激しいだけの音楽』のようなイメージが、彼の没後70年を経てもなお存在しているというのに、そこへまたこんな映像が世界中に流失したら?本質とは違う、偏ったイメージによるステレオタイプの見方が、さらに蔓延するきっかけになってしまわないかしら…。私の大きなため息は、そんな危惧からでした。
ショッキングな画像には多くのコメントが寄せられました。「そのピアニストはサムライだね!」「そこまでして弾ききった彼は、あっぱれ」と、その参加者を讃えるコメントもみられた一方、「ピアニストたらんとするもの、このようなことは決してしてはいけないし、あってはならないこと」「精神的にもテクニック的にも、誤った方向性。バルトークの音楽への冒涜だ」という、ピアノ教育者からの厳しい意見もありました。
過剰な反応を避けて静観するのもひとつの選択肢だと思いつつも黙っていられなくて、この記事をシェアした友人の投稿に「何かの間違いで、これは血ではなくストロベリーソースでありますように…。少なくとも、これを見た方が、バルトークの音楽とこの映像は無関係であることをご理解くださることを祈ります」と、書きました。
インターネット、なかでもフェイスブックやツイッターといったSNSが生活に深く入り込み、人々のさまざまな情報源になってどのくらいになるでしょう。膨大な情報が押し寄せるなか、それに流されず冷静に正しい判断を行っていくことは、どんどん難しくなっているようにも感じます。
先ごろ、友人がSNSでの発言をまったく不本意な、妙な方法によって告発され、職務の辞任に追い込まれました。本質を充分に探求することなく、不確かな情報やいたずらな噂に流されることは、単なる誤解だけでなく、戦争にも結びつくようなとんでもない悲劇を招きかねません。
こんな時代だからこそ、物事の本質をきちんと見極めることを心がけ、パソコンや端末ではなく人と向き合って話すことを大切にしていかなくては…と、気を引き締めているこの頃です。
■第720回 ホンモノの自由と研究を!
「夏休みの宿題、進んでる?」生徒さんにたずねると、感心なことにほとんどの子供達が「はい!」と、元気な声と笑顔で答えてくれます。
私事ですが、夏休みの宿題で気が重かったのは、なんといっても自由研究でした。研究のテーマの見つけかたや、その方法を学校で習ったり実習したりしているわけでもないのに、いきなり「やっていらっしゃい」と言われるのは、まるで、憲法のことを何も教えてられていないのに「今回の憲法改正案について、自由に所見を述べなさい」と言われるようなものです。自由に、ではなく、◯◯(例えば、保守的、革新的、など)な考えの立場立って、などという条件をつけられるのでしたら、まだわかります。でも、やぶからぼうに“自由に”といわれても、ねぇ…。
そもそも、自由に、と言われることほど当惑と不自由を感じることはありません。しかもその判断には、自己責任も伴います。音楽用語にも“ad libtum(自由に、任意に)”という表記があります。皆さんが略して「アドリブ」という言葉ですが、これはそのままただ“気まぐれに”弾きなさい、ということではなく、前後の展開や曲のキャラクター、全体におけるその部分の意味などをいろいろと考察した上でいかにふさわしく弾くかを追求し、“あたかも”自由きままに弾いている“かのように”演奏しなさい、ということが、暗に要求されていたりするのです。
のびのびと個性豊かに自己を表現することや、その人らしく生きることは、なにより大切なことです。でも、それと秩序や調和を無視することは、別。そのあたりをきちんと教えずして、子供に「自由に」やりなさい、生きなさい、というのは、無謀にして無責任なことなのではないでしょうか。
さて、自由研究の話に戻りましょう。“自由に”う〜ん、困ったぞ。“研究”これも、何も教わっていないのにどうしよう?・・・それまでは順調に宿題をこなしてきた子どもも、多くはここでハタと当惑してしまうことでしょう。無理もありません。
いやいや、心配御無用。ひとたびネットを使えば、そのヒントがいくらでも出てくるのが今のご時世です。「色の変わる飲み物をつくろう!」「卵の殻をとかしてみよう!」「地域の特産品を調べよう!」「捨てるもので掃除してみよ
う!」「調味料を手作りしよう!」大人がみても、楽しそうなテーマが目白押しです。ご両親も、インターネットさえみれば、子どもたちに相談されても鬼に金棒でしょう。
でも…。“研究”に一番大切なのは、テーマにたどり着く“動機”だと思うのです。どんなきっかけで興味を持ったのか、どうして調べたいと思ったのか。一番重要なそこを与えられてしまうのでは、研究の必然性がありません。
以前、高校で教えていた時、進路についての面談で、「やはり音大に進むのは諦めました」といった生徒がいました。「なぜ?」と聞くと、「両親から、モノになるのはよほどのことだと言われましたし、私自身も音楽では食べていけないと思うからです」なんとしっかりと現実を達観しているのでしょう!高校時代の無鉄砲な自分に、聞かせてやりたくなるような返事でした。でも、ふと気になって、そもそもなぜ音楽大学を目指そうとしたのかを尋ねると、「他に適当なものが思いつかなかったから」
人生の方向づけをする動機による揺るぎない支えが、彼女になかったのです。なるほど、現実を見据えた時、冷静にストップがかけられたわけです(私の場合は、どうしてもそれがしたい、という気持ちが良くも悪くも強く、才能や可能性の有無、職業としての安定などの条件は完全に無視でした)。彼女があのとき進路を変更したことを後悔することなく、スキルを活かしてのびのびと人生を楽しんでいますように…。
何かのきっかけを得て、心から「これがやりたい!」、さらに「これを一生やっていたい!」と思えるものに出会えることほど、生きるパワーをもらえることはないような気がしています。子どもたちのすべての体験は、そんなかけがえない出会いのために、大人が思っている以上に大切なものなのではないでしょうか。
与えられたテーマで無難にレジュメをまとめる、“自由研究”という名の“研究ごっこ”などではなく、人生そのものを研究、探求するきっかけが得られるような体験を、彼らにはなるべくたくさんしてほしいし、そんな導きがさりげなくできる大人になりたい…。心からそんなことを願ってやまない、夏休みです。
■第719回 法則なんて吹き飛ばせ!
このところ、「暑いですね」という挨拶と同じくらい頻繁に登場するフレーズが、「早いですねぇ」になっています。時間の流れのことです。
つい先日、一年の半分が過ぎてしまったと思ったら、はや8月。いったい時間はどこへ飛んで行ってしまうの?…と、思っていたら、それを心理学的に説明したものがあることを知りました。19世紀のフランスの哲学者・ポール・ジャネが発案し、甥の心理学者・ピエール・ジャネがその著書において紹介した、“ジャネの法則”です。
これは、主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く感じるという現象のこと。この法則では、例えば1歳の1年を365日とすると、50歳の1年は体感的にはその1/50の約7日…つまり、50歳に感じる1年の長さが1歳で感じる7日分しか相当しない、という計算になるといいます。
これらの数字の受け止め方はともかく、子どもの頃よりも時間の経つのが早く感じられるというのは、確かです。理由としては、知らないことが多かった頃に比べて刺激が少ないから、とか、同じような毎日の繰り返しだから、などと言われますが、程度の差こそあれ、それを体感しない人は少数派なのではないでしょうか。
車で10数分のところに、通い始めて5年ほどになるとびきり美味しい自家焙煎の珈琲を飲ませてくれるカフェがあります。マスターの息子さんMくんは生後3ヶ月でかなり深刻な胆道閉鎖症と診断され、長い入院生活にはいって、生後半年で生体肝移植手術を受けました。その後、一つ一つおおきな山を越え、少し前にやっと、喉にはいっていた最後の管がとれました。Mくんは3歳になっていました。
「そのとき初めて、Mの泣き声を聞いたんだよ。それまでは、泣いても涙がぽろぽろ眼から落ちるばかりで、気管切開をして声がでなかったから」まだ片腕で抱きかかえられるほど小さいのに、表現したいことがあっても言葉どころか声すらでないなんて…。Mくんの苦しみやストレスの大きさ、ご両親の辛さを思うと、心が締め付けられます。
その間私にできたのは、彼らを励まし(実際には逆に励まされていたのですが)、Mくんに千羽鶴を折ることぐらいでしたが、Mくんがどんなに危ない局面にあるときにも、マスターは誰も起きていない早朝に焙煎機を回し(家庭のガスが使われる前の時間の方が、ガス圧が安定しているからだそう。ほんの微妙なガス圧の変化でローストの加減が変わってしまうのです)、カフェのカウンターに立ち続けました。もちろん、いつも元気いっぱいの笑顔で。
「初めは『なんでうちの子が?』って、不運を恨んだよ。でも入院したら、Mのために日本最高の医療チームが精一杯のプロの仕事をしてくれていることや、たくさんの人からの励ましをもらっていることに、感謝する気持ちしかなくなっていったんだよね。そして、考えられないほどの厳しい命の危機と修羅場を、何度もくぐり抜けて生き抜いているこいつは、すごい3歳児だ、と…」私も、Mくんのことを心から尊敬しているひとりです。
「僕は同じ血液型だったけど、心電図で引っかかっちゃって移植はダメだと言われて。かといってウチのは血液型が違うからダメだろうと思っていたら、2歳までは、人って血液型が違う人間からの臓器移植にも対応できるんだって。すごいよね」奥さまからの肝臓移植は成功し、拒否反応もありませんでした。「でも、もしかしたら、将来どこかに障害が出るかもしれないし、また肝臓移植の必要がでてくるかもしれない。僕ができることは、想定できることに対して最大のことができるように、準備しておくことだけなんだよね」
今度の移植ではどこも引っかからないよう、マスターはMくんの入院以来お酒を一滴も飲んでいません(彼曰く「65歳まで飲めなくてもまったくかまわない」)。また、将来Mくんに障害がでても継がせられるよう、仕事を充実させていかなくては、と話してくれました。「自家焙煎珈琲はどこにも負けないと思ってやっている。でも、かといって今の仕事にこだわっていたいわけじゃない。これがもしダメになったら、どんなにやったことのない仕事でもやるよ。そのくらい必死で生きて家族を守っていって、腹をくくってるんだ」
マスターにとってのこの3年間は、ジャネの法則など吹き飛ばしてしまうほど、生きていることに感謝しない日は1日たりともない、充実した日々だったことでしょう。訪れるたび、美味しい珈琲だけでなく心が満たされるいい時間をご馳走してくれるマスターに、心から感謝です。
■第718回 “晴遊暑読”な夏休み
この十数年、この時期の恒例になっているピアノコンクールの審査。今年は酒田、鶴岡、会津若松、郡山、いわきの五か所で、7日間の審査を仰せつかりました。
少子化の傾向にある日本ですが、なぜかピアノコンクールは増える一方。日本人は何級、とか、何段、といった階級による評価に抵抗が少なく(というより、むしろ好んでいる?)、資格の取得など具体的な結果を求める傾向が他の国の人に比べて強いように見受けられます。コンクールの、努力がかたちになって達成感が得やすいところが、そんな国民性に合っているのかもしれません。
コンクールだけでなく、最近では夏休みを利用して海外のサマースクールやホームステイに参加する子どもたちも増えてきて、みんなすごいなぁ、と、その意識の高さや向学心に感心するばかりです。
その頃の自分の夏休みはというと…。夏休みだからといってコンクールに挑戦するでもなく、暑い日は扇風機の前で図書館からどっさり借りてきた本を読みふけったり、たまにラジオ体操に参加したりするくらいで、父母の実家がある高崎と目黒へ家族で里帰りするのが一大イベント。至極のんびりしたもので、言ってみれば“晴耕雨読”ならぬ“晴遊暑読”な日々でした。
夏休みの宿題は、今考えても教育的主旨がよくわからない“自由研究”以外は、そこそこ楽しみながらやっていました。文章を書くのはピアノを弾くのと同じように抵抗がなかったので、日記はストレスなくこなしていましたし、読書感想文はピアノの練習以上に(?)身を入れて、推敲に推敲をかさねて仕上げました。
小学生時代のいくつかの作文が、手元にあります。同じような年頃の生徒さんを教えているので、ちょっと興味があってぱらぱらと読みかえしてみました。
例えば、二年生の時の作文。二年間担任をしてくださったO先生へのお別れの手紙は、いきなり『もう、O先生とおわかれね。』と、昭和歌謡の歌詞みたいなずっこけた冒頭にびっくりさせられました(“おわかれですね”、あるいは“おわかれなのですね”、と書きたかったのを、うっかりしたのでしょう)が、その
あとは『学校の中にはいらっしゃるけれど、やっぱりさびしいです』と、ちゃんと尊敬語、丁寧語になっていてホッとしました。
文章は稚拙ですが、ひとつ気づいたのは小学校低学年の頃からすでに敬語と謙譲語の使い分けを心がけていたことです。『◯ちゃんの家に上がらせていただいた時に、』『おばあちゃんに、あんこのはいったおもちを、いただきました』『N先生が、そのときわたしにおっしゃいました』 などなど、案外的確に使えているのです。
これは、当時の担任の先生が日本語の使い方にたいへん厳しかったこともありますが、本を読むのが大好きだったことも関係しているかもしれません。本を読む、といっても、ストーリーを受け止めることだけにはとどまらず、主人公の気持ちになって泣いたり笑ったり、場合によっては声に出して読んで台詞を覚えたりしていました。
ところで、日本語の“美”を追求した文豪、谷崎潤一郎氏の著書『文章読本』は、お気に入りの一冊です。氏は、『口語文といえども、文章の音楽的効果と視覚的効果とを全然無視していいはずはありません』『文章は「眼で理解する」ばかりでなく、「耳で理解する」もの』として、言葉と音の関係性、重要性を説いています。『眼と耳とが共同してものを読む』という考えかたです。そういえば、コンクールの講評用紙に、何度「文章を読むように、句読点やフレーズを感じて弾くことを心がけてみましょう」と書いたことでしょう。
子どもたちの夏休みのミッションは、学校の宿題はもちろん、コンクールやサマースクールだけではありません。イベント参加や、部活に塾の夏期講習…大人顔負けの多忙さです。でも、せっかくのバカンス。あえてゆっくりと本を読んだり音楽を聴いたりして、美しいもの、心地よいものを、味わったり表現したりできるような感性を育む時間を、できるだけもってもらいたいと願っています。
こんなふうに高温注意報が続く、暑さ厳しい夏休みは、家で読書や音楽鑑賞をするのにうってつけだと思うのだけど。
■第717回 結果は、のちほど
「中学生になってショパンのワルツを習ったときに、ワルツのリズムがどうしてもつかめなくて、すごく苦戦したの。でね、何回目かのレッスンでS先生から、ちょっといらいらした口調で『鈴木美奈子ちゃんはこの曲、二回目で暗譜してきましたよ』っていわれちゃって…あれは今も忘れられないわ」中学や高校時代の同級生と話していると、たまにこんな思い出話がとびだします。「美奈子ちゃんはすごいってわかってはいたけど、ああ、自分には無理なんだ、という気持ちが大きくなってしまったの。以来、しばらくショパン恐怖症になっちゃった」
彼女は今、某大企業で総合職についてバリバリ活躍する傍ら、アマチュアのオーケストラでヴァイオリンを弾いています。ショパンへの気持ちはこの時手折られてしまったかもしれませんが、音楽への気持ちは今も生き続けていることに、思わず感謝しました。一方で、“悪意なく言った何気ない言葉が、場合によっては長い時間にわたって相手を傷つけうる”ということをわかっていなければ、と、気を引き締めたのでした。
特に多感な年頃には、大人がふともらした一言が人生を変えるほど大きく響くことがあります。心ない言葉を浴びても屈することのない、強靭な精神を育むことも大切ですが、彼女のように、傷つきやすい繊細な感受性を持っているということも、それはそれで素晴らしいことだと思います。そうやって、自らの心の動きを見つめるきっかけを得ると、人の気持ちをくめる“思いやり”のある人に成長できる気がするのです。
「二人が睦まじくいるためには / 愚かでいるほうがいい / 立派すぎないほうがいい」ではじまる吉野弘さんの詩、『祝婚歌』。「正しいことを言うときには / 少しひかえめにするほうがいい / 正しいことを言うときは / 相手を傷つけやすいものだと / 気づいているほうがいい」正しい方向に導こうとしても、力みすぎて相手を傷つけてしまっては、お互いにとって悲劇です。生徒さんを教える時にも、このフレーズをいつも胸に抱いていようと心がけるのですが、夢中になるとつい、忘れてしまいがちになります。
生徒さんはレッスン中、私の話しに驚くほど集中し、演奏がたちどころに良くなっていきます。付き添いのお母さまが感心して「上手に弾けたわね。おうちでもそんな風に弾けるように、おけいこしなきゃね」と労ってくださるのをみると、私まで嬉しくなります。でも、そんな彼らもレッスンが終わると自然に気持ちが切り替わるのでしょう。特に一人できている生徒さんは楽譜をバックに収めたり靴を履いたりしながら「あのね、先生、今日クラスの◯◯くんがね…」「(演劇部で)今度の役、決まりました〜!」など、いろいろな話しをしてくれるのを聞くのは、とても楽しいものです。
お母さまに報告するみたいに次から次へと話題が尽きず、つい玄関トークが長引くこともあります。「あれ?前にもこれと似た感じがあったな。なんだろう?」と気になっていたのですが、思い出しました。それは学校からの帰りに、それまでそぞろ歩きながら話してきた友人といよいよ離ればなれになる分かれ道の角で、明日もまた会えるというのに名残惜しくていつまでも話し続けていた、あの感じでした。
何度もこちらを振り返りながら、「じゃあね、先生。さようなら!」と、小さな手を振ってくれる小さな生徒さんの笑顔を見送るたび、「ああ、笑顔で帰ってくれてよかった。またあの子の笑顔に会えますように…」と、心から願います。同時に、彼らの人生の一端にピアノを通して関わらせていただけたことに、感謝したくなるのです。
今年も、ピアノコンクール審査のお仕事の季節になりました。お一人お一人への講評用紙は、参加した皆さんと私たち審査員をつなぐ大切なメッセンジャー。できる限り皆さんのこれまでのお勉強を否定することなく、改善できるといいなと思われるポイントを盛り込むように書くことを心がけています。
確かに、ピアノが上手になることも素晴らしいことです。でも、懸命にとりくんだ末のステージ経験から学んだり感じたりするものの大きさに比べたら、コンクールの成績の持つ意味はどれほどのものでしょう。レッスンやコンクールなどの体験をとおして様々な感情を経験し、ご自身の長所を伸ばして目標を見いたしていくきっかけを得てくださること、ひいては、音楽がその方の人生に豊かな実りをもたらしてくれることを、願ってやみません。
■第716回 心と魂を満たすもの
個人的に大好きな演奏家が必ずしも有名な方とは限らないように、憧れの大好きなシェフはメディアにそれほどは登場しない方だったりします。それは、今のように美容院と同じだけ(?)イタリアンレストランがあるような時代ではなかった1977年に単身イタリアに渡って修行を重ね、日本人料理人として初めてイタリアで労働許可証を取得した方で、皇族邸(高円宮邸)でイタリア料理を作った最初のシェフでもある、M氏です。
氏の個性が溢れ出ている一冊が、手元にあります。というと、さぞかし専門的なリチェッタ(レシピ)が載っているのだろうと思われるかもしれませんが、意外なことにテーマはアウトドア・クッキング。M氏自身、釣りやアウトドアの達人で、紹介されているのは河原でもできるような大胆にしてシンプルなメニューがほとんど。とはいえ、“豚ロースとりんごのクリームソテー”“ヤマメのマリネ ラズベリーヴィネガー風味”“ローストビーフの洋梨包み”など、そのラインナップから只者ではないセンスが伝わってきます。
“生ソーセージとマスカットのスプマンテ(イタリアの甘口スパークリングワイン)蒸し”を作ったときは、感動でした。作り方そのものに何も難しいことはないのですが、食材の組み合わせや調理法が絶妙だからでしょうか。塩味、甘み、酸味、食感、香りがバランスよく調和し、経験したことがない味わいに、新鮮な感動を覚えました。それでいて、「そうそう、これこれ!ああ、出会えてよかった…」と、なぜか懐かしさのようなものも感じたのです。
M氏の信条は、「(例えば)これはトリッパという旨いものです」と説明ではなく、丁寧な下処理など、あらゆる手を尽くして素材の旨み、香りを表現し、初めて食べた人にも理屈やうんちくなしで「美味しい!これは何という料理なの?」という感想を抱いてもらうことなのだそうです。氏はまた、「アウトドアでの料理は、普段よりも二〜三割美味しさが増す。そうやって五感で味わうことの楽しさ、豊かさも、料理人として伝えたいことなんです」とも語っていらっしゃいました。
M氏のお料理には、「自分はこんな手練手管をもっているんだぞ」とか、「向こうでこんなスゴい料理を作ってきたんだぞ」という衒いは全く感じられない代わりに、「みなさん、こんな美味しいものがありますよ。食べることは生き
ることそのもの。もっともっと楽しみましょう!」と、その喜びが謳歌されているようです。
「フランス料理の味の体系はいわばピラミッド型で、頂点はひとつという感じがします。ですから、他国でもある水準の味が出せるのです。ところがイタリア料理は円筒型で頂点がひとつではありません。したがってその土地の気候や素材によって大きく影響されてしまうのでしょう。でもこれがイタリア料理の良さなのですから、その良さを感じるようになる時代がくることを望みたいと思います」M氏のこのコメントが専門誌に掲載されたのは、今から30年も前のことです。“イタリア料理”に“クラシック音楽”を当てはめ、うん、うん、と頷きながら拝読しました。
パスタという言葉すら一般的ではなく、スパゲッティといえばナポリタンかミートソースだった日本で、本場の郷土料理を展開していくのには大変なご苦労があったと思います。でも、本当に美味しいもの、本物は、国籍も文化も超えて必ず伝わるはず、という信念を貫き、1991年には後に再びイタリアに渡り、ピエモンテ州になんと外国人のためのイタリア料理学校を開校したM氏は、本当のチャレンジャーです。
M氏をよく知る親しい友人によると、釣り竿を自作したり、新しいリチェッタを考えついては、「これ、どう?」と、意見を求めていらっしゃるのだとか。「その顔がさ、少年みたいなの。奥さまがまたなんともステキな方で…ソウルメイトとしか言いようがないほどの仲良しなんだよ」そう語る友人も、なんとも幸せそうな笑顔になっていました。
本当に情熱のある方の人間力に心惹かれ、その方から表現される何か(料理、思想、芸術など、なんであれ…)に引き込まれるとき、ひとは幸福を感じるものなのではないでしょうか。それは、“共感”という言葉では表しきれない、心や魂を満たす“響き合い”のようなもののように思います。
聴いてくださったかた、関わってくださったかたに、そんな幸せを感じていただけますように…。先人が残してくれた素晴らしい作品の魅力を、これからももっともっと心を込めてお伝えしていきたい、と願ってやみません。
■第715回 弾くことは、生きること
「悲しいときも苦しいときも、音楽があればなんとか乗り越えていける」なんていうフレーズを、どこかで聞いたことがあるような気がしますが、まさにそれを実践しているような人生かもしれません。
音楽の魅力をあげれば、きりがありません。例えば、自由にイメージを膨らませ、想像の世界に遊ぶことができるところや、具体的な言葉や映像を持たない(特に器楽曲は)ので、誰をも傷つけることがないこと。学びを深めていくほどに、作曲家や演奏家の人となりがその音楽や演奏からリアルに垣間みえてくること、さらには、作曲者と会話しているような気持ちになれること。時代や国を問わず、時空や理屈を飛び越えて共感を覚えるときや、民族性の強い音楽になればなるほど、人類共通の感情やリズムが息づいているのを強く感じるときのなんとも言い難い幸せ、などなど…。
とはいえ、音楽以外のものに癒しを得ることも、あります。音楽だけでなく、言葉の世界で心に響くフレーズに出会うのも、楽しい経験です。
東北地方に育ったことが影響しているのか、岩手県出身の宮沢賢治の詩には、好きなものが多くあります。賢治の詩は、声に出して読んだとき、その言葉がリズムという生命を得て、心をそっとノックしてくれる感じがします。思いを強く押しつけるのではなく、読み手を透明な光でふんわりと包み込んで、寄り添ってくれるのです。独特の語感は、あるいは彼が大の音楽好きだったことに関係があるのかもしれません(新潮文庫の『宮沢賢治詩集』の最後に、彼が作詞作曲した歌曲が四つ、紹介されているのは、案外知られていないようです)。また、地質学や天文学に造詣が深かったことも、彼の詩が、どこか現世を超越した宇宙を感じさせることに繋がっているように思います。
以前、このエッセイで紹介した『告別』は、くじけそうになると紐解いて、何度も繰り返し読んできた詩のひとつです。“おまへのバスの三連音が / どんなぐあひに鳴っていたかを / おそらくおまへはわかっていまい / その純朴さ希みに充ちたたのしさは / ほとんどおれを草葉のやうにふるはせた ”で始まるその長い詩は、教え子との別れによせた、教師(賢治自身?)からのメッセージになっています。
ここでの音楽的要素は、メタファー(暗喩)でしょう。この語り手…“教師”…は、「どんな人も、長所や、その人を輝かせる才というものを持っている。ただ、それを大切に受け止め、磨くことをせずにのほほんとしているうちに、多くはいつしかそれを失ってしまう」ことを説き、自分の才能を守ることの難しさと尊さを伝えながら、“もしもおまへが / よくきいてくれ / ひとりのやさしい娘をおもふやうになるそのとき / おまへに無数の影と光の像があらはれる / おまへはそれを音にするのだ”と、励まします。
次回の生徒さんの発表会が決まりました。だいたいはそれぞれの生徒さんのレベルに合わせ、2〜3曲の候補をご紹介した上で、最終的にはご本人に選んでいただくことにしているのですが、なかには奥ゆかしい方もいらして「そのなかで、私が少しでもまともに弾けそうなのはどれでしょう?」「先生はどれがいいとお考えですか?」との質問を受けることがあります。そんなときは、「どれも同じくらいオススメですよ。選曲にあたっては、どうぞ、“どの曲なら弾けそうか”よりも、“どの曲を弾きたいか”、で決めてください」とお話しします。そうして曲を決め、勉強を深めていくなかで、やがて“どのように弾きたいか”というテーマへと進んでいきます。
自我はエゴとも訳され、エゴイストとは利己主義者、つまり自己チュー、と、悪い意味にとられてしまいがちですが、社会の中で自分の本来の使命をまっとうし、世の中に貢献するためには、自我や自らの意志を貫きとおそうという強い姿勢は、とても大切なのではないでしょうか。
“どのように弾きたいか”という自問自答は、私にとって“どのように生きたいか”に通ずる大きなテーマです。ごつんと思いっきり壁にぶつかったり、はたまた大きな起動修正を余儀なくされたり…と、失敗もナマ傷?も絶えない人生ですが、歳を重ねるにつけ、それも少しずつ楽しめるようになってきている気がします。
自問自答は、これからもまだまだ続きそうです。
■第714回 楽想をよぶ言葉
「イタリアに旅行したとき、フライトに間に合うよう、ちょっと急いでもらおうとタクシーの運転手さんに“アレグロ・ペルフォヴォーレ(アレグロでお願いします)”って言ったら、運転手さんが楽しそうに鼻歌を歌いはじめてしまった…」という笑い話を聞いたことがあります。
アレグロ(Allegro)…確かに音楽の教科書には、“速く”“快速に”という意味、とあります。先のフレーズはきちんと伝わりそうなものですが、イタリア語としての意味あいは、少々違うのです。辞書を引いてみると「陽気な」「活発な」「明るい」と続き、さらには「何も考えていない」とか「ほろ酔い気分の」なんていう意味まで登場しています。イタリアの運転手さんが歌を歌ってくれたことは、心を込めてアレグロを正しく表現してみせてくれたことになります。急いでほしいなら、「プレストPresto(急速に)」という言葉を使うほうが適切だったのです。
音大入試のための楽語の覚え方にもいろいろあるようですが、そのなかに“カランド三兄弟”というのがありました。これはカランド、モレンド、ペルデンドシの三つの楽語を指していて、どれも“次第に弱めながら次第に遅く”と同じ意味なので、三つをまとめて覚えるように、というものでした。
ところが、楽譜に指示されているそれらの楽語をみるにつけ、どうも作曲家は意図的にそれぞれを書き分けているような気がしてならないのです。イタリアで10年近く演奏活動をしていた友人を捕まえて、尋ねてみたところ「カランドcalandはcalare…“下降する、落ちる”という意味の言葉からきているし、モレンドmorendoは、morente“瀕死の”という言葉から“命が途絶えるように”というニュアンスを持っている。ペルデンドシperdendoshiはperdere“なくす、失う”という意味。その3つは確かに違うよ」との返事でした。ああ、やはりそうだったのです。
音楽用語…いわゆる“楽語”は、フォルテ、クレッシェンド、ドレミという音名など多くがイタリア語ですが、例外もあります。例えば、一拍目以外の拍から始まる“弱起”のことは“アウフ・タクト”とドイツ語ですし、シューマンやマーラーなどドイツ語圏の作曲家は、速度指定などにもドイツ語を用いることもあります。
さて、今度のリサイタルで取り上げるグアスタヴィーノやヒナステラ、ピアソラなどの作曲家を育んだアルゼンチンは、スペイン語圏の国。たまに楽語の表記にスペイン語が登場します。例えば、tiernoは、柔らかく、優しく。muy espressivoは、非常にmoltoの代わりにmuyというスペイン語が使われたもので、同じラテン系の言葉ですから案外わかりやすいのですが、逆にあまり他の国の作曲家には見られないようなイタリア語の楽語が出てきたりもします。calido (温かく)、 landuido (せつない)、など、言葉を聞いただけでも胸がキュンとするようなものもありますが、ときには sersuale (官能的に)のように、キュンを通り越してドキュンとどぎまぎさせられるような単語にも、出くわします。
音楽は、音でそのすべてを表現する芸術。でも、楽譜にはこのように、「音符だけでは伝え足りない!」とばかりに、作曲家の心の叫びのようなメッセージが、しばしば書き込まれます。
私は生徒さんに、よく「楽譜は台本のようなもの。棒読みにならないように、どんな表情、どんな声色…そしてどんな気持ちでそれを話すのか、想像してみてくださいね」とお願いするのですが、それをいうなら楽語は作者によるセリフの合間の“ト書き”のようなもの。そこには、解釈や演奏にとって、とても大切なヒントが潜んでいるのです。
ここで、リサイタルで弾くプログラムの中から、ある曲の出だしに指示されている言葉を一つ、ご紹介しましょう。
これはさすがに注文つけすぎでは?…という気もしないでもありませんが、なんとか表現するしかありません。きっとこの作曲者はとてもロマンチストだったのでしょう。え?それは誰かって?いえいえ、それは企業秘密です。特別な予備知識なく、まっさらな状態で演奏を聴いたときに、なんとなしにそうお感じいただくことが、我々演奏家の役目なのですから!
■第713回 恵まれていない、というしあわせ
ここしばらく、以前よりも頻繁にコンサートに足を運ぶようになりました。若い世代の演奏家たちが頑張っている姿を見ると、心からエールを送りたくなります。その一方で、年齢やキャリア、プロかアマチュアかを問わず、本当に心が揺さぶられるような演奏に巡り合うことの少なさを、実感したりもします。良い刺激だけでなく、音楽に対する自分自身の姿勢について自問するきっかけを得られるのは、ありがたいことです。
つい先日、あるヴァイオリニストが協奏曲のソリストを務めるコンサートに行きました。満員のお客様を前にしての、たいへん立派な演奏でした。その方をよく知る友人によると、彼女はコンサートで緊張することはほとんどなく、本番前もあとも、ケロッとしているとのこと。なるほど堂々たるステージ姿でしたし、オーケストラと多少ずれてもまったく動じることもなく、常によくコントロールされ、プロフェッショナルな安定感がありました。
「すごいなぁ。爪の垢でもいただきたいものだわ…」音大生時代から緊張とは長いお付き合いの私は、聴きながらただただ感心していたのですが、演奏終了後ふと、ひとつの問いが心に浮かんできました。自分でも意外な問いでした。「それなら尋ねるけど、もし彼女と才能を交換してもらえるとしたら、交換したいと思う?」
「う〜ん…」ひとり、うなってしまいました。どうしても答えがイエスにならないのです。あんなに恵まれた素質と交換したくないなんて、いったいなぜ?と戸惑いつつ、強がりでも意地でもなく、私の心は素直にノーと言うのです。
話は変わりますが、ここ10数年、コンクールの審査に携わっています。参加者それぞれの渾身の演奏は甲乙も点数もつけがたく、採点中に心の中で何度「ごめんね」をつぶやくことか!
同じように良い演奏でも、その方がもともと40くらいだったところから80の完成度まで高めていったものと、もともと70くらいのちからを持っている方が80までひょいっと持ち上げたものでは、同じ80でも受ける感動が違います(もちろん、その違いは明白にわかります)。前者は、時に悔し涙を流しながらもひたむきにピアノに向き合ってきた日々が演奏ににじみ出て感動を呼びます。
音には自ずと思いがこもり、一種の強さをもって聴く人の心をとらえます。一方、後者は楽々と天真爛漫に弾いていて伸びやか。その才能や素質は強みとして聴き手にアピールされます。
どうしてもこの二人のどちらかに優越をつけなくてはならなかったら、どちらを選ぶか?…何100という演奏を審査していると、そんな悩ましい局面にしばしばぶつかるのですが、そのあたりに先ほどの答えのヒントがありました。つまり「交換したいとは思わない。なぜなら、彼女の演奏に感心はしたけど、感動はしなかったから」
ひたむきさ、懸命さ、真摯さ、愚直さ。人はそんなものにえも言われぬ共感と親近感を覚えますし、その先にこそ“感動”があるのではないでしょうか。何かと必死に向き合い、苦労してなし得たものにしか宿らない、人間の体温のような温かさ、包み込まれるような豊かさ、努力のすえに到達する信念の豊かさ…。そうした感動の主成分は、生まれた時から才能や素質が備わっていた人には、逆に身につける機会を得るのが難しいものかもしれません。
“恵まれる”。いうまでもなく“よい機会、境遇、才能などが運よく与えられる”という意味ですが、改めて考えてみると、それはあくまでも“与えられ”るもの、“与えられ”たもので、自らの力で得たものではありません。恵まれていないことから、多くを学び、挫折のなかからひとつひとつをつみ重ねていけるとしたら、人生としては案外、そちらの方が魅力的かもしれません。
とはいえ、才能に恵まれることは大変喜ばしいことですし、健康に恵まれることも、なによりありがたいことです。正直に告白しますと、結婚運に恵まれることも夢見ておりました(すみません)。
でも、恵まれないところにこそ、人間としての成長ののびしろがある…。そう思うと、案外私もいい人生を送っているのかもしれないな、なんて思われてくるのですから、我ながらお気楽なものです。
コンサートの帰り、最寄りの駅を降りて「恵まれていないこともまた、恵まれていることになるのかも」などと考えてながら、大きく息を吸いこみました。雨に濡れた木々の、豊かな香りがしました。
■第712回 青きドナウの空に その8
ウィーンを流れるドナウ川をみるたび、「同じドナウ川でも、ブダペストのほうが美しい」と思う。違うのは川の風情だけではない。ウィーンの人々のエレガントな物腰は、ブダペストの人々とは一味もふた味も違う特質だ。一方、ブダペストの人々には、ウィーンっ子にはない独特の親しみやすさを感じる。ほんの数百キロしか離れていないのに、民族も言葉も醸し出される雰囲気もこんなにも違うものかと、訪れるたびに再認識させられる。
違うからこそ、同じところは大事に認め合うし、違うところは“如何に”違うのかをきちんと検証し、整合性についてしっかりと議論する。ヨーロッパで生きていくためには、国家も人も、協調性や融通性と共に、確固たる考えや主張をもっていなければならない。つまり、しっかりとした主張を持ちつつも、他者を受け入れる、といった柔軟性が求められるのだ。それは、留学時代にも音楽表現においてひしひしと感じたことだった。
その積み重ねは自ずと表現の洗練、成熟を産む。貴族社会の繁栄や宗教的な権力の流れと相まって、小さな源流が徐々に川幅を増しやがて大河となるように、芸術もまた、そのようにして長い歴史の中で拡がり、深められてきた。
彼らにとっての芸術は、美術館やコンサートホールなどでのみ触れる機会を得るといった類のものではないようにみえる。芸術、あるいは芸術的なものに触れる喜びは、そのまま人生の豊かさに結びつき、個々の尊厳の認識につながる。芸術は、触れることによって自らに立ち返り、時に啓示を得ることができる、人生の必需品なのだ。毎日目にする街並み、建物の窓枠や床にまでゆき届いた調和のとれたデザイン、街路樹や花壇のカラーコーディネートやカフェでのマナー…どれ一つとってみても、美意識が息づいている。
ウィーンの美術史美術館は、今までも何度か足を運んできた、個人的にはヨーロッパでもっとも好きな美術館の一つである。だが、今回は念願叶って、さらに、憧れのMAK応用美術館を訪れることができた。ウィーンのカフェハウスで用いられるトーネットの曲げ木椅子や、ビーダーマイヤー様式のソファ。ヨーゼフ・ホフマンのデザインした打ち出し銀器のティーセットは、どれもうっとりするような完璧なフォルムだ。その他、ガラス製品、陶磁器、テキスタイルなどの分野で最高レベルのユニークなデザイン製品を生み出したウィーン工房のさまざまな作品を味わうことができ、いつまで見ていても飽きない。
そこには、“用の美”だけではなく、ウィーンの人々が好む美学“Gemütlichkeit(心地よさ)”が息づいていた。
ウィーン最後の夜は、一人旅の通例に従って、よく眠るために土地のお酒を求め、お惣菜と一緒に部屋でひとりのんびり楽しむことにした。昨年からほとんどお酒をのまなくなってめっきり弱くなったので、白ワインを炭酸水で割った、オーストリアの定番スプリッツァーを選んだ。
アルコール度数は、ちょっとしっかりめのビール程度。半分ほどいただいてほろ酔いになったところに友人から電話がはいり、そのまま日付が変わるまで長い間おしゃべりが続いた。彼女とオペラ座の前で最後に別れた時、人目をはばからずにいつまでも抱き合ったあと、「元気でね。幸せになってね」と、目を赤くしていた彼女が瞼に浮かび、最後は涙声になった。名残惜しくも、満ち足りた時間だった。
出発の朝。新しくできた交通手段CAT(city airport train)を使って空港にアクセスしてみた。なんと、乗車前に搭乗手続きができ、座席も指定してもらえた。車内には荷物スペースがたっぷりと確保され、ダブルデッカーになっていてインテリアもさすがに洗練されている。所要時間はたったの16分だ。
パンフレットに、動力の92%が水力発電、8%が風力発電…つまり100%クリーンエネルギーから供給されていると書いてあり、驚いた。昨夜、日本でリニアモーターカーの最高速度計測実験が成功したというニュースが流れていたことを思い出す。スピードや効率の重要性もわかるが、安全で環境に優しい、というのがこれから求められる本当の意味での高性能ではないだろうか。
同時に、「本当の意味での豊かさとは?」という問いが頭を巡りはじめた。ウィーンフィルのコンサートや友人との懐かしい再会を振りかえり、ドナウ川流れる二つの街を見守る青い空を眺めていると、その疑問はいつしか「そんな豊かさを、与えることのできる人になりたい」という願いに変わっていた。
(*青きドナウの空に 完)
■第711回 青きドナウの空に その7
老舗ホテルに宿泊する楽しみの一つは、その朝食だ。とはいっても、元来贅沢なほうではないので、その土地のローカルなパンや新鮮な果物が何種類かと、できればホテルメイドのクーヘン(焼き菓子)やプディングがあればおおむね満足である。とはいいつつも、カフェが銀製のポットでサーブされたら、さらに言うことはないのだが。
ウィーンで宿泊したホテルは、その点も申し分なかった。温かい野菜や卵の料理、数え切れないほどの種類のハムやチーズが並んでいるのを見ているだけで、幸せになる。留学時代、一年も二年もお寿司やてんぷらが食べられなくてもまったく意に返さなかったが、美味しいチーズやオードブルが食べられないのは忍び難い私にとって、銀のトレイに美しく並べられたコールドミールの数々は、限りなく美しく、リッチな景色にみえる。
ブダペストの時同様ゆっくりと朝食をとり、そのあといそいそと身仕度をする。9時半に大事な待ち合わせがあるのだ。この旅の大きな目的のひとつ、ブダペスト時代からの友人で今はウィーンに在住している同じくピアニストのYさんと、数年ぶりの再会を果たすことになっているのである。
約束の時間ぴったりに現れた彼女は四半世紀前とまったく変わりなく、私よりも年上なのに少女のような風貌はそのままだ。挨拶もそこそこにおしゃべりに夢中になって、ベートーヴェンが遺書を書いたハイリゲンシュタットに向かう途中も、うっかり乗り換えをやり過ごしてしまいそうになった。
ブダペストで毎日のように顔を合わせていた時には、彼女とウィーンで再会を果たすことになるなんて、思いもしなかった。ヴァイオリニストのお嬢さまと3年ほど前からここに住んでいるのだが、今は彼女自身もここウィーンで伴奏の仕事をこなしながら、充実した毎日を過ごしている。旦那さまとは、出会ってすぐに電撃的に「私の赤い糸はこの人とつながっていたのだ!」と直感したそうだ。ハンガリーからアメリカへの留学、結婚、そして離婚…。人生の大切な決断の時には必ず彼女の存在があって、誰よりも深く私に関わってきてくれた。
ベートーヴェンが散歩しながら楽想を得たという道を並んで歩きながら、お互いの近況や悩み、最近感じることなどについて、なんのてらいもなく話し合
う。空は眩しいほどに美しく青く晴れ渡り、時折聞こえて来る愛らしい小鳥のさえずりのほかには、風が奏でる葉ずれの音と、私たちの話す声や足音しか聞こえない。霊的な感性を持ち合わせている方ではないが、ふと、ベートーヴェンも隣で話を聞きながら、一緒に歩いてくれているような気配を感じる瞬間があった。
午後から仕事がある彼女と別れ、ウィーン郊外の中央墓地に向かう。映画『第三の男』のラストシーンで有名になった並木道があるこの広大な土地の中の第32区に、モーツァルトやベートーヴェン、シューベルトやブラームス、ヨハン・シュトラウスといった、そうそうたる楽聖たちが眠っている。肌がじりじりと音を立てて焦げてしまいそうな陽射しのなかを直感にまかせて歩き、やがてそこに辿りついた。ベートーヴェンのお墓の前で手を合わせた時、心に浮かんだ挨拶は「こんにちは。あなたの熱烈なファンです」だった。花が手向けられているそれぞれの墓石は教科書に出てきたままの印象だったが、ベートーヴェンとシューベルトのお墓が思いのほか近いことに驚いた。ほとんど、親戚同士のような近さである。これなら夜な夜なの音楽談義には不自由しないだろうと思われて、不謹慎ながらふと笑みがこぼれた。
昨日のウィーン・フィルのコンサート以来いっそう強く感じていたのだが、この地で彼らは、今も生きているように思われてならない。いや、生きているのだ。そして、ここの音楽家たちは彼らの確かな鼓動、気配を感じ、それをそのまま音に託している。彼らの書いた楽曲は、その素材の素晴らしい個性や美しさを余すところなく、のびやかに表現され、きらきらした光を放ちながら羽ばたいて、人々の魂にそっと寄り添い心をノックする。ノックの音は、天使の訪れの知らせのように、幸せをもたらす。…ここではまさに、芸術が人々のなかに息づいているのである。
高ぶった気持ちを鎮めたくなった私はドナウ川沿いを歩き、足はそのままプラター(遊園地)へと向かった。地元のたくさんの老夫婦や家族連れと一緒になって、ぶらぶらと並木道を歩き、歴史のある木製の大型観覧車のある方に行ってみる。子供の笑い声はどこも同じだ。地球上のどこに住んでいる人々にも、等しくこのような平和で穏やかな休日が与えられんことを、願わずにはいられなかった。
■第710回 青きドナウの空に その6
ヘジェシュハーロム。このローカルな響きの地名は、共産圏時代にハンガリーからオーストリアへの国境を渡ったことがある人間には忘れがたいものだ。かつてはこの国境付近の駅で列車が一時停止し、パスポートコントロールがあった。われわれ外国人は基本的には簡単にチェックされるだけだったが、時には「ちょっと預からせてください」と、上官?のところにパスポートを持って行かれてしまい、不安になったりもした。ハンガリー人はさらにしっかりとした検問を受け、持ち出しする外貨の額について聞かれたり、時にはトランクを開けて中身を確認されたりしていた。
自由化になって25年もの歳月が経つというのに、今もこの地名をきくと当時が思い出され、軽い緊張感を覚える。だが、私の緊張をよそに列車は何事もなくするりと国境を越え、いつしかオーストリアに入っていた。
ウィーンに新しくできた中央駅に到着。すばらしく立派な建物だが、旧東ドイツの都市のそれとも似た、特徴をさほど感じない“EUらしい”駅だ。1ユーロも持っていなかったので、両替をして地下鉄に乗り込む。
ウィーンの宿は、街のシンボルでもあるシュテファン寺院のすぐそば。モーツァルトやリスト、ワーグナーも宿泊した、歴史あるホテルだ。ウィーン風のエレガントなホスピタリティーを身につけたフロントマンに迎えられてチェックインし、えんじ色の絨毯の敷き詰められた螺旋階段の中央に設えられた二重扉のクラシックなエレベーターに案内される。1メートルもの厚さのある部屋の壁は、この建物がたいへん古いものであることを物語っているようだ。
その夜は、楽友協会ホールでのウィーンフィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会に出かけることになっていた。リッカルト・ムーティの指揮で、シューベルトの交響曲第9番“ザ・グレイト”を聴ける…そう思うと、嬉しくていてもたってもいられず、ブダペストからの移動の疲れもどこへやら、いそいそと身支度をして早々に部屋を出た。
グラーベン通りや目抜き通りのケルントナー通りなどをふらついてみる。かつては威圧的なほどに重厚な趣きの老舗が軒を連ねていたこれらの通りも、今は表参道や渋谷にもあるような量販店や、アメリカ系のカフェ、ファストフード店がずいぶん目につくようになっている。90年の自由化のあとに急速に進んだ
グローバル化は、ここでも観光客の誘致には機能している一方、大きな資本をもつ企業の経済的優位と文化の単一化を助長させているような印象を否めなかった。
楽友協会ホールのあるベーゼンドルファー通りにほど近い老舗カフェまで歩き、食事をとる。留学時代はこの街でこんなふうにゆっくり散策したり、コンサートを聴くこともほとんどなかった。物価は高いしハンガリー語は通じないし(当たり前だ)…、アウェイ感に襲われて居心地が悪く、必要な用事をすませてそそくさとブダペスト行きのオリエント急行に乗り込んでしまっていたのを思い出す。
テラス席に座って一息つくと、食べたくなったのはハンガリー風のシチュー“グラーッシュ”だった。日本ではまず、一人分のお皿には使われないであろう大きなお皿いっぱいに盛り付けられた、パプリカソースの仔牛のシチューと付け合せのクネーデルは、すべてあっという間に私の胃袋に収まった。ヨーロッパを旅すると、とてもお腹が空く。そして何を食べても美味しくて、日本では食が細い方に入る私が、リラックスしているせいか人並み以上の食欲を発揮するのは、我ながら不思議なことだ。
開演一時間前に、楽友協会ホール“ムジークフェライン”の入り口に並ぶ。人気のコンサートで席を取り損ね、辛うじて取れたのは立ち見席だったが、運良く一階奥中央の場所を陣取ることができた。立っていなければならない、ということをのぞいては、響きも眺めも(ムーティの真後ろだった!)申し分なかった。しかも、チケットはわずか6ユーロである。
演奏は、天上の響きというものがあるのならこういうものをいうのだろう、と思うほどの素晴らしいものだった。始めの一音から、それまで聴いてきたものとは別物だった。シューベルトは、今も生きていた。そして私たち聴衆は、ムーティの棒によって紡ぎ出されるウィーン・フィルの柔らかくも深い表情に満ちた響きと音楽の流れに包まれ、シューベルトの世界の中で呼吸をしていた。全てが終わり、楽団員がはけた後も聴衆は帰ろうとせず、ムーティは一人ステージに呼び出された。私は、今が本当に21世紀であることが信じられないような、不思議な感覚に襲われながらも、音楽の大きな喜びに心を震わせていた。とても幸せな夜だった。 (*青きドナウの空に その7に続く)
■第709回 青きドナウの空に その5
センテンドレからホテルに戻り、一息ついたあとリスト音楽院に向かう。
私が留学していた社会主義の時代には真っ黒に煤けていた建物が、白亜の…とまではいかないまでも、まったく別の壁の色に変わっていて、抜けるような青空を背景に眩しいくらいだ。最上階近くに鎮座しているリスト像も、気のせいか誇らしげに見える。音楽院前のフランツ・リスト広場は、しゃれたカフェが軒をつらねるおしゃれな一角になっていた。太陽の光にキラキラ輝くワイングラスを片手に、テラスでおしゃべりに夢中になっている人々は、一見してそれとわかる観光客がほとんどだ。
開場の時間になり、中央の重々しい扉が開いた。エントランスロビーの間取りは基本的に変わっていなかったが、かつて受付があった場所がビュッフェスペースになっているし、以前はいい感じのおばさんがチケットをもぎってくれたのに、今は若くて見目麗しい制服姿のお兄さん、お姉さんがエレガントな手つきでチケットをチェックしている。
通路に面した真ん中の席に体を沈め、ホールをそっと見渡してみる。やはり素晴らしい!見事なシャンデリアも金色がふんだんに使われた内装も、全体の様式感が統一されていてちっともいやらしくない。この舞台でショパンやシューベルトを弾けたことが改めて光栄に思われてきて、しばしボーッとなってしまった。
ふと我に帰った直後、斜め前の座席のご婦人がある老人と挨拶をかわし、その後なぜか私を振り返って微笑みかけた。「ほら、あの方よ」と言っているようなその表情にハッとして、彼女が挨拶した相手の方をみなおすと…果たしてそれは、私のよく知っている方だった。リスト音楽院時代、室内楽を習っていたバルトーク弦楽四重奏団の第二ヴァイオリン奏者、D氏だ。でも、介添えの若者の手を借り、杖をついておそろしくゆっくり歩いていらっしゃるし、足の震えのためか席につくのも一苦労なさっているように見えた。本当に先生なのだろうか?「すみません」妙にドキドキしつつも勇気を出して、目が合ったご婦人に話しかけてみた。「あの方…D先生でしょうか?」ご婦人はにっこりとうなずいた「ええ。そうですよ」
本当なら、大喜びで先生のところに挨拶に飛んでいくところだろう。でも、
躊躇があった。先生はまだ60代のはずなのに後ろ姿は痛々しいほど年齢を感じさせていたし、あの、明晰にして妥協のない指導で私たちを叱咤激励してくれた、ダンディーなD先生とは別人のような佇まいなのだ。
「失礼します。D先生でいらっしゃいますか?随分前にこちらでご指導いただいたスズキミナコと申します。覚えていらっしゃいますか?」「ああ、そう。よく僕がわかったね」「ええ。お会いできてとても嬉しいです。前回ブダペストに来た時には、素敵なレストランに連れて行ってくださって…」「そう。君、楽器は?」「ピアノです」「ピアノの留学生はわからないな」そこで先生の愛弟子だった弦楽器の何人かの名前をだすも、どなたもわからないご様子だった。私は、先生がご存知に違いない固有名詞を探した。「ハンナ(先生のお嬢さま)の結婚式にも、呼んでいただいたんですよ」「ああ、そうだっけ。先週も彼女と孫たちに会ったよ」「ラダイ通りの先生のお住まいにも何度かお邪魔しました。今もそちらに?」「よく覚えているね、そうですよ。で、君は誰?」
ハーゲン弦楽四重奏団の演奏会は、素晴らしかった。終演後、第二ヴァイオリンを弾いている友人のライナー・シュミットに会うためバックステージの入り口で待っていると、また先生と一緒になった。「おや、あなたのコートは?すみません、このご婦人が、コートが見つからなくてお困りだよ」と、スタッフにおっしゃるので、慌てて「ありがとうございます、コートはあります。どうぞご心配なく」とお伝えすると、先生は腑に落ちないご様子で首をかしげた。「このホールは綺麗になったね。なにしろ改装に3年もかかったんだ。私?1年半前に退職したよ。これ(杖)はなかなか便利だね」介添えの若者は、ご家族ではなく介護サービスのスタッフのようだった。バックステージに案内されると、先生はメンバー一人一人に懸命にご感想を伝えていらした。その時はいくらか生気が戻り、語調も強まっていたようだった。
「あのD先生が、認知症に?」その夜、ベッドに横になってからも、モーツァルトの美しいメヌエットの余韻に、悲しみの影がさし続けた。「That’s life!(人生こんなものさ)」ハンナの結婚式のとき、私にそう言って寂しいお気持ちを隠すようにウインクした先生の表情が瞼に浮かび、しばらく消えなかった。 (*青きドナウの空に その5 に続く)
■第708回 青きドナウの空に その4
翌日の朝も、えも言われぬ愛らしい鳥の鳴き声で目覚める。胸のすくような青空と爽やかな風にさそわれ、郊外を訪れることにした。ブダペストからほど近い、ドナウ川沿いの人気の街、センテンドレへと向かう。
「あの橋のちかくの駅からHEV(鉄道)に乗り換えて…」記憶は確かなはずなのに、そこに駅が見当たらない。いや、正確にいうと、駅入り口が閉鎖されていて入ることができないのだ。これもまた“改革なき改革”のための工事なのか。聞くと、隣の駅までバスがリレー運行しているという。
なんとかその駅にたどり着くも、券売機はあるものの窓口がひとつのこらず閉まっていて、チケットの値段も買い方もよくわからない。地元の人も困っている様子だ。「チケットは、どうすればいいのでしょう?」作業服姿の係員にたずねているが、彼も駅員ではないようで要領を得ない。私は券売機についている受話器をとり、通話ボタンを押してみた。「こんにちは。どうなさいました?」「こんにちは。今、○○駅からセンテンドレ行きのHEVに乗ろうとしているのですが、チケットをどうしたらいいのかわからないんです。窓口はみんな閉まっていて誰もいないし、券売機もわかりにくくて…」「一定区間の定期券など、何かお持ちですか?ブダペスト内のどこから乗車するかという条件によって、料金も違うのです」「定期はありませんが、有効期限内の24時間フリーパス、というのを持っています」「ああ、それならそのままご乗車ください。車内でそれを車掌に見せれば、差額をご精算いただけますから」
私が話し終えると、いつのまにか後ろに何人かのハンガリー人が待っていた。「それでそうやって通話ができるのね。知らなかったわ。で?チケットはどうするのですって?」なぜ、外国人ツーリストの私が地元の皆さんに?本来は逆なのでは?…と、少々混乱しながら「お持ちのチケットや定期の種類にもよるようですが、どうやら車内で精算できるみたいです」
そういえば、いつかブダペストから日本への直行便に乗る時にも、搭乗ゲートの売店で店員さんに呼び止められ、「ごめんなさい、そこのかた。ゲートの日本人グループのどなたかが、これ、置き忘れていったみたいなのよ。皆さんに聞いてみてくれる?」と、小さなポーチの主を探すよう頼まれたし、機上で客室乗務員に「あなた、これ、日本語でアナウンスしてくれない?マニュアルにはハンガリー語と英語しか書かれていないし、今日は日本人乗務員が搭乗して
いないのよ」と、機内放送のマニュアル本と、口に横に当てて話すあのマイクを手渡されたこともあったっけ。ハンガリー人はひとを使うのがうまいのか、はたまた私が隙だらけなのか。
乗り込んだ電車では、後ろの座席の熟年カップル四人組が、のべつ幕なしに話をしている。「そうだわ、センテンドレに着いたら、お昼代わりにランゴシュ(揚げパン)を食べましょうよ」「いいわね、そうしましょう。お天気もいいし、外で食べるのはきっと気持ちいいわ」と、女性陣。どちらかの旦那さまは「いいけど、新しい油を使っている店でお願いしたいね。いつかランゴシュを食べたら胃がもたれて、ひどい目にあったよ。あれは油が古かったんだろうな」と、少々渋い調子だ。
センテンドレは半日もあれば歩きつくせるような小さな街だが、しゃれた美術館やカフェがあって、ぶらぶら歩きにはぴったりだ。ランゴシュと聞いて、私はここで“食べる”ミッションをふたつ果たすことにした。ひとつ。昔よくランゴシュを食べたお店にいって、ン10年ぶりにそれを食べること。ふたつ。歩き回って疲れたら、ハンガリーの定番スイーツ、ショムロイ・ガルシュカ(生クリームとチョコレートソースをたっぷりかけたプディングケーキ)を食べること。
かつてと同じく、ランゴシュにサワークリームと刻んだスモークチーズをトッピングしたものをオーダーするも、あまりの大きさ(日本の揚げパン4〜5個分)に途中で断念。当時は難なく平らげていたのに…そんなに胃が小さくなったのかしらと少々悔しくなった。その後、たくさん歩いた後に入ったカフェでは、大きなボウルにてんこ盛りの、日本なら3〜4人前はあろうかというボリュームのプディングケーキを、リベンジといわんばかりに完食した。
往路は鉄道だったので、ブダペストへの復路はバスを使うことにした。夜のコンサートに備えて、ホテルでちょうど一休みできそうだ。風景、人々…すべてを美しく輝かせてくれる陽の光につつまれながら、連日気持ちの良い天気に恵まれていることに心から感謝した。その日の夜に悲しく衝撃的な出来事が待っていることなど、この時の私は予想だにしなかった。(*青きドナウの空に その5 に続く)
■第707回 青きドナウの空に その3
中央市場をひやかしたり目抜き通りでウインドウショッピングを楽しんだりしたあと、せっかく素晴らしいダイニングキッチンがあるのだから、何か簡単なものを作って部屋で食べようと、近所のスーパーで食料を買い込んでホテルに戻った。
いそいそと夕食の支度をすませ、さぁいただきます、という時になって初めて、ダイニングテーブルの一通の手紙に気づいた。昨夜もホテルの支配人からの手紙が置かれていたが、それは片付けたはず…。まさか、ご丁寧に支配人から毎日手紙が届くのかしら、と確かめてみると、そこには伝言が書かれていた。“ご不在の間に、セーケイ・イシュトバーン氏から連絡がありました。お戻りになったら電話をください、とのことです。電話番号は…”
「え?うそ…」思わず声に出してしまった。イシュトバーンはその才能を若くして認められ、世界的に活躍していたピアニスト。かつての私の師だが、一緒にシカゴのラヴィニア音楽祭に参加した友人でもある。たまにメールでやりとりをしていて、今はリスト音楽院での教授活動や演奏活動に区切りをつけ、たまに作曲をしながら一般の音楽学校でピアノを教えているそうだ。今回、彼と会えたらと願ってはいたが、二ヶ月ほど前から音信が途絶えたままになっていたので、諦めていた。私は、最後のメールで今回のブダペスト滞在の日程と宿泊先を告げたことを思い出した。
電話をすると待ち構えていた様子で彼が出て、挨拶もそこそこに、体調を崩してしまって昨日のうちに連絡ができなかったことをしきりに詫びた。ひとしきり話しをして、翌日の午前中と、彼の仕事が終わったあとに会うことになった。「26年ぶりの再会ね。信じられる?」「そうだよね。ええと、どこかわかりやすいところ…コルビン・ネージェドの映画館わかる?」「わかる!黄色い建物ね」「そう。じゃあ、そこの入り口で待ち合わせよう」
翌朝、約束の時間の2分前現地に到着。その30秒後にイシュトバーンが現れた。久しぶりすぎて、わかるかしら…という心配には及ばなかった。お互いに遠くから確認でき、彼は「やあ!」と、目配せしながら近づいてきた。「君のことすぐわかったよ」「私も」「ごめん、一昨日まで38度の熱が出ていて…昨日、なんとか下がってよかったよ」
私たちはブダペストの街を散歩しながら、またランチを食べながら、今までのことや現在のこと、仕事のこと、ブダペストの音楽事情についてなど、時間を惜しんで語りあった。夕刻また同じ場所で落ち合い、ドナウ川の素晴らしい夜景(私は世界一美しいと思っている)を見ながらそぞろ歩いて、さらに様々なことを話した。「少し前にはマラソンにも挑戦したのよ」「まさか!」「本当だってば。ただ、フルマラソンじゃなくて…」「だよね。40㎞じゃなく4m、でしょう?」「いくらなんでも、そこまで短くないわ!5mくらいです」
以前と変わらず、しばしばあまり面白くない冗談を飛ばしつつ、話題はブダペストが今、置かれている状況の危うさにも及んだ。「急激すぎる改革に、実経済はぜんぜんついていっていない。言うならば、“改革なき改革”。意味ないよ。ほら、あれ見てごらん」「貸し自転車ね。決められたところで乗り捨てもできて、便利なんでしょう?ドイツでもたくさん見かけたけど…」「僕の意見としては、これも馬鹿げてると思う」「なぜ?」「だって、他の国と違って自転車専用レーンが整備されていないんだよ?形だけ性急に整えようとして…脆弱な方針を象徴しているみたいだよ。この国が自由化になってからというものの、経済的にも政治的にも、バランスが目に見えて崩れてしまった」「道路や建物…これまで見たこともないほどあちこちで“工事”をしているけど、それって…」「そう。予算を使うための、無意味なものがほとんど」「わあ。それ、日本も同じ!」「そうなの?」
でも、現在のここの状態は、日本が終戦後、復興のために国民がひとつの方向に向けて歩んだものとは大きく違う。国民不在の改革は物価高と貧富の差をよび、政府の方針に人々は対応しきれていない。急激すぎる変化は危険だ、というのが、彼の主張だった。
時間は飛ぶように過ぎ、いつのまにか日付がかわる時間が迫っていた。「今日は時間をつくってくれて本当にありがとう」ホテルの入り口まで送ってくれた彼に、告げた。「なんの!ミナコがくるのはビックイベントだったからね」
会っていなかった26年という時間がとても信じられないほど、リラックスしたひとときだった。私たちはごく自然に「じゃあね、おやすみなさい」と言いあって別れた。今度はいつ再会できるかわからないのに、すぐに次の“26年後”がやってくるような、不思議な感じがした。
■第706回 青きドナウの空に その2
やはり未明に目が覚めてしまい、空港でもらった『ブダペスト春の音楽祭』のパンフレットに目をおとす。一ヶ月以上にわたって行われるこのフェスティバルがブダペストの春の文化的な風物詩になって、もうどのくらいになるだろう。
パンフレットは、上下をずらしながらジャバラのように折りたたむモダンな形状になっていて、ロゴデザインといい、一見してきちんとしたデザイナーによって製作されたものとわかるものだった。滞在中にはどんなコンサートがあるのかと見てみたら、ウィーンに発つ前夜、友人がメンバーになっているハーゲン弦楽四重奏団のコンサートがリスト音楽院大ホールであることがわかった。明日は、このフェスティバルのオフィスにチケットを買いに行くところからスタートすることに決め、再びうとうととする。
ヨーロッパでの朝がいつもそうであるように、この日も小鳥のソプラノの歌声で目覚めた。まだ6時だったがすでに空は明るくなっていて、ダイニングからだろうか、パンの焼けるいい匂いが漂ってくる。身支度をすませ、ダイニングのあるフロアに降りた。テラスもある気持ちの良いダイニングには、食べきれないほどの種類のチーズやハム、サラミ、パンや、たっぷりの果物(これがわたしにはとても大切!)などが並んでいた。スタッフとハンガリー語で会話でき、思ったよりも覚えていることがわかって少しホッとした。
ゆっくり朝食を楽しんだが、オフィスが空くまでまだ少し時間があるので、周辺を散歩してみる。すぐのところに大きなショッピングモールになっていて、その向こう隣には映画館もある。ドイツ系のスーパーマーケットもすぐ近くだし、見るからに新しいいくつかのマンションの一階部分はおしゃれなカフェになっている。かつてはあまり治安がよくないと言われていたペスト側のこのエリアも、今や住みやすい新興住宅地、といった雰囲気になっていた。
「ブダペストは、やはりずいぶん変わったな」少し寂しい気持ちになっていったん部屋にもどるとドアが開いていて、ちょうど掃除中だった。掃除しているのは、美しく感じの良い、30代と思しきご婦人だ。「おはようございます。ごめんなさい、かまわずお掃除続けてね」「おはようございます。ありがとう」「良いお天気ね」「本当に!仕事したくなくなっちゃう」彼女の自然な言葉に
二人顔を見合わせ、声を出して笑う。「そうよね、わかるわ」「あ、でも大丈夫。仕事は午前中だけなので、そのあとは子供たちとゆっくりできるわ」「なら、良かった!…ええっと、部屋の鍵、カードキー…どこに置いたかしら」「化粧室じゃなくて?」「ううん。私いつもこうなの。いやになっちゃう」…といいつつ、半分ふざけて冷蔵庫を開けて探すと、それを見て彼女はまた声を出して笑う。
なんのことはない、カードキーはバックの中だった。考えてみたら、戻ったときドアが空いていたので、キーはそこから取りだしていなかったのだ。ともあれ、彼女とのリラックスしたやりとりで、旅の緊張がすっかりとけた。
ドナウ川沿いに新しくできた劇場兼音楽祭事務所の入っている建物の立派なこと!…近代的な内装のチケットオフィスは高級ホテルさながらの洗練された雰囲気で、若くて優秀そうなスタッフが窓口に控えている。あえて英語で話しかけてみたら、ハンガリー訛りの英語がかえってきて、ちょっとホッとした。
無事にチケットを手に入れ、冴え冴えと晴れた空の下、ドナウ川を渡ってペストからブダ側に向かう。バラの丘、という愛称で呼ばれる丘の一角に建つ、バルトークがかつて住んでいた館(記念館になっている)を訪れたが、定休日でもないのに門が閉まっていた。その後、私が住んでいた12区のアパートメントのあたりを散策し、近所のお菓子屋さんでティータイムをとる。店構えも店員も変わってしまっていたが、良心的な値段と地元の人で賑わっているのは変わっていなかった。
「カッテージチーズのパイとチェリーのお団子(大好物なのだ!)、それにエスプレッソをください。ここでいただきます」「コーヒーにミルクは?」エスプレッソはミルクを使わない分安いのに、ここではお客の好みを聞いて融通してくれたことを思いだす。「ありがとう、お願いします」「温めたのと冷たいの、どちらがいい?」なんと丁寧な心遣い!懐かしいハンガリー語と相まって、私よりもずっと若い店員さんなのに田舎のおばあちゃんに聞かれたような錯覚に陥ってしまった。第二の祖国に戻ってこられた、という実感が心を満たしていく。
一つでも充分すぎるボリュームで知られるハンガリーのお菓子。先ほどバラの丘でアイスクリームパフェを食べたというのに、お皿いっぱいにのった大きなお菓子二つともをペロリと平らげてしまった。もちろん、久しぶりに頂いたこの店のコーヒーが格別に美味しかったことは、言うまでもない。 (*『青きドナウの空に』その3に続く)
■第705回 青きドナウの空に その1
新しくなったチューリッヒ空港で、ゲート間を移動するためのスカイメトロに乗り込む。しばらくすると、スピーカーから牛の鳴き声やカウベル、ヨーデルの歌声などが聞こえてきて、面食らった。こんな効果音を車内に流すなんて、スイスといえども以前は考えられなかった。観光産業という大きなビジネスの影響を受け、ブダペストもずいぶん変わっているのだろうな、という不安のようなものが、頭をよぎった。
ブダペストとウィーンへの旅を思い立ったのは、昨年11月だった。半世紀の節目になる誕生日を迎えとき、ブダペストやウィーンに住んでいる大切な知人の顔が浮かび、「会いたい人には会えるうちにあっておこう」と思ったのだ。
ところが、そのうちの一人、ブダペスト留学時代の大家さんはすでに亡くなっていると、後日知った。もう一人の友人とも、その知らせを受けたのとほぼ同じ時期に、連絡が途絶えてしまった。すでに航空券もホテルの予約も取ったというのに…。それでも、旅は決行することにした。なぜか、かの地に呼ばれているような気がした。
チューリッヒからブダペストまでのフライトは、素晴らしかった。眩しいほどの青空。パイロットは尾翼を左右に大きく振りながら飛行し、まるで空中散歩を楽しんでいるようだった。眼下に広がるチロルの山並み、大地を悠々とうねるドナウ川…。ハンガリーが近づいてくるにつれ、初めてブダペストを訪れた時の感動が蘇ってきた。
留学当時、仙台で発行されていた月刊音楽機関誌に、毎月エッセイ『ハンガリー留学日記』を寄稿することになっていた。以下、その第一回“ブダペスト・カルチャーショック”の一部を紹介させていただく。1987年のものである。
上野から新幹線に乗るともう、東北のにおいを感じることがある。同じことが、フランクフルトからハンガリー国営の飛行機に乗ったときにおきた。あちこちから聞こえるマジャール語。機内食はパン、チーズ、オリーブやプラム、アップルパイのほか、ミートローフ、ローストビーフ、サラミ、ポークハムにビーフステーキと、肉づくし!コーヒーに粉末ミルクがついてきたのでためしに入れてみたら、やっぱりいつまでたっても溶けないで、ダンゴになって浮いていた。
私が住むことになったアパートメントは、リスト音楽院からドナウ川を隔ててすぐのところにある。エレベーターは二重のドアを手で開ける往年のスタイル、ガスコンロは“火打ち石”で点火する。「あなたの住居は、とても設備の整った、モダンなところですよ」と、リスト音楽院の学生課から通知を受け取ったのを思い出し、おかしくなってしまった。電話やテレビ、洗濯機の普及率は日本と比べものにならないほど低い。公衆電話の多くは故障中、ジュースやタバコの自動販売機は一つも見当たらない。(*後略)
私の住居にも電子レンジはもちろん、電話もテレビも洗濯機もなかった。冷蔵庫はあったが冷凍室はない。のちにテレビと洗濯機は導入されたが、テレビは白黒で映るのは二つの国営放送のみ、洗濯機はキューブ型の1キロ以下の容量用のぐるぐる回るだけのもので、とても使えたものではなかった。西側では走行を認められていない有鉛ガスを排気するロシア製の車のおかげで、街の空気はうっすらと排気ガス臭く、建物は煤けて黒ずんでいたが、夜になると重要な建造物周辺は見事としかいいようのないライトアップがほどこされ、ドナウ川沿いのそれは夢のような美しさだった。コンサートホールもオペラも、連日ほとんど満員。この国の経済面と文化面の豊かさのギャップに、えらく戸惑ったのを思い出す。
オンタイムでブダペストの空港に到着。そうだ、フェリヘジ空港、という以前の名はとっくに変わり、フランツ・リスト空港になっていたのだった。その他、人民共和国通り、レーニン環状道路、革命記念広場、モスクワ広場…。共産圏をイメージさせる地名は、みんな変えられている。
空港からの乗り合いタクシーで、ホテル前までつけてもらう。電子レンジや電気オーブン、電気コンロや電気ポットなどを備えたセンスのいい最新式のキッチンにダイニングセット、大きな液晶テレビに広いバルコニー。自由化になる前、四半世紀後にここがこんなに様変わりすることを、誰が想像できただろう。
すでに外は真っ暗に暮れていたが、星の瞬きが眩しかった。(*『青きドナウの空に』その2に続く)
■第704回 ぶつかり合いをおそれずに
「先生、“秘密の花園”って知ってますか?」レッスンのあと、玄関でおもむろに靴を履きながらSちゃんが私に尋ねました。「ああ、読んだことあるわよ。素敵なお話よね。バーネットだっけ?」「そうです、バーネット。でも、今の子って誰も『秘密の花園』、知らないんですよ〜?友達に聞いても皆に『しらな〜い』って言われて…」麗しいセーラー服姿のSちゃんが“今の子”なんて言うのがちょっとおかしくて、笑いそうになるのをこらえながら、「へえ、そうなの?」
彼女は海外文学が大好きで、ディケンズが目下のお気に入り。翻訳が固いと読みにくい、とか、原作を児童文学用に簡略化しすぎるのは如何なものか、とか、まるで同年代同士のように、感じていることをあれこれ屈託なく話してくれるのが嬉しくて、つい“玄関トーク”が長くなります。“今の子”風に、セーラー服の丈をアレンジすることは一切せず、長めのスカート丈でオーソドックスなシルエットを保っている制服の着こなしにも、いたずらに周囲に流されない、彼女らしさが現れています。
文学だけでなく、音楽の感想を話してくれる生徒さんも、います。例えば、次に勉強する新しい曲を弾いてみせると必ず「すご〜い!きれい!雨のつぶが、ぽつんぽつんって降っているみたい!」などと、目を輝かせて感想を伝えてくれる、小学一年生になったばかりのRちゃん。すごい感受性と表現力です。「そうね。先生は特に、おしまいのところがステキだと思うの。ほら、こんなふうに音がふわっと消えるように終わるところ…」「ほんとだ、かわいい!」
自由に感じたことを語りあえるのが、芸術の楽しさです。生徒さんからちょっと「?」と思うコメントをもらったときも、そうは見せずに「そっか、そんなふうに感じるのね。例えば、どんなところをそう思ったの?」と突っ込んでたずねると、なるほどそういう見方もあるのか、と感心してしまうような返答をもらえたりします。
感じたことをはっきり伝えるのは良いこととはいえ、誰かを中傷するようなことになっては、一般的にあまりよろしくありません。それでも、臆することなく自らの著書のなかで特定の人物(しかも大先輩にあたる)を名指しで批判した三島由紀夫氏は、やはりたいそう肝のすわった人だと思います。
『(太宰治の“斜陽”について)作中の貴族とはもちろん作者の寓意で、リアルな貴族でなくてもよいわけであるが、小説である以上、そこに多少の「まことらしさ」は必要なわけで、言葉づかいといい、生活習慣といい、これほどちがった描写を見せられては、それだけでイヤ気がさしてしまった。貴族の娘が、台所を「お勝手」などという。「お母さまのお食事のいただき方」などという。これは当然「お母さまの食事の召し上がり方」でなければならぬ。なんでも敬語さえつければいいと思って…(略)』(*三島由紀夫著“私の遍歴時代”より)
後日、太宰氏と対面した折に、ご本人に面とむかって「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」と、言ってのけるあたり、やはりただ者ではありません(もっとも、「そんなことを言ったって、こうして(僕に会いに)来てるんだから、やっぱり好きなんだよな」と、言い返す太宰氏も負けず劣らずすごいと思うのですが)。
時代小説などを読むにつけ、昔の人は今の人より精神的に忍耐強い反面、これはという局面では敵を作ることをも恐れずに、自らの真意を潔く伝えているような印象を受けます。はっきりとしたライバルの存在や激しいせめぎ合いのなかからお互いを高めていくしたたかさ、逞しさも、今の人より強いように感じます。本音のぶつかり合いなんぞで壊れることのない、真実の信頼関係や友情こそ人生の宝…と、憧れのようなものを抱くこともあります。
思えば、ブダペスト留学時代は毎日が本音のぶつかり合いでした。ハンガリーの人は、よくも悪くも、思ったことを歯に衣着せずに相手に伝えるのです。「それはあなたには似合わない」「いやならやめれば?くよくよ悩むのは時間の無駄だよ」「分からなかったなら、分かったふりしないでそう伝えてくれないと。それが誠意ってものでしょ?」言われた当時は「うう、キツいなぁ」と思いましたが、振り返るともっともな話で、むしろ感謝することばかりです。
来週、とても久しぶりにかの地へ旅に出ます。この10年以上のあいだに、ブダペストもずいぶん変わったことでしょう。変わったところ、変わっていないところ…そのいずれとの出会いも、楽しみたいと思っています。
■第703回 失敗に乾杯!
「今日は入学式だったよ」「クラス替えで、仲良しのお友だちと一緒になれなかったの」「担任の先生ね、厳しいことで有名な先生で…」生徒さんが、新学期の報告をしてくれます。レッスンが始まる前、ちょっと緊張気味な面持ちで「こんにちは」と入ってくる生徒さんですが、終わるとホッとするのか急におしゃべりになって、堰を切ったように話しはじめます。学校やクラスの様子を聞くのはなんとも楽しく、玄関で立ち話が長引くこともしばしばです。
親御さんがしっかりと教育していらっしゃるのでしょう。小学生の生徒さんも、次に生徒さんが入ってくる時にはドアを開けたまま支えて通しますし、お月謝の袋を渡すときにはその向きを改め、きちんと両手を添えて差し出す習慣が身に付いています。中にはピン札が入っていることがほとんどで、ご両親に愛されているのだな、と感じて、温かい気持ちになります。
お習い事は、その上達だけでなく、礼儀作法や師を尊ぶことなど、一つのことを長い時間をかけて“学び続ける”ことからさまざまなことを感じとり、気づき、それを人生の楽しみや“糧”にする…といった、貴重な副産物を与えてくれるものだと思っています。
私自身、ピアノを学ぶことが発端になって、「音楽と舞踏、音楽と言語の結びつきとは」「芸術と宗教の関係性とは」「国家と民族とは」「地域の気候的環境と土着芸能とのかかわりとは」ひいては「人類の共存のために芸術が機能する道とは」などといった問いかけが絶えず湧いてきて、そのたびに歴史書を紐といたり、言葉の語源や言語体系を学んだり、宗教や信仰について調べたり、時には、19世紀末の芸術音楽を少しでも理解すべく、フロイトの『リビドー理論』やマルクスの『共産党宣言』を読んだり…と、40年以上も学び続けている今もなお、関心ごとには事欠きません。
もっと外国語も学びたいと思っていますし、民族を育む大地…風土や郷土料理についても、知りたい。ピアノというたったひとつの楽器をアイコンに入り込んだ、芸術音楽の底なしの魅力と深みを知るにつけ、興味と楽しみは深まるばかりです。「“これだ”と思えるものをひとつ見つけ、それに徹底的に打ち込みなさい。人生の楽しみは、そこにあるのだから」父はよく、そんなことを私たちに話していましたが、そう言われる前から心は決まっていました。
現在はピアノのレッスンを受けてはいませんが、ステージ経験を積むことから勉強を続けられているのは、本当にありがたいことです。思い返すと、特に多くの収穫を得られるのは“失敗”から、という気がします。失敗には種類があり、ときに化学変化(?)するのが面白いところです。例えば、自分ではいくらうまくいったと思っても、聴いた人の反応が今ひとつであれば、それは成功とはいえせん。反対に、過去の失敗をふまえて練習や勉強の仕方を見直し、ほんの少しでもその成果があげられたのであれば、過去の失敗はもはや、失敗ではなくなります。
生徒さんにとっての発表会も、そんな場のひとつ。事実、ステージでの小さな失敗が、その後の生徒さんの大きな成長につながった、という素晴らしい実例を、これまでたくさん見てきました。“お習い事に打ち込む”のは、“人生を一段と輝かせる、楽しみを得る”ことであると同時に、“貴重な失敗を経験するチャンスを得る”ことともいえるかもしれません。
「ミスを怖がらないで。ピアノは跳び箱やサッカーと違って、たとえミスしたって痛くないんだから、ね。間違えたら、何が原因で失敗したかを見直せばいいの。そして、どんな弾き方をしたらよくなるか、あれこれ試してみることが大切なのよ」最近、生徒さんによくこんなことを言っている気がします。
失敗は、反省だけでなく励みや謙虚さを与えてくれる貴重な“教え”であり、真摯に向き合うと必ず好転に導いてくれる・・・敵にまわすと嫌だけど、味方につければいかにも心強い・・・人生の相棒なのではないでしょうか。受験や仕事で失敗をすることは避けるべきかもしれませんが、お習い事ではぜひ、失敗をたくさん経験していただきたいものです。
さぁ、ご一緒に楽しく失敗を重ね、ぐんぐん成長しましょう!鈴木美奈子ピアノ教室は、レッスン室の扉を開けて皆さまの入門をお待ちしております。
■第702回 “幸感神経”を健やかに
「今日は素敵なお着物の方とお会いできて、いい日だわ!お仕事で着ていらっしゃるの?」昨日ホームで電車を待っていたら、ふいに見知らぬ初老のご婦人から声をかけられました。「いえ…仕事ではないのですが」「まぁ、ごめんなさい。着なれていらっしゃる雰囲気だったものだから…。その帯結び方、いいわねえ。なんというの?」「ありがとうございます。今日は半幅帯で、割り角出し、という結び方にしてみました」
辛いことを耐え忍び、たくさんの苦労を重ねたとしても、それゆえに思いやり深い奇特な人格が得られたなら、悪い人生とはいえないかもしれません。“いい人生”“いい演奏”“いい恋愛”…どの定義もひとつではなく、価値観や受け止めかたによってさまざまです。“いい日”も然り。着物姿の人を見ることやその相手と話すことが、昨日のご婦人にとって“いい日”になる要素だったなら、期せずして私はその方のよき一日のために、ほんの少しの貢献ができたことになります。
お酒を飲まなくなってからでしょうか。一日の最後の寝入りばなに、なんとなしにその日をふりかえって休むようになりました。頭のなかで、日記を書くような感覚です。ああ、失敗したー、と思うこともありますが、よかった、と思えることもそれを上回るくらいたくさんあることに、やがて気づきました。
朝、気持ちよく目覚めた。食事が美味しくいただけた。桜がきれいだったし、沈丁花も良いにおいだった。ピアノが練習できた。外国語の勉強もできた。好きな着物で過ごせた。しかも、いつになく上手に帯が結べた。読書中の本が佳境に差しかかり、続きが楽しみでしかたない。疎遠になっていた友人からメールが届いた、などなど。ささやかながら、ほぼ毎日が“いい日”になっていました。
先日、部屋を整理していたら、20年ほど前の生徒さんの発表会の写真が出てきました。そこには30人近い生徒さんが写っていました。仙台にいた当時は、母校での非常勤講師や年間10回〜20回のコンサート、さらにたくさんの生徒さんのレッスン…と、今では考えられないような仕事量をこなし、そのうえ結婚生活もしていたのです。
その頃に比べて、今は仕事量も収入もずっと少なくなっていますが、不思議と「あの頃はよかった」という感慨にはいたりません。今は当時よりも気持ちのゆとりをもって、誠意をこめてレッスンできるようになっていますし、演奏活動も“量より質”ではありませんが、ひとつひとつじっくりと取り組める現状に、満足しています。今思い返すと、以前はとにかく“こなす”ことに精一杯で、幸福に感謝することもなく、嵐のような毎日をただ夢中でやり過ごしていたような気がします。
さて、ご存知のように、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚を『五感』と呼びます。それらをコンビネーションして得る幸せの感覚を、このたび勝手に“幸覚(こうかく)”と命名。さらに、“幸覚”を感じさせてくれる神経のことを、交感神経・副交感神経を超える“幸感神経”と呼ぶことにしました。
美しいものを見たり、いい音楽を聴いたり、美味しいものを食べるといった、視覚、聴覚、嗅覚、味覚から得る幸せは実感しやすいですが、案外“触覚”も大きいのではないでしょうか。針仕事が上手な母は「布をさわっているとなんとなく気持ちが落ち着く」と言ってパッチワークを楽しんでいますし、父は趣味と実益をかねて家庭菜園の“土いじり”に勤しんでいます。キャリアウーマンの妹も、自由な時間には好きな編み物を楽しんでいるようです。
着物がくれる触覚の幸せにも、言い表わしがたいものがあります。なめらかな正絹の“やわらかもの”は、着ている時だけでなく、たたむ時すら豊かな心持ちになりますし、しゃきっと素朴な風合いの紬には清々しさを感じます。
ピアノの鍵盤の感触?もちろん大好きですとも!鍵盤のわずかな感触(タッチ)の違いが、かくもさまざまな音に変換されるなんて、奇跡としかいいようがありません。
“幸感神経”を健やかに保つべく、これからもささやかな“いい日”を積み重ねていきたいものです。
■第701回 エヴァンゲリストへの道
昨年4月にスタートした月に一度の『大人のための音楽講座MUSICAVITA(ムジカヴィータ)』も、無事に一年を終えることができました。自宅でのこぢんまりとした会ですが、学校では決して教えてもらえない(!)音楽史の裏側や音楽家の横顔、作品のうまれた背景などをお話して、厳選した音源を聴いて、皆で楽しいひと時を過ごしています。予習の必要はもちろん、テストも宿題もレポート提出も一切ない、気軽に単発参加できる講座です。
こちらは、以前から講座(4年続いています)を受けてくださっているご近所の方や、ピアノの生徒さんとそのご関係の方々の参加がほとんどですが、ピアノのレッスン受講を希望される方はほとんど、このサイトをご覧になって問い合わせをくださっています。「エッセイを拝見して、ぜひ美奈子先生にお願いしたいと…」という、なんとも光栄なお言葉をいただくと、こんなつたない文章だけど、何かをお伝えできているのかな、と嬉しくなります。そして、そのご期待に添えますように、と、つい張り切ってしまいます。
「途中で中断はしながらも、今までずいぶん長いことピアノを習い続けてきましたけど、こんなに深く音楽の真髄を教えてくださるのは美奈子先生が初めてです」「美奈子先生は、私をこれからピアニストにしてくださるおつもりなのかしら、と思うくらい、熱心に教えてくださる…。いつも感謝しているんですよ」「先生のおっしゃったことをすべて語録にとどめたら、すごい本になるのでは?と思われるようなアドバイスを毎回惜しげもなく下さって…。私なんかがそんな貴重な教えを頂いてよかったのかしら、という気持ちでドキドキしながら家に帰るんですよ」
大人の生徒さんからしばしば頂くコメントです。「褒め過ぎでは?」と思う反面、「あらら、そんなに踏み込んでしまっているなんて自覚していなかったわ。知らずしらず、生徒さんを戸惑わせてしまっているかもしれない」と反省することも…。
その方が少しでもピアノをもっと楽しむ手助けになるよう、そして音楽の魅力をよりたくさん感じてくださるよう、生徒さんの目線になってナビゲーター役を務めるよう心掛けているつもりなのですが、どうやら、無意識に専門的な部分に言及してしまいがちなようです。でも、言い訳するようですが、決して無
理にお願いしているのではないのです(お伝えしたいことがたくさんあることは認めますが)。ほんのちょっとの意識・・・音楽的所作ともいえる、ちょっとしたアプローチ・・・の違いで、その演奏の印象が大きく変わるのも、クラシックの魅力。生徒さんとご一緒していると、それを一緒にワークして、感じ取っていただきたい気持ちでいっぱいになるのです。それは、相手が音楽大学を目指す生徒さんであれ、趣味でなさっている4歳や80歳の生徒さんであれ、かわりません。
人にはそれぞれ、社会のなかに役割があるとするなら、私のそれは音楽の伝道師(エヴァンゲリスト)になることだと思っています。つまり、私の演奏、レッスン、あるいは講座、コンクールの講評…いずれを通じてでも、素晴らしい芸術音楽の世界を皆さまにお示しして、より楽しんでいただけるようにそのきっかけを提供することだ、と。
演奏の精度、完成度を極めることも大切ですが、演奏家が第一にすべきは、世の中に“自分の有能さ”を示すことではなく、人生を豊かにしてくれる“音楽の素晴らしさ”を伝えることだと思っています。
そんな私がこのごろ、以前にも増して魅力を感じている言葉のひとつに、 "道"があります。といっても道路ではなく、人や物が通るべき、自然の法則や道徳的な規範、美や真実の根元など、哲学的な広い意味における"道(タオ)"です。精神をも豊かにする何かに向かってその“道”を感謝しながら歩むことは、神様から人間だけに与えられた、最も崇高な行為なのではないでしょうか。
演奏家として何か大きな偉業を成し遂げるというよりも、そんな“道”を、時に生徒さんやお客さまといった素敵な“道づれ”を得ながら日々歩きつづけていくことが、夢です。私の職業は、確かにピアノ演奏家…ピアニストですが、音楽の素晴らしさを伝える手段は演奏だけではないので、ピアノ弾きというよりも“音楽伝道師”と位置づけたほうがピンとくるような気がしています(『職業』欄には書けないけど)。
皆さまの明日が、よき音楽のように豊かなものでありますように…。
■第700回 共感をはげみに、共鳴をかたちに
断酒して3ヶ月が経過しました。私がお酒をやめたと知ったときの相手の反応は、実にさまざまです。「え〜っ?なんでまた!?」と驚かれる時もあれば、「へえ、そうなの」と、あえてさらっと流してくれる場合もあります。わけを言いたければ、「ねぇねぇ、聞いて。お酒、ドクターストップかかって飲めなくちゃった〜!」などと自分から話すのでしょうから、あれこれ聞かずにそっとしておいてくれるのは、とてもありがたいことです。
何かを思い悩んでいる人が目の前にいる時、私は自分からは根掘り葉掘りたずねません。相手がそれを話しかけて途中で言いよどんだとしても、「もし気が乗らないなら、無理して話さなくてもいいのよ」と、けろっと笑ってみせることにしています。悩みや重大なことに直面したとき、それを誰かに話すべきか否か、あるいは誰に話すか、どこまで話すか…というのは当事者にとって大事な選択ですから、いたずらに踏み込むべきではないと思っています。
私の断酒の理由は、ドクターストップなどといった医学的なものではありません。でも、かといって、ひと言で簡潔に説明できるようなものでもありません。複数のいろいろな出来事や思いが重なってのことなので、ちょうど離婚の理由を聞かれてもハキハキ答えられないのと同じように、返答に困るのです。
でも、3ヶ月の間に周囲の反応にも慣れ、少し余裕もでてきました。「あれ?飲まないの?」と聞かれて断酒を告げるとき、今では相手の返答のしかたや表情を観察するのが楽しみにすらなっています(ちょっと意地悪かな?)。「どうして?」は一般的ですが、「うん、いろいろあって」と答えるも、一向に納得してくれず…というのは、残念な例。デリケートなことなのだし、相手から話さないなら、よほど気の置けない間柄でない限りここから先に首を突っ込むことは控えるべき、と、反面教師にしています。
「ストイックだね。今日ぐらい飲んでみたら?」これは言うまでもなく、最も良からぬ例。ご当人にそんなつもりはなくても、相手の決意や意思を尊重するどころか踏みにじりかねない、無責任な悪魔のひと言です。でも、そんなことを言う方はだいたいその手に酒杯を持っているわけで、せっかく気持ちよく酔っていらっしゃるところに噛み付くのは野暮というもの。「勘弁してくださいよ〜」などといいながら薄ら笑いを浮かべ、できるだけ気にしないことにします。
ちょっと意外だったのは、「えらいなぁ。自分も断酒してみようかな」と言われることが少なくないこと。これは、たとえウソだとしても(!)、共感してくれようとする優しい気遣いが感じられる反応です。そんなふうに言っていただけるとホッとして、逆にお酒や断酒にまつわる話題も広がりやすく、しばらく楽しい会話が続きます。
でも、一番驚いたのは、実家に電話した折、母が切り際に“付け足し”のようにひょろっと言ったことでした。「そういえばね、あなたがお酒やめたって聞いて、お父さんもずうっとお酒飲んでいないのよ」
つい最近まで“休肝日”すらなかった父。家での晩酌が何よりの楽しみゆえ、夜は外食をしたがらないあの父が、なんと私に内緒で断酒していたのです。
断酒の理由などいっさい聞かず、娘の決断にそっと寄り添って“共鳴”することでひそやかに応援してくれていたなんて…。電話を切ったあと、父の愛情や思いやりのとてつもない深さとありがたさに、頭が下がるのを通りこして涙が溢れました。昔から何事においても人一倍厳しい、父。思春期には、他の兄妹のだれよりも反発していました。この歳になってなお、心配をかけているなんて、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
でも、父のそんな静かなる“共鳴”は、「そっと見守ってくれている」という安心感で私の心を満たし、大きな励みも与えてくれました。そして、「私たち芸術家の目指すこと、すべきことは、西洋と東洋の音楽や文化がいかに違うか、の表現ではない。むしろその反対に、それぞれ違ったバックグラウンドを持ちながらもなお、民族が民族を超えて互いに感じうる、こんな“共鳴”をかたちにして“共感”を届けることなのではないか」と、思ったのでした。
このエッセイも今回で700回目。これまで支えてくれた両親、周囲のみなさまに、感謝あるのみです。
■第699回 『春の嵐』
季節の移ろいのなかでもっとも好きなのは、晩秋です。実りの秋、枯れゆく秋、冬への歩みを一歩一歩すすめていく秋。そのすべての瞬間は、自然の豊かさ、厳しさとともに、世の中の“諸行無常”をも示唆してくれます。感謝すること、学ぶこと、すべてを受容すること…。晩秋はわたしにとって、それらの大切さを、言葉を介すことなく静かに悟らせてくれる大切な季節なのです。
さて、新年度が4月から始まる日本では“別れと出会いの季節”ともいわれる春の足音が、近づいてきました。春の女神は、ある時には美しい微笑みのようにきらきらした、あたたかな陽射しを注いでくれたと思うと、翌日には身も凍るような冷たい風を吹き付けたりします。そう、春の到来はいつも“ツンデレ(すでに死語ですね)”なのです。
春は冬の間息を潜めていた草木が次々に芽吹き、命を謳歌する季節ともいえますが、その激しくすらある強さに、ある種の畏敬を感じ、たじろぐことがあります。そこに、女性から新たな命がうまれる瞬間と同じような、“産まれいずる苦しみ”とその喜びの両方を、一度に感じるからかもしれません。
ですから、私にとって、“実りの秋”に対して、春は激しさに満ちた“嵐の春”なのです。先日、これを音にしたらさぞけたたましいだろう、と思った狂気のような南風に吹きつけられた瞬間、ふと少女時代に読んだヘルマン・ヘッセの小説『春の嵐』を思い出しました。
当時は、音楽も文学も食べ物も、とにかく西洋のものや西洋風のものが好きでした。その頃、よく夢にでてきたお屋敷があります。木造の洋館で、つるバラやマーガレットが咲き乱れ、良い香りの漂う気持ちのいい庭で遊ぶのが好きでした。生け垣の傍らには黒すぐりが植わっていて、実を見つけてはつまみぐいしました。家の内部にはコブラン織りのタペストリーのかかった応接間があって、猫足のソファーと象眼細工のテーブルが置いております。白い木枠の窓のある階段の踊り場は、お気に入りの場所でした。かなりディテールがリアルでしたが、読んだことのある小説の影響だったのでしょうか。
学校の帰り道に、夢のなかでその庭に漂っていたのとまったく同じ香りに出くわして、とても驚いたことがありました。正確に言うと、その時と同じ匂いのする香水をつけていたご夫人と“すれ違った”のです。中学三年の時でした。その後、それがなんという香水なのか知りたくて、ずいぶん長い間気になっていましたが、数年後についに探し当てました。アメリカのエリザベス・アーデンというブランドのものでした(アーデン女史は、なんと第二次大戦の戦時中からヨガのエクササイズを美容メソッドに取り入れていたそうです)。
少女時代の夢には香りがあった、ということを思い出したら、当時は小説や詩を読んでいると頭の中に音楽が鳴ることがしばしばあったことを思い出しました。知っている曲のときもあれば、知らないメロディー(自作ってこと?)が浮かぶこともありました。ベートーヴェンの交響曲を聴いて、つぎつぎに詩が浮かんだこともあったっけ。残念なことに、今はそんなことはすっかりなくなってしまいました。子供は皆、のびやかなインスピレーションに溢れているものですが、私にもかつてそんな時があったのかも…。
話がわきにそれました。そんな“西洋かぶれ”な少女にとって、イギリスのブロンテ姉妹やルイス・キャロルは勿論、クラシック音楽ともリンクするドイツ文学は大好物でした。小学生の頃からゲーテ、ヘッセ、ハイネにロマン・ロラン…色々と読みあさりましたが、なかでも『車輪の下』に感動してそのつぎに読んだヘッセの『春の嵐』は衝撃的でした。
登場人物は深く音楽と関わっていて、幸福とは、孤独とは、愛とは…という普遍的なテーマが容赦なくたたみかけられます。当時は何もわかっていなかった子供でしたが、苦悩し、大きな不安を感じながらも自身の意思と愛をつらぬく主人公の姿に、何度も涙しました。
振り返ると、当時読んだ本には少なからず影響を受けています。迷ったとき、その頃であった作品を読み返して、我に立ち返ることもあります。本をたくさん読むようにすすめてくれた母には、心から感謝しています。
■第698回 麗しのボディーガード
なににでもきっかけはあるものです。その成りゆきがあまりに自然すぎて、きっかけをきっかけと認識しないこともあるでしょう。でも、大体はなにかしらの布石や動機があるものだと思います。
ワインを知ろうと思ったきっかけは、はっきりと覚えています。それは10年以上の前のこと。リサイタルでワインに詳しい友人からいただいた、一本の赤ワインでした。忘れもしないボルドー・スペリオール…素晴らしいヴィンテージのAOCだったのですが、飲むときの適温や開栓してからの時間のおき方、合わせるお料理についての知識などをまったく持ち合わせておらず、フランスのお肉料理ならまぁなんでも大丈夫だろうと、アルザス地方のシュークルートという郷土料理(*リースリングなどの白ワインと相性がいいもの)を作って、あろうことに開栓してすぐに飲んでしまったのです。
豊かなはずのタンニンも温度が低すぎて渋みに感じられ、絶妙なセパージュによるグラマラスなバランスも、香りが開く前に飲んでしまったために充分に楽しむことができませんでした。別の機会に同じようなボルドー・スペリオールを頂いたときは、その違いに愕然とすると同時に、下さった方への申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
“ザ・飲ん兵衛”というイメージの強い私ですが、実は離婚するまでは相方の影響でお酒を頂く習慣はさほどなく、日本酒を頂くのも、コンクールのお仕事で接待して頂くときぐらい。演奏旅行で福岡に行った折には、本番前夜にお料理が美味しいと評判のお店に行って、店長さんがあれこれサービスをして出してきてくださるまま、ほとんど飲んだことがなかったアルコール度数の高い“乙類の焼酎”をそうとは知らずに頂いてしまい、翌朝ひやっとしたこともありました。
いろいろが重なった末、『無知は時として罪になりうる』という結論に達しました。元来の貧乏性も加わって、せっかく頂くからにはより美味しく、ありがたく楽しむために、ある程度の知識を持っていなくては…と、お酒についての本を読んだり、お店で頂く時にはホールの方にできるだけアドバイスや意見を頂いて、知識を蓄えるようになりました。端からは、ずいぶんと“お酒に熱心”に見えたかもしれません。
当初はそうだったのですが、いつのまにかありがたみを感じることなく、惰性で飲むようになってしまっていました。そこで、断酒でリセットし、何年も健康診断とは縁遠くなっている身体とも向き合うことにしました。とは言っても、相変わらず健康診断は受けません。四半世紀(それ以上?)にわたって我慢に我慢を重ねてきた、右足指の変形に伴う痛みをなんとかしよう、と思いたったのです。
そうして、友人のご主人が院長をしていらっしゃる整形外科の病院の門を叩いたのが、昨年末のことです。そして、ダンサーやバレリーナの方の足もたくさん治していらっしゃる、とある大病院の名医をご紹介頂いて年明けに受診したところ、手術に踏み切る前に靴を見直して様子をみましょう、ということになりました。
夕方にはあまりの痛みに耐えかねて、足がぴくぴく痙攣するのもおかまいなしに(痛みには強いほうなのかしら)、ピンヒールばかりを好んで履いていたのですから、変形も進むはずです。かといって、いまさらペタンコのズックなど受け入れられそうにありません。ただでさえ足が短いのに…。
その時でした。天の声(流行りのスピリチュアルな世界で言うところの、“ハイアーセルフ”?)の声が、はっきりと聞こえてきたのです。「美奈子、着物よ。着物の生活になさい。足袋や草履はあなたの足指を圧迫することもないし、そもそもあなたの典型的な日本人体型には、洋服よりも着物があっているのよ」
かくして私は、半世紀を折り返した節目の年はじめに一大決心をするに至ったのでした。着物には、着る人の個性を受け入れ、その人の思考やセンスを映し出す不思議な力があるように感じています。第一、着物を着ていたら泥酔なんて絶対できませんし、おかしな輩に声をかけられることもなくなりそう。これ以上頼りになって、かつ足指にも優しいボディーガードは、まずいないでしょう。
着物にますますのめり込みそうな予感に包まれている、私です。
■第697回 文は人なり、装いもまた…?
着物を着ることをはじめて以来、自分の様々な変化を感じています。もともと単純な性分なので、影響をうけやすいのでしょう。
「え?なになに?洋食には興味がなくなってきたとか?」いえいえ、そんなことはありません。確かに、着物姿の時にファストフード店に入りたいとは思いませんが、そもそも西洋芸術をなりわいとしているのですし、西洋の食文化にも服飾文化にも、相変わらず興味は津々です。
でも、色とか素材、デザインやモティーフに対する見方は、変わってきました。着物は、フォルムは限られたものですが、だからこそ素材の組み合わせや織り、染めの種類の違いが引き立ち、また、多様な色や柄とその合わせ方などがとても大切になってきます。同じ色合わせでも素材が違えばまるで違う印象になりますし、帯締めや帯あげのような小物の効かせ方もまた重要なポイントになります。例えば、帯と着物で色は好相性でも、時代性や様式感の違いすぎる文様を合わせた場合、成功すればとてもアヴァンギャルドに格好よく決まるけど、失敗するとちぐはぐで残念な印象になってしまうこともあります。
平安時代には、御簾からのぞく着物の袖の素材や色の合わせ方、焚かれているお香などから、殿方がその女性の知性やセンス、位(家柄?)までもを推したというのも、よくわかるような気がします。直接言葉を交わすことができなかったりお姿を見ることが叶わないなど、制限されたなかだからこそ、ちょっとしたところに本当の意味での美的感性やお人柄などが表現され、それを感じとることができる殿方というのもまた、そうしたセンスを常日頃から磨いていらっしゃる方、ということになるのでしょう。
和装について知るにつれ、日本人の色に対する感覚の細やかさや、その手仕事の素晴らしさ、美しいもの、希有なものを享受する懐の深さを感じ、改めてその豊かな感性に驚きを感じます。同時に、普段それらをすっかりどこかに忘れてしまっていることを、恥ずかしく、また、もったいなく思うのです。
季節感と素材、色の関係。染めや織りの種類。文様の歴史や伝来…。更紗ひとつとってみてもインド、ペルシャ、シャム、ジャワ…世界地図でしばらく楽しめるほど種類がたくさんあって、それぞれに特徴があります。知れば知るほどおもしろく、普段の生活のなかでも窓枠や器、マンホールの蓋の柄など、ちょっとした“かたち”に目が留るようになりました。何をみても楽しいのです。
もちろん、洋服にも興味はありますが、以前のように欲しいとは思わなくなりました(注:達観して欲がなくなったわけではありません。夏ものの絽の帯がほしいわ、とか、麻の小千谷ちぢみの掘り出し物はないかしら。いや、それよりお仕事こないかな…などなど、残念ながら頭の中は煩悩でいっぱいです)。私のような目の形でアイラインを引くと、和服にはどうもしっくりこない気がして、メイクは薄化粧になってきましたし、アクセサリーも、以前はぶらんぶらんと音をたてんばかりに揺れる大ぶりのピアスを好んでいましたが、ちんまりした控えめなものに手が伸びるようになりました。
歌舞伎は相変わらず好きですが、それよりもお能に心惹かれるようになってきました。能面や動きなど、制約があるなかに表現が凝縮しているあの感じや、鳴り物との掛け合い。台詞のリズムや、簡潔に描き出される登場人物の心理。それらをある緊張感のなかで演者と観客が共有しあうところなど、クラシック音楽に近い魅力を感じます。
なにより驚いているのは、弾きたいと思う作品が少しずつ変わってきていることです。嬉しいことに、以前にもましてバッハが好きになってきました。限られたフォルムのなかで最大限に繰りひろげられる彼の音楽の宇宙感に、和装の世界に通じる美学を感じているのかもしれません。
こんなことを話したら、友人に「美奈子ちゃんって、本当に単純ね」と笑われそう。でも、徐々に本来の自分にリセットされるような感覚もあって、なにやら新鮮です。とはいえ、まだまだ着物生活一年生。これから自分がさらにどんなふうに変化するのか、楽しみです。
■第696回 センスアップに、大切なこと
春節も雨水も過ぎ、暦ではすっかり春ですがまだまだ肌寒いこの頃です。
首都圏で雪が降るととんでもないパニックになりますが、雪深い土地には、その特性を生活にいかす昔ながらの智恵があります。例えば、雪の中で野菜を保存して鮮度を保ったり、甘みを高めたり。秋に収穫したそばの実を、あえて氷が浮かぶような冷たい川にさらし、甘みと風味を深めた“寒晒し蕎麦”は、首都圏では頂くことができない格別な味わいです。凍えるような寒さのなか家に帰り、温かい部屋でいただくお茶やおかゆの湯気すらもごちそうだ、という人もいます。どんなところにも、なにかしら他にはない“とっておき”があって、人の心をとても豊かな気持ちにしてくれます。
さて、断捨離ブームは一段落したのでしょうか、今度は60歳を超えたおしゃれな外国人女性のスナップ写真集や、『◯◯人は10着しか服を持たない』などといった、ライフスタイルを見つめなおしてふさわしいものを取捨選択したり、カッコ良く歳を重ねるためのあれこれについて伝えている本が、ベストセラーになっています。
スキルアップ、ファッション、美容に趣味…。世の中の女性たちの向上心や前向きな姿勢には、頭が下がる思いです。ニューヨークのセレブなマダムたちやおしゃれなパリジェンヌのスナップを眺めて美意識を高めるのも素敵なことですし、何万円もする化粧品をずらりとそろえて、女磨きにいそしむもよし。また、お気に入りのブランドの時計やジュエリーを身につけ、気分良く過ごすもよければ、体調を整える食事や運動を心がけ、身体からキレイになるという手も。その他、好きな芸能人の追っかけをして若返るのもいいし、教養を深めたり旅行で見聞をひろげたりして心の充実を図るもよし、です。
西洋のレディーのライフスタイルやファッションセンスを上手に取り入れるのは、たいへん興味深いことです。でも、彼女たちにはなく、私たちにあるものに、もっと目を向けるスペースがもう少しだけあっても良いような気がします。例えば、ご先祖からいただいた、腰が低く歩幅が小さいという遺伝子は、洋服よりの和服の時にその所作の美しさを発揮しますし、微妙にくすんだ深い色合いは、西洋人より東洋人の肌にぴたりと栄えます。装いだけでなはありません。ものを手渡すとき、受け取るときに両手を添える習慣、会釈のしかたに
懐紙の使いかた…、ちょっとしたしぐさにも、日本人ならではの美しさはたくさんあるはずです。
着物を着ると、そんな所作に自ずと意識が向くようになることに気づきました。着るときはバサっとやらず、後ろに手を回して肩に着物をかけますし、しまうときは、洋服ならひょいとハンガーにかけておしまいですが、和服の場合は美しくないシワがでないよう、畳の上に膝をついて広げ左右にさばき、折り目にそって丁寧にたたみます。たとう紙に包んで、崩れないよう両手で下から持って…と、ひとつひとつの動作に、大切に扱っているという意識を自然に感じることができます。
先日、愛用している香水のブランドのブティックに立ち寄って、アドバイザーの方としばし話し込みました。曰く、「おひとりひとりの体温や体臭、その日の体調や湿度などによって、香り方、感じ方は違ってくるものです。香りはそんなパーソナルなものなので、自分にはどんな香りが似合うかしら、とか、この香りはもう少し年齢を重ねてから…とか、これは春夏には重すぎるから軽いものを…などと形にとらわれず、お好みや感性で自由に選び、つけこなしていただきたいのです。例えば颯爽としている方が濃厚な甘い香りを纏ったり、女らしい印象の方がユニセックスな香りを漂わせる意外性も、ステキなものです。香りをご自身のものにして『これがわたしよ』と表現して楽しんでいただくことが、調香師の本望なのではないでしょうか」
“香り”を“音楽”に、“調香師”を“作曲者”に置き換えても同じことが言えるかもしれません。ファッション、ライフスタイル、お習い事…。なんであれ、他の人の意見や流行、形にこだわらず、自身の好みや個性を尊重して、ひとつひとつを丁寧に吟味することから、本当のセンスが成熟していくような気がします。
着物を手にするようになって、そこに息づいている洋服にはない美学や、日本人の類い稀なる感性、繊細さと大胆さ、遊びと品格…などを、改めて実感しています。人生と心を豊かにしてくれるものを自分できちんと選択できる人こそ、本当にスタイリッシュで賢い人なのだと思います。
■第695回 バレンタインもいいけれど
中国ではそろそろ春節(旧正月)の休暇に入るとのことで、都内の百貨店や宿泊施設は、かの地からのお客さまをお迎えする準備に余念がないようです。
日本がバレンタイン騒ぎに巻き込まれるしかないような風潮にのまれるこの時期に新年のお祝いとは、なんだか羨ましいような気がします。かつては私も、いそいそとチョコレートを買いにいったり、チョコレートのお菓子を作ってみたりもしたのですが、本来のバレンタインデーとあまりにかけ離れた商業イベントになってしまっていることにさすがに辟易として、今年は一切チョコレートの類いは買わないことに決めました。
それにしても、一製菓メーカーが仕掛けたイベントがここまで定着し、しかもどんどん進化(?)し続けているというのは、すごいことです。私の子供時代は、学校にチョコレートを持っていくことは禁じられていましたが、今や小学生にとってもバレンタインは大切な行事になっているようで、義理チョコならぬ“友チョコ”を、何十個(何百個?)も用意しなくてはならないのだと、生徒さんから聞きました。
「でも、そんなにたくさん買うお小遣いがないから手作りするんです。けど、それがまた大変で…。ラッピングとかはおかあさんにも手伝ってもらうんです」と、聞いたときにはあまりに驚いて、「はぁ、あらら、ずいぶん大変なのねぇ」と、間の抜けた反応になってしまいした。
年が明けて一ヶ月が過ぎ、新年のあれこれはさすがに落ちついたものの、まだまだ寒い日が続いて花も咲きそろわないこの時期。バレンタインデー以外の日本でお馴染みの国民的?行事といっても、哀しいかな確定申告ぐらいしか思い浮かびません。この季節に、中国の春節のようなにぎやかな伝統行事が日本にあったら、バレンタインはここまで根付かなかったかもしれません。
そんな二月のある日、思いがけず歌舞伎を観に行く機会を得ました。ある知人が、その公演に行く予定だったご家族が急な用事で行けなくなってしまったから、と、チケットをありがたくもお譲りくださったのです。
歌舞伎は大好きで、東銀座の歌舞伎座には10代の頃から何度となく足を運んできました。今回は、大規模な改築工事後初めてだったのですが、建物の一部は巨大な高層ビルになったものの劇場内はさほどの変化も違和感もなく、ホッとしました。多摩市に住んでいる叔母と待ち合わせ、美味しいものが少しずつ、可愛らしく詰めあわされている歌舞伎座特製の幕の内弁当を一緒に選び、舞台がちょうど良く見渡せる中央の座席に身を沈めて、数年ぶりの歌舞伎を心から楽しみました。
梅が咲き、春告鳥が鳴き…舞台は日本の昔ながらの春の風情に溢れていました。舞も衣装も素晴らしかったのですが、大胆な舞台仕掛けや、見事な長唄や三味線など鳴物にも引き込まれました。観劇を終えて外に出ても、興奮のあまりに身体が熱を帯びていたのか、ちっとも寒さを感じませんでした。お茶をいただきましょう、と入ったカフェで開口一番「なんだかアイスクリームがたべたいわ」と言った叔母も、同じ感覚だったようでした。
歌舞伎だけではありません。改めて言うまでもなく、日本には素晴らしい文化や習慣がたくさんあります。昨年、やっとバレンタインデーが終わり、いよいよ女の子の節句だ、と、生徒さんに何かお雛様の可愛らしいお菓子をあげようと探しに出かけるも、目に入るのはホワイトデーのブースばかりで、なにやら心淋しい思いをしたのを思い出しました。
今も目を閉じると、菊之助さんが演じた、動く浮世絵のように美しい小野小町の姿が、まぶたに浮かびます。ふと、高校時代に、彼女の短歌“夢路には足もやすめず通へども現(うつつ)に一目見し如(ごと)はあらず”(*あなたを思って夢の通い路を足しげくあなたのもとに通いつづけるけれど、夢の中でいくらお目にかかっても現実にたった一目お逢いしたものとは比べものになりません。一目でいい、お目にかかりたいのです)と出会い、憧れの人を想って心をときめかせたことを思い出しました。
あの頃より、このような歌の美しさや感情のゆかしさ、切なさ、そして日本人の感性の豊かさを理解できるようになってきたことに、感謝しているこの頃です。
■第694回 夜更けの境内で
そのフレーズを数秒聞いただけで…まさに一瞬で、その時好きだった人、その時の空気の匂いがよみがえって、時に涙があふれたりすることって、誰にも起こりうることです。そんな瞬間、何よりも大きなパワーを音楽に感じて、思わず身震いすることがあります。
先日、ひょんなことから知人とある神社を散歩しました。一日中零下に近い気温で、震えるほど寒い日の夜更けだったのに、境内の御手洗で手を清めたときその水が肌に柔らかく、不思議なほど温かく感じられました。杉の大木は夜空に向かってどこまでもまっすぐに伸び、その向こうからは満月が今世に生きるわたしたちを穏やかに見守っていました。全てがつながり、互いを慈しみあっているようでした。
一緒にいた知人は「夜にこういうところに来るの、全然怖くないの?」と驚いていましたが、私が霊的なものをさほど怖いと思わないのは、バッハやベートーヴェン、ショパンの書き残した譜面に彼らの霊感や魂が生き生きと息づいているのを、いつも全身で感じている…あるいは、“感じようとしている”からかもしれません。
昨年末ふと、ブダペスト留学時代にお世話になった大家さんのカティに連絡をとってみよう、と思いたちました。もう何年ぶりになるのか、思い出せないほど久しぶりなことです。10年ほど前に離婚して以来、近況を伝えるのが憚られて、ずっと音信不通なままになっていました。
住所が変わっていなければいいのだけど…と、思いつつ手紙を投函して一ヶ月半ほどがたったある日、彼女の住所から返事が届きました。一見してカティと分かる筆跡…かと思いきや、差出人を確認すると彼女ではなく、お嬢さんのアグネスになっています。
「あれ?」と思いつつ手紙を開けてみると…やはりそれは、アグネスからのメッセージでした。「ミナコ、私たちのことを思い出してくれて嬉しいわ。でも、悲しい知らせをお伝えしなければならないの。母は、一昨年の秋に肝臓ガンで天に召されました。60歳でした。最後まで希望を持って治療に励んでいたけど、病気の進行が進んでしまっていて…でも、とても穏やかな最期だったのよ。母は今も、父と私の心の中に生き続けて、いつも励ましてくれています」
手紙を読みながら、ブダペストの空港で初めてカティと会ったときのこと、一緒にシーツを取り替えながら交わした他愛のない会話、日本から送られてきた荷物が入っていた段ボールを捨てるのが忍びなくて、きれいな包装紙や小道具を使って私がちょっとした物入れにリメイクしたものをみて「まあ、ミナ(カティは私をこう呼びました)!これ、とてもすてきだわ。売っているものよりもずっとロマンチックね!」と、目を輝かせながら褒めてくれたことなどが、次々に思い出されてきました。
才女で、数ヶ国語を自在に操り、インド大使館で通訳のお仕事をしていたこともあるカティ…。実は再来月、彼女に会いにブダペストに行こうと計画していたのです。お母さんとそっくりな筆跡のアグネスの手紙を読みながら、どうしてもっと頻繁にお手紙を書かなかったのだろう、もっと早く会いに行かなかったのだろう、という思いが重なって、途中からみるみる涙が溢れて手紙が読めなくなってしまいました。
手紙には、ハンガリーのカロチャ地方の美しい刺繍がプリントされた便箋と一緒に、写真が二枚同封されていました。留学時代はまだちいさくて、当時カティに「私の大切なベイビーちゃん!」と呼ばれていたアグネスはすっかり素敵なレディになって、恋人と寄り添って微笑んでいます。もう一枚の写真はカティの旦那さまのラースロー。白髪にはなっていますが、相変わらずバルトークそっくりのハンサムです。
夜更けの境内を歩いたのは、アグネスからの返事をもらったまさにその日の晩でした。雲の切れ目に見え隠れする満月のひかりの向こうの世界と、それに照らしだされている現世とが穏やかにつながっているのを感じながら、そっと合掌しました。願わくば、彼女の魂が天国で安らかにあらんことを。そして、彼女への感謝の気持ちも、ブダペストでの思い出も、すべてが私のピアノの音に溶け込んで、ずっとずっと息づいてくれんことを…。
なぜか、寒さをまったく感じませんでした。彼女の笑顔は、アグネスやラースローだけでなく、私をも励ましてくれる…そんな気がしています。
■第693回 ある冬の日の雑感
「これまで、何回お見合いしたかわからないわ。婚活?そんな言葉がでてきたずっと前からよ!」と、豪快に言い放った大学の同窓生Kちゃん。昨年秋、卒業して以来四半世紀ぶり(!)に会った彼女は学生時代よりもずっとあか抜け、言葉とは裏腹に結婚できない悲壮感などみじんもなく、きらきらと輝いていました。
『結婚できない人をゼロに』という結婚相談所のキャッチコピーをみるたび、「いやだわ、これ。だいたい、“できない人”っていうの、お客さまに対して上目線じゃない?結婚していない人のうちの大半は、“できない”のではなく“しない”のよ」などと、心の中でつい噛み付いてしまう私は、『婚活』という言葉をどうも好きになれません。
だいたい、部活、という存在すらも恨めしいのです。いったい何人、何十人の優秀な生徒さんが、部活のためにピアノをやめてしまったことか!(語弊のないよう補足します。部活自体が悪いということではないのです。ただ、チームや集団でプロジェクトや試練に立ち向かうのは、社会に出てからいくらでも経験できることなのに対して、ピアノソロによる“個”への飽くなき追求とその表現を学ぶ機会は、実は社会ではなかなか得られないものなのです)。
ところで、流行り廃りの早いこのご時世、既に“婚活”という言葉は、すでにピークを過ぎた観があります。このごろは人生の最後のしめくくりを整える“終活”という言葉を頻繁に見かけますし、定番“就活”の他にも“菌活(発酵食品を摂って健康に!)”、“朝活(早起きしてスポーツや読書でスキルアップ!)”、“離活(離婚の準備)”、“転活(天丼とカツ丼、どちらにするかを熱く語る…ではもちろんなく、転職活動です)”、“笑活(笑ってストレス解消)”、“涙活(逆に、思い切り泣いて気分スッキリ)”、“温活(身体を温めて代謝を良くすると同時に、体温をあげることで癌の予防にも)”…もう、キリがありません。
ところで、お酒を飲まなくなってから食べ物の好みが少し変わってきたように感じています。前にもまして好きになったのが果物、ドライフルーツ、ナッツの類。反対に、あまり食べなくなったのは生クリームを使ったケーキや市販のお菓子です。飲み物の好みにも変化があって、以前はそれほど積極的に飲みたいと思わなかった紅茶やハーブティーが、コーヒーと同じぐらい好きになりました。
その他、ザクロのジュースをますます好んで飲むようになりました。ザクロのジュースはソウルで初めて飲んで以来、その少しクセのある味わいの虜になっていました。以来、いくつかの種類を試してみました。濃縮還元のものは何かものたりないし、国産のものもスッキリし過ぎて、ザクロならではの“えぐみ”が足りません。いろいろ試した結果、イラン産かトルコ産の、有機栽培されたザクロのストレート果汁が好みと分かりました。
あれこれネットで調べているうちに、ザクロにはポリフェノールだけでなく、女性ホルモンと同じ成分、エストロンやエストラジオールが含まれることから、不妊や生理不順が改善させたり、豊富なビタミンやカリウムなどが酸化防止、むくみや動脈硬化の予防にもよいとされているそうです。つまり、ザクロジュースは究極の“妊活(妊娠しやすい身体と生活リズムをつくる!)ジュース”だったのでした。
“妊活”。この言葉にもやはり抵抗があります。生命に関わる立派な活動だとしても、なぜかそうは聞こえないのです。美しい日本語はたくさんあるのに、最近の流行り言葉には豊かな語感の言葉が少ないように思われてなりません。
今日、東京はこの冬初めての積雪を観測しました。ほんの“ごあいさつ”のような可愛らしい雪に、マスコミも人々も戦々恐々として、なんだかせっかく降りてきてくれた雪に申し訳ないようでした。
「今日ね、雪、降らなくてつまんなかったな」レッスンを終えて帰る際に、ちいさなMちゃんが残念そうに言いました。Mちゃんは雪に“あいさつ”するのを、楽しみにしていたのでした。
冬ながら空より花の散りくるは雲のあなたは春にあるらむ
Mちゃんを見送り、ふと古今和歌集におさめられている清原深養父の歌を口ずさみました。短歌の端正なリズムと美しい響きを、英語よりも先に小さいMちゃんに知ってもらいたい、と思いました。
■第692回 きれいな光のふるさとへ
千葉に拠点を移して、いつのまにか15年目になります。住めば都。気候も人も温かく、とても好きな場所になりましたが、何年が経てもどうしても馴染めないのは、山並みがみえないことと、千葉に地名のつくメジャーな人気スポットが少ないことです。
例えば、ディズニーランドやディズニーシーは“東京”の二文字が鎮座していて千葉のチの字も浦安のウの字もありません。成田空港も正しくは“東京国際空港”だし、ファミリーに人気の公園に“東京ドイツ村(袖ケ浦市)”なんていうものも。“マザー牧場(富津市)”のように地名がないだけならまだしも、なぜ“東京”なのか…。考えるたび、なんだか悔しいような気持ちになるのは私だけでしょうか(その点、“鴨川シーワールド”や“市原ぞうの国”はえらい!)。
それとはちょっと違う話になりますが、例えばブダペストが“ドナウの真珠”、と呼ばれるのは素敵な喩えだと思うのです。でも、“東洋のナイアガラ”(沼田市吹割の滝)、“南米のパリ(ブエノスアイレス)”など、別の地名に置き換えて表現されるのは、本家の二番煎じのようで個人的にはあまり好きではありません。地名ならまだしも、人の場合はどうでしょう。ご本人のお気持ち次第かもしれませんが、例えば中田喜直さんは“日本のシューベルト”なんて紹介がなくても素晴らしいのに…などと、つい、いらぬことを考えてしまいます。
ところで、山形県置賜郡ご出身の童話作家、浜田広介さんは“日本のアンデルセン”と呼ばれているようです(*19歳年上の大分県出身の児童文学者、久留島武彦氏も、そう呼ばれているようですが)。以前、このエッセイにも書きましたが、『泣いた赤おに』をはじめ彼の児童文学は子供の頃から大好きで、彼の故郷高畠町にある記念館にも何度か訪れました。壁面に杉のせご板が敷き詰められた、150人ほど収容できる円形の“ひろすけホール”があまりにも可愛くて素敵で、ああ、こんなところでコンサートができたらなぁ…と、思わず夢みてしまいました。
広介さんの童話に惹かれるのは、そこにきれいな涙、きれいな光、そしてきれいな心がたくさん出てくるからです。『泣いた赤おに』で、赤おにが最後に友人の青おにの手紙を読み、その真意を知って流す涙。『りゅうの目になみだ』
で、男の子のあたたかい心に触れてりゅうが流す嬉しい涙。その涙は川となり、竜は船となって子供たちの役に立とうとします。自分が星のように明るい光になることを願い、最後にきれいな光をともしてとうとう倒れてしまう“がい灯”が主人公の、『ひとつのねがい』。その他、『琴の名人』『光の星』…物語に登場するものたちはそれぞれに苦しみ、悩みながらも、自分のなかに美しい光のような信念をみつけ、それを貫くのです。
話は変わりますが、歴史ある音楽専門誌『音楽の友』最新号の特集“2014年コンサートベスト10”で、高名な音楽評論家でラテン音楽の権威でいらっしゃる濱田滋郎先生が、私の出演したDuo E-vitaのアルゼンチン・ナイトをそのなかに挙げてくださいました。先生は評論、著書も多く、歌曲、オペラなどの翻訳、訳詞などもたくさん手がけられているだけでなく、ギター界にも多大な貢献をされている方で、昨年日本初演されたアルゼンチンの作曲家ゴリホフの“アイナダマール”の先生の感動的な訳詞に涙したのは、つい最近のことです。国内外のそうそうたる超一流アーティストに混じっての、ベスト10入りでした。あまりに光栄なことに、未だ実感がわきません。
濱田先生は、私がファーストアルバム『piano pieces from Finland』をリリースした折にも、『レコード芸術』誌に素晴らしいレビューを書いてくださいました。マイペースで細々と活動してきた私にとって今回のことは、それこそ広介の童話にでてくる美しい光のようなお励ましだわ、と思っていたまさに今日、先生はなんと、かの浜田広介さんのご次男でいらして、あのひろすけホールでギターを演奏されたこともあると知りました。
今、目の前に浜田広介記念館で購入した広介さんの童話集と、濱田先生の著書『スペイン音楽のたのしみ』の2冊の本があります。『スペイン音楽のたのしみ』の見返しには、先生にお会いした時にサインしてくださった『鈴木美奈子様 心より友情を込めて 濱田滋郎』という、流れるような美しい文字が書かれています。
それを眺めながら、広介さんの直筆を思い出しています。そして、あたたかくなったら、彼の童話の舞台そのもののような、あののどかな置賜をもう一度訪れたい…などと考えています。
■第691回 古典落語の愉しみ
地元のとある場所で月一回行われている『古典落語を愉しむ会』の会員更新の時期がやってきました。会員になって三回目の更新ですから、会員歴四年目に入ることになります。
当初は落語のことは何も分からずになんとなく通い始めたのですが、もともと江戸時代の町人文化には興味があったということも手伝って、その面白さにどんどんはまりつつあります。噺家さんの高座を楽しむために集い、笑顔と笑い声が溢れる空間を皆で共有できる時間は、なんとも気持ちのよいものです。
特に中期から後期にかけての江戸の文化は、私にとって興味のつきない憧れの対象です。ファッション、芸能、人々の生活スタイル…。それらほとんどすべてに息づいている“粋”の美学には、以前から心惹かれるものを強く感じています。
実は江戸時代のある時期、その人口は128万人で、世界一だったとも言われています。しかも、二位のロンドンが85万人ですから、遥かに上回っていたことになります。清潔さにおいても類を見なく、ロンドンやパリが糞尿やゴミにまみれ、人々が疫病になやまされていた時、江戸はというとそれらはすべてきれいにリサイクルされていました。でも、なんといっても群を抜いていたのは、識字率の高さです。江戸の成人男性の7割に対してロンドンは2割、パリは1割でした。
古典落語のルーツには諸説あるようです。小咄がふくらんで一席にまとまった、とは古今亭志ん生師匠の説。その他、お坊さんの説教をみんなに分かりやすく説き聞かせたのが発端とか、御伽衆とよばれる人たちが殿様に聞かせた笑い話がはじまりである、などと考えられているようです。
興味深いのは、そのストーリーの元をたどると日本古来のものだけでなく、他国からのものもあって案外グローバルだということ。ものによってはその原話がグリム童話だったり、アフリカはマダガスカルの口承民話だったりするというのですから、驚きです。人間はいつの時代にどこに生きていても、本質はそんなに変わらないのかも…。
単なるシャレや冗談ではなく、人の心のおもしろさを笑うところや、一つの噺を自由にふくらませてアレンジできるところも、古典落語の魅力です。また、大切な『粋』という美学ですが、これは上方と江戸で若干ニュアンスが違ったようです。上方では『粋』を“すい”と読み、性格や身なりに華や艶があり、贅沢や遊びを極めた先に到達する洗練の境地を言ったそうです。尊敬される粋人(すいじん)に対して、軽蔑されるのは“不粋(ぶすい)”。
それに対して、江戸の粋(いき)とは、性格や態度、身なりなどがさっぱりとあか抜けていて、さりげない色気があることをいい、芸事や遊びに長けているだけではなく、人情の機微にも通じていることが大切だとされていたようです。そんな美意識の基本である“粋”の反対にあたる“気障”や“野暮”は、馬鹿にされたとか。
貧しくても富んでいても、それを卑下したりひけらかしたりすることなく、人間としての尊厳とユーモアをもって堂々と人生を愉しんでいる大人の姿に、子供たちは「早く自分もあんな大人になりたい」と、健全な憧れを感じながら育つことでしょう。古典的でありながら庶民的でわかりやすく、他国の要素もうまく取り入れられているところや、『粋』を美徳とするあたりにはなんだかアルゼンチン音楽に通じるものも感じられて、興味は深まるばかりです。
最近は、“くすぐり(笑わせる部分。ギャグ)”よりも心憎い“間”に惹かれます。そして、だんだん落とし噺(笑いが主体の噺)よりも、人情話が好きになってきました。噺家さんの着物の着こなしを見るのも楽しみのひとつです。
着物といえば、いつか浅草演芸ホールや鈴本演芸場あたりに、江戸小紋なんぞをさらりと着て出かけてみたいものです。鈴本なら浅草だけど、梅園のあわぜんざいをいただくのは、高座の後がいいかしら、前がいいかしら…。今年の目標のひとつに「自分で着物が着られるようになること」をちゃっかり加え、お散歩コースを妄想したり、美しい着物の本を眺めてはにやにやしているこの頃です。
■第690回 心の恋人ヘルマン・プライ
年が明けるときは、いつも清々しい気持ちになります。新たなスタートをきっかけに、自分の一部がリセットできるような感じがするからでしょう。
でも、なにも一年に一度の節目ではなくても、一日の終わりに好きなことを楽しんでリラックスしたり、起きたらすみやかにに外に出て、朝の空気を思い切り吸ったりすることで、かなり気分をリセットできることに気づきました。
最近、楽しんでいるのは、就寝前の読書タイム。特に女流作家さんのエッセイや小説を読むのが気に入っています。情感にうったえすぎない、抑制の利いている簡潔な文章に惚れ惚れして、思わず「いいなあ、男前だなあ」と心惹かれるのは、なぜか女性が多いのです。
私もどちらかというと文章を書くのは好きなほうですし、実際、書くことを生業とはしていないとしていない周囲の人よりも文章を書いているほうかも知れませんが、彼らプロの文章に触れるとそのあまりのレベルの差に、圧倒されます。その、打ちのめされる感じがまた、好きなのです。プロの技に触れ、感動を覚えるのは、それが何の分野であっても心持ちのよいものですし、なにやらパワーを頂けるような気がするのです。
逆に、寝る直前にすすんでしないのは、クラシック音楽(特にピアノ演奏)を聴くこと。こちらは気分のリセットどころか、自分の状態によっては一日を(下手すると、これまでの音楽人生を!)猛烈に反省して、眠れなくなってしまうことになりかねないからです。分野が違うからこそ打ちのめされることも楽しめるのであって、本業の甘さを反芻しはじめたら心安らかではいられません。
ところが、例外的にむしろリラックスさせてくれる演奏家も、います。つまり、お説教的なところがまったくなく、おおらかにすべてを包み込んで許してくれるような深い懐の持ち主で、音楽への愛情に満ちあふれた温かな音楽で幸せな気持ちで体中を満たしてくれる類い稀なる演奏家…。私にとってそのひとりが、バリトン歌手のヘルマン・プライです。
プライは、同じドイツ出身で5歳年上の偉大なバリトン歌手、ディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウとよく比較されてしまいます。オペレッタのようなくだけたレパートリーよりも、どちらかというとリート(歌曲)や宗教曲などに本領を発揮し、文句のつけようのない端正な芸術的品格の持ち主である帝王ディスカウに対して、プライは柔らかな声と気負わない自然な歌い回しが魅力。時に不安定になる音程すらもチャームポイントとして愛され、オペラやオペレッタなどの舞台で見せるチャーミングな“身のこなし”にも人気のある方でした。
以前は私も、「リートは、どちらかというとプライよりディスカウよね」と思っていた節がありますし、確かにディスカウのシューベルトは非の打ち所がない、比類なき人類の宝であることには間違いありません。でも、ブダペスト留学時代にリスト音楽院大ホールでシューベルトのリートによるプライのリサイタルを聴いたときには、あまりの素晴らしさに身震いしてしまいました。シューベルトが楽譜から抜け出し、親しげな微笑みを浮かべながらすぐ近くにきて、私たちに向かって語っているかのようだったのです。それは、ゲイジュツなんていうよそよそしいものではなく、どんな時にも寄り添ってくれる近しい友人の体温を思わせるものでした。プライはそれ以来、心の恋人です。
「シューベルトは私の人生の中心点です。彼の絶望的な部分に強い共感を覚えるのです。私自身もたくさんの絶望を味わってきましたから。でも、人間にとって下から上に這い上がろうとする力こそが、成長につながるのではないでしょうか。私が落ち込む状態になるのは、成長を求めているときなのだと思っています」
プライのてらわない表現と優しく包容力のある声は、そんな自然体な彼の人間性そのものなのでしょう。嗚呼、彼のように落ち込んでいる人にもそっと寄り添って、温かな気持ちになってもらえるようなピアノ弾きになれたら、どんなに幸せなことか!…ブダペストで彼を聴いてから10年も経たない1998年、69歳の誕生日を迎えた直後にお亡くなりになったのは、とても悲しいことでした。ドイツの新聞各紙は一斉に、トップ記事でその訃報を伝えたそうです。
■第689回 柔能く剛を制す
近年、年末の恒例になっているイベントの一つに、『今年の世相を漢字一文字で表すと』が投票され、その結果が発表される、というのがあります。今年の一位は“税”、二位は“熱”、三位が“嘘”だったとか。熱、というのはまだしも、四位以下も“災”“雪”“泣”…と、なんだか切なくなるような一字が並んでいます。
「こんなこと(この投票のこと)しようと言い出したのは、ぜったい男だと思うし、投票しているのも男が多いんじゃないかな」「どうして?」「ほら、よく言われるでしょ、“男性は過去を語りたがり、女性は未来を語りたがる”って」「なるほど。確かに、過去の栄光とか功績とかを語りたがるひと、男に多いよね」「そうそう。それに、分析好きな傾向も、男のほうがあると思わない?」「そうよね。私たち、べつに一文字でまとめてくれなくてもいいんですけどー、って感じするし」
電車の中で女性同士の会話に耳を傾けると、時になかなか面白い(鋭い?)見解が飛び出てきて、興味深いものです。私はと言うと…やはり今年がどうだったかを反芻するよりも、来る年がどうであってほしい、ということをあれこれ夢見るほうが好きです。過去を振り返り、反省を生かすことも大切だとは思います。でも、過去には戻れませんが、未来は無限。そちらをどのようにしたいかを考えたほうが建設的だと思うのです。
そこで、今年はさておき『来年の自分を漢字一文字で表す』というのを考えてみました。来年はどんな自分でありたいか、ということを一文字でシンボリックに表現してみよう、という試みです。でもいざ考え始めると、一文字で簡潔に、というのは案外難しいのです。しかも、スローガンのような立派なものではなく、自分の隠れテーマになるさりげない言葉が望ましかったのですが、なかなか思いつかず悩んでしまいました。
と、今日、生徒さんのレッスン中に一つの言葉が目に飛び込んできました。“dolce(ドルチェ)”。頻繁に楽譜に登場する、中学校の音楽の教科書にもでてくるイタリア語で、“柔和に”という意味の音楽用語です(もっとも、この言葉をもつ国イタリアではビスコッティーなどの固いものをのぞいた、ジェラートやティラミス、パンナコッタなどのデザート全般のことをさす単語なので、単に音楽専門の言葉というものではありません)。
これです!“柔”という一文字、これこそ、私のイメージにぴったりな言葉でした。柔らかい、というのは一見軟弱なようですがそればかりではなく、様々な困難があっても柔軟にそれに対処するしなやかさがある、ということでもあります。意味を調べると、“しなやかで弱い”という意味とともに“おだやか”“心やさしい”という説明が並んでいます。
海外ではしばしば、葦がそれに例えられます。か細く弱い印象がありますが、それゆえに折れることがない。風になびきながらも根はしっかりと張っている…。「人間は考える葦である」というフレーズばかりが思い浮かびがちですが、西洋では一見弱くみえても強いものとして、独特の意味合いを持っていると聞いたことがあります。
頑(かたくな)にならず、いつもおだやかに、やさしく柔和な心持ちでひとと接することができますように。でも意思がゆらいだりぶれたりしないよう、しっかりと根を張って、たとえ悲しいこと、苦しいことがあっても心がくじけてしまうことなく、しなやかな強さをもってそれを乗り越えていけますように。
来週の今頃はもう2015年。ショパンとアルゼンチンの音楽に明け暮れ、駆け抜けていった2014年もあと5日で終わりです。その間にも、生徒さんのレッスン、年賀状書き(遅い!)、大掃除、6日分の荷造りをして仙台に移動、高校時代の同級生との忘年会(これは楽しみ!)、実家でのお正月料理のお手伝い…、と、まだまだ予定は山積みです。でも、気ぜわしい時ほど柔らかな心を忘れないで、ゆったり自分と向き合いながら丁寧に日々を生きていきたいものです。
皆さんの2015年は、どんな一文字にしたいですか?…いずれにしましても、今年も一年間お付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。来年もどうぞ宜しくお願い致します!
■第688回 “香り“の愉しみ
忘年会たけなわ。友人には「趣味は飲酒です」なんて豪語する愉快な人物も、いたりします。
お酒やタバコ、コーヒーなどはよく“嗜好品”というくくりに入れられます。その定義は辞書によって多少ニュアンスが異なりますが、だいたいは『生体の生命維持には直接の関係をもたないが,刺激性,麻酔性,または特種な芳香性のある物質で,味覚,触覚,嗅覚,視覚などに快感をあたえる食料,飲料,?料(かみりよう),嗅料(かぎりよう)の総称』とか、『栄養分として直接必要ではないが,人間の味覚,触覚,嗅覚,視覚などに快感を与える食料,飲料の総称』などという説明の後に、『茶、コーヒー、たばこ,酒、漬け物(!)などがこれで、カフェイン、タンニン酸、アルコール、苦味物質、揮発油成分を含むものが多い』といった例が挙げられています。
そこで疑問が。嗜好品とは私たちに何らかの快感を与えるもので、口から入るものだけでなく、嗅ぎタバコのように鼻から吸うものも含まれるということですが、食料ではないけど“嗅料”ではある香水などの“香り”はそれに当てはまるのでしょうか?
そうだとしたら、私の最大の嗜好品はアルコールよりもむしろ香りかもしれません。お酒なら何日も飲まなくても平気ですが、香水の類いを手に取らない日は一年を通して一日もないのです。何種類かの中から、その日の気分にあわせて香水を選ぶのは、私にとってささやかにして大きな楽しみになっています。
身体に纏うだけでなく、ルームフレグランスやアロマデュフューザーでお部屋にほんのり香りを満たすのも好きです。本番前にリラックスしたいときは、レッスン室にラベンダーのアロマを炊いたり、ゆっくり睡眠をとりたいときには寝室にシダーウッドを香らせてみたり。そういえば、お料理にもスパイスやハーブを使うことが多いように思います。
インドのアーユルベーダをはじめ、伝統的な医食同源の国には、食べるものも香りも健康維持のためにとても大切なものだ、という思想があります。もちろん日本にも柚子や木の芽など季節折々の香りを楽しむ習慣はありますが、健康のため、という意識とはまた少し違うように感じます。
ピアニストの友人が、ステキなタイトルのアルバムをリリースしています。ずばり“Les Parfums(ル・パルファン)”…フランス語で香り、という意味です。私もフランス語で夜、という意味の“Le Soire(ル・ソワール)”というタイトルの、やはりフランス音楽のアルバムを出しているので、お互いにそれが分かったときには「まぁ、なんて偶然!」と、笑いあいました。
彼女がタイトルについて“「香水」ではなく抽象的な「香り」全般をさしています”と説明しているとおり、いい香りの余韻のようなものが感じられる、彼女らしいセンスに溢れたアルバムです。それを聴いていると、聴く人が心地よいアロマに包まれてリラックスしたり気分をリフレッシュしたりできるようなアルバムを作ってみたくなって、うずうずしてきます。独身をつらぬき、若い頃からの美貌にますます磨きがかかっている彼女の口から「恋は芸のこやし」なんていう言葉をきくと、かっこいいなぁ、と、ついぼーっとしてしまいます。
あまり周囲の人にこんなことを力説していると、「ずいぶん彼女のコマーシャルに熱心ね。美奈子ちゃんは欲がないのね」なんて指摘をされ、え?そうかしら、と我にかえることがあります。
ピアニスト同士です、というとよく「じゃあ、ライバルね」と言われるのですが、私は音楽仲間でもある友人たちに対して、そういう意識はまったくないのです。むしろ、家族のようにお互いの成功や幸せを喜びあえる存在があるのは嬉しいこと以外の何ものでもありませんし、喜びも刺激も与えあえるそんな友人たちに恵まれていることには心から感謝しています。
そういえば、音楽家の友人はみんな美人ぞろい。いい音楽もステキな香り同様、人の心を健やかに保ち、若返らせる秘薬なのかも…!
■第687回 夢を叶える贈り物
「夢が叶う、ってどんな感じなのかしら…」長い間それを想像していました。ピアニストになることは最大の夢だったとはいえ、まだまだ精進の途中だという気持ちが強く、夢が叶ったという実感がないのが正直なところなのです。
『人間だけが、寝ないで夢をみる』なんてキャッチフレーズの広告がありましたが、そんな人間の夢はひとつとは限りません。考えてみたら私も、いくつかのちいさな夢は叶っているのです。たとえば留学したいという夢や、音楽とともにピアノで生きていきたい、という夢。でも、ほとんど諦めていたのですが、心のかたすみで秘かに願い続けてきた、口に出すのも憚られるような夢が、あったのです。
それは、『敬愛する作曲家から、曲を献呈してもらう』という、とんでもない夢でした。
もの心ついた時から楽譜と向き合ってきたおかげで、曲のタイトルの一番近くに書かれている“◯◯夫人に捧ぐ”とか“◯◯公爵に献呈”というのが、ずっと気になっていました。例えばベートーヴェンによくあるように、いわゆる“身分の高い方々”からの依頼がそもそもの作曲の動機になっている、というケースはその完全に「発注生産」になりますが、そうではなく、作曲家自らが任意にある人に贈る、という場合について、です。
例えばイザイが同胞の先輩の作曲家フランクから結婚祝いにあの素晴らしいヴァイオリンソナタを献呈されたとき、いったいどんな気持ちになったのだろう。そして、どんな気持ちでその作品を弾いたのだろう。愛弟子ラヴェルから『水の戯れ』を献呈されたフォーレは?『蝶々』や『木枯らし』を含む、12曲のエチュード作品25をショパンから献呈されたマリー・ダグー夫人は?多くの作品を彼女のために書いたシューマンの妻、クララは?…でも、献呈を受けた人たちはいずれも歴史にその名を残している素晴らしい大人物ばかりで、とても足下にも及ばないような遠い存在です。
ところが、そんな途方もない夢がつい数日前、何の前ぶれもなく叶ったのです。贈り主はブダペスト留学時代からの友人で、近年はピアニストとしてだけでなく作曲家としても活躍している、まさに私の敬愛する作曲家でした。氏はこれまでにもたまに自作の楽譜を送ってくれていたのですが、ある朝、届いて
いたメールに添付されたファイルを開いてみて、びっくり!タイトルの下に確かに“ミナコ・スズキへ”と、記されているではありませんか。
「え?」我が眼を何度も疑いながら、すぐさま印刷して弾いてみました。こういう時は、いつも以上に譜面に注意深くなるものです。うっかり見誤ることないように…と、一音一音を丁寧に読み込んでいきました。弾きたいテンポで弾けるようになるまでのもどかしさも、いつもに増して感じます。
“rainy walk”というタイトルのその作品は、演奏時間5分ほどのえもいわれぬ美しい小品でした。楽譜の最後の日付をみると本当にできたて!もちろんまだ出版されていない作品です。贈っていただいた感激に、しばらくはその曲が頭から離れませんでした。そして、弾くほどに次なる気持ちがふつふつと沸いてきたのです。「こんなにステキな曲を独り占めしてしまってはいけない。作曲者への感謝を何か形にしなくては」という…。
きっとイザイもクララも、そう思ったことでしょう。つまり、公開の場で演奏し、その作品の魅力を多くの人々に伝えたい、そして、できることならば作品を後世にも残したい、と。もちろん私には彼らのような力はありませんが、それでも何かの形で皆さんにご紹介したいと思わずにいられませんでした。できることは限られていますが、何か方法があるはず…。
そんなことを考えていたら、地元の知人がかつて映像のお仕事をしていらした方を紹介してくださいました。早速連絡を下さって、YouTubeなどへの投稿を考えているのなら力になりますよ、と言ってくださったのです。なんたるタイミング!あれよという間に、来週には打ち合わせをさせていただけることになりました。
打ち合わせで整合性が確認できて、作曲家の許可を得てからの話にはなるのですが、できれば来年の2月か3月頃YouTubeにアップできたらと思っています。皆さんに聴いていただける日が、今から楽しみです。
■第686回 夢はおおきく
今年もあとわずかです。振り返るにはまだ早いかな、とも思うのですが、ここから先はいつもまたたく間に過ぎてしまうものです。
今年は、近年になく忙しい一年でした。いつも年に一度のペースで行っている自主リサイタルですが、今年はデュオのステージや新潟放送主催の公演などが重なったため、例年よりたくさんの本番がありました。だからでしょうか、いつも以上にあっという間に過ぎ去った一年だったような気がします。
先月、なんとか韓国には行けたものの、毎年訪れていたヨーロッパに行けなかった一年でもありました。一週間ものお休みをとれるタイミングがなかったのです。何をするわけではなくても、ヨーロッパの空気を吸うと故郷に降り立ったような懐かしさに心からホッとして、リフレッシュ感が得られる体質の自分としては、少々淋しいことです。
「来年はどんな年にしたい?」友人と、このごろよくそんな話になります。「そうだなあ、やりたいことをもっとやれる年にしたいわ。今年は仕事に追われて終わっちゃったから」「そうね、そういう時間と心のゆとりが欲しいよね」「人生、とっくに折り返しているんだし…」そうだ。来年は私も、いつもに増してやりたいことをどっぷりやる一年にしようではないの!…と、ふと約一年前、新春第一弾のエッセイにどんな抱負を書いていたのか気になって、読み返してみました。
ふむ、心に誓った三つのこと、とあります。どれどれ…まずはその一“音楽講座の再開”。これは毎月一度、自宅で大人のための音楽講座を実際に開講して、順調に実行しています。よしよし。その二“新しい音楽ジャンルへの挑戦”。これも、今年はアルゼンチン音楽を一年じっくり探求することができました。実はまだまだ弾きたりないので、来年のソロリサイタルはアルゼンチン魂炸裂!なプログラムを考え中です。その三“ヨガ”あれれ…?
これは、やる気がなかったどころかちゃんとヨガのスタジオに入会し、ある期間週に二回ほど通ったのです。でも、腰の調子を崩して以来、すっかり遠ざかってしまいました。きちんとインストラクターに手ほどきを受けていたのですが、考えてみたら30人近くもの生徒にたったひとりの先生なのに、ひとりひとりに眼を行きわたらせるなんて不可能に近いことです。あるいは、ヨガとはまったく関係ないことが原因だったかもしれません。
来年は是非、ヨーロッパ行き…それも、久しぶりにブダペストやウィーンへの再訪を実現させたいです。そして、アルゼンチン音楽だけでなく、新作なども積極的にレパ—トリーに入れたいと思っています。そして、新しくお習い事を始めるというよりも、これからの人生がより豊かになるよう、語学の勉強を習慣づけたいな、とも。インターネットという便利なツールがある今、英語やハンガリー語がもっとできたら、現地のニュースやラジオなど、様々なソースを通じて楽しみを広げることができるでしょう。
特にハンガリー語はすっかり錆びついて、動詞の活用も冠詞、不定冠詞も忘れてしまっています。来年に向けて(実はもう航空券を手配済み)少しずつブラッシュアップをしていこう…と、文法の本を引っ張りだしてみなおしてみたら、ウラル語族(フィンランド語も同じ)の文法の特異性に、改めて驚きました。ハンガリー語は他のヨーロッパとは完全に違う言語体系で、どちらかというとアジアのそれに近いのです。
ノーベル文学賞を受賞したハンガリーの作家ケルテース・イムレ(ハンガリー語表記につき、名字ケルテースが先です)の作品は、映画化された『運命ではなく』以外、残念なことにほんの一部しか日本語に翻訳されていません。生徒さんに、フランス語が趣味で、ノーベル文学賞受賞作を言語で読む、というサークルに入っている方がいるのですが、彼女を見習ってハンガリー語で彼の作品を読めるようになるべく、気合いを入れてみようかしら…。
などと、途方もない(?)夢を胸にベッドにはいったら、その晩早速夢の中でハンガリー語を話していました。しかも、我ながらけっこう流暢に話しているのでした。相変わらずお気楽な性格だなあ、と、目覚めたときひとり苦笑してしまいましたが、こうなったら正夢になるよう、前進あるのみ!
■第685回 深きsoulのソウル 3
かくして、私の“焼肉”“整形”“反日”という、韓国に関する恥ずかしいくらい貧相なイメージは、様々な角度から覆されたのでした。
初日に訪れた精進料理のお店のレジ横で求めたレシピ本を改めて見てみると、すぐに他の同じ類いの本とは大きく異なっていることに気づきました。お寺ごとのお料理が美しいレイアウトで紹介されているだけでなく、お寺での鉢盂供養のようすや境内の殿や灯籠について、また周辺の環境などの説明を通してそれぞれの仏教理念がどう料理に反映しているかが、写真と文章で詳しく綴られているのです。料理やお茶を通して、和尚と村民がどんな風に過ごしてきたかなども紹介されています。
日本語の訳も素晴らしく、いわゆる外国のものを翻訳の専門家ではない現地の方が訳したようなものとはまったくクオリティーが違います。みると、日本語に訳された方は慶応義塾大学の文学部を経てエジンバラ大学の修士も卒業され、数年前からソウルで執筆、翻訳活動を行っていらっしゃるという、しっかりとした経歴の専門家でした。
「食事で治らない病気は医者にも治せない」といわれるほど、医食同源の根づいている韓国。私たちが伺ったお店のオーナーであり、この本の著者でいらっしゃる金演植さんは、はしがきを「本書は、現在に至るまでの約35年間、私が全国の名刹を尋ねて老僧の話を記録し、それをもとに再現した精進料理を紹介しつつ、寺を取り巻く環境と食との結びつきを吟味したいという意図のもとに記した紀行である。心身を健やかにしてくれる精進料理が、仏門にのみ限られたものではなく一般の人々も広く親しむことのできる大切な文化として根を下ろし、また塞いだ心を貫く一陣の風のごとく、多くの皆さまの記憶に末永くとどまることを願う」という文章で結んでいました。ふたつめの文中の“精進料理”を“芸術音楽”に、“仏門”を“専門家”に置き換えても、まったくそのとおり当てはまります。
私たちは滞在中、精進料理や焼肉、マントゥ(餃子)やカルグクス(うどん)、豚の豚足など屋台のB級グルメや、ザクロ100パーセントの絞りたてジュース、伝統茶などをあれこれ味わいました。32センチもあるソフトクリームにも挑戦しましたし、韓国を訪れたニューヨーカーたちが絶賛を寄せる、モロッ
コ風サンドイッチのお店に繰り出したりもしました。たくさん運動しているとはいえかなりの量を食べているな、という実感と満足感がありましたが、帰国後体重を量ってみたらほとんど増えていませんでした。
仁川空港に向かう時、チェックアウトしたホテルの最寄り駅で老紳士が声をかけてきました。「日本へ帰るのですか?」「はい、そうです」「空港へ行くのですね。仁川ですか」「はい」老紳士は母が韓国語を理解できると分かって親しみを抱いてくださったようで、こんどは日本語で「韓国は…何が良かったですか?」と尋ねました。母が何か言いたそうにしていたのですが、私は間髪入れずに「人です。とにかく、韓国の人がとても親切で感激しました」と答えました。その瞬間、老紳士の眼の表情が変わったのが見て取れました。「どうもありがとう…感謝します」そして、ご自身が日本のあちらこちらに滞在していたこと、色々な仕事をしたことなどを話し始めました。
母がおずおずと切り出しました。「お歳を伺ってもいいですか?」「歳は記憶していないのですが…産まれたのは1930年のようです」ユーモアたっぷりの受け答えといい矍鑠としたご様子といい、とてもそんなお歳にはみえません。「人情に触れるのも旅のよい思い出になるものですからね。これも何かのご縁、私がここから空港へご案内しましょう」そんなお手数をかけては、と遠慮しようとすると「いいのです。人の役に立つことができたら嬉しいんですから」そうおっしゃると、杖をついてはいらっしゃるとはいえ、迷いのない足取りで的確に案内してくださいました。
そして空港行きの鉄道の改札口にくると、「この先のエスカレーターの下がホームです。そこに仁川空港行きの電車が入っていますからそれにお乗りなさい」「本当にありがとうございました。なにかお礼ができれば良かったのですが…」私がそういうと老紳士は「では、もし東京で私をみかけたら、その時はにっこり笑いかけてください」と言って微笑みました。
成田までの機内で、ずっとこの国の人たちの慈悲深い心に感謝していました。深くも温かい、素晴らしいソウル(魂)に、たくさん出会えた旅でした。隣の座席から、母も同じ思いでいるのが伝わってきました。
(深きsoulのソウル 完)
■第684回 深きsoulのソウル 2
特に美味しいものが食べられることを期待していたわけではありませんでしたが、どんな食材もとても丁寧に調理されているのには感心しました。ほとんどの料理は味付けが優しく、また他のアジアの国々に比べて化学調味料の使用も少なくて、素材の自然な味わいが生かされていたことは、韓国料理は辛くて味つけが強い、というイメージがあっただけに意外でした。ティータイムや食後に、伝統茶とともに出してくださる韓国の典型的なスイーツ“油菓”も、甘みが控えめで油っこさをまったく感じません。かといってもの足りないということもなく、甘みのある伝統茶にぴったりと絶妙なバランスで、洗練されている印象さえ受けました。
この国では、外食が続いても野菜の摂取不足になる心配は少ないのではないでしょうか。地元の野菜だけでなく、エゴマや豆乳、黒豆やクルミなど身体にいいものが使われる料理も多く、高級なお店だけでなく下町の屋台風の店構えのところでも、おかあさんがステキな手さばきで次々に包むマンドゥ(餃子)の美味しいことといったら!カルグクスというあっさりしたスープの中に麺やマンドゥの入ったものも食べたのですが、焼肉のコース料理のように値の張るようなものよりも、そんな庶民の味にこそその国の食のレベルが垣間見えたりするものです。
でも、もっとも強く感激したのは食べ物ではありませんでした。それは、韓国の“人々”にでした。
良くも悪くも、体裁や“人にどう思われるか”を世界一気にする国民性ではないかと思われる日本人と違うのは当然としても、とにかく皆がおおらかで気取りがなく、さらにとても親切なのです。例えば、街中で行き先が分からないような様子を見て取るとすぐさま声をかけてくれて、「では、私も一緒に行きましょう!」と、案内してくださったことが、短い滞在中何度もありました。
また、食堂で母が韓国語で注文すると、すかさずとなりのテーブルから「どうして話せるの?」「どこで勉強しているの?」と矢継ぎ早に質問が…。母が、近所の韓国人留学生による小さなサークルで学んでいる、答えると、今度は「まぁ、えらいわ。なんて素晴らしい方でしょう!」と、感激していることを隠そうともせず、涙を浮かべんばかりになって喜んでくれるのです。
別の日に、仁寺洞のホテルの近くにある韓国伝統の陶器店の老舗で買い物をしていた時のこと。果敢に(?)値切る母に対して、嫌な顔ひとつせずにこやかに対応してくださった店のご主人は「日本の、どちらから?」「娘は東京の近く、私は仙台というところからです」すると、とたんに顔を曇らせて「ああ、あの大きな災害があったところですね。津波の被害は大丈夫だったのですか?」と心配してくださいます。「私たちはこんなに近くにいて、共感できることも助け合えることもたくさんあるはず。なのに、政府の思惑やらのお陰で仲良くなれないのは、本当に残念なことですね」ご主人は私たちの買った茶碗を包む手をいつしか止め、心からそう話してくださいました。
出発前、韓国フリークの友人が「韓国の人って、おせっかいというか、おしゃべりが好きでにぎやかというか…。なんだか関西の人に近いような感じなのよ」と、好意をこめて教えてくれました。確かにそんな感じがしないではありません。でも、何かそれとはまた違うものも感じていました。私のよく知っている何かに、もっと似ている。何だろう?
それが何なのか分かるまでに、大して時間はかかりませんでした。こちらが分かろうと分かるまいと一生懸命話しかけ、何か役に立とうとしてくれる親切な人々。豊かな食文化やレベルの高い工芸品の発展の奥に潜む、深い支配の歴史。それなのに、大陸的なおおらかさでよそ者にも心の中をそのまま見せてくれるような親しみをもって接してくれるその感じは、私がハンガリーに留学した時にブダペストの人々から受けた印象そのものだったのです。
韓国を一度訪れて、すっかりファンになってしまう人たちの気持ちが、分かる気がしました。韓国の人々は私たちの持っていないものをたくさん持っているし、またその逆もあるのだと思うのです。ということは、タッグを組めたら最強のコンビになれる、ということ!…陶器店のご主人の「仲良くなれないのは、本当に残念なことですね」という言葉が、何度も頭をよぎりました。
(深きsoulのソウル 3に続く)
■第683回 深きsoulのソウル 1
「美奈ちゃん、お願いがあるの」母にはめずらしい切り出し方でした。「なあに?」「一緒に韓国にいってくれない?」
10月上旬だったと思います。私から旅のお誘いをすることはあっても、母から、しかも海外へのお誘いを受けるのは初めてのことでした。母が3年ほど前から韓国語を勉強しているのは知ってはいましたが、今までその国の名前が行ってみたい国にラインナップされてはいなかったので、やはりちょっと意外でした。トランジットで仁川空港に行った時も、ここも旅行したいわね、という話にはなりませんでした。「いいけど…なんでまた、韓国なの?」
深い歴史と関わり合いがありながら、国交関係の現状は穏やかではない韓国と日本だけど、行ってみないとわからないことが必ずあるはず。自分の目で韓国を見て、何を思うか、感じるかを試してみたい…“韓国”を体験したい、というのが母の希望でした。それは、かねてから私も思っていたことでしたし、そんなことで少しでも親孝行になるのなら望むところです。11月の新潟でのリサイタルのあと、3泊4日で行くことに決まりました。宿は、私たちの旅行に一番適切と思われるところを母が検討して予約し、航空券の手配は私がしました。
当日。飛行機に乗ってしまえば、あっけないほどすぐに到着です。ゲートに降りて入国審査をすませると、母は勝手知ったる…という様子で、ずんずん歩いていきます。「市内行きのバスに乗るのよね。乗り場、わかるの?」「わかるわかる。そこを出ればもう目の前なの」母はそうとう予習をしたらしく、バスターミナルの形状や目指すバスの番号や乗り場までも、ほぼ把握しているようでした。
バスからホテルへの移動中、近代的な街並と紅葉が目に入ってきました。日本とほとんどかわらないような風景でした。母が選んだ仁寺洞のホテルにチェックインするも、スタッフの方の日本語が上手でびっくり。部屋で小休止したあと、早速周辺をぶらぶらすることにしました。
街は人であふれかえっていました。カップルや女の子同士、親子が仲良く手をつないであるく姿が多くみられます。甘いものやら揚げ物、焼き物、果物などの屋台が数えきれないほどでていて、みんな好きずきに食べたいものを求めてはその場で食べたり、歩きながら食べたりしています。にぎやかなのになぜか喧噪という感じはなく、かわりにリラックス感があるのが印象的でした。
私たちは街をくまなく歩き回り、韓国伝統茶がいただけるお店で一休みしながら、買い物をするお土産屋さんや夕食をとるお店を見定めました。せっかくなので、韓国ならではのきちんとした郷土料理を食べてみよう、ということになりました。母が選んだのは、精進料理の老舗でした。
細い路地をさらに奥にはいったところの家屋。靴を脱ぎ、奥のテーブルに案内されたのですが、そこからはもう、驚きの連続でした。肉、魚はもちろん卵も不使用なのに食材の種類がとても豊富で、それぞれが違った味付けになっています。目にも身体にも優しい心づくしのお料理は、とても数えきれないほどの品数です。贅沢なものはありませんが、お米のとぎ汁や豆の煮汁、どんぐりの粉やなども上手に使われ、丁寧に味付けされて、どれも木をくりぬいて作られた器に美しく盛りつけられています。お箸も木ならスープをすくうのも竹杓子。気づいたら、チゲ鍋の鋳物以外、食べ物や口に触れるものはすべて自然の素材でできていました。
食前に供された味わい深い植物の発酵飲料、食中にいただく温かいはす茶、食後の油菓と一緒に出されたニッキのシロップ…。飲み物もそれぞれに素晴らしく、満足感に満たされて、お酒が飲みたいという気持ちがまったくおこりません(実際、この旅行中には一滴のお酒も飲みませんでした)。
「すごいね」「美味しいね」感心がいつのまにか感動になって、気づいたら涙ぐんでいました。「わたし、お料理に感動して泣いたの、初めて」私がそう言うと、母も目を赤くしながら「奥が深いわね。こんなに素晴らしいなんて、想像していなかったね」オンドルで温められた床にも癒され、幸せな充実感に包まれて初日を終えたのでした。
(深きsoulのソウル 2 に続く)
■第682回 音も口ほどにものを言う
私ごとですが、一週間前…リサイタルの前日に、誕生日を迎えました。半世紀を生きたことになるその節目のその日、誰にも会わずお祝いの乾杯もせず、ひたすら翌日の本番のためにピアノに向かい、集中力を高めるべくお坊さんのように勤勉な一日を過ごしたことは、すでにいい思い出になりつつあります。
実際に人と会うことはありませんでしたが、お祝いのお花が届いたり、予想外にたくさんの方からメールやSNSなどでメッセージをいただけたので、思ったよりもさびしいと感じずにすみました。何より、ゆっくりショパンと向き合って過ごせたのですから、それはそれでよい誕生日だったと思っています。
今年、10代の頃からずっと憧れてきた、ショパンの最高傑作の一つ『24の前奏曲』を3都市で演奏できたのは、本当に幸せなことでした。ただ、回を重ねるほどに「今度はもっとよく弾きたい!」という気持ちが増すのは、我ながら困ったことです。いずれまた、必ず挑戦したいレパートリーです。
それにしても、ものごころついた頃からピアノをひたすら弾き続けてきた、あっという間の半世紀でした。これだけやってもまだまだ足りないし、弾きたい作品が次から次に出てくるのは嬉しいような困ったような…。でも、勉強は苦手ですが、音楽の勉強はまったく苦にならないのは、救いです。嫌なことや悲しいできごとがあったとき、いくらお酒をのんでも気持ちの乱れは整いませんが、美しい音楽を聴くと心が落ち着きます。ピアノに出会っていなかったら、そしてこの道に進んでいなかったら、いったいどうなっていたことでしょう。
来日アーティストにキャスターが「あなたにとって音楽とはなんですか?」と尋ねているのを見かけるたび、そんな質問をされたらとっても困るなぁ、と思います。みなさん「音楽は自分の人生そのもの」とか「水や空気のように、あって当たり前な存在」とかお答えになっているけど、私はどんな言葉でも言い尽くせそうにありません。
果たして言葉は何よりも的確に感情を伝えられるものなのでしょうか?私はそうは思えないのです。言った言わないは喧嘩のもとだし、顔をみることなく文面だけで気持ちを伝えるのは、なんとも難しいものです。
ハンガリーの作曲家、クルターグ・ジョルジュ(ハンガリー語は姓名が日本語と同じ並びなので、クルターグが名字になります)が1990年に書き上げた「言葉とはなに(Mi is a sz?)」という作品があります。晩年失語症に苦しんだアイルランドの劇作家小説家でノーベル賞も受賞しているサミュエル・ベケットの文章と、交通事故で失語症になった歌い手モニョーク・イルディコーにインスピレーションを得て書かれた作品です。ハンガリーで、まさにモニョークさんの歌で聴いたことがあります。
わかりやすいメロディーらしきものはなく、歌い手は時にどもりながら、語ったり、悲鳴のような声をあげます。その間、伴奏のピアニストが一本指で演奏し、音のきっかけを与える…という独特の演奏スタイルは、聴き手にかなりの緊張感を与え、自ずと何かを考えさせます。言葉にならない、言葉。声にならない、声。歌にならない、歌。ところがそこには確かなる音楽があり、雄弁なメッセージがあるのです。ショッキングと表現した方がいいような、貴重な音楽体験でした。美術や音楽にはたくさんコンテンポラリーなもの(いわゆる“現代アート”)がありますが、このように人の感情に介入して魂をゆさぶる、強いメッセージを持っているものはその中にほんのわずかしかありません。
「偉大な音楽は常に、まず感情からおこるものでなければならない。知性はその次だ」モーリス・ラヴェルの言葉です。音楽に大切なのは知性よりも感情だということに、異論はありません。いいえ、音楽のみならず、人生にとっても同じかもしれません。
“目は口ほどにものを言う”ではありませんが、多くを伝えるまなざしのように、音でもっとさまざまなことを伝えられるピアノ弾きになりたい…。そんなことを夢見た誕生日、“人間だけが、眠らないで夢をみる”という何かの広告のキャッチが、妙に心に残りました。
■第681回 はらこめしが教えてくれたこと
県外に住んでいて、「はらこめし」と聞いて郷愁を感じない宮城県人は、まずいないことでしょう。鮭の身と“腹の子”、つまりイクラを使った、目にも鮮やかな郷土料理です。
はらこめしの本場、宮城県亘理町によると、その由来は“藩制時代に仙台藩主貞山公(伊達正宗公)が貞山堀臨検の際に、亘理藩の荒浜漁民が元来漁師料理として食していた鮭の腹子をご飯に炊いた「腹子飯」を献上したところ、貞山公はことのほか喜び、側近へ吹聴したのが、世に珍重されるに至った始まりと伝えられている”とのこと。
町内にははらこめしを提供する20店もの飲食店があるといいますが、その旬は、まさに今。こだわっているお店では、腹子イクラはもちろんメスのものだけど、身の部分はオスを使うのだとか。メスの身は卵のために栄養を取られ、痩せて味が落ちているからなのだそうです。鮭の身を、醤油、みりん、酒など(家庭によって、砂糖や生姜も使うところも)の割り下で煮て下ごしらえし、その煮汁を米に加えてごはんを炊きます。鮭は、大きな身は策切りにしてトッピング用にし、骨や皮の近くの身は丁寧にほぐして、ごはんに加えます。
枯れた落ち葉の色を思わせる、醤油味のごはんの上にのった薄紅色の鮭のスライスは、紅葉のよう。そのあいだにキラキラと赤く輝くイクラは、まさに太陽にきらめくナナカマドの実のように美しい表情です。新米の季節、シンプルに白いごはんでその香りや甘みを味わうのもいいのですが、どんぶりの上のかくも絶妙な“景色”を愛でつつ、秋を心ゆくまで堪能するのも、また格別なのです。それは、やがて来る厳しく長い冬を前に、気落ちをひきしめつつも宮城県人が楽しみにしている、郷土の味覚です。
つくづく、料理は小さな宇宙だと思います。地球(大地、海)の恵み、そこに生きる人間の知恵、歴史や文明などが、その一皿に集約されているのですから。芸術家たちのなかには、決して経済的には豊かでなくても、食べるものにはこだわりをもっていた人が多いのは、なんだか分かるような気がします。
「どうして東洋人の私が西洋の音楽をするのか。その意味はあるのか、あるとしたらどこにあるのか」こんなことをずいぶん長いあいだ、考えては悩んできました。でも、歳を重ねるにつれその答えはクリアになりつつあります。
そもそも、西洋、といってもラテンとジャーマンは違う。いいえ、ラテンでもフランスとスペインでは違うし、もっと言えば、同じ国のなかでもバスクとカタルーニアは、違う。むしろ、近しいほどに相容れなかったりする傾向は、宗教戦争などを考えても明白なところです。
一方、美味しさ、美しさ、楽しさ…国籍や民族が違っても、分かりあえるものはたくさんあります。つまり、私たちは違っているからそれぞれ存在価値があるし、違っているのに共感できるからこそ、素晴らしいのです。ベートーヴェンにはオランダ人の、ラヴェルにはスペイン人の、ショパンにはフランス人の血が混ざっています。彼らが奇跡的な発展性を発揮できたのは、そのことと無縁ではないでしょう。文化も然り。混ざりあって、進化してきたのです。
今日はらこめしの画像を見て、それを再認識しました。違う部位を用いて、それぞれを生かす調理法をほどこした海の恵み鮭と、畑の恵みのお米、という異素材の組み合わせ。もっちりしたごはん、ふんわり柔らかい鮭の身、プチプチしたイクラ…それぞれの食感のコントラスト。そこにごはんの薄茶、鮭の薄紅、イクラの緋色、といった色合わせの妙が加わるのですから、これはまさに究極のアンサンブルではありませんか!
答えは、こうです。西洋同士だって、異なるところがある。西洋と東洋だって異なるところはもちろんあるけど、洋の東西を超えて共通することがある以上、それらを融合させたり、対比を楽しんだり受け入れたりするところに、芸術が育つ。だから、異文化に挑むことはなんら無意味なことではないどころか、むしろ意味深いことである。
嗚呼、理屈(屁理屈?)をこねていたら、ますますお腹が空いてきました。そうなんです、なんのかんの言っていますが、要するに、いますぐはらこめしが食べたい気分になっているだけなんです。
■第680回 急ぐのは悪魔のしわざ
このところバタバタして、なかなかゆっくり料理する気持ちと時間の余裕がないのですが、料理に関することを考えるだけでも気分転換になる性分。レシピ本を眺めるだけでも幸せな気分になります。
日本は流行り廃りの激しいところがあって、食べものはもちろん調味料ひとつとっても、突然ヒマラヤの岩塩が台頭してきたり、食べるラー油が異常なブームになったり、塩麹がはやったと思ったらいつのまにかレモン塩になったり…と、あまりにくるくると流行が変化するので、もう何がなんだかわかりません。
実はレモンの塩漬けは、塩レモンなるものが知られていなかった3年ほど前から、自家製を仕込んでいます。モロッコ料理が出てきて、そこここでタジン鍋を見かけるようになった頃だったでしょうか。ロンドンで出会った中近東の料理の美味しさが忘れられず、これまで折に触れて中近東“もどき”な料理を作ってきました。タジン鍋も欲しいのですが、どうも場所をとることが気になって未だに購入には至っていません。それより先に、燕三条あたりで作られている、大きな蒸し器が欲しい、ということもあります。その他に、バスク地方のピルピルというタラの料理を作るための銅製の鍋も心惹かれるし、トルティーリャを焼くための鉄板も欲しい…。
何でもそうかもしれませんが、趣味というのは道具に凝りだすと大変なことになってしまうものです。短くない年月を生きてきたお陰でさすがにそのあたりの分別はつくようになってきたのか、あまり多くの調理器具が家を占拠するのはスマートではないから、と、ブレーキをかけられるようになりました。
特別な道具を使わなくても豊かなレパートリーは楽しめるはずです。買い足すのはなるべく食材だけにして、いろいろな家庭料理を楽しみたい…というのが、いつのまにか自分のポリシー(?)になってきました。
一番好きなのはもちろん和食ですが、今は南インドやペルシャの料理に心惹かれています。いずれも、肉や魚よりも野菜や豆をたくさん食べられて、その上ステキなスパイスが用いられるのが魅力です。特に中近東は、豆やヨーグルトの他にアーモンドやカシューナッツ、クルミといった、私が愛してやまない種実類が多く料理に使われるばかりか、ザクロやプルーン、イチジクといったフルーツも、活躍します。
これは、ナッツとフルーツがあればご機嫌な私には、こたえられません!お鍋同様、レシピ本もあまり増やしすぎなうようにしてはいるのですが、我慢できずに先日、ついにペルシャ料理の本を手に入れてしまいました。
ドライフルーツとナッツのサラダ、プルーンと野菜とラム肉の重ね煮、白身魚のオレンジサフランソース添え、ヨーグルトと肉団子のコレシュ(*煮込みのこと)、レンズ豆と麦となすのペースト…。ため息がでるほど食べてみたい、作ってみたいと思うメニューが、ずらりと並んでいます。
そんな夢のような目次のメージをめくると、はじめに、という項目になって、そこにはペルシャ料理の特徴が7つのトピックで紹介されていました。始まりは紀元前であることやスパイスを穏やかに用いること、バラから抽出されるローズウォーターをスイーツや紅茶によく入れることなどが紹介されているのですが、その最後の7つめに書かれている言葉にドキッとしました。
そこには、『急ぐのは悪魔のしわざ』とありました。料理を作るにも食べるにも、決して急ぐことなく、ゆっくりと…が、彼らの美学だというのですが、それは私がしばしば生徒さんにアドバイスしてきた言葉そのものだったのです。「一週間で弾けるようになろうとしなくてもいいんですよ。ゆっくり、ゆっくり、ただしできるだけ丁寧に…。急ぐのは悪魔の“そそのかし”。そんなものには惑わされないようにしましょう」と。
そういえば、最近モロッコを旅してきた友人も、その時間の流れのゆったりと優雅なことに感銘を受けて帰り、人生観が変わったかも、なんて言ってたっけ。急ぐことなく、ゆっくりと…。それは、来週の誕生日で半世紀を生き抜いてきたことになる私への、天からのお祝いのメッセージかもしれないな、と、ふと思ったのでした。
■第678回 シネマの秋
金木犀の花は、夕暮れ時にいちばん強く香るような気がします。風に舞う落ち葉、黄金色に輝く田畑、目にしみいるほどに鮮やかな空の色。自分が産まれた時期だからかもしれませんが、やはり秋が一番好きです。
食欲の秋、収穫の秋、読書の秋、芸術の秋…。さまざまな秋がありますが、そのいずれに他の季節を当てはめてもピンときません。秋じゃないといけない何かがあるのでしょう。ふと冷たい風が吹いて身震いしたり、勝ち誇ったように輝く太陽の光に戸惑ったり。秋は、感性が揺さぶられるような瞬間が多いように思います。月夜をのんびり味わいたくなったり、夜更けまで読書をしていたくなるのも、この季節。
映画をゆっくり楽しみたくなるのも、私にとっては秋です。夏は子供たちであふれる大型映画館も、さすがにこの時期の平日となると静かです。「映画は娯楽!ジェットコースターみたいに、ハラハラドキドキを楽しめれば、それで満足」という、アメリカ映画ファンもいますが、私は感情移入したり、疑似体験をしたりしながら観賞して、余韻までじっくり噛み締められるような作品が好きです。
カメラワークや特撮に頼りすぎて人物描写が浅かったり、肝心のストーリーが弱かったり、役者さんの演技よりも特殊メイクが話題になるような映画は、何を楽しめばいいのか分からなくなってしまいます。アメリカも、往年のハリウッド映画には俳優さんといい音楽といいストーリーといい、今でも…そして、何度観ても新鮮さが衰えないような傑作がたくさんありましたが、最近はわざわざ劇場に足を運んで観にいきたい、と思うものがとても少なくなってしまいました。トシのせいなのかもしれませんが。
類は友を呼ぶのか、私の周囲にもそんな友人が少なくなく、アメリカ映画の話になると、たいてい皆同意見になります。一方、ヨーロッパ映画やアジア映画、最近ではインド映画にもとても素晴らしいものが増えていて、嬉しい限りです。
先日も、友人たちに誘われて久しぶりに映画館に行きました。『バルフィ!人生に唄えば』というインド映画でした。昨年の『きっと、うまくいく』も3時間でしたが、こちらもたっぷり2時間半。でも、時間を感じさせることなく、まったく飽きさせない構成は見事としか言いようがありません。
あまり内容について触れるのは好きではないのですが、ほんのちょっとご紹介すると…、『雨に唄えば』など古き良き時代のハリウッドミュージカルのパロディーや、『アメリ』の名シーン、はたまた『プロジェクトA』のアクションシーンや、北野武監督の『菊次郎の夏』など世界各国の名作へのオマージュが盛り込まれていて、映画ファンはみんな、それぞれにこっそり心のなかで「!」を楽しむことができます。映像も洗練されているし、何と言っても役者さんのみなさんの演技が素晴らしいのです。
帰り道、友人たちと「いい映画ってなんだろう」という話になりました。「(いい映画を観ると)終わった後、誰かに話したくなるよね?」「そうそう。なにかの行動にかき立てられるようなパワーがもらえたり、ね」「う〜ん、いいコンサート、もまったく同じだよなぁ」語りあいながら、こんなことを共有できる友人がいることを心から幸せに思うのでした。
ところで、映画は米語で“ムービー”と言いますが、生理的にどうもしっくりきません。映画は“シネマ”と言いたい…。ムービーというと、ただ「動くもの」「動画」というイメージなのですが、シネマは「映画作品」というニュアンスを感じるのです。同じ英語圏でも、イギリスでは映画をムービーと言わず、フランス風にシネマと言います。ところが、調べてみたら最近ではアメリカでも、アート的な作品は一般の映画“ムービー”と区別して、“シネマ”という傾向があるとか。案外、アメリカ人も感じていることは同じなのかもしれません。
■第677回 ブエノスアイレスへの道 其の六
「今度、アルゼンチン音楽を弾くのよ」と話すと、かなりの確率で「タンゴを弾くの?踊ったりは?」という、冗談とも本気とも判断しかねるようなリアクションをいただきます。そのたびに「一般的なタンゴ音楽ではなくて…」とお答えすることになるのですが、そうすると相手の方はたいてい「?」といった表情になります。
無理もないことです。それだけアルゼンチンタンゴは広く知られているということでしょう。でも、別の見方をすると、それはアルゼンチンにはタンゴ以外の音楽のイメージがあまりない、ということにもなります。
「じゃあ、どんな音楽なの?」と聞かれて、何度説明に窮したことか。そもそも、音楽を言葉で表現することほど難しいことはありません。美しい音楽だと言っても、相手の方が想像する美しさとは違うでしょうし、新しい感じの音楽だと言ったらコンテンポラリーな無調性音楽を想像されてしまうかもしれません。しかも、今回は取り上げませんが、ヒナステラのようなまさにコンテンポラリーな作曲家もいるのです。
「ええっと、あのね。今回弾く曲には、確かにタンゴをルーツにしているものもあるけど、純然たるタンゴミュージックというわけではないの。新鮮な感じはするけどどこか懐かしい感じもあって…情熱的だけど、ただ明るいというわけではなくて、ね。味わい深さはあるけど、分かりにくいっていうことでもなくて…」こんな七面倒くさい説明を聞いて、はたして「ぜひ聴きたい!」と思っていただけるかどうか。
難しいのは、説明だけではありません。同じドイツ語でもドイツとオーストリア、スイスではそれぞれアクセントが違うように、同じクラシック音楽でも、アルゼンチンの音楽・・・特にピアソラやブラガートなどの作品・・・は、これまで私が学んできたヨーロッパのそれとは、明らかに違いがあるのです。例えば、四拍子。一般的にヨーロッパでは一拍目と三拍目を“強拍”として重みを感じ、逆に二拍目、四拍目は軽やかさをもってとらえる傾向があるのに対して、アルゼンチン音楽では他のポピュラー音楽のように、四拍目に一拍目以上に重みを感じて演奏するのです。
タンゴを起源としている音楽独特のグルーヴ感、というのでしょうか。それをもって演奏しないと、アルゼンチン音楽らしいニュアンスが充分に表現できないのです。永い年月をかけて“ヨーロッパ流音楽的発音”を身につけてきた私にとって、四拍目の重み、など独特の“グルーヴ感”を身体の中に入れ込むのは、想像以上に大変なことでした。役作りのために、京都弁やクイーンズイングリッシュの発音やイントネーションを徹底的に仕込まれる役者さんの苦労が、分かる気がしたほどでした。
自分の演奏曲だけを勉強していたのでは事足りないと思い、一日中インターネットラジオでアルゼンチンのタンゴチャンネルやスペイン語を聞いたりアルゼンチン文学を読んだり、他の作曲家の作品を譜読みしたり…と、思いつく限りのことをしました。少しずつ“グルーヴ感”が身体に入ってくるにつれ、アルゼンチン音楽らしさを増していくのが実感できたのは、救いでした。
取り組むにつれ、さらにその豊かな魅力が感じられるようになりました。アルゼンチンの音楽には、民族の誇りや日本の“粋”にも通じるような美意識が溢れています。スペイン音楽の影響を受けながら追求された独自のスタイルはたいへんに洗練されていて、「どうだ」という自信に満ちています。
同時に、「どう弾いたらいいのか」という迷いはあっさりと拒絶されるような強さも感じられます。「こう弾きたい」「こう弾くぞ」というはっきりとした意志をもって臨まないと、その真髄に到達することができないのです。
私の挑戦は、みなさまにどのように受け止めていただけるのか。7月4日の第一弾に続いて行われる10月10日の第二弾では、もっともっとアルジェンティーナに近づけるよう、前進あるのみです。
(*ブエノスアイレスへの道 完)
■第676回 ブエノスアイレスへの道 其の五
それからほどなく、彼女と引き合わせてくれた共通の知人から、デュオ・エビータDuo E-vita旗揚げ公演のコンサート会場をおさえたという連絡が入りました。恵比寿のアートカフェという、ライブハウスとしても場所を提供しているカフェレストランでした。嬉しかった反面、日程を聞いて不安になりました。私のオールショパンプログラムのリサイタルから、たったの3週間後だったのです。
ところで、私はどうも他の人から、なんでもテキパキとこなすようなイメージにとられることが多いようです。ひとりでの海外旅行もふと思いついて実現させてしまっているように見られることもあるのですが、実際はさにあらず。時間をかけてああでもない、こうでもない、と、日程やら航空会社、宿、移動ルートなどの検討にもたもたするし、石橋を叩いても渡らないような、慎重というよりも臆病なところがあるのです。
音楽的なことに関しては、いっそうその傾向は強く、消化するのにはたくさんの時間が必要になります。当然、譜読みも速いほうではなく、人一倍時間をかけて、なんとか人並みにもっていくタイプです。ましてや、アルゼンチン音楽はほとんど未知のレパートリー。彼女は10数年前にピアソラの作品集をレコーディングして以来、しばしば演奏しているのですが、私は今まで弾いたことがあるのはピアソラのリベルタンゴくらいで、他はまったく初めて譜読みする曲ばかりなのです。
そんな私が、デビュー公演がリサイタルの3週間後と聞いて不安を感じないわけがありません。様々なことを次々に決めていくスキルも、私は残念ながら持ち合わせていないのですが、幸い相方の植草さんがそれをカバーする勢いでどんどん話を進めてくれました。彼女のだんな様がまた、そういったマネージメントをしなれていらして、私はあれよという間にいつのまにか様々な段取りが組まれていくのに、目を白黒させながらついていくのが精一杯でした。
ほどなく、自分のリサイタルの準備と平行して、慌ただしい準備の日々が始まりました。フライヤーの制作はどうするか…デザインは誰に頼むのか、どのようなコンセプトを打ち出すのか、また、ロゴを作った方がいいかどうか。また、それに伴う写真撮影の段取りとその打ち合わせ。プロモーションビデオ制作とその場所、日程について。その他、肝心のデビュー公演でのプログラムはどうするのか。そして、二人のリハーサルの日程調整やデザイナーさんとの打ち合わせ、カメラマンの方の都合や撮影場所などのアレンジ、などなど。
それは、自分が大きな波に“乗っている”というよりも、“のみ込まれている”といった、なにか不思議な感じでした。気がつくと、プロモーションビデオ制作日は目の前。自分のリサイタルのためのフライヤー制作などの準備や練習に追われる中、その日を迎えることになりました。
それでも、勢いというのはコワいもので、録音はなんとか順調に終えることができました(録音も編集も、植草さんのだんな様が引き受けてくださいました)。動画は質の高いものが撮れないことから、写真をコラージュのように加工していく手法をとることになりました。フライヤーのための撮影やデザイナーさんとの打ち合わせもトントンと進んだのでいったん一区切りにして、私はショパンのリサイタルに向けてまた、照準をあわせていくことになりました。
とはいいつつも、選曲した作品のピアノパートはどれもかなり高度で、リサイタル終了後に取り組んだのではとても間に合わないと思われました。結局、スローペースの私がリサイタル後3週間後までにきちんとした形にするには、ショパンとそれらを平行して練習していかなくては間に合わない、という結論に至りました。
リサイタル前以上に、リサイタルの後、一般的なヨーロッパのクラシック音楽のそれとはまったく違う難しさを目の当たりにして、大変な苦悩をすることになるのですが、その時の私はそれがどれほどのことなのか、想像が及んでいなかったのでした。
(*ブエノスアイレスへの道 其の六に続く)
■第675回 ブエノスアイレスへの道 其の四
そのあとの約三時間は、またたくまに過ぎてしまいました。かつて彼女も私と同じように、アメリカのシンシナティというところに留学していたことは知っていましたが、なんと、あろうことに同じアパートメントに住んでいたことが判明したのです。しかも、同じ部屋に!
そこで私はやっと、ある記憶にたどり着くことができました。退去するとき、「美奈子ちゃんの部屋が空くなら、知り合いの日本人留学生がその部屋に入りたい、と言っているの。家具や食器なんかはそのままにしておいていいみたいよ。よかったね」と、友人に言われていたのです。
アメリカはヨーロッパと違って、家具付き、台所の一式付き、というアパートメントは一般的ではありません。仕方なく、ハンガリーで節約した分のお金をつぎ込んでひととおりをそろえたので、できれば無駄にしたくないな、と思っていた私は、それを聞いてとてもホッとしたのでした。その日本人留学生が、彼女だったのです。友人が彼女の名前を「いねちゃん(植草ひろみさんのニックネーム)」と、呼んでいたことも、ずいぶん後になって思い出しました。
その時私は、ほんのお近づきのしるしに、大好きなイラストレーター山田和明さんの絵葉書をお二人にプレゼントしました。いねちゃん、こと植草ひろみさんには可愛い小鳥とチェロと描かれている『カザルスに捧ぐ』というタイトルのものを、そして、今回のセッティングを買ってでてくださった元フジテレビアナウンサー横井克裕氏には、ラッコがバンドネオンを弾いているものを選びました。
怪訝そうに「どうして僕はラッコなの?」と尋ねる横井氏に、「このラッコの風貌というか、体型…に、なんとなく横井さんに近いものを感じたので」と、不躾にも正直に(失礼!)答えてしまいました。ああ、しまった、と思いつつ「ウサギがバンドネオンを弾いている『ピアソラのウサギ』っていうタイトルのもあったけど、それは自分用に買ったの。ピアソラは、来日したとき、聴きに行った思い出があって…」と話を変えると、いねちゃんが「ピアソラ?美奈ちゃん、彼の生演奏を聞いたの!?すごい、うらやましい!…私、ピアソラの曲をレコーディングしているし、ブエノスアイレスにも行ったのよ!」
それからは、アメリカで同じ部屋だったという奇跡的偶然すら、どこかに飛んでいってしまったと思われるほどの興奮状態で、アルゼンチンの話が続きました。彼女がブエノスアイレスに、ピアソラの無二の親友、ホセ・ブラガートに会いにいったこと。そこに、亡きピアソラの愛犬がいたこと。まだ出版されていないブラガートの手書き譜もたくさん持ち帰ったこと。私は私で、ピアソラの生演奏がどんなに素敵だったかや、タンゴの四拍目のバスの半音階上行型を弾くたび、ついつい気合いが入ることなど、話が止まらなくなってしまいました。
それから一ヶ月も経たないうちに、私は彼女の実家でピアソラやブラガートなどの膨大な譜面を、片っ端から初見で彼女のチェロと合わせていました。どれもこれも、もっと広く知られてしかるべき素晴らしい作品ばかりでした。そして、これはデュオを結成するしかない、ということになりました。「これはもう、運命ね!」二人のくちから、何度もその言葉がでました。
気づくと、とっくに夕飯の時間になっていました。なんと、6時間以上も夢中で話したり弾いたりしていたのです。そこで、彼女の知っている近所のイタリアンレストランで一緒に食事をとるも、話題はずっとアルゼンチン音楽とデュオのことでした。「デュオの名前、つけた方がいいよね」「うん、つけた方がいい」「何かイメージ、ある?」「う〜ん…」そんな会話がふと途切れたとき、彼女が小さな声である歌を口ずさみました。それは、マドンナが主演の映画『エビータ』の主題歌、“アルゼンチンよ、泣かないで”でした。
「いねちゃん、それよ!エビータ!!」「エビータ?」「うん!だって彼女、アルゼンチン女性のシンボルでしょう?でも、そのままだと平凡だから間にハイフンを入れてE-vitaにするとか。ほら、Vitaってイタリア語で“人生”じゃない?だから、E(いい)人生、っていう意味もかけて…」「Duo E-vita!いいね、それだ!!」
私は彼女からたくさんの譜面を受け取って、帰宅しました。その日はなかなか寝つけませんでした。
(*ブエノスアイレスへの道 其の五に続く)
■第674回 ブエノスアイレスへの道 其の三
そのウイスキーのコマーシャルをきっかけに、ピアソラは大ブレイクしました。もともとはバンドネオンのソロや、バンドネオンのはいるアンサンブルのために書かれた作品が、またたく間にチェロだけでなくフルートやヴァイオリンなど、ピアノの入る室内楽用にアレンジされ、楽譜売場にずらりと並ぶようになりました。ちょっとしたサロンコンサートなどではリベルタンゴが“ウケる”ということになって、私も何度となく演奏しました。
でもその頃の私は、ピアソラの世界に本格的に入り込むにはあまりにも慌ただしい毎日を過ごしていました。常に目の前のいくつかの室内楽やソロのコンサート(サロンだけではなく…)をかかえ、プライベートの生徒さんを多数教えながら母校での非常勤講師も務めていたのです(ついでにいえば、結婚もしていました)。そんな、海外旅行にでるのもままならないような月日が、どのくらい過ぎていったことでしょう。
その後離婚して、身辺の環境が変わり始めました。ソロアルバムをださないかという友人の後押しと、さまざまな素敵なご縁に恵まれてCDをリリースすることになったり、室内楽のコンサートが減ったかわりにじっくりとソロリサイタルの準備ができるようになったり。週に一回、仙台の生徒さんのレッスンと母校での仕事のために週に一度仙台に通うというペースは相変わらずでしたが、徐々に気持ちに余裕ができて、好きな料理が思う存分楽しめるようになったのは嬉しいことでした。ひとりで海外旅行に出かけるようにもなりました。
圧倒的に音楽家、演奏家の友人が多かったのが、いつのまにかそうではない友人のほうがずっと多くなりました。そして自ずと、彼らの声をよく聞くようになったのです。クラシック音楽は「やはり難しい」「知識がないと楽しめないというイメージがある」「曲がたくさんありすぎて、何から聴いたらいいのか分からない」というような…。
自分たち音楽家は当たり前のように知っている作品や作曲家も、場合によってはそうでない方の大半は知らないのだ、ということにも気づきました。私のやってきた、例えばバルトーク・チクルスのようなものは、どんなにか取っ付きにくい企画だったことでしょう。もちろん、演奏家である以上、新しいものやあまり知られていない作品もどんどん紹介していくという使命があります。
でも、もっとも大きな使命は、クラシック音楽をもっと多くの方にもっと好きになっていただくことであり、親しんでいただけるようにすることなのです。
そこで私は、お客さまに少しでも興味を持っていただけるように、リサイタルのプログラムをあるストーリーを設定して組み立てることにしました。また、“大人のための音楽塾”と称して、楽器が弾けない方やクラシックに詳しくない方でも楽しんで学んでいただけるような…いわば、「学校では教えてくれないクラシック音楽」の世界をお伝えする講座を企画したりもしました。
その後3.11が起こり、同時に私の仙台通いも終わりました。そして去年、ある知人から「植草ひろみさん、知ってる?」と尋ねられました。もちろん、名前は知っていました。でも、きちんとお会いしたことはありませんでしたのでそれを伝えたら「確か、彼女も(私と同じように)シンシナティに留学していたはず。震災復興のチャリティーも一生懸命取り組んでいるし、きっと通じるところがあるのでは?」それなら是非、一度三人で会いましょう、ということになりました。
やっとその日が来たのは、それから半年も過ぎた頃でした。その間、約束していた日の直前に植草さんのお父さまがお亡くなりになったり、いよいよ会えると思ったら当日になって今度は私が風邪で倒れてしまったり、と、タイミングがあわなかったのでした。
皇居近くのホテル内のイタリア料理店。迷ってしまったために時間に遅れそうになり、走って駆けつけたので、店内に案内されるや外の冷気との温度差で鼻水が出そうになり、慌ててバックからティッシュを取り出したその次の瞬間、ボーイさんが「こちらです」と、そのテーブルを示しました。もう二人とも着席していました。彼女を見た瞬間、私は「彼女を知っている」と思いました。いいえ、現実としては会ったことはなかったのです。でも、間違いなく彼女を知っている、と“感じ”たのです。それも、ずいぶん前から。
■第673回 ブエノスアイレスへの道 其の二
その頃私は、東洋人である自分が異国の音楽を学び、その世界で生きていくことに疑問と不安をいだいていました。たとえば、外国人が俳句を詠んでも、“外国人なのに”日本語が達者だね、とか、“外国人のわりには”いいセンいってるよね…など、条件付きの評価になりがちです。自国の言葉や文化によるものではない『西洋音楽』を弾くのが上手になったとしても、それはモノマネのようなものでしかないのではないか、と悩んでいたのです。
でも、そんな思いとは裏腹に、心惹かれる音楽はどれもそれぞれの国や民族に根ざしたものばかりでした。ポーランドのマズルカの哀愁。ハンガリーの農民歌の生き生きとした息吹。スペイン音楽の、粋で心躍るようなアクセントやリズム…。なかでも、バルトークのハンガリー、トランシルバニア地方などの民族音楽によるピアノ曲の数々には、心をわしづかみにされました。そこに、東洋のものとも受け取れるような親しみを感じたからです。
のちに、バルトークが演奏旅行に訪れた北アフリカのとある宿で、彼の故郷ナジセントミクローシュで祖母が口ずさんでいた、その土地に口伝えで伝承されている歌(他の土地の人は知り得ないような)に酷似したものを、現地の老婆が歌っているのを耳にします。そして「すべての民族音楽はその本当に深い、根底の部分でつながっているのではないか」と考えるに至りました。彼はそれを追求することを決意すると同時に、ハンガリーの民族音楽を極めていくためには、周辺のそれもくまなく調べる必要があることを感じたのです。
私が彼の作品の一部に、小節に似たメリスマの用方など、かつて長野県の山奥で歌われていた民謡に近いものを感じたのも、あながち間違いではなかったのかもしれません。日本の祭り囃子のようなリズムが登場するバルトークの作品『舞踏組曲』に出会ったとき、私は「ハンガリーのリスト音楽院にいこう」と心に決めました。そこで東洋や西洋といった区別や民族を超え、単純に“人として”西洋音楽に向き合えるような何かが見つかると感じたのです。
それから留学を果たし、ハンガリーの地方都市ソンバトヘイで行われているバルトークセミナーも受講しました。バルトークの権威であるピアニスト、ゾルターン・コチシュのマスタークラスでバルトークの『15のハンガリー農民歌』を弾いた際、彼が「彼女のバルトークは、日本人もハンガリーの民族音楽を
深く理解しうるといういい例だ」と、聴衆に向かって言ってくれたことはとても大きな心の支えになりましたし、自信にもなりました。
バルトークの音楽の探求は、留学時代のみならず帰国後も続きました。でも、気合いを入れてオール・バルトークプログラムを組んでも、室内楽も入れてのバルトーク・チクルスを企画しても、周囲の反応はいまひとつ。聞こえてきたのは「バルトークの音楽はわからない」「難しい」といった声でした。
ある程度、想定していたことではありました。でも、白状すると音楽家は「わからない」と言われることほど悲しいことはないのです。音楽は頭で理解するものではなく心や身体で感じるものですし、理解するより、共感し共鳴しあいたいものだからです。それは、人と人との関わりと似ています。お互いを完全に「理解した」と感じているカップルが果たしてどのくらいいらっしゃるのか。相手の思いがけない一面をみてさらに惹かれることは少なくありませんし、仮に頭で「理解」していても、心からの「共感」がなくてはどこか空しいものではないでしょうか。
私は、西洋東洋の壁を取り払ってくれたバルトークの音楽を、ただ好きになってほしかったのです。ありがたいことに、レッスンを通じて生徒さんとは共鳴しあうことができました。子どもたちはバルトークを大好きになってくれるのです。でも、ステージではその思いはなかなか成就せず、せつない“片思い”の日々が続きました。
そんなある日、ぼんやり見ていたテレビから流れた大手酒造会社のウイスキーのCMに、息が止まるほどハッとさせられました。そこには桐朋学園にもいらしてくださったことがある世界的チェリスト、ヨー・ヨー・マが映し出されていましたが、私が反応したのは彼ではなく、彼の奏でている曲の方でした。久しく聴いていなかったあのアストル・ピアソラの作曲した、『リベルタンゴ』。…ピアソラの生演奏を聴いて14年近くが経った、1998年のことでした。
■第672回 ブエノスアイレスへの道 其の一
「良いバイレ(踊り手)は、踊りが上手なだけではない。特別なアイレをもっているものです」ずいぶん前に、フラメンコの先生がおっしゃっていました。アイレとは、日本語には“空気、大気”とも“雰囲気”とも“気品”とも訳され、音楽用語としては“調べ”という意味ももつ、スペイン語独特な単語です。もしかしたら、今の流行語でいうところの“オーラ”というニュアンスも含まれるかもしれません。
スペインの音楽のもつリズムの“粋”に心惹かれ、それを身体で実感したい、とフラメンコを習っていたことがありました。言いようのない魅力に取り憑かれて留学した国ハンガリーも、スペインと共通するのはロマ族(ジプシー)の存在がその民族音楽や民族舞踏などに色濃く反映しているところです。
もちろん、ロマの音楽とハンガリーの民族音楽は完全に同じなわけではありません。でも、彼らが現地の音楽のテイストを自らのそれに盛り込んで、より高く評価される(=たくさんチップをもらえる)パフォーマンスを追求したのは確かですから、どこからどこまでがロマのもの、なんていう線引きをするのは限りなく不可能に近いし、案外不必要なことかもしれません。お互いに影響を受け合ったことは、事実なのです。
以前、「あなたの前世はジプシーです」と、ある方に断言されたことがあります。自分はまったく前世が何であったかを感じる能力がないのですが、無条件に心惹かれるものにそのテイストが含まれることが多いのは、あるいはそのせいなのかもしれません。
ハンガリー語も、摩訶不思議で愛らしい響きを持つ言語でしたが、スペイン語も好きです。イタリア語同様、音楽的リズムがあって、そのまま発音するだけでも歌のよう。サンフランシスコ、ラスベガス、ロサンジェルス…。アメリカで人気のあるこれらの地名はスペイン語だというのは、よく知られていることですが、外国におけるスペイン語の地名のなかで、私がひときわ魅力的に感じたのは、ブエノスアイレス…“良いbuenosアイレaires”でした。
実は、本当はフラメンコよりもタンゴを習いたかったのです。でも、タンゴはどうしても、男性と組まなければなりません(照れくさい!)。ひとりで練習するのも難儀そうだし、脚を強調するあんなセクシーな衣装はとてもとても着こなせません(どうでもいいことなのですが、脚は形といい短さといい、コンプレックスなのです)。
タンゴに興味を持ったのは、桐朋学園在学中のある日、ラジオから流れてきたアストル・ピアソラのバンドネオンに惚れ込んでしまったことが発端でした。それは、とてつもなくせつなくて情熱的な調べでした。バンドネオンという楽器に、これほどまでの豊かな表情があることに衝撃を受け、すっかり魅了されてしまったのです。ラジオの前にフリーズしたように釘付けになって、全身で聴き入りました。
しかも、そのピアソラが近々来日するというではありませんか!これはぜひとも聴きにいかなければ…。クラシック音楽以外のコンサートにいくなんて、産まれて初めてのことでした。友人たちはピアソラなんて誰も知りませんでしたし、誘うのも気が引けたので、自分ひとりでいくことに決めチケットを予約しました。ピアソラの二回目の来日で、私が20歳になったかならないかの頃でした。
会場のお客さまは中高年のおじさま、おばさま方がほとんどで、20歳の乙女がひとりで来ているのは私ぐらいのようにみえました。MCやPAがはいるコンサートは初めてだったので少々戸惑いましたが、そのパワフルなステージはどの曲もとても素晴らしく、ゲストの藤沢嵐子さんの歌声はそれまで聴いたこともないような—————堂々としていて、すみずみまで力がみなぎっていながらまったく力みがなく、包み込まれるような—————声でした。
昨年、嵐子さんがお亡くなりになった時には、自分がこんなにもアルゼンチン音楽にのめり込む運命にあるとは知りませんでした。来週の更新日(8月22日)は、嵐子さんの一周忌です。
■第671回 ゼロ親等以上にがちんこで!
最近、「ゼロ次会」という言葉をよく耳にするようになりました。要は、飲み会などにおける一次会の前に、少人数で(ある時は、単独で?)、軽くフライイングして別のお店で“ひっかける”ことを言うようです。「一」の前だから「ゼロ」…よく考えたものです。
高校生の頃だったでしょうか。「ゼロ親等」という言葉を知ったとき、かなり驚きました。親子が一親等、兄妹でも二親等なのに、夫婦はゼロ親等だなんて、と。血のつながった親子以上に、特定の他人同士がつながる方が“密”である、という考え方に、違和感を覚えたのです。もしかしたら離婚してしまうかもしれないのに。
それから何年か経て、いろいろな人から話を聞いたり、経験を重ねていくなかで、そういう考え方もあるかも、と思うようになりました。産んでくれた親ではあるけど、常に諍いが絶えずに「子は親を選べないからね」と、目を伏せる人は、周囲に少なくありません。一方、全然違う運命を辿ってきたのに、あるきっかけを得て生涯の伴侶となり、心から信頼しあい、育児を果たして社会に貢献をするカップルは、まさに国家の宝です。
でも…。フランスのように、戸籍を共にしなくても法的に婚姻関係が成立するような国では、どう考えられているのでしょう。それに、仮面夫婦よりもずっと深い絆で結ばれている未婚のカップルも、います。そもそも、人と人との関わりを数字で表すことなど無理があって、それらは単に、法規的機能を果たすための便宜的なものにしかすぎません。家族、とか家庭、という形とは違っても、真剣に…“がちんこ”で関わっているグループには、異性同士でも同性同士でも、二人でも三人でも、ゼロ親等に近い関わりは存在するように思います。
例えば、半世紀にもわたって同じメンバーで活動し続けている弦楽四重奏団。困難なプロジェクトを達成したチーム。人生において、とても大きな影響を受けた恩師とその生徒。場合によっては、生存していない人とも、近しい“親等”になりうるかもしれません。
私の場合、“一生運命を共にする伴侶”には出会えませんでしたが、その方の存在にとてつもなく感謝せずにいられない、貴重な示唆をくださる人には恵まれています。しかも、ありがたいことに年を重ねるにつけ、増えています。
それは、社会の中でかなりのステータスをお持ちでいながら、まったくそれを鼻にかけることも偉ぶることもなく、あたかも対等であるかのようなスタンスで接してくださる恩師であったり、あるいは、まるで身内のように親身に関わりを受け入れ、共に向上していくことやお互いの幸せを心から願い、喜びあえる仲間だったり。精神的な支えや心からの励ましをもらえる人の存在の大きさは、とても数字や等級で表せるものではありません。
今年から音楽活動の上でのパートナーになった植草ひろみさんとのセッションは、リハーサルであれ本番であれ、あるいはその後の反省会であれ(!)、いつも全力投球にして真剣勝負。パフォーマンスのクオリティーをあげていくために、なにをどうすべきか。もっともっとお客さまに喜んでもらえるようにするには、どうしたらよいのか。リハーサルや打ち合わせは、たいてい数時間にわたります。
もっとデュオの完成度を高めるために、試練も突きつけられます。「私は彼女のパートナーに本当にふさわしいのだろうか」と、混乱することもありますが、結局最後には二人して前向きな言葉や将来の“夢”を語っているのです。「必要とされる演奏家になりたいね」「ジャンルに拘らないで、いいものをどんどん発信していこう!」音楽にその人生を救われてきた、というところでの大きな共感と音楽への情熱が、彼女と私の命綱です。今の二人の関わりの深さは、間違いなく“ゼロ親等”…いいえ、それ以上かも知れません。
お客さまに、心底「いい!」と思っていただけるようなパフォーマンスができるように…。これからも、彼女との“がちんこ”なリハーサルは続きそうです。
■第670回 2014年飯館村通行記
コンクールの審査で訪れた、郡山。会場へいく道すがら、街のそこここに除染記録が掲示され、現在の放射能汚染値が電光掲示板みたいなもので表示されています。担当者の方に教えていただいて、草の生え方とか土の状態を見て、そこがいつ頃除染したのか、あるいはしていないのかが、わかるようになりました。計測した結果、放射線量は正常値の範囲、といわれていた彼の家も、後日測り直したら雨樋の下などで局所的に高い数値が出て驚いたといいます。
その一週間後、私は南相馬市にいました。やはりコンクール審査のお仕事でした。常磐線は途中で寸断されていますし、原発に近いところを通らなければならないので、東京方面から直接行くことができません。一度仙台まで北上して、そこからバスで南下するしかないのです。
南相馬地区予選は、震災後やっと今年再開することになったのでした。帰る際に、南相馬から仙台へのバスの本数が少なく、一時間以上も待たなければいけないことが判明したので、主催者の方が福島駅まで車に乗せて送ってくださることになりました。県道12号線で、途中飯館村を通るルートです。
車窓を眺めていると、飯館村に入ったとたん、明らかに異様な雰囲気になりました。まず、民家の様子がおかしいのです。人が住んでいないのだから当たり前と思いきや、それだけではありませんでした。「このあたりには、飯館牛という地元のブランド牛があったんです。それが、震災があって、飼い主が可哀想に思って逃がしたところ、野生化してしまって。その他、豚やイノシシも放し飼いになって、民家を襲うわけです。豚なんかはもう何代目かになっているのですが、当然伝染病の注射もしていないわけで…。放射線被害だけでなく、動物の被害も手を付けられなくなりつつあります」ハンドルを握りながら話してくださるのは、福島に根ざして現状を伝えてきた福島民報社の方です。
お話を伺っているそばから、県道や民家のあちらこちらに「除染作業中」の旗がたち、作業員の方がごく簡単なヘルメットと作業着姿で除染作業にあたっています。その数のあまりの多さは、衝撃でした。しかも、汚染された土や草をまとめた大きな黒い袋が、あるところには無造作に置かれ、またあるところには新しくできた山のように数限りなく積まれていて、それらほとんどの行き先は、未だに決まっていないのです。
それにしても、車で走れば走るほどに、美しい山郷です。穏やかな曲線をなす山並みに見守られ、斜陽が緑の丘にキラキラと輝いて、眼下には川が流れ…。県道沿いにはねむの木のやわらかな花が、まるで何事もなかったかのようなのどかな姿で咲いています。でも、かつてはヤマメやイワナをつかまえる少年たちの声や、紅葉を愛でながら芋煮を楽しむ人で賑わったであろう河原にも、今は人ひとりの姿もありません。
村の中をいけどもいけども、あるのは荒れ果てた家屋、除染をする作業員。それはまるで、村全体がビニール特有のツヤを放つ、汚物の入った黒く大きな袋に乗っ取られてしまったかのような、痛々しい姿でした。“目を覆いたくなるような”という表現がありますが、まさにそんな光景でした。
郡山でも南相馬でも、子どもたちはとても良く弾いていました。外で遊べるのか、その食べ物を口に入れても安全なのか。いつまで、という期限も言い渡されることなく、不安を抱き、放射線量を気にしながら、過ごして来た3年以上もの年月の苦しみは、子どもたちにとって計り知れないものでしょうし、きっと体験しなければわからないものでしょう。そんな中で、こんなにも立派な演奏を聴かせてくれた子どもたち…。全員に100点をあげたくなりました。
「私も、がんばらなければ」福島から帰りの新幹線に乗り込み、座席に身を沈めながら、思いました。そういえば、ねむの木の花言葉は“歓喜”です。いつか、福島の子どもたちにも、たくさんの試練をこらえてきた大人にも、心から歓喜できる日が訪れますように。そのために、ほんの微力でも役にたつことができる人になりたい。いや、日本人として、必ずやそうならなければいけないのだ。…福島を背にしながら、そんな決意を胸に抱いたのでした。
■第669回 ホットな鶴岡滞在記
コンクールの審査で鶴岡に行ってきました。鶴岡は、山形新幹線からも東北新幹線からの上越新幹線からもいまひとつアクセスが悪く、空路以外の方法だと自宅からどうしても5時間半はかかってしまいます。私は今回も上越新幹線で新潟に行き、そこから在来線に乗って移動しました。
その日の審査は午後からでしたが、始発でも間に合わないので、やむなく前日入りすることに。白状すると、やむなく、といいつつ、実はちょっとした目論みがあったのです。庄内地方は今、岩牡蠣のシーズン。昨年も訪れたホテルの近くのあるとお店に立ち寄り、他では味わえない旬の味覚を堪能しようというわけです。
鶴岡はしっとりとした佇まいの、由緒正しい城下町。赤ちょうちんに女性ひとりで飛び込むのはあまり一般的なことではありません。私がのれんをくぐると、大将がちょっと驚いた様子で「いらっしゃい」。大将以上に、カウンターの常連さんと思しき男性からも視線を感じます。でも、そんなことにたじろいではいられません。
「白梅の俵雪(*地酒)と、南禅寺ください。それと、岩牡蠣ありますか?」「ありますよ」「じゃ、お願いします」南禅寺とは、この地方でこの時期に食べられる、くみ上げ豆腐のこと。鶴岡といえばだだ茶豆の本場ですから、お豆腐の美味しさはかなりのものなのです。
「鶴岡には、お仕事で?」カウンターの男性二人組が、やはり声をかけてきました。「はい、明日」「なんの仕事?」「音楽関係です。去年もちょうど同じ時期に、このお店に寄せてもらったんですよ」すると少し奥にいた大将が下駄をならしながらこちらに来て「思い出した!確かコンクールの審査とかって…」「そうそう!それです」「ブラスバンドだっけね?」「…え〜っと」ま、似たようなものなのですが。
「はいよ」大将に手渡された、ぽってりとつややかな岩牡蠣を写真におさめようとすると「そーんな、たいして旨そうでもないものないもん、写真さ撮らなぐても〜」「え〜!?美味しそうなこと極まりないじゃないですか〜!友達に自慢しなきゃ」「んだば、笑貝さ食ってみれば?こいづ(相方さんをこづいて)がおごるから!」「んだ。笑貝な〜」「蒸しと焼き、どっち?」と、大将。
「そりゃ、焼きだべ〜!」男性二人が仲良く声を揃えました。
それは、見たこともないような大きなムール貝でした。親切なことに、噛み切る時にやけどしないよう二つに切ってありました。それでも、その一切れをほおばると、海の香りと甘みのつまったぷりっとした食感で口の中がいっぱいに。ちっとも大味じゃないことは、嬉しい驚きでした。お二人と大将にお礼を言って、おいとましました。
翌日は午後からの審査なので、暑い中午前中に二時間ほど市内を散策。歴史的な建物や神社、公園などを歩いて巡れるのが、鶴岡の魅力です。昼食は、ぶらぶらしながら「ここだ!」と感じたお店で、と決めていました。麦きりのお店や、11時なのに大きな駐車場がいっぱいになっている定食屋さんもありましたが、どうもピンとこないままやり過ごしているうちに、会場に着いてしまいました。まだ一時間あります。ふと見ると、入り口の真向かいにちょっと個性的なエントランスの喫茶店がありました。よし、ここだ!
「こんにちは」お店の中は薄暗く、誰もお客さんがいませんでした。「どうぞ」中からマスターと思しき男性が出てきて、私が席に着くと、メニューと一冊の雑誌をとても自然な所作でテーブルに置きました。サライの最新号でした。「わあ、嬉しい!これ、買おうか迷っていたんです!」マスターは微かににっこりして、ひと言「そう?」。やがて運ばれてきたナポリタンは、昔懐かしい喫茶店の味。とても美味しくてあっという間に平らげてしまいました。とり放題のサラダバーのレタスはシャキっと新鮮。みずみずしいキュウリにはきれいな飾り切りがほどこされ、美しくスライスされた真っ赤なトマトはとても甘く、きちんと皮を湯むきしてありました。
食後のコーヒーの前に、マスターがサライのバックナンバーを8冊ほど持って来て、またもテーブルの上にスマートに置きました。「これ、よかったら好きなだけ持ってって。重くなるかもしれないけど…」「え〜っ?いいんですか!?」「どうぞ。どっちみち処分するから」お言葉に甘えて、二冊を持って帰りました。
一見ぶっきらぼうだけど、心温かな鶴岡の人たちとの思い出に浸って、帰りの5時間半はあっという間でした。
■第668回 カードは知っていた?
今年もコンクールのシーズンがやってまいりました。といっても、このごろは一年中、世界のどこかでコンクールが開催されているので、お話ししたのは“私にとってのコンクール審査のシーズン”という意味です。
いろいろな巡り合わせで今年はかなり審査のスケジュールが集中しています。明日からの鶴岡市にはじまり、山形市、福島県内の三カ所!熱演に点数や甲乙を付けるのは至難の業ですが、点数よりもひとりひとりの講評用紙に書くメッセージをしっかりと受け止め、これからのお稽古の励みにしてもらえるよう、今年も心掛けるつもりです。
「ね、もうオーダイにのった?」同窓生が集まると、誰からともなくこんな質問が飛び出します。そう、東京オリンピックの年度に産まれた私たちは、いま大きな節目の年を迎えているのです。
年齢を重ねると、それまで気づいたり感じたりできなかったことも少しずつ分かるようになって面白くなる反面、様々な不安要因も増えてきます。健康上の不具合や容姿の変化(あえて“衰え”とはいいません)は想定内。そのほか、家族の介護や看病などが発生すると、それまでの生活が大きく変わることになります。
不安、というほどではないかもしれませんが、ある程度のキャリアを築いていくと、正直な指摘をしてくれるひとが少なくなる、ということもあります。例えば、学生の頃は試験の前にお互いに演奏を聴きあって、ここはもっとこうしたら、とか、こういうところに配慮したらもっとよくなるのでは、などという意見を交わして、切磋琢磨してきました。それが、コンクールの審査員とか、大学の教授とか、プロの演奏家のような一定の社会的地位につくと、なかなか言ってもらう機会を得難くなるものです。
それでも、夫婦やパートナー、家族と一緒に生活していれば、言い分やら直してほしいことやらを、お互に話しあうことになるでしょう。言われた方はカチンとくるかもしれませんが、そこはお互いさま。結局は円熟につながるのだと思います。そこへいくと私は仕事でも一匹狼ですし、プライベートでもひとり暮らし。自由気ままに生きられる反面、ものの見方、考え方が偏ったりしないよう、注意を払わなければいけません。
さて、そんな私が今年久しぶりにデュオを結成し、仕事上のパートナーを得る機会に恵まれました。よいアンサンブルを構築するためには、単にテンポやタイミングを合わせるだけでなく、音楽的な価値観や音楽の感じ方などについて、きちんと意見を交わし、接点を見いだしていくための真剣なセッションを重ねて行く必要があります。どちらかがひたすら他方に“合わせる”亭主関白方式では、個性と個性のぶつかりあいの先にこそ発生する、プラスの化学変化はのぞめないのです。なので、リハーサルでは妥協は許されません。
いい音楽、アンサンブルを作ることに情熱を傾け、ズバズバと(いい意味で!)指摘をしてくれる相棒の存在があることは、とてもありがたいことです。というより、この歳になってそんな出会いがあったことは、奇跡に近いことかもしれません。運命に感謝しなければ!
思えば、昨年12月に初めてタロット占いというものをしてもらった時に「まだ動き出す準備ができていないようですが、いったん動き出したら、大変な…怒濤のような…日々がやってくる暗示がでています。そうなったらもう、誰にも止められないでしょう」と言われました。「そして、運命を決定づけるようなことが、再来年におこるようです」とも。「同時に、“集団への帰属”が発生する、という暗示のカードが出ています。ここでの集団というのは、新たな職場だったり、特定のパートナー、といったものです。いずれにしても、あなたの判断力が鍵になります。」
デュオを結成するきっかけを得たのは、そのわずか二週間後のことでした。あまり占いは信じない方ですが、思い返すと言われたことがあまりにぴたりと当てはまっていて、怖くなります。
そして、気になるのは「再来年」に何がおこるのか、です。当時の再来年、は来年のこと。う〜ん、どんな出来事がおこることやら…。ドキドキです!
■第667回 夢は“公園デビュー”?
「アルゼンチンの風が吹いてましたよ!」先週行われたコンサートのあと、多くの方がそんな感想を伝えてくださいました。とてもありがたく、嬉しいことです。なんと言っても初めてのオール・アルゼンチン音楽によるプログラム。一生懸命アルゼンチンのグルーヴ感を身体の中に入れこむべく、自分でもよくやったと思うほど、がんばりました。
でも…なんということでしょう、終わって間もなく気づいたのですが、いつのまにか腰をやられてしまったようなのです。まっすぐにしていても横になってもいやな違和感があって、動きにぎこちなさを感じますし、痛みがあるのでヨガもできません。丈夫なだけがとりえだったのに、大ショックです。
そういえば、コンサートの前日にマッサージに行ったときにも、施術師さんに「お体、辛かったでしょう?こんなになるまで、よく我慢できましたね」と言われて「あまり自覚がなくて…」とおずおず答えたことを思い出しました。「明日ぎっくり腰になってもおかしくないような状態ですよ!」腰ばかりでなく、体中が凝りかたまって、緊張していたのでした。練習に夢中になっていたし、コンサートにすっかり気持ちを奪われていたので、気づかったようです。
ある人に話したら「それはよくないよ。無理している自覚がないのが一番危ない。僕が脳梗塞で倒れた直前もそうだったんだよね」と言われて、さすがに自分の無頓着さを反省しました。たまにヨガのレッスンを受けて身体をほぐしたりしながら、適度に気晴らしもしていたので、特に問題は感じていなかったのですが、身体の方が正直な反応…悲鳴に近い…を示したということなのでしょう。
でも、“腰が痛い→身体を動かすのがこわい→動かさなくなる→ますます身体が固くなる”では、悪循環です。しかも、体調はひとが思っている以上に心の調子に大きな影響を与えるもの。マイナス思考になったり、消極的になったりしがちになるのでこれはなんとしても改善しなければ!さて、どうしたものか。
大好きなヨガですが、しばらくはお休みしなければならなそうです。その代わりになる、何か心と身体を整えるのにいいものってないかしら?ヨガもそうですが、できれば歴史があって、医学的にも裏付けされているものがいいのだけど。しかも、心拍数が上がるような運動ではなくて、気の流れや呼吸を整えてくれるような…。
ふと、「10年以上、太極拳をやっているの」と言っていた友人の言葉が思い浮かびました。なるほど、あれだったら緩やかな動きで身体に負担も少なく、少々の腰痛があっても無理なくできそうです。例えば中国政府が制定した24式というものをひととおり行ったとしても、所要時間は5分ほど。朝にできたら、さぞ、爽快な一日のスタートがきれることでしょう(*妄想中)。だいいち、何の道具もいらないし、その気になればいくつになっても続けられそう。
楽器の練習では、一部の筋肉や腱などを酷使するので、前身をくまなく使うことが望ましいのですが、太極拳ならそのへんもクリアです。音楽に合わせて(?)動くのも、音楽が心底好きな私としてはポイント高し!です。しかも、普段接している西洋音楽とは違うので、気分転換にもなることでしょう。
ここしばらくブームだから、ということもありますが、日本のヨガの先生は食べ物やライフスタイルにもこだわりや美意識を持っている方が多く、スタイリッシュなイメージですし、レッスン生も20代〜40代くらいの美しい女性がほとんどです。そこへいくと太極拳は年齢層も幅広く、おじいちゃん、おばあちゃんとも親しくなれそう。いつの日にか憧れの台湾に行ったときに公園での太極拳に参加して、地元のひとと仲良くなれたら楽しいだろうなあ(*さらに妄想中)。それを先ほどの友人に伝えたら、「私も中国で“公園デビュー”したわよ」
いいぞいいぞ、太極拳!よし、さっそく教えてくれるところを探してみよう。あ、でもそれより、DVD付きの本でも買って、少し予習した方がいいかしら。
…夢がどんどんふくらみます。嗚呼、夢で腰痛がなくなってしまえばいいのに。いや、なくなる気が、します。
■第666回 アンゼンチンまで飛んじゃいたい
有名ピアニストで、文章も上手な中村紘子さんの『アルゼンチンまでもぐりたい』という著書があります。ウィットに富んだ素敵なエッセイです。
なぜアルゼンチンなのか、というのはエッセイを読んでのお楽しみなのですが、アルゼンチンというところが、日本から遥かかなた…いわゆる“地球の裏側”(向こうから見れば日本が裏側になるのでしょうけど)というイメージによるものとは想像していただけるかもしれません。
確かに、現在アルゼンチンまでの直行便はないので、簡単には行くことはできません。ダラス、ヒューストン、アトランタ、ニューヨークなどを経由して行くのが一般的で、通常日本を午後に出発し、ブエノスアイレスには翌日の午前中に到着。所要時間は経由地での乗り継ぎが2〜7時間として、25.5〜33時間とのことですから、一週間程度の日程では行きにくい遠さです(そろそろ直行便、でないかしら)。
でも、私はそんな遥か彼方の地に一瞬でワープすることができる技をもっています。しかも、お金もほとんどかかりません。夢のようなその方法とは…なんのことはない、かの地のラジオを聞くことです。インターネットラジオの普及のおかげで、世界の何百何千(?)ものラジオ局の放送をいつでもどこでも聞くことができるのは、音楽や外国語の響きを聞くのが大好きな私にとっては、まさに夢のようなご利益です。テレビよりもラジオの方が、映像がないぶんイメージをひろげやすく、目をつぶって聞くと自分がブエノスアイレスの街角にいるような気分になれます。遥か彼方の地というだけだけでも思いが募るのに、そこにご当地ならではのおいしい食べ物や、魅力的な音楽なんぞがあったら、もう、居ても立っても居られない気持ちになります。
ところで、アルゼンチンとチリはお隣同士でともにスペイン語を母国語とし、ワインの産地としても有名ですが、アンデス山脈を隔てると性格が逆になるとかで、国民性は大きく異なると言われています。チリの人はフレンドリーで親しみやすく、アルゼンチンの人はプライドが高く個人主義、というのがステレオタイプな評価だそうです。チリ人は勤勉で気性も穏やか。どこか日本人に近いところがあるけど、アルゼンチン人はいいかげんで、明日でもできることは明日やろう、という考え方をする人が多く、雨が降ろうものなら約束はキャン
セルされるのが当たり前なのだとか。学校さえも、「雨が降ったから」を理由に欠席できるとも聞きました。
そして、アルゼンチンの音楽…特にタンゴには日本人はある程度馴染みがありますが、チリの音楽といわれても何も思い浮かびません(勉強不足のせい、というのも多々ありますが)。一緒くたに“中南米”といっても、かなりの違いがあるようです。
人間には不思議なことに、自分に近いものに親しみを感じる部分と、違うものに心惹かれる部分の、両方があるようです。考えてみたら、同じ部分がまったくないのはキツいけど、かといって似通っているばかりでは刺激に乏しく、物の見方やら考え方もひろがりませんもの、ね。ですから、“違うけど共感できるところがある”のは、最強です。私にとっての西洋のクラシック音楽やアルゼンチン音楽は、まさにそういう存在なのです。
長いこと親しんでいるクラシック音楽の流れをアルゼンチン音楽が受け継いでいるのは、スペインに支配されていた歴史を考えると合点がいきます。私にとって、特にアルゼンチンの音楽はまさに「親しみを抱きつつも、新鮮な響きやリズム、グルーヴ感に満ちた、刺激的なもの」。今、そんな魅惑的な音楽につつまれる本番のための支度をしているところです。
アルゼンチンは私にとって、恥ずかしいときにもぐりたくなるような場所ではなく(あ。これって、前出のタイトルの“ネタバレ”?)、できることならすぐにでも飛んでいきたい憧れの地。来るコンサート『アルゼンチンナイト』では、お客さまにも、アルゼンチンへのそんな気持ちを抱いていただけますように…。
それでは、いってまいります!
■第665回 感性のアンテナ
オリンピックやワールドカップがあると、メディアも人々もその話題で持ちきりになりますが、気にあることがあります。そういったスポーツの祭典の裏にも、常に報道されるべき問題が同時進行しているというのに、そちらの情報が会期中、希薄になるように思われてならないこと(特に海外での紛争や戦争についてなど)。それから、ここ数年、純粋にスポーツを楽しむはずの晴れの舞台が、時として政治的な思惑の表現の場となってしまうこと。
選手たちの素晴らしいプレーには目も心も奪われるばかりですが、そこに政治的な訴えが掲げられては、応援している人々だけでなく、選手の士気を下げることにもなりかねません。今回も、素晴らしいゲームを展開して観客を魅了しているアルゼンチンですが、先日、一部のサポーターによる「フォークランド諸島は我々のもの」といった文言が映し出され、残念な気持ちになりました。
一方で、選手たちが内戦を終わらせるきっかけを作った国もありました。コートジボワールです。2005年のワールドカップで、試合後ロッカールームにカメラマンを呼び入れ、選手税員でひざまずいて語った以下のようなメッセージに、世界中が注目しました。「北も南も、西も中央も無い。コートジボワールはひとつです。この豊かな国を、戦争の犠牲にしてはいけない。武器を置いて、心を一つにしよう!」
その後、アフリカの最優秀選手に選ばれたドログバ選手は、内戦でもっとも傷ついた街の人々に代表チームによる試合をプレゼントしました。感激し、彼の実家に押し寄せた一万人近い人たちに向かって彼が「コートジボワール市民の皆さん。北部出身の、南部の、中部の、そして西部出身の皆さん。私たちはこうやってひざまずき、皆さんに懇願します。コートジボワールほどの偉大な国がいつまでも混乱し続けるわけにはいきません。武器を置いて、選挙を実施してください。そうすればすべてが良くなります」と、訴えたことが大きなきっかけになって、その一週間以内に戦闘が止まりました。
人々が戦地で闘っているのは、本当に大義のためでしょうか?言うまでもないことですが、いつの時代のどんな戦争も決して良いものになりえないのは、それが人を悲しませるからです。戦争を推進するよりも止める方がずっと難しいのは明らかです。それを行えるリーダーが、世界に増えることを祈るしかありません。
それにしても、いくら大きな影響力を持つ人だからといって、国を動かしてしまうなんて、すごいことです。ドロクバ選手は「大統領よりも力がある」「フランス軍よりも国連平和維持軍よりも実績がある」と評価され、『タイム』誌でも「世界で最も影響力のある100人」に選ばれました。彼は確かには素晴らしいのですが、実は国民はみんな理解していたのだ、という気もします。戦争が何も産まず不毛なものであるということを。彼のメッセージは人々の気持ちを正しい判断へと導かせ、行動に踏み切らせる大きな“きっかけ”になったのではないでしょうか。
そんな、ふと気が楽になったり、我に帰って大切なものに気づいたりするきっかけになるメッセージは、実は案外身近なところにたくさん在るのかもしれません。それを受信するアンテナさえあれば、自分にとって良い啓示となるようなメッセージを、もっともっと受信できるのかもしれません。
そんな、人間にとってとても大切なアンテナを、実は皆持っているのです。ただ、日常の生活のせわしなさの中で、ついついメンテナンスを怠ってしまいがち。感度が鈍くなったり、ネジがゆるんでいたりするのに気づかずに過ごしてしまいやすいのです。芸術は、そんなアンテナに意識を向けるきっかけとしても、よいツールなのではないでしょうか。なぜなら、そこには様々なメッセージがいっぱい詰まっているからです。特に音楽は、作曲家による入魂のメッセージに演奏者のメッセージが重なる、濃密で魅力的な芸術だと思います。
素敵なメッセージを受信(インプット)できる“感性のアンテナ”を持ちつつ、他の人に受け止めてもらえるメッセージを送信(アウトプット)できる音楽家を、目指したいものです。まずは来週の金曜日に行われるコンサート“アルゼンチンナイト”で、皆さまにアルゼンチンの風や光をお送りできますように…。
■第664回 「どうだった?」は続く
「いくつでピアノを始めたのですか?」よくされる質問です。子どもにいくつから始めさせたら良いのか、という質問も。でも、その答えには困ります。小さい子どもにとって、半年は大きな違い。同じ4歳でも、産まれた月によって体格や指の強さには思いのほか差があったりします。3歳からでも始められる子もいれば、4歳でもまだじっと座っていられない子もいるのです。
私が正式に(?)始めたのは4歳のときです。でも、自力でピアノの椅子に座れない頃から鍵盤はさわっていましたし、習い始める前から“即興演奏”も楽しんでいました。指や手のひらで音を奏で、自分なりに高音と低音、強い音と弱い音を組み合わせて、変化をつけて一つのストーリーを描くのです。強打したり優しいタッチで弾いたり、とけっこう工夫をしていました。
一曲弾き終えては母に「どうだった?」と感想を聞きにいくのですが、母にしてみれば子どもがおもちゃで遊ぶように、私がピアノで好き勝手に遊んでいるようにしか聞こえなかったことでしょう。いつもその答えは同じでした。「上手だったわよ」
私はそれが不満でした。めちゃくちゃに弾いているようで、会心の出来映えの時とちっとも良くなかったな、という時があったのです。ドラマティックな表現がちゃんと実を結んで、弾き終えた時に達成感があったときと、なんだか緩慢でしまりがなかったときなどいろいろありました。それがみんな同じ反応というのは納得がいかないな、と子どもながらに思っていたのです。ですから、特にうまくいったと思っていたときには「上手だったわよ」の答えに対して「ねぇ、どのくらい上手だった?」と、しつこく突っ込みをいれていました。
「どうだった?」という問いかけは、今も続いています。リサイタルをするのは、それが聞きたいがため、といってもいいくらい。聴いてくださった方が感想をお寄せくださるのが、なにより嬉しいのです。
オールショパンのリサイタルのあと、高校時代からの友人から手紙が届いたときには、心が震えて嬉しさで涙があふれそうになりました。手作りの封筒にはやはり手作りの美しいラッピングが施された茨木のり子さんの詩集とともに、彼女自らが装丁した便せんに、綿綿とリサイタルの感想が綴られていたのです。以下、その一部をご紹介します。
みなちゃん
私の不思議!を聞いて!
みなちゃん。音は、香り?複雑なアロマ。
二つのノクターンを聴いた時…2番のほうね。あれは、私の持っている”陰”と”陽”のアロマの”陽”と同じ香りがした。
やさしくて柔らかで、少し華やかで…“インプレッシヴ”
ネロリの香りがわ〜、とただよっていきて、とても幸福感に包まれたのでした。
あれは、なんなんだろう?音は香り?
ネロリ、ローズマリー、ラヴェンダー、ベルガモット、グレープフルーツ、シダーウッド、バジルスイート。
ひとつひとつの香りがひとつひとつの音に呼応しているみたいに重なって、香りがみなちゃんのピアノからただよってきたよ。
(中略)
どうして音楽は、一瞬にして、人の心を正気にさせるのでしょうか。
正気に…というのは、人間と言う者は、日常の中では、正気ではないと思うからなのですが…。
音楽を聴く時(みなちゃんのピアノを聴く時といったほうが正しい)、私は正気になるような気がします。
悲しい粒子、楽しい粒子、うれしい粒子。
人の感情をつくる粒子のようなものがあって、音というのは、それに、それぞれが呼応しているのでしょうか。
不思議で不思議でたまりません。
(中略)
作曲家はそのことを知っているのでしょうか。
少なくともショパンは、香りも粒のことも、知っていたんだ…と思ったのでした。
(そしてみなちゃんはシャーマンだから、そのことを伝えられるのね。)
ショパンのリボンがかけられたくちゃくちゃの封筒(*)を見ていたら、この詩集を送りたくなりました…。
ショパンに。
なので、シャーマンみなこにたくします。
素晴らしい夜をありがとうございました。
そしてそして、アルゼンチン・ナイト…。
私は、みなちゃんの真実が、あふれでる舞台になるような予感がしておりまする。
(*リサイタルのプログラムの表紙に載せた、ショパンが“我がかなしみ”と記した封筒のこと)
—−—−—−—−—−—−—−—−—−—−—−—
次なる公演『アルゼンチン・ナイト』まであと二週間を切りました。“私の真実”は果たして伝えられるかしら…。次の「どうだった?」に向けて、気持ちのよい緊張に包まれています。
■第663回 終わらない、幸せ
リサイタル“ショパン 昇華するメランコリー”の仙台公演、東京公演が終了しました。ありがたいことに、両公演とも本当にたくさんのお客さまに恵まれました。今はとにかく、忙しい中いらしてくださったおひとりおひとりの皆さんに、感謝の気持ちでいっぱいです。
引退の理由を「ステージで自分の100パーセントの演奏ができなくなったから」といって、ステージを降りたある演奏家がいました。ステージで100パーセントの力を出し切るためには、普段の練習が少なくとも120パーセント以上でなくてはならないでしょう。う〜ん、常に100パーセントを維持するなんて…すさまじいまでのストイックさです。
ストイック、というのとは違いますが、「美奈子ちゃんはまじめだね」と、よく言われます。確かに、子どもの頃から学級委員に選ばれるタイプでした。今までは“まじめ”という言葉には“不器用”というニュアンスが感じられて、あまり歓迎できなかったのですが、このごろはなんだかまじめも悪くないような気持ちになってきました。だって、不器用にあっちこっちぶつけながら歩いていくほうが、うまいことスイスイやってのけるよりも、様々な発見があって楽しそうではありませんか?
ピアノが好きで好きで、ピアニストになった私は実に幸せ者です。その幸せに感謝しつつ、毎日の練習をおこたらないよう心掛けているつもりですが、よほど不器用なのかステージで100パーセントを発揮できたことなんて、未だかつてありません。普段が100とするならば、せいぜい70前後くらいです。
そこで、今回のオールショパンプログラムのリサイタルに向け、自分でもすごいなと感心するほど(!)、たくさんの練習を重ねました。果たして、仙台公演が終わった後は、とても幸せでした。100パーセントではないにせよ、弾いている間、雑念を排してショパンの世界にどっぷりと没頭することができたのです。それは、ステージ活動を始めてから20数年を経て、初めてのことでした。
東京公演ではもっと完成度を上げ、もっと深いところに入っていけるよう、さらに猛練習を重ねました。ところがその結果、深く入り込めたものとそこに行き着かなかったものとの、ばらつきが生じてしまいました。出来不出来の差が出てしまったのです。やはり、どうしても100パーセントに到達できません。ほとほと切なくなって、心がシクシク痛くなってきます。
そんなときに何よりの励みと慰めになるのは、聴きにきてくださった方からのメッセージです。「共感しました」「演奏もお話も楽しくて、あっという間の時間でした」「美奈子さんの誠実さが伝わってきました」…そんな温かい言葉にわだかまりはすっかり吹き飛んで、「よし!めげてなんていられない。明日からまた、たくさんピアノ弾くぞ!もっと完成度をあげるぞ!」という気持ちになります。つくづく、子どもみたいに単純な精神構造の持ち主なのだと思います。
なかなか100パーセントにたどり着けそうにありませんし、ステージへの不安はそう簡単にはなくなりません。でも、ふと気づいたのです。人間には不安や心の痛みはつきものですが、それらがあるが故になんらかの行動や努力を、する(せざるを得ない)。そして、その努力が実を結ぶと、感謝の気持ちでいっぱいになる。だとすると、あらゆる不安や心の痛みは、感謝につながる、ということになるのでは?私は日頃から、「幸せとは、心から感謝することにある」と考えているのですが、ならば、不安や心の痛みこそ、幸せを育てる種子であると言えるのではないか…。
なんだか理屈(屁理屈?)っぽくなってしまいましたが、要は100パーセントの自信が得られないままステージに上がることへの不安には、幸せの鍵が隠されている、ということなのです。不安を敵視し排除するのではなく、受け入れ、向き合ってそこから学ぶことが、器用じゃない私にとっては、必要なようです。
100パーセントを目指す幸せな試練は、まだまだ続きます。音楽が大好きでいる限り、それは終わらないでしょう。
■第662回 答えは自分のなかに
「速く弾こうとしなくてもいいの。丁寧に弾くこと、そして丁寧に聴きながら弾くことを心掛けて」「こう弾きたい、というあなたの意思が何より大切です。その意思を見つけていくことや、それを表現するための工夫を重ねていくのが、有意義な練習なのよ」
生徒さんに、レッスンの中で無意識にたびたび伝えているこのような言葉のうち、半分以上は自分に向けて言っているように思います。
潜在意識、という言葉をよく耳にします。これまでの人生の中で感じてきたこと、考えたり気づいたりしたことが、無意識にそこに息づいているのだそうです。顕在意識、はそれと対をなす言葉で、こちらは意識が働いている状態での心の領域。何かを決意したり選択する時に直接的に働き、不安や悩み、願望を持つものだとされています。
ユングはそれらを氷山にたとえました。つまり、水面から突き出ている部分を顕在意識、水面下に隠れている部分が潜在意識で、人間にとって潜在意識の占める部分の方が圧倒的に大きく、全体の9割を占めるのだとか。しかも、その部分は当の本人にはっきり自覚できないものなのです。
潜在意識は、非常事態に直面すると、普段イニシアティブをとっている顕在意識の制約を押しのけて台頭し、これがいわゆる“火事場の馬鹿力”を発揮するのだそうです。睡眠中にみる夢も、潜在意識が影響しているのだといいます。それどころか、現実的な呼吸、新陳代謝など、身体の機能を動かしているのも潜在意識の働きによるものだというのですから、いかに大切かということでしょう。
また、潜在意識は過去における学びや、考えたことなどがたくさん蓄積された、洞察力や直感力の宝庫だといいます。一方で、物事を批判、判断する機能や、現実と想像を区別することがなく、与えられたものをそのまま受けとります。そして、ひらめきや直感を生み出すのだそうです。
セラピストをしている知人にそのへんのことを尋ねると、こう言っていました。「そこでいわれている潜在意識からの呼びかけを、私たちはもう1人の自分…ハイヤーセルフ、と呼んだりするの。つまり、高次の自分、高次の魂ね。訓練をつむことで、普段は自覚できないハイヤーセルフ…内なる自身の声、を聞くことができるようになるのよ」
そう聞くとなにやらちょっと怪しい感じもしますが、ふとした瞬間に自分の内なる声?らしきものが聞こえることは、案外あるのではないでしょうか。母は学生時代に、どうしても“顕在意識”のなかで解くことができなかった数式を、夢の中の“潜在意識”のちからで見事に解いたといいますし、ある友人は「今の部署に配属になったら、なぜかずっと腰が痛くて…。で、ある日ふと気づいたの。なぁんだ、椅子の高さがあってないじゃない?って。3センチ変えたら、腰痛がウソのようになくなって驚いたわ」と話していました。
感覚や無意識のなかには、その時の自分にとって重要なメッセージが隠れているのかもしれません。私もまた、何気なく生徒さんに話している言葉のなかに、自分が直面している問題の解決の鍵になるようなことを無意識に言っているのです。
何かに迷ったり悩んだりしたときに、“おうかがい”をたてるのは、自分の中の顕在意識。その時、なかなかよい解決策がみえてこないとしても、相手は自分の一割に満たない意識と判断力しかもっていないのだから、仕方ないと思えば諦めもつきます。
でも、憧れの潜在意識くんはきっとその答えを知っているのです。彼ともっとお近づきになるにはどうしたらいいのやら…。ぼんやり考えていたら、ある時ハイヤーセルフ?が答えました「それには、夢を語ることです」。えー?その夢って、願望でしょう?顕在意識の中の願望でしょう?…いやまてよ、睡眠中の夢には潜在意識が息づいているのですから、潜在意識は“夢”と近いところに在るのかもしれません。
『努力する者は夢を語り、怠ける者は不満を語る』とは誰の言葉だったかしら…。よし、決めた。我がくちびるに、もっと夢を語ってもらおう!そうすれば、きっと何かがおこる…ような気がしてきました。
■第661回 緊張が教えてくれること
無くて七癖、という言葉があります。確かに、ほとんどの場合自分で自分の癖は把握しづらいものです。
長袖の洋服を着ている時には腕まくりをしてからピアノを弾く、という癖があるようですが、そんな癖とはまた別に、意識して習慣的に行なっていることも、あります。私は練習するとき、曲を弾く前に必ず音階の練習をします。音階は、一オクターヴ以内の12の音を主音とする全調で、長音階、和声的短音階、旋律的短音階の3種類を2往復ずつですから、一つの主音につき6往復。それが全調ですから72往復を、4オクターヴ行います。
それぞれ指使いや調号などパターンは変わりますが、何往復も繰り返しているうちに、指や身体、そして気持ちも落ち着いて、音の世界に引き込まれていくのを感じることができて、好きなウォーミングアップです。同じことを毎回行うことで、その日のコンディションの善し悪しも、なんとなくつかむことができます。
生徒さんの様子を観察すると、それぞれの個性を目の当たりにすることができてとても楽しいものです。特に小さな子どもたちは、みんなそれぞれに本当にユニーク!挨拶のしかた、部屋への入り方、お月謝のわたし方…。ちゃんとお母さんに言われたとおりにできている子、うっかりしてしまう子、いろいろです。
ピアノを弾き始める時の呼吸の整え方も、さまざま。Mちゃんは、意識してか無意識でか、その曲の拍子を…例えば4拍子なら「1、2、3、ハイ!」と、正しいテンポで自分に号令をかけてから弾きはじめます(曲の途中から弾くときもそれを同様に行うのが、とても愛らしいのです)し、Tくんは鍵盤の上に手を置いて、しばらくじっと考え、納得がいくまで指と気持ちの準備ができてから音を出します。3歳のRちゃんは指の場所を確かめたあとに大きく一息ついてから弾き始めますし、Tちゃんは身体をゆらして音楽に入っていきます。
もちろん、あまり呼吸をとらずに慌てて(?)弾き始めてしまうひとも、います。でも、みんなそれぞれに音の始まる瞬間に感覚を研ぎ澄ませ、よい緊張を感じながら懸命に楽器と向き合っているのが見てとれて、それだけでももう「ありがとう!」という気持ちになるのです。
そう、彼らは意識していようがいまいが、確実に“緊張”しているのです。お稽古したことをちゃんと発揮できるように、とか、先生に上手になったことを見てもらいたい、とか、そういった前向きな気持ちが、彼らを緊張させているのです。私も、そうでした。ピアノの先生の前で弾く時にはいつも身も心もふだんよりずっと引き締まり、その結果思わぬところでつまづいたりもするのですが、レッスンに付き添っていた母はたいてい、「美奈子ちゃんは先生のお宅では、うちで練習しているときよりもずっといい音で弾くわね。音に真剣さがこもっている感じがする。いつもそういうふうにお稽古できたらどんなに上達するかしら、と思うわ」と言うのでした。
一般的に、緊張は悪者にされていますが、緊張感やストレスが一切なくなってしまったら、人間は幸せを感じないのだそうです。緊張を上手にコントロールして、緊張と弛緩のバランスをとっていけたら理想的なのでしょうけど、なかなか思うようにはいかないものです。
どなたかは覚えていないのですが、ある高名な演奏家が「緊張しないようになったら、それはステージを降りるときだ」ということをおっしゃいました。緊張感こそがよい演奏をひきだし、またそれがために練習にも手を抜かないで、謙虚な気持ちで勉強を続けることができる…。まさに“初心忘るべからず”の教えです。
ですから、このごろは緊張を感じるたび「神さまが私に、謙虚でありなさい、地道に稽古を積み重ね精進なさい、と教えてくれているんだ」と考えることにしました。歳を重ねていくほどに、直接「謙虚になりなさい」なんて言ってくれるひとは少なくなってしまうことを思うと、緊張を感じる機会はとても貴重にしてありがたい機会だということになります。本当に一流の方々は、みなさん実に謙虚でいらっしゃるのも、うなずけます。
これまでにも何度かこのエッセイに緊張について書いてきました。緊張といかに向き合い克服するかは、私たち演奏家の永遠の?テーマです。
諦めるのではなく、闘うのでもなく、緊張を受け入れつつもそれ以上に音楽の素晴らしさを「伝えたい!」気持ちを強くもって、本番にのぞみたいものです。そして、これからもできるだけ長くステージに立ち、緊張を味わい続けたいと思っています。
■第660回 恩師、E先生のこと
リサイタルが近づいてきました。ドキドキ感(あえて緊張感、とはいいません)も増してくる時期ですが、最近ではそれを払拭するくらい、楽しみも増すようになってきました。
リサイタル当日は、懐かしい同窓生や、お世話になった先生のお元気なお姿にであえる日でもあるからです。ご案内を出してもお忙しくてなかなかお出かけいただけなかった先生に数年ぶりにお会いすると、変わらないご様子に心から嬉しくなりますし、私のリサイタルで何人かの同窓生が顔を合わせて、親好をあたためるきっかけになったりするのはとても心はずむことです。
中学から高校にかけて、お世話になっていた作曲家のE先生が、今回いらしてくださるとのお返事をくださいました。E先生には、はじめは本科のピアノとソルフェージュ、聴音、楽典…音楽の勉強のすべてをお習いしていました。音大受験が近づいた高校時代には、ピアノは東京の先生にレッスンに通ったりしましたが、その間もみっちりと楽理全般を教わりました。
当時は何とも思っていなかったのですが、晴れて音大に入って改めて感じたのは、E先生がいかにたくさんの大切なことを私に叩き込んでおいてくださったか、ということ。しかも、実際にはレッスンは“叩き込む”というイメージとはかけ離れ、楽しみながらいつのまにか高度なことを習得させてもらっていたのでした。
例えば、スコアリーディング。普通は指揮科でも受験するのではない限り学ぶ機会がないのですが、ト音記号、ヘ音記号だけでなくハ音記号(何種類かあります)の入り交じった、数段におよぶ総譜(スコア)を読み取って、ピアノで弾く、というものです。あるいは、通常は大学に入ってから学ぶことになる数字付鍵盤和声(なんだ、それ?とお思いになる方が多いと思うのですが、バロック音楽を鍵盤楽器で弾く時に大切なものなのです)なども、ひととおり教えていただきました。
時おり先生が淹れてくださるコーヒーが大変に香り高く、当時カフェもそれほどなかったし、第一高校生の身分で喫茶店にすらそうそう入れなかった私にとって、どんなにかそれが楽しみで、しかも美味しかったことか!音楽の話、
ヨーロッパの話、はたまたお酒の話…。時には先生の教えていらっしゃる音楽大学のオリエンテーションの余興?で使うために先生が自作された、クラシック版“イントロ当てクイズ”を私に試したりなさって、先生ご自身も楽しまれているようでした(イントロ当てクイズは、全問正解して先生を驚かせた記憶があります)。
大学に入ってから帰省してご挨拶にお伺いすると、だいたい「夕ご飯を食べていきなさい」とおっしゃって、料理上手の奥さまの手料理をお腹いっぱいごちそうになりました。お酒をうまれて初めて頂いたのも、E先生のお宅でした。ウィーン在住のアルト歌手の妹さんから送られてきた写真を見せて、「美奈子くんも、いつかは行かないとね」と、励ましてくださったりもしました。年齢を聞かれると、必ず「37歳」と答える茶目っ気の持ち主でもありました。
今度のリサイタルでは、大好きな同窓生に加え、久しぶりにE先生にもお会いできることになって、今からとても楽しみなのです。「サンタクロースみたいになったよ」と、絵文字いっぱいのメールを下さいましたが、先生のお髭はもともとサンタクロース並みにご立派でした。
それにしても…ふと、気づいては不思議に思うのです。私が学生時代に出会って、大きなお導きを頂いた先生方と自分が、いつのまにか同じような年齢になっているのだ、ということを。いつまでも成長しない生徒のような自分が、あの頃の先生方と同じなんて、実感が湧きません。果たして私は先生方のように、きちんと生徒さんを指導できているのかしら?生徒さんを幸せに導くことができているのかしら?
その自信はちっともないのですが、少なくとも生徒さんからたくさんの幸せをいただいているのは、確かです。ということは、先生方からも、生徒さんからも、幸せをいただいていることになります。こりゃたいへん。なにかのかたちできちんと世の中に還元しないと、罰が当たりそうです。
リサイタルで弾くショパンもまた、永きにわたって幸せをくれている存在です。私のショパンを聴いてくださる方が、少しでも幸せになってくださったら…!そんな気持ちで、ピアノに向かっている毎日です。
■第659回 味は「人生」?
ごく幼い頃からピアノを始めて今も学び続けていますが、その他の習い事は5年以上続いたためしがありません。その他の習い事、というのも、これまでに経験があるのは4年ほど続いたフラメンコが最長で、あとは小学生の頃に少しだけ習ったヴァイオリン、不定期で行っているヨガのレッスンぐらいです。
習い事ではありませんが、スポーツクラブに数ヶ月通ってトレーニングをしたことはありました。でも、それも半年後に地元のロードレースに出たところ、期せずして6位入賞という成績をとってしまい、それでなんとなく“燃え尽き症候群”になって終わってしまいました。
基本的に、ピアノが仕事でありながら趣味でもあるので、それ以外の趣味で人生を満たそう、という欲がないのかもしれません。ピアノだけでも、もう充分すぎるほど大変だし、飽きないし、やりがいがあるのです。この先も一生、同じように感じていくことでしょう。幸せなことです。
一方で、たくさんの趣味やお習い事を楽しんでいる方は、いったいどんなふうに意欲を維持し、どんな楽しみ方をしているのか、興味があります。そういう方はきっと、様々な知識や経験を積み重ね、魅力的でバランスのとれた人付き合いができていらっしゃるのだろうな…。
はて、大作曲家はどうだったっけ?ドヴォルザークの鉄道好き(特に蒸気機関車、時刻表!)は有名ですし、今、毎日ランデブーを重ねているショパンは、ちょっとしたイラスト(漫画的?)を書くのが得意だったようです。絵画を本格的に習い、かなりの腕前だったのはメンデルスゾーン。若くして音楽家としての大きな成功を収め、さっさとオペラからは身を引いたロッシーニは美食家としては生涯現役で、自ら「自分はピアニストとしては三流だが、美食家としては世界一」と言っていたとか。うーん、それぞれ楽しそうです。
同級生と会うと、みんなそれぞれ自分の趣味を楽しんでうらやましく思います。茶道、合気道、スイミングやヨガ…。皆、心の豊かさと身体の健康のために、きちんと仕事以外の有意義な時間をもつことを心掛けていて、感心します。
そもそも趣味とは、仕事、職業ではなくても夢中になれて、「好き」「楽し
い」と感じるもののことです。習い事ではないけど、好きで続けていることを考えてみると、文章を書くことが私の趣味にあたるのかもしれません。性格上、好きじゃなければ毎週の更新を10数年も続けられないでしょう。金曜日の夜の宿題のような存在にもなってはいますが、書き始めると時間を忘れてしまいますし、何かおもしろいことがあると「ネタになるかしら」とメモしたり…けっこう楽しんでいるのだと思います。
趣味には、自由時間に好んで習慣的に繰り返しおこなう行為、事柄やその対象のこと、という定義もあります。ということは、私の場合、自由時間も仕事時間もピアノを弾いているので、人生そのものが趣味ということになったりして。「趣味は、人生です」…ちょっと格好いいかも!
ところで、なぜ弾いたり書いたりするのが好きなのかというと、それは自分以外の第三者とのつながりを持ちうるからです。聞いてくださる人、読んでくださる人…。必ずしも直接お話できなくても、そこには、共感を持っていただけるかもしれない、という希望や夢があるからなのだと思います。つくづく「ひと」が大好きなのでしょう。
生後2か月で1万人に一人の肝臓の難病が見つかって手術を3回。その後、国立成育医療センターで肝移植という大手術をし、術後も長期間のICU暮らしが続きました。やっと病棟に上がってからもなかなか人工呼吸器が外れませんでしたが、リミットぎりぎりでなんとか外れ、無事退院…という、大変な約2年間を送った2歳の男の子を知っています。よくお邪魔するカフェのマスターのご子息、Mくんです。
Mくんは、カフェのお客さまとすぐに仲良しになります。光栄なことに、昨日は私の頬に「ちゅ」してくれました。ご両親はもちろん、たくさんの人から差し伸べられた手と、みんなの気持ちに支えられながら小さな身体で難病と戦い、自らの命を守ってきたM君。彼を見ていると、関わってくれる「ひと」のありがたさを深く理解しているように感じられてなりません。
ひとは、支えあって生きています。それが実感できる時に幸せを享受できるのが、ひとです。これからも「ひと」を好きでいつづけていきたい、と改めて思ったのでした。
■第658回 こだわらない、というコダワリ
ふと思い返したら、最後にヨガのレッスンを受けたのはもう数ヶ月前のことです。ということは、もう何ヶ月もまともに運動していないではありませんか。
レッスンを受けていなくても、自分でストレッチやジョギングをしていればいいのですが、このところのバタバタに追われそれも怠っています。これはいけません。意を決して、近所のヨガ教室の受講生になることにしました。
このエッセイを読んでくださっている方から「美奈子さんは、ライフスタイルや食べ物、言葉の使い方などにこだわりを持っていらっしゃいますね」とおっしゃっていただくことがあるのですが、いやいや、そんなこともないのです。ここだけの話、毎週のネタがないので無理矢理取り上げているようなところがあって…。
現代では、こだわりがある、というと“信念を持つ”とか、“ポリシーを持って妥協をしない、自分のやり方をつらぬく”といった、良いほうの意味が一般的です。
でも、実は“こだわり”という言葉にはもともと「なんくせをつける」「文句をつける」という意味があるのです。そして、“こだわる”とは「ちょっとしたことを必要以上に気にする。つっかかったり、ひっかかったりする」さらに「心が何かにとらわれて、自由に考えることができなくなる」という意味だとのことです。
こだわり、とは、私がもっとも避けたいものだったのです。だって、演奏中に小さなミスを「必要以上に気に」したくないし、「つっかかったり、ひっかかったりする」のは勘弁してほしい。第一、芸術家たるもの「自由に考えることができなくなる」なんて、致命的なマイナスです。
むしろ、望みたいのはその反対です。つまり、物事を必要以上に気にすることなく、何かにとらわれない自由な心と発想をもって、滑らかによどむことなく弾くこと、です。
良いほうの意味での、こだわり…「ここはこう弾くべし!」のような信念も、もちろん大切です。でも、とらわれて固執するのはどうもいけません。と、いうことは、好ましいのは“こだわりをもちつつ、こだわりにこだわらない”というイメージでしょうか。う〜ん、なんだか禅問答のようになってきました。
ヨガ教室の申し込みをした翌日・・・つまり昨日、ある住職さんとお会いしました。ゆっくりお話しを伺って、少し瞑想を教えていただきました。日本人はどうも、宗教的理念をとらえるのが苦手なところがありますが、実は宗教の思想には多くの示唆に満ちていると、常々思っています。そして、深く知ろうとすればするほど、どの宗教も根っこの部分ではつながっているように感じられてならないのです。住職さんからインドやチベット起源の密教のお話を伺うにつれ、そんな思いを深くしました。それには経典によって教えが開かれることもあれば、文字によらず「得るか否かはきみの情(こころ)にかかれり。ただ手を握りて契約し、口に伝えて心に授けるのみ(空海)」という教えも存在するのだそうです。
経典による教えと、文字に頼らない教え。どちらが正しいかを論ずるのは、フォーカスポイントではありません。その両方が大切なのだとしたら、寛容なのは良いものを自分に取り込み、それらを融合、結合させること、ということになります。「ヨガというのは、サンスクリット語で“結合”結びつき、を意味するのです」転じて、乱れて散らばった心を結びつけ、本来の健やかな状態に整えることや、心と身体のバランスを整えること、ひいては、宇宙と自分とを、さらにはあらゆるものを統合するということを意味するそうです。「無になる、というよりも“空”になることです。身体や意識は存在するのですから。むしろ有るものを空っぽにすることです。」
お話を伺って、ハッとしました。実に先週のこのエッセイで『作曲家、演奏者、聴き手による幸福な三位一体』を目指している、と書いたばかりだったことを思い出したのです。しかも、ヨガのレッスンを始めることにした翌日にそんなお話を伺うことになるなんて…。なんだか、目には見えないけど確実に流れている“気”の存在を感じてしまいました。
そもそも芸術とは、調和と対比、という、相反するものの融合と結びつきで成り立っているものです。異なるもの同士の融合、結合。これは、自然と文明の共存や、国際社会における各国の協調を見いだすためのキーワードでもあるように思われます。
手放した方がいい不必要なこだわりと、何かときちんと向き合うために必要なコダワリ。その両方を結合させることができたら、平常心でリサイタルにのぞめるようになるかしら。
■第657回 楽こそ物の上手なれ
先週の日曜日、郡山でのレクチャーコンサートを終えました。もう15年以上審査員として関わらせていただいているピアノコンクールの課題曲について、ポイントをお話ししながら演奏をするお仕事です。
毎年、公開レッスンやアナリーゼ、今回のようなレクチャーコンサートなど、コンクールの審査だけではなく、いろいろな形で参加者や指導されている先生方と接する機会を頂いています。ありがたいことです。もともと、音楽に甲乙を付けるコンクールは好きではなかったのですが、どのような形であれ、ステージでの経験を重ね、他の人の演奏から刺激を得て、さらに進歩していくきっかけを得るのは良いことだと思うようになりました。
その日のコンサートは、正味2時間で課題曲50曲ほどを解説しながら演奏する、という、無謀とも思われる内容でした。始めは、その曲について説明をしたあとに演奏していたのですが、だんだん白熱して曲を弾きながら話したり、時間が足りなくて一部ソナタの再現部をカットすることになってはしまいましたが、なんとか予定していた曲をすべて演奏することができました。 10分ほどの休憩をはさんでの2時間10分。決して短い時間ではありません。お客さまには先生方だけでなく、コンクールに参加する小さな生徒さんもいましたが、皆さん最後まで集中して聞き入ってくださって感激しました。
終演後、「歳もいっておりますし、こういったものには随分いろいろ参加しておりますが、美奈子先生のは非常に分かりやすかったです。ありがとうございました」と、素敵なご年配の先生がねぎらって下さいました。「今日は福島市から来たんです。とてもよかったので…」と、私のCDを求めてくださった先生も。そうそう、毎度のように頂くお声に「写真やコンクールの会場ではお姿を拝見していましたが、外見のイメージと違って、ジツブツの美奈子先生はとても楽しくて気さくな方なんですね!」というものが…(え〜っと、なんだろう?すましてみえるのかしら?)。
でも、何より嬉しいのは小さな生徒さんの感想でした。片付けをすませ会場の外に出ると、女の子がお母さまと待っていて「先生、今日はたくさん弾いてくれてありがとうございました」と、まっすぐに私の目を見て言ってくれました。お母さま曰く「この子が“わたし美奈子先生みたいになりたい。美奈子先生に自分でありがとうって言いたい”と、きかなくて…」また、可愛い男の子が
とことこと近づいてきて「僕ね、今日先生が弾いてくれたソナチネを練習しているよ。ピアノは楽しいね!」と、話しかけてくれました。うん、そうだ、そのとおり!「そうね、楽しいよね。先生もピアノが大好き!これからもたくさんの素敵な曲を練習していこうね」
楽しい。そう感じることができるものに対して、その人は才能があるのだと考えています。母や妹は“面白い”と言ってまるでパズルゲームでもするように楽しそうに数学の問題を解いていましたが、私はそれを楽しいと感じたことがありません。また、子どもの頃は音楽を聴くのとピアノを弾くのが同じように楽しかったのですが、今は自分が弾くことの方ずっと楽しくなりました。毎日のように何時間も向き合っていますが、飽きることがありません。
正直にいうと、向き合うほどに、思いどおりに弾けないこと、難しいと感じることは増える一方なのです。でも、作曲家、演奏者、聴き手による幸福な三位一体がうまれることを夢見つつ、少しずつ理解と共感を深めていく喜びは、たとえ苦しさをともなうとしても手放せないものです。
楽、とは一般的に“心身に苦痛などがなく、快く安らかなこと”とか“たやすいこと。簡単なこと”という意味ですが、その字には音楽、調べ、という意味もあります。ある辞書には“楽器を用いた快い音曲。音楽”と記されています。それを見たとき、楽しい気持ちそのものがすでに音楽につながっているようで、嬉しくなりました。
そうそう。最近とても楽しくなってきたことの一つに、生徒さんのレッスンがあります。若い頃は、自分がまだまだ学び足りていないのに人に教えるなんて…と、どこか腑に落ちていないところがあったのですが、この頃は心から生徒さんとの時間を楽しめるようになってきました。教えることから教わること…つまり、学ばせてもらうことが多いことを実感するようになったからかもしれませんし、生徒さんのレッスンというよりも、音楽仲間と過ごす貴重な時間、という意識に近くなっているのかもしれません。ピアノは楽しい、と感じてもらうように導くことがどんなに大切かも、身にしみるようになりました。
ところで…逆に考えれば、楽しい気持ち、楽しむ気持ちを失ってしまっては、音楽にならない、ということにもなります。うむ。心していなければ!
■第656回 スーホの白い馬
最近、めっきり肉を食べることが減りました。冷蔵庫に一切の肉類が入っていない日々がかれこれ二ヶ月以上続いていますし、先日もよくよく考えてみたら一週間近く肉類を食べていないことに気づいて、あわてて食べたほどです。
今やベジタリアン、という単語を知らない人はいないでしょう。ところが、ひとくちにベジタリアンと言っても、かなりその内容は細分化(?)されているのだそうです。例えば、肉類だけでなく魚類も食べないストリクト・ベジタリアン。ニンニク、にら、らっきょう…といった、仏教で禁じられている五葷も食べないオリエンタル・ベジタリアン。肉・魚類、さらに卵も食べないけど、乳製品は摂るラクト・ベジタリアンに、肉類、魚類、卵、乳製品のいずれも摂らないダイエタリー・ベジタリアンなどなど。
ベジタリアンの中でもっとも厳しいヴィーガンと言われている人たちは、肉類、魚類、卵や乳製品、蜂蜜などの動物由来のものを一切食べないだけでなく、動物製品を身につけることすらしないし、化粧品も動物性のものが含まれないものを使っているそうです。「そこまでこだわっている人、いるの?」なんて言われてしまいそうですが、案外たくさんいらっしゃるようです。特にハリウッドセレブなどの芸能人、そしてミュージシャンにも多いのだとか…(もちろん、日本人も)。
彼らがヴィーガンになる理由は様々のようですが、そうなると通常の外食はまず無理でしょう。コンビニやスーパーのお弁当やお惣菜も難しくなるので、お仕事をしていらっしゃる方は特定の専門レストランを探すか、お弁当を持参することになります(余計なことだけど、お得意さまとの会食などのおりには、どうするのかしら…)。そして、靴、バック、コートはもちろん、時計のベルトに至るまで制約がかかります。もはやダイエットとか食生活、嗜好の問題ではなく、思想とか生き方の問題になってきます。
それを聞いて、ふと思いました。音楽家にもヴィーガンはたくさんいらっしゃいますが、彼らがもし、弦楽器奏者ならどうするのだろう?だって、演奏するときに右手に持つ弓は馬のしっぽでできているし、楽器に張っている弦だって、ガットといって羊の腸を伸ばしたものが用いられています。他にも、特に民族楽器には、三線の蛇の皮の例のように、動物の素材を使っているものなど
が多くあります。私も、子どもの頃には象牙でできたピアノの鍵盤を触っていましたし、チェンバロのジャックの爪も、ヒストリカルなものはコンドルや鷹などの羽でできています。
食の安全が叫ばれるようになり、様々な添加物や化学調味料、ひいては家畜の飼育環境やら飼料などの問題が取りざたされている今、ある程度の危機感と情報をもつことは、大切なことかもしれません。かくいう私も一時期、マクロビオティックなるものに興味を持って、勉強してみたことがありました。マクロビオティックの世界では、卵や動物類は勿論、精製してある砂糖や精米したごはんすら、よしとしません。さりとて野菜であればよいということでもなく、有機栽培にこだわり、徹底的にケミカルなものを排除しようとします。
動物を食べないことが悪いとは思いません。宗教上の理由や、特定の主義に基づいて、どんな選択をしようと自由です。でも、「自分たちが生きていくために動物を殺すなんて…」というだけの理由には少し抵抗を感じます。だって、植物だって生き物なのでは?食物連鎖を考えたら、生き物にとってはどれもそれぞれ、お互いに大切なのではないでしょうか。
それよりも、気になるのは食品ロスです。なんでも、日本で年間約1900万トン排出される食品廃棄物のうち、食べられるのに捨てられている食べ物…食品ロスは、年間500万トンとも900万トンとも言われています。動物であれ植物であれ、そんなにもたくさんのものが粗末に扱われる現況は、深刻です。
子どもの頃、大好きだったお話の一つに、モンゴルの民話『スーホの白い馬』がありました。スーホ少年がかわいがっていた白馬が、ある時矢にうたれて死んでしまいます。嘆き悲しむスーホの夢に白馬が現れ、「スーホ、元気を出して。そして、私の身体を使って楽器を作ってください」と言います。スーホは、白馬をつかって馬頭琴を作った…というお話です。
悲しいラストに、読むたび涙が出てきましたが、なぜか好きな物語でした。生命とは、絶望とは…そして、白馬を撃った権力者とは、いったいなんという存在なのか、子どもなりに考えを巡らせたように記憶しています。命あるものときちんと向き合うことで、人間も生き物としての天命を全うできるのだと思います。
何かを避けることよりも、どのように受け入れるか、受け止めるか、を大切に、責任を持って様々な選択を重ねていかなければ、と、思います。
■第655回 “さわる”をたのしむ
辞書や本、楽譜などにビニールのカバーがかかっていることがあります。わたしはそれがどうも好きじゃなくて、すぐにとってしまいます。本を広げるとたわんで邪魔になるし、しばらくすると薄汚れたり破れてきたりと、しょぼくれた感じになるのもその理由ですが、なんといってもその手触りがいやなのです。
手にしているのは紙(あるいは革?)の本のはずなのにその感触ではなく、代わりに買い物袋を持っているみたいな気分になるのは、いつも違和感です。楽譜に貼るフィルムシートもありますが、使ったことがありません。もちろん、それらを使えば汚れや劣化をある程度防げます。でも、そのためにある“汚れ役”アイテムはどれも苦手なのです。例えば、キッチンマット。キッチンの床は汚れるに決まっているのだから、マットなんてしかずに毎日ささっと水拭きする方がずっと気分がいいものです。コンロの周りに設置して油などのハネから壁を守る、アルミのレンジカバーも同じです。
スマートフォンのカバーも、つけていません。そそっかしいので、落とすことを想定し、衝撃に強いシリコン製のカバーを一時つけたことがありましたが、あのゴムのような感触が好きになれなくて、すぐやめました。汚れよけ、衝撃よけ、などの効用(?)は分かりますがそれがもつ質感を楽しむことにはかえられない、という結論にいたる性分のようです。
南インド料理を、現地と同じスタイルで頂いたことがあります。つまり、お皿を使わず、バナナの葉のうえにごはんや付け合わせ、薬味、そしてステンレス製の小さなボウルに入った何種類かのカレーやラッサムをのせ、それらをごはんにかけて右手で混ぜ、そのまま手で食べる“ミールス”です。
その時、カトラリーを使って口に運ぶのとのあまりの違いに、とても驚きました。結論から言えば、思ったよりずっと、美味しく楽しめたのでした。手を使うことによって、口に入れる前に食べ物の温度や固さ、食感すらも手で直接味わって、それを口の中にいれて改めて味わって…と、二段構えでじっくりと味わうことができたのです。「手で食べるなんて…」野蛮、とでもいいたそうに眉をひそめる人もいるかもしれませんが、私は反対だと思いました。医食同源…“食べることは生きること”と理解し、食べ物、そして食べることを大切にしているからこそ、自然に生まれた文化だと感じたのです。
最近、寝具のカバーを麻100パーセントのものに変えました。こちらも、かなりの違いを感じました。今までは、早く乾くからと、綿にポリエステルが入ったものを使っていたのですが、もうあれには戻りたくない、と思うほど気持ちのよい肌触りで、寝る前の至福度が増します。睡眠中は意識がないとはいえ、一日に何時間も触っているものなのに、なぜ今まで何も気にしなかったのでしょう。
気のせいか、子供用のプラスティックの食器を使わない、あるいはあまり使わない国は、美意識や食に対する意識の高い国のように思います。歩けるほどに成長した子供なら、器の感触や持った時の重みなどで、割れやすいものかそうではないのか、すぐに判断できるようになるものです。きちんとした食器できちんと食べることを学び、壊れやすいものを大切に扱っていくうちに、テーブルマナーはなぜ、なんのためにあるのか、自然に理解できるようになることでしょう。
そうそう、ずいぶん前にフランスに行った時、『さわってごらん』というタイトルの絵本を見つけ、友人のお嬢さんへのお土産に買ってかえってことがありました。ウサギ、馬、カエル…さまざまな生き物たちのイラストと、そこに上手に張り付けられたそっくりな感触の素材がよくできていて、タイトルの示すとおり触って遊びながら読み進めていく、楽しい絵本でした(ちょっとお高めだったけど…)。ドイツのシュタイフ社のテディベアノの素材には、今も素材には最高級のアンゴラモヘアやアルパカが用いられていて(*アクリルのものもある)、知人がそれを2歳の子どもに与えたところ、その子はそのぬいぐるみばかりを抱っこするようになったそうです。
手触り、肌触り、舌触り…。どれも、繊細かつ丁寧に意識していたい感触です。それに対して、同じ語感−———○○ざわり———でも字が異なる、耳障り、気障り、目障り、といった言葉は、できるだけ避けたい、よろしくない意味なのは、おもしろいことです。
話はそれますが、名伴奏者ジェラルド・ムーア氏の著書に『お耳ざわりですか』というのがあったっけ。伴奏だからと歌手に遠慮して小さな音で弾くのではなく、音楽に従ってのびやかに弾くことを大切さにしていた彼のメッセージがつまった、ユーモア溢れるエッセイだったように記憶しています。また読み返してみたくなりました。
■第654回 ショパンへの賛辞
生演奏を聴いてみたい故人を三人あげろ、と言われたら、バッハ、ショパン、リストと答えるでしょう。ラフマニノフやバルトークも聴いてみたくてたまらないのですが、彼らは一応録音が残っています。その点その三人の演奏については、聴いた人の感想からそれを想像するばかりです。
『音楽の父』として知られるヨハン・セバスチャン・バッハですが、信じられないことに生前は、人々の間で偉大な作曲家としての認識より、優れたオルガン弾き、という認識のほうが強かったといわれています。悪魔に魂を売り渡した、と思わせるほどの凄まじい腕前だった、という声も残っています。
ショパンもまた、たぐいまれなる演奏で人々を魅了しながらも、実際に人前での演奏を行ったのはわずかな回数だけでした。どうやら、ショパンはいやだったようなのです。「公開演奏をする前の三日間は、僕にとってどんなに辛かったことか」彼はリストに、舞台へ登ることの恐怖を打ち明けてもいます。「僕は演奏会をするには不適当です。聴衆は僕をおびえさせるし、彼らの物珍しそうな視線に接すると神経が麻痺してしまい、見知らぬ多くの顔の前に出ると僕は唖のようになるのです」
それでも、彼の演奏、そして作品は意識の高い人々に熱狂的に受け入れられました。「諸君、脱帽したまえ!彼こそ天才だ」という有名なセリフでショパンをパリの音楽界に紹介したのは、シューマンです。彼はショパンの才能に心底惚れ込んで、まるで恋に落ちたかのように激しく、のめり込むように惹かれたのでした。
リストもまた、そんな一人でした。ショパンの演奏会を聴いた彼は、その感想をある音楽雑誌に長々とレポートしています。その内容について、ショパン演奏の大家コルトーは彼の著書のなかで、「異常な記述なのにもかかわらず、その全文を引用しないわけにいかない」と前置いて、たくさんのページを裂いています。
「彼が公衆の前で弾いた例は極めて少ない。その才能の詩的な素質が、彼を公衆に近づけなかったのだ。夕刻なっていよいよ香り高い芳香を放つ花にも似て、彼の心の中で寛いでいる旋律の翼を自由に羽ばたかせるためには、平和な、瞑想的な雰囲気が必要なのだ。音楽、それは彼の言葉である。この世のものならぬその言葉によって彼は、少数の人々にのみ理解されるべき、感情の世界を表現する」
「公衆というよりも、社会のあるグループに向かって、彼はあるがままの彼自身————悲劇的な、深みのある、純潔で夢見るような詩人としての彼自身を示した。彼は驚かせようとも、人の心をつかもうとも思っていなかった。彼は燃え上がるような熱狂よりも、むしろ繊細な共感を求めたのだ」
特に前奏曲について「ショパンの前奏曲はまったく独自な範疇の作品である。これは、タイトルの示すごとく、他の作品に対するイントロダクションのようなものではないばかりか、現代の大詩人のそれにも等しく、黄金の夢の中に魂を静かに揺り、理想の領域にまで高揚させる詩的前奏曲なのだ。その多様性は感嘆すべきものであり、最初の一音からして飛躍であり、不意打ちである。まことにそれは、天才の作品の特徴たる自由と、堂々たる威容を示している」
当時、たくさんの人々を熱狂させることにおいては右に出る人がいないカリスマピアニストだったリストが、彼自身とは違うショパンの魅力、個性に触れて強く心を動かされた様子がありありと伝わってきます。彼は数年後にもこの演奏会を「彼は詩的な感情に新しい局面を拓いてくれ、かつ芸術の形式に喜ばしい革新をもたらした」と振り返っています。
ショパンの同郷の知人ルグーヴは、ルーアンで開かれた彼の演奏会について「これは音楽界における重要な一事件である。滅多に公衆の前で演奏しないショパン、魔法の島にも似たショパン、一度耳にしたらもう忘れることのできぬショパンが、500人の聴衆を前に演奏会を催したのだ」彼の興奮は続きます。「素晴らしかった!実に素晴らしかった!心を魅了する旋律、その演奏のえもいえぬ繊細さ、憂愁とともに情熱的な霊感。会場は電気にかかったような感情や、法悦と驚愕の囁きにみちた」
実は充分な体力が無かったショパンは、度々「彼はピアノから、ごく慎ましやかな音しか引き出せなかった」といった批評もされていました。彼の演奏にしばしば“繊細”という言葉が用いられるのは、そういった部分からかもしれません。ショパンの曲を弾くにつけ、何度となく「ああ、彼はここをどんなふうに弾いたのだろう」と思いが溢れます。天国の彼に喜んでもらえる演奏ができるようになるには、まだまだ勉強しなきゃ!もっともっと練習しなきゃ!…でも、意気込みすぎて、繊細なショパンに怖がられないよう、気をつけなくてはいけませんね。(引用=新潮文庫『ショパン』コルトー著、河上徹太郎訳 *一部変えてあります)
■第653回 めざせ!返答名人
されると困る質問、というものがあります。「なぜ離婚してしまったの?」も困ると言えば困りますが、最近は余裕?もでてきて、差し障りのない返答の仕方も覚えました。「好みの異性のタイプは?」これは困ります。よく、すらすらと答えている人を見かけて感心するのですが、私はどうにも答えようがありません。コルトーは限りなく好みのピアニストですが異性としてどうなのかは分かりませんし、たとえ外見は好みだとしても価値観が異なる人とは結局気持ちが離れてしまうような気がします。
でも、それよりもずっと困ってしまうのは、専門分野についての質問です。以前、このエッセイで「一番好きな作曲家はだれですか?」や「得意な曲はなんですか?」と聞かれるととても困る、ということをお話ししましたが、なかでも最も答えにくいのが、音楽畑にいない方からの「○○さん(ピアニスト)は好きですか?」という質問です。
基本的に嫌いなピアニストはいないのです。みなさんそれぞれが違う良さや個性、魅力をもっていらっしゃるし、尊敬しています。でも、コルトーやフランソワ、リヒテルのようなド級の名人は別として、一般的にひろく名前の知れているピアニストであっても「好き」という感情を抱かないこともありますし、それを正直に言ってよいものかどうなのか。
「好きです」と答えたら、相手の方は、私はそういう好みと価値観の持ち主なのだ、ととらえるでしょうし、場合によっては「プロのピアニストも好きなくらいだから、○○さんは知名度に見合った実力をもっているのだ」と理解することでしょう。だからといって「あまり好きではありません」と答えるのも、同業者に対して気が引けます。そんな時には「立派なピアニストですよね」と答えて、お茶を濁すしかありません。
その点、食べ物飲み物の好みを聞かれるのはずっと気が楽だと思っていましたが、最近ではそうでもなくなってきました。「美奈子さんが一番好きなワインって何ですか?」これも案外、困るのです。気候にもよりますし、どんなところで何を食べる時に頂くのかにもよるからです。その質問を受けると決まって「ええと…そうですね、時と場合によっていろいろで…」と、しどろもどろになって、要領を得ないことこの上ありません。
先日、近所で行われたワイン講座で、ワインのインポートのお仕事をしていらっしゃるOさんとお話しさせていただく機会がありました。そのとき、同席していた方がOさんにまさに同じ質問をしたのです。私は彼がどう答えるのか、興味津々でした。
「好きなのは、ビオワインのように、ストレス無く作られた雰囲気のワイン、です」ビオワインというのは、農薬は化学肥料などの使用をなるべくひかえた有機農法で、出来る限り自然のままの製法で作られたワインのことです。
「ワインって、日本酒などとは違って比較的シンプルに作られるものなんです。で、シンプルなだけに、その土地の気候や土壌、ぶどうの品種の持つ個性が素直に反映されやすいわけです」ふむふむ。「僕は、そこの畑の断片を味わえるような素朴さが、ワインの楽しさ、そして魅力だと思っているんですが、ワインって素直なあまり、作り手のストレスすら味わいにうつし込まれるようところがあるんですよ」ほお〜!
「大手の作り手さんと会って話をすることもありますが、彼らはなんというか…農夫というよりも、契約の交渉を淡々とこなすビジネスマンといった印象なんです。そこへ行くと、ビオでワインを作っていのは、本当に農家の人たち。自分たちが作りたいだけの量を、農薬や肥料で土やぶどうに無理をかけずに作っている。彼らにはビジネスマン的なストレスがあまりないように感じました。そういう作り手さんによって作られたワインには、やっぱりストレスがない、田舎育ちらしい素朴な味わいがあって…」Oさんは、高級なものよりも、そうやって健やかに育ったぶどうで愛情をかけてつくられた、のびのびとしたワインが好きだとのことでした。
う〜ん、なんてスマートな返答でしょう!さりげなく蘊蓄が盛り込まれているけど、ちっとも理屈っぽくありません。お話を聞いているうちにOさんのワインへの思い入れが感じられてますますワインに興味がわき、ワインを選ぶこと、味わうことが楽しみになってきました。
ああ、私もそんなふうに、質問に答える時には、相手を楽しませたりわくわくさせるような答えができる人になりたい!…新たな憧れを抱いた昼下がりでした。
■第652回 別れ、のち出会い
先日、春一番が吹きました。いつも思うのですが、春というのはなぜ、こんなに人騒がせな風とともにやってくるのでしょう。植木をなぎ倒し、電車のダイヤを狂わせ、びゅうびゅうと恐ろしいほどの音を立てて。しかも、三寒四温といわれるように、温かくなったかと思うとまた冷たい風をふきつけられて、着るものやらなにやらに人は翻弄されるばかり。春の到来はまさに、今流行っている(え?もう終わったの?)“ツンデレ”そのものです。
卒業式、離任式…。春というと別れの季節でもあります。でも、お別れにつきものなのは、個人的には涙ではなく、“出会い”だと思っています。旅立ちは、新たな出会いをもたらすものです。
ところで、このところ少しずつ部屋の模様替えをしています。これまでもカーテンやソファーカバーを変えるなどのマイナーチェンジは試みてきましたが、昨年末に和室の箪笥を処分したら、隣のリビングも変えたくなりました。
必然的にラックの中や山のような書物、書類などを整理することになります。そうするとだいたい、懐かしい写真だの手紙だのがでてきては、作業の手が止まって一向に捗らない、というのがお約束。ご多分に漏れず私もそうなってしまいました。ついに運命的な出会いが訪れ、電撃的に結婚を決意したことを知らせる手紙。妊娠を知って、地球がひっくり返りそうなパニックに陥って大騒ぎしている愉快な手紙。恩師からいただいた、味わい深い文字で書かれたリサイタルのご招待に対する丁寧なお礼の手紙。
どれも一字一字美しく生き生きとした肉筆で綴られ、眺めているとその方の姿や表情が目に浮かんで、自然に微笑んでしまいます。電子メールとは比べ物にならない価値を感じます。
そんな手紙の中には、生徒さんから頂いたお礼の手紙もかなりありました。東京の大学への進学が決まって、ピアノから離れることになった仙台の生徒さんからの手紙や、セミナーなどで教えた生徒さんからの手紙などなど。
中に、今は第一線で活躍する売れっ子フルート奏者になっている方からのものもありました。「先生の音楽に対する姿勢をこの三日間ずっと拝見することができ、本当に数多くの他切なことを学ばせていただきました。中でも“アンサンブル”とは自分と相手をぴったり合わせるものではなく、お互いのよさを受け入れ、混ぜ込んでいくものであるという考えには、とても刺激を受けました。相手に染まるのでも依存するのでもなく、互いが個として確立し、互いの個を認め合う、そんな関係の先に築かれる音楽はどんなに美しく、魅力的なものになるだろうと思います。」
アンサンブルはまさに、人間関係そのものです。数枚にわたって、彼女が感じたことが細やかに書かれていましたが「手紙には書ききれないほどに、まだまだ先生に教わったことは沢山ありますが、何度も何度もメモを読み返して、早く自分の中に吸収できるよう、頑張ります」と結ばれていました。
また、大学受験ぎりぎりまでレッスンを受けながらも、目指す東京の大学に見事合格した仙台の生徒さんから「美奈子先生にレッスンを受けるようになってからの6年半の間、ピアノを演奏する技術だけでなく、レッスンを通して精神面においても幅広い知識を得ることにおいても、大きく成長できたと思っています。特にここ1、2年は以前よりもいっそうピアノを演奏することに大きな喜びを感じ、毎週のレッスンを本当に楽しみにしていました。レッスンをやめなければならないことは、私にとってあまりにも苦しいことなのですが、今までも沢山の積み重ねを決して無駄にすることなく、ピアノを生涯弾き続けていきたいと思っております。」彼女はお母様と最後の挨拶にきたとき、ほろり、ときれいな涙をこぼしていたっけ…。
古い家具とお別れするにあたって、すてきな手紙たち、そして大切な友人たちの当時の思いとの“再会”を果たすことができました。明後日から、新たな家具との新たな毎日が始まります。これまで20年以上使い続けてきた家具への愛着は、新しい家具に引き継がれることでしょう。
春一番は、冬までに積もりに積もったストレスや余計な心配事を一掃して、新たな春を清々しく迎えるために、あんなに強く吹くのだ、という気がしてきました。今年も春もまた、新鮮な感動や楽しい出会いをたくさんもたらしてくれますように。
■第651回 ある万年筆への愛着
無くしたとばかり思っていた懐かしいものが、ひょいと出てきました。かつて愛用していた万年筆です。
それは高級品でもなんでもなく景品としてもらったもので、メーカーもわかりません。でも、カートリッジ(これも一緒に出てきました)を差しこむと、まもなくペン先からすらすらとブルーブラックの線が流れでてきました。「わあ、まだ書けるんだ!」思わず、声を出してしまいました。
何を隠そう、小学生の頃から大人になって結婚するまで、毎日日記をつけていました。あるときは数行で終わりでしたが、あるときには数ページに及びました。ひたすらお目当ての音楽大学入学を目指していた高校時代、初めて親元から離れて過ごした大学時代、そして当時まだ共産圏だったハンガリーのリスト音楽院留学時代…。毎日、一日の終わりにはその日の出来事や感じたことを、日記に綴っていました。
出てきた万年筆は、中学入学祝いに旺文社から頂いたものでした。月刊誌の購読キャンペーンか何かのプレゼントだったと思います。中学時代から大学を卒業するまでのあいだ、日記を書くときは主にそれを使っていました。もともと景品のクオリティ。安っぽさはいなめませんし、傷だらけで見栄えはよくありませんが、ペン先はしっかりとしていて書き味は悪くありません。Obunsha という文字が刻み込まれているのも、きちんと見て取れます。
ハンガリー留学時代は、かの地の文房具はあまり質が良くなくて品薄にもなりがちだと聞いていたので、日本からパイロットのごく一般的な、100円ほどで買えるボールペン一本とカートリッジ一ダースを持っていき、インクがなくなってはカートリッジを入れ替えて大切に使っていました。日記と沢山のエアメールのため、二年弱のあいだに12本分のインクはほとんど消耗されました。でも、ボールペン“本体”は壊れることなく日本に持ってかえることができました。
「美奈子ちゃんは“物持ち”がいいね」と、たまに言われます。確かに、20年以上前に買ったスカーフを今も愛用していたり、靴ですら10年前のものをまだ履いていたりします。ファッションに関するものは流行もあるのでちょいちょい買い足していますが、それでも、お気に入りのロングコートは愛用歴13年。
基本的に気に入ったものを長く使う方が好きなのです。物がいたずらに増え、家の中が圧迫されるのも極力避けたいほうです。
触った感触が心地よく、古くなってもできるだけみすぼらしくならないもの(むしろ、古くなって味わいを増すもの)が好きなので、プラスチックや樹脂のコップなどは自宅では決して使わず(たとえ洗面所でも!)、洗剤や液体石けんも、陶器の入れものに詰め替えています。一つのものを使い倒して、いよいよだめとなった時に次を買い求めるので、筆記用具も足りているうちは自分用には買いません。
このところ、身近な人が万年筆を素敵に使いこなしているのを目の当たりにすることが重なり、「万年筆…やっぱり、いいなぁ。ひとつ、適当なものを買おうかしら…」と思っていました。で、あれこれ見始めていた矢先にそれが出てきたものだから、今、新しいものを買うのをためらっています。だって、新しい万年筆を使うようになったら、この子は使われることがなくなり、そのうちにまた忘れられてしまうかもしれないでしょう?せっかく出てきてくれたのに、そうやって使われるでもなく捨てられるでもなく過ごさなければならないなんて、もしわたしがその子ならそんな哀しいことって、ない…と、思うのです。
そんな話をある人にしたら「美奈子ちゃんはやっぱり、1人にとことん“尽くす”タイプなのね。反対に、そういうものを次々に買い求める人って、1人では飽き足らず浮気をしたり、愛人を何人もつくったりするタイプが多いんですってよ。だけど、景品にそんなに愛着が湧いちゃうなんて…。美奈子ちゃん、つまんないオトコにつかまらないように気をつけなきゃ。相手をよーく見定めて…ね!」と、ぽんっと肩を叩かれてしまいました。え〜?男性は、選ぶ車に好みの女性像が反映されやすい、という話は聞いたことがありますが、ペンや万年筆がそうだなんて…?
いずれにしても、愛着は私にとって、とても大切なものですし、これからも大切に育んでいきたいものです。だって、音楽、故郷、お気に入りのものたち…愛着を抱く相手は、私にとてもあたたかなパワーを与えてくれるように感じるんですもの。
■第650回 熱出(いで)て意思かたまる
数日前、久しぶりに熱をだしました。熱自体よりも辛かったのは、身体の節々がまるでトンカチでごんごん叩かれているように痛み、身体が言うことをきかなくなること。そして、何を何枚重ねても身体がガタガタふるえるほどの悪寒が止まらないことでした。
そんな時は「病院に行きなさい」といわれても、「病院に行けるほど“元気”ないんだもん」と返すしかありません。実際、高熱でぐったりしているときは顔を洗うのもやっとなのに、外に出るなんて無理!病院の待合室でじっと診察を待つほどの体力レベルになるまでに、しばらく時間がかかります。
こんな時、つい気弱になろうものなら病魔の思うツボ。あいつときたら、人を不安に陥れさらなるダメージを加えることに生き甲斐を感じている、とんでもなくブラックな魂の持ち主なのですから。そこで、横になってうんうんうなりながらも、果敢に口に出して宣戦布告します。「こういう時こそ、楽しいことを妄想して自力で病気を退治するぞ!」
「私、声に出して言ったことは、次々現実になるの」真顔でそんなことを話してくれる友人が、何人かいます。それも、結婚したいとか転職したいとか、そんな一般的な類いのことではなく、周囲からあきれられるような“突拍子もない”ことなのにもかかわらず、というのです。
ある友人曰く、「私ね、前から自社ビルを持ちたいと思っていたの。思っているだけじゃなく、レイアウトをあれこれ考えて、一階にはなに、二階にはなに、フリースペースはこんな感じ、屋上からは花火が見えるよう、東方向には目の前を遮る建物がないか、建てられない場所で…みたいに、なるべく具体的にイメージをしていたのよ」別の友人曰く、「音楽ホールを持つのが長年の夢だったの。それも、家の中のサロン風なスペース、というのではなくて、きちんとした響きのある500人くらい収容できる、音楽専用ホール。で、私がコンサートの企画をしたり、出演者を検討して交渉したりする、音楽監督的なポジションを務めるの」(あら?偶然にもどちらも女性!)
そして彼女たちは、形がどうあれ若くしてその夢を現実にしてしまったのです!「形?そんなの、思っていたのとまったく同じじゃないからこそいいのだし、面白いのよ。思っていたとおりではつまらないでしょう?そしてね、
それを思っていた以上のものに育てていくの!」
ポジティブな人は、キラキラと輝いてみえるものです。最近、つくづく思うのです。どんなにきれいにメイクしても、どんなに素敵なファッションに身を包んでも、夢の実現を信じている人がポジティブな言葉を発する唇と、その時の笑顔の魅力にはかなわないのでは、と。彼女はこうも言っていたっけ。「もう、ね。したいことはどんどん声に出して言うの!そうすると、大体かなうものよ。ほら、美奈子ちゃんもどんどん言って言って!」・・・
「そうだなぁ…」ベッドの中で、おずおずと声に出してみます。「被災地での演奏の機会が、もっと増えるといいな。そして、人の心に寄り添う演奏ができるようになりたい。聴いている人が、その時ばかりは他のことをすべて忘れて、ただ音楽から幸せを授かってくれるような。…そのためは楽器と“格闘”しないピアノ弾きにならないと。向き合うけど、格闘はしないの。作品と楽器と私が自然に一つになって、それによって周りが幸せになってくれたらいいなぁ」
う〜ん。夢といえば夢だけどソフト面ばかりで、彼女たちみたいなハード面に何も具体的なものが浮かびません。スケールも小さいみたい。きっとその辺りに、着々と前進している彼女たちと相変わらずの私の違いがあるのでしょう。
「東日本大震災は2万人が死んだ一つの事件ではなくて、1人が死んだ事件が2万件あったと考えるべきだ。この震災を『2万人が死んだ一つの事件』と考えると、被害者のことをまったく理解できないんだよ。人の命は2万分の1でも8万分の1でもない。そうじゃなくて、そこには『1人が死んだ事件が2万件あった』っていうことなんだ」
昨日、北野武監督の談話を見てハッとしました。「忘れてた!ずっと夢みてたこと、あったー!」それは、映画と関わってみたい、ということでした。もちろん、音で、です。それも単なる劇中の音楽ではなくて、タイトルバックに流れるような、作品そのものの印象を左右する重要なところで聞こえる曲で…。
さ、言ったぞ。あとはもっと具体的にイメージを膨らませながら、いつ実現するのか楽しみにするとしよう!でも、その前にちゃんと体調を整えなくちゃ、ね。
■第649回 ライブ・アライブ・マイライフ
場所にもよりますが、都内の場合、だいたいの音楽ホールは二年前から予約ができることになっています。土日や祝日などは、解禁日の解禁時間に予約が埋まってしまうどころか、抽選になることも珍しくありません。
ということは、「ここ!」というホールをどうしても押さえたい場合、二年前には日程を決めておかなければならないことになります。とはいえ、ホールだけ決めるのは難しく、例えばバッハのようなものならこういう響きのところが望ましい、とか、こういうプログラムならAホールよりもBホールの方がピンとくる、なんてことが絡んでくるので、ある程度の内容も決めておかなければなりません。
「再来年かぁ…。私、それまで生きているかしら」先日、同い年のある演奏家と、お互いの今後のコンサートの予定について話し合っていたときに、彼女がふっとつぶやきました。それが、冗談っぽくもなく深刻なふうでもなく、さらっと自然な感じで発せられたので、ちょっとドキッとしました。
もちろん、この長寿国にあってまだまだそんなことを心配するような歳には至っていませんが、人間どこでどうなるかわかりません。「まだこの曲を弾く歳には至っていないから」と遠慮していたら、結局弾かないまま生涯を閉じることだって、ありえなくはありません。
大好きな詩人が、先月から今月にかけてお二人、亡くなりました。お一人は1926年生まれの吉野弘さん。教科書に載っていた『夕焼け』という詩がとても印象的だったのでお名前を覚えていましたら、数年前に彼の『祝結歌』に出会い、ますます好きになりました。“人が睦まじくいるためには 愚かでいるほうがいい”という出だしで始まるその詩に胸を打たれ、このエッセイでも紹介しました。
そして、今朝お亡くなりになったまどみちおさん。吉野さんも長生きでしたが、まどさんは享年104歳でした。『ぞうさん』『やぎさんゆうびん』『おさるがふねをかきました』『一ねんせいになったら』…。まどさんの詩による動揺はどれも優しさとユーモアに溢れていて、一度聞いたら身体にすっと入ってくるような、しなやかな語感がありました。歌うたび、言葉とメロディーの幸福な出会いを感じて、どんどん音楽が好きになっていきました。
作曲家も詩人も、後世に作品が残ります。その点、演奏家は残すことができません。もちろん、CDなどの媒体には残すことができますが、演奏家の本領が発揮されるのはなんといってもライブです。コルトーにはたくさんのレコーディングがあって、かなりの演奏を聞くことができますが、たとえCDを1000回繰り返し聴いたところで、1回の生演奏に触れる幸せには及びません。
命が絶える日がくるまで、当人の納得のいくレベルを維持し続け、よいコンディションでステージにあがれるのは、ごく僅かな選ばれた人だけ。となると、私がステージに立てる時間は、案外残り少ないのかもしれません。やりたいことは積極的にやっていかなければ…。
若い頃は、さまざまなレパートリーをこなし、ある程度の評価を得ることがまずは大切、と考えて、できる限りいろいろな作品を演奏してきました。ソロだけでなく、デュオやトリオなどの室内楽や協奏曲や、新曲の世界初演などもさせていただいたりチェンバロを弾かせてもらったり。とてもめぐまれた経験を重ねることができたと、感謝しています。
でも、最近は本当に追求したい作曲家は、それほどたくさんではなくなってきました。あれこれ…ではなく、一人一人の作曲家や、一つ一つの作品を深く掘り下げていきたい。という気持ちの方が強くなってきました。
6月のオールショパンのリサイタル。そして、その後予定されているヨーロッパではない国の作曲家たちによるいくつかのコンサート。プログラムはそれぞれ、今とても心惹かれている作曲家によるものばかりです。
与えられている命に感謝しながら一日一日を大切に積み重ね、本番当日には平常心で楽器と向き合えるようになっていたいものです。
■第648回 気になる言葉遣い
どうでもいい些細なことなのに、気になってしかたがない、と感じることがあります。職業柄、こと音楽においては特に多いようです。
スーパーマーケットで流れているクラシック音楽のアレンジが陳腐だったりすると、さっさと用をすませて一刻も早くその場から立ち去りたくなりますし、フィギアスケートの音楽がオリジナルの作品を切り貼りしたものだと、選手の演技よりもそちらばかりに気を取られてしまったり…。好きなメニューがあるお店で食事を楽しむも、そのお店にかかっている音楽の傾向がどうしても好きになれないために、やがて行かなくなってしまった、ということも少なくありません。
最近は音だけでなく、言葉遣いが気になることも増えてきました。例えば、何か食べ物を注文したあとに確認される「ご注文は○○でよろしかったでしょうか?」という言い方(なぜ、簡潔に「よろしいでしょうか?」と言わないのだろう?)や、注文したものを持ってくるときの「○○になります」という決まり文句(「○○です」とか、「○○をお持ちしました」とか、いろいろ選択肢はあるはずなのに、よりによってなぜ“成る”なのか?)。「○○のほう」という言葉が本来とは違う使い方をされているのもよく耳にします。「お品物のほうになります」「店長のほうにお伝えします」なんて言われると、もう頭の中は「?」でいっぱいです。
買い物をするとき、店員さんに「五千円からお預かりいたします」といわれることがあるのですが、それもまた「え?五千円から、何を“預かる”の?」と、気になってしまいます。“預かる”のは五千円なのだから「五千円、お預かりいたします」。もし、どうしても“から”をいれたいなら「五千円から頂戴いたします」になるのでは?
政治家すらも頻繁に発言する「今の現状を…」というのも、ひっかかります。そもそも“現状”は、現在…今、のありさまをいうのに、なぜわざわざ“今の”をつけ加えるのか。それでは、“外人の人”とか“頭痛が痛い”などというお笑いのフレーズと変わらなくなってしまいます。
会話だけではありません。メールなどで「こんにちわ」「こんばんわ」という書き出しも、よく見かけます。若者同士や親しい友人同士で、わざとくだけた感じを演出しているのならいいのですが、仕事などオフィシャルなものや、目上の方へのメールにも、見かけることが増えました。
以前は、「だからぁ〜」、「日曜日はだめだしぃ〜」のように語尾をのばすのが流行ったこともありましたが、近頃は流行語とか流行の話し方云々というよりも、言葉のつかいかたそのものが乱れているように感じます。言葉のエキスパートでもない私が気になるくらいなのですから、その道のプロの方々の違和感はいかばかりかと思います。
2020年の東京でのオリンピック開催に向け、英語教育を充実させる動きなどが報じられています。子供への英語の授業を英語だけで行うメソッドなども提案されているようですが、とんでもないことだと思います。正しい日本語の文法もまだきちんと習得していない児童にいきなり外国語を外国語で学ばせるなんて、とても意味があることとは思えません。
かくいう私も、レッスンで生徒さん(子供)と接するときに、きちんとした日本語を話しているか、と聞かれたら…情けないことに、まったく自信がありません。レッスンの雰囲気が厳つくならないように「お!いいね、いいね」などと無粋な言い方をしたり、緊張をほぐして笑わせたいあまり、あえて「あ、またキョドってる〜」などと流行語をつかってみたり。
でも、考えてみたら言葉と音楽とは、密接な関係があるものです。ハンガリー語のアクセントはそのままハンガリーの民族音楽に反映されていますし、フランス音楽のフレーズにはリエゾンを彷彿とさせるものが息づいています。
音楽を奏で、語り、伝えるものとして、言葉をもっと大切に扱わなければ…。フィギュアスケートの中継をみながらそんなことを考え、反省したのでした。
■第647回 春よ来い
「現在、5センチの積雪です!」「無駄な外出はなるべく控えてください!」「転倒を防ぐため、歩くときには歩幅を小さくして…」今日も、雪。テレビではアナウンサーが一日中、叫ぶように呼びかけています。雪国では当たり前の日常が、ここでは大ニュースです。
事態は深刻です。雪のために交通網は乱れに乱れ、ビジネスにも支障を来たし、何千世帯もが停電。物流が麻痺することを恐れる人たちが買いだめに走り、スーパーもコンビニもパンやお惣菜の棚は品薄状態。まさにパニックです。
自然に溶け、蒸発してしまうただの雪に、首都圏の都市機能が麻痺。多くの人の生活も振り回されました。ここでは想定されていないほどの寒波だからとはいえ、自分も含めて、雪に対するあまりの無防備さに失望感が否めません。
周囲には、慣れない雪かきに筋肉痛になり、やっと収まったと思うとまた降り積もる雪に辟易として、「いい加減にしてくれ」と怒りをあらわすひとも少なくありません。厳しい寒さを、それを当たり前としてじっと耐え、一年の半分近くものあいだ来る日も来る日も黙々と雪かきをして過ごさなければならない場所での生活の大変さは、いかばかりかと思います。
「おらほの土地では、一年のうち、半分は雪があることが前提。んで、あとの6ヶ月に春と夏と秋の三つの季節が凝縮されんだよ」ある、北国の人がそんなことを話してくれたことがありました。北国の人たちが我慢強いのは、自然と向き合う中で培われた必然なのだとつくづく思いますし、改めて尊敬します。「だけっども、我慢は必ず報われっからね…」その地の春の美しさはまさに桃源郷のような素晴らしさで、こらえた寒さの分だけ喜びも大きいといいます。
かくいう私の故郷にも、それはそれは美しい春がやってきます。まず、雪の間からフキノトウが顔を出すのを見つけると、みんな大はしゃぎ。北国では、フキノトウは春を告げる妖精のような存在なのです。やがて、それまで枯れたようになっていた枝いっぱいにキレンギョウが色を添え、ユキヤナギがそれに続き、桃や梅が次々に目覚めます。長い間水墨画のようにモノトーンだった世界が、黄、白、ピンクや紅といった色彩に溢れかえり、生命を謳歌する小さな花々たちに誘われるように、木の葉が次々に芽吹き始めるのです。
その頃になると、外にいるとどこからともなく花の香りがするようになってきます。そして、雪で覆われていた山々が、今度は赤ちゃん葉っぱの、薄緑というよりも白に近い、なんとも初々しい色に包まれるようになるのです。故郷の人々はそれを、春の喜びをこめて「山笑う」と呼び、毎日のように変化していくその色や表情を愛でるのです。
千葉に住んで、10数年。私もいつの間にか、新年になるとまもなく水仙の花が咲きはじめ、菜の花の便りが届き、梅がほころんで新タマネギがスーパーに並ぶのが普通のことと感じるようになっています。気候に恵まれた千葉は、夏は少々暑いけど冬はさほど厳しくなく、一年中おしなべて過ごしやすいのですが、それも当たり前に思うようになっていました。
でも、雪から喝をいれてもらい、少し背筋がしゃんとなった思いです。冬の寒さを乗り越えてからこそ、春のありがたみもたくさん享受することができるというものです。
「多くを望んではいけないよ。思い通りにならないこともあると、理解していなさい。そして、今あるものに感謝をしなさい」雪に、そう諭されたような気がしています。
さて、今回、滅多にないできごとに翻弄されるどころか、それを存分に楽しみ尽くした“勝ち組”は、子供たちでした。大雪の翌日はいたるところに雪だるまやかまくら、雪のすべり台などの作品がみられ、街がちょっとした雪のギャラリーのようになりました。親子や兄弟で雪投げして遊んでいる姿は、とても微笑ましいものでした。
何かあったときに、それを辛いと感じて生きるも、楽しいと感じて生きるも、自由。ならば、子供たちを見習って、後者でいたいものです。
■第646回 きたれ、楽友!
歳を重ねるにつれ、感謝できることが増えてきたように思います。若い頃はそれが当たり前だと思っていた自分の健康な身体に。好きなことを思う存分やらせてくれた両親に。あるいは、今もなお変わらない友情で心からの支えになってくれている学生時代の友人たちに。そして、好きな音楽への情熱が今なお色あせない、自分の単純さに。
最近いっそう強く感じるのは、周囲の人たちへの感謝です。例えば、かけ出しの頃はこんなにも生徒さんに恵まれるなんて、想像もできませんでした。私にとってピアノの生徒さんは単なる“お弟子さん”ではなく、共に一対一の濃密な時間の中でセッションを重ねる、大切な音楽仲間。時には、レッスン中にいろいろなお話をさせていただく中から、思いがけない示唆をいただくこともあります。
生徒さんはみんな、大好きです。近頃は「こんなに好きな人がたくさんいるのに、さらに好きな人を見つけて結婚したい、なんて、あまりに欲深いことなのかも。できなくても仕方ないのかも」なんていう考えも、よぎるようになりました。う〜ん、これは悟りのなか、諦めなのか…。
先日、美しいキャリアウーマンにして二児の母Yさんのレッスンで、ひょんなことから「最近の若い女の子は細すぎる」という話題になりました。彼女にはお年頃のお嬢さまがいらっしゃるのですが、ちょっとぽっちゃりしていてチャーミングなのに、ご本人はそれをコンプレックスに感じて、もっと細くなりたいと日夜嘆いているのだそうです。
「女の子らしい体つきがとっても可愛いらしいのに、言ってもわかってもらえないんですよね。周りの子がみんな細いから…」かくいう彼女は、実に女性らしい素晴らしいプロポーションの持ち主。ファッションもぬかりなく、指先のネイルも完璧で、いつもほんのりといい香りが漂っていて同姓ながら惚れ惚れとしてしまいます(旦那さまは幸せだろうなあ)。
そんなYさんご自身が体重を気にしたことは、人生の中で一度もないそうです。「若い頃からずっと、食べたいだけ食べているんです。美味しくて楽しいことが身体や美容に悪いなんて、思いたくないし、身体にいい我慢なんて、興味がない。でも、自然に若い頃のようには量をたくさん食べられなくなりました
ね。体重は気にしたくないから健康診断の時以外は測りませんけど、数字に一喜一憂して食事を気にするなんて、絶対いや。それでも極端に体型がかわることもないし、私はこれでいいの」
う〜ん、かっこいい!過去に、不自然なまでに体重が落ちて周囲に心配をかけた経験がある私には、彼女の堂々と筋の通った女優級の女っぷりが、まるで女神のようにまぶしく輝いてみえます。
彼女のみならず、小さな生徒さんも大人の生徒さんも、みなさん個性と才能豊かで一緒に時間を過ごすのが楽しみな方ばかり。それだけでも感謝すべき恵まれたことなのに、今年に入ってさらなる野望がふつふつと湧いてきています。第642回のエッセイでちらっとお話しした『大人のための音楽塾』の復活です。
それは、楽器を離れて生徒さんたちと音楽のお話をしたり、とっておきの音源を聴いていただいて感想をのべあったり、お勉強のあとにティータイムをご一緒したり…、と、“塾”とはいってもリラックスしながら学べる、楽しいひととき(と、願っています)。「準備が大変でしょう?」という友人もいますが、私にとって資料を用意したり、お話しする内容を時間の配分を考えながらあれこれと検討するのは、心からわくわくすることなのです。
なるべく気兼ねなく行うためにも、以前にように他の場所をお借りするのではなく、自宅でやってみよう、という考えに至りました。そうすれば場所にかかる費用を抑えることもできますし、受講生の皆さんと、もっと和気あいあいとした時間が過ごせるような気もするのです。
開講と受講生募集のフライヤー製作は、大好きなデザイナーさんにお願いすることができました。来月の今頃には、皆さまのお目にかけられる予定です。音楽塾の名前は“MUSICAVITA”(ムジカビータ)。イタリア語の、音楽MUSICAと、人生VITAを掛け合わせた造語です。人生の一ページを、よき音楽とよき仲間——−楽友——−とご一緒できる日が、今から待ち遠しくて仕方ありません。
■第645回 弦が切れた!
こちらのエッセイでもしばしばご紹介しているように、私の愛器はウィーン製のベーゼンドルファーです。制作されたのは20数年前だと思われます。
ベーゼンドルファーは世界三大ピアノの一つですが生産台数は少なく、それだけに価値もあると考えられこともあります。評価の高さで双璧をなすスタインウェイの、十分の一ほどしか作られていないのです。部品の数、加工など制作のための複雑な工程も多く、たくさんはとても作れないとのことです。
視覚的に特筆すべきなのは、内部の金属フレーム塗装の美しさ。何度も重ね塗りを施すのだそうです。コンサートホールで弦楽器の木の色とマッチするまろみのある絶妙な色合いを出すために、何度も重ね塗りを施すのだそうです。でも、私にとってそれよりも重要度が高いのは、なんといっても響きです。ベーゼンドルファーの響きの特徴とその素晴らしさの秘密は、ふくよかな低音にあります。
ピアノは低音になると弦が長くなるので、そのままではピアノの外側の“箱”に収まりきれません。そこで、コイル状に巻くことになるのですが、その“巻き”をベーゼンドルファーは今もって手で作業しているのです。手巻きなのです。
大変に重要にして高い技術を要する工程なので、熟練のマイスターがそれにあたることになります。巻く人が変わると、おやっと思うほど響きの違いが出てしまいます。
実際のところ、名匠と言われた方が退職なさってからベーゼンドルファーの響きが変わってしまった、と嘆く声がたくさんあがりました。私はその方の現役時代の楽器をある方に探してもらい、幸運にも手に入れることができました。
その名匠渾身の手巻きの弦が、昨日一本切れてしまいました。場所はFの最低音。ベーゼンドルファーではコイル状の一本弦になる、はじめの音です。もう二度と、同じ弦は手に入れることができないと思うと切なくなってしまいましたが、そんなことがきっかけでふと、音楽史上歴史的なある出来事を思い出しました。“タングルウッドの奇跡”です。
そのストーリーを話してくださったのは、高校時代の音楽の恩師H先生でした。それは、14歳のあるヴァイオリニストが、アメリカのタングルウッド音楽祭でバーンスタインの指揮するボストン交響楽団と共演した時のこと。演奏中に弦が切れてもまったく動じずに、コンサートマスターから借りたストラディヴァリウス(当時、小柄な彼女が身体の大きさに似合わせて使用していた四分の三サイズより大きな、四分の四サイズの!)に持ち替えて演奏を続けるも、またも断線。今度は副コンサートマスターのガダニーニを借りて見事に最後まで弾ききり、バーンスタインが彼女に驚嘆と尊敬の意を表してひざまづいた、とういうお話でした。その少女の名前は五嶋みどりさんです。
それから数年後、偶然にもアメリカで彼女とお会いする機会がありました。ステージ上の圧倒的な存在感からは意外に思われるほど小柄で、気取りのないチャーミングな方でした。当時はまだ赤ちゃんだった彼女の弟の龍君(今や彼もまた、押しも押されぬ人気ヴァイオリニスト!)が可愛くて仕方がないようすで、ずっと抱き上げたりあやしたりしていた姿が印象的でした。
彼女は今年、アメリカ音楽界最高の名誉といわれているグラミー賞の最優秀クラシック・コンペンディアム賞を受賞されました。素晴らしいことです。考えてみると、偉業を成し遂げた方は皆、アクシデントやピンチに怯むことなく、それを大きなチャンスにしてしまう強さを持っているように思います。もちろん、運の強さもあるように見えますが、悪運すら逃げ出してしまうほどの精神力とひたむきな向上心を持っている、ということなのでしょう。
大切な弦が切れてしまったのは残念なことですが、もしかするとこの弦が、私に降りかかるはずだった凶運の身代わりになってくれたのかもしれません。そう考えると、悲しみよりも感謝の気持ちがわいてきました。きっと、これからよい方向が見いだせる…、そんな希望とともに。
■第644回 バーチャルリアリティーより、リアリティーを!
ツイッター、フェイスブックなどのSNSが広く親しまれるようになって、どのくらいになるのでしょう。
いまさらですが、SNSとはソーシャル・ネットワーキングサービス、の略。インターネット情の交流を通して、人と人とのつながりを促進、構築するサービスのことです。
それを通じて、何年も音信が途絶えていた友人とウェブ上での再会を果たし、交流を再開できたり、友人のつながりから思いがけないご縁がひろがったり…と、今のところ私は楽しく利用していますが、それがきっかけでコミュニケーションやプライバシーに不審をつのらせ、大きなストレスを感じてやめてしまう人も、少なくありません。
自分の投稿に対する知人の反応を気にしすぎて、仕事や日常生活に支障をきたす“フェイスブック鬱”なる症状を抱える人が増えたり、思わぬプライバシーの侵害を受けて大変な思いをされたケースも聞きます。なりすましなどの偽装や誹謗中傷によるトラブルなどの被害も、毎日のように報告されています。
電子メールが手書きの手紙に成り代わり、文字の表情から相手の方の人柄を感じるとることもめっきり少なくなりました。声の代わりに、ラインやスカイプなどのチャットによって、お互いの感情を伝え合うことが主流にすらなってきていますが、最近、ウェブ上でのコミュニケーションには、やはり限界があるように感じ始めています。
演奏だって、CDと生演奏ではまったく伝わり方が違うもの。家で手軽に聴くのではなく、スケジュールを調整し、身支度をして会場に“出かける”こと自体のわくわく感も、コンサートの感動の重要な成分になったりするのです。
最近、SNSからではありませんが、ふとしたことからブダペスト時代の知人との交友が復活しました。ブダペストにいた頃の思い出話に花が咲く中で、当時共産圏だったハンガリーで便せんを買うのにも一苦労したり、手紙を書きすぎてすぐにインクを使い切ってしまうので日本からカートリッジを送ってもらっ
たり、せめて美しい記念切手を貼って手紙を出そうと郵便局をちょくちょくのぞいては着々とストックしていたことなどが、懐かしく思い出しました。
アパートメントには電話がなかったので、友人との連絡手段は音楽院の掲示板、あるいはメモを置きに直接家にいったりするしかありませんでしたが、アパートメントでの一人の時間は、テレビやオーディオをつけなければ静寂を確保できました(通りを走る市電はうるさかったけど)。ウィーンやパリにすむ友人は、ドイツやフランスなどの輸入楽譜も手に入らず、通信手段も限られているハンガリーでの生活を「不便でしかたないでしょう?」と、心配してくれましたが、そんな環境でピアノの練習に集中できたのは、むしろ恵まれたことだったように思います。
「年賀状は、宛名を手書きする」という話をした時、「私も同じ!正直言うと、できれば電子メールも極力使いたくないアナログ人間なの」と、言っていた大学時代の友人が、最近あるSNSをやめました。「もとの私に戻るわ」という言葉と一緒に。文学にも食にも美学をもっている、ピアニストとしてだけでなく女性としてもステキな彼女は、私よりもずっと深く、ネットによるバーチャルコミュニケーションに違和感を感じていたようです。
便利なものには必ずマイナスの要素があるものです。時流に従うだけでなく、便利さがもたらすご利益とマイナス要素を理解した上で判断、選択することが大切なのでしょう。(ちなみに、母は“お掃除ロボット”は使わない、と決めたようです。曰く、「手で拭き上げたときの気持ち良さには至らないでしょうし、第一自分が動いた方が身体にもいいから」)
もし、家族や友人たちとウェブ上でしか会ったり話したりすることができなくなるとしたら、あるいは、レッスンがリアルではなく、ネット環境などを介してのバーチャルレッスンになってしまったら、そんな心寂しいことはありません。
生演奏に触れて何かを感じ取ってほしい、演奏者と同じ空間の中で何かを共有してもらいたい、と願ってやまないピアノ弾きとしては、世間がどうなろうと、これからも「生(リアル)」にこだわっていきたいところです。
■第643回 憧れのアルゼンチン
芸術家というと、神経質なほどの厳格さや強いこだわりに支配された特殊な人格、収入が不安定で生活が破綻している…といったマイナスなイメージを持たれることがあります。実際、生活に安定や保証を求める人に適した職業とはいえないでしょう。でも、常に美しいもの、新しいものに触れて刺激を受け、魅力的な何かに取り憑かれ、恋に落ちるようなときめきを生涯享受できるうえ、自身の感動を他の人と分かち合うことができる、世にもステキな職業だと思っています。
でも、考えてみたらそれは芸術家に限ったことではないのです。心の奥底で感じたことを何かしらの形にして他者に伝える職業…例えば、作家やシェフにも、デザイナーや映画監督にも、共通する部分があるのではないでしょうか。
写真家も、しかり。撮った方が被写体に深く心惹かれ、感動を覚えながらシャッターを切っているのが感じてとれる写真と出会うと、共感できる喜びに心が震えるような気持ちになります。
アルゼンチンとチリにまたがる、パタゴニアという美しい大地を撮った写真集と出会いました。息をのむような空、湖、山々。豊かな森や野生動物たち、崩れ落ちるときの爆音が聞こえてくるような氷河の写真…。どれも素晴らしいのですが、ひときわ印象的だったのは先住民のポートレートでした。
現在のパタゴニアではモンゴロイドの先住民は極めて少数で、白人やメスティーソ(混血)が大半を占めているといいます。1885に始まったゴールドラッシュで凄まじい数の白人が押し寄せ、またヨーロッパ人によってもたらされた天然痘や麻疹などの疫病によって、その数は激減してしまったと知りました。先住民には、地域によっていくつかの部族にわかれていて、魚や海鳥を獲るもの、釣りやアザラシを捕るもの、齧歯類を常食とするものなど、それぞれが独自の生活習慣をもっていたとのことです。
ヤーガン族もそのひとつ。いまや、プーロ・サングレ(純血)といわれる先住民は二人の姉妹を残すのみとなってしまったそうです。印象的なポートレートはその姉妹のもので、写真家の方がお二人とかわした会話も紹介されていました。こんな内容でした。
僕はこんな質問を投げかけてみたくなった。「嫌いな人はいますか?」
「生きるというのは、光と闇の間を歩いていくようなもの。大切なのは、心の声にいつも敏感であること、自然を敬うこと、そして周りの事象の意味を常に考えること(*野村哲也著『パタゴニアを行く』中公新書)」シンプルでありながら奥深い、素晴らしい示唆です。ポートレートには、それを聞いた瞬間の彼の感動が写りこんでいました。
先日、あるアルゼンチンの楽譜が欲しくて注文したら、欠品中でした。再入荷がいつ頃になるか尋ねたところ「通常なら3週間程度ですが、何分にもアルゼンチンのことなのではっきりと申し上げられません」との返事でした。同じ南米でも、チリ人は勤勉、アルゼンチン人は怠慢、とよく聞きます。
でも、勤勉さも怠慢さも、部外者が勝手な基準で評価しているたけのもので、現地の人々にとってはそれが当たり前なのです。日本人だって、世界的には異常といえる労働日数に耐え、黙々と仕事をこなすのが“普通”です。
アルゼンチンの音楽には、支配を受けた歴史があるスペインのリズム性やイタリアの歌謡性が、ミロンガ、タンゴなど独自のスタイルに複雑に混ざり込んでいます。混血は始めから混血なのではなく、純血が時を経て混ざり合ったもの。そんなアルゼンチンの“混血”音楽に、今とても心惹かれています。そこには、信仰、愛、諦め、救い、哀しみ…さまざまなものが渾然一体となって溶け込み、生々しい体温を感じさせるのです。
私の中でそれがまた新たな“混血”となって、聴く人に思いが伝わることを、願っています。
■第642回 ありがたき、初春
子供の頃はなにより楽しみにしていたクリスマスですが、この数年はさほどではなくなりました。昔と違って、やれハロウィンだバレンタインデーだ…と、年間をとおしてイベントが増え、ありがたみ?が少なくなっていることもありますが、日本の行事を大切にしたいと願う気持ちが強くなってきたこともあるように思います。
ひな祭りが近づいているのに、ホワイトデーのお菓子ばかりが店頭に並んでいたり、クリスマス関連の飾り付けや商品は10月末のハロウィンが終わった直後から二ヶ月近くにも及んで街やお店を賑わせるのに、肝心なお正月のものはそれが終わってからの一週間くらいが“勝負”。日本古来のよき風習が外来のあれこれの向こう側に追いやられ、小さくなってしまっているように感じるのは私だけでしょうか。
一人暮らしで、クリスマスだからといってプレゼントやケーキの用意をすることもないので気持ちが盛り上がらない、ということもありますが、逆にお正月のありがたみは、年々強く感じるようになっているように思います。
両親ともに健在で、実家で帰りを待っていてくれること。帰省して母の手料理を食べられること。家族でいつもの神社に初詣に出かけられること。晴れ着(着物)を着せてもらって、ゆっくりと親子でくつろいで過ごせること。そのありがたみは、ひとつひとつは些細なことですが、私にとっては一つかけても淋しくなるであろう掛け替えのないものです。
何より、年が明けたときの身が引き締まるような新鮮な気持ちが、大好きです。新しい年を無事に迎えることができたことへの感謝や、家族がこの一年も元気に過ごせますようにと、いう願い…。新たな一年に向けてのさまざまな抱負やわくわく感は、クリスマスや他の時にはない、新年ならではの感慨です。
「この気持ちを、一年中ずっと抱いていられたらいいのに」そこで、それを今年の抱負にすることにしました。今年も有言実行の願掛けを込めて、この場でもう少し詳しくお話ししますと、新年に心に誓った新たな三つのことを実現させよう、というものです。
一つめは、以前からの念願だった、『おとなのための音楽塾』の再開。以前のような大きな?形ではなく、サロンのような小規模なものになるかもしれませんが、くつろいでさらに身近にクラシック音楽を楽しんでいただけるようなスタイルを思案中です。春の開講を目指して、少しずつ詰めていくつもりです(ご近所の方、ぜひともお楽しみに!)。
二つめは、新しい音楽ジャンルへの挑戦。昨年末に運命的ともいえるステキなご縁があり、こちらももう動き始めています。そのジャンルとは、中南米のラテン音楽。種別としてはクラシックに入るものですが、まだまだ広く知られているとはいえないものです。ご当地ですらほとんど演奏される機会がないそうなのですが、眠らせておくのにはあまりにももったいない、たいへんに素晴らしい作品がたくさんあることを知りました。貴石の原石のように力強く、深く熱く心に響くそれらの音楽を、なんとか皆さんにご紹介したい!…という思いを、今年、形にする予定です。
三つめは、昨年に続いて“ヨガ”です。大好きなのですが、昨年は忙しさにかまけてなかなかレッスンに通えませんでした。ところが、5年のヨガ歴を持つ友人から「レッスンより、毎日やり続けることが大切なのよ」と聞きました。「私、レッスンは月に一度くらいしか受けてないけど、自宅で毎日しているの」彼女は就寝前に、いくつかのアーサナ(ポーズ)と呼吸法を実行しているそうです。「でね、体だけじゃなく、顔もストレッチするの!リンパに沿って正しくマッサージすると、フェイスラインもぜんっぜん違ってくるのよ」「すごい!でも、毎晩〜?(←弱気)」「それがね、やり始めたらみるみる体調がよくなるし、ぐっすり眠れるしで、ちっとも苦にならないどころかやらないと気持ち悪く感じるようになっちゃって…」
幸いにも、年末に受けた健康診査の結果、現在のところほとんど何の問題もないことが判明しました。彼女の域に達するのにはかなりの修行が必要だと思いますが、せっかく親にもらった健康を維持するためにも、少しずつでも取り組んでいきたいと思います。
いずれも、楽しんで取り組めることばかり。気張りすぎず、丁寧に2014年を過ごしたいものです。
■第641回 “志が走る”師走
年末になると、決まって思うことがあります。例えば、時間の経つのが年々確実に速まってきているな、とか、今年も“今年の抱負”を全うできなかったな、とか…。
12月に入る前からぽつりぽつりと届き始める喪中を知らせる葉書に、元気に生きていることは必ずしも当たり前のことではないのだと気づかされたり、はたまたその年にあった貴重な出会いに改めて感謝したり、来年こそ実現させたいことに思いを馳せたり、と、心がそわそわ、ぞわぞわ、してしまいます。
先日、ここ数年年末の恒例になっている、自宅での夕食会をしました。今回はイタリアの地方料理がテーマ。イタリア土産のドライトマトやポルチーニ、パルミジャーノレッジャーノなどを使った料理などをあれこれ10品以上用意したり、二種類のチーズを自家製したり、三種類のエクストラバージンオイルを食べ比べたり…と、トスカーナ旅行の余韻も手伝っていつも以上に熱が入りました。気の置けない10人のゲストはみんなよく語りよく笑い、そして気持ちがいいほど美味しそうに料理を平らげてくれて、皆が私の一年の厄落としをしてくれたような、幸せで楽しいひとときでした。
「こんなお料理、どうやって作り方を勉強するの?」とよく聞かれます。もちろん、習ったことはありません。どなたかのレシピを参考にしつつ、実際には、自分が現地で食べた味を思い出しながらアレンジを加えたオリジナルレシピになります。例えば、そのままでは塩分やカロリーが高すぎると思われる時は素材や調理法を変えますし、チーズを作ったときにできる乳清を煮込み料理に使い回してみる、といった具合に。
試作もします。シエナ風の、ほうれん草とリコッタチーズのパスタのソースをつくるのに、よりヘルシーになるようリコッタチーズを牛乳ではなく豆乳で試してみたところ、それはそれで充分美味しかったのですが、ソースに加えるナッツ(クルミ、または松の実)とかすかに感じられる大豆の風味が、わずかながらバッティングしている印象があって、ボツにしました(今流行の、リコッタチーズを使ったふわふわパンケーキなどには良いと思いますが)。
何日も前からたくさんの料理本をあれこれ見比べてレシピを見極めたり、パーティーの雰囲気を盛り上げる、イメージに合うテーブルクロスを探しにお店をまわったり、ゲストがそれぞれ好きなグラスを選べるようにグラスコーナーを設けたり、サプライズ(見かけからは味の想像がつかない、何か)の一品や当日のタイムテーブルを考えたり、ゲストが来てから最小限の仕上げの作業ができるよう段取りを工夫したり、ユーモアも交えたお品書きのカードを書いたりしていると、もう夢中になってしまいます。ホームパーティーで一番楽しんでいたのは、私でしょう。
でも、この日ある確信を持つことができました。それは、自分が人に対して何か行動を起こすときに、それを心底楽しむことの大切さです。来る2014年は、自分が心惹かれるものを徹底的に楽しんで人に伝え、それを共有できることのありがたさや幸せを実感できる年にしたい、という目標もうまれました。今も、ここしばらく雲のようにぼんやりと心の空に浮かんでいた“やりたいこと”が、じわじわと形をなしてくるのを感じています。
それが何で、どういうものなのか、は、後日、きちんと具体的に詰めてからお伝えしたいと思いますが、先日のホームパーティーで、美味しいものを囲んでゲストのおしゃべりがはずんだように、ゲストが音楽を囲んで、くつろぎつつも上質な芸術がもっているパワーや、心を満たしてくれる深さに触れ、豊かな時間を共有していただけるようなものを形にしたいと考えています。
私にとっての「師走」は師が走るというより、「志走」…つまり、目標や意思があれこれとうまれ、実現に向けて走り出したい気持ちになる時なのかもしれません。
年末年始は仙台に帰省して、高校時代からの同級生のみんなや生徒さんに会えることになっているのも、大きな楽しみです。きっと彼女たちからも、あたたかなパワーやステキなときめきをもらえることでしょう。
明日の仕事納めが終わったら、新年への希望を胸に、大掃除に励みたいと思います(年賀状も書かなきゃ!)。
■第640回 アワードインフォメーションより
トスカーナ旅行の連載が終わり、たまには“ピアニスト”らしい内容を…と考えたすえ、今回は長年関わらせていただいている山形県ジュニアピアノコンクールの受賞者のご案内に掲載された私の記事をご紹介することにしました。内容は、今年のコンクール本選を終えての全体総評です。ピアノを勉強している方もそうでない方も、コンクールにご興味のある方もそうでない方も…。何かの参考にしていただけましたら幸いです。
===================================
コンクールにご参加くださいました皆さん、今年もすばらしいステージを楽しませていただいて、ありがとうございました。年々皆さんのレベルも上がり、狙った賞をとれずにがっかりした方もいらっしゃるかもしれませんが、実をいうと特に本選は接戦で、皆さんがもう一度弾いたら違う順位になるかも、と思うほどその差は小さいものでした。
審査をしていて、ふと、皆さんが本番を目指す中でとても気にしていることと、それほど気にしていないことのふたつがあるように感じましたので、そのお話をしてみたいと思います。
例えば、ミスタッチをしないことや、立派なテンポで弾くこと。先生に教えて頂いた様々な曲想の変化をつけること、などは、前者でしょう。確かに、完成度の高い演奏のためにとても大切なことばかりです。でも、より音楽的な演奏のためには他にもたくさんの大切なポイントがあるのです。
まず、その曲がどんな個性を持っているのかをよく見極め、感じてみること(例えば、ダンスならどんなダンスなのか)。楽譜を丁寧に学び、どんな表情や音色でアプローチするのがふさわしいのか、“音楽的空気を読む”ことは、その曲に対しての大事な“役作り”にもあたります。また、速いパッセージがただ無機質に速くならないよう、美しく響かせるように心掛けることや、単にメトロノームの数字的にテンポをとらえるのではなく、正しい拍子感をもって曲にあった適正な速さを判断することも、重要です。
他にも、あります。音をきちんと“弾く”のと同じように、音をよいタイミングで“離す”こともことにも注意を払うこと(これは、音符の長さやお休みを守ることにも、質の高いレガートにもつながる重要なことです)。もちろん、“弾く”ちから以上に“聴く”ちからをしっかりと身につけることも大切ですね(ここでいう“聴く”は聞こえてくる、の“聞く”と違って、音を観察するように注意深く“聴く”ということです)。ペダルを使用する場合は、どこに、どのくらい踏むのか、前もって決めて練習しますが、当日の演奏の中で自分の出している音の響きを聴きながら、リアルタイムで判断して臨機応変に応用させるちからも、要求されます。
まだまだ、あります。思ったとおりの音を出したりタッチをコントロールするために、よい体の使い方と脱力ができているか。テンポの揺らしすぎや大きくかけすぎたリタルダンドなどによって、音楽の健やかな流れが損なわれていないか。フレーズを大きくとらえ、自然なイントネーションで旋律を歌っているか。左手のパートも、音楽的なおしゃべりが楽しくできているか。
…と、あれこれお話ししましたが、最終的には弾く人がその曲に対して感じたことを、自分の言葉で表現することがなにより大切なのです。大変なことに思うかもしれませんが、そうやっていろいろなことに注意と意識を向けながら練習を積み重ねたすえの演奏は、世界でただ一つの、掛け替えのないものになることでしょう!
最後に、私が密かに実行しているおまじないをご紹介しましょう。ピアノを弾く前に、いつもその曲を書いた作曲家の顔を思い浮かべるのです。そして、どうか演奏を気に入ってくださいますように、と、お祈りをして弾き始めます。自然に丁寧な気持ちになって、あわてず落ち着いて弾くことができる気がします(気のせい?)。よかったら試してみてください。
===================================
(*山形県ジュニアピアノコンクール実行委員会発行
■第639回 『トスカーナの傑作』 其の九 最終回
翌朝。案内されたテラスルームに入ると、白と赤のチェックのクロスがかけられたテーブルの上に、自家製のフォカッチャやタルト類はもちろん、ペストリーにクロワッサン、プロシュート(生ハム)やコッパ、サラミなどの加工肉やパテに牛肉のカルパッチョ、そしてこれまた自家製のマスカルポーネやリコッタ、モッツァレラはご丁寧にボッコンチーニとさくらんぼう大のチリエジーネの二種類に、もちろんカプレーゼ、…といった何種類ものチーズ類、たくさんの果物などがところせましと並んでいました。
「これはすごいな!これまでで一番のごちそうだね」父は感激しきりです。「本当に!この素晴らしい朝食を明日の朝は食べられないのが残念ね。7時には出発しなければならないから…」と、私。ならば、今朝はゆっくりと(たっぷりと?)頂いて、旅行最終日を無事、元気に過ごすことにしよう、ということになりました。
予約してあった自家用車タクシーに乗り、小さくても情緒豊かな旧市街地へ。どうしても訪れたかったのは、教区博物館でした。小さな街の外れにひっそりと慎ましくたたずむその建物は、まさか内部に素晴らしい作品をそんなにもたくさん所蔵しているようには見えませんでした。会いたかった絵は、やはりフラ・アンジェリコの『受胎告知』。フィレンツェのサン・マルコ美術館で同じ作者の『受胎告知』に感激したばかりで、まだその残像がまぶたに残っているようでしたが、ここで見たものはさらに鮮やかでマリアの表情もまったく別ものでした。浮き上がるようにほどされた金箔がその厳かなシーンにリアリティーを持たせ、絵の前でしばし釘付けになってしまいました。
気ままに散策し、昼食をとったあとは、天空に浮かび上がっているようなこの街の周囲を見渡しながらゆっくりと城壁を散歩することにしました。雲の影をおおらかに写すトスカーナらしい穏やかな丘、そこここに生えているかわいらしい糸杉、同じ煉瓦色をした建物や、古い教会…。眼下に絵本のような風景をめでながら、ゆっくり一歩一歩を踏みしめて、歩いていると、なんだか夢の中にいるような気がしました。両親と三人で、こんなところを歩いているなんて。しかも、日本人観光客が決してこないようなところを!
帰宅してロレンツォに明日のタクシーの手配などについて確認しました。「駅は近いから、7時20分でも大丈夫だよ。その時間に来るよう、頼んでおくね。
そうだ、よかったらその前に朝食を食べていってね」「え?でも、時間が早すぎるので…。だって朝食は8時からでしょう?」「いや、僕も母も6時過ぎには来て支度しているから、大丈夫だよ。君たちの予定にもよるけど、遠慮しないで、ペストリーやケーキだけでも…あるいは、コーヒーだけでも飲んでいって」
その翌朝は、荷造りもあるので5時半に起きました。ひととおりを終えてふと外に出るとまだ空には星が輝いていました。とても美しい星空でした。朝食のテラスにはすでに、灯りがともっていて、厨房と食堂を忙しく行き来するロレンツォの影がみえました。
「おはよう!」「おはよう、ロレンツォ。星がたくさんね。いつもこんなに美しいの?」「どうかな。…でも、今日はいい天気になることは間違いなさそうだね。よかったら中でコーヒーでもどう?」「ありがとう。お言葉に甘えて果物とペストリーを頂いていってもいい?電車の中で食べるのに…」「もちろん、いいよ!好きなだけどうぞ!」やがて時間どおりにタクシーが迎えに来て、ロレンツォは最後まで笑顔で送り出してくれました。
コルトーナから空港のあるフィレンツェに向かう車中で、美味しいペストリーと果物を頂いてホッとひと息ついた時、ふと人気女優ジュリエット・ビノシュ主演の映画『トスカーナの贋作』を思い出しました。旧東ドイツを一人旅したときに帰りの機内でみた、私たちが訪れたアレッツォが舞台になっている映画です。
男女の出会いやすれ違い、登場人物も含めた人物・心理描写が素晴らしく、男女の愛とは?結婚とは?を、さりげなく問いかける作品でしたが、何にもましてその舞台が魅力的にみえ「いつかトスカーナをゆっくりと旅してみたい」と願ったのでした。あれから二年。金婚式を迎える両親とともにその願いが叶って、感謝の気持ちでいっぱいでした。
風景も、人々も、食べ物も、美術作品も、今朝の星空も…。私にとってはすべてが素晴らしいトスカーナの“傑作”に感じられました。そして、傑作とたくさん出会えたこの旅もまた、私の中で思い出の“傑作”になることでしょう。
(*『トスカーナの傑作』おわり)
■第638回 『トスカーナの傑作』 其の八
アレッツォで最も美しい教会といわれるピエーヴェ・ディ・サンタマリア教会。そのユニークな半円筒形の後陣部がみえるグランデ広場に面した回廊のカフェで休んでいるとき、ふと気づきました。「そうだ、シエスタなんだ!」
シエスタという長いお昼休みを取る習慣がある国としてはスペインが有名です。子供もお父さんも一度家に帰って家族そろって昼食をとり、場合によってはお昼寝をするのです。シエスタの時間(13時から15〜16時くらいまで)には他の家を訪問するのはもちろん、電話をかけるのも控える、というのが暗黙のエチケットになっています。
今では、スペインといえども必ずしもシエスタをとるわけでもなくなっているようですが、スペイン以外の国にもシエスタをとる習慣があるところがあって、ギリシャやイタリアが、まさにそう。フィレンツェもシエナも都会で気がつきませんでしたが、アレッツォではシエスタのために、昼下がりに多くのお店や銀行が閉まっていたのでした。
私たちは駅前のインフォメーションに戻り、荷物を受け取って、古き善き情緒と習慣の残るこの小さな街を後にしました。ローカルバスで、いよいよ旅の最終目的地コルトーナへの移動です。途中から乗ってくるのはほとんどが地元の人々。皆バスの運転手さんとすっかり顔見知りのようで、運行中もひっきりなしに世間話をしたり、バス停がないところで適当に降ろしてもらったり…と、のんびりとした田舎の雰囲気があふれています。
一時間ほどでコルトーナの広場に着きました。でも、周りをみてもがらんとしていて、タクシーの気配なんて微塵もありません。「あの〜、タクシーの乗り場ってどこでしょうか?」「タクシー?ここにはタクシーはこないよ」「え?」中・長距離バスが発着するメインの広場なのに?…私は状況が飲み込めず、「では、タクシーに乗るのにはどこに行ったらいいでしょう?」運転手さんに尋ねると「だったらレプッブリカ広場に行ってみたら?バルの人に呼んでくれるよう、頼んでみてごらん」と、その広場への行き方を教えてくれました。
これまではお天気に恵まれてきたのに、この時に限って、雨。古い街特有の、石畳の急な坂道を、重い荷物を引きずって登りながらも、タクシーをどうやって頼んだらいいものやら、思案に暮れていました。レブップリカ広場に到着するも、やはりタクシーは一台も見当たりません。両親には雨宿りできる場所で待っていてもらい、私は電話がありそうな何件かのバルに駆け込んで「すみません、タクシーを呼びたいのですが…」と、頼んでみましたが「タクシー?それは難しいな、ごめんよ」と断られるばかりでした。でも、めげてはいられません。なんとかしなければ!
午後6時を過ぎ、どんどん暗くなってきました。バルを諦め、感じのいい小さなホテルを見つけてフロントの若い男性に事情を話したら「わかりました。電話して聞いてみましょう」と、取り合ってくれました。ところが、どうしたことか次々と断られてしまいます。「ごめんなさい」すっかり恐縮して謝ると「こちらこそ。別なところに聞いてみるから、もうちょっと待ってね」と、彼は終始爽やかな笑顔です。ついに6件めで、手応えを得ました。「30〜40分後になるようだけど、大丈夫?」「はい!ありがとう、お願いします」こうなったらもう、何分後でもかまいません。
「タクシーだよ!」その30分後、声が聞こえた方を向いて反射的に「はい!」と答え小走りにそちらに向かうも、その車はどうみても一般の車両でした。「お待たせして悪かったね!」運転手さんが私たちの荷物をトランクにてきぱきと乗せながら「行き先はホテルのフロントに聞いたよ」どうやら頼んだタクシーに間違いないようでした。
「街中でタクシー、見かけなかったでしょう?」「ええ、一台も」「でしょう?この街にはタクシー会社がないんだ。だから、住民が当番制で予約に応じてシフトをして、副業で業務を行っているんだよ。自家用車でね(笑)」タクシーを頼む場合、ある程度事前に予約しなければならないというのは、そういった事情からだったのです。お店の人が呼んでくれなかったのは、予約をしていないなら呼べるとは限らないということからだったのでしょう。ロレンツォが「三日前までに」と言っていた意味がわかりました。コルトーナは“タクシーのない街”だったのです。
予め知らせておいた到着予定時間よりも小一時間ほど遅れての到着になってしまいましたが、宿に着くとロレンツォが温かく迎えてくれました。彼の気取りのない穏やかな笑顔と、彼に教えてもらった近所のレストランでいただいたウサギのソースの自家製の手打ちタリアテッレやハウスワインの美味しさに、移動の疲れはあっけなく吹き飛んでしまいました。さらにその10時間後には、想像を絶する極上の朝食が待っていたのです。
(*『トスカーナの傑作』其の九 最終回 に続く)
■第637回 『トスカーナの傑作』 其の七
たくさんの素敵な思い出をくれたシエナに別れを告げる日がきました。チェックアウトの時、「部屋は問題なかった?」と尋ねるオーナーに、「ありがとうございます、完璧でした!あ、でもひとつだけ、ほんの小さなことですが…」私はちょっと茶目っ気をこめて続けました。「母が、トイレの便座が高すぎて具合が悪い、と。残念ながら私たち、あまり長い足を持っていないものですから」笑いをとろうとして(?)言ったのに、彼は真顔で丁寧に答えました。「それは理解しています。ご不便をおかけしてごめんなさい。ただ、あの便座や手すりなどの仕様は、実は身体障害者に対する国の規定に基づいたものなのです。」
頑丈な手すりと、それにつかまらなければよじ登れない?高い便座は、車椅子の方が用を足す際の利便性を考えての設計とのこと。考えてみたら一般的なイタリア人も、ジャーマン系、スラヴ系の人たちのように、足長ののっぽさんが多くはないのです。健常者が障害者のために少々の不便を被り、お互いに助け合う、といった場面には、他のヨーロッパでもよく出会いました。でも、イタリアは北欧のように社会保障や障害者のためのインフラが整っているイメージがなかったので、意外に思いました。
三日前に、迷ったおかげでだいたい勝手がわかったシエナ駅から、ローカル線でまずはアレッツォを目指します。まずは、というのは、今回のトスカーナ旅行最後の宿があるコルトーナという街へはシエナからダイレクトに移動する交通手段がないため、そこで乗り換えなければならないのです。
ヨーロッパにいると、不便だな、と感じることが山ほどあります。そして、いかに日本が“便利な”国かというのがよくわかります。でも、四苦八苦しながらもヨーロッパで過ごしているうち、自分が、便利さにいつのまにか“飼いならされて”しまっているような危機感におそわれることもあります。便利さの犠牲になっているもののことを考えることなしに、目の前の安易な道具やシステムに頼りすぎ、創意工夫することや判断する力、動物的な感覚や逞しささえ、奪われているのではないか…と、不安になるのです。
でも、このとき移動中の私を不安にさせていたのは、コルトーナから宿への移動のことでした。というのは、シエナの時もそうでしたが、コルトーナの宿のオーナー、ロレンツォからも、気になるメールをもらっていたのです。
「うちに来るには公共の交通手段はないので、コルトーナ市街地からタクシーを使ってもらうことになります。僕がタクシーを予約してあげることはできるけど、その場合には少なくとも三日前までに、正確な時間と場所を知らせてもらう必要があります」
タクシーでしかいけないところ、というのはよく分かります。なぜなら、私が選んだ最後の宿は“アグリツーリズモ”と呼ばれる宿だから。アグリツーリズモとは、もともとは「農作業を手伝いながら宿泊する」という意味があったのですが、近年ではむしろ、広い敷地や家屋を利用してツーリスト用の宿泊施設を作り、自分の土地で取れた農作物を使った食事を振舞う、といったペンション風のところが増えていて、トスカーナ地方はまさにそのアグリツーリズモの宝庫。街から離れた、少々不便なところに多いのは当然です。でも“少なくとも三日前”って、どうしてかしら?結局、時間も場所も行き当たりばったりになるので、それを彼に知らせることができなかったのでした。
さて、アレッツォに到着しました。主演、監督、脚本でオスカーを受賞したロベルト・ベニーニの映画『ライフ・イズ・ビューティフル』の舞台にもなり、彼自身の生まれた街でもあるアレッツォは、かつてフィレンツェやシエナに次ぐルネッサンス文化の中心地でした。街を散策する2〜3時間の間、荷物を預けるところがどこにもなかったので、インフォメーションのお姉さんに「この辺りに、荷物を預かってもらえるところはありませんか?ホテルとか…」と尋ねると、「それが、近くにはどこもないのです。でも、4時まででよければ私ここにいますから、奥の控え室に預かりますよ」と、女神のような笑顔で救いの手を差し伸べてくれました。なんてラッキーなの!…私は心配ごとも吹き飛んで、元気がわいてきました。
一時をまわっていたので、駅のフードコートで軽くパニーニとカフェの昼食をとり、身軽になって旧市街地をぶらぶらし始めてしばらくすると、父が街の様子を怪訝に思い始めました。「今日は日曜日でもないのに、休みの店が多いね」「あ、本当だ。なんだろう…この地域だけの休日かなにかかしら」知らぬ間に私たちは、想像もつかなかった“不便さの聖域”のような世界に、足を踏み入れていたのでした。
(*『トスカーナの傑作』其の八に続く)
■第636回 『トスカーナの傑作』 其の六
「シエナでは職種や年代に関係なく、自治体のしっかりとしたコミュニティの中で助け合ったり話し合ったりできるのはとても良いことだけど、別の見方をすれば閉鎖的であるともいえます。革新や変革を求めないしそうした欲求もないので、なかなか進歩を果たせないのです」
バスの中でアンドレアがまじめに話をしているところに、ゲストの一人が「違う自治体の男女が結婚するのは問題ないのかい?」と尋ねました。「ないことはないよ。でも、それはコミュニティ云々以上に家同士の判断や裁量によるところじゃないかな。だって、同じ自治体同士で結婚すれば必ずうまくいく、ということでもないのは、皆さんご存知でしょう?…なあんて、こんなこと言っている僕の妻は、実はフィレンツェの女性です。へへ…」
おいおい。シエナの男、だめじゃないか!たのむよ…、という声が、笑い声とともにあがりました。「わかっているさ。でもね、シエナの人間から見るとフィレンツェの女の子って、なんていうか、所作もファッションも洗練されているし、話し方も物腰も優雅で…。僕なんてもう、真夏の太陽の下のジェラートのようにとろけちまったんだよね〜」またもバスに明るい笑い声が響きました。
そうこうしているうちにバスは、世界遺産に登録されている中世の塔の町サン・ジミニャーノに到着しました。アンドレアが“僕よりもずっとこの町に詳しい”現地のガイドさんによると、ピサ、フィレンツェ、シエナの三角形のちょうど真ん中に位置するこの町は交通の要所としても栄え、11〜12世紀の最盛期には富の象徴の塔が72も林立していたほどだったけど、フィレンツェの軍によってことごとく撃たれ、今では14だけが残っているということでした。
その時間が止まったような街並みは、中世からの人々の争いや営みをずっと見守ってきた落ち着きと、深い哀しみをたたえているようにも見えました。小雨が降っていたのも手伝って、グレーの雲の下、煉瓦造りの建物の佇まいや濡れた石畳の小さく曲がりくねった路がなんとも風情豊かでした。私はここでたくさんのシャッターを切ったのですが、納得のいくものは撮れませんでした。独特の哀愁が写り込んでいるものは、一枚もなかったのです。
バスに戻り、しばらくすると空も明るくなってきました。「さあ、お次は
皆さんお待ちかねのワイナリーへ向かいます。簡単なおつまみと一緒に、ワインの試飲をたっぷり楽しんでいただきますよ。バスに戻る頃には皆今よりずっと饒舌になっていること、間違いなし!」
まもなくテヌータ・トルチャーノというワイナリーに到着しました。私たちが二つのテーブルにわかれて着席すると、ワイナリーの方が次々とワインを持って来ては、説明をしてついでくださいます。クロアチアの時とは違って、きちんと着席してパンやチーズと共にゆっくりとテイスティングさせてもらえるあたりは、さすがワインの世界的名産地キャンティです。しかも、そのひとつひとつは、試飲というよりも立派なグラスワイン一杯分の量でした。
「さて皆さん、お次はうちの一押しのワインです!なんと四種類もの樽にかけて熟成させた、スーパータスカンの…」真打ちが出てくる頃には、皆すっかりいい気分になっていました。「このテーブル、インターナショナルで楽しいわ!あっちはアメリカ人ばっかりよ」インターナショナルなうち分けは、スペイン人、ドイツ人、イギリス人、父と同じ大学に留学した経験があって日本語がぺらぺらなオーストラリア人と、私たち日本人三人でした。「あらほんと、このワイン美味しいわ」「そう?私はひとつ前のワインの方が好きだったわ。これはなんていうのかしら、ちょっと気取りすぎよ」「ねぇ、お兄さん、もう説明は結構よ。ごめんね、お買い物しに来たわけじゃないの。ほほほ…」
ワインがすっかり体に染み込んで皆口々に好きなことを言い始め、笑い声も大きくなってきました。両親が用を足しに退席した時、隣の婦人が「お二人はあなたのご両親ね?」「ええ。彼らの金婚式のお祝い旅行で、こちらに来たんです」「まぁ、なんて素晴らしい!スペインでも金婚式はお祝いするのよ」「よし。じゃ、お二人がトイレから戻ったら皆で“おめでとう!”って言おうよ」オーストラリア人ジョンが言い出しました。「そうしよう、そうしよう!」
果たして、何も知らずに戻ってきた両親は、我らがインターナショナルテーブルの一同から「おめでとう!」という大きな声と拍手の祝福を受けたのでした。「ありがとうございます」戸惑いながらも、照れくさそうにイタリア語と英語でお礼を言う父も母も、いつもよりも頬が上気してみえましたが、それはワインのせいだけではないでしょう。(*『トスカーナの傑作』其の七に続く)
■第635回 『トスカーナの傑作』 其の五
午前6時前から、私はそわそわして仕方ありませんでした。イタリアで朝焼けがこんなに待ち遠しくなるなんて、考えもしませんでした。何度も外に出て空を確認するうちに、いよいよ太陽が昇りはじめ、周囲がほの明るくなってきました。
明るくなるに従って、テラスからパノラマで見渡せる丘はぼんやりと雲海に覆われていきました。太陽の明るさや雲のかかり方とリンクしながら、刻一刻とその色は変化していきました。淡いピンクになったり、テラコッタのようなオレンジになったり…。光と陰のコントラストが高まって、はっきりと太陽の光を感じられるようになるまで、中世の絵画がそのまま動き出したような神秘的な光景が、目の前にくり広げられました。
その日は快晴でした。マンジャの塔にのぼってシエナの街の壮大なパノラマを見渡しながら、この景色はいったいいつ頃から続いているのだろう、と思いました。あのテラスからの眺めといい、ずいぶん長い間大きくは変わっていない風景なのではないだろうか、と。そんなふうに、街が昔からの美しい面影を保っていられるなんて、本当にうらやましい限りです。
大聖堂ドゥオーモは、圧巻でした。幸運なことに、この日は普段は保護のため板で覆いがかけられて見られない床の大理石の象眼細工のすべてが、公開されていました。ガイドさんの説明によると、この世界でもまれにみる床の装飾は、14世紀後半からおよそ200年にわたって何人かの芸術家の手により完成されたそうですが、シエナ近郊で採掘される色とりどりの大理石を使い分けて聖書の題材などが精巧に描かれていて、その素晴らしさに声を失いました。
なかでも、ベッキャフーミという人の作品は群を抜いていて、彼がミケランジェロに勝るとも劣らないほどの才能の持ち主であることを感じさせました。いいえ、ガイドさん曰く「シエナの人に言わせると、彼は“ミケランジェロをしのぐ天才”」なのだそうです。「でも、現在、彼の名前と作品を知っている人は少ないのです。建築関係や美術史を専門に学んだ方なら別ですけど…」
「どうしてそれほどまでの人が、ミケランジェロやラファエロのように知られてはいないのですか?」私は思わず、彼女に質問しました。
「それは、彼が権力に興味を持たない人だったからです。例えば、ベッキャフーミはシエナから一歩も外には出なかった。たいがいの芸術家たちは、より高い評価と報酬をもとめ、かつステイタスになるような仕事のためにあちこちの街に移り住んでは作品を残したのだけど、彼は一切そういうことをしなかったのです」
床に描かれている装飾には、自分の欲のために兄弟を殺してしまい、地獄へ落ちた人物が描かれているものもありました。シエナの人からすると、絢爛豪華なフィレンツェは権力主義にみえるのだとか。本当の幸福は、権力を求め、それを誇示したり保持したりすることに力を費やさない人生にあるのだという理念が、ここの人々の間にはあるようなのです。
それは、身の丈にあった簡素で心地よい日々を楽しむ、というウィーンのビーダーマイヤー的なものともまた違って、権力や富という甘い誘惑に屈することなく、人間の本当の幸せや大切にすべき尊いものを見失わないで生きる、といった、確固たる信念を感じさせました。何もわかっていなかっていないまま、トスカーナを大きくまとめてとらえようとしていた、自らの無知を恥じました。
「フィレンツェとシエナは、みなさんお察しのとおり、確かに仲が悪いのです。では、シエナは一丸となって団結しているかっていうと、それもちょっと違う。何しろここはこんな小さな街なのに17もの自治体があって、それぞれが違う旗を掲げ、長い歴史にわたって何かと競い合っているという具合なんですからね。各自治体がその沽券をかけて戦う春のホースレースなんて、その最たるものです。まったくもって観光客向きのイベントでも観光客のためのものでもありませんが、シエナでは他のどんな行事よりも大切なものなんですよ。審判への賄賂?ないわけがない!(笑)でも、他の自治体も同じことをしているから、意味をなさないんですがね」
その翌日、サンジミニャーノやキャンティのワイナリーを巡るミニバスツアーの冒頭で、ガイドのアンドレアが話し始めました。この日が三人にとって生涯忘れられない一日になろうとは、この段階では誰も知り得ませんでした。
(*『トスカーナの傑作』其の六に続く)
■第634回 『トスカーナの傑作』 其の四
レストランは宿から目と鼻の先のところでした。実は、両親には夕食の時間まで部屋で休んでもらって、その間に明日の予習のため旧市街地を1時間ほど散策したのですが、その帰りに、「よさそうなレストランだな。シエナ滞在中、一度はここに来てみよう!」と思ってチェックしていたお店でした。
イタリア人も他の国からの観光客も、比較的夕食の時間は遅めです。というより、普段6時とか6時半くらいには夕食(晩酌?)が始まる鈴木家は、日本人としても早い方だと思います。予約の時間にお店に入った時には他のお客様はどなたもいらっしゃいませんでした。
「今晩は!先ほど宿から予約を入れていただいたスズキです」「お待ちしておりました。こちらへどうぞ!」ホール担当の方は、まったく気取りのない気さくな笑顔で案内してくれました。さて、メニューを決める前に大事なお仕事が…。ワイン選びです。「ええっと。この地域の赤ワインでオススメはどのあたりですか?あの〜、できればあまり高くないもので…」「うちのハウスワインはオススメですよ。特徴が出ていてバランスもいいワインです」彼は誠実な笑顔で、一番値ごろなハウスワインをすすめてくれました。もちろん、それに従うことにしました。
70代の夫婦に40代女性一人、の日本人三人組です。イタリア人のように、前菜、プリモ(パスタ)、セコンド(メイン)の三つは食べられないので、残さず食べられる量を考えて、つい変則的なオーダーになってしまいます。この日は前菜を二種類、パスタを二種類、メインと付け合わせを一種類、というオーダーになりました。イタリアではテーブルに予めパンがあるので、私はパスタの代わりにメインをリクエストしたのでした。「お持ちするタイミングはどうしましょう?前菜とパスタは一緒にお持ちすることもできますが…」
そうなのです。ヨーロッパでは、お料理を運ぶタイミングがとても大切にされるのです。例えば三人とも同じように前菜3品、パスタ3品なら、きちんとそれぞれを一度に持ってきてくれるのが当たり前。誰かのパスタがなかなかこなくて、「お先に召し上がってください」なんて気を遣うことは、まずありえません。
私は彼に、前菜は三人でシェアするので先に持ってきてください、パスタと
メインは付け合わせと一緒にお願いします、と伝えました。待たせすぎることも早すぎることもなく、よいタイミングを見計らって出来立てのお料理をすべてそろえてテーブルに持ってくるには、目配りだけでなくホールの方が厨房にこちらの食事のペースをマメに伝えていることが必要なはずです。彼は完璧でした。
旬のイチジクにカリッと焼いたパンチェッタをくるりと巻いて、その上に松の実とシェーブルチーズをちらした前菜は絶品でした。もちろん、リコッタチーズとほうれん草のタリアテッレやポルチーニのフィットチーネなど、どれも美味しくて、ハウスワインととてもよく合いました。お待ちかねのメイン、レモンと白ワインを加えて煮込まれたお肉にたっぷりのオリーブが添えられるトスカーナの伝統料理“甘酸っぱいウサギの煮込み”が運ばれた頃には、お店はすっかり満席になっていました。
パスタはまったく脂っこくなく、ソースが余ることも足りないこともなく、塩加減はおしなべて日本よりも柔らかな印象でした。付け合わせに選んだ野菜のスフォルマート(野菜を卵で蒸し焼きにしたふんわりとしたプディング)は、まさにスフレのような繊細な口当たりで、これには母がいたく感心していました。そして意外なことに、どのお皿もニンニクの香りをほとんど感じさせないのでした。イタリア料理というとしっかりとニンニクがきいているオリーブオイルたっぷりのトマトソース、というイメージですが、オイリーでなくニンニク臭くもなく、しかも多くのトスカーナ料理はトマトも使われてもいないのです。
すっかりお腹も心も満たして会計をすませ、お店の外に出ると、なおもお客さまが何組か入店を待っていました。「美奈ちゃん、メニューを選ぶの、上手ね!」と、母。「いや〜、全部うまかった!」父も満足そうです(旅の間、なんだかんだいって父が一番よく食べよく飲み、よく眠っていました)。私も心から満足しましたが、部屋の前のテラスから見えるであろう朝焼けがいったいどんな美しさなのかが気になって、なかなか寝つけませんでした。お天気は下り坂のような予報でしたが、空を見上げると、うっすらと浮かんでいる雲の隙間から、キラキラと星がまたたいていました。
(*『トスカーナの傑作』其の五に続く)
■第633回 『トスカーナの傑作』 其の三
ヨーロッパのほとんどの歴史ある都市の旧市街地は、鉄道の駅やバスのターミナルからはちょっと離れたところにあります。古くからの美しい街並を守るための不便さを、街の人は誇りに思っているようにみえることもあります。
でも、フィレンツェは空港も比較的街の近くですし、主要駅であるサンタ・マリア・ノヴェッロ駅も街中。見所もまとまっていて、とても観光しやすいところです。市民の台所でもあり、お土産に持ち帰りたいごちそうの数々が目に飛び込んでくる中央市場もホテルからすぐのところにあったので、シエナへ発つ日の午前中、そこでの買い物を楽しみました。市場は、朝7時から。みんな朝からよく働いています。
イタリア人というと陽気で商売熱心、時間の感覚がルーズ、男性が女性に優しい、などという感じがステレオタイプなイメージですが、イタリアもところによってそれぞれなのではないでしょうか。日本だって…いいえ、宮城県だって、海沿いと山間部とでは言葉も人の気質も異なるくらいなのですから。
さて、大きな駅なので、念のため早めに駅に着いて列車の出発ホームを確認するも、早すぎるのかまだ表示されていません。どうも30分前くらいにならないとわからないようです。やはり日本人はせっかちなのかしら、と思って周りを見渡すと、欧米人観光客も同じようにホームが表示される電光掲示板の前にたち、じっと目的の列車が表示されるのを待っていました。
やがて私たちの列車の案内があり、時刻どおりに出発しました。チケットを買った時、窓口の方に「混みますか?」と聞いたら「シエナ行きは頻繁に出ているから、まずそんなことはないよ」と言われましたが、そのとおりでした。途中、地元の人たちがしょっちゅう乗り降りはしていましたが、私たちはゆったりと車窓を眺めながら、先ほど中央市場で買った美味しいお惣菜パンやらレモンクリームのペストリー、果物などをほおばりました。
時刻通りにシエナ到着。さあ、ここからが今日の難関です。まず、教わったとおりに地下のバスターミナルを探しますが、これがなかなか見つからない!何人もの方に尋ねてやっとたどり着いたのは、ちょうど一本前のバスが行ってしまった直後でした。ほどなく、同じようにターミナルが見つからなくて困っていた男性がやってきました。
「ここ、わかりにくいですよね」「そうね。僕は前にも何度か来ているのに、その度に迷っているよ。まったくバカみたいだ」
わかりにくいとは言いながらも、気がつくと、電光掲示板に表示されているとおり一分と違わずぴったりの時間に次々とバスがやってきます。なんだかんだいって、ここでは乗り物はとても時間に正確なのでした。一般的なイタリアのイメージとはかなり違う気がして、意外でした。
やはりぴったりの時間にやってきた目的のバスに乗り込み、これならちゃんとたどり着けるか気をもむこともなかったな、と思ったその時。プスンとバスのエンジンが止まって乗客が次々と降り始めました。何事?…慌てて運転手さんにたずねます。「あのー、このバス17番になるんでは?」「どこまで行きたいの?」「バッリの方です」「ああ、それならね、すぐ前のバスに乗り替えればいいんだよ(にっこりウインク)」え〜?本当?聞いてない…。
戸惑いながらバスを降りようとすると、運転手さんと話していた初老の男性が「大丈夫、僕も乗るからいらっしゃい」と、声をかけてくれました。乗り換えたバスはたくさんの乗客で満員です。これでは、宿の方の指示のように運転手さんに地図を見せ、降りるとき教えてください、なんてお願いできそうにありません。
結局、その親切な初老の男性に教えてもらって、なんとか最寄りのバス停で降りることができました。宿は、門を入ってからしばらく、オリーブの木がたくさん植えてあるパサージュを進まないと建物にたどりつかないほど、大きな邸宅でした。門を入ると、貴族の出身なのでは?という雰囲気のオーナーが、微笑みを浮かべて出迎えてくれました。
案内された部屋の前には、これぞトスカーナの丘!というような素晴らしいパノラマが広がっていました。「ここからみる朝焼けはとても美しいんですよ」オーナーのもの静かで落ち着いた口調と物腰に、またもイタリア人のイメージが覆されるような戸惑いを感じました。彼に夕食のことを相談すると、近所の素晴らしいレストランを予約してくれました。そこでの夕食ときたら! (*『トスカーナの傑作』其の四 に続く)
■第632回 『トスカーナの傑作』 其の二
ピッティ宮は15世紀後半に建てられ、以後様々な歴史を経て1859年までトスカーナ大公の住居として使われていたところで、現在は7つもの美術館や博物館と、優雅にして広大なイタリア式の庭園をもつ宮廷です。
なかでもパラティーナ美術館は、歴代トスカーナ大公によるルネッサンスからバロックまでの珠玉のコレクションが公開されている、とても貴重なスポット。ティツィアーニやイタリア一との誉れ高いラファエロのコレクションは、美術ファンならずとも魅せられてしまう素晴らしいものでした。
特に“聖母の画家”といわれたラファエロの描く女性像は、どれもため息が出るほど美しく、それらを天井ひとつとっても手のこんだ歴史的建物のなかで、時間を気にせず、すぐ手の届きそうな距離でじっくりと鑑賞できる幸せときたら!オペラにしてもそうですが、ヨーロッパでは、建物自体に芸術を五感でゆったりと享受する楽しみへと誘ってくれる雰囲気と気品が漂っているのは、うらやましい限りです。一歩を踏み入れたとたんに、芸術をとても近しく、しかも尊く感じられるようになる魔法に、かけられた気分になるのです。
そんな時に、難しいことを語り合う必要は、ないのです。私たちもただただ、その素晴らしさに感動して「すごいね」「なんて美しい…」などと短い感嘆の声をあげるばかりでしたが、本当に何かに感銘を受け、圧倒されるとき、人が言葉を失うのは自然なことだと思います。
つい先日、現代を代表する世界的女性アーティストやダンサーのポートレートを撮り続けている女流カメラマンの松本路子さんの写真展にお邪魔しました、ご本人お会いしてお話を伺うことができたのですが、「(撮影中は)ほとんど相手と会話を交わしたりはしないの。人間が本気で何かに向き合い、集中している時にはあれこれと言葉がでてくるものではないし、研ぎ澄まされた雰囲気の中でお互いに何を感じ合うか…その空気や人間の背景までもが、写真に映り込んでいかなければ意味がないんです。とても難しいことだけど」と語ってくださったのは、とても印象的でした。
一日中フィレンツェ旧市街地を歩き回り、あまりにもすごい宝物の数々を目の当たりにして、ホテルに戻る頃には三人ともどっぷりと疲れてしまいました。でも、私にはまだやっておかなければならないことがありました。
明日のシエナへの移動の手配です(御年70代の両親に、駅でたくさんの時間を待たせるわけにはいきません)。夕食までの間、部屋で休んでいてもらうことにして、私はサンタ・マリア・ノヴェッラ駅に向かいました。
案の定、窓口はどこも長蛇の列でした。それも、日本と違ってなかなか一人が終わらないのです。一応、オートマティックな券売機もあるのですがなにやら操作が複雑らしく、係の方がつきっきりで対応するも一向に列は進みません。本当はインフォメーションで時刻表を確認してからチケット窓口に並んで買おうと思ったのですが、そんなことをしていたらいったいどれだけ時間がかかることやら!
チケット売り場の窓口に並ぶこと数十分。やっと番が回ってきました。「ボナセーラ。明日のお昼前後のシエナ行きの列車の時刻を教えていただきたいのですが…」「それならこのチケット窓口じゃないよ、インフォメーションの窓口に並びな!」「いえ、教えていただいたらここでチケットを買いますから」途絶えることのないたくさんのお客への対応で、窓口の男性は疲れきっている様子でした。そこへきて三枚お願いしたのに手渡されたチケットは、一枚。不安になって「あの〜、三人なんですけど」ときくと「いいの。ほら、ここに三人分と書いてあるでしょ?」確認すると、なるほど、一枚で三人分になっていました。三人が同じ行動をとるのですから、これで事足りるのです。
なかなか合理的だな、と、このときはちょっと感心したのですが、旅の最後にコルトーナという街から同じくフィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ駅までの切符を買った時には、三枚でてきました。どうも一貫性がないのか、窓口の方の気分なのか…未だに謎です。
明日は午前中にフィレンツェ名物(?)の中央市場に出向いてお土産や食材を物色したあと、三泊するシエナへの移動です。宿のご主人から「駅からは、地下のバスプールから17番のバスに乗ります。それが途中サレ広場でしばらく停車して番号が2番に変わるけど、降りずにそのまま乗り続けてね。ヴァッリ、というバス停になったら教えてくれるよう運転手に頼んで、必要ならここの住所もみせて…」などと、事前にメールで細かい指示をもらっていました。う〜む、なにやら難易度高そう。果たして無事にたどり着けるのかしら…。
■第631回 『トスカーナの傑作』 其の一
イタリアは、20年以上ぶりです。その時は冬のベニスでしたが、アドリア海からの風の凍えるような冷たさにもかかわらず、溢れかえるような観光客の多さに圧倒され、ドゥカーレ宮殿の黄金の階段にさらに圧倒され、その大広間にある世界最大といわれるティントットの絵画に圧倒され、さらにはお店の人の商売熱心さに圧倒され…、と、ただただ打ちのめされるような強い衝撃を受けた印象が残っています。
今回は、両そんなベニスを州都とするベネト州から南へ進んだところ…イタリア中央部のトスカーナ州への、両親との三人旅です。州都フィレンツェを筆頭にピサ、シエナなど、魅力的な観光地も多くあるこの地方は、キャンティやスーパータスカンなど、よいワインの産地や美食の地としても知られています。
「西洋の芸術を学んでいるのだから、トスカーナ…特にフィレンツェにはぜひとも行くべきだよ。素晴らしい芸術に触れて心や感性を育てることは、楽器の練習以上に大切なことだからね」ハンガリー留学時代の恩師、バルトーク弦楽四重奏団のヴァイオリニストだったシャンドール・デイヴィチ先生が、よくおっしゃっていました。先生は特にラファエロがお好きとのことでした。「フィレンツェに行ったら、ラファエロの素晴らしいコレクションがある美術館があるから、訪れてみなさい」フィレンツェにはそれはたくさんの美術館があって、すべてを見ようと思ったら一週間どころか一ヶ月間滞在しないといけないのではと思うほどですが、ぜひともそこは訪れたい…。
さて、旅の初日。夜遅くに、旧市街地のド真ん中にして有名な大聖堂(ドゥオモ)のすぐ近くにある、15世紀の建物をそのままホテルにした宿にたどり着きました。スタッフによると、このフレスコ画も当時からのオリジナルで、絵を良い状態で保存するため、この部屋はホテルとしての創業以来ずっと禁煙室なのだそうです。
天井まで8メートル近くある立派な部屋に案内され、天蓋のついている素晴らしいベッドや、それに横たわらずとも目に飛び込んでくる、天井に広がる天使のフレスコ画を眺めているうちに、ひとつの願いが頭に浮かびました。今回はベニスの時のようにただ圧倒されるのではなく、何かに気づいたり感謝したくなるような滞在にしたい、と…。
ウフィツィ美術館やアカデミア美術館などのようなところで、観きれないほどの至宝たちに圧倒されるよりも、街をゆっくり歩き、人々と触れあうなかで、私たち日本人とは違う部分や同じ部分をニュートラルな気持ちで感じたい。そして、自分の原点にたちかえるきっかけを得られたら…と、思ったのです。
「ねえ、ママたちはウフィツィ美術館には入ったことあるのよね?じゃ、今回はそこへはいかないでサン・マルコ修道院に行ってみない?“天使の画家”といわれているサラ・アンジェリコの美術館になっているの。そのあと、ベッキオ橋をゆっくり散歩して…ランチの後、ピッティ宮のパラティーナ美術館を観るっていうのはどう?そこは“聖母の画架”ラファエロのコレクションで、世界的にも有名なところなのよ」
二つ返事で承諾をもらい、ゆっくりと朝食をとったあと部屋を出ました。修道院の美術館には陽当たりのよい回廊があり、修道院のままの間取りが残されていて、修道女たちの小部屋もそのまま展示に使われていました。サラ・アンジェリコは生涯をかけて“神の愛”を描き続け、絵筆を取る前には必ず長い祈りを捧げたと伝えられている画家です。『受胎告知』は他にもたくさんの画家が手がけたテーマですが、彼のそれはひときわ素朴で優しいタッチで描かれていて、マリア様の素直な驚きをたたえた表情が、とても印象的な作品でした。
ウフィツィ美術案も、あのミケランジェロのダビデ像があるアカデミア美術館も、噂に違わずチケット売り場は長蛇の列。素晴しいマスターピース(傑作)の数々は、美術ファンならずとも一目見てみたいと思うのは人情ですが、せっかく観るならゆっくり鑑賞したい。でもそうすると外を歩き、街で過ごす時間がその分減ってしまう…時間に限りがある旅行者のつらいところです。
宝飾店のきらびやかなショウウインドウや、お買い得なのかは微妙な革製品のお店などは、ほとんど素通り。そのかわり、ランチのお店についてはじっくりと吟味しました。今が旬のポルチーニ茸のタリアテッレを注文した父は、アルデンテに茹であげられたパスタの美味しさはもちろんのこと、日本ではなかなか味わえない生のポルチーニの濃厚な風味やしっかりとした食感に、たいそう感激していました。脂っこくなく塩気もきつくなく、素材の味をシンプルに生かしたイタリア料理を堪能した三人は、この日のハイライトピッティ宮を目指してお店を後にしました。 (*『トスカーナの傑作』其の二 に続く)
■第630回 金婚式は、トスカーナで
「美奈子先生。この前ね、授業参観があったの」生徒さんから授業参観、という言葉を聞くたびに、ずいぶん前に妹が言ったことを思い出します。
私たち、授業参観っていつも楽しみだったよね、という話題になったときのこと。妹曰く、「だって、私ママが一番きれいって思っていたもの。お友達のなかで、私のママが一番きれいだし、私のパパが一番ハンサムだって思ってた。」
妹のように“一番”に思っていたかどうかはわかりませんが、私もまた、パパとママは美男美女のカップルだなあ、と、ひそかに思っていました(ちなみに、私は本当に小さい頃、当時某清涼飲料水のコマーシャルをしていた加山雄三さんのポスターを見つけては、それを指差して「ぱぱー!」と叫んでいたそうです。母は、世間の誤解を招いてはと、一応、慌てたそうです)。考えてみたら、なかなかおめでたい姉妹です。
おめでたいついでに、九つ年下の弟もまた、自分の母親の本当の年齢を、つい最近まで(?)知りませんでした。母が冗談のつもりでウソの年齢(もちろん、実際よりもかなり少ない数です)を教えていたのを、疑いもせずなが年そのまま鵜吞みにしていたのです。よく考えればわかりそうなものなのに!…彼もまた、かなりのおめでた君といえるかもしれません(彼の名誉のためにお話ししますが、それでも私よりずっとしっかり者です)。
そんな両親も二人とも70代になり、来月金婚式を迎えます。結婚して50年…半世紀が経つということは、私が生きてきた時間よりも長い間、ずっと夫婦でいるということ。昨年、私もデビューして25年も経ったんだわ、と、ひそかに感慨にふけったのですが、その二倍の時間です。
その間、聞き分けのない長女がピアニストになりたいとゴネたり、やっと音楽大学を卒業すると思ったら今度はヨーロッパに留学したいといってきかなかったり、留学から帰ってきたかと思いきや結婚したいと言いだし、その10数年後には離婚までしてしまう…、とまぁ、どんなにか心労をかかえ続けていることでしょう。
今、書きながら気づいたのですが、姉弟の中でおめでた度ナンバーワンの私ばかりが、両親に心労を提供しているようです。この問題児が原因で、離婚の危機に見舞われ、家庭崩壊になってもおかしくなかったところですが、こらえてくれたことには、心から感謝しなければなりません。私のせいで両親が離婚、なんてことになったら、妹と弟に申し訳がたちませんもの。
さて、いよいよ「親孝行」というより「罪滅ぼし」と言ったほうがぴったりくるような、金婚式記念のトスカーナ三人旅が近づいてきました。
これまでも、両親とは何度か海外旅行をしています。初めて父を海外に引っぱりだした、スペイン旅行。南国でゆったりリゾートを過ごす経験をしてもらおうと、プレゼントしたバリ島旅行。父に国際免許を取ってもらい、イギリスの湖水地方からスコットランドのエジンバラまでドライブし、個人経営のファームハウス滞在を楽しんだイングランドの旅。デザインホテルに宿泊し、国立公園、地方都市探訪やサウナを堪能したフィンランド旅行。
今回は、あまりアクティビティーを予定しないで、自由気ままに過ごす旅にしよう、ということで、三人の意見が一致しました。もともと私は、“観光”より“滞在”を楽しむ旅が好きなので、ますます楽しみです。いつもなら入念に下調べをするのですが、今回はあえてあまり予備知識をもたず、現地でたくさん戸惑ったり、感動したり、驚いたりする旅になったらと思っています。
美しいものをみることも、美味しいパスタや郷土料理を食べることも、カフェでまったりと過ごすことも、地元のワインを味わうことも大好きな、三人の珍道中。どんな出来事に遭遇するか、今からどきどきしています。折しも、ポルチーニやトスカーナ名物の栗のシーズンまっただ中。食べ過ぎてお腹をこわさないよう気をつけて…行ってまいります!
(*トスカーナ旅行のため、来週12日の更新はお休みいたします。次回の更新は、19日夜に致します。)
■第629回 ひらけゴマ!
秋の清々しい空や風に、「素敵な贈り物をありがとう!」と、感謝したくなるこの頃です。
この季節になると毎年のように、このエッセイで食べ物の話をしているような気がします。確かに、季節限定の栗や柿のお菓子が目に付くようになりますし、各地からの新米も続々と店頭に並び始める時期です。そこへきて、新酒の案内やら故郷からの芋煮の便りやら…。そわそわするな、といっても無理な話です。よく“女心に秋の風”といいますが、それって、美味しいものに落ち着きを失って、つい気持ちが不安定に揺れ動いてしまう、というのが本当の由来だったりして…(!?)。
よく「人生最後の晩餐に、何を食べたいか?」という質問を見かけます。シンプルに卵かけごはんがいい、とか、いやいや自分は納豆派だ、とか、色々な意見が飛び交いますが、私の心は決まっています。それは、ある和菓子です。
それを言い当てることができる人は、おそらく周囲にはいないと思われます。なぜなら、幸せそうにそれを食べている姿を知る人は、とてもわずかだから。もったいつけるほどのこともないので白状しますと、それは宮城県や岩手県などで一串105円ほどで売られている、ごまのお団子です。
「え?ごまのお団子なら、関東にもあるよ」…いえいえ、違うのです。この辺りのごまのお団子はほとんど小豆の餡が主体で、そこにじゃりっとた摺った黒ごまを混ぜ込んでだもの。あるいは、みたらしのような甘いお醤油ベースのたれに、摺った黒ごまが混ぜ込んでいるものだったりして、東北地方で当たり前に皆がごま団子として親しんでいるものとは、味わいも食感も全く別物なのです。
かの地のごま団子は、濃厚でとろりとなめらか、かつ、香ばしく、うっとりするほど美しく艶やかな黒色のごま餡に包まれたもの。中でも、宮城県大崎市という有名な米どころで生産される“みやこがね”という餅米が使われているお団子は、もちもちとしながらとろけるような舌触りです。もちろん、添加物の類いは一切不使用。こんな極上スイーツが105円で食べられる幸せときたら…!
豆食いの私としては、おはぎやぜんざいなど、小豆の甘味も大好きです。でも、小豆は甘いものだけに使われるイメージですが、ごまはお料理にも甘味にも、何にでも万能な働きをします。栄養価、滋養や効能、風味、アレンジ性…どれをとっても素晴らしいし、じっくりと絞って作られるごま油も大好きです。そう、私の中でゴマは、マルチで頼りになって、個性豊かでありながら周囲と調和しそれを引き立てる、理想の男性のようなものなのです。
東北地方以外ではなかなか見かけることがなく、かといって買って帰るにも日持ちしないのが、ごま団子の唯一の不満です。翌日にはお団子が固くなってしまうのです。従って、私が唇を黒くしながら嬉しそうにそれを頬張っているのを目撃しているのは、仙台の実家の両親と、ほんの一部の友人だけ、ということになります。
私のゴマ好きはどこで育っても同じだと思うので、もし東北に縁がなかったら高野山のごま豆腐あたりを最後の晩餐に選ぶことになったのかもしれません。
ごまの原産はアフリカだそうですが、最近そのゴマの花や鞘を見てますます好きになりました。美しい緑色の鞘の中に、きれいに整列してびっしり入っている種たちこそが、ごまの正体。一つの鞘に、100粒ほど入っているそうです。でも、99.9パーセント以上を輸入に頼っていて、国産はほんの僅かなのだそうです。鹿児島県の喜界島に、そんな貴重な国産のごまと黒砂糖を使ったお菓子を、昔から変わらぬ製法で作り続けているところがあるのだとか。う〜ん、食べてみたい!そうそう、一般的にごま油は白ごまから作られるとのことですが、鹿児島には黒ごまの油を作っているところがあるそうです。
“ごまかす”“ごまをする”など、言葉上は今ひとつ良い意味に用いられることが少ないイメージがあるゴマですが、とびきりステキな呪文がありました。「ひらけごま!」…その語源には諸説あるようですが、ごま好きな私としては、鞘がはじけ、中の宝物のようなゴマの実が飛び出してくるように、ミラクルな出来事がおこりますように!…と願う意味、という説を信じたい気持ちです。
■第628回 ハッピー・コミュニケーション!
ピアニストのひとり言 第628回 ハッピー・コミュニケーション!
「実は、人見知りなんです」テレビをつけると、よく人気タレントさんが照れくさそうな表情でそう語っていますし、周囲にも、一見とてもそうは見えないのですが“自称人見知り”の友人が少なくありません。
そもそも、人見知りとはどういうことなのでしょう?もちろん、本来は子供が知らない人に対して、恥ずかしがったり泣いたりすることをいう言葉ですが、このごろは「内気」「はにかみ屋」というニュアンスで大人にもよく使われます。でも、あまり親しくない、あるいはまだそれほど親しくなっていない相手に「人見知りです」とアピールできること自体、すでに立派なコミュニケーションスキルを持っていることになるのでは?もしかしたら子供の時には人見知りだったのかもしれませんが、とっくに克服していることになります。大人になってなおも本当に人見知りだという人は、そういったことをうまく相手に伝えることができないのではないでしょうか。
ところで、私はどうだったのでしょう?…極度な人見知りでもなく、特別社交的でもなく、ごく普通の必要最小限の社会性で幼児期を過ごしてきたように思います。
でも、幼稚園も小学校も中学校も途中で変わり、入ったところを卒業できたのは高校が初めてでした。つまり、小さい頃から筋金入りの転校生でした。
転校経験のない人にはイメージして頂きづらいかもしれませんが、学校にはそれぞれに校風とか、クラスごとのカラーやローカルコードのようなものが、はっきりとあります。地域によっては言葉も違いますし、校則も違います。細かいことを言えば、朝礼のスタイル、ゴミの捨てかたや掃除の仕方、制服に体操着…何から何まで違うのです。
例えば4月の新学期から何日も何ヶ月もの年月の間を経て、すでに成熟?しているソサエティーの中に、他所から、他所の空気を漂わせ、皆には見慣れない制服でぽつんとその中に入るのは、子供ながらにプレッシャーでした。案外繊細なところもある私は、その違いを感じるたびに戸惑いましたし、転校が好きになれませんでした。
でも、そんな中で身に染みたこと、身に付いたこともあるように思います。例えば、何も分からずにおろおろしている私に優しく声をかけ、これから一緒に学校に通いましょうよ、と言ってくれたのは、必ずしもクラスの優等生や学級委員とは限りませんでした。でも、彼らは共通してとても温かい思いやりを持っていて、ただ自分の知識をひけらかしたり、自分の話したいことを話すのではなく、一生懸命に私との共通の話題を見いだそうとしたり、自分の友達を私の友達にしようと気を遣って、何かにつけて助けてくれました。そんなクラスメイトたちの優しさに、これまでどんなに救われてきたことでしょう。
転校を繰り返すたび、人ときちんとコミュニケーションをとれるということは、学校の勉強ができること以上に必要なことかもしれないし、相手を安心させたり、楽しい気持ちにさせたりできるって、すごく素晴らしいことだ…と、身を以て感じるようになりました。よいコミュニケーションをとれることは、人としてのマナーなのではないかしら。そういうことができる人に、私もなりたい、と心から思うようになりました。そして、皆とよいコミュニケーションがとれるよう、自分なりにあれこれと心掛けるようにしました。
今思うと、転校を大きな重荷に感じ、ちいさな戸惑いを膨らませてしまいがちだった私は、必ずしも社交性に長けているとはいえませんでした。でも、今は周りから「美奈子ちゃんと話すのは楽しい」とか、「また、いろいろ話を聞かせて」と、嬉しいことを言ってもらえるようになりました。外国であまり気後れすることなく、人と話すことが出来るのも、そんなひとつひとつの経験があったからこそかもしれません。
地元の友人も増え、先日20代から50代の友人10数人と海へ一泊旅行に出かけました。年代も職種も異なる男女のグループでしたが、心からくつろいだ、楽しい時間を過ごすことができました。大人になってこんな素敵な仲間ができたことに、感謝です。
周囲の人との関わりを大切に育てていける自分でありたいし、いくつになっても人とのコミュニケーションを楽しめる柔らかさを持っていたいです。優しく接してくれたクラスメイトたちの思いやりに、応えるためにも…。
■第627回 年月の積み重ねに、乾杯!
東京でのオリンピック開催が決まり、世の中に様々な意見が錯綜しています。
東北出身の私の思いがどのようなものであるかをお話しするのは、ここではやめておきます。喜んでいらっしゃる人もたくさんいますし、良いこともたくさんあるはず…。いいえ、決まった以上はそれを信じるべきだとも思いますので、あえて水を差すことは遠慮します…というコメントに、複雑な想いをこめるにとどめましょう。
ところで、開催決定のニュースに湧いた日、ある同級生のFacebookの投稿には思わず苦笑しました。「56年ぶりに東京で開催!と、朝からアナウンサーが何度となく繰り返し報じているが、まだ7年も先の話。同級生には分かると思うけど、その数字を聞くたび一気に年をとった気がしてならない」
そうです。その、“7年後の56年ぶり”…つまり、今から49年前の東京オリンピックの年こそ、私たちの産まれた年なのです。
その年は東京・大阪間を結ぶ東海道新幹線や地下鉄日比谷線全線、また東京モノレールも開業して、日本にとってなんとも輝かしい一年になりました。余談ですが、ライオンが“デンター”を、カルビーが“かっぱえびせん”を、またロッテが“ガーナチョコレート”を発売した年でもあります。
アスリートで陸上競技の選手だった父は、第一子である私の出産予定日がオリンピック開催期間と重なり、たいそう喜んだそうです。聖火の一文字をとって、女の子なら“聖子”という名前まで私に用意していたらしいのですが、予定日が過ぎ、閉会の日が近づいてきても産まれる気配がありません。結局、私は産まれる前から散々父をイライラさせ、すっかり五輪が閉会したあとに、満を持して3800グラム級の大きな体でこの世にお目見えしたのでした。聖火台の日が消えて一週間も過ぎた後…11月1日のことです。
もはや、タイミングを外して産まれてきたこの赤ん坊の名を「聖子」にする意味はない、というわけで、私の名前は今のものになったのですが、父には申し訳ないけど、私自身は聖子という名前よりも今の自分の名前の方が気に入っています(あー、遅れて産まれて良かった!)。ちなみに、私が産まれた三日後の11月4日に、仙台空港が開港しています。意外にも、山形空港が開港になったのはその約5ヶ月前です。
と、いうことは。私が産まれる一年前に結婚した両親は、今年金婚式を迎えることになります。ありがたいことに二人とも今も元気で、父は毎日のように家庭菜園にでて畑仕事に精を出していますし、母は相変わらずパワフルにパソコンを使いこなし、気になる本を片っ端から読破し、ハングル語で日記をつけています。
彼らは私の産まれる前から、当たり前のように一緒だし、結婚後50年が経とうとしている今もそろって元気にしていますが、それは当たり前のことと、というよりも、とても貴重な、感謝すべきことです。
大好きな音楽の道に進ませてもらうにあたって、両親に色々と無理をお願いしてきた私は、「大きくなったら親孝行しなくちゃ」と、何度も自分に言い聞かせていたはずでした。で、もうとっくに「大きくなって」はいるものの、果たして親孝行できているのかしら。
そこで、なにか思い出に残る親孝行を…と、三人での旅行を計画することにしました。三人で旅するのは、父に国際免許証を取ってもらい、湖水地方からエジンバラまで車で回った6年前以来です。食べ物が美味しく、文化遺産も豊かでのんびりできる美しいところ…と考え、来月秋のイタリアのトスカーナ地方を訪れることにしました。団体旅行では訪れないような村や、美味しいオリーブオイルなどを自家製しているアグリツーリスモと呼ばれるファームハウスにも、滞在する予定です。
先ほど「美奈子ちゃんから苗をもらった葡萄、収穫しましたよ。5〜6キロはある!これから実と皮を分けてジャムにします」と、弾んだ声が聞こえるようなメールが届きました。今ごろ、鼻歌をうたいながらくつくつと煮詰めていることでしょう。キッチンに甘い香りを漂わせながら…。
■第626回 恋の終わりは、愛の始まり
雷や竜巻、台風と大雨…。猛暑の夏の終わりに人々はかつてないほど激しく変化する気候に翻弄され、体調まで乱されがちです。私もまた、自然の力の恐ろしさを身にしみて感じることになりました。落雷の影響で、愛機iMacが大乱調。まるまる一日、復旧やら対処に追われ、他のことがいっさい出来なくなりました(残念ながら、マシンの問題は未解決のままです)。
そうかと思えば、朝夕には秋の気配が感じられることも増えてきました。人にキビシい試練を与えたかと思うと、ホッと和ませてくれたり、はたまた今度はいつまた牙をむかれることか、と、皆気が気ではではありません。これはまさに、「ツンドラ」ならぬ「ツンデレ」気候です。
そうはいっても、秋は秋。待ちに待った収穫の秋です。旬の農作物や魚、新米や果物。この頃とみに思うのですが、ごちそうとは贅沢な食べ物のことではなく、美味しい食材を美味しくいただくことに他ならないのではないでしょうか。どんなに美味しい食材も調理が適切でなければ素材の良さを生かしきれませんし、たとえどんなに美味しいお料理が目の前にあっても、美味しくいただく楽しい雰囲気や会話がなければ、味気のないものになってしまいます。
食べ物もさることながら、私は秋の草花が大好きです。例えば、吾亦紅(ワレモコウ)の凛とした姿と深い色。ぽってりと愛らしいまるみを帯びた花びらの秋明菊は、見るたびに実家の庭を思い出し、懐かしい気持ちで胸がいっぱいになります(ちなみに、秋明菊は菊と名がつきますが、キク科ではなくキンポウゲ科だそうです)。
数年前に鮮烈な出会いをして以来、大好きになった秋の花の一つに、チョコレートコスモスがあります。花の形はポピュラーなキバナコスモスとそっくりですが、特別なのがその花の色と香り。ビターチョコレートのようにシックで個性的な黒紫色に、かすかにチョコレートのような香りがするのです。メキシコ原産で、日本に入ってきたのは大正時代というデータがありますが、花屋さんに出回るようになったのはここ最近…2000年代に入ってからではないでしょうか。
初めて出会ったのは、プライベートで大きな変化があり、日本で初めての一人暮らし(寮生活は除いて)が始まったとある秋の日。友人のフローリストさんの営むお花屋さんで、でした。「コスモスにも、こんな種類があるんですよ」と差し出された瞬間、ふわっと包まれた特徴的な香りにも驚いたのですが、それ以上に心惹かれたのは、色でした。ピンクでも白でも黄でもないコスモス。媚びることなく個性を主張し、圧倒的な存在感を放っているその姿に、「皆と同じじゃなくても、あなたの人生、あなたらしく謳歌すればいいのよ。私みたいにね!」と、どん、と背中をおされたような気持ちになったのを覚えています。
ふと気になって、チョコレートコスモスの花言葉を調べてみました。「恋の終わり」「移り変わらぬ思い」とありました。
一瞬「え?気持ちが移ろってしまったから、恋が終わったのでは?このふたつの言葉、矛盾していない?」と思ったのですが、よくよく考えるうちに、なんとなく意味が分かってきたような気がしてきました。
まず、恋とはなんぞや?ということです。恋は、誰かを思って心がときめき、まるで熱病にかかったように?強く相手を求める気持ちでしょう。そんな時、人は相手がどうあれ、自分が会いたい、一緒にいたい、と欲する激しい気持ちに支配されがちになります。一方、愛とは?愛することとは?
ある意味でそれは恋とは正反対に、自分よりも相手を思いやる穏やかな気持ちなのではないでしょうか。相手に何かを望む以上に、相手のために何が出来るか、見返りを求めることなく問うことで、男女間だけのものとは限りません。
そうなのです。超持論ですが「移り変わらない思い」を抱く人の「恋の終わり」は、熱病を経て、それを克服した人の新たなるステージである「愛の始まり」を意味するのではないか、と…。
なぁんて、ガラにもなくちょっとおセンチなことを考えてしまうのも、秋風のせいでしょうか?ともあれ、今年の秋、チョコレートコスモスがますます好きになりました。
■第625回 体づくりも大切!
今年もまた、10年以上関わらせていただいているジュニアピアノコンクールの、本選審査の季節が巡ってきました。地区予選を勝ち進んできた皆さんの、満を持してのビッグステージです。
先週、福島県でのコンクール本選審査を終えました。参加者の皆さんのわずか数分のパフォーマンスから、それまでの練習やご両親、担当の先生の熱意などが痛いほど伝わってきて、皆さんそれぞれ素晴らしく、点数をつけるのが忍びない気持ちになります。
演奏のレベルはおしなべて年を追うごとに高くなっているのですが、いつも「はて?」と疑問に感じることがあります。それは、テクニック…なかでも、体全体の使い方についてです。全体のテンポやまとまりなど、表面的なことはしっかりと作り込まれているのに比べ、体の使い方や和声感など、本来、演奏の完成度を大きく左右するはずの“基礎”が、案外伴っていないな、追いついていないな、と感じることが多いのです。
よく、音楽や演劇などの部活動を文化系、陸上や球技、水泳など、各種スポーツを運動系、と呼びますが、実は文化系もかなりの運動能力が必要とされます。ことに演劇は、走り込んで呼吸を深くしたり、横隔膜や腹筋を使う、きちんとした発声法をトレーニングしたり、はたまた必要に応じて様々なダンスも学ばなければならなかったり…と、かなりの運動量を必要としますが、音楽の演奏もそれに近いものがあるのです。
運指だけでなく、自然な呼吸を心かげ、自分の腕の重みを楽器に伝えつつも、肩にも首にも…さらには顎にも口元にも、余計な力がかからないよう脱力ができていなければなりません。その上で、肩から手にかけての自然な動きや手首の柔軟性によって、指先の細やかなタッチのコントロールを得ていくのです。そうした“よい体の状態”という、楽器を弾くためにふさわしい“環境”が整わずして、安定したテクニックを身につけていくことは、とても困難なのです。
ところが、どうやら日本のピアノ教育をみていると(他の楽器のことはよくわからないので)、案外この大切な基礎の部分がおざなりになりがちで、生徒さんは一見立派に曲を弾きこなしているようでも、よく聴くと表情の変化に乏しかったり、パートごとの弾き分けがきちんとなされていなかったり、何より、全体の音色が不必要な力みによって硬くなっているケースが多くみられるのです。
これは、指導者だけの問題ではないように思います。早く格好良く曲を弾けるようになりたい、という、勤勉にして少々せっかちな国民性の影響や、難しい曲を弾けるようになるのがえらいことなのだ、と、考えがちな習い手のニーズが、つい指導者に基礎を“はしょらせて”しまったり、上達が実感しにくい練習には、生徒さんが飽きてしまいやすい…などなど、問題の根は深い気がします。
(和声感については、さらにいろいろと感じることがあるのですが、話が少々小難しくなるので、ここでは割愛することにしましょう。)
先日、偶然テレビでレッスン番組をみました。レッスンといっても楽器ではなく、水泳のレッスンです。もとオリンピック選手の指導者が、生徒役のタレントさんに「水は液体ですから、そもそもつかむことが出来ないものですよね?それを無理に力で征服しようとしないで、水と一体になって動く、という感覚が大切なんですよ」とアドバイスしていたのが、とても印象的でした。演奏も同じなのです。曲を支配しようとせず、自分の体の状態を意識しつつ、自然な呼吸と動きで音楽と一体になる…、その感じを掴むための体の基礎練習が、実はとても大切だったりするのです。
もちろん、作品の読み込みや解釈、正確なタッチをもって自分の表現を形にしていくことは、大きな目標です。でも、それを実現するためのよい体づくりについて、もう少し意識を向ける価値があるのではないかしら、それによってぐんと伸びる子供たちが、たくさんいるはず!…と、思ってしまうのでした。
今度の週末は、二日間にわたって山形でのコンクール本選の審査のお仕事が待っています。音楽を心と体で感じ、受け止め、のびのびと私たちに表現してくれる演奏を、期待してやみません。
■第624回 マゾヒスティックな宿題
関東地方ではもう二ヶ月ほども厳しい暑さが続いています。無理して努力することはせず、お昼寝したり練習や外出を減らしたりしてだましだましやり過ごしていますが、それでもだんだん体が重くなってきました。
一心同体?の相棒である愛器ベーゼンドルファーも、このところご機嫌ななめです。特定の音に雑音がでてしまったり、音程が狂ったり…。毎日気温だけでなく、湿度も高いのですから無理もありません。なるべく除湿はしていますが、どうもコンディションが安定しません。
ふと、初めてヨーロッパでピアノを鳴らした時のことを、思い出しました。ブダペストのリスト音楽院のレッスン室でのことでしたが、あまりの響きの違いに驚いて、「え?」と、思わず楽器を弾く手を止めてしまったほどでした。毎朝、音楽院専属の調律師がメンテナンスしているハンブルク製スタインウェイの音の素晴らしさに感激したのはもちろんですが、空気の違いもさることながら、天井の高さ、内装や建材の違いなどがすべて響きに反映され、それまで日本で聴いてきた自分の音とは大きく異なっていたのです。
湿度…空気中の水分は、こんなにも音を吸収するものだったのだ、と実感しながら、日本の独特の重たい湿気だけでなく、家や部屋に使われている木も壁も、この国の建材である石や、部屋に置かれている音を乱反射させる石の彫刻などとはかなり違う響きの環境をつくっていたのだ、と改めて感じました。
同時に、日本で弾いていた奏法では、必ずしもよい響きが得られないことにも気づきました。力を抜いて、らくに弾いた方がよほど伸びやかに響く音が出るのです。日本では欠点ばかりを目の前に突きつけられるようなデッドな響きの中で練習していましたが、適度な残響や美しく響く自分の音をほれぼれと聴きながら練習できるのが嬉しくて、ますます“弾く”“奏でる”ことが楽しくなりました。
ピアノですらそうなのに、弦楽器の響きかたやコンディションに至っては、その違いはもっと明らかでした。当たり前のことですが、やはりこういった楽器はこの地で産まれ育まれたもので、この環境の中でこそ最高のレスポンスを発揮するものだったのです。
外国で飲んでとても美味しかったワインをお土産に買って帰ったものの、日本で飲んだらそれほどではなくてがっかりした、という話はよく聞きます。その環境の中でこそ引き立つ味わい、というものは確実に存在するのだと思います。日本では特別食べたいとは思わない、こってりしたフランスの郷土料理も、かの地で食するとなんとも美味しくて、するすると食べられてしまった、ということも、よくあります。
さて、日本の夏は暦の上ではそろそろおしまいのはずですが、まだしばらく高温多湿の日々が続きそうです。寝苦しい夜が続いて疲れがとれない人が増え、病院には「睡眠外来」なるものもできて、連日患者さんで大にぎわいだといいます。この過酷な環境の中で心と体の健康を保とうとするならば、確かに何らかの工夫は必要かもしれません。
エアコンやクールグッズを使って体を冷やすのも一つの方法かもしれませんが、やりすぎるとかえってダルさが残ってしまうので注意が必要です。そこで、私はここ数年、心理作戦に出ています。
例えば、ガラスや寒色系の食器を使うこと。清涼感のある香りのバスグッズを使うこと。涼やかな印象の音楽を聴くこと。エアコンなどで体を外から冷やすよりも、トマトや瓜、旬の果物など、体を内側から冷やす食品を摂るように心がけること。
また、人と会う時には、なるべく他の人から涼しそうに見えるような装いをすることも、心がけています。あえてこっくりした色の浴衣を着ることもありますが、その時には普段よりもしっかりとベースメイクをして、できるだけお化粧くずれしないように気を配ります。「崩れ←汗←暑い」というイメージが伝わってしまうからです。
そうやってなんとかしのいでいるうちに、秋の風が吹く日がやってきたら、きっととてもありがたく感じられることでしょう。その時までもうしばらく、酷暑を楽しむ、というちょっとマゾヒスティックな宿題を、自分に与えることにします。
■第623回 夏休みらしい夏休みを
夏休み真っ只中。でも、これを休みと呼んでもいいのかしら、と疑問に思うほど、子供たちは忙しそうです。
個人差はありますが、生徒さんに聞くと、その過密なスケジュールに驚かされることが少なくありません。私のころは夏休みといえば、数日間のプールとたまの登校日に学校へ行く程度でしたが、今はそれ以外にほぼ毎日の部活動、塾やらスイミングやらの夏期講習、もはや日本の名物(迷物?)になっている“自由研究”というなにやら壮大な響きのものを含む膨大な宿題、それらをぬっての家族でのお出かけなど、まるでちょっとした芸能人並み?のスケジュールです。
「宿題は進んでる?」と聞くと、だいたいの生徒さんから「うん、もうほとんど終わったよ!」と、頼もしい答えが返ってきます。うむ、さすがは我が生徒。「わぁ、すごいなぁ。…ところで、ドイツの小学校って宿題がほとんどでないんですって」「え〜?」「勉強は学校でしっかりとすませてしまうんだって。例えちょっと宿題のようなものがでたとしても、みんな家に帰る前に終わらせてしまうのだそうよ」「へぇぇ…すごい!」勤勉なイメージのあるドイツですら、です。
「でね、学校が終わったら、部活もないの。塾の話も聞いたことないし。子供は学校が終わったら、お家で家族とゆっくりお話ししたりして過ごすべきだ、という考え方なのだって、ドイツの人が言っていたよ」「いいなぁ。宿題がないなんて!部活は、楽しいからまぁいいとして…」「そうね、学校の部活がなくても、校外でジュニアオーケストラの活動をしたり、少年サッカーのチームに所属したり、ということは、個別にできるしね」
ことのほかヨーロッパでは、たくさんのことを“記憶”するよりも、自分でじっくりと“思考”“試行”する力をつけることに重きを置いて教育をしているので、政府や学校の指導方針やカリキュラムの組み方も、自ずと日本とは違ってきます。そして、受験のあり方も。
仕事が終わっても、「接待」「付き合い」といった“宿題”が待っている一般的な日本のお父さんたちのパターンは、案外、小学生や中学生たちの生活スタイルの延長線上に、いつのまにか築かれて来たものなのかもしれません。
もちろん、それだけの理由ではないことは理解しています。でも、強制ではないにせよ(私の時はほとんど強制的でしたが)、参加することが前提になっている部活動のように、「付き合い」が発生すると、強制的ではないにせよ、参加する前提で空気が流れていく、といった部分も、あるような気がするのです。
考えてみたら、ヨーロッパの人たちは“区切り”をつけることがしっかりと身に付いているように思います。子供たちの家と学校での過ごし方を分ける生活パターンしかり。他にも、バカンスは一ヶ月以上充分にとり、それを一年の家族イベントの主軸に置いて生活にメリハリをつける、とか、コンサートやディナーなど、夜に外出する時には昼間とは服装やアクセサリーを変える、とか。また、電車の中は公的なスペースなので、泥酔して眠りこけるようなことは、彼らは決してありません。
はて、自分はどうかしら、と、振り返ってみます。音楽家という職業柄、レッスンなどの仕事がない日もピアノの練習や音楽の勉強はしますし、趣味としても音楽を愉しんで聴いたりもしますから、そういう部分での“区切り”は他の職業の方たちよりも曖昧かもしれません。でも、そういえば、家でのレッスンの時、仕事や遊びで出かける時、家でくつろぐ時、就寝する時、と、服装は変えています。例えば、仕事の前、仕事の後と着替えるので、仕事のある時は一日に4回、着替えていることになります。それを区切りに、無意識的に気分転換しているのかもしれません。
最近の社会人は高度成長時代の頃の人たちよりも、付き合い飲み…いわゆる“飲みニケーション”をしなくなった、と言われています。それが良いことなのか、良くないことなのかは、表面的なことだけではわかりません。自分のペースと主義をもって行動を選択している、というなら良いことでしょうし、協調性に欠きコミュニケーション自体がとれなくなっている、ということなら良くないことになるでしょう。生徒さんたちが大きくなって社会に出た時に、どんな考えをもって、どんな選択をするようになっているのか…。いずれにしても、夏休みをたくさんエンジョイして、自分らしさをたくさん見つけてほしいと願いつつ、見守っている日々です。
■第622回 ナンバーワンのハンバーガー
巷では空前の“パンケーキ”ブームなのだとか。でも、パンケーキを食べるために3時間もならぶとか、それに1000円以上も出すのだったら、まだハンバーガーの方がバリューを感じる…なんてことから、ハンバーガーの話題になりました。やがて「自分が一番好きなハンバーガーは、どれ?」という、他愛のない話になりました。
ハンバーガーではないけど某ファストフード店のフィレオフッシュが好きだという人、そんなもの食べたことない、という人。日本生れのハンバーガーチェーン店、Mバーガーのものが好きという人、ハワイアンスタイルの、ボリュームのあるバンズ(ハンバーガーに使われるパンのこと)にアボカドが入ったものが好き、という人…案外多岐にわたっていて誰かと重なることがなく、それぞれの好みに違いがあることが判明しました。
かくいう私は、残念ながらマヨネーズやアメリカンスタイルの食べ物があまり得意ではないので、ハンバーガーそのものがちょっと苦手なのですが、よくよく考えてみたら毎週でも食べたいと思ったハンバーガーの存在があったことを思い出しました。
それは留学時代によく食べた、共産圏時代のハンガリーはブダペストのブダ側…市電のターミナルになっている“モスクワ広場”の一角にある小さなスタンドのものです。そこにはホットサンドイッチという、バケットを縦に半分にしたものの表面に、たっぷりのトマトパプリカソース、サラミ、キノコなどの具とチーズをのせて焼いたハンガリー風ピザバケットのようなメニューもあって、そちらも大好きでしたが、そこのハンバーガーを初めて食べた時の衝撃は忘れられません。
まず、おばさんに手渡された時のその重み!…食べたことはありませんが、ビックMック、というものよりもはるかに重く、しかもそれよりもふた周りほど大きいのです。しかも、はさまっているのは、ずっしりと分厚く大きな牛肉のハンバーグと、これまたたっぷりの酢漬けキャベツ!レタスやマヨネーズの姿は、そこにはありませんでした。
牛肉のステーキのような油の甘み、赤みのお肉らしいしっかりとした味と香りが酢漬けキャベツの酸味とよく合って、美味しいのなんの…。しかもそれが値段にして、100円もしないほど!当時出来たばかりのマクドナルドブダペスト店の「ハンバーガー」の、半分から三分の一でした。
自分の乗るはずの59番の市電を何本かやりすごしつつ、真正面にそびえ立つアールデコ建築の郵便局(いわれなければ、それとは分からないほど立派なのです)と、その中心に燦然と輝く共産主義のシンボルの真っ赤な星をぼんやり眺めながら、大きな口をあけてハンバーガーにかぶりつきます(そうじゃないと、厚さがありすぎてバンズだけしか口に入らないのです)。市電のガタンゴトンという音、無愛想にバタンバタン閉まるドアの音などにまみれて、「お花はいりませんか?お花はいかが?」という、まるく広がるフレアースカートを履いた花売りのおばあさんの声やら、「新聞〜、新聞〜!」と、独特のダミ声(失礼!)で呼びかける新聞売りのおじさんの声が聞こえてきます。
駅もそうですが、ターミナルのような場所は浮浪者も多いし、ロマの人たちもかなりたむろしていました。そんなふうにぼんやり立ち食い(あちらでは普通のことではありますが)をしていると、東洋人の珍しさにしばしば声をかけられることもあって、気候の良いときは、市電に乗らずにそこから自分のアパートメントまで、歩いて帰ることもありました。
脇を通り過ぎる東ドイツ製のトラバント(有鉛ガソリンで走り、排ガス規制でひっかかるため、例えば、オーストリアや西ドイツなど西側の国では走行できない車)の放つ強烈な排気ガスの臭いや、いかにも馬力のなさそうな乾いたエンジン音、通り過ぎる市電のカンカンというけたたましいクラクション?などの喧騒のなか、ブダペストの丘の石畳を歩きながらほおばったハンバーガーの味は、他のどこでも味わうことの出来ないものでした。
さて、一番好きなハンバーガー。「美奈ちゃんは?」と聞かれて、まさかそれを説明するのはなぁ、と答えに困っていたら、誰かに「美奈ちゃんはハンバーガー食べるイメージ、ないなぁ」と言われてしまいました。え?じゃあ、どんなもの食べているイメージなの?「ほら、もっときちんとした西洋料理とか…じゃなければモツ煮とか!」「そうそう!カマ焼きとか、イカ焼きとか…」あの〜、みなさぁん!イメージがかなり偏っていませんか〜?
■第621回 ゆるめる修行を
夏休みに入り、あっという間に8月に突入しました。蝉の声で目覚める朝が続いています。私の住んでいる所ではさまざまな種類のぶどうやイチジク、採れたてのトウモロコシや色鮮やかなトマトなどがその美しさを競っているかのように並び、早くも地元産の幸水まで出回ってきました。
レッスンに来る子供たちは皆、太陽のにおいがするような色に日焼けして、帽子をかぶり、水筒を斜めにかけ、女の子は動きやすいワンピース姿。…まるでピクニックに行くようないでたちで楽譜の入ったレッスンバックを持って、元気いっぱいにやってきます。夏休みを謳歌している彼らを見ていると、夏もいいものだ、と思われてきます。
もともと、暑い、とか、湿気が不快、などと口に出して言うのはあまり得意ではありません。言うとさらに暑さ不快さが増すような気がして、つい憚られるのです。良いことはどんどん口に出して、マイナスなことはあまり表にひっぱりださないようにすると、随分心持ちもちがうように思います。
さて。このところ、少しずつヨガのレッスンを再開しています。ヨガはここ数年大きなブームになっていて、ヨガスタジオはどこも大流行り。スポーツジムでも人気のプログラムになっていますし、本屋さんにいけばDVD付きのレッスンブックなどがずらりと並んでいます。一時期はセレブリティなライフスタイルのキーワード“ロハス(Lifestyles Of Health And Sustainabilityの頭文字をとった略語)”な暮らしにふさわしいシンボル的な習い事のようにもいわれていました。
ヨガにもいろいろな流派があるようですが、私が目下とりくんでいるのは、ハタヨガという、もっとも基本的(伝統的?)なものです。体が堅いとか、筋力が弱い、といった条件とは全く関係なく、呼吸に意識を向けたり、いつのまにか凝り固まってしまっている部分を伸ばしてみたりしながら、自分の体に向き合い、心と体を“ゆるめて”いく感じが、好きなのです。
レッスン中は、インストラクターの先生の誘導されるまま、頭を空っぽにして呼吸に集中し、ちょっと辛いポーズをとっている時こそ深い呼吸をして口元を食いしばらないようにゆるめます。顔もなるべくぽかんとして、力を抜くようにするのです。すると、なんとなく辛さがやわらぎ、のびきっていなかった部分が確実にもう少し伸びてくるのは不思議なことです。
前回のレッスンが終わって、体がゆるんだのを感じたとき、ふと、以前母が話してくれた、私を産んだ時のことを思い出しました。「産まれてみたら随分大きな赤ちゃんだったけど、初産なのにとても安産だったのよ。呼吸に集中しているうちに、“早く出ていらっしゃい”っていうお母さんの気持ちと“外に出たい!”っていう赤ちゃんの気持ちが一緒になって、息が合ってくるような感覚になるの。そうなると、痛みよりも早く会いたいっていう気持ちの方が大きくなって…。辛くて大変だった、なんて、感じなかったわ」
母にとってはとても素晴らしい経験だったようでしたし、実際にも見事な安産だったようで、担当医だった院長先生からお褒めをいただき、「まもなくお母さんになる妊婦さんたちに、あなたの出産経験を話してくださいませんか」と頼まれたそうです。
男性には申し訳ありませんが、出産というのは人類にとって、もっとも尊い、神様に近い行為なのではないでしょうか。呼吸に集中し、辛いとき“辛さ”にチャンネルを合わさないで、自然の力に身を任せる。そうすると、奇跡のような素晴らしい何かを感じることができるかもしれない。…私は前回のヨガのレッスンの後、「もしかすると、ヨガってどこか出産にリンクしているのではないかしら」と思ったのです。
暑い、などマイナスなことを口に出すと余計に辛さを感じる気がしたのは、案外真理なのかもしれません。落ち込むことや辛いことがいろいろあるのも、生きている証。不要でマイナスでしかない感情なんて、ないのです。
心も体も柔らかくゆるめて、夏の暑さや冬の寒さも、辛いことや苦しみも、最終的に“生きる愉しみ”に変えていける人になれたら…!でも、そうなるためにはまだまだ修行が要りそうです。
■第620回 ハンドメイドよりハートメイド
久しぶりに仙台に帰省して、家族でよく利用する近くの温泉に入ってきました。
ちょうど良い温度の源泉掛け流しのお湯に体をうずめて「ふう〜っ」とひと呼吸…。日本人なら誰もが無条件に感じる、なんとも幸せな瞬間です。しかもその大浴場には、一面に大きなはめ殺しのガラス窓があって、湯船につかりながら眼下に清らかな渓流が見えるようになっているのです。「ああ、こんなにいい温泉に入れるなんて、本当に幸せなことねぇ」隣で母がもらした言葉にはたっぷりと実感がこもっていました。「そうね、すごく贅沢なことね」そう答えながら、温泉に入れることにも増して、元気な両親とこうして一緒にゆったりとくつろいだ時間を過ごせること自体が、なんて幸せで贅沢なことかしら、と思ったのでした。
さて。そもそも贅沢ってなんでしょう?私にとっての最高の贅沢とは、大好きな場所で、大切な人と、時間を気にせず心豊かに過ごすことに他なりません。ですから、二ヶ月も三ヶ月もの間、必ずしも便利とはいえないロッジなどで家族とゆっくり、何をするでもなしに過ごすヨーロッパの人々のバカンスは、私にとって憧れのシンボルなのです。日常の環境から離れたところに身を置いてのんびり過ごす日々の中で、仕事への新鮮な感謝やら家族のありがたさやら、自然との共存の実感を味わい、放電したり充電したりできることでしょう。
そうなのです。私にとっての贅沢とは、心ゆくまで時間を味わうこと。それはそのまま、音楽の真理愉でもあります。音楽はまさに、時間を音で紡ぐ芸術なのです。
自家栽培の農作物を大切に頂くこと。手作りのお料理をゆっくりと味わうこと。わざわざ一度外から家に帰り、着替え直して、コンサートホールに出かけて生の演奏を楽しむこと。さらに、一緒だった友人とそのコンサートについてとことん語り合うこと…。そんな時間をすごす贅沢を享受し、楽しむのが、どうやら遺伝子レベルで(?)私たちよりも上手なのがヨーロッパの人たちです。
ですから、日本人がぽんとその中に入っていくと、確かに時間がとてもゆっくりに感じられます。何をするにも時間がかかるのです。例えばレジの係の人はお客さまとのおしゃべりが忙しくて手が止まりがちになるし、注文したお料理がなかなかでてこないなんて、ざらです。ホテルのチェックインに一時間もかかったこともありますし(別にトラブルではありません。フロントの方と話し込んだだけです)、お財布一つ買うのに店員さんといろいろな話で盛り上がり(正確には、彼から質問攻めにあい)、二時間もお店にいたあげくに彼のお母さんを紹介されたこともありました。
効率を求めるよりも、時間を楽しむことの贅沢…それが身に付いているから、時間を大切に楽しむことが出来るのでしょう。ファストフードよりスローフード。マシンメイドよりもハンドメイド…。
ところが、ある日本人デザイナーがこんなことを言っていました。「ハンドメイドとマシンメイドは対立するようにも言われますが、大切なのは機械を使いこなす手や心をもちうるか否か。つまり“ハートメイド”であることなのです」なるほど、クールなバランス感覚です。確かに、いくら精緻な手作業を重ねても、そこに心…ハートが感じられないのでは、よいものとはいえません。大切なのは形ではなく、あくまでも中身です。
例えば、忙しいときには、無理して手料理を作らなくても、半分出来合いのクイックメニューですませるも、よし。フルメイクするのが面倒なら、ポイントだけでも、よし。要は、どこかにユーモアとか、笑顔とか…心のゆとりがあればいいのです。例えば冷凍食品をチン、の時「これ、お母さん渾身のハートメイドよ。たくさん“氣”を入れといたからね!」なんて言いながら笑顔で食卓に置けば、それだけでも違う気がします(いつもより美味しく感じるかも!)。メイクが手抜きでも、お気に入りの香水を身に纏うだけで、気分が変わります。
私たちが奏でる音楽は、マシンメイドではなく、一音一音がハンドメイド。何ヶ月ものバカンスを過ごす夢はかないませんが、せめてハートにバカント(ゆとり)を持って毎日を心愉しく過ごし、ハンドメイドをハートメイドに格上げすることを、この夏のひそかな目標にすることにしました。
■第619回 幸福なピアニスト
これまで、本当にたくさんの生徒さんとのご縁をいただいています。
仙台には留学から戻ってから千葉県に移り住むことになるまでの約10年間、自宅や実家での個人レッスンを行っていましたし、始まりの時期はずれますが、母校での非常勤講師のお仕事も、途中からは東京から通いつつやはり10年ほど務めさせていただきました。
千葉に来てから15年以上が経過しているので、長い生徒さんとはかれこれ四半世紀もの間、お付き合いさせて頂いていることになります。これはほとんど、私のピアニストとしてのキャリアと重なる年月。感慨深いものがあります。
生徒さんとの関わりは私の宝物ですが、なかでもひときわ親しくお付き合いさせて頂いているひとりが、Yさんです。出会った当時、彼女は中学生でした。他の先生から「先生を変えた方がいいと思われる生徒さんがいるのだけど、美奈子先生お願いできませんか?」とのお話をいただいて、私がみることになったのです。引き継ぎの時に「あまり積極的に話をする子ではないし、反応が分かりづらいところがあるかもしれません」と伺ったのを覚えています。
確かに、始めはそうでした。でも、あれよという間に、止まらないほどおしゃべりしてくれるようになり、それと同時に音楽表現も闊達に、のびやかになっていきました。そして、希望だった音楽大学への入学を果たしたあとも、ちょこちょこレッスンを受けに顔を出してくれました。大学生活について、大学でのレッスンについてなど、相変わらずたくさん話をしてくれるのが嬉しくて、聞きながらちょっとお母さんになったような気分になりました。
音楽大学を卒業して地元石巻のピアノ教室の講師になってからも、レッスンを受けにきてくれていましたが、ある日…「美奈子先生、私、結婚が決まりました!」と報告をもらいました。「わぁ!それはおめでとう!!」感激する私に彼女は「それで…。結婚式に、美奈子先生にも出席して頂きたいんです」と、さらに嬉しい追い打ち?をかけてくれました。「いいの?嬉しい!喜んで!」
出席させて頂いたのは、結婚式や披露宴だけではありませんでした。彼女の地域には、披露宴終了後に新郎新婦それぞれの親族同士に分かれ、改めて“後宴”をもうけるという風習があって、それにも是非でてください、とお誘いをいただいたのです。
それがまた、それまで経験したことのないような、なんともあたたかい宴でした。披露宴でさんざんごちそうもお酒も頂いたのに、さらなる心づくしのお振る舞い。親族同士での気の置けない雰囲気の中、唯一の“他人”である私にも皆さんが親しく話しかけてくださり、カラオケのデュエットまでさせて頂きました。お母さん気分を味わわせてくれた彼女は、かくも大切な日に私に親族気分まで味わわせてくれたのです。
彼女は東松島で海苔の養殖をしている旦那さまを支えながら、やがて可愛らしい女の子のお母さんになり、その後、すばらしくハンサムな男の子のお母さんにもなりました。東日本大震災がおこったのは、そのわずか数ヶ月後でした。
津波で家も養殖も流されてしまいましたが、家族は全員無事でした。その年の夏に私が帰省した折り、まだ落ち着いていない中、彼女は家族で元気な顔を見せにきてくれました。ご両親や子供たち…すばらしい家族とともに立派に家庭を築いている彼女にはキラキラとした笑顔が満ち、反対に悲壮感はかけらもなく、私の方が励まされた思いでした。また、仙台でのリサイタルの時には、石巻から必ずかけつけてくれました。
昨日、彼女が、お父さま、旦那さま、二人の子供たちをつれ、総勢5人で千葉の自宅に遊びにきてくれました。お母さんぶりはますます板についていたものの、相変わらず優しくてめんこい娘さんのままです。一年半ほど前からピアノを習い始めたというお嬢さんが、ピアノを聴かせてくれました。その上手だったことといったら!
そう。彼女は私に、お母さんのような気分、親族のような気分だけでなく、孫の成長に目を細めるおばあさんのような?気分まで、味わわせてくれたのです!…駅でお見送りして彼らにいつまでも手を振りながら、「私はなんて幸せなピアノ弾きなのかしら!」と、感謝をかみしめました。
■第618回 思い出は心の中に
新しいパソコンがやってきて以来、この数年間のパソコンやソフトの機能のめまぐるしい変化と進化を実感している毎日です。ついていくのに必死…というより、とてもついていっている状態ではないのですが、焦らずゆっくり、と言い聞かせています。
新しいものがきたことだし、この機会に古いものを整理しなくては。…ふと、かつて熱心に新聞や専門雑誌のラジオ欄をチェックしては録りためた、おびただしい数のカセットテープたちのことを思い出しました。小型のタンスのようなごついケースに入ってピアノの下に眠ったままになっているのを、もう処分しよう、と思い始めたのはどのくらい前だったかしら…。何度も繰り返し聞いてはピアニストになる日を夢見ていた頃の思い出がたくさん詰まったカセットテープをすっかり手放してしまうのも寂しくて、捨てよう、と決心しても結局は躊躇してしまうのでした。
でも、やっと捨てる決心がつきそうです。なんのことはない、インターネットのYouTubeというサイトがきっかけでした。
こちらは皆さんご存知のとおり、世界のありとあらゆる(と、いってもいいほどの)演奏などの投稿を無料で見聞きすることができるサイトで、せんえつながら私の動画もアップされています。このサイトで検索をかけると、私が大切にしていたアーカイブ的なライブ録音も、うまくすると映像付きで(中には動画なしの静止画だけのものもあります)、いつでも好きなだけ再生することができるのです。それどころか、数十年も前の外国のローカルテレビ番組の映像までどんどん出てきます。
あれこれ検索していたら、大きな刺激を受けプロのピアニストを目指すことをはっきり決意するに至った1975年のショパン国際ピアノコンクールのドキュメントや、その時の優勝者、憧れのクリスティアン・ツィメルマンの地元ポーランドでのトーク番組出演の時の映像も出てきました。
20歳になったツィメルマンは、少年のように可憐な風貌だった二年前のコンクールの時よりもずっと大人びて、すでに一流のピアニストとしての風格のようなものすら感じられました。
「ある曲を僕が気に入る。すると、それを勉強したくなる。そして誰かに伝えたくなる。…ステージに上がった時、その曲を世界でもっとも美しい曲だと信じ、聴衆にも信じてもらいたい…そう思うわけです」まさに、私も常日頃思っていることでした。彼はこうも話していました。「僕は、やる気がすることしかしてこなかったんです。こんなこと言って良いのかわからないけど(ここでキャスターが「もう、言っているわよ」と突っ込みを入れます)、スケールとか、そういうものを練習するのは嫌で…。でも、僕は楽しいと感じることを続けます。これが自分の仕事のレベルを保つ鍵です」こんな録画・録音をいつでも家で見ることができるすごい時代になったことを、映像を見ながら改めて実感しました。
ツィメルマンが初来日したときは父の仕事の関係で名古屋に住んでいたので、名古屋公演をひとりで聴きに行きました。毎日その演奏をカセットテープで聴いては憧れてやまなかったピアニストの生の演奏に触れた感激は、とても言い表すことのできるものではありませんでした。しかも、図々しくもリサイタル終了後楽屋にいって、しっかりサインまでもらうことが出来たのです。
その日は、ぽ〜っと夢見心地で家に帰ったのを覚えています。最寄りの地下鉄の駅からさらにバスに乗り換えて家に向かう途中、その駅のバス停で会社帰りの父と偶然居合わせました。「パパ!あのね、今ツィメルマンのリサイタルに行ってきたの。サインまでもらっちゃった!」興奮して話す私に父はにこりともしないで、一言「お前はサインをもらいにリサイタルに行ったのか?ちゃんと聴いてきたのか?」…ビシッとたしなめられ、高揚していた気分は一気に冷めてしまいましたが、厳格な父らしいもっともなコメントでした。
たとえカセットテープを捨ててしまっても、こうしてYouTubeでさまざまな映像をみることもできるし、心に残り続ける愛おしい思い出が私にもたくさんあることに気づきました。大切な思い出はモノに宿るのではなく、心の中にあるのです。
■第617回 心のメンテナンス
最近、意を決してパソコンを買いかえました。りんごの会社のものへの乗り換えです。
今まで使っていたものの型番を調べてみたら、2005年4月のモデルだそうです。もう10年ぐらい使っているつもりになっていましたが、まだそこまでではありませんでした。とはいうものの、既に8年が経過しての9年目…。堅牢につくってある13キロものマシンを処分するとなるとかなりの勇気がいりますが、ここしばらく動作が不安定になっていましたし、仕方なく決心しました。
そこへいくと、楽器は長持ちして心強い限りです。弦楽器ほどではなくても、きちんとメンテナンスを行っていればピアノもかなり長いこと使えます。ピアノも、そして家も、自分でメンテナンスができれば一番いいのだろうけど…という話をある人にしたら「いやぁ、専門家に任せるほうが確実だよ。家のメンテ?美奈子ちゃん、それならカレシを作ったほうが早いって!」と、一笑に付されてしまいました。確かに私、不器用だからなぁ。
体のメンテナンス…つまり、健康診断にもすこぶる消極的な病院嫌いの私ではありますが、我ながらマメに行っているメンテナンスがあります。それは、心のメンテナンスです。
まず、無理をしないこと。そして、疲れやストレスを貯めないこと。この二つを守るために心がけていることは、楽しい時間を持つことと、よい心持ちで過ごすためのちょっとした贅沢、です。
贅沢といっても、本当にささやかなことなのです。朝一番に大好きな音楽を聴くとか、お気に入りのフィンランド製マグカップでたっぷりのコーヒーを頂くとか。そうそう、最近は夜と朝で違う香りのボディーソープを使いわけることを楽しんでいます。夜、ゆっくりお風呂に入るときにはリラックス効果の高いラベンダーなどハーブの香りするものを使い、朝のシャワーの時には気分がすっきりとするような、スパイシーな香りを使います。
最近のヒットは、ヨーロッパなどの高級ホテルのアメニティーによく使われているロンドンのモルトンブラウンというブランドの製品で、大好きなピンクペッパーがテーマのもの。なんでも、説明書きによると“エデンの園にのみ生息していたといわれ、楽園の実と呼ばれているブラジル産ピンクペッパーポッドを主成分に、アフリカンジンジャー、カルダモンなどのエッセンシャルオイルがブレンドされ、エキゾチックで官能的なアロマ を放つ”のだとか…。
同じブランドで違う香りのハンドウォッシュとハンドミルクも愛用中。日本にはないヨーロッパの空気を感じさせる香りに、手を洗うたびフワッとかの地に降り立つような気分に浸っています。お値段は少々お高いですがパッケージデザインも洗練されていて、見るたび使うたびに味わえる贅沢な気分や、心の健康維持を考えると安いものです。
ネットでも買えるのですが、これまた私のプチ贅沢のひとつはあえてお店で買うこと。いいお店のレイアウトや設計にはかなりしっかりしたデザイナーが関わっていてインテリアひとつとっても目の保養になりますし、なにより製品についての専門的で幅広い知識をもった接客のプロ…店員さんとのおしゃべりは、とても楽しいものです。なるべく時間に余裕を持って、平日の混み合わない時間帯にでかけるようにしています。
この、ピンクペッパーポッドのプロダクツに出会ったときも、店員さんと話し込んでしまいました。「ピンクペッパーっていう発想がまたステキですね。あ、ピンクペッパーって“ペッパー”属ではないのですってね」「そうなんです、植物的には黒胡椒、白胡椒などの胡椒の類とはまったくちがう実なんです。よくご存知ですね!ちなみにうちの製品に使われているのはブラジル産のピンクペッパーで…」ブラジル産とペルー産の違いについてや、気候と風土が植物にあたえる影響についてなど話は尽きず、お買い物というよりちょっとした講義をうけているような感じでした。
自家製の野菜やジャムを頂くこと。庭やベランダから摘んできた花を飾ること。…日常には、ちょっとした贅沢として楽しめることがたくさん溢れていることに気づくと、生きていることに感謝したい気持ちでいっぱいになります。
心のメンテナンスは、今日もばっちりです!
■第616回 一人芝居のようなもの
先日、初めてミュージカルの舞台『レ・ミゼラブル』を観に行きました。オーディションに合格した実力派の役者さんによる、言わずと知れたミュージカルの金字塔的名作。これはもう、感動しないわけがありません。原作は読んでいましたが、最近の映画もDVDも観ていなかったことを幸運に思いつつ(先入観がほしくなかったので)、期待に胸をふくらませて帝国劇場に向かいました。
役者さんの渾身の演技、歌。ピットに入っているオーケストラの奏でる壮大な音楽に、ドラマティックに変化する舞台。衣装も演出も素晴らしく、ぐんぐん引き込まれていきました。
確かに、素晴らしいのです。役者さんの歌はそれぞれとても表現力豊かですし、コーラスも完璧!ここまでになるために、いったいどれほどの練習やお稽古を積み重ねてきたことでしょう!!ジャンルは違うものの同じ舞台人として、頭が下がる思いでした。でも…。始まってまもなく、どこかに違和感をおぼえ、すこし後ずさりして戸惑っている自分に気づきました。原因はいくつかあるようでした。
まず、すべての台詞を節にのせて話す(うたう)のに、ストーリー展開がはやすぎるのです。うたうのは、話す以上に時間がかかるものですし、言葉も限られます。これが歌舞伎なら、役者さんは時として台詞から離れて踊りに入り、代わりに長唄が小粋に心境をうたうことで、じっくりその場面や登場人物の気持ちを味わうことが出来たりするのですが、トントンとテンポ良く話しが進みすぎて、ゆっくり味わう間がないのです。
また、今しがたまでしっとりと聞き入っていた悲しいアリアの余韻にもっと浸っていたいのに、場面がすぐに変化してあっという間に次の事件が起きる。心理描写よりも、小気味いいストーリー進行や構成が優先されてしまうのは、お芝居の性質上ある程度仕方のないことなのですが、私のようなスローペースな人間は「ちょっと…もうちょっとだけ、待って」と、いいたくなってしまうのです。
それから、これもまた、しかたのないことなのですが、最後まで慣れなかったのは音響でした。マイクで拾われ、拡音されたスピーカーからの音や声を聴いていると、どうしても耳が疲れてしまうのです。言うまでもありませんが、クラシックはどんなに大きな会場でのコンサートでも、基本的に生音。だからこそ、歌い手や弾き手の、響きに対する意識や作品の微妙なニュアンスが感じてとれ、それが何より楽しみなのです。それが、ゴージャスに“水増し”された大音響に圧倒され続けなければならないのは、生音に慣れている私の耳には、いささか過酷でした。
良くなかった、楽しめなかった、というのでは、決してないのです。心から、堪能したのです。要は、私があまりにも“不慣れ”だったということなのです。きっと、初めてきちんとしたレストランでフレンチのフルコースを頂くとき、マナーやお店の雰囲気に圧倒されて、せっかくのお料理の味がよくわからなかった、などというエピソードをよく聞きますが、それに近い感じかもしれません。
帰り道、つくづく自分は、“粗食”的な簡素な音の響きが好きなんだ、と思いました。フォアグラもキャビアもいいけれど、私にとってピアノをはじめとするクラシック音楽の生音は、毎日のように口に運ぶごはんやパン、お味噌汁やお漬物のように、心からホッとできて、欠かすことのできないもののようです。
ふと、良い舞台、良いパフォーマーとはなんだろう、と、考えました。もちろん、作品や脚本、演出や構成は大切ですが、役者さんはいくら歌が上手でもお芝居に魅力がなければ、お客さまを楽しませるには不充分です。さらにそこに、舞台人としての“華”…人を惹きつける、存在感のようなものも、求められます。トータルなバランスが、思いのほか大切なのかもしれません。
考えてみたら、私のしているリサイタルは、作曲家が書いてくださった作品、脚本を自ら演出、構成して主演する、一人芝居のようなものです。もっともっとお客さまに楽しんでいただくために、まだまだ出来ることや見直さなければいけないことがあるような気が、してきました。
よい刺激をうけ、次回のリサイタルの構想が固まってきました。ミュージカルに誘ってくれた友人に、感謝です。
■第615回 目指すはDIY女?
ピアニストのひとり言 第615回 目指すはDIY女?
今の住居に引っ越してきて、12年以上の年月が経っています。この連載よりは短い歴史ですが、それでもあちこち不具合(?)が気になるようになってきました。壊れることがあるなんて思ってもいなかったリモコンで調光できるタイプの照明器具がつかなくなったり、テレビが突然ブラックアウトしたり…。プリンターはいくらクリーニングをしてもムラが解消されず、排紙トレイを開けていても「排紙トレイを開けてください」というメッセージが消えずに印刷されなくなってしまうし、これを書いている相手…パソコンも、反応が日に日に怪しくなっています。
調光できるタイプの照明器具は、最近主流になってきている省エネタイプのLED電球が一切使えません。もともと蛍光灯が好きではないので、キッチンにある埋め込みタイプの照明以外はすべてが白熱灯使用の照明です。そのせいもあって、節電を心がけてはみても電気代がなかなか下げられずにいましたので、これを機会に、順次各部屋の照明の買い替えをはかるのもいいかもしれません。
そして、テレビ。デジタル対応の液晶テレビにすれば電気代も安くなるし、なによりケーブルテレビの契約を解約できるのは大きいことです(もともと、あまりテレビは見ないのです)。
そこで、さっそく家電量販店に行ってみました。でも、気がついてみたらテレビ自体よりも、テレビ台…ラックばかりをチェックしているのです。「う~ん、こういうのはピンとこないなぁ。うちのリビングに置くとしたら、もっと、こう…」気がついたら、家電量販店は早々に退散し、家具屋さんのラック売り場をうろうろしていたのでした。「実は、テレビ買う気、ないでしょ?」自分に突っ込みをいれてしまいました。
よく「液晶テレビなんて安いんだから、さっさと買い換えちゃえば?」と言われるのですが、もともと貧乏性なのでその寿命が全うされないうちに廃棄するのは、どうも気が引けてしまうのです。品番から調べてみたところ、1999年製ということが判明しました。もちろんブラウン管です。なんでも、『「FDトリニトロン」搭載のフラット画面により、画面全域で歪みのない均一な画像表示が可能に。さらに、通常のテレビ、ビデオ、DVD映像を、独自のデジタル信号処理アルゴリズムにより4倍の情報量をもつHDに近い高画質映像につくり換え、テレビが自動でアップサンプリング処理を行うことで、画質をブルーレイ画質に引き上げる』…という、当時としては画期的な機能がついているモデルなのだそうです(正直いうと、説明を読んでもよく理解できないのですが…)。
世界のテクノロジー最前線で頑張っていた(もちろん頑張っているのは現在も同じだと思うのですが、当時の経済的バックグラウンドを背景に今よりもさらに、という意味で)ソニーという会社の意気込みが感じられます。技術開発者が、生産コストや使いやすさ、耐久性やデザイン、価格設定などをあれこれと胃が痛くなるほど考え、努力してつくり上げたものなのだと思うと、やはりすっかり電源が入らなくなるまでは使い続けよう、と思ってしまいます。
買い替えが切実なのは、パソコンとプリンターです。プリンターはすでに限界だし、パソコンばかりはある日突然電源が入らなくなってしまっては、とても困ります。得意な分野ではないのですが検討しないわけにもいかず、詳しい方に相談したり、自分なりにリサーチしてみたりするのですが、やはりこちらも機能よりも(テレビと同様、説明を読んでも理解できないことが多く…)サイズ感やデザインを重視してしまいます。そして、本屋さんに立ち寄ってはそちらの分野ではなく、インテリアの本を手にとって「この際、リビングの一角をこの写真みたいにプチ・ソーホー(*SOHO Small Office/Home Office(スモールオフィス・ホームオフィスの略)化しちゃおうかしら。でもそうすると、お客さまを呼んでのホームパーティーのときに、テーブル周りが狭くなっちゃうよね。あ、いっそのこと、隣の和室を洋室にしてリビングを拡大するっていうのもいいかも!」と、いつのまにか妄想にふけっているのです。
そんなある日、ポストにマンションの管理会社からのリフォーム提案のパンフレットが入っていました。なんとタイムリーな…!でも、お金をたくさんかけて業者にお願いするのでは芸がありません。それに、自分でできるようになれば、気が変わったときや壊れたときのメンテナンスも、思いのまま!これからも続くであろう“御一人さま”人生に向けて、きちんとDIYの技術を学ぼうかしら。それは私にとっては、語学を学ぶよりずっと必要なことかも…。
ところで、最近では歴史好きな女性を歴女、クラシック音楽好きの女性をクラ女というのだそうです。となると、DIYできる女性はDIY女?それを目指して、近々また本屋さんでその関係の本を物色するんだろうなぁ、私…。
■第614回 ステージの妖精
先週の日曜日、生徒さんの発表会がありました。3歳から81歳までの私の大切な生徒さんの、年に一度の晴れ舞台です。
私の発表会は、いつも次のように進行します。まず、代表の生徒さん(小さな子のことが多い)に、開会のあいさつを舞台上で言ってもらいます。陰マイクのアナウンスは大人の生徒さんや、ご両親。あらかじめおひとりおひとりに演奏する曲についてや、今回のステージにかける思いなどについてのコメントを書いてもらい、それを演奏前にアナウンスの方に読んでいただいて、演奏者の登場、演奏…という流れです。
この日はもっぱら、ステージマネージャーとして裏方に徹します。例えば、演奏者の譜面台や小さな子の足台の準備や、椅子の高さの調整などの舞台セッティング、生徒さんのステージへの送り出し…などといったことを担当するのです。いつもはステージに送り出される方の身なのですが、この日ばかりは逆の立場になるわけです。
ステージ袖から本番用スポットライトに照らされているステージにでていく瞬間の生徒さんたちは、ゾクッとするほどきれいでした。緊張感が美しさに昇華する瞬間、そしてその先に紡ぎだされる渾身の音色…。生徒の皆さんの姿を見て、またその演奏を聴いて、改めてステージってなんて素敵なところなのだろう、と、心がふるえました。
よく「○○さんは90歳を越えているのに舞台を続けていて、すごいパワーね」という声を聞きますが、○○さんはパワーがあるから舞台に立てているのではなく、むしろ舞台を続けているからこそ、パワーを得ているのだという気がしています。
確かにステージには、魔物もいるかもしれません。でも、その魔物は、緊張という武器をふりかざして襲いかかり、そこに立つ人をおとしいれようとしているのでは、ないと思うのです。真剣勝負を全うしたあかつきにはきっといい友人となり、様々なことを教えさとして、成長させてくれる。つまり、パワーを与えてくれるのです。彼(彼女?)は、実は心持ちのいい信頼できる人(?)で、しばらく会わないでいるとまた会いたくなる、不思議な魅力を持っているのです。
演奏してくれた生徒さんはみんな、輝いていました。みなさんも、魔物との真剣勝負をとおして、素晴らしい何かを感じ取ってくれたのだと思います。
「発表会、どうだった?」小さな生徒さんにたずねると、上手に弾けた子もちょっぴり間違えてしまった子も皆、目をきらきらさせて「楽しかったー!」と答えてくれます。ある大人の生徒さんは「発表会へ向けての一日一日が、とても大切で良い日々でした。本番での出来は、自分の中では100点(努力賞!)と、思っています。自分なりの精一杯のおしゃれをしてステージでグランドピアノを弾く、という、子どもの頃からの夢がかないました。ありがとうございました。」と、ご丁寧なお礼状を下さいました。
小さなHちゃんのお母さまは「とても素晴らしい一日でした。他の子どもたちの成長にも、感激しました!大人の方々の演奏には、もう胸を打たれてしまって…。自分は弾いてもいないのに、音楽っていいなぁって、もう、涙がでそうになってしまいました。おひとりおひとりの人生が、音から聞こえてくるようでしたよね」と、嬉しいコメントを伝えてくださいましたし、また、中学生のAさんのお母さまは「家で弾いているのを聞いて、こんな調子で大丈夫なのかしらと心配していたんですけど、発表会の前日のレッスン(そのお母さまは、その時同伴していらっしゃいました)で美奈子先生に魔法をかけていただいたおかげで、あんなに上手に弾けて…」と、喜んでくださいました。
皆さんの反応を頂きながら、私はステージにいる魔物を、これからは魔物と呼ぶのはやめよう、と思い始めました。単なるコトバの問題ですが、やはり「魔」がつくと、どうしてもどこか得体がしれず不気味なイメージになってしまいますもの。ステージで待っているのは魔物ではなく“妖精”ということにしました。
それにしても、こんなにステキな輝きとパワーを与えてくれるなんて、やっぱり音楽は百薬の長!まだステージを経験されてない方は、身心の健康維持のためにもピアノのレッスンを始めてみませんか?(笑)
■第613回 晴れるもよし、雨もまたよし
関東地方は6月になる前に梅雨入りしました。
雨が降るのはとても良いことですし、生き物にとっても地球にとっても大切なことには間違いないので、あまり雨をきらわないことにしています。旅行中もしかり。突然の雨がきっかけになって、思いがけないロマンスがうまれないとも限らないですし…。
なぁんて冗談はさておき、嵐や竜巻ならいざしらず、多少の雨降りを「あいにくのお天気」「残念なお天気」と、マイナスにばかり表現するのは、あまり好きではありません。雨があがった後のすがすがしい空気のにおいや、ほこりを落として瑞々しい本来の色彩をとりもどした木々の姿はなかなか良いものですし、雨上がりの小鳥たちのおしゃべりにはなかなか楽しい響きがあったりします。
五月雨、穀雨、など、日本には雨にまつわる美しい言葉がたくさんありますが、なかでも好きなのは、青葉に降りそそぐ「翠雨(すいう)」、音もなく降る細かな雨「米糠雨(こぬかあめ)」。ひとつの単語でしかないのに、まるで映像のようにその風景が目の前にひろがる言葉で、晴耕雨読、雨降って地固まる、などの句とはまた違ったファンタジーを感じます。
とはいえ、湿度の高い日が続くと、気になってくることもあります。まずは湿気をきらうピアノのコンディション。私の愛器はウィーン生まれのウィーン育ちなので、日本の多湿な気候にはなかなか馴染んでくれませんが、こればかりは仕方ありません。除湿剤やカビをやっつける洗剤などのコマーシャルも、多くなってきます。
ハウスキーピング全般にあまり神経質な方ではないのですが、唯一気にしていることは“風通し”。家に風をとおすこと、部屋の空気をこまめに入れ換えて、淀まないようにすることです。
それを、スピリチュアルな世界に詳しい知人に話したところ、「美奈子ちゃん、それはすごく大切なことよ!」と、褒められました。なんでも、風水の原理もそこにあるそうで、風通しに気をつけて家を清潔に保ち、余計なものをきちんと整理することは、そこに住む人の心と身体の健康に深く関係して大きな影響を及ぼすのだとか。「家に空気をとおして、いらないもの、よからぬものを溜め込まずに一定のスペースを確保しておくようにすると、そこに自分に必要な、“よい”ものが入ってくるの。逆に、空気やいらないものが家によどんでしまうと悪しきものがはびこって、よいものが入ってくることができないの」
う~む、なるほど。それがよからぬ方向へエスカレートしすぎると「財産はすべてお布施にしてしまいなさい」というお告げに従ってしまうのでしょう。幸か不幸か私には差し出す財産がないので、そこまで及びようがないのですが。
でも、確かに理にかなっている部分は感じられます。不要なものに囲まれて狭いスペースであくせくするよりも、本当に必要なものだけをきちんと管理して、それらを大切にしつつすっきりのびのび暮らしていけたほうが、快適に決まっていますもの。
先日、あるカフェで友人に偶然再会しました。月に一度ほどしか行かないカフェでしたので、お互いに驚きましたが、彼女は「今日はなんだか会うような気がしていたの」と言ってさらに私を驚かせました。「そうそう、今度の日曜日、またフリーマーケットをやるの。前回もすべてを売り切ったのよ。収益以上に、お客さまとのやりとりや自分の家が片付くのがおもしろくて…」
フリーマーケット!それだ!「私も、出してみたいな」「そう?何だったらお預かりするわよ。ダンボールに入れておいてくれたら、車で回収にうかがうけど…?」話はとんとんと進み、彼女はつい先ほど、真っ赤なドイツ製の愛車で荷物を取りにきてくれました。「当日の天気は雨の予想だけど、晴れ請いするから大丈夫。きっと売り切ってくるわ!」颯爽と去っていく彼女は、確かにすっきりのびのびして見えました。
さて。初めてのフリーマーケット出品の成果は、如何に…!?
■第612回 青春はショパンとともに
このところショパンの楽譜をひっぱりだしてきて、あれこれ弾いています。弾きながらふと、小学生の頃に「ああ、ショパンの曲をなんでも弾きたいだけ弾けるようになったらどんなにステキだろう!」と、夢みていたことを思い出しました。
あの頃―――小学生から中学生にかけて―――は、明けてもくれてもショパンだったなぁ…。ショパンを弾くほどに、こっぱずかしい思春期の記憶があれこれ蘇ってきました。
中学生の頃にはやっていたスチール?製の“缶ペン”とよばれた筆入れの裏面に、当時ショパンコンクールで弱冠18歳での優勝を果たした憧れのピアニスト(*クリスティアン・ツィメルマン)の名前を書いて、たまにひっくり返してそれをながめては人知れず胸をときめかしていたこと。アンネの日記をまねて、自分の日記の出だしにショパンのファーストネームを借りて“フレデリックへ”と書き出していたこと。一週間分がまとめて記載される新聞のラジオ欄を、蛍光ペンを片手に隅々まで見てショパンが流れる番組はすべてチェックし、できる限り録音していたこと。
―――こうなると、想い出は堰を切ったようにどんどん蘇ってきます。
ショパンの伝記が買いたくて、図書券欲しさに音楽雑誌『音楽の友』の読者投稿欄に応募したこと(3回投稿しましたが、結果的に3回とも採用でした)。やっと手に入れた伝記をなんどもなんども繰り返し読んでは、彼が若くして結核に倒れる場面で毎回飽きもせず涙していたこと。当時のNHKの番組“名曲アルバム”で彼の祖国ポーランドの映像が流れようものなら、まばたきもみじろぎもせず見入っていたこと。ノートの裏にショパンやその憧れのピアニストの似顔絵を書いてはときめいていたこと。どうしても手に入れることのできないショパンのマイナーな作品の音源をもとめ、NHKにリクエストしたこと。その葉書きを読んでもらえて、リクエストに答えていただけたこと。
そんな少女でしたから、初めてショパンの曲を先生から頂いた時の喜びは、とてつもなく大きなものでした。忘れもしない、作品42の“グランドワルツ”!ワルツの中ではかなり技巧的で、規模も大きな作品でした。レッスンの帰り道、はやくその楽譜を見たくて、顔が緩むのも気にせず小走りで帰りました。
それまでも先生には内緒で、ひそかに幻想即興曲やら雨だれのプレリュード、などは弾いていたのですが、きちんとレッスンで見ていただけるなんて!…考えただけでも、今でいうところの“鳥肌”がたちそうでした。
もちろん、青春にはほろ苦さがつきもの。甘美な思い出ばかりではありません。高校時代は大学入試やコンクールの課題曲になっているショパンのエチュードに四苦八苦させられましたし、晴れて憧れの桐朋学園音楽学部に入学できてからもショパンにはバッハ以上、ベートーヴェン以上に悩まされました。今思い返すと、好きすぎて思い入れが強かったので、挫折や行き止まり感もその分大きかったのだと思います。
一番ショッキングだったのは、前出のツィメルマンが師事していた先生の公開レッスンで、先生にいわれたひと言でした。「よく弾いているけどあなたのは自己流のショパン。わたしたちの伝統的な解釈とは違っています」そのあと、しばらくショパンがよくわからなくなりました。その先生の演奏や、“伝統的”“正統的”と評価されているポーランドの大御所ピアニスト(注:パデレフスキーは入っていません)の演奏を片っ端から聴いてみました。でも、自分がどういけないのか、どうしたらよくなるのか、なかなかみえてはきませんでした。
そんな私に光を与えてくれたのは、アルフレッド・コルトー、サンソン・フランソワといったフランスの巨匠たちでした。アプローチはポーランドの先生方とは大きく異なりますが、心を大きく揺さぶられる表情の豊かさ、独自の解釈や表現に惹きこまれ、たちまち魅せられました。フランソワの自由奔放な演奏は時に“オレ流”と評されますが、そのチャーミングなことといったら!そしてコルトーはピアニストとしてだけでなく、ショパンの楽譜の校訂や、パリにコンセルヴァトワールを設立して後進の指導にも力を注いだ方で、高校時代に出会ってから今に至るまで大きな影響を受け続けています。
思春期や青春の節目にいつもそばにいた、ショパン。今の自分は、どんなふうに彼の音楽と向き合えるかしら。…久しぶりにじっくりと勉強してみたくなりました。
■第611回 憧れのトスカーナ
外国人による作曲家の評伝などを読むと、日本人の著者とはまた違った観点や切り口をもつものが多く、とても新鮮に感じることがあります。
もちろん、日本のものにも様々なものがありますし、外国人、といってもヨーロッパの人なのかアメリカの人なのか、さらにユダヤ系の方なのかによってもおおきく異なりますし、安易にひとくくりにできるものではありません。でも、ごく大雑把な傾向を述べるなら、日本の人は作曲家をとても敬い、尊厳を保って、間違っても失礼(?)や誤解のないように細心の注意が払われている印象があるのに対して、外国の方は言いたいことははっきりと主張しますし、場合によっては、不名誉なこともばっさりと言い切っています。
それはあたかも、“可もなく不可もなく”や、“毒にも薬にもならない”提言や発表をしても、ちっとも面白くないだろう、といわんばかり(*日本のものが可もなく不可もなく…だということではありません)。「私の意見や考えをあなたがどう受け止めるかは、自由です。議論は大いに結構!アンチテーゼも大歓迎!」そんな、挑戦的・挑発的な姿勢が垣間見えるときもあって、なかなか刺激的です。
音楽に関する専門書に限らず、時に旅行ガイドですら外国のものはちょっぴりシニカルで、苦笑を誘うことがあります。日本ならガイドブックと提携していたり、スポンサーになっている企業やお店との利権やらしがらみがあるので、よほどのことがない限り名指しで先方を批判することはありません。でも、そういった支援を一切受けずに発刊されているガイドブックは歯に衣着せぬ正直な記事が書けるようで、容赦ないのです。
日本で手に入る外国の旅行ガイドブックは少ないのですが、手軽なところでよく参考にするのはロンリープラネットというシリーズです。国によっては日本語版もでています。旅行ガイドだというのに辞書よりも厚く、巻頭カラーの数ページを除いて写真はなし。でも、その記事内容のマニアックともいえる詳しさは、他とは比べものになりません。
街のトピック、コラムも充実していますが、なにより興味深いのはその文章です。例えば、イタリアのトスカーナで人気のキャンティ地区について「確かに有名だが、ここばかりが騒がれすぎという気もしないではない。トスカーナに
は他にもたくさんの素晴らしい田園地帯がある。あまり気を悪くしないでほしいが、トスカーナの田園地帯は決してキャンティだけではないということだ」泣く子も黙る世界遺産のサン・ジミニャーノも「東の丘から頂上まで上っていくと、この城壁の14の塔は中世のマンハッタンのように見える」「(ここには旅行者が殺到するため)冬か早春に来れば多少物思いにふけることができるが、夏だと観光客をよけるのに苦労するだろう。『美しい塔の街』のうたい文句に反して、デザインに乏しく単調で、ただ天突く高さに圧倒されるだけ」…。
かと思うと、まず日本のツアーには登場しない小さな村であっても「1~2日をのんびり過ごすのに最高の場所」と賞賛していたり、地元の人も知らないようなイベントやお祭のこと細かな紹介があって、読み物としても楽しめるようになっています。街の歴史やなりたちについての記述、宿の情報(「この宿のバスタブはフィアットの車がはいるほど大きい」など、ユーモアたっぷり)、詳しい交通案内からバーのトイレの情報(例えば「このバーでは、ペルージャで一番しゃれたトイレもチェックしておこう」など)に至るまで、かなりディープなレベルです。
今はリアルタイムで、世界中のどこでもネットを通じて航空写真を見ることができます。街の美しい写真も、検索すればいくらでも出てきます。以前は、「なるほど、このあたりはみんなレンガ色の屋根なんだ。あら?地図とは違って、実際にはこんなふうに南西方向にカーブしているのね。じゃ、このわき道を進んだほうが近いかも…」など、旅に出る前に調査したこともあったのですが、あらかじめビジュアルで確認してしまうと、その分感激が減ってしまう気がします。
その点、ロンリープラネットのような旅行ガイドは、記述に著者の主観が入っているのがはっきり分かっているので、それはそれとして参考にしつつも、いろいろと想像を膨らませて遊ぶことができるところが、気に入っています。
その地を訪れるのがさらに楽しみになるようなこのガイドブックのように、その曲を聴くのが楽しみになるようなガイドトークができるようになりたいものだ、と願いつつ、秋に予定しているトスカーナへの旅に想いをはせているこの頃です。
■第610回 母の日に寄せて
関東地方は初夏を思わせる陽気が続いています。この暑さをまえに、二週間前のリサイタルで頂いたお花たちもだんだん力つきてきました。一枚一枚、はらはらと花びらをおとすカサブランカやアルストルメリア。首をもたげ、花びらが茶色に枯れてくるバラ。花ばかりではなく、葉もまたかつての青々とした生命の力強さをうしなって、色褪せ、静かに余生を送っている風情になってきます。
以前は、そんな植物たちの命の終焉を目の当たりにすると悲しくなって、また、くださった方のお心遣いに少しでも長く感謝したい気持ちもあって、ドライフラワーにしたりもしました。でも、あるときふと花は永遠ではないところにこそ美しさ、尊さがあるように思われて、以来、からからに乾いてまで部屋を飾る使命を果たしているドライフラワーの姿が花のミイラのように痛々しく見えてしまい、自分でつくることはしなくなりました。
私たちは時として“永遠のもの”に憧れを抱きます。永遠の若さ、永遠の美しさ、永遠の愛、永遠の幸福…。でも、永遠の命なんてありません。命は永遠ではないから、命なのです。人の身体も雄大な自然も、生きているものは永遠ではありません。だからこそ、私たちは命の美しさに触れたとき、無意識に心惹かれるのかもしれません。
生演奏も、まるで命のように、その場限りのはかないものです。でも、そんな“生身”のものだからこそ、繰り返し聴けるCDなどとはまったく違う魅力があるのだし、まさにライブ(=生きている)ならではの強い印象がうまれるのだと思います。
歳を重ねても生き生きと輝いている人生の先輩を、何人も知っています。みなさんに共通しているのは、前向きな姿勢や、若い人のように(若い人以上に?)さまざまなことへの興味、ものごとに感動をする心をもっていらっしゃること。そして、運命の不遇や身体の不具合について、いたずらに愚痴らないことです。たとえ「この歳になってまいりますと、ね…」なんて前置きをされても、そのあとのコメントはおちゃめで、どこか楽しげだったりします。
老い、とか高齢者、という言葉はありますが、自分も歳を重ねるにつけ、それは数字のことではないな、とつくづく思います。しょせん年齢なんて、暗号のようなもの。老いを憂うよりも、身体の不完全さを受け入れ、その不完全さすら楽しんでしまうほうが、身心の健康にいいことは間違いありません。
もしも永遠の若さや美しさがあるとしたら、それは外見ではなく内面にあるのだと思います。外見的な若さや健康状態のコンディションは歳とともに衰えるのが自然ですが、精神は努力次第で無限に成長できるのではないでしょうか。つまるところ本当の若さ、美しさは心もちの強さ、健やかさ、潔さにあると思いますし、もし永遠の愛があるとしたら、それはだれか相手との関わりの中にあるのではなく、実は自分の心に育て続けるものの中にあるのだと思います。
ベートーヴェンやバッハが持ち続けた音楽芸術への情熱が生涯変わらなく永遠に近いものだったのも、彼らがそれに対する情熱を自らの中に育て続けたからではないでしょうか。
新約聖書のなかに、好きなフレーズがあります。有名なコリント人の手紙です。「愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、いらだたない、恨みをいだかない。不義を喜ばないで真理を尊ぶ」しばしば結婚式で牧師さんに読み上げられる聞きなれた言葉ですが、ハンガリー留学時代に恋の悩みを相談したクリスチャンの友人からこれが書かれた手紙をもらって知り、その手紙をお守りのように大切にして折に触れて読んでいました。
私たちはつい、目に見えるものや確約された言葉に安定を求め、それに安心してしまいがちです。でも、すべての尊いものは目に見えないところにあるのだ、と改めて思います。
「もう、誕生日やクリスマスのプレゼントはいらないからね。でも、お花は好きだから母の日にはお花を贈ってくれたら嬉しいわ」数年前に母から言われました。もうすぐその、母の日です。
それは、命を大切に思う気持ちや自分を育ててくれた感謝の気持ちを、永遠ではない命をもつ花に託してお母さんに伝える日。母になったことも、もちろん母の日の花を贈られたこともない私ですが、大好きな年中行事のひとつです。
■第609回 得がたきものを得るために
今年の自主リサイタル“クララ・シューマンへのオマージュ”仙台と東京の二公演が、無事終わりました。両会場ともたくさんのお客さまに恵まれて、微力ながら震災復興支援としてお役にもたつことができ、ほっとしています。
「リサイタルとコンサートの違いは、何ですか?」以前、尋ねられたことがありました。それにはカプチーノとカフェラテの違いのように諸説あるようですが、出演者が1名、もしくはごく少人数の演奏会の場合にはリサイタル。グループや楽団など大人数の場合にコンサート、と使い分けるのが一般的なようです。
これまで数え切れないほどのコンサートやリサイタルを重ねてきましたが、一人ですべてを完結させる“リサイタル”ほど、大きな試練と学びが得られるものはないような気がしています。コンセプトやテーマをどうするか。プログラムの選曲や構成、全体の流れやバランス、さらに私の場合はところどころで入れるトークの内容と分量の検討。主旨にふさわしいフライヤー(チラシ)の作成とその配布など広報活動とDMの送付など集客のためのあれこれ、そして、いくらしても足りない自分の練習や、最初から最後までたったひとりぼっちのステージ。…身を削るような日々ではありますが、それらを積み重ねてこそ得られるなにやら“得がたいもの”があって、惹きつけられるのです。
終わった後に感じる一番大きなものは、これまで関わってくださったすべての方々や、大好きな音楽を続けさせてくれた両親への、感謝です。お忙しい中いらしてくださり、お気持ちをお寄せくださった方々に、感謝の気持ちを込めてお礼状を手書きでしたためていると、改めて“メール”と“手紙”の違いを感じたりします。
先日、そうやってお礼状書きをしていたら、リサイタルに来てくれた友人から“手紙”が届きました。もちろん手書きの文章で、文面のイラストも手描き。封筒すら手作りのもので、切手もそのデザインとセンスよくコーディネートされていました。彼女の思いやりと微笑みが封を開ける前から感じられ、感激のあまり、開封するときに誤って便箋を一部、破いてしまいました。
「みなちゃん。今回もとても素晴らしいピアノを聴かせていただけてありがとう。昨年とまた違ってとってもおもしろかった!みなちゃんが言っていたとおり“玄人好み”ということかもしれないけど、音楽ってただ美しいだけではなくて“創作”なんだ!と、あたり前のことなのかもしれないけど思ったよ。どの曲もとても興味深かった!!」
「(中略)クライスレリアーナは圧巻でした。もしも絵画作品だったら、この絵巻物のような曲をどう表現できるんだろうと思ったよ。絵巻物にしてしまったらあまりにも説明的になるし、かといって一枚の絵のみでは難しい。では立体か?映像か?映像が近いのか?…他の何でもなく音楽であることの魅力をとても強く感じたよ。ピアノたった一台でこの長い長い感情や情景の表現をするって、とんでもなく高度なことね。そして、作曲ってすごいことなのね。作曲家がいて、楽器があって、弾き手がいて…。音楽というこの合作は、他の芸術作品とはまったく違うのよね。」
「(中略)昨年のリサイタルはとにかく、魂がふるえちゃったひとときだったけど、今年はより、音楽というものを知ってみたいと思ったわ。すごいわね、みなちゃん。私、なぜか音楽には相当うとい人生だったけど、おかげさまでとても目覚めた。」
「みなちゃん、もっと小さな会場で、年に季節ごとに四回くらい?トークを交えての音楽会やってほしいな。みなちゃんの話はおもしろいし、とてもとても、世界がひろがる!!ぜひ!!ね!!」…
彼女らしい、流れるような自然な筆跡で、感想をそのまま語るように書き綴ってくれたうえに、愛情たっぷりの宿題?まで提示してくれているその文面に、私こそ魂が震える思いでした。演奏を通じて、こんなふうに心を通いあわせることができたことが素直に嬉しくて、何度も何度も読み返し、心の中で、ありがとう、と繰り返し言いました。今回は彼女のほかにもたくさんの方が素晴らしい感想を熱心にお寄せくださって、夢のように幸せな気持ちです。
演奏を褒められたのが嬉しいのでは、ありません。音楽のもつ無限のちからやその素晴らしさを改めて実感できたことや、それをわたしのつたない演奏を介してみなさんと共感できたことが、なにより嬉しいのです。
音楽との、ピアノとの、周囲の方々たちとの…すべての出会いに心から感謝すること以上に、私を楽器に向かわせる強くエネルギーはないように思います。そう。“得がたいもの”の正体は、深い感謝の気持ちなのかもしれません。
■第608回 ゆっくり進むということ
リサイタル“クララ・シューマンへのオマージュ”の、仙台公演を終え、東京公演を目前にしているタイミングでこの原稿を書いています。
ステージで弾くことの怖さ、厳しさ、楽しさ、掛けがえのなさ。その経験から習得することのできるさまざまな学びの多さには、毎回のことながら驚くばかりです。
よく生徒さんにもお話しするのですが、ピアニストに限らず演奏家というのは、ほかのアーティストとはまた一線を隔した特殊性をもっている気がしています。絵画や彫塑、建造物なら創り手がいて観る人がいて、それで完結しますが、音楽の場合は作曲家という創り手と聴く人の間に、私たち演奏家というものの存在が要る。いわば演奏家は、作曲家の残した楽譜だけでは鑑賞できないものを音にして、聴き手にその中味を伝える“語りべ”の役です。
したがって、演奏家は作曲家にも聴き手にも、両サイドに寄り添うことが求められています。二者のあいだに、たっているのです。作曲家の書いた“台本”の意図をくみ、自分の“声”でそれを読み上げ、聴き手とのコミュニケーションをとるのです。
正確に伝えることに徹しすぎて、演奏が面白みに欠けてしまうのも、望ましいことではありません。かといって、あれこれ遊びすぎて本筋からはずれてしまうのは、もってのほか。いいバランスをみつけるのは、容易なことではありません。そんなふうに考えだすと、自分のしていることがとてつもなく大変な…てっぺんのみえない難儀なことのように思われて楽しくなくなってしまう?ので、普段はあまり考えすぎないようにしています。
どんなに準備をしても、どんなに練習をしても、緊張していつものようには弾けないことがわかってはいるのに、どうしてもステージに向かわずにいられないのは、自分が心底、音楽が好きだから。弾くのが好きで、楽しいから。そしてそれを、できることなら誰かとわかち合いたいから。それだけなのです。
リサイタル直後は、疲れやら反省やらいろいろなキモチが錯綜して「ああ、大変だった!しばらくリサイタルをするのはやめよう…」と、弱気になってしまうのですが、それがいつの間にか「今度はどんなプログラムにしようかな…」
なんてことを一日中考えるようになっているのです。つくづく、懲りない性分です。
でも、です。“継続は力なり”という諺がありますが、継続を支えるのは案外、この“懲りない性分”なのではないでしょうか。どんなに下手でも、どんなに失敗をしても、好きな気持ちは変わらない。飽きることがない。やめられない、やめたくない。…そんな何かと出会うことができたら、人生はそれだけで相当に楽しくなるはずです。
他の習い事が長続きしないのは、私にとっての王道“ピアノ”が他とは比較にならないほどにあまりに大きな存在だからなのでしょう。きっと、とても単純なアタマの構造なのだと思います。パカっと脳みそを開けてみたら、音符しか入っていないのではないかしら…。
大好きなイタリアのことわざに、“Chi va piano va sano e va lontano.”というのがあります(フランスにも同じ意味のことわざがあるので、どちらが本家かわかりませんが)。その意味は“ゆっくり進むものは、より遠くにたどりつく”。ゆっくりていねいに一歩一歩を積み重ねていく方が、はやく結果を出すべく効率よく進むよりも結局は多くを学びつつ高いところまで到達することができる…そんな意味なのだそうです。
これは、レッスンのなかでも、すぐにできるようにならない生徒さんによく話すフレーズです(同時に、自分にも言い聞かせているのですが)。実際のところ、いわゆる器用ではない生徒さんのほうが、器用にすぐできてしまう生徒さんよりも本番でいい演奏をすることがあったり、長い目でみて大きな成長を遂げることが多い気がします。
私も、決して器用なタイプではありません。最近はそれを、以前ほどうらめしく思わないようになりました。短所も克服しようと努め続ければいつしか長所に転ずるし、長所も驕れば短所に転ずるもの。短所をうらめしく思わずきちんと受けとめながら、まもなくの東京公演も愚直にピアノに向かいたいと思っています。ピアノが好き、音楽が好き、という気持ちを相棒に。
■第607回 シューマンの“献呈”について
君は僕の魂、僕の心
君は僕の喜び、僕の苦しみ
君は僕の生きる世界
君は僕の求める天国
あぁ、君は僕の悩みを永遠に葬った 僕の墓穴!
君は憩い 君は安らぎ
君は天から僕に授けられたひと
君に愛されることが僕を生かす
君の眼差しが僕を輝かせ
君の愛が僕を高める
君は僕の善き霊、より善きわが分身!(*筆者拙訳)
ロベルト・シューマンが結婚前夜に妻となるクララに贈った歌曲“献呈”の歌詞です(タイトルのドイツ語Widmungは、本当なら献呈、というより献身、と訳するほうが適切な気もしますが)。26曲からなる歌曲集『ミルテの花』の第一曲です。ロベルトは“愛する花嫁へ”としるしたその譜面にミルテの花を添えて、クララに贈ったといわれています。
ちなみに、ミルテの日本名は銀梅花(ギンバイカ)。古代ギリシャでは豊穣の女神デーメーテールや、愛と美と性の最高の美神アフロディーテに捧げる花とされていたとのことですし、古代ローマにおいては愛と美の女神ウェヌスに捧げられる花とされていたことから、ヨーロッパでは結婚式にもよく用いられる、純潔のしるしのような花です。
こんな美しいタイトルの美しい詩による美しいメロディーの歌曲をプレゼントされたら、いったいどんな気持ちになることでしょう!しかも、ロベルトとクララの二人は結婚をクララの父親から猛反対され、父親に対して結婚訴訟までおこし、出会ってから12年も経てロベルトが30歳のときにようやく結婚することができたのです。
この“献呈”を贈られたクララは、この作品を自らが独りで弾いて楽しめるようにピアノソロ用に編曲しました。原曲をいかして伴奏のパートに歌のパートをそのまま加えた、簡素なアレンジです。それをまた、フランツ・リストが「ピアノソロには歌詞がないので、そのぶん音で存分に表現しましょう!」とばかりに、テクニックを駆使して華麗なアレンジに仕立て上げ、クララに捧げています。後半にはもう原曲のイメージからすっかり離れ、華やかなパッセージやオクターブのオンパレードになっていますが、それも比類なき名ピアニストだった彼ならではのご愛嬌…(今度のリサイタルで弾きます)。
ところで、この歌曲集『ミルテの花』にはハイネなど全部で7人の詩人による詩が用いられていますが、この最初の一曲“献呈”と、最後の曲“エピローグ”はいずれもドイツの詩人リュッケルトによる詩で、始まりと終わりを結び付けています。ロベルトの文学的構成を大切にする創作姿勢やこだわりがうかがえます。
リュッケルトの詩は彼の他にも、フランツ・リスト、ヨハネス・ブラームス、リヒャルト・シュトラウス、フーゴー・ヴォルフなど、多くの作曲家たちを触発しました。特にグスタフ・マーラーの『亡き子をしのぶ歌』『リュッケルトの詩による5つの歌曲』は有名です。アラビア語やペルシャ語も学び、東洋詩の翻訳家としての一面も持っていたそうです。
“愚者は最後に、利口者は中間で、賢者は最初に目標を見さだめる”という彼の格言を聞くと、ずいぶんなキレもの、というイメージが思い浮かびますが、“酒と美しい娘は二本の魔の糸。よほど経験を積んだ鳥でもこれにはまんまと引っかかる”などはちょっとほほ笑ましくて、親しみを感じます。
ささやかな作品ひとつにも、実にさまざまな背景が沁みこんでいるものですね。あれ?こんなに詳しくご紹介してしまったら、当日お話するネタがなくなっちゃう…?
■第606回 潮には流されずに
二落ち、という言葉を最近知りました。お芝居の世界の言葉です。緊張しながらも、実はその緊張感に良い意味で支えられて初日の公演を終え、そのあとの二日目(二回目)の本番で今度は慣れの気持ちから緊張感を欠き、結果的に芝居の質を落としてしまうことをいうそうです。世阿弥のいうところの“初心忘るべからず”にも通ずる言葉かもしれません。
緊張は悪いばかりのものではありませんが、本番が近づくとともにひたひたと音もなく迫ってくる不安を、苦手と感じない演奏家はいないでしょう。なにしろ、なんでもなく弾けていたところがある時突然弾けなくなったり、ちょっとした瞬間から暗譜が怪しくなってしまったり…と、いやなミスが増えてくるのです。そうなってくると練習すればするほど不安がつのってしまいそうで、ますます怖くなってしまう…。大御所演奏家が実は練習嫌いだったり、ステージに上がるときには実際に誰かに背中を押してもらわなければならなかった、という話をたまに聞きますが、ほとんどが嘘ではありません。
試合前にインタビューされたスポーツ選手は、しばしば「ライバルは自分です」とか「自分のやるべきことをやるだけです」と、さわやかに答えていますが、あのさわやかさの奥には人には言えないような…恐怖にも似たプレッシャーがあることは、想像がつきます。楽しんでプレーする、と口では言っても、本当に楽しめる境地に至るのは並大抵なことではありません。
それでも、彼らを突き動かす根元には、私たち演奏家が楽器に向かうのと同じようなものが息づいているように思います。第一に、どんなに苦しくても苦しめられても、心底それに魅力を感じていて好きであるということ。そして、自分の能力がどうかという以上に、見てくれる人に何かを感じてもらいたい、何かを与えられるかもしれない、と、祈るような気持ちで望んでいることです。
先日、ヒロインと現役の海女をしている祖母とのあいだに、こんな会話がありました。
「ねえ、おばあちゃんは、何で潜るの?」
そのやりとりを聞きながら、無意識に“潜る”を“弾く”に置き換えていました。「そうだなぁ。何で弾くか、と聞かれれば、面白いからだよなぁ。弾きながら音楽のことを考えているときはいいけど、ふっと他のことを考えたスキに、あのいや~なミスの悪魔が入り込んでくるんだよなぁ。あれは、潮に流されているってことなんだなぁ…」前日の練習での問題点をふりかえると、潮が雑念に思われてきました。
歳を重ねれば、いろんなところが衰えるのは自然なことです。中には、そうはさせじと体力作りやアンチエイジングに情熱を傾け、健康や美容の管理にとても熱心な方もいらっしゃいますし、それはそれで立派なことだと思うのですが、だからといって衰えや疾患を絶対的“負”であると敵対視しすぎる必要もないと思っています。
あれもこれもを望むのが若さだとすれば、あれもこれもが手に入らなくてもいたずらに不安を感じることなく、自分にとって本当に大切なものをきちんと見据えて、“今”を受け入れ感謝して日々を送る…というのが目標です。残念ながら実際にはそうはいかなくて、練習の調子に右往左往しているのが現状なのですが。
川の流れに逆らわず、さりとて潮に流されることもなく…。ドラマのおばあちゃんのようにまっすぐな心持ちで、ピアノを弾き続けていたいものです。
■第605回 春に寄す
咲いたとか散ったとか…。この時期の日本人は、芸能人のゴシップ以上に桜の話題を好みます。全国的に今年は例年よりも開花が早く進んでいるので、いっそうその話題でにぎわっているようにも感じます。
去年の4月初旬のある日、ある在日外国人の方の「皆さん、そろそろ桜の話題はおしまいにしませんか?」というフェイスブックのウォールへの投稿が目に留まりました。その方は、来る日も来る日も、あまりにも“似たような”桜の写真や開花の報告の投稿が続くので、なんとなく辟易としただけで、もちろん他意はなかったはずなのですが、私はちょっぴり悲しくなりました。なぜなら、それは私のふるさとではまだ“桜の開花”という春が訪れていない時期だったからです。
東北の人々は、長く厳しいかの地の冬ゆえに、関東や関西の人たち以上に春を強く待ち焦がれていることはよく知っていますし、桜はその象徴のような花。北の国からその喜びの便りを聞くのを、私はいつも楽しみに待っているのです。「ああ、早く向こうにもこんな温かくうららかな春が訪れますように」と、祈るような気持ちで…。
今ではあまり聞かれなくなりましたが、サクラサクというフレーズはかつて、願いが叶うことの喩えに使われていました。折りしも東日本大震災の一年後。桜の開花が首都圏よりも遅いのは例年のことではあるのですが、昨年は復興が思うように進まない現実と、春に置いてきぼりにされているような感じが勝手にだぶって、その方の投稿が妙に心に引っ掛かってしまったのです。
確かに、桜には心おどる特別な魅力があります。今までの苦労が報われ、それまでの努力が一気に実を結んだかのような誇らしげな華やかさ。柔らかな春の陽ざしに似つかわしい、はんなりとしたピンク色。それがほんの数日ではらはらと散ってしまう儚さと潔さ。桜は日本人の好む“雅”や“粋”の心をあわせ持っているようです。
川ぞいの絢爛な千本桜、風光明媚な一本桜…。全国各地にそれぞれ素晴らしい桜の名所があります。そんなところで心ゆくまで桜を味わうのも素晴らしいこととは思うのですが、私はどちらかというと近所をのんびり散歩して、なんでもない公園や学校に咲く桜の姿を愛でるのが好きです。そこでは、よちよちと歩く小さな子の手をひくお母さんや、踊るように飛び跳ねてひらひら舞い散る花びらを拾う女の子や、はたまた地面に落ちた花びらをそっと避けて踏まないように歩く男の子、ゆっくりとそぞろ歩く老夫婦…。たくさんの素敵な人たちに出会えるからです。
そのことと因果があるかどうかわかりませんが、世界遺産や観光名所と呼ばれる場所にもあまり興味がありません。考えてみたら、観光客でごった返す名所を訪れたときの思い出よりも、お昼ごはんをもって近所の公園にピクニックに行き、妹と手をつないで歌いながら歩いたことや、母とシロツメ草でティアラを作って頭にのせ、お姫さまになったような気分になったときのときめきの方が、鮮烈な思い出になっています。どうも、子どもの頃から有名なものや立派なものよりも、日常のなかでささやかな楽しみや幸せを感じる時間の方を好んだようです。
音楽はそんな私にとって、魔法のツールでした。なんでもない日曜日の朝も、父がかけるベートーヴェンのレコードで極上のホリディの始まりになりましたし、夜更けにヘッドホンでそっと聴くショパンは、私を恋する乙女の気分でいっぱいにしました。音楽以上に、日常のなんでもない時間を特別なものにしてくれるものは、ありませんでした。
北欧の作曲家、グリーグに『春に寄す』という題名のピアノ曲があります。彼はまた『蝶々』という可愛らしい曲も残しています。いずれも3分ほどのちいさな作品ですが、そこには北国の人々の春を迎えた喜び、春を愛でる気持ちがあふれています。そして、弾くたびに「特別な日に幸せを感じるよりも、毎日を特別に感じる幸せを大切にしたい」という気持ちにさせてくれるのです。
皆さんおひとりおひとりに、素敵な春が訪れますように…。
■第604回 疲れは風とともに去りぬ
地元の高校で教鞭をとっている知人から高校生を対照とした特別講義の依頼を受けました。先日、無事に終えたその二時間に及ぶ講義のタイトルは『20世紀初頭の音楽とその背景』、副題は“世界情勢とクラシック音楽の関わりを聴く”というものです。
あの大バッハの産まれた17世紀、ベートーヴェンやモーツァルトが活躍した18世紀、ショパンやシューマンなど、ロマン派の作曲家たちが色とりどりの作品を咲かせた19世紀に比べ、20世紀は時代的には言うまでもなく現代に近いというのに、その芸術についてはなかなか親しみをもって理解されるところにまで至っていないというのが現状ではないでしょうか。
確かにその時代の音楽には、一見して(音楽だと、“一聴して”?)分りやすいとはいえないものが多く、難解であったり無機質であったり、とかくとっつきにくい印象を持たれやすいのは確かです。そこで、時代的・歴史的な背景をふまえての予備知識を持って作品にアプローチすることで、とらえ方がどう変わるか、ということを体験してもらおうと思ったのです。しかも、この時代には現代にもつながっている重要にして深刻な民族問題をはらんでいるのに、音楽の時間ではほとんどその歴史に触れることがないまま、彼らは大学生に、あるいは社会人になって、そのあとはよほどその専門分野に進まない限りは学ぶ機会を失ってしまうことがほとんどなのです。
講義の幕開けではワーグナーの“トリスタン和音”の響きを聴いてもらい、それまでの音楽の変遷をダイジェストにお話しして、ロマン派の終焉や調性音楽の崩壊(?)について触れたあと、なんの紹介もなくあるピアノ作品を生徒さんたちに聴いてもらいました。「どんな感じがしましたか?」と質問したところ、ある生徒さんは「何か、研ぎ澄まされた…とても綺麗な空気や、澄んだ水が思い浮かびました」と答えました。挙手をしてくれた別の生徒さんは「厳しいものと温かいものの両方が、混在しているように感じました」と答えました。
私は、とても驚きました。というのは、ほんの数分の曲を聴いただけで、彼らがその20世紀を代表する作曲家の特徴のすべてを簡潔に言い表したからです。私が弾いたのは、バルトークの『三つのチーク地方の民謡』という作品でした。耳に馴染みのない和声や、変則的なリズムなどを乗り越えて、彼らはその本質を感じ、スッと体に取り込んでしまったのでした。素晴らしいことです!彼の真実の民族音楽への厳しい探求について、古いものに根ざした新しい音楽への熱心な取り組みについて、を、当時のハンガリーのおかれていた歴史的な背景やハンガリー語のアクセントの特徴との絡みを交えて、お話しました。
その他、ヨーロッパにおける民族と国家についてや、ホロコーストで友人を失った事件をきっかけにうまれたショスタコーヴィチのピアノ三重奏曲など、さまざまなお話と作品の紹介をして、あっという間に二時間が過ぎてしまいました。
高校一年生、二年生の生徒さんにとっては必ずしも頭にも耳にも優しくなく、重く難解な部類の音楽なのは分っていましたが、あえて投げかけてみました。きっと何かを感じ取ってくれるはず…と思ったのです。高校生の感性の素晴らしさは、私自身母校で10年ほど非常勤講師を務めた経験から、確信していました。彼らは最後まで静かに―――時に、熱心にメモを取りながら―――まっすぐに私のほうを見て講義に聞き入ってくれました。
生徒の皆さんがひとりひとり、講義の感想を寄せてくれました。「歴史にはどこかに嘘があるものだと思っていましたが、芸術は素直な真実だと、今日思いました。音楽もまた、歴史の証でありうると知ったような気がします。」「音楽はただ感じて楽しむものだと思っていましたが、作品の背景を知って聴くことでさらにイメージや理解がひろがることが分りました。」「自分もピアノを習っているが、ただただ音を鳴らしていたように思う。違う視点からものを考えることを大切にしたい。」「今度コンサートへ訪れる時は、歴史的背景を学んだうえで、自由なイメージをもって拝聴したい。」
どれも私が感じとって欲しいと願ったことばかりです。確かに知識は大切ですが、それにとらわれる必要は、ありません。むしろ、理解を深めるために知識というステキな道具?を上手につかって、存分に楽しんでもらいたいのです。キレイで分りやすい音楽だけでなく、手ごわそうに聞こえがちな現代音楽も楽しめる人になったら…平坦で安定した人生だけでなく、山あり谷ありでドラマティックな人生も楽しめるようになるかもしれません!?
前日の準備であまり寝られなかったことからの疲れも、若くすばらしい感性に触れて―――さらに、ご褒美に頂いたフルーツパフェの後押しによって―――春の風とともにどこかに吹き飛んでいきました。
■第603回 恋とメランコリー
もうすぐ、リサイタルの一ヶ月前になります。私はいつも、この時期が要注意。スランプというほどのものではありませんが、刻一刻と本番が近づいてくるのを実感して焦りはじめたり、上達が実感できなくて悩んだり、表現をまとめるための突破口がなかなか見つからなくなったりしやすいのです。そこへきて、お知らせの文書を書いて皆さまにお送りしたり、その送り先のリストを作成したり…といった苦手な事務的作業も、ちょうどこの時期にどっと押し寄せてきます。
そんな軟弱な心の持ち主である自分に鞭打ちながらピアノを弾くにつけ、芸術家(作曲家)たちの強靭な精神力や、命を削ってまで…というほどの創作にかける意欲や執念のすさまじさに、圧倒されっぱなしです。彼らをそんなに創作に駆らせるものって、何なのでしょうか。もちろん人にもよるとは思うのですが、ほとんどの作曲家たちが地位や名声といったものを目指していたのではないことは確かです。
彼らを突き動かしているのは、自身のアイデンティティーを表現したい、よりよい形にして人に誠実に伝えたい、というまっすぐな思いです。具体的にその作品を捧げる(もしくは聴いてほしいと願う)特定の相手が決まっているときは、さらにその思いは深まるかもしれません。
ブラームスを弾いていると、特にそれを強く感じることがあります。自分のなかで対話を繰り返し、どうどう巡りする想いに時にいらだち、時に諦めを感じ、不安定な気分のうつろいに葛藤しながらも、心やすらかな境地を求め続けているように感じることがあるのです。あるいはそれは、自らが背負っている罪の救いを求める、キリスト教的な精神にもつながるのかもしれません。
私は作曲家でもキリスト教徒でもないのに、そんな感じがとてもわかる気がするのはなぜだろう、と不思議に思っていたのですが、考えてみたらこれは不思議でも何でもないことでした。その感じというのは、あるものにとても似ていることに気づいたのです。“恋”です。
相手に振り向いてもらいたい、気に入られたい、という純粋な気持ち。一方で、そのままの自分を理解し受け入れてもらいたいし相手をもっと知りたい、相手にもっと近づきたい、という願望。ちょっとした相手の反応に一喜一憂
し、どうしたらいいのかと悩んだり、どうにもならないと絶望したり。相手と過ごしてときめきを感じつつも安らぎを覚えたり、自分を振り返って落ち込んだり不安になったり…。
ブラームスがシューマンの妻で、自分よりも14 歳年上のクララにあてた手紙に、こんなものがあります。「あなたの虜となったこの疲れ果てた男は、(中略)詩人がこう表現しているとおりなのです。『心は重く、憂いは広がり、目を閉じても眠れず、体は疲れ、忍ぶ力も消えうせているのに、別離の暮らしは続き、理性は乱れ、心はここにあらず』こうして嘆いたところで苦悩の炎が消えるわけではありませんが、切ない思いに心乱れて別離に悩める者の苦しみは、和らげられるのです。」
実はこれは彼自身の言葉ではなくある文献のなかの手紙の引用なのですが、それを差し引いてもかなり直球のラブレターです。
その翌年には、クララにこんな手紙を送るに至っています。「クララ、愛するクララ。…貴方への愛を思うと私はますます喜ばしい気分になって心が安らいできます。貴方がいない寂しさはそのつどいっそう募るのですが、その一方で、貴方に恋いこがれることに喜びを覚えるといってもいいほどです。これほど熱い気持ちになったことは決してありませんでした。」(音楽之友社ハンス・A・ノインツィヒ著『ブラームス』より)
まさにこの境地はそのまま、彼の作品から感じて取ることができます。すごいことです。その、深く複雑な思いを、演奏をとおしてどれだけ皆さんにお伝えてできるのか…。誰もが共感できるはずの要素ではありますが、果てしなく難しいことのようにも思われてきます。でも、弾くと決めたい以上、腹をくくって挑むしかありません。そう、ブラームスではないけれど、実らない恋なら充分(?)経験しているんですもの!
ところがそう思った矢先、ニーチェが彼を評して語ったこんなコメントを見つけました。「ブラームスが創造したものは、無能力のメランコリーだ。」むむ?メランコリーですって?失恋してもそれほど落ち込まない私は、その感じとなるとまったく自信がありません。ああ、困った…。あら?これって一種のメランコリー?
■第602回 ウーマン・オブ・ウーマン
先日フェイスブックに以下の投稿をしたところ、多くの反響を頂きました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
“美魔女”…。 「魔法をかけているかの様に美しい」才色兼備の35歳以上の女性
をいう流行語だそうだけど どうしても美しいイメージがわかなくて、悩み中。 例えばオードリー・ヘップバーンやバーグマンみたいな人を、美魔女、とは呼ばないはず…。
魔女ってどんなに美しくても、どこか超自然的不自然さがある気がするのは、 わたしだけなのでせうか?へそまがりなのでせうか? 美しさに年齢の定義が入っているところも、ちょっと違和感なのかも。
…そもそも美しさって、若く“みえる”とか、パーツ?が整っているとか、 社会的ステイタスがあるとか、そういうことではないと思うのだけど…。
日本人の美的基準が、どうもわからなくなってきております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この投稿にコメントをお寄せくださった方の大半が男性で、しかもそのほとんどが私と同様に、この言葉に共感が得られないというご意見だったのは、意外でした。
同じような戸惑いを感じる流行語に、“ハンサムウーマン”というのもあります。こちらは某放送局のドラマのヒロインの宣伝に用いられている造語ですが、男性にではなく女性に対して“女っぽい”というのも、なんとなくむずむずします(もちろん、“女らしい”なら問題ありません)。
その、最近トレンドの“ハンサムウーマン”には、一説によるとかのココ・シャネルも該当するのだそうですが、果たして彼女がもしご存命だったら、その言葉を喜んで受け入れるかどうか…。何しろ彼女は、品格、ということをとても重視して“下品さ”をたいそう嫌った人だったようなのです。曰く「下品な服装は服だけが目につき、上品な服装はその人物を引き立てる」。
もしも演奏にも上質なものとそうでもないものがあるのだとしたら、同じことが当てはまるかもしれません。つまり、「上質でない演奏は演奏家が前に
出て、上質な演奏はその作品が前に出る」。それは、演奏家が独自の解釈で作品に迫り、それぞれの個性で表現するのはよしとしても、それが不完全だとその人のクセや嗜好だけのお仕着せになってしまって、作品の真髄を伝えることから遠ざかってしまう、という警鐘に聞こえます。
彼女は、こうも語っています。「贅沢は貧しさの反対だと思われているけど、それは違う。贅沢は、下品さの反対です」。品格を身につけるため、それ保つために投資する贅沢は、貧しさの対極ではない…。男性顔負けの行動力とバイタリティで巨大な財力を築き上げ、男性中心の社会から自立する自らのエレガンスを追及した彼女らしい哲学です。
ココ・シャネルのすべてに傾倒しているわけではありませんが、彼女がそれまでの社会の風潮や逆風にめげず、多くの人々を牽引していくに必要なぶれない理念や戦略をもっていたのは事実でしょう。そんな彼女をハンサム、と、男性に対する褒め言葉で形容するのが、果たして的確といえるのか。私にはどうも、ぴんときません。
彼女の格好良さは、男勝りなところからではなく、女性が女性ならではの発想と視点と大胆さからなるものだと思うからです。むしろ、“ウーマン・オブ・ウーマン”…女の中の女、とよぶ方がふさわしい気が、します。音楽家としてずば抜けた才能を持ち、たくさんの子どもたちの母親でもあったシューマンの妻クララも、その一人かもしれません。
私の個人的な感覚としては、ウーマン・オブ・ウーマンは、何も彼女たちのようにキャリアとステイタスのある、自立した女性だけをさすわけではありません。家庭のなかで太陽のように明るく気丈に家族をささえ、決してくじけない心をもって彼らを見守るお母さんも、立派なウーマン・オブ・ウーマンだし、例え結婚していなくても自らの人生を前向きに受け入れて、社会のなかでのびやかにそれを謳歌する女性たちもまた、ウーマン・オブ・ウーマンです。
心強いことに、私の周囲にはそんなウーマン・オブ・ウーマンが何人もいます。彼女たちと話すにつけ、日本はまだまだ大丈夫!という気持ちになります。そしていつの日か、私も彼女たちの仲間入りしたいものだ、と心から願うのです。
■第601回 ハートを射止める主成分
先日、ありアマチュアオーケストラの定期演奏会を聴きました。あるピアノの生徒さんのご家族がメンバーとのことで、ご招待を頂いたのです。
プログラムはシューベルトの交響曲第5番、ベートーヴェンの交響曲第3番“英雄”など、大曲揃い。楽団のコンセプトや意欲が伝わってくる選曲です。春の嵐、というにはまだまだ冷たい風が吹き荒れてはいたものの、陽射しに恵まれた日曜日の午後、勝どきの晴海トリトンスクエアにあるホールに出かけました。休日の観光地意外の都内(特にビジネス街)は人も少なく、歩いている人の足取りもゆったりとしていて、あまり忙しいのが得意ではない私にはありがたいのんびりとした雰囲気があります。
もともとは同じ大学のOB同志によって結成されたという室内管弦楽団。長い時間、音楽について語り、ともにアンサンブルを重ねてきたであろう仲間の結束が感じられる、とてもステキなコンサートでした。
それだけでなく、各メンバーが縦のタイミングを合わせること以上に音楽表現の方向性を合わせることに努めつつ、楽曲の本質に近づくためのより適切なアプローチについて真摯な取り組みを積み重ねているのが感じ取られ、胸に迫る感動的な瞬間が何度も味わえました。特にベートーヴェンは、彼の凄まじいエネルギーや高い精神性がひしひしと伝わってきて、作品の素晴らしさを充分に味わうことができました。
帰り道、人を喜ばせ感動させる成分があるとしたら、それは何なのだろう、と、改めて考えました。卓越した熟練の技術もそれに含まれるかもしれませんが、それがメインではないのは明らかです。なぜなら、人が本当に感動するときは、その矢はアタマ(思考)を一気に飛び越えて、ハートをグサッと直撃するから。「このパッセージは難しいのによく弾けている」「このような新しい解釈に、よくぞ至ったものだ」など、アタマで解析している間もなく、訳もわからぬまま、瞬時に心が震えるのです(私だけかな?)。
それはまさに、恋に落ちる瞬間と同じ。一定のレベルや条件を満たしているかどうか、なんていう条件はひょいと乗り越えて、よく見かける矢に打ち抜かれたハートのイラストよろしく、一瞬にして捕らえられ、虜になってしまうのです。「う~ん、なんだかよく分らないけど、とにかく好き!」と…。
果たして、その気になる主成分とは?…人によって違うものだとは思いますが、私にとってそれは、たぐい稀なテクニックでも、周囲をうならせる冴え冴えとした洞察力、解析能力でもなく、まっすぐに人の目をみて話しをするときの小さな子どもの瞳のような、純粋さ、ひたむきさです。衒いのない、あどけない、まっすぐさです。
天才少年、天才少女、といいますが、個人的には子どもはみんな天から授かった才能に溢れているものだと感じています。普通なら成長するにつれ、残念ながらいつのまにか手放してしまうその才をずっと持ち続けつつ、伸びやかに才能や個性を開花させて楽しんでいる大人こそが“天才”なのだと思うのです。
その室内管弦楽団では、そんなステキな大人たちが熱心に…そして無心に、音楽を奏でていました。弾いている人も、聴いている人も、そして、ちょっとオーバーかもしれませんが天国のベートーヴェンも、同じような幸せを感じているような気がしたひとときでした。
「うちのオーケストラと、ピアノ協奏曲を演奏していただけないでしょうか?」…その室内管弦楽団の主要メンバーを務めていらっしゃるある方から、オファーを頂きました。なんて幸せなことでしょう!もちろん二つ返事で、喜んで!と、お答えしました。
休日のオフィス街をそぞろ歩きしている人ようにのんびりペースで生きている私ですが、たまにこんなふうに、天からのご褒美をいただけます。ありがたいことです。来月には、県内のある高等学校から、高校生を対象とした特別講義(レクチャー)を仰せつかりました。周囲の人からいただけるさまざまな刺激を栄養に、心やわらかに過ごしたい春です。
■第600回 石の上にも13年
気がつけば、このエッセイも今回で600回目です。一年365日、たまにお休みするもほぼ毎週更新しているので一年に約50回。600回というと、もう12年ほど続いていることになります。
ホームページビルダーというソフトを使って、とてもささやかな手作りのサイトを立ちあげたのが、きっかけでした。当時はブログというものがなかったので、皆さんがたびたびサイトに遊びに来てくださるきっかけになれば、という軽い気持ちで週に一度のエッセイを書き始めたのでした。
考えてみたら、12年というのはなかなか長い時間です。こんなに長く続いていることって、ピアノ以外にはないと思います。ただただ「楽しい」「もっと深く知りたい」という思いだけで、物心ついた頃から今もずっと続いている音楽の勉強と違って、毎週ある程度の文章をまとめなくてはならないのは、いくら軽い気持ちで始めたとはいえ多少の努力を伴うものです。というのも、ものを書くのは嫌いではありませんが、さりとて決して得意ではないからです。
それでもここまで続けられたのは、ひとえに読んでくださる方のお励ましあってこそ!例えば、お会いしたことのない方から「毎週の更新を楽しみにしています」というメールをいただいたり、もう何年も美奈子さんのエッセイのファンなんですよ、とおっしゃる方から「今週のエッセイはとてもステキでした」というご丁寧なメールをいただいたり。初対面でお会いしたときに「いつも読ませていただいております」と、ご挨拶くださる方もいらっしゃいます。そのたび、ああ、つたない文章でも書き続けてきてよかった、と、心から嬉しく思うのです。
石の上にも三年、といいます。たとえ座るのには耐えがたいほどに冷たい石の上にも、三年間がまんして座り続ければ温かくなるであろう、という意味だそうです。「なにも三年も座り続けなくても、もっとはやく温まるでしょうに」とのご意見もあがりそうですが、私は逆に、物事を好転させたり、何かをモノにするためには、三年では足りない方だと考えています。だって、三年なんて、あまりにあっという間なんですもの。中学や高校時代の三年間の短かったことといったら!大学なんて、四年もあったのにさらに短く感じたほどでした。
ピアノを教えていると、ふと、同じようなことを繰り返し生徒さんにお伝えしていることに気づくことがあります。それは「ゆっくり」という言葉。ゆっくり弾く、という意味でお話することもありますが、大半は「どうぞ、早く結果を出そうと慌てないでください。音楽は、ゆったりとした心持ちで味わうものなのです。丁寧に、ゆっくり、上達していきましょう」という意味です。「なかなか味わう余裕、ないんですよね」とおっしゃる生徒さんもいらっしゃいますが、心に余裕をもって、ご自身の奏でている音に、耳だけでなく、気持ちもじっくりと傾けながら弾くことは、音楽の学習にとても大切なのです。
それは、俳句などで実際に詠唱し、言葉や語調を吟味して推敲を重ねることや、絵でしたら時おり目をキャンバスから離し、客観的に被写体と実際の絵を見比べながら書き進めていくことと同等に、あるいはそれ以上に大事なことなのです。なぜなら、ピアノを弾くことは、楽譜を見て、考えて、ひとつひとつの音のタッチを確かめ、響きに耳をすませ、感じたことをまた音に映しこみ…と、人間の五感を、いいえ、もしかすると第六感までもを総動員して行う、とても複雑にして愉快きわまりない行為だからです。
それを、心に余裕のないまま慌てて譜面を見てしまえば必ず読譜ミスが発生しますし、自分の出した音を充分に聴くことをしないで次に進んでしまっては、音楽のよさを感じることは難しくなってしまいます。ゆっくりと、一歩一歩。これは果物の木を植えてから、一定量が収穫できるようになるまでのように時間のかかるものなのだ、という気持ちで、ゆったりと“育てる楽しみ”を感じていただきたいのです。
このエッセイも、13年目。なかなか上達はしませんが、石の上にも13年…という気持ちで、これからもこつこつ書き溜めていきたいと思っております。
どうぞ、これからも末永くお付き合いくださいませ。
■第599回 クララ・シューマンへのオマージュ
来る日も来る日も、クララ・シューマンと向き合っています。今回のエッセイのタイトルは、今度のリサイタルの副題です。
ドイツの大作曲家ロベルト・シューマンの妻にして、当代一の人気ピアニストでもあった美しいクララ。何人もの大作曲家たちから彼女に、いったいどれだけの作品が捧げられてきたことか!その質、数…。どちらをとっても、バレンタインデーにたくさんのチョコレートをもらうどの男性も、かなうものではないでしょう。
クララがモティーフになっているのは、音楽作品ばかりではありません。彼女の肖像はユーロに加盟する前の現地通貨マルク紙幣にも登場していましたし、クララを題材にした映画も、これまで何本も製作されてきました。
例えば、近いところでは2009年公開のドイツ映画『愛の協奏曲』。最近BSで偶然見たのですが、ブラームスの末裔であるヘルマ・サンダース・ブラームス監督が、クララ、ロベルト、そしてその二人ともと深い関係にあったブラームスの三人の人間模様が、女性監督らしい視点で誠実に…、時に大胆に描かれていました。
例えば、二人の男性の間で心が揺れ動き、苦悩しているクララに、14歳年下のブラームスが「君は遊びを知らない少女なんだよ」と迫るシーン。精神を病んでしまったロベルトが、気持ちを乱して思わず「ヨハネス(ブラームス)を僕から奪わないでくれ!」と、クララに懇願するシーン。真剣に人を愛するゆえの狂気とその純粋さ、哀しさが痛いほど伝わってきて、これぞヨーロッパ映画!という、ずっしりとした見ごたえを感じました。
古いところでは1947年公開のハリウッド映画『愛の調べ』。こちらは、クララを大女優キャサリン・ヘップバーンが演じ、リストやクララのピアノの演奏をあの、巨匠アルトゥール・ルービンシュタインが葺き替えている豪華版です。…とはいえ単なる娯楽作品ではなく、きちんとある程度の歴史的史実に基づいてストーリーが組み立てられていて、音楽作品としてもじっくりと楽しむことができるものになっています。白黒映画ですが、ヘップバーンの美しさや細やかで丁寧な演技が際立ち、良質なハリウッド映画ならではのよい余韻を味わうことができます。
他にも、ナスターシャ・キンスキーがクララを演じている『哀愁のトロイメライ』がありますが、これはまだ見たことがありません。1981年公開のドイツ映画で、監督・脚本はペーター・シャモニ。こちらも演奏はバリトンのディートリッヒ・フィッシャー・ディスカウ、ピアニストのヴィルフェルム・ケンプといった名手が音を吹き替えているそうです。キンスキーがクララに扮した美しい写真はネットで見ることができますが、本編もきちんと見てみたいものです。
これまでの長い歴史のなかにおける音楽家の妻、恋人のなかで、彼女ほど、さまざまに取り上げられる女性はまず、いないのではないでしょうか。今回のリサイタルで取り上げる作品は、すべて彼女にまつわるものばかり。しかも、素晴らしい傑作ぞろいです。それらの曲を弾くにつけ、彼らがクララにどんな気持ちでその作品を書き、捧げたのか…。彼女の存在感の大きさにただ、圧倒されるような思いです。
オマージュ、とは、尊敬、敬意、献辞、といった意味。クララには遠く及びませんが、ピアニストとして、女性として、私にもどこかに彼女と共通するものがあるかもしれない…、という想いを胸に、毎日楽しんでピアノに向かっています。。